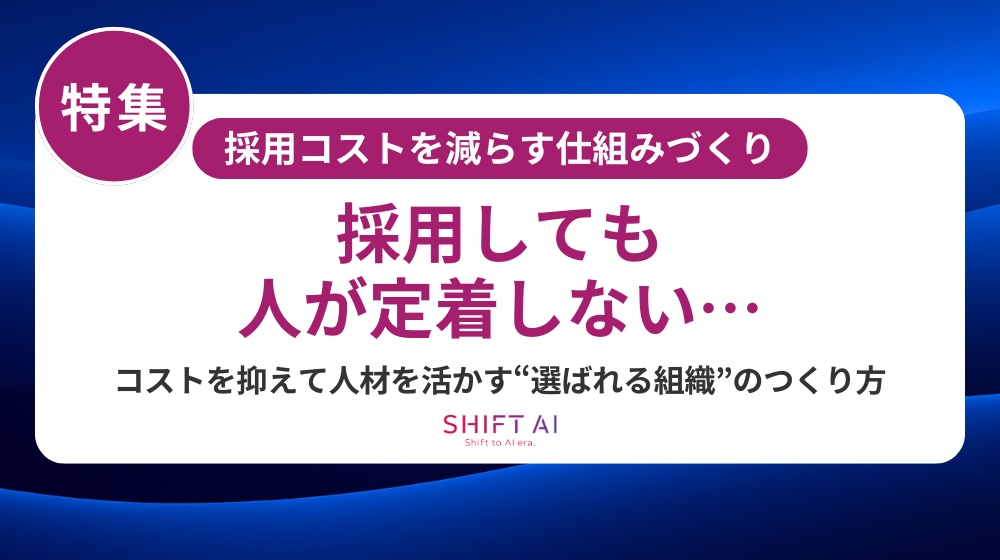「採用してもすぐ辞める」「広告費がかさんでいるのに成果が出ない」──
そんな“採用コスト”に悩む企業は少なくありません。
新卒・中途ともに、1人の採用にかかるコストは平均で50〜100万円以上とも言われます。とくに中途採用においては、年収の30〜35%が紹介手数料として発生するため、相応のコストがかかります。
人材紹介の手数料や求人広告費だけでなく、面接・育成にかかる人件費や、早期離職による再採用も大きな負担になります。
本記事では、そうした採用コストの課題に対して、実際に削減に成功した企業の事例を5社分、業界別に詳しく紹介します。
「なぜその方法で成果が出たのか」
「自社で再現するには何が必要か」
という視点で各事例を読み解きながら、“真似できる・再現できる”採用改善のヒントを得られる構成にしています。
また後半では、採用数に頼らず“育成と業務設計”で現場を回す組織づくりの考え方にも触れています。
AIや自動化の力を活用することで、採用数そのものを抑えつつ、より強いチームを作る視点も解説します。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
採用コストの内訳と平均相場を押さえよう
採用コストを削減するには、まず「そもそも何にコストがかかっているのか」を正しく把握することが不可欠です。
ここでは、採用にかかる費用の内訳と、よく使われる算出方法を整理しておきましょう。
採用コストの基本式:「採用単価」で考える
一般的に、採用コストは以下の式で算出されます。
採用単価(円)=採用活動にかかった総費用÷採用人数
この「採用単価」を正確に出すことで、削減対象を見つけやすくなり、改善の指標にもなります。
採用コストの主な内訳とは?
採用にかかるコストは、大きく以下のように分類されます。
| コスト項目 | 内容例 |
| 直接コスト | 求人広告費、人材紹介料、採用イベント出展費など |
| 間接コスト | 面接にかかる担当者の人件費、面接会場の確保、移動交通費など |
| 隠れコスト | 早期離職による再採用費、定着失敗による生産性ロスなど |
とくに見落とされがちなのが「隠れコスト」。
採用したものの早期に退職されてしまえば、また広告費・面接工数・研修コストがかかり、結果的に倍のコストがかかることになります。
採用コストの平均相場はどれくらい?
一般的な平均相場は以下の通りです。
- 新卒採用:1人あたり約50万〜100万円
- 中途採用:1人あたり約70万〜150万円(業種や役職で変動)
たとえば、中途採用で人材紹介会社を利用すると、年収の30〜35%が手数料として発生するため、1人当たり100万円超えも珍しくありません。
自社の採用単価、見えていますか?
多くの企業で、採用活動は「今まで通り」「なんとなく」で続けられており、コストの全体像が見えないまま予算を使ってしまっているケースが少なくありません。
まずは「自社の採用コストの全体像」を見える化することが、削減すべきポイントを見つける第一歩です。
関連記事:属人化しない組織とは?文化・仕組み・AI活用による根本対策
採用コストが膨らむ5つの原因と、よくある落とし穴
自社の採用コストを把握できたら、次は「なぜこれほどコストが膨らんでいるのか?」を明確にしましょう。
以下では、多くの企業が陥りがちな5つの原因と、気づきにくい落とし穴を解説します。
①求人媒体への依存が常態化している
「とりあえず〇〇ナビに掲載」「前年と同じプランを継続」――
こうした慣習的な出稿が、成果が出ていないのに高コストを垂れ流す要因になっています。
特に応募者数や歩留まりの改善が見られない場合、媒体選定そのものの見直しが必要です。
②高コストな人材紹介に頼りすぎている
人材紹介はスピード感に優れる反面、費用負担が大きくなりがちです。
特に年収が高いポジションでは、紹介手数料が100万円を超えることも。
それでも「すぐに採りたい」「広告で来ない」と依存を続けてしまい、構造的にコストが高止まりするリスクがあります。
③採用活動が長期化・非効率になっている
応募者との面接日程調整に時間がかかったり、合否連絡が遅れたりといった選考プロセスの遅延は、見えにくいが大きな損失です。
採用担当者が多忙だったり、マニュアルが整備されていない属人的な運用が長期化の原因となります。
④面接や育成が“担当者頼み”になっている
面接官のスキルや評価軸が属人化していると、採用判断のブレやミスマッチが発生しやすくなります。
また、オンボーディングや研修も特定の社員に依存している場合、退職や異動時にノウハウが失われるリスクもあります。
⑤早期離職による“再採用のループ”に陥っている
せっかく採用しても、入社後すぐに辞めてしまうと「再度の採用→再度の教育」と、何重にもコストが発生します。
これは単なる“採用の失敗”ではなく、育成や業務設計の仕組みが整っていないことによる構造課題です。
コストは「採用」だけでなく、「定着」「育成」とつながっている
ここまで見てきたように、採用コストの膨張には「媒体」「人材紹介」「工数」「離職」など様々な要因が絡んでいます。
しかし裏を返せば、採用活動を“仕組み”で支えれば、コストは確実に下げられるということでもあります。
採用コスト削減の代表的な方法
採用コストの内訳や原因が見えたところで、次は「どのような手法で削減できるのか?」を整理してみましょう。
成功事例の前に選択肢のフレームを提示しておくことで、自社の状況に合った施策を見極めやすくなります。
①採用チャネルの見直し【媒体から自社主導へ】
- 求人媒体からダイレクトリクルーティング(スカウト)やリファラル採用(社員紹介)に切り替える企業が増加
- 求人広告のような出稿コストがかからず、ターゲットを絞った効率的なアプローチが可能
- 「人が来ないから出稿する」から、「会いたい人にアプローチする」スタイルへ
②採用業務の効率化【ツールやRPOの活用】
- ATS(採用管理システム)やAI面接アシスタントなどの導入で、面接調整や進捗管理を自動化
- 一部業務を外部に委託する採用代行(RPO)も有効。コア業務に集中できる体制に
- 属人化を防ぎつつ、“人がやるべき仕事”のみに集中できる構造をつくる
③面接評価の標準化・テンプレート化
- 面接ごとに評価基準がバラつくと、ミスマッチが増えて離職リスクも上昇
- 面接質問や評価シートをテンプレート化するだけで、判断の精度と一貫性が向上
- 後述するChatGPTなどの生成AIを活用すれば、業種・職種に応じた質問集の自動生成も可能
④入社後のオンボーディングと育成の強化
- 採用数だけでなく定着率を上げることで、再採用コストを削減できる
- 社内の育成体制やマニュアル整備によって、採用コスト削減と人材育成が連動する仕組みに
- 特に現場リーダー層への研修や育成支援が鍵となる
⑤生成AIの活用による採用業務の効率化
- ChatGPTなどを活用して、求人票の文案作成、面接質問の自動生成、候補者とのQ&A対応などが可能に
- 採用工数の削減に加え、「採用×生成AI」の取り組み自体が社外ブランディングにもつながる
- 導入時には社内展開をスムーズにするためのAIリテラシー研修もセットで検討すると◎
フレームに沿って、事例をどう読むか
次章から紹介する企業事例では、これらのうちどの手法を採用し、どのように成果につながったのかを具体的に解説していきます。
単なる「成功話」で終わらせず、「自社ならどの方法が使えるか?」という視点で読み進めてみてください。
採用コストを削減した企業事例5選【業界別】
ここでは、実際に採用コスト削減に成功した企業の取り組みを、業界別にご紹介します。
それぞれの課題・施策・成果からは、自社にも応用できるヒントが見えてきます。
事例①:IT業界|人材紹介から求人広告へ切り替え、採用単価を80%削減
課題:年収500万円クラスのエンジニアを人材紹介経由で採用していたが、1人あたり150万円前後の紹介料が発生し、採用単価が高止まりしていた。
取り組み:求人媒体を活用した自社主導型の採用に切り替え。ターゲットを明確化し、採用サイトの導線設計も最適化した。
成果:採用単価が約150万円→約30万円に改善。媒体掲載コストはかかるものの、採用人数が増えてもコストが分散され、費用対効果が高まった。
再現ポイント:人材紹介への依存から脱却し、自社ブランディングと情報設計を強化することで、広告型でも優秀層の母集団形成に成功。
事例②:製造業|採用事務を自動化し、選考業務の工数を6割削減
課題:面接調整、エントリー対応、評価集約などに人事担当者が毎月50時間以上を割いていた。対応漏れやタイムロスも発生。
取り組み:ATS(採用管理システム)と面接日程自動調整ツールを導入。さらに、書類選考基準をスコアリング化し、初期選定を自動化。
成果:採用事務の作業時間を月20時間以下に削減し、担当者のリソースを本質的な人材見極めに集中できるようになった。
再現ポイント:採用業務を洗い出し、自動化・代行できる領域から着手。属人化を解消し、ミスや対応遅れも大幅減少。
事例③:飲食業|社員紹介(リファラル)で人材紹介料を完全カット
課題:店舗社員の入れ替わりが激しく、毎年1,000万円以上の人材紹介手数料を支払っていた。
取り組み:社員紹介(リファラル)制度を導入。紹介者にはインセンティブを設けつつ、紹介された側には入社後のサポート研修を実施。
成果:制度初年度で30名以上をリファラルで採用。紹介料ゼロでも安定した採用数を維持し、現場の満足度も向上。
再現ポイント:制度設計だけでなく、紹介後の定着支援(教育・フォロー体制)をセットで設計したことで持続的に運用可能に。
事例④:小売業|採用サイトとスカウト活用で広告費をゼロに近づけた
課題:店舗職の中途採用で毎月数十万円を求人広告に費やしていたが、採用単価は改善せず。
取り組み:自社採用サイトを強化し、会社の文化や働き方を伝える動画・インタビューコンテンツを整備。併せて、スカウト型サービスでの能動的アプローチを開始。
成果:採用サイト経由応募が全体の6割に達し、月間求人広告費を10万円以下に抑制。質の高い母集団形成にも成功。
再現ポイント:採用ブランディングとスカウト施策を組み合わせ、広告に頼らない自走型採用へと転換。
事例⑤:サービス業|オンボーディング強化で離職率を50%→20%に改善
課題:入社後のミスマッチで、3ヶ月以内の離職が多発。再採用と再教育にコストと時間がかかっていた。
取り組み:業務フローを見直し、入社前〜初期研修〜現場立ち上がりまでのオンボーディングプログラムを再構築。事前資料や動画マニュアルも整備。
成果:3ヶ月以内の離職率が50%→20%に改善。結果として再採用数が激減し、1年で採用関連コストを600万円以上削減。
再現ポイント:「採って終わり」ではなく、「入社後に活躍してもらう仕組み」を設計することが、最終的に採用数そのものを減らすことに直結。
共通する成功の鍵は「仕組み化」と「最適手法の選定」
これらの事例に共通するのは、単にコストを削るのではなく、「採用〜定着〜活躍」の一連の流れを構造的に見直したことです。
求人チャネルの切り替え、工数の効率化、制度設計、育成強化。
どの企業も、自社の課題に即して最適な手法を選び、再現性の高い仕組みとして運用することで、持続的なコスト削減を実現しています。
成功事例から学ぶ、再現性のある5つの共通点
ここまでご紹介した5つの企業事例からは、単なる「うまくいった話」ではなく、共通する“成功の構造”が見えてきます。
ここでは、それらを再現性の高い5つの視点として整理します。
①採用“前”の段階で社内の連携体制が整っている
「どんな人を、いつまでに、どのポジションで採るのか」
これが不明確なまま走り出すと、どんな施策も成果につながりません。成功企業は、採用要件を経営層・現場・人事で早期にすり合わせる“連携起点”をつくっていました。
②工数の見える化とタスク分解ができている
面接、連絡、調整、評価記録…採用業務には多くの「隠れタスク」があります。成功企業は、まず何にどれだけ時間がかかっているかを可視化し、自動化すべき業務/人がやるべき業務を切り分けていました。
③担当者だけに依存しない仕組みを作っている
採用担当者が変わると回らない、という属人化構造はコスト増の温床です。事例企業では、面接マニュアルや評価テンプレートを整備し、複数人で対応可能な体制を構築していました。
関連記事:業務の属人化を解消する5つの方法|生成AI時代の新しい組織づくり
④採用だけでなく「定着」と「育成」も含めて設計している
せっかく採用しても辞められてしまえば、また一から採り直し。
成功企業は、オンボーディングや内製化支援など「入社後の仕組み」にも力を入れており、結果として採用数自体を減らせる構造を築いています。
⑤生成AIなど新たな手段を“現場で使える形”で導入している
ChatGPTを使った面接質問の自動生成や、求人票の素案作成、面接官向けのロープレ資料作成など、AIを「使える業務」に落とし込む工夫が共通しています。ただ導入するだけでなく、研修やテンプレート整備とセットで“活用定着”まで設計している点がポイントです。
「この5つ」が揃えば、自社でも再現できる
本当に成果を出している企業は、派手な施策ではなく、地に足のついた業務設計・見える化・仕組み化を行っています。
そしてそのなかに、生成AIのような新しいテクノロジーを“人と組織の力を引き出す道具”として組み込んでいるのです。
採用コスト削減には「採用数を減らせる組織作り」がカギ
採用コストを本質的に削減するためには、広告費や人材紹介料といった“外からの見直し”だけでは不十分です。
最も効果が大きいのは、そもそも「採用を増やさなくても回る組織」を作ることにあります。ここではそのための重要な視点を、3つの切り口で解説します。
採用数を抑えるには「定着」と「育成」が不可欠
採用してもすぐに辞めてしまい、また新たに採用が必要になる――この“再採用スパイラル”は、多くの企業にとって無意識の出費要因です。
この連鎖を断ち切るには、「採ったら終わり」ではなく、「どう定着させ、どのように育てるか」に視点を移すことが必要です。
成功企業では、マニュアルや業務フローの整備、オンボーディングプロセスの明確化など、育成や定着の仕組みを“属人化させない形”で構築しています。これにより、1人あたりの教育コストを抑えつつ、離職率を低下させ、結果として採用数そのものを抑えることに成功しています。
育成の仕組み化に「生成AI」を活用する
近年では、生成AIの活用によって、育成コストをさらに下げながら教育の質を保つ企業が増えています。
例えば、ChatGPTを活用して業務マニュアルやロールプレイングのシナリオを自動作成する企業では、現場社員が教育資料を準備する負担が激減し、育成スピードも向上しています。
とはいえ、AIをただ導入するだけでは効果は限定的です。成功している企業は、AIを「誰が・どの業務で・どのように使うのか」まで定義したうえで、社内に活用を定着させる工夫をしています。そのためには、AIリテラシー研修や、現場主導での運用ルールづくりなどが不可欠です。
採用を減らしても成長できる組織へ
採用数を減らすというと、事業成長を鈍化させるように感じるかもしれません。しかし実際には、むしろ“少数精鋭で成果を出せる組織への進化”と捉えることができます。
既存人材の能力を引き出し、仕組みで業務を回せるようになれば、人員を増やさずとも生産性を高めることが可能です。
採用を増やす前に、「本当に必要か」「既存の人材で回せないか」を問い直すことが、採用コスト削減の最も根本的な打ち手になります。
まとめ|事例から学び、自社に合った“仕組み”を作ろう
採用コストの課題は、どの企業にも共通する悩みのひとつです。
今回ご紹介したように、広告費や人材紹介料といった目に見える支出だけでなく、面接対応の工数や早期離職による再採用といった“見えにくいコスト”も含めると、その負担は想像以上に大きくなります。
ただし、コストがかさんでしまう原因は単なる支出の多さではなく、仕組みの不在や属人化にあることが多いのです。
実際に成果を出している企業は、「採用のやり方」を変えただけではありません。
採用に至るまでの情報設計や業務プロセスの見直し、面接の評価基準の標準化、入社後のオンボーディング体制の強化など、組織全体で“人を迎え入れる仕組み”をつくっていました。
さらに、近年では生成AIを活用することで、こうした仕組みづくりのスピードと汎用性が飛躍的に高まっていることも大きなポイントです。
面接設計や業務マニュアルの作成といった煩雑な業務も、AIの力を借りることで迅速かつ標準化された形で提供できるようになってきました。
もちろん、すべての企業が同じ施策を導入すればうまくいくわけではありません。大切なのは、事例のなかから“自社に合ったやり方”を見つけ、それを再現性のある仕組みに落とし込むことです。
- Q採用コストの「平均額」は業種によってどのくらい違いますか?
- A
一般的には、新卒採用で1人あたり50万〜100万円、中途採用では70万〜150万円程度が目安です。
ただし、ITや医療など人材ニーズが高く競争が激しい業界では、200万円を超えるケースもあります。
人材紹介を利用する場合、年収の30〜35%が手数料として発生するため、より高額になる傾向があります。
- Q採用コストのどこを削減するのが一番効果的ですか?
- A
最も効果が大きいのは、「再採用の原因となる早期離職」を防ぐことです。
求人広告費や紹介料を削っても、離職が繰り返されれば結果的にトータルコストは増えてしまいます。
定着率の向上と育成体制の強化は、コスト削減の根本的な対策となります。
- Q生成AIは本当に採用や育成に役立つのでしょうか?
- A
はい、実務に落とし込めば非常に効果的です。
たとえば、面接質問の自動作成、求人票の文案作成、FAQの整備、育成用のケーススタディ作成など、採用〜育成の各プロセスで業務工数を大幅に削減できます。
SHIFT AIでは、こうした活用を現場で定着させるための研修プログラムも提供しています。
- Q採用コスト削減を進める際、最初に何から手をつければよいですか?
- A
まずは「採用単価(=総採用コスト÷採用人数)」を可視化することが第一歩です。
媒体費や人材紹介料だけでなく、面接にかかる人件費や離職後の再教育コストも含めて洗い出すと、改善すべき優先度が見えてきます。
次に、自社で属人化している業務や、改善余地の大きい領域(例:媒体依存・育成の仕組み不足)を洗い出しましょう。
- Q採用担当が1人しかいないのですが、改善できますか?
- A
はい、むしろそのような体制こそ、仕組み化・標準化の導入効果が大きいと言えます。
たとえば、ChatGPTなどを活用して面接テンプレートを自動生成したり、ナレッジ共有のためのマニュアル作成を支援させることで、業務の属人化を防ぐことが可能です。
また、社内の他部門にも採用プロセスの一部を共有することで、負荷分散と組織全体の巻き込みが実現しやすくなります。