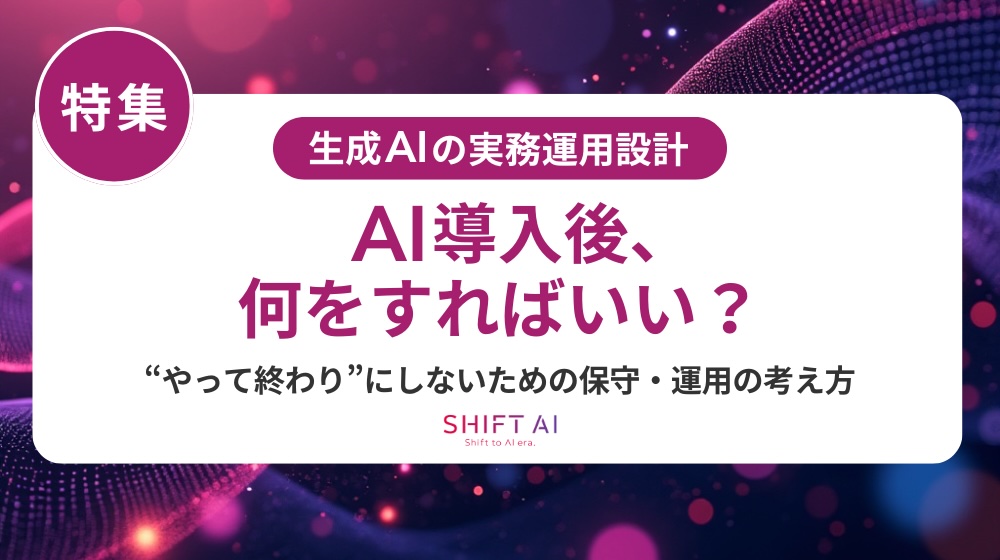生成AIに質問してみたけれど、期待通りの答えが返ってこない――。
そんな経験、あなたにも一度はあるのではないでしょうか?
ChatGPTをはじめとする生成AIは、確かに便利なツールです。
しかしその性能は、「どんな質問をするか」で大きく左右されます。
出力の精度がイマイチなのは、AIのせいではなく、“プロンプト(質問)の設計”に問題があることがほとんどです。
本記事では、生成AIを使いこなす上で欠かせない「質問のコツ」を、基礎から応用、実務への展開方法まで徹底的に解説します。
「使ってみたけど、うまく活用できない」
そんなモヤモヤを抱えるあなたにこそ、読んでほしい内容です。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
生成AIの「質問力」が業務成果に直結する理由とは?
生成AIは「なんでも答えてくれる魔法のツール」ではありません。
むしろ、その性能は“指示の出し方=質問の質”に大きく依存します。
AIは、過去の膨大なデータをもとに「もっともらしい答え」を導き出す存在です。
つまり、曖昧な質問には、曖昧な答えしか返せないという宿命があります。
たとえば「これ、いい感じに直して」と指示しても、AIには「どこを」「どう」「誰向けに」直せばいいか判断できません。
業務でよくあるNG例には、以下のようなものがあります。
- 抽象的すぎる:「わかりやすくして」「もっと端的に」
- 情報が足りない:「この文章を要約して」←誰向け?何の目的?
- 出力形式が未指定:「説明して」←箇条書き?文章?表?
こうした“ふんわりした質問”が、AIとのすれ違いを生みます。
逆に、目的・前提・出力形式を明確にしたプロンプトなら、AIはぐっと精度の高い回答を返してくれるようになります。
だからこそ、「AI活用の第一歩は質問力を磨くこと」なのです。
この“プロンプト設計力”こそが、業務成果に直結するスキルといえるでしょう。
関連記事:AIリテラシーとは何か|育て方・研修設計・定着支援まで企業向けに徹底解説
【基本編】生成AIに効果的に質問する5つのコツ
生成AIの回答精度は、「質問の設計次第で決まる」といっても過言ではありません。
ここでは、誰でもすぐに使える“基本の質問テクニック”を5つご紹介します。
コツ①:目的を明確に伝える
→「何をしたいか」が曖昧だと、AIの出力もブレる
たとえば、「この文章を直して」ではなく、「この文章を上司への報告用に、簡潔かつ丁寧な表現に直してください」と伝えるだけで、出力の精度は大きく変わります。
AIは「指示された目的」に忠実に従うため、まず最初に“ゴール”を明示することが重要です。
コツ②:AIに役割を与える
→「あなたは〇〇の専門家です」で、出力のトーンや深さが変わる
質問の前に「あなたは採用担当のプロです」「あなたは中学生向けに教える教師です」
と役割を設定するだけで、AIはその人格を想定して応答します。
対象や専門性が明確になり、より文脈に沿った答えが得られます。
コツ③:前提条件を与える
→誰向けに?何のために?をセットにして伝える
「この資料を説明して」では情報が足りません。
「この資料を、営業未経験の新入社員向けに、図解中心で説明して」など、前提情報を足すことでAIは“想定読者”にあわせて出力を調整します。
コツ④:出力形式を指定する
→出力が読みづらいと、使えるはずの回答も無駄になる
「箇条書きで3つ」「表形式で」「手順をステップ形式で」など、見やすい・使いやすい形を指定することで、そのまま業務に活用しやすくなります。
コツ⑤:一度に聞かない
→分割して聞くと、出力精度と理解度が上がる
複雑な依頼は、1回の質問で完結させようとせず、「前提を確認」→「要件の整理」→「出力指示」と段階を分けるのがおすすめです。
これは、人間同士のやり取りでも同じですね。
AIにとっても、丁寧な順序設計は理解のカギになります。
これらのコツを押さえるだけでも、「なんか違うな…」と感じていた出力が、「これは使える!」に変わるはずです。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
【応用編】質問を“磨く”ためのプロンプト改善テクニック
基本の質問テクニックを身につけたら、次は「より狙い通りの出力」を得るための改善ステップです。
ここでは、生成AIを思い通りに動かすための“ひと工夫”をご紹介します。
テクニック①:プロンプトに「制約条件」をつける
→出力のブレや冗長さを抑える効果あり
生成AIは、ときに必要以上に長文を返したり、話が逸れたりします。
そんなときは、以下のような制約条件を加えると効果的です。
- 「500文字以内で」
- 「小学生でも理解できるように」
- 「3つのポイントに絞って」
- 「です・ます調で、論理的に」
出力を使いやすく、業務に“そのまま流用できる形”に整えるための工夫です。
テクニック②:出力イメージの例を提示する
→「こういう形でほしい」が伝わるとAIも対応しやすい
たとえば、「以下のような形式でお願いします」とフォーマット例を渡すことで、
出力の形式ブレが大きく減ります。
例
【質問】
以下の情報をもとに、次のような表形式で整理してください。
- タイトル
- 概要
- 対象者
AIは“模倣”が得意です。出力の型を見せれば、それに倣った形で安定した出力が得られます。
テクニック③:「再質問」を前提とした思考ループを設計する
→一発で完璧を狙わず、ブラッシュアップを前提に設計する
生成AIとのやりとりは、一問一答ではなく改善のラリーです。
- まずはざっくり生成してもらう
- 回答を見て「ここの表現をもっと短く」「事例を加えて」など微調整を指示
- 最終版を整える
この“再質問設計”を前提に考えることで、生成AIとの対話は「結果が出るプロセス」になります。
「質問は、最初の一発勝負ではない」
むしろ、“どう改善するか”を前提にした設計こそが、生成AIの本領を引き出すカギです。
【職種別】業務に効く!生成AI質問テンプレート集
ここでは、さまざまなビジネスシーンで使える「プロンプト例(質問文)」と、
それに対する「想定出力イメージ」をセットでご紹介します。
営業|提案資料の構成案を考えたい
プロンプト例
「中小企業向けの業務効率化サービスを紹介する提案資料の構成案を、5ページ分提案してください。1ページごとの目的とタイトルも記載してください。」
想定出力イメージ
- 導入:現状の課題と背景
- 解決策:自社サービスの特徴
- 成果:導入事例と効果
- 導入方法:導入ステップとスケジュール
- 次アクション:問い合わせ・デモ依頼案内
総務・人事|議事録を要約したい
プロンプト例
「以下の会議内容を3点に要約し、箇条書きで出力してください。内容は経営陣向けです。」
出力イメージ
- 新規採用制度の導入について議論され、10月以降の適用で合意
- 営業部のKPI見直し案は次回に持ち越し
- 来期の研修費予算を現状維持とする方向で承認
情報システム部|エラー原因を調べたい
プロンプト例
「以下のPythonエラーの原因と解決方法を、初心者にもわかるように解説してください。出力はステップ形式でお願いします。
TypeError: unsupported operand type(s) for +: ‘int’ and ‘str’」
出力イメージ
- エラーの意味:int型とstr型を足そうとしている
- 原因:数値と文字列を混在させて加算している
- 対処法:str()関数で数値を文字列に変換する、またはその逆
採用・教育担当|面接質問の案を出したい
プロンプト例
「営業職の中途採用面接で使える質問を5つ挙げてください。それぞれの質問に対する意図も添えてください。」
出力イメージ
- 「これまでの営業実績で最も苦労した経験を教えてください」
→忍耐力と課題解決力を評価 - 「新しい商材を扱うとき、どのように学びますか?」
→自主学習力・吸収力を評価
(以下略)
これらのテンプレートをベースに、“自社用にアレンジすることでナレッジ資産化”も可能です。
関連記事:生成AIで業務効率化を実現!業種別の活用事例6選と導入ポイントを解説
【落とし穴】生成AIにうまく質問できない人がやりがちなNG例
生成AIがうまく答えてくれないとき、つい「AIの精度が低いのでは?」と考えがちです。
ですが、多くの場合の原因は“質問の仕方にある”ことがほとんどです。
ここでは、ありがちなプロンプトの失敗パターンを紹介します。
どれもよく見られる“落とし穴”なので、要注意です。
NG例①|抽象的すぎる指示:「いい感じに直して」
- ❌:「この文章を、いい感じに整えて」
- ✅:「この文章を、社内報告書としてフォーマルに、簡潔に修正してください」
なぜダメ?
「いい感じ」とは何か、AIには判断できません。
修正の方向性を“目的ベース”で明示するのが鉄則です。
NG例②|複数の要望を一度に詰め込む
- ❌:「この資料を要約して、図表にして、さらに改善点も出して」
- ✅:「まずは要約だけお願いします。次に図表化、最後に改善点と順番に依頼」
なぜダメ?
処理対象が多いと、AIが意図を混同しやすくなります。
複雑な依頼はステップを分けて、段階的に進めるのが正解です。
NG例③|背景や前提の省略:「これ、直して」
- ❌:「これ、修正お願いします」
(※何の目的か不明、誰向けの資料か不明) - ✅:「以下の文章を、クライアント向けの提案書の冒頭文として、丁寧に修正してください」
なぜダメ?
目的や読み手が不明だと、AIが適切なトーンや構成を選べません。
“誰に・何のために”を伝えるのは最低条件です。
NG例④|出力形式を指定していない
- ❌:「わかりやすく説明して」
- ✅:「以下の内容を、小学生でも理解できるように、3つの箇条書きで説明してください」
なぜダメ?
“わかりやすさ”の定義も人それぞれです。
具体的な出力形式を指定すれば、意図が伝わりやすくなります。
これらのNG例を知っておくだけでも、質問の質は確実に上がります。
プロンプトの失敗は、AI活用が社内に広がらない大きな原因にもなるため、避けられるミスはあらかじめ潰しておきましょう。
【組織で成果を出すには】質問設計を標準化するという考え方
生成AIは、「使える人」が1人いれば成果が出る──そう考えていませんか?
実際には、その“属人化”こそが、AI活用が定着しない最大の壁です。
なぜ、うまくいく人といかない人が分かれるのか?
質問の仕方(=プロンプト設計)にはスキルの差が出ます。
ですが、これは「センス」ではなく「知識と型」で改善できる領域です。
つまり、「一部の人がうまく使っている」状態から、「誰でも一定レベルで使える」状態に移行するには、プロンプトを組織的に“標準化”することが不可欠なのです。
質問設計の標準化とは?
- よく使う質問のテンプレートを整備する
- 想定される回答形式とその使い方を共有する
- 用途ごとのプロンプト集をチーム内にストックする
- 「うまくいったプロンプト」の再利用を促すナレッジ運用
このように、“型”と“ルール”を持つことで、誰でも迷わず活用できる状態を実現できます。
「使える人」だけに頼らない運用が、全社成果を生む
- 属人化→特定の担当者に質問が集中し、現場が回らなくなる
- 使い方がバラバラ→成果が出るチームと出ないチームで差がつく
- 教育がない→「なんとなくで使ってる」状態が続く
だからこそ、“質問設計の標準化×教育”のセット導入が重要なのです。
関連記事:AIリテラシーは“教える側”にも必要?教育者に求められる4つの力と落とし穴対策
まとめ|質問の質が、生成AI活用の成果を決める
生成AIの出力は、その“質問の質”で決まる――。
これは、実際に業務に活用している多くの現場で実感されている事実です。
曖昧な質問からは曖昧な回答しか返ってきません。
逆に、目的・前提・出力形式を明確に設計した質問であれば、生成AIは、非常に有用なアシスタントになります。
今回ご紹介したコツやテクニックは、どれも再現性が高く、“センスではなく構造”で誰でも再現可能な内容ばかりです。
そして、これらを属人化させず、組織全体で使えるようにするためには、質問設計の標準化と、教育の仕組み化が欠かせません。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
- Q生成AIにうまく質問できるようになるには、何から始めればいいですか?
- A
まずは「目的」「前提」「出力形式」を明確に伝える質問設計を意識しましょう。
記事内で紹介した5つの基本コツを押さえるだけで、出力の精度は大きく変わります。
- QChatGPTや生成AIに同じ質問をしても、人によって答えが違うのはなぜですか?
- A
プロンプト(質問文)の表現や構成が微妙に違うだけで、AIの解釈は変わります。
また、GPTのバージョン(3.5と4.0など)によっても出力傾向に差があります。
- Q業務でよく使う質問をテンプレート化しておきたいのですが、どうすればいいですか?
- A
よく使う業務(議事録要約・資料構成・アイデア出しなど)ごとに、
想定する目的・対象・出力形式をパターン化し、テンプレートとして整理しましょう。
チーム内で共有しておくと、属人化を防ぎやすくなります。
- Q部署内でプロンプトの使い方に差が出て困っています。全社的に教育する方法はありますか?
- A
生成AIの活用は、「使える人」だけに頼ると属人化します。
全社で一定の活用レベルを担保するには、AIリテラシー研修や質問設計の標準化が不可欠です。
- Q回答がいまいちでも、どう改善すればいいかわからないのですが…
- A
一度で完璧を目指す必要はありません。
「どこが違うか」を自分なりに言語化し、再質問・再調整の思考ループを回すことで、
プロンプトはどんどん精度が上がっていきます。