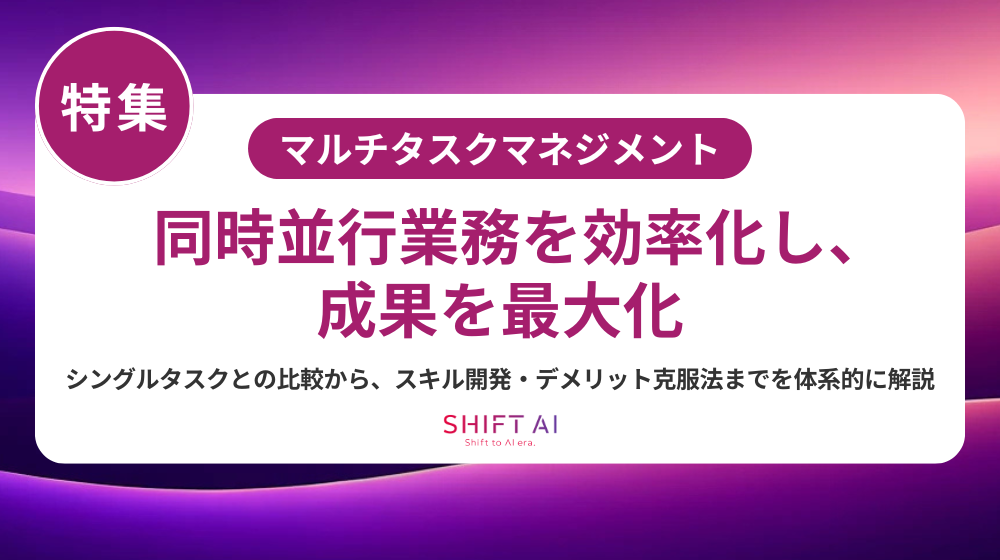「あの人はいつも複数の作業を同時にこなしていてすごいな」と感じる一方で、「自分はひとつのことしか集中できない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
マルチタスクとシングルタスク、どちらが効率的なのか?この疑問に対する答えは、実は「使い分け」にあります。
脳科学の研究によると、人間の脳は本来シングルタスク向きに設計されていますが、現代のビジネス環境ではマルチタスクが求められる場面も多く存在します。
特にAI時代の到来により、生成AIツールを活用した効率的なタスク管理が可能になりました。本記事では、マルチタスクとシングルタスクの違いから実践的な活用法まで、2025年最新の知見をもとに詳しく解説します。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
マルチタスクとシングルタスクの違いと定義
マルチタスクとシングルタスクは、脳の処理方法が根本的に異なる作業手法です。どちらにもそれぞれの特徴があり、適切な場面で使い分けることが重要になります。
💡関連記事
👉マルチタスクとは?定義・メリット・デメリット・やり方を解説【2025年版】
マルチタスクとは複数作業を同時進行すること
マルチタスクとは、複数のタスクを同時に、または短時間で切り替えながら進行する作業手法です。
ビジネスシーンでは日常的に行われており、例えば会議に参加しながら議事録を作成したり、電話対応をしながらデータ入力を行ったりする場面が該当します。
スマートフォンの普及により、多くの人が無意識にマルチタスクを実行しています。パソコンで資料作成をしながらメッセージアプリをチェックする行為も、典型的なマルチタスクと言えるでしょう。
シングルタスクとは1つの作業に集中すること
シングルタスクとは、1つの作業のみに集中して取り組む作業手法です。
人間の脳は本来、シングルタスク向きに設計されています。1つの作業に集中することで、より深い思考と高い品質の成果物を生み出せるのが特徴です。
プログラミングや企画書作成など、創造性や論理的思考が求められる業務では、シングルタスクの方が効果的とされています。集中力を1点に向けることで、作業効率と品質の両方を向上させられます。
脳科学的に処理方法が根本的に異なる
人間の脳は実際には複数の作業を同時処理できず、高速でタスクを切り替えているだけです。
脳科学の研究によると、マルチタスク時の脳は前頭前野で頻繁な切り替え作業を行っており、これが認知負荷を高める原因となっています。
タスクの切り替え時には集中力の回復に時間がかかり、この「切り替えコスト」がマルチタスクの生産性低下を招く主要因となっています。
マルチタスクとシングルタスクのメリット・デメリット
マルチタスクとシングルタスクには、それぞれ異なるメリットとデメリットがあります。業務内容や状況に応じて適切に使い分けることで、生産性を最大化できます。
マルチタスクは複数プロジェクトを効率化できる
マルチタスクの最大のメリットは、複数のプロジェクトを同時進行できることです。
締切が重複する複数の業務を抱えている場合、マルチタスクにより全体的な進捗を管理しやすくなります。また、一つの作業で行き詰まった際に、別の作業に切り替えることで時間を有効活用できるでしょう。
さらに、複数の業務を同時に把握することで、プロジェクト間の関連性や全体像を見渡しやすくなります。これにより、より戦略的な意思決定が可能になるのです。
マルチタスクは集中力低下とストレスを招く
マルチタスクの大きなデメリットは、集中力の分散によるパフォーマンス低下です。
タスクを切り替える度に脳は再調整が必要となり、本来のパフォーマンスを発揮できません。結果として、それぞれの作業の品質が低下してしまう可能性があります。
また、複数の業務を同時に抱えることで、精神的な負担が増加します。全ての作業が中途半端になりがちで、達成感を得にくくなることもストレス要因となるでしょう。
シングルタスクは品質向上と持続性を実現する
シングルタスクの最大のメリットは、高い集中力による品質向上です。
一つの作業に集中することで、深い思考と創造性を発揮できます。複雑な問題解決や新しいアイデアの創出など、高度な知的作業においてシングルタスクは特に効果的です。
また、作業の完了による達成感を得やすく、モチベーションの維持にもつながります。ストレスレベルも低く抑えられるため、長期的な生産性の維持が可能になるのです。
マルチタスクが苦手な人の特徴と克服方法
マルチタスクが苦手な人には共通する特徴があります。これらの特徴を理解し、適切なアプローチを取ることで、マルチタスクスキルを向上させることが可能です。
完璧主義でこだわりが強すぎる
完璧主義の人は、一つひとつの作業に高い品質を求めるため、マルチタスクが困難になります。
完璧主義者は作業の途中で他の業務に切り替えることに強いストレスを感じがちです。「中途半端な状態で放置したくない」という心理が働き、結果的にマルチタスクを避ける傾向があります。
このタイプの人は、まず「80%の完成度で一旦区切る」という考え方を身につけることが重要です。完璧を求めすぎず、段階的に作業を進める習慣を作りましょう。
優先順位をつけるのが下手である
優先順位をつけるのが苦手な人は、どの作業から手をつけるべきか迷いがちです。
重要度や緊急度を適切に判断できないため、複数の作業を効率的に進められません。結果として、全ての作業が中途半端になってしまう可能性があります。
改善策として、アイゼンハワー・マトリックスなどのフレームワークを活用しましょう。重要度と緊急度の軸で作業を分類することで、明確な優先順位を設定できます。
スケジュール管理ができていない
スケジュール管理が苦手な人は、時間の見積もりや配分が適切にできません。
各作業にかかる時間を正確に把握できないため、複数のタスクを同時進行させると混乱してしまいます。締切に追われる状況が続き、品質の低下を招くことも少なくありません。
解決策として、まず各作業の所要時間を記録する習慣をつけましょう。タスク管理ツールを活用し、視覚的にスケジュールを管理することで改善が期待できます。
AI時代のマルチタスク・シングルタスク活用法
AI技術の進歩により、従来のタスク管理の常識が変わりつつあります。生成AIを効果的に活用することで、これまで以上に効率的なマルチタスクとシングルタスクが実現可能です。
生成AIでマルチタスクを効率化する
生成AIを活用することで、人間の認知負荷を軽減しながらマルチタスクを実行できます。
ChatGPTなどの生成AIに定型的な作業を任せることで、人間はより創造的で戦略的な思考に集中できます。例えば、AI に資料の下書きを作成させながら、同時に会議の準備を進めるといった使い方が可能です。
また、AI による情報整理や要約機能を活用することで、複数の情報源からの情報収集と分析を並行して行えます。これにより、従来よりも高品質なマルチタスクが実現できるでしょう。
デジタル疲れを防ぐマルチタスク管理をする
現代のデジタル環境では、通知やメッセージによる中断が生産性を大幅に低下させています。
Slack、Teams、メールなど複数のコミュニケーションツールを同時に監視することで、常に注意が分散してしまいます。これを防ぐために、通知時間を制限し、集中タイムを設けることが重要です。
ノイズキャンセリング機能やフォーカスモードを活用し、意図的に情報を遮断する時間を作りましょう。デジタルデトックスの時間を設けることで、質の高いマルチタスクが可能になります。
AIでシングルタスクの集中度を高める
AI による情報収集と整理を並行させることで、人間はより深い思考に集中できます。
背景調査や関連情報の収集を AI に任せることで、人間は核心的な分析や意思決定に専念できます。この役割分担により、シングルタスクの品質を大幅に向上させることが可能です。
組織全体でこうした AI 活用スキルを身につけることで、個人レベルから会社全体の生産性向上を実現できるでしょう。
組織でマルチタスクとシングルタスクを使い分ける方法
組織レベルでのタスク管理最適化には、職位や業務内容に応じた戦略的アプローチが必要です。全社的な生産性向上を実現するための具体的な方法を解説します。
職位別に最適なタスク管理を設計する
職位や役割に応じて、マルチタスクとシングルタスクの最適な配分が異なります。
管理職は戦略的思考をシングルタスクで行いながら、情報収集や部下とのコミュニケーションをマルチタスクで処理するのが効果的です。一方、専門職は深い集中を要する業務でシングルタスクを重視すべきでしょう。
中間管理職は、チーム調整のマルチタスクと専門業務のシングルタスクのバランスが重要になります。個人の特性と職務要件を総合的に判断し、最適な作業スタイルを設計することが求められます。
チーム全体の生産性を最大化する戦略を立てる
プロジェクトのフェーズや目標に応じて、チーム全体のタスク管理戦略を調整する必要があります。
企画立案フェーズではシングルタスクによる深い思考を重視し、実行フェーズではマルチタスクによる効率的な進行管理が効果的です。チームメンバーの個人特性も考慮し、適材適所の配置を行いましょう。
定期的にチーム全体の生産性を測定し、タスク管理手法の効果を検証することも重要です。データに基づいて継続的に改善を行うことで、最適な生産性を維持できます。
全社員に効率的なタスク管理を教育する
組織全体の生産性向上には、全社員が効率的なタスク管理スキルを身につけることが不可欠です。
個人レベルでの最適化だけでなく、組織全体として統一されたタスク管理手法を導入することで、より大きな効果を期待できます。特に、AI 活用スキルを組み合わせた包括的な能力開発が重要になります。
体系的な研修プログラムを通じて、マルチタスクとシングルタスクの適切な使い分け方法を全社員が習得することで、組織の競争力を大幅に向上させられるでしょう。
まとめ|マルチタスクとシングルタスクの使い分けで生産性を向上させよう
マルチタスクとシングルタスクには、それぞれ異なる特徴とメリットがあることが分かりました。重要なのは、どちらが優れているかを決めることではなく、業務内容や個人の特性に応じて適切に使い分けることです。
完璧主義や優先順位の設定が苦手な方は、まずタスクの細分化から始めてみましょう。また、AI時代の到来により、生成AIを活用した効率的なタスク管理が可能になっています。個人レベルでの工夫に加えて、組織全体で統一されたタスク管理手法を導入することで、より大きな効果を期待できるでしょう。
今日から実践できる小さな改善から始めて、段階的にスキルを向上させることが成功への近道です。
さらに体系的にスキルを身につけたい場合は、専門的な研修プログラムの活用も一つの選択肢となります。

マルチタスクとシングルタスクに関するよくある質問
- Qマルチタスクは本当に効率が良いのですか?
- A
マルチタスクは状況によって効率性が変わります。人間の脳は本来シングルタスク向きに設計されており、タスク切り替え時に集中力の回復時間が必要になるためです。複数のプロジェクトを並行して進める場合はマルチタスクが有効ですが、創造性を要する業務ではシングルタスクの方が高い成果を生み出せます。
- Qシングルタスクだけでは仕事が回らない場合はどうすれば良いですか?
- A
現実的には完全なシングルタスクは困難な場合が多いため、意図的なタスク切り替えを行う「タスクシフト」という手法が効果的です。2時間ごとに作業を区切り計画的にタスクを切り替える方法や、生成AIを活用して定型作業を自動化し、人間はより重要な業務に集中できる環境を作ることが可能です。
- Qマルチタスクが得意な人と苦手な人の違いは何ですか?
- A
マルチタスクの得意・不得意は、主に個人の特性や思考パターンによって決まります。完璧主義傾向が強い人や優先順位付けが苦手な人は、マルチタスクに困難を感じやすい傾向があります。ただし適切なトレーニングとツールの活用により、マルチタスクスキルは向上可能です。まずは自分の特性を理解することから始めましょう。
- QAI時代にマルチタスクやシングルタスクはどう変わりますか?
- A
AI技術の発達により、従来のタスク管理の常識は大きく変化しています。生成AIに定型作業を任せることで、人間はより創造的で戦略的な思考に集中できるようになりました。AIによる情報収集と人間の分析を並行させることで質の高いマルチタスクが実現可能です。AI支援により深い集中を要するシングルタスクの品質も向上させられるでしょう。