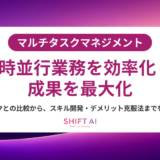最近、中間管理職が次々と退職していく——そんな職場の変化を目の当たりにし、「自分もこのままでいいのか?」と不安を感じていませんか?
かつては安定したポジションとされていた中間層ですが、いまや板挟み・低評価・将来不安といったプレッシャーを抱えながら働く“苦しいポジション”となっています。
実際に辞めていく人たちは、どんな理由で、どんな覚悟でその決断をしたのでしょうか?
そして、辞めなかった人たちは何を選び、どう生き抜いているのでしょうか?
本記事では、中間管理職が辞めていく構造的な理由から、実際の退職後キャリア、そして最後には「辞める・残る」に縛られない“第三の選択肢=変わる”という視点まで、徹底的に掘り下げて解説します。
AI時代を生き抜く管理職として、いま本当に必要な行動とは何か?
不安の先に希望を見つけるヒントが、きっとここにあります。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ中間管理職は辞めていくのか?【構造的な背景】
中間管理職の退職が相次いでいるのは、単なる偶然や個人の都合ではありません。
その背景には、“役職の構造そのもの”に起因する共通の課題が存在しています。
現場と経営のあいだで調整を求められ、成果に対して十分な裁量や評価が与えられず、
しかも企業の変化が遅い中では「このままここにいても成長できない」と感じる人も少なくありません。
ここでは、そうした中間層が抱える構造的ストレスを4つの観点からひもとき、
なぜ今「管理職=辞めたくなる役職」になってしまっているのかを明らかにしていきます。
役割と責任のアンバランスに疲弊している
中間管理職は、プレイヤー業務に加えてチームマネジメント・部下育成・経営層との折衝など、幅広い役割を担っています。
しかし実態としては、「任されているのに、裁量がない」「責任だけが重い」というケースが少なくありません。
例えば、現場の声を経営に届けても聞き入れられず、成果を出しても評価は不明瞭。
業績はチーム単位で追われるのに、報酬や査定には反映されにくい。
「この役割、誰が得しているんだろう?」と感じた瞬間、モチベーションは一気に下がります。
裁量もない、評価もされない“板挟み構造”
中間層のつらさを最も象徴するのが「板挟み」という状態です。
上からは「数字を出せ」と要求され、下からは「働きづらい」と不満が上がる。
その調整に追われながら、自分の意見や判断が尊重される場面は限られています。
しかも最近では、管理職であっても成果に直結しない“空気の仕事”が増加。
「役職者としての責任はあるが、権限がない」というねじれた構造が、“抜け道のない消耗戦”を生んでいるのです。
管理職なのにマネジメントできない現実
本来、管理職とは“人やチームを動かす”立場のはずです。
ところが実際は、日々の業務に忙殺され、人材育成や戦略設計に手が回らないという声が多く聞かれます。
さらに、プレイングマネージャーとして現場を兼任していると、どちらにも全力を注げないというジレンマも。
結果、マネジメントの本質から遠ざかり、「自分は何のために管理職になったのか」という疑問を抱き始めるのです。
数字重視・変化なしの環境に将来を見出せない
「売上を上げろ」「コストを下げろ」——
これまで通用していた評価軸が、時代の変化に追いつかなくなっています。
にもかかわらず、多くの企業では管理職に“変化を拒む文化”が根づいているのが現実です。
中間層である自分は変わりたいのに、会社は変わらない。
このギャップこそが「もうここにはいられない」と思う決定打になるのです。
管理職を辞めた人たちは今、どうしているのか?
「辞めたい」と思っても、その後のキャリアを考えると不安で踏み切れない——。
そんな気持ちを抱えている方も多いのではないでしょうか。
では、実際に退職という決断をした中間管理職たちは、その後どうしているのか?
「辞めた人=キャリアを手放した人」ではありません。
むしろ多くのケースで、新しい価値観に沿った“再設計されたキャリア”を歩んでいるのです。
このパートでは、プレイヤー復帰・独立・スキル転換など、リアルな事例をもとに“辞めた後の今”を解き明かしていきます。
プレイヤーに戻ることで再評価される人たち
管理職を辞めたあと、あえてプレイヤー職に戻るという選択をする人は少なくありません。
現場で自分の専門スキルを活かし、成果をダイレクトに出せる立場に戻ることで、「やっぱりこの仕事が好きだった」と再確認する人もいます。
プレッシャーや責任の大きさに比べて、評価や裁量が乏しかった管理職時代と比べ、
成果と評価が直結するシンプルさに満足感を感じる人も多いのです。
特にスキルや実績のある中間層は、スタートアップやベンチャーなどで即戦力として再評価されやすい傾向があります。
「もう一度、自分の手で仕事を動かしたい」という気持ちを実現する場として、プレイヤー職への復帰は有効な選択肢になっています。
副業・独立・フリーランスに転身する人も
中間管理職の退職後キャリアで増えているのが、「会社員をやめて自分で働く」という道です。
特に近年は、副業・フリーランス・個人事業主といった多様な働き方が現実的な選択肢として広がっています。
過去に築いた人脈や専門性を活かし、コンサルタントや研修講師、業務委託などで独立後に安定した収入を得ている人も多いのが特徴です。
一方で、営業力や事業の継続性といった壁もあり、「なんとなく辞めてなんとかなる」ほど甘くはありません。
そのため、退職前から副業やスキルの棚卸しを進めておくことが重要です。
「この会社ではできないけれど、自分にはこんな働き方がある」——そう思える準備が、安心して退職を選ぶ土台になります。
辞めた後に後悔する人・しない人の違いとは?
すべての退職がうまくいくとは限りません。
実際に辞めた後で、「思っていた以上に孤独だった」「スキル不足を痛感した」と後悔する人もいます。
一方で、前向きにキャリアを再構築し、やりがいや自由を手にした人たちも確実に存在します。
この違いはどこにあるのでしょうか?
最も大きな差は、「辞める前に何をしていたか」です。
自分の市場価値を把握していたか、スキルアップや人脈づくりを始めていたか。
辞める・辞めないにかかわらず、「変わる準備」ができていた人は、環境が変わっても前向きに動き続けられるのです。
“辞めた後の自分”に備える行動こそが、後悔しないキャリア選択のカギになると言えるでしょう。
辞めたいけど辞められない中間管理職のリアル
「辞めたい」という気持ちはあっても、実際にその一歩を踏み出すのは簡単ではありません。
中間管理職というポジションには、生活や責任、将来への不安が複雑に絡み合っているからです。
ここでは、「辞めたくても辞められない」と感じている人が抱えがちな3つの葛藤を取り上げ、
その背景にある心理やリアルな声に迫っていきます。
「生活」「年齢」「家族」が決断を鈍らせる
辞める=収入が途絶える。
中間管理職世代にとって、この現実的なリスクは重くのしかかります。
子どもの教育費、住宅ローン、親の介護——誰かのために働き続けなければならない状況が、多くの人に共通しています。
さらに、40代・50代になると転職市場での競争も激しくなり、「次が見つからなかったらどうしよう」という不安が、決断を鈍らせるのです。
「辞めたいけれど、辞めることが許されない」。
そんな自責のような気持ちを抱えて、今日も同じ職場に向かっている——そんな現実があります。
「自分の価値が社外で通じるのか」への不安
「今の会社ではそこそこ評価されているけれど、外に出て通用するのだろうか?」
そんな疑問を持ちながら、行動に移せず立ち止まっている人も多いのではないでしょうか。
管理職としての経験があっても、それが汎用的なスキルとして認識されていないと、転職市場では武器になりづらい。
業務内容が属人的だったり、会社特有の文化に依存していたりすると、余計にそう感じてしまいます。
しかし、これは裏を返せば、「武器にできる形に変えれば価値になる」ということでもあります。
その第一歩が、“自分のスキルの言語化”と“社外目線での棚卸し”です。
「何か変えたい」のに方法がわからない葛藤
「このままじゃダメだ」と思ってはいても、何をすればいいのかわからない。
気持ちだけが先行し、行動に移せない状態が長く続くと、自己肯定感の低下や無力感につながりやすくなります。
毎日忙しく働く中で、「変わる」ための余力が残っていない——。
そんな“時間も気力もない状態”に陥ってしまうと、改善どころか悪循環が進んでしまいます。
だからこそ、必要なのは「変わる方法を知ること」です。
方法さえ見えれば、小さくても一歩を踏み出すことができる。
その一歩が、後のキャリアを大きく左右します。
「辞める」でも「残る」でもない、“変わる”という第三の選択肢
「辞めたいけれど辞められない」「残っても将来が見えない」——
そんな二択の板挟みに悩む中間管理職が、いま見落としがちな“もうひとつの選択肢”があります。
それが、辞めずに“自分を変える”という選択肢です。
ここでは、「変わる」ことがなぜ現実的で、むしろ一番リスクの少ない選択なのか。
そして、そのためにどんな行動を起こすべきかを、具体的に紹介していきます。
キャリアの軸を変える=働き方を変えること
キャリアに迷いが生じたとき、多くの人が「職場を変えること」ばかりに意識を向けがちです。
でも実は、環境ではなく“自分の軸”を変えることで、今いる場所で状況を大きく動かせることもあるのです。
たとえば、「マネジメント=我慢」と思い込んでいた軸を、「マネジメント=変化を生み出す役割」へと置き換える。
自分が会社やチームに与えられる価値を再定義することで、今の仕事の意味も、将来の可能性も変わってきます。
辞める前に、自分の中の“当たり前”を見直すこと。
それが「変わる」ための第一歩になります。
会社にいながら“価値のある人材”に進化する方法
「会社に残る=停滞」ではありません。
むしろ、今いる環境を活かして“社内で変わる”ことができれば、それは極めて戦略的な行動です。
たとえば、業務の見直しや改善提案に生成AIを取り入れてみる。
マネジメントの仕組みをデータドリブンで考えてみる。
こうした“変革”を担う存在になることで、自分自身の価値は格段に高まります。
今後は、「AIと共に動ける管理職」が企業に求められる時代です。
スキルを磨き、意識を切り替えるだけでも、会社にいながらキャリアの再設計は可能です。
スキル再構築が中間層キャリアの分岐点になる
変わるには、“学び直し”が必要です。
でもそれは、決して遅すぎることではありません。
むしろ、中間管理職は豊富な業務経験があるからこそ、AIや新しいツールを「どう活用すれば現場が変わるか」がわかる立場にあります。
今後求められるのは、「AIを使える」ことではなく、「AIを使ってチームを動かせる」人材です。
スキルの再構築は、単に生き延びるためではなく、キャリアを“武器化”するための手段です。
あなた自身の価値を上げる学びが、これからの数年を大きく変えていくはずです。
AI時代に管理職が磨くべき“新しいスキル”とは?
これからの時代、管理職がキャリアを維持・発展させるためには、従来の経験や肩書きだけでは不十分です。
急速に変化するビジネス環境では、「自分はマネジメント側だから技術はわからなくてもいい」という考えが通用しなくなりつつあります。
特に、生成AIや業務自動化の進展により、プレイヤー業務は再定義されつつあります。
その中で、管理職は“人を動かす”だけでなく、“変化を設計できる”存在へと進化することが求められているのです。
では、具体的にどんなスキルが求められているのか?
今後を見据えた、3つの重要スキルを紹介します。
現場指示ではなく“変化を設計する力”が問われる
従来の管理職は「現場の進捗を管理し、業務を滞りなく進める」ことが主な役割でした。
しかし今後は、単なる指示出しではなく、「変化の方向性を描き、実行計画を設計する力」が問われます。
業務フローの見直し、部下の業務に対する再配分、新しいツールやAIの導入といった取り組みは、
従来の“安定志向の管理職”には荷が重いと感じられるかもしれません。
けれども、その「設計力」こそが、AI時代において管理職の最大の武器になります。
部下の力を最大化するには、まずは「業務の設計者」である自分が変化を受け入れる必要があるのです。
生成AIを業務に組み込むマネジメント力
今や、ChatGPTやCopilotなどの生成AIは、メール文書作成・議事録生成・アイデア出しなどに幅広く活用されています。
とはいえ、それを「部下が勝手に使っている」状態で放置していては、組織としてのリスク管理や効率化は進みません。
これからの管理職には、AIの利用をチーム戦略に落とし込む“実践的マネジメント力”が求められます。
- 業務フローのどこにAIを活用するか
- 利用ルールをどう整備するか
- 成果や業務時間にどう反映させるか
このような「AI活用をマネジメントする力」こそが、組織に新たな価値をもたらします。
自分とチームの価値をアップデートできる人材へ
管理職が本当に目指すべきは、「役職で評価される人」ではなく、「価値を提供し続けられる人材」です。
そのためには、自分自身だけでなく、チームや部下の能力も引き上げる必要があります。
たとえば、AIツールの使い方を共有したり、マニュアルを作成したりすることで、
チーム全体の生産性や満足度を高める動きそのものが、次世代のリーダーシップといえるでしょう。
価値をアップデートし続ける人材は、会社の中でも社外でも必要とされ続けます。
だからこそ、今、学ぶ。今、変わる。その選択が未来の武器になります。
迷いを“行動”に変えるために、今すぐできること
ここまで読み進めてきたあなたは、きっと「このままではいけない」と感じているはずです。
でも、気持ちだけがあっても、実際に動き出すのは難しい。
だからこそ大切なのは、“小さな一歩”を今日始めることです。
ここでは、退職に踏み切る前でも、会社に残りながらでもできる、「行動に変える3つのステップ」を紹介します。
このステップを踏むことで、あなたのキャリアは確実に前に進み始めます。
今の仕事・環境・スキルを棚卸ししてみる
まず最初にやるべきは、「自分の現在地」を客観的に把握することです。
仕事の内容、役割、日々の負担、評価のされ方——これらを紙に書き出すだけでも、
「何が不満で、何に満足しているのか」が見えてきます。
あわせて、自分が持っているスキルや経験、他者からよく頼られる仕事なども整理しましょう。
それらが「自分の価値」や「強み」を再発見するヒントになります。
この棚卸しは、辞める・残るにかかわらず、キャリアの再構築に不可欠な第一歩です。
外の情報・市場価値を知る
今の会社の中だけにいると、自分の市場価値や他社での働き方が見えづらくなりがちです。
そこで、転職サイトの自己分析機能を使ってみたり、キャリアコーチの話を聞いてみることも有効です。
また、同年代・同職種でAIツールやDXに取り組んでいる人たちの事例を見るだけでも、
「自分にもまだできることがある」と前向きな刺激になります。
自分の可能性を知ることは、不安を減らすことにつながります。
変化の第一歩に「AI×キャリア研修」を活用する
変化の波に備えるなら、学び直し(リスキリング)から始めるのが最も確実です。
中でも、生成AIや業務効率化ツールの活用を軸にした研修は、中間管理職の「変わりたい」を現実のものにする手段として非常に注目されています。
たとえ辞めなくても、AIリテラシーを身につけることで、
社内での評価が変わる/業務の負担が減る/新しい役割が生まれるといった変化が起こりえます。
「今すぐ会社を辞めるわけではないけれど、何か始めたい」——
その気持ちを、未来に効く行動へと変えてみませんか?
まとめ:辞めるか、残るかではなく「変わる」ことで道は拓ける
中間管理職が次々と辞めていく時代。
それは単に“我慢が足りない人が増えた”のではなく、役職の構造と時代の変化が噛み合わなくなっているという背景があります。
この記事では、
- 辞めた人がどこへ向かっているのか
- 残る人が感じるモヤモヤの正体
- AI時代に必要なスキルの再定義
などを通して、あなたの今とこれからを整理するヒントをお届けしました。
そして今あなたが感じている「何かを変えたい」という想いこそが、キャリアにとって最も大切な原動力です。
- Q中間管理職を辞めた後、年収は下がるのでしょうか?
- A
一時的に下がるケースもありますが、戦略次第で維持・向上も可能です。
プレイヤー復帰や専門職への転身、副業・起業といった道を選ぶ人も増えています。
特に、AIやDXに強い人材は再評価されやすくなっているため、スキルアップは大きな武器になります。
- Q「上からも下からも板挟み」の状況が辛いです。改善策はあるのでしょうか?
- A
業務の見える化やAIツールの導入が、負担軽減に有効です。
マネジメントの中間層が「業務のボトルネック」になりやすい今、
情報整理やナレッジ共有を自動化することで、板挟みからの解放につながります。
- Q辞めるか残るか、判断の基準がわかりません…。
- A
判断には「価値観」と「変化への耐性」の両軸を持つことが大切です。
今の職場で“何を変えたいか”“何を変えたくないか”を明確にすることで、
自分にとっての最適解が見えてきます。
- QAIやDXの知識がまったくないのですが、今からでも間に合いますか?
- A
はい、むしろ今が絶好のタイミングです。
中間管理職だからこそ、現場と経営の橋渡し役として“翻訳者”のような役割が求められています。
生成AIやツールの基本を押さえるだけでも、社内での価値は大きく変わります。
- QAI研修って部下向けでは?マネジメント層にも必要ですか?
- A
管理職こそ“AIリテラシー”が求められる時代です。
現場任せにせず、自分が使いこなすことで、活用推進・業務改善・リスク管理の三拍子が整います。