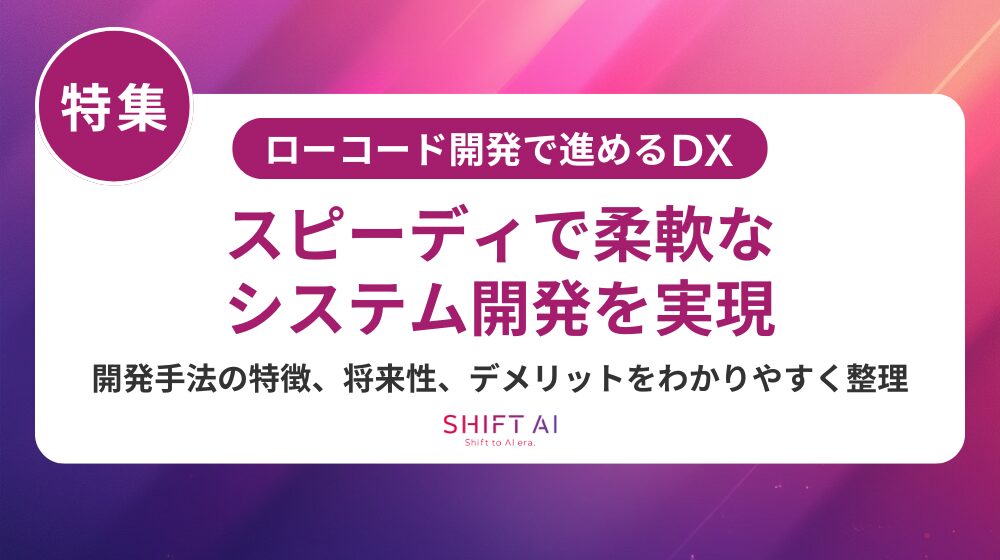企業のDX推進が加速するなかで、「ローコード開発」は注目度を高めています。少ないコードでアプリやシステムを構築できるため、IT人材不足や開発スピードの遅れといった課題を補う手段として導入が広がっています。
一方で、「本当に将来性があるのか」「複雑な業務にも対応できるのか」と疑問を持つ声も少なくありません。
本記事では、ローコード開発の基本から市場予測、生成AIとの融合による進化、導入における課題までを徹底解説します。経営層・情報システム部門・エンジニアそれぞれにとっての影響を整理し、これから導入を検討する企業が押さえておくべきポイントを提示します。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
ローコード開発とは?ノーコードとの違いと現状整理
ローコード開発の定義と特徴
ローコード開発とは、従来のようにすべてをプログラミング言語で記述するのではなく、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)を使いながら、最小限のコードでシステムを構築する手法です。ドラッグ&ドロップやテンプレートを活用できるため、開発スピードが速く、専門エンジニアでなくても一定の開発が可能になります。近年は業務アプリや社内システムの内製化を目的に、多くの企業で採用が進んでいます。
ノーコードとの違い
ローコードとよく比較されるのが「ノーコード開発」です。ノーコードは文字通りコードを一切書かずにアプリを構築できるのに対し、ローコードは必要に応じてコードを書き足せる柔軟性がある点が特徴です。ノーコードは小規模・単機能アプリに適しており、ローコードはより複雑な要件や既存システムとの連携にも対応しやすいという違いがあります。
関連記事:
ノーコードとは?メリット・デメリットとローコードとの違いを徹底解説
国内外での普及状況
調査会社のレポートによれば、世界のローコード開発市場は年平均20%前後の成長を続けており、国内でも行政・金融・製造業を中心に導入が拡大しています。背景には「2025年の崖」問題や、IT人材不足の加速があります。これまで外注が当たり前だった開発を、社内主導でスピーディに行う動きが強まっており、ローコードはその中核を担いつつあります。
関連記事:
ローコード開発で具体的に何ができる?メリット・デメリットから導入手順まで解説
ローコード開発が注目される背景
IT人材不足と開発スピードへのニーズ
国内では2030年までに最大79万人のIT人材が不足すると予測されており、開発リソースの逼迫は深刻化しています。従来型のスクラッチ開発では要件定義から運用までに長い時間を要し、ビジネスのスピードについていけないケースが増えています。ローコード開発は、少人数でも短期間でアプリを構築できるため、人材不足を補う選択肢として注目されています。
DX推進と内製化トレンド
企業のDX推進においては、業務部門が主体的にシステムを作り、改善を繰り返す「内製化」の動きが加速しています。従来の外注頼みでは、コスト増や改善スピードの遅れが課題でした。ローコード開発を導入すれば、現場のニーズを取り込みながら俊敏にシステムを作れるため、“現場主導のDX” を実現しやすくなります。
「2025年の崖」とレガシーシステム更新課題
経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」では、レガシーシステム維持による経済損失が年間12兆円に達すると指摘されています。システム刷新をスピーディに進めるには、外注よりも効率的で、既存資産との連携も可能なローコード開発が有力な手段となります。
非エンジニアでも参加できる開発体制
現場の社員が自らアプリ開発に関われる点も、ローコード開発の強みです。ExcelやAccessで業務を回していたような非エンジニア層でも、GUI操作を中心にシステムを作れるようになり、「市民開発者(Citizen Developer)」 として企業のIT推進に参加できる体制が整いつつあります。
ローコード開発の将来性を裏付ける市場予測と動向
国内外市場規模と成長率
調査会社Gartnerは、世界のローコード開発市場が2025年には約450億ドル規模に達すると予測しています。特にアプリケーションプラットフォームや業務プロセス自動化分野での需要拡大が顕著です。国内市場においてもITRやIDC Japanのレポートでは、年平均20%前後の成長が続くとされており、今後数年で導入企業が一気に増加すると見込まれます。
利用が拡大する産業領域
ローコード開発は、すでに金融業界での顧客管理システムや、製造業での在庫・品質管理、行政での窓口業務効率化などに広がっています。業務効率化だけでなく、顧客体験(CX)の向上や新規サービス開発の迅速化に直結する点が導入を後押ししています。医療・ヘルスケア領域でも、予約システムや患者データ管理などで採用が進み始めています。
大手ベンダーの戦略と製品ロードマップ
Microsoft、Salesforce、OutSystemsといったグローバルベンダーは、ローコード開発を中核に据えた製品戦略を加速しています。特にMicrosoft Power PlatformはOffice製品との親和性を強みに、国内中小企業でも採用が拡大中です。大手ベンダーが継続的に投資を行っていること自体が、ローコード開発の将来性を裏付けています。
ローコード開発を加速させる新潮流 ― 生成AIとの融合
生成AIによるコード補完・自動生成
近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、コード補完や自動生成が急速に進化しています。従来のローコード開発ではGUI操作が中心でしたが、生成AIを組み合わせることで自然言語からコードや処理を自動生成する仕組みが整いつつあります。これにより、開発効率はさらに向上し、非エンジニアでも高度なアプリ構築が可能になります。
ローコード+AIで変わる業務開発のスタイル
従来のローコードは「単純な業務効率化」に強みを持っていましたが、AIと融合することでデータ分析・意思決定支援・自動化フロー構築といった領域まで拡大しています。たとえば、営業現場でAIが商談内容を分析し、その結果を基にカスタマイズされた管理アプリをローコードで素早く構築するといった取り組みが可能になります。
市民開発者を後押しするAIアシスタント
生成AIは、コードの知識がない社員にとっても心強いサポーターです。「こういうアプリが欲しい」と自然言語で入力するだけでプロトタイプが生成される世界が現実に近づいています。これにより、市民開発者(Citizen Developer)の裾野が広がり、社内全体での開発文化が加速することが期待されます。
ローコード開発のメリットと企業が得られる効果
開発スピードとコスト削減
ローコード開発の最大のメリットは、開発スピードを大幅に向上できることです。従来数カ月かかっていたシステム構築が、数週間から数日で完了するケースも増えています。開発期間の短縮はそのままコスト削減につながり、特に新規事業や業務改善のスピードが重要な企業にとって大きな効果を発揮します。
内製化による業務効率化と柔軟性
外部ベンダーに依頼せず、社内でシステムを内製化できる点も重要です。現場部門が主体的にアプリを作れるようになることで、改善スピードが早まり、現場の声を即座にシステムに反映できます。これにより、業務プロセスの効率化だけでなく、顧客対応の柔軟性も向上します。
エンジニア人材の高度活用
ローコード開発は「エンジニア不要」と誤解されがちですが、実際にはエンジニアの役割をより高度な領域へシフトさせる効果があります。基盤やセキュリティ設計などのコア部分にエンジニアを集中させ、業務アプリの部分は市民開発者が担うことで、リソースを最適に分配できます。結果として、エンジニア不足を補いながら組織全体の生産性を高めることが可能になります。
関連記事:
ノーコードWebサイト制作の始め方|メリット・デメリットと企業が押さえる運用ポイント
ローコード開発の課題とリスク
複雑システムへの適用限界
ローコード開発は業務アプリや単機能システムに強みを持ちますが、基幹システムや大規模な処理が必要なシステムには不向きな場合があります。特に高度なパフォーマンスチューニングや複雑な要件が求められる領域では、従来型の開発手法が欠かせません。
セキュリティとガバナンスの懸念
市民開発者が増えることで、セキュリティリスクやガバナンス上の課題も浮上します。アクセス権限の管理やデータの扱いが不十分なままアプリが拡散すると、情報漏洩やコンプライアンス違反のリスクを招きます。IT部門による統制や監査体制が不可欠です。
ベンダーロックイン・属人化リスク
特定のローコードツールに依存しすぎると、他システムへの移行コストや柔軟性の低下を招く恐れがあります。また、特定の社員だけがアプリの仕組みを理解している状態になると、異動や退職で属人化リスクが高まります。
既存システムとの統合・移行コスト
新規にアプリを作る場合はスムーズでも、既存システムとのデータ連携や移行には課題が残ります。API連携やカスタマイズが必要になり、「ローコードでも結局エンジニアのサポートが欠かせない」ケースは少なくありません。導入前に全体アーキテクチャを見据えた計画が求められます。
関連記事:
ノーコードツールのデメリットとは?落とし穴と回避策・3年TCOで徹底解説
将来を見据えた導入戦略と成功のポイント
小規模導入(PoC)から全社展開へのロードマップ
ローコード開発をいきなり全社で導入すると、既存システムや運用との摩擦が起きやすくなります。まずは小規模プロジェクトでPoC(概念実証)を行い、効果を検証してから段階的に展開することが成功への近道です。成果を可視化することで、経営層や現場の理解も得やすくなります。
エンジニアと市民開発者の協働体制構築
市民開発者が増えることで、IT部門と現場部門の役割分担が重要になります。エンジニアは基盤設計やセキュリティ統制を担い、市民開発者は業務改善アプリを構築するという協働体制を作ることで、開発効率と安全性の両立が可能になります。
ガバナンス・セキュリティを組み込んだ運用設計
導入効果を最大化するには、ルール設計や統制の枠組みを最初から組み込むことが欠かせません。承認フローや利用ガイドラインを整備し、監査ログを活用することで、セキュリティとコンプライアンスを維持しながら開発を進められます。
教育・研修によるAI/DX人材リスキリング
ローコード導入を定着させるためには、社員が正しく使いこなせるようになることが必須です。AIやDX研修をあわせて実施することで、現場に新しい開発文化を根付かせられます。
読者タイプ別に見るローコード開発の未来
経営層にとってのROI・競争優位性
経営層が注目すべきは、投資対効果(ROI)と市場競争力です。ローコード開発を活用すれば、新サービスや業務改善を迅速に形にできるため、ビジネススピードが競合優位性に直結します。IT外注コストの削減や、開発リードタイムの短縮による機会損失の回避は、経営にとって大きなメリットとなります。
情報システム部門にとっての役割シフト
情報システム部門は「全社の開発を一手に担う立場」から、プラットフォーム提供者・ガバナンス管理者としての役割へとシフトしていきます。ローコードを現場に解放することで、従来の属人的な開発負荷を軽減し、システム全体の統制やセキュリティに注力できるようになります。
エンジニアにとってのキャリア展望
エンジニアにとってローコードは「仕事を奪う存在」ではなく、高度な領域へ集中する機会をもたらします。基幹システムやセキュリティ設計など、専門性が必要な分野にリソースを割けるため、キャリアを深化させるチャンスです。また、AIとローコードの融合により、開発スキルの幅を広げる新たなキャリアパスも生まれています。
5年後・10年後のローコード開発シナリオ
普及が進み「当たり前の選択肢」になる未来
今後5年以内に、ローコード開発は「一部の先進企業の取り組み」から多くの企業にとって標準的な開発手段へと変化していくと予測されます。新規アプリ開発や業務改善プロジェクトの多くがローコードを前提に進められるようになり、スクラッチ開発は特殊要件や高度な領域に限定される可能性が高いでしょう。
AIによる更なる自動化と“ハイパーオートメーション”への進化
10年後を見据えると、ローコードは生成AIやRPA、プロセスマイニングと融合し、“ハイパーオートメーション” と呼ばれる自動化の進化形に近づくと考えられます。単なるアプリ開発の効率化にとどまらず、業務そのものを自動化・最適化する仕組みへと進化することが期待されます。
逆風シナリオ:規制や技術的限界への懸念
一方で、ローコードの将来が常に順風満帆とは限りません。セキュリティ規制の強化や、ツール依存による移行の難しさ、複雑な要件に対応できない技術的限界が顕在化する可能性もあります。「ローコードで何でも解決できる」という過度な期待を避け、適材適所で活用する視点が重要です。
ローコード開発の将来性を正しく理解し、次の一歩へ
ローコード開発は、IT人材不足やDX推進の流れを背景に、今後も成長が続く分野です。開発スピードやコスト削減といったメリットだけでなく、生成AIとの融合によって業務改善や新規サービス創出を支える中核的な手段へと進化していくでしょう。
一方で、複雑システムへの対応やセキュリティ・ガバナンスの課題も存在します。導入効果を最大化するためには、小規模な導入から全社展開へ段階的に進めること、エンジニアと市民開発者の協働体制を構築すること、そして人材教育・研修を通じて正しい運用を根付かせることが不可欠です。
AIやDXの進展とともに、ローコード開発は「選択肢の一つ」から「企業競争力を支える標準ツール」へと変わりつつあります。将来性を正しく理解し、適切に取り入れることで、自社の成長を加速できるはずです。

ローコード開発の将来性に関するよくある質問
- Qローコード開発は今後なくなる可能性はありますか?
- A
なくなる可能性は低いと考えられます。むしろ、生成AIや自動化技術との融合により、業務開発の標準手法として拡大していくと予測されています。スクラッチ開発は特殊要件や高度な領域に残り、ローコードは広範囲に定着する流れです。
- Qローコード開発はどんな企業に向いていますか?
- A
スピード重視で業務改善を進めたい企業や、IT人材不足に直面している企業に向いています。特に中小企業や自治体、医療・製造業など、現場主導でアプリを作るニーズがある組織で効果を発揮します。
- Qノーコードとローコードはどちらを選ぶべきですか?
- A
小規模・単機能で十分ならノーコード、大規模展開や既存システム連携が必要ならローコードが適しています。詳細は ノーコードとは?メリット・デメリットとローコードとの違いを徹底解説 をご覧ください。
- Qローコード開発を導入する際の注意点は?
- A
属人化やセキュリティリスクを防ぐために、ガバナンス体制や教育研修を同時に整備することが重要です。PoCから始め、段階的に展開することで失敗リスクを抑えられます。
- Qローコード開発はエンジニアの仕事を奪いますか?
- A
奪うのではなく、エンジニアの役割を高度領域にシフトさせるものです。基幹システムやセキュリティ設計など、専門性が必要な領域に集中できるため、むしろキャリアの幅を広げるチャンスとなります。