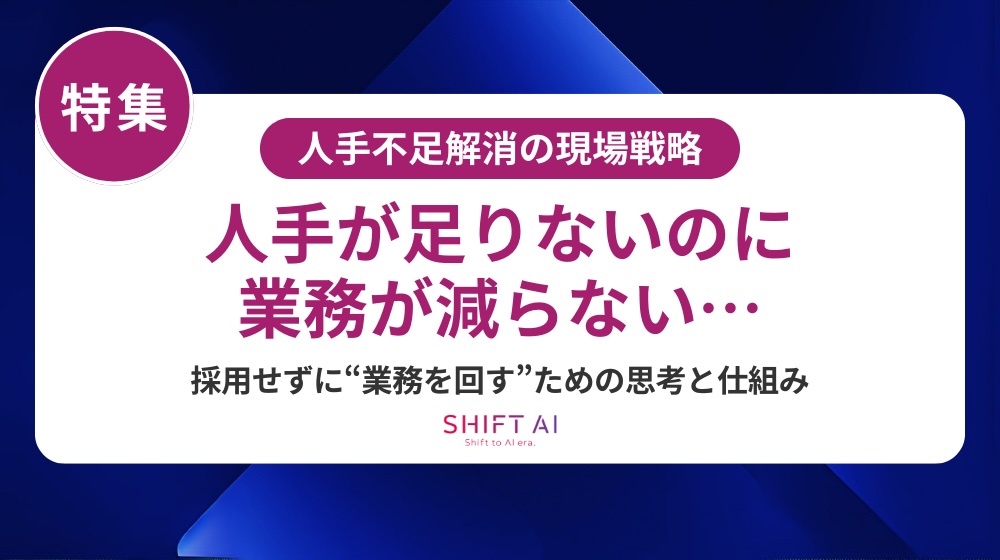2025年上半期、人手不足を原因とする企業倒産が202件に達し、過去最多を更新したことが帝国データバンクの調査で明らかになりました。これは前年同期の182件から20件増加しており、2年連続で記録を塗り替える深刻な状況です。(出典:人手不足倒産の動向調査(2025年上半期)|帝国データバンク)
特に注目すべきは、売上が好調な黒字企業でも人手不足による倒産が発生していることです。「仕事はあるのに人がいない」という状況で事業継続が困難になり、やむなく廃業を選択するケースが急増しています。
本記事では、人手不足倒産の実態と原因を詳しく解説し、従来の対策に加えてAI活用による根本的な解決策まで包括的にご紹介します。あなたの会社を人手不足倒産から守るための具体的な方法を見つけてください。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
【2025年上半期】人手不足による倒産が過去最多を記録
人手不足による倒産は2025年上半期に202件を記録し、これまでにない深刻な状況となっています。帝国データバンクの最新調査によると、前年同期の182件から20件増加し、2年連続で過去最多を更新しました。
業種別では建設業54件、物流業28件で全体の40.6%を占め、2024年問題の影響が顕在化しています。
また老人福祉事業や労働者派遣業などサービス業でも倍増しており、人手不足による倒産リスクが全業界に拡大していることが明らかになりました。
転職市場の活発化により人材確保が困難な状況が続く中、人手不足倒産は今後も高水準で推移すると予測されます。
出典:人手不足倒産の動向調査(2025年上半期)|帝国データバンク
人手不足で会社が倒産する4つのパターン
人手不足による倒産には明確な4つのパターンがあり、どの企業にも起こりうるリスクです。
従業員の退職、採用の失敗、人件費の高騰、後継者不在など、それぞれ異なる要因で事業継続が困難になります。
従業員が退職して業務が回らなくなる
従業員の退職による業務停止が最も直接的な倒産要因となります。少数精鋭で運営している中小企業では、一人の退職でも業務が大幅に滞る可能性があります。
特に危険なのは連鎖退職です。一人が退職すると残った従業員の負担が増加し、過重労働により次の退職者が生まれます。この悪循環が続くと、最終的に業務を遂行できる人員がいなくなり、事業継続が不可能になります。
技術者や営業担当など専門性の高い従業員が退職した場合、後任の育成が間に合わず倒産に至るケースも少なくありません。
求人を出しても応募者が集まらない
採用活動を行っても応募者が集まらず、慢性的な人員不足状態が継続することで倒産に追い込まれるパターンです。
求職者よりも求人数が多い状況が続く中、特に中小企業は大手企業と比較して知名度や待遇面で劣ることが多く、優秀な人材の確保が困難です。労働条件が厳しい業界や地方の企業では、この傾向がより顕著に現れます。
求人広告を出し続けても応募がないため、既存従業員の負担は増加し続け、最終的に事業運営が立ち行かなくなってしまうのです。
人件費が高騰して資金繰りが悪化する
人材確保のための人件費高騰が企業の財務状況を圧迫し、倒産に至るケースです。
最低賃金の引き上げや転職市場の活発化により、採用時の提示給与も年々上昇しています。既存従業員の流出を防ぐための「防衛的賃上げ」も必要となり、総人件費が急激に増加する企業が増えています。
売上が伸び悩む中で人件費だけが上昇すると、利益率が大幅に悪化します。特に労働集約型の業種では人件費が経営を圧迫し、運転資金が不足して倒産に追い込まれてしまいます。
後継者がいなくて事業継続できない
経営者や幹部の突然の離脱時に、事業を引き継げる後継者がいないことで倒産するパターンです。
経営者の病気や事故、高齢による引退などで経営の舵取りができなくなった際、適切な後継者や経営陣がいないと事業継続が困難になります。事業承継には長期間の準備が必要ですが、この準備を怠っていた企業が該当します。
創業者の属人的な経営に依存していた企業では、その人がいなくなると顧客との関係維持や重要な意思決定ができなくなり、急速に業績が悪化して廃業を余儀なくされることが多いのです。
人手不足で倒産を引き起こす4つの原因
人手不足倒産の背景には、日本社会が抱える構造的な問題があります。
少子高齢化による労働力減少、転職市場の活発化、企業の魅力度不足など、複数の要因が絡み合って深刻な人材不足を引き起こしています。
少子高齢化で働く人が減っているから
生産年齢人口の継続的な減少が人手不足の最も根本的な原因です。日本は世界でも類を見ない速度で少子高齢化が進んでいます。
出生率の低下により新たに労働市場に参入する若年層が減少する一方、ベビーブーム世代の大量退職が続いています。働く人の絶対数が減少しているため、企業間での人材獲得競争が激化し、中小企業ほど人材確保が困難になっています。特に労働集約型の産業では、この影響が顕著に現れており、慢性的な人手不足状態が続いています。
転職市場が活発化して人材流動が激しいから
労働者の転職に対する意識変化により、人材の流動性が大幅に高まっています。終身雇用制度の崩壊とともに、より良い条件を求めて転職する労働者が増加しました。
賃上げの機運が高まる中、現在の職場に満足しない従業員は積極的に転職活動を行うようになっています。この結果、企業は常に人材流出のリスクにさらされ、安定した人員確保が困難な状況が続いています。
特に専門性の高い人材ほど市場価値が高く、好条件を提示する企業への移籍が活発化しています。
労働条件が厳しくて人が集まらないから
過酷な労働環境や待遇の悪さが求職者から敬遠される大きな要因となっています。長時間労働、低賃金、休暇取得の困難さなどが問題視されています。
建設業や物流業では肉体的負担が大きく、危険を伴う作業も多いため、若年層からの人気が低下しています。また、飲食業では深夜勤務や休日出勤が常態化しており、ワークライフバランスを重視する現代の労働者には受け入れられにくい環境です。
労働条件の改善なしには、持続的な人材確保は困難な状況が続いています。
企業の魅力度が不足しているから
企業自体の魅力や将来性への不安が人材確保を困難にしています。給与水準、キャリア成長の機会、企業文化など、総合的な魅力度で大手企業に劣る中小企業が多いのが現実です。
特に知名度の低い企業や成長性に疑問符がつく業界では、優秀な人材の獲得が極めて困難です。求職者は安定性と将来性を重視する傾向が強く、不透明な経営状況や限定的なキャリアパスしか提供できない企業は選択肢から外されがちです。
企業価値の向上と魅力的な働く環境の整備が急務となっています。
【従来】人手不足による倒産を防ぐ従来の4つの対策
人手不足倒産を回避するには、即効性のある短期的対策と持続可能な長期的対策を組み合わせることが重要です。
外部人材の活用から労働環境の改善まで、段階的なアプローチで人材確保と定着を図る必要があります。
外部の人材サービスを活用する
人材派遣や業務委託の戦略的活用により、即座に人手不足を補うことができます。正社員採用に時間をかけられない緊急時には、最も効果的な対策です。
人材派遣会社を活用すれば、必要な期間だけ即戦力となる人材を確保できます。特に繁忙期や欠員補充では、派遣社員の活用が有効です。また専門性の高い業務については、フリーランスや業務委託契約での外部人材活用も選択肢となります。
採用代行サービスを利用すれば、採用業務そのものをアウトソーシングして効率化を図ることも可能です。
労働環境を改善して働きやすくする
働きやすい職場環境の整備が従業員の定着率向上と新規採用の成功につながります。労働条件の見直しは人手不足解消の基盤となる重要な取り組みです。
残業時間の削減、有給休暇の取得促進、フレックスタイム制やリモートワークの導入などにより、ワークライフバランスの改善を図ります。福利厚生の充実も効果的で、健康管理サポートや資格取得支援制度などを整備することで、従業員満足度が向上します。
労働環境の改善は時間がかかりますが、長期的な人材確保には不可欠な投資です。
採用戦略を見直して人材確保する
採用手法の多様化と条件の最適化により、より多くの候補者にアプローチできます。従来の採用方法だけでは限界があるため、戦略的な見直しが必要です。
求人広告の掲載先を増やし、ハローワーク、転職サイト、SNS採用など複数のチャネルを活用します。募集条件についても、年齢制限の緩和や勤務時間の柔軟化を検討しましょう。
採用サイトの充実や職場見学の実施により、求職者に企業の魅力を伝えることも重要です。入社後のギャップを防ぐため、面接では仕事の大変さも含めて正直に伝えることが長期的な定着につながります。
既存従業員の定着率を向上させる
リテンション対策の強化により、貴重な人材の流出を防ぐことができます。新規採用よりもコストを抑えながら、安定した人員確保が可能になります。
研修制度や人事評価制度の整備により、従業員の成長機会を提供します。明確なキャリアパスの提示と定期的な面談により、将来への不安を解消することが重要です。
社内コミュニケーションの活性化も効果的で、チューター制度やメンター制度の導入により、職場の人間関係を良好に保ちます。従業員が長く働きたいと思える環境づくりが、人手不足解消の鍵となります。
【AI活用】人手不足による倒産を防ぐ、これからの解決方法4選
従来の人材確保策には限界があり、AI技術の活用こそが人手不足問題の根本的解決への道筋です。
業務の自動化から全社的な生産性向上まで、AIを戦略的に導入することで少ない人員でも事業を継続・発展させることができます。
💡関連記事
👉人手不足を解消する15の方法|従来手法+AI戦略で効率化を実現する最新戦略
ChatGPTで事務作業を大幅に効率化する
生成AIによる事務業務の自動化により、従来人手に頼っていた作業を大幅に効率化できます。資料作成、メール対応、データ入力などの定型業務をAIが代替することで、貴重な人的リソースをより付加価値の高い業務に集中させることが可能です。
ChatGPTを活用すれば、会議資料の作成、報告書の下書き、顧客への提案書作成などが短時間で完了します。また、議事録の作成や社内マニュアルの整備も自動化でき、従来数時間かかっていた作業が数分で終わります。
メール の返信テンプレート作成や問い合わせ対応の下書きなども効率化でき、一人当たりの業務処理能力を飛躍的に向上させることができます。
💡関連記事
👉企業向け生成AIツール15選【2025最新】選び方から導入まで解説
顧客対応をAIチャットボットで自動化する
AIチャットボットの導入により、24時間365日の顧客対応が可能になり、人手不足による機会損失を防げます。よくある質問への回答や初期対応を自動化することで、スタッフはより複雑な業務に専念できます。
最新のAIチャットボットは自然な会話が可能で、顧客満足度を維持しながら人件費を削減できます。電話対応やメール対応の一次受けをAIが担当し、必要な場合のみ人間のスタッフにエスカレーションする仕組みを構築すれば、少数のスタッフでも多くの顧客に対応可能です。
導入初期の設定は必要ですが、運用開始後は大幅な省人化効果を実現できます。
データ分析業務をAIツールで省人化する
AIによるデータ分析の自動化で、専門知識を持つアナリストがいなくても高度な分析が可能です。売上データの分析、顧客行動の把握、在庫管理の最適化などを自動化できます。
従来は専門スタッフが数日かけて行っていたデータ分析を、AIツールなら数時間で完了できます。グラフ作成から傾向分析、改善提案まで自動生成され、経営判断に必要な情報を迅速に取得できるでしょう。
データの可視化や レポート作成も自動化でき、リアルタイムでの業績監視も可能となり、人手をかけずに精度の高い経営管理を実現できます。
社内AI研修で全社の生産性を向上させる
全従業員のAI活用スキル向上が、組織全体の生産性向上と人手不足解消の鍵となります。一部の部署だけでなく、全社的にAIを活用できる体制を構築することで、根本的な解決が可能です。
段階的な研修プログラムにより、従業員のスキルレベルに応じてAI活用能力を向上させます。基礎的なChatGPTの使い方から、業務特化型AIツールの活用まで、実践的なスキルを身につけることで、一人一人の業務効率が飛躍的に向上します。
継続的な研修により、新しいAI技術への対応力も養成でき、持続的な競争優位性を確保できます。
人手不足による倒産を回避するための4つのステップ
人手不足倒産を防ぐには、現状把握から実行まで段階的なアプローチが必要です。
緊急度に応じた対策の優先順位付けと、短期・中期・長期の計画的な取り組みにより、確実にリスクを軽減できます。
ステップ1.現状の人手不足リスクを診断する
客観的な現状分析が効果的な対策立案の出発点となります。感覚的な判断ではなく、データに基づいた正確なリスク評価を行うことが重要です。
まず従業員の年齢構成、退職予定者、採用計画の進捗状況を整理しましょう。離職率の推移、求人への応募状況、面接から内定までの歩留まり率なども把握します。
業務量に対する人員の充足率を部署別に算出し、どの領域で人手不足が深刻化しているかを明確にします。競合他社の採用条件との比較も行い、自社の競争力を客観視することが診断の精度を高めます。
ステップ2.緊急度に応じて対策の優先順位を決める
リスクの緊急度と影響度によるマトリクス分析で、限られたリソースを最も効果的に配分できます。すべての問題を同時に解決することは困難なため、優先順位の明確化が不可欠です。
事業継続に直結する部署や、顧客対応に影響する業務を最優先とします。退職予定者がいる部署、採用が全く進んでいない職種、過重労働が常態化している現場などは緊急対応が必要です。
一方で影響度は高いが時間的猶予がある問題については、中長期的な計画で対応します。各対策の実施コストと期待効果も考慮し、費用対効果の高い施策から着手していきます。
ステップ3.短期・中期・長期の実行プランを立てる
時間軸を明確にした段階的な改善計画により、持続可能な人手不足解消を実現できます。短期的な応急処置と長期的な構造改革をバランス良く組み合わせることがポイントです。
短期計画(3ヶ月以内)では、人材派遣の活用や残業時間の適正化など即効性のある対策を実施します。中期計画(6ヶ月〜1年)では、採用手法の見直し、労働環境の改善、研修制度の充実を進めます。
長期計画(1年以上)では、企業ブランディング、組織文化の改革、キャリアパスの整備などに取り組みます。
各期間の目標値を設定し、定期的な進捗確認と軌道修正を行うことで確実な成果を目指します。
ステップ4.AI導入で持続的な解決策を構築する
AI技術の段階的導入により、人手不足に依存しない事業モデルへの転換を図ります。従来の対策と並行してAI活用を進めることで、根本的な問題解決が可能になります。
まずは導入しやすい生成AIから始め、事務作業の効率化を実現します。次にチャットボットや自動応答システムを導入し、顧客対応業務を省人化します。データ分析の自動化により、意思決定の迅速化と精度向上を図ります。
最終的には全社的なAI研修により、組織全体の生産性を底上げし、少数精鋭でも高いパフォーマンスを発揮できる体制を構築します。AI導入には初期投資が必要ですが、長期的には大幅なコスト削減効果を期待できます。
まとめ|人手不足倒産は今すぐ対策すれば防げる経営リスク
人手不足による倒産が過去最多の202件を記録した現在、この問題は全ての企業にとって深刻なリスクとなっています。従業員の退職、採用難、人件費高騰、後継者不在という4つのパターンで倒産に至る可能性があり、黒字企業でも安心できません。
しかし適切な対策により、この危機は必ず回避できます。外部人材の活用や労働環境の改善といった従来手法に加えて、AI技術を戦略的に導入することで根本的な解決が可能です。
ChatGPTによる業務効率化、AIチャットボットでの顧客対応自動化、データ分析の省人化など、AI活用により少ない人員でも高い生産性を実現できます。
重要なのは現状のリスク診断から始めて、緊急度に応じた段階的な対策を実行することです。人手不足倒産を防ぐための第一歩として、AI活用スキルの向上から始めてみてはいかがでしょうか。

人手不足倒産に関するよくある質問
- Q人手不足倒産とは何ですか?
- A
人手不足倒産とは、従業員の退職や採用難、人件費高騰などにより必要な人材を確保できず、事業継続が困難になって倒産することです。売上が好調な黒字企業でも発生する可能性があり、2025年上半期には過去最多の202件が記録されています。仕事はあるのに人がいないという状況で、やむなく廃業を選択するケースが急増しています。
- Qどのような業界で人手不足倒産が多いのですか?
- A
2025年上半期のデータでは、建設業54件、物流業28件で全体の40.6%を占めています。これは2024年問題として懸念されていた時間外労働の上限規制の影響が現れたものです。また老人福祉事業や労働者派遣業などサービス業でも大幅に増加しており、人手不足倒産のリスクは全業界に拡大している状況です。
- Q人手不足倒産を防ぐ最も効果的な方法は何ですか?
- A
従来の人材確保策とAI活用を組み合わせた戦略が最も効果的です。短期的には人材派遣の活用や労働環境の改善を行い、中長期的にはChatGPTによる業務自動化やAIチャットボットでの顧客対応効率化を進めます。全社的なAI研修により従業員のスキルを向上させ、少ない人員でも高い生産性を実現することが根本的な解決につながります。
- Q中小企業でもAI導入による人手不足解消は可能ですか?
- A
段階的な導入により中小企業でも十分に効果を期待できます。まずはChatGPTを活用した資料作成やメール対応の効率化から始め、次にチャットボットでの顧客対応自動化を進めます。高額なシステム投資は不要で、既存のクラウドサービスを活用すれば初期費用を抑えながらAI導入が可能です。重要なのは従業員のAI活用スキル向上です。
- Q人手不足倒産の前兆はありますか?
- A
連鎖退職の発生や求人への応募者激減が代表的な前兆です。一人の退職により残った従業員の負担が増加し、次々と退職者が出る状況は危険信号です。また求人を出しても応募がない、面接まで進む候補者がいない状況も要注意です。人件費の高騰で利益率が悪化している場合や、後継者育成が進んでいない企業も倒産リスクが高まっています。