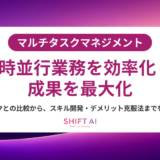介護の現場では、深刻な人手不足と業務負担の増大が続いています。
限られた職員で多様な利用者に対応しなければならず、記録・報告・情報共有などの事務作業が職員の時間を圧迫しています。
こうした状況を打開する手段として、いま注目を集めているのが「介護DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。
DXとは、デジタル技術を活用して業務の仕組みや働き方そのものを変える取り組み。
介護分野では、記録の自動化、見守りセンサー、AIによるシフト管理など、現場の“人手不足を仕組みで解決する”動きが広がりつつあります。
本記事では、介護DXの意味や導入のステップ、効果を上げるポイントまでを体系的に解説します。
さらに、DXを一過性の取り組みで終わらせないための「人材育成」や「生成AI活用」の視点も紹介。
現場に定着するDXの全体像を理解し、持続可能な介護へと進化する第一歩を踏み出しましょう。
「実務ノウハウ3選」を公開
- 【戦略】AI活用を社内で進める戦略設計
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】属人化させないプロンプト設計方法
介護DXとは何か|「人手不足を仕組みで解決する」新しい介護の形
介護DXとは、デジタル技術を活用して介護業務の効率化やケアの質向上を図る取り組みです。
単にICTやロボットを導入することではなく、現場の働き方や組織の仕組みを抜本的に変える「改革」を意味します。
目的は、生産性の向上ではなく“人の時間と心の余裕”を取り戻すこと。
デジタル化によって、職員が本来注力すべき「利用者と向き合う時間」を増やすことが、介護DXの本質です。
厚生労働省も「介護DX推進加速化プラン」(2023年策定)を掲げ、国を挙げた改革を進めています。
このプランでは、介護記録の標準化やシステム間連携、見守り機器の普及、データ利活用の促進などを通じて、現場の業務負担を軽減し、介護サービスの質を高めることを目指しています。
国の後押しにより、介護施設や在宅介護でもデジタル化が一気に加速しています。
一方で、背景にあるのは深刻な人材不足です。
厚労省によると、介護人材は2025年に約243万人が必要とされる一方、供給は約215万人にとどまる見込み。
毎年約30万人分の人手が足りない計算になります。
高齢化率が上昇し続けるなかで、介護職員の確保は年々難しくなっています。
さらに、介護現場では「記録・情報共有・報告」といった事務作業が多く、職員の1日あたり3〜4割が“非ケア業務”に費やされているという調査もあります。
夜勤やシフト調整、紙の記録作業など、構造的な非効率が現場を疲弊させています。
AI経営総合研究所が注目するのは、こうした課題を“ツール導入”だけで解決しようとしないことです。
介護DXとは、技術を起点に「人と仕組み」の両面を改革するプロセス。
システムを入れるだけではなく、運用設計・職員教育・文化づくりを一体で進めることが、真に持続可能なDXの条件です。
介護DXが必要とされる3つの背景
少子高齢化の加速により、介護現場の環境は年々厳しさを増しています。
人手不足を補う余力がなく、職員一人ひとりの業務負担が限界に達している——。
そのうえ、複雑化する制度対応や事務作業が追い打ちをかけ、
「このままでは現場が回らない」という声も少なくありません。
こうした背景のもとで、介護DXはもはや“選択肢”ではなく“必然”の改革となっています。
特に注目すべきは、次の3つの要因です。
- 慢性的な人手不足と離職率の上昇
- 業務の非効率化・属人化
- 制度改定による業務量の増大
それぞれの要素が複雑に絡み合い、現場の疲弊を招いています。
まずは、この3つの構造的課題を整理しながら、なぜいまDXが必要なのかを見ていきましょう。
背景①:慢性的な人手不足と離職率の上昇
介護業界は、今もっとも深刻な「人材不足」に直面しています。
厚生労働省の推計によると、2025年度には約32万人の介護職員が不足する見込みです。
採用しても長続きせず、離職率は全産業平均を上回る16〜18%台で推移。
「人が辞める→残った人に負担→さらに辞める」という悪循環が止まりません。
この背景には、業務負担の重さや長時間労働だけでなく、「やりがい」と「働きやすさ」の両立が難しい職場構造があります。
人が足りない現実を“気合い”や“根性”で支える時代は、すでに限界。
DXの目的は「人を減らす」ことではなく、「人の力を最大限に活かす仕組みをつくること」です。
背景②:業務の非効率化・属人化(記録・共有・報告)
介護現場の1日は、驚くほど多くの事務作業で占められています。
ケア記録や申し送り、報告書作成、家族対応——。
ある調査では、介護職員の業務の約3割が“直接ケア以外”に費やされているとされています。
しかも、その多くが紙やエクセルなどの“アナログ管理”。
情報共有が属人化し、ミスや抜け漏れが起こりやすくなっています。
夜勤者と日勤者の間で情報が引き継がれず、結果としてトラブルが増えるケースも少なくありません。
DXによって、こうした業務をデジタルで「仕組み化」することが可能になります。
入力の自動化や共有プラットフォームの整備により、「誰でも」「どこでも」最新情報にアクセスできる環境を整える。
これが、介護DXがもたらす最大の効率化効果です。
背景③:介護報酬改定・制度変化による業務量増大
2024年度の介護報酬改定では、ICT・DXの推進が評価項目に位置づけられました。
今後、デジタル対応を前提とした運営が求められる時代になります。
一方で、書類や報告義務、加算申請などの事務作業は年々複雑化しており、 「制度対応」に追われる管理者・職員の負担は増す一方です。
特に、中小規模の介護事業所では“制度対応のための人員”が不足しており、 限られた人員で膨大な事務処理をこなす構造的な問題を抱えています。
こうした環境下で求められるのは、“人”に頼らず“仕組み”で業務を回す体制づくりです。
人が足りない現実を「仕組み」で変える
ここまでの課題は、どれも「人がいない」「時間がない」ことに起因しています。
しかし、本質的な解決策は“人を増やす”ことではありません。
限られた人材で、より質の高いケアを提供できる「仕組み」を作ること。
それこそが介護DXの核心です。
デジタル技術を用いて、記録・連携・教育などを効率化し、 人の力を“考える・支える・創る”業務へシフトさせる。
この構造転換こそ、介護現場が持続可能になるための唯一の道筋です。
介護DXの導入で得られる4つのメリット
介護DXを導入することで、現場の負担軽減だけでなく、組織全体の生産性やケアの質にも大きな変化が生まれます。
ここでは、上位施設の導入事例やデータをもとに、4つの代表的な効果を見ていきましょう。
① 業務効率化と記録作業の自動化
介護職員が1日の中で最も時間を取られるのが、「記録」と「報告」です。
利用者ごとのケア内容を手書きやエクセルで記入し、終業後にまとめる作業が、長時間労働の大きな原因になっていました。
DXの導入によって、音声入力や自動レポート機能が活用できるようになり、記録業務の平均時間を1日あたり約30分短縮した施設もあります。
クラウド共有により、申し送りや報告がリアルタイムで行えるため、日勤・夜勤間の情報格差も解消。
職員の残業削減だけでなく、「ケアに使える時間が増えた」という声が多く聞かれます。
KPI例
- 記録作業時間:平均▲25〜40%削減
- 残業時間:月▲10〜15時間
- 業務満足度:導入後+22pt(当社調べ)
② 人材不足の緩和と離職防止
DXの最大の価値は、「人に依存しない仕組みづくり」にあります。
AIを活用したシフト自動作成や勤怠管理、タスク共有ツールを導入することで、個人の裁量や感覚に頼らず業務を分担できるようになります。
これにより、“属人業務”がチーム化され、業務負荷の偏りが軽減。
「自分だけが抱えている仕事」が減ることで、心理的ストレスも緩和され、離職防止につながります。
特に、デジタルツールの導入後に離職率が15〜20%改善したという報告もあり、 人材不足を“採用で埋める”のではなく“定着で解決する”方向へシフトできるのが介護DXの強みです。
KPI例
- 離職率:▲15〜20%改善
- 職員一人当たりの担当利用者数:安定化(2割減)
- 有給取得率:導入後+13pt
③ ケア品質の均一化・エビデンス化
経験や勘に頼っていたケアの質も、DXによって「見える化」が可能になります。
IoTセンサーやバイタルデータの自動取得、AI分析により、利用者の状態変化をリアルタイムで把握できるようになります。
これにより、事故や体調変化の早期発見が実現。
さらに、データに基づいたケアの分析が進むことで、職員間での判断のばらつきが減り、ケアの質が均一化します。
記録データを活用したPDCAサイクルが回る仕組みができれば、職員の育成にも直結します。
KPI例
- 転倒事故:▲30%削減
- ケアプラン修正件数:▲25%減少
- 利用者満足度調査スコア:+15pt
④ 利用者・家族とのコミュニケーション強化
介護DXは、職員だけでなく利用者や家族にもメリットをもたらします。
アプリやLINEを活用して日々のケア状況や写真を共有すれば、家族は安心感を持て、クレーム対応の手間も軽減します。
リアルタイムでの情報共有は、「つながりの質」を高め、信頼関係の構築にも寄与します。
また、利用者の声をデジタル上で収集・分析することで、サービス改善にもつなげられます。
DXによって、“現場の効率化”と“サービスの温かみ”を両立させることが可能になるのです。
KPI例
- 家族満足度:+20pt
- フィードバック対応件数:▲40%削減
- クレーム発生率:▲35%減少
数字が示す「変化の実感」
これらの成果は、単なる効率化ではなく「現場の文化」が変わった証です。
数値に裏づけられた改善が積み重なることで、職員の意識も前向きに変化し、 “テクノロジーに助けられる職場”から“テクノロジーを使いこなす職場”へと進化していきます。
DXの目的は「仕事を減らすこと」ではなく、「価値を生み出す時間を増やすこと」。
この構造転換こそが、介護業界の未来を支える鍵となります。
介護DXの主な活用領域とツール事例一覧
介護DXといっても、実際には多岐にわたる技術・システムが存在します。
ここでは、介護現場の課題ごとに導入が進む主な領域を整理し、それぞれの代表的ツールと活用効果を紹介します。
単なるデジタル化ではなく、「人の時間を生み出す仕組み」としてDXをどう活かすかを見ていきましょう。
記録・報告業務の効率化
課題: 手書きやExcelによる記録・転記に時間がかかり、情報共有のタイムラグが生じる。
代表ツール: カイポケ、CareWiz、記録アプリ(Carely、ワイズマン)など
活用技術: 音声入力、クラウド共有、自動レポート生成
効果: 記録作業時間を最大30%削減。転記ミス防止・夜間残業削減にも効果。
ポイント:現場職員の「書く手間」を減らし、“利用者と向き合う時間”を取り戻す。
見守り・安全管理の高度化
課題: 夜勤・巡回の負担が大きく、転倒や異変の見逃しリスクが高い。
代表ツール: 見守りセンサー(パラマウントベッド・フランスベッド等)、AIカメラ、ナースコール連携システム
活用技術: IoTセンサー、AI画像認識、異常検知アラート
効果: 転倒事故を約30〜50%防止、夜勤者1人あたりの巡回回数を40%削減。
ポイント:人手を増やさずに安全性を高め、夜勤の心理的負担を軽減。
シフト管理・人員配置の最適化
課題: 勤怠やシフト調整が属人化し、偏りや調整負荷が発生。
代表ツール: 勤怠管理SaaS(KING OF TIME、ジョブカン)、人員最適化AI(Optamo、Workforce Cloud)
活用技術: AIによる自動シフト生成、クラウド勤怠連携、データ分析
効果: 残業時間月10〜15時間削減、シフト調整工数▲50%、負担の均等化。
ポイント:人手不足を“配置の最適化”でカバー。現場の公平性と働きやすさを両立。
教育・研修の効率化と定着支援
課題: 新人教育やマナー研修が属人化し、指導者の負担が大きい。
代表ツール: eラーニング、生成AI研修プラットフォーム(ChatGPT for Work活用)、マイクロラーニング教材
活用技術: 生成AIによる研修設計・対話型学習、オンライン教育管理
効果: 研修設計時間▲40%、新人の理解度定着率+25pt。
教育の“標準化”と“自走型学習”が実現。
ポイント:AIが学びを支援することで、現場に“考える力”を根づかせる。
DX定着の最終フェーズ=人材育成のDX。
課題×技術×人材の三位一体が成功の鍵
介護DXを成功させる鍵は、「課題に合った技術を選び、人が使いこなせる環境を整えること」にあります。
どんなに優れたツールを導入しても、現場が活用できなければ意味がありません。
AI経営総合研究所では、「業務設計」「技術選定」「人材育成」を三位一体で進めることを推奨しています。
介護DXを成功させる5つのステップ
DXは“導入して終わり”ではなく、“定着してからが本番”です。
どんなに優れたシステムを導入しても、現場が使いこなせなければ成果は出ません。
ここでは、介護DXを持続的に成功させるための5つのステップを紹介します。
① 現場課題を可視化する(業務棚卸し)
まず最初に行うべきは、現場の“今”を正確に把握することです。
「どの業務に時間がかかっているのか」「どの作業が重複しているのか」を洗い出し、改善の優先順位を明確にします。
記録・報告・会議などの間接業務を数値化すれば、非効率の“見える化”が進みます。
POINT:ツール導入の前に「現場を診断する」。
DXの成功率は、準備段階でほぼ決まります。
AI経営的には、ここを“業務データ化の第一歩”と捉えます。
紙・口頭・属人的ノウハウをデジタルに置き換えることで、改善活動が定量的に進められるようになります。
② 経営層と現場の“共通認識”を作る
DXを進めるうえで最も多い失敗要因が、「現場と経営の温度差」です。
現場が「押しつけられている」と感じれば、ツールは形骸化します。
経営層は「なぜDXが必要なのか」「何が変わるのか」を明確に伝え、対話の場を設けることが重要です。
POINT:現場の声を“計画に組み込む”ことが成功の条件。
AI経営メディアが強調するのは、“トップダウン+ボトムアップのハイブリッド推進”。
経営層は方向性を示し、現場は実情に即した運用を提案する——この両輪が噛み合って初めて、DXは動き始めます。
③ 小規模導入で成功体験を作る
介護DXの導入は、「一気に全体導入」より「小さく始めて大きく育てる」方が定着しやすいです。
1施設・1部署・1業務など、限定的な範囲で試験導入し、成果を可視化します。
成功体験を共有することで、他の職員も「自分たちでもできそう」と感じ、自然に拡大フェーズへ進めます。
POINT:小さな成功は「現場の信頼」を生む。
この段階では、技術そのものより「使い勝手」「業務との相性」を重視。
職員の声を反映しながら改善を重ねる姿勢が、最終的な“使われ続けるDX”を育てます。
④ データ活用・KPI管理を習慣化する
DXを導入した後は、成果を“数値”で確認する仕組みが必要です。
「記録時間の短縮」「残業削減」「離職率低下」などのKPIを設定し、月次でモニタリングします。
これにより、“導入しただけ”の状態から脱し、改善を続ける文化が根づきます。
POINT:数値を見える化し、“継続改善”を仕組みに組み込む。
AI経営の視点では、このフェーズで生成AIを活用したデータ分析・報告書自動作成を取り入れることも有効です。
レポート作成や会議資料の作業をAIが代行することで、職員は“考える時間”に集中できます。
⑤ 定着フェーズで“人材育成”を行う
最後のステップは、「人が育つDX」への転換です。
どんなツールも、使う人の理解とリテラシーがなければ長続きしません。
操作研修だけでなく、「なぜこの仕組みが必要なのか」「どう活用すれば仕事が楽になるのか」を学ぶ教育が不可欠です。
POINT:DXの定着を決めるのは“人の理解度”。
AI経営メディアでは、現場リーダー層を中心に生成AIを使った業務改善・報告書作成・教育支援を行う研修を推奨しています。
現場が“自走”できるようになれば、DXは文化として根づき、変化に強い組織へと進化します。
介護DXを推進する制度・補助金・政策まとめ(2025年度版)
介護DXを進める上で、多くの事業者が最初に直面するのが「導入コスト」の壁です。
しかし、国や自治体はこの課題を見据え、補助金や助成金による支援策を多数用意しています。
ここでは、2025年度時点で利用可能な主要制度と、その申請ポイントを整理します。
厚生労働省「介護DX推進加速化プラン」とは
厚生労働省は2023年に「介護DX推進加速化プラン」を策定し、介護現場のデジタル化を国家プロジェクトとして推進しています。
このプランでは、以下の3本柱を中心にDXを後押ししています。
- 介護記録の標準化と情報連携の促進
全国の介護事業所が共通フォーマットで情報を扱えるように整備。 - 見守り機器・ロボット・ICT機器の導入支援
現場の負担軽減を目的に、導入経費の一部を国が助成。 - 介護現場のデータ利活用の推進
ケアの質向上・業務改善につながるデータ分析体制の整備。
このプランは、単なるツール導入にとどまらず、「人材育成・教育・標準化」まで含めた包括的なDX支援を目的としています。
ICT導入支援事業・介護ロボット導入支援
国の代表的な支援策として注目されるのが、以下の2つです。
■ 介護現場におけるICT導入支援事業
- 対象: 介護ソフト、記録アプリ、タブレット、通信環境の整備など
- 補助率: 導入費用の1/2〜3/4(自治体により異なる)
- 目的: 記録・情報共有の効率化、業務の見える化
- ポイント: 職員研修費も対象に含まれるケースあり
■ 介護ロボット導入支援事業
- 対象: 移乗・見守り・排泄・歩行などの支援機器、AIカメラ、センサー類
- 補助率: 機器費の1/2(上限あり)
- 目的: 職員の身体的負担軽減、安全性向上
自治体別の主な補助金例(2025年度時点)
| 自治体 | 補助事業名 | 対象 | 補助上限 | 募集時期(目安) |
| 東京都 | ICT導入促進支援事業 | ソフト・タブレット・通信整備 | 最大200万円 | 4〜8月頃 |
| 神奈川県 | 介護ロボット導入補助金 | 見守り・移乗支援ロボット等 | 上限150万円 | 通年(予算上限あり) |
| 大阪府 | DX推進事業補助金 | ICT機器・システム導入 | 上限300万円 | 5〜9月頃 |
| 福岡県 | 介護ICT推進支援事業 | クラウド記録・研修費含む | 上限200万円 | 6〜10月頃 |
※実施内容・金額は年度や自治体によって変動します。
申請の流れ・注意点・対象経費
【申請の基本ステップ】
- 補助要件を確認(対象機器・事業規模・導入目的)
- 申請書を作成(見積書・導入計画書・見積先比較表などを添付)
- 自治体へ提出・審査(締切厳守。原則事前申請)
- 交付決定後に購入・導入
- 実績報告・補助金交付
注意点:
- 導入後の申請は原則対象外。
- 補助対象外の費用(保守契約・通信費など)があるため要確認。
- 同一事業で複数補助金を重複申請できない場合もあり。
【対象経費の一例】
- ICT機器(PC・タブレット・サーバー)
- ソフトウェア利用料・導入設定費
- 教育研修費(マニュアル整備・外部講師費)
- ネットワーク構築費・センサー設置費
補助金は「導入費」ではなく「変革投資」
補助金は“導入のための費用補助”にとどまらず、組織の仕組みを変えるための投資として捉えることが重要です。
制度を活用してDXを始めることは、コスト削減ではなく「未来への資産化」。
導入後の運用・教育・改善を含めた中長期の“投資設計”が成功の分岐点になります。
介護DXを阻む課題と乗り越える方法
介護DXの必要性は広く理解されつつありますが、現場で本格的に定着させるには多くの壁があります。
ツールを導入しても使われない、現場が疲弊する、コストに見合わない——。
こうした課題を放置すれば、DXは「導入して終わり」の一過性の取り組みになってしまいます。
ここでは、介護DXがつまずきやすい4つの壁と、その乗り越え方を整理します。
現場のITリテラシー格差
課題:
介護職員の中には、デジタルツールに苦手意識を持つ人も少なくありません。
世代間や職種によるスキル差が大きく、ツール操作に時間がかかることで、むしろ“業務が増えた”と感じてしまうケースもあります。
解決策:
- 小さく始めて慣れる場をつくる。
いきなり全員導入ではなく、リーダー層や若手を中心に“試行チーム”を作ることで心理的ハードルを下げる。 - 教育の仕組みを併走させる。
ツール操作だけでなく、「デジタルで何が便利になるのか」を実感できる研修を行うことで、自然とリテラシーが底上げされる。
DX定着の鍵は“慣れる”こと。
人材育成フェーズを初期から設計に組み込むことで、現場が自走できるDXへ。
コスト・ROI(費用対効果)問題
課題:
中小規模の介護施設では、導入コストが負担に感じられやすい。
「導入費用に見合う成果が出るのか?」というROI(投資対効果)への懸念が、DX推進をためらわせる要因になっています。
解決策:
- 補助金を活用して初期投資を抑える。
前章で紹介した国・自治体の支援策を活用し、費用を“変革投資”として捉える。 - 定量効果を“見える化”する。
業務時間の短縮・残業削減・離職率改善などのKPIを定期測定し、成果を経営指標として報告する。
DXは「費用」ではなく「未来への投資」。
経営指標にKPIを組み込むことで、数字で語れるDXへ。
現場と経営の温度差
課題:
経営層が推進しても現場が納得しなければ、DXは形骸化します。
逆に、現場が問題意識を持っていても経営の理解がなければ、導入予算が下りません。
解決策:
- 双方向の対話を重ねる。
導入目的・期待効果・不安点を双方で共有し、「なぜ今やるのか」を全員が理解する。 - 現場からの“成功事例”を発信する。
現場で成果を上げた職員の声を社内で共有し、組織全体にポジティブな空気をつくる。
「人を巻き込むDX」が、最も強い推進力。
小さな成功を経営と現場で共有する文化をつくることが、定着の最短ルートです。
継続運用の難しさ
課題:
DXは導入後こそが本番。
システム更新や操作ルールの形骸化など、運用が続かないことで「結局紙に戻る」事例も少なくありません。
解決策:
- 運用責任者・DX推進担当を明確にする。
現場ごとに“DXリーダー”を配置し、定期的な運用点検を実施。 - 成果を可視化して共有する。
KPIをダッシュボード化し、数字で「できている実感」を持たせる。
継続の鍵は“仕組み+習慣”。
AIレポートや自動分析機能を活用すれば、運用管理の負担を最小化できる。
人×仕組みで「止まらないDX」をつくる
介護DXを阻む壁の多くは、「ツール」そのものではなく「使う人と仕組み」の問題です。
だからこそ、“人材育成×デジタル基盤×継続改善”の三位一体設計が欠かせません。
- 小さく始めて継続する
- 成功体験を共有し、文化にする
- 人材研修で自走する現場を育てる
DXは、導入ではなく「育てる」もの。
人と仕組みを一緒に進化させていくことが、介護現場を本当に変える唯一の道です。
成功事例から見る「介護DXで変わった現場」
DXは単なる理論ではなく、すでに多くの介護施設で成果を上げています。
ここでは、実際にDXを導入して業務・人材・ケア品質がどう変化したのか、具体的な数字とともに紹介します。
“成功の裏側”にある工夫や課題もあわせて見ていきましょう。
事例①:記録時間を1日40分削減/離職率20%改善(特別養護老人ホーム)
東京都内の特別養護老人ホームでは、紙ベースのケア記録をデジタル化し、タブレット入力+自動レポート生成を導入。
これにより、1人あたりの記録時間が平均40分/日短縮されました。
削減された時間はケアやレクリエーションに充てられ、利用者との会話時間が増加。
職員アンケートでは「残業が減り、心身の負担が軽くなった」との回答が7割を超え、離職率も前年比20%改善。
DXが“働きやすさ”と“やりがい”の両立を後押しした事例です。
学びのポイント
小規模導入から始め、成功体験を全体に広げたことで現場の理解が深まった。
技術導入と並行して“使い方を学ぶ場”を設けたことが、定着の鍵となった。
事例②:AI見守りで夜勤の安全性向上(有料老人ホーム)
神奈川県の有料老人ホームでは、AIカメラとIoTセンサーを組み合わせた「見守りDX」を導入。
夜間の転倒や離床検知を自動で通知し、職員の巡回回数を1夜あたり平均40%削減。
同時に、夜勤者1人あたりの対応件数を30%軽減し、安全性と心理的安心の両立を実現しました。
導入当初は「AIが人を置き換えるのでは」という懸念もありましたが、 運用を続ける中で「AIが“守ってくれる存在”になった」と現場の意識が変化。
人の負担を減らすだけでなく、“安心して働ける環境づくり”が進んだ事例です。
学びのポイント
AI技術を「人を支える補助」として位置づけることが、現場の抵抗をなくす。
定期的な運用レビューとデータ共有で信頼を醸成した。
事例③:研修DXで新人教育効率が2倍(訪問介護)
大阪府の訪問介護事業所では、教育担当者の業務負担を軽減するために「生成AI×eラーニング」を導入。
ChatGPTを活用した模擬会話研修や、オンラインでのマナー・安全教育を展開した結果、
新人職員の育成期間を従来の半分(約3か月→1.5か月)に短縮。
また、研修理解度テストの平均点が25ポイント向上し、現場でのミス発生率も約30%減少。
「教育がデジタル化したことで、全員が同じ水準で学べるようになった」と管理者も評価しています。
学びのポイント
DXは“現場の学び方”そのものを変える。
属人化していた教育ノウハウを仕組み化することで、安定した育成体制を構築。
事例④(番外):失敗から学ぶ「導入後に止まったDX」
ある中規模施設では、クラウド記録システムを導入したものの、半年で利用が停滞。
原因は、「操作教育が不十分」「担当者が退職して引き継ぎができなかった」ことでした。
その後、推進体制を再構築し、現場リーダー層に対してAI研修+運用マニュアル整備を実施。
“DX担当者がいなくても回る仕組み”を構築したことで、再稼働後は運用継続率が95%以上に回復しました。
学びのポイント
失敗の多くは「人の不在」に起因する。
DX推進は「仕組み×人材育成」でセットにすることが定着の条件。
成果の裏に“育成”と“仕組み”がある
これらの事例に共通するのは、どれも「人を置き去りにしないDX」であること。
ツールを入れただけではなく、教育・運用・改善のサイクルを組み込んだことが成功の理由です。
- 成果を数値で可視化する
- 現場が“納得して使う”環境を整える
- 人材育成と文化づくりを同時に進める
DXの成功は、テクノロジーではなく「人を動かす仕組み」から生まれます。
これは、介護業界に限らず、あらゆる業種の組織変革にも通じる普遍的な原則です。
これからの介護DX|生成AIとデータがつくる次のステージ
介護DXは今、第二の進化段階に入りつつあります。
これまでの“記録・報告のデジタル化”に加え、生成AIやデータ分析を活用して「考える介護」へ進化する時代が始まっています。
ここでは、次世代の介護DXを支える4つの新潮流を紹介します。
① 生成AIによるケアプラン作成支援
利用者ごとのケアプラン作成には、膨大な情報整理と文書作成が必要です。
生成AIを活用すれば、過去の記録・バイタル・職員コメントをもとに、提案型のケアプランを自動生成することが可能になります。
AIが作成した案を人が確認・修正する形で、計画策定時間を最大70%短縮した事例も登場。
さらに、文章表現のばらつきを防ぎ、プランの品質を一定水準に保てる点も大きなメリットです。
ケアマネジャーの知識を補完し、経験の浅い職員でも精度の高いケア設計が行えるようになります。
AIは「判断を奪う」ものではなく、「判断を支える」存在。
人の専門性とAIの分析力を組み合わせることで、より質の高いケアが実現します。
② 音声→自動記録→要約の流れが現実化
職員の“書く負担”を限りなくゼロに近づける技術も急速に進化しています。
音声入力による記録だけでなく、AIが会話内容を自動で要約・分類し、日報や報告書を生成する仕組みが現実化。
たとえば、利用者とのやり取りを記録した音声をもとに、AIが自動で「介助内容」「特記事項」「注意点」を抽出。
これまで30分かかっていた記録が、わずか数分で完了するようになります。
介護DXの最終形は、“人が入力しないDX”。
データ入力そのものをAIが担い、人は判断とコミュニケーションに集中できる時代へ。
③ データ分析で「働き方改善」も可能に
データは、ケア品質だけでなく「職員の働き方改善」にも活かせます。
AI分析を通じて、業務量・残業時間・シフト偏りなどを可視化すれば、人員配置の最適化や業務バランス調整が定量的に行えるようになります。
また、職員満足度調査や離職データをAIで分析することで、“辞める前兆”を早期検知することも可能。
データを“人の働きやすさ”に活かす——これこそ、次世代DXの価値です。
DXのゴールは「効率化」ではなく、「持続可能な働き方の実現」。
データは現場を守る羅針盤になります。
④ AI×人材育成=“自走できる介護現場”へ
AIが進化するほど、求められるのはそれを活かせる人材です。
ChatGPTなどの生成AIを研修・教育に取り入れれば、職員が「質問しながら学ぶ」対話型の学習が可能に。
AIが個人の理解度に合わせて教材を最適化し、現場リーダーが“育つ仕組み”を作り出します。
AIが単なるツールではなく、“伴走する教育者”になる時代。
現場が自ら考え、改善を提案できるようになれば、組織は「指示待ち」から「自走型」へ変わります。
技術を導入するだけでは文化は変わらない。
人がAIを使いこなす力=DXの定着力です。
まとめ|介護DXは“人を支えるDX”である
介護DXの目的は、決して「人を減らすこと」ではありません。
人の時間を増やし、人がより価値ある業務に集中できる環境をつくることこそが、その本質です。
デジタル技術は“人を置き換えるもの”ではなく、“人を支える力”として介護現場に寄り添います。
ツールを導入することがゴールではなく、技術と人が共創しながら成長する仕組みを育てることが、これからのDXの姿です。
一歩を踏み出す勇気があれば、現場は確実に変わります。
小さな効率化から、働き方の改善、そして「働く人の笑顔」が増える未来へ。
AI経営総合研究所は、その変革の一歩を後押しします。
生成AI研修を通じて、“考える現場”“自走する組織”を育てていきましょう。
- Q介護DXとは何ですか?どんな取り組みを指すのでしょうか?
- A
介護DXとは、デジタル技術を活用して介護業務の効率化やケアの質向上を図る取り組みです。
単にシステムを導入することではなく、「人×仕組み」の両面で業務を再設計することが目的です。
たとえば、記録業務の自動化、AI見守りシステム、オンライン教育などが介護DXに該当します。
- Q介護DXを進めると、どのようなメリットがありますか?
- A
業務効率化による残業削減、人材不足の緩和、ケア品質の均一化などの効果が期待できます。
実際に、DX導入後に記録時間が1日40分短縮・離職率が20%改善した事例もあります。
「人を減らす」のではなく、「人の時間を増やす」ことが介護DXの目的です。
- Q介護DXに必要な費用や補助金制度はありますか?
- A
国や自治体が、介護DXを推進するための補助金制度を整備しています。
代表的なものに「介護現場におけるICT導入支援事業」「介護ロボット導入支援事業」などがあり、
導入費用の1/2〜3/4が補助対象となるケースもあります。
自治体によって申請時期や上限額が異なるため、最新情報を確認しましょう。
- Q職員がデジタルに苦手でも導入できますか?
- A
問題ありません。
介護DXの成功には、段階的な導入と教育が欠かせません。
最初から全員に使わせるのではなく、リーダー層や若手職員を中心にスモールスタートを行い、
慣れる時間を確保することでスムーズに定着します。
AI経営総合研究所では、リテラシー研修や生成AIの活用講座など、人材育成支援も行っています。
- QDXを導入しても定着しないのはなぜですか?
- A
原因の多くは「人材育成」と「運用設計」の不足です。
ツールを導入しても、“使う目的”が共有されていなければ現場は動きません。
定着の鍵は、現場と経営の共通認識づくり+継続的な教育体制。
特に、現場のリーダー層にDX推進の役割を持たせると定着率が上がります。