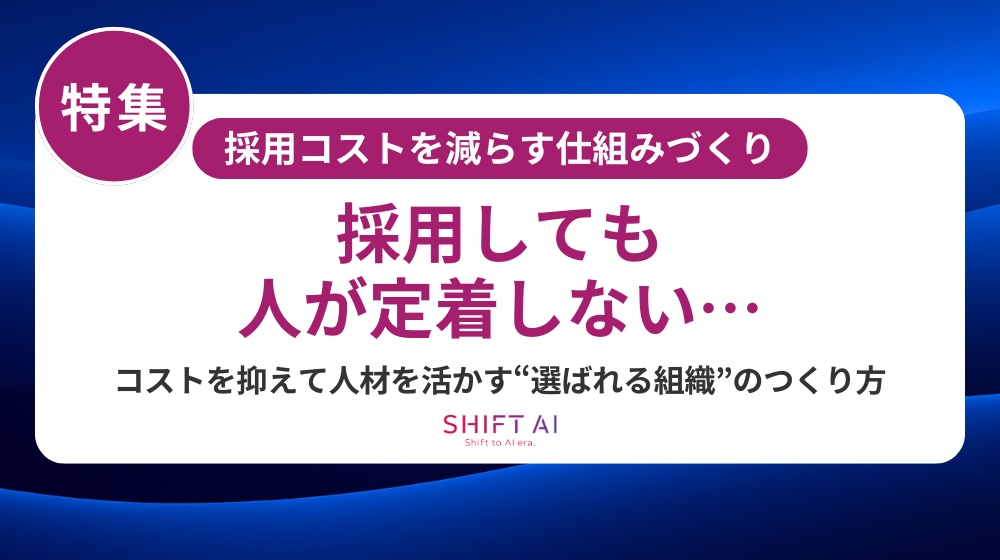「人が辞めるたびに、また採用。教育も現場任せで属人化している──」
そんな状況に心当たりはありませんか?
多くの企業が人材不足に悩む中、「採用してもすぐ辞める」「教育にコストをかけても定着しない」といった声が後を絶ちません。その原因の多くは、育成の仕組みが社内に存在しないことにあります。
外部研修に頼りきっても、現場との乖離や一過性の「やった感」で終わってしまうことも少なくありません。いま求められているのは、「採用よりも社内で人材を育てる力」。そして、それを仕組み化することです。
本記事では、属人化せずに社内で人材を計画的に育てる方法を、下記の内容で詳しく解説します。
- 育成が機能しない理由
- 成功企業の育成戦略
- 教育体系・スキルマップのつくり方
- 生成AIを活用した効率化手法
SHIFT AIでは、法人向けに生成AI研修をご提供しています。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ今、社内で人材育成を強化すべきなのか?
人材不足が続くなか、多くの企業が「人が足りない」ではなく、「育たない」「育てられない」という壁に直面しています。
採用してもミスマッチや離職が続き、教育に投資しても定着しない。こうした状況を抜け出すには、属人的な教育や一時的な外部研修に頼るのではなく、社内に人材を計画的に育てる「仕組み」が必要です。
ここではまず、なぜ今「社内育成」に本気で取り組む必要があるのかを、3つの観点から深掘りしていきます。
採用に頼り続けるリスク:コスト高騰・人材のミスマッチ・定着率の低下
「採用コストは年々増えているのに、採ってもすぐ辞める」これは、いま多くの人事・経営者が抱える現実です。
- 1人あたりの採用単価:中途で約30万円、新卒で約50万円
- 定着率:新卒で3年以内離職が約30%、中途でも1年未満離職が急増中
さらに、採用にはコストだけでなく「時間」「現場の工数」「オンボーディングの手間」も発生します。
そしてなにより、「ミスマッチだった」「想定よりスキルが低かった」というケースが多発すれば、現場の疲弊と士気低下にもつながります。
結果として、人材確保が目的化し、本来注力すべき「育成」や「活躍」への視点が置き去りになってしまうのです。
出典:リクルートエージェント|ダイレクトリクルーティングの費用相場は?料金形態やサービスの選び方を紹介
出典:厚生労働省|新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します
H3|外部研修の限界:「やった感」で終わる/業務と乖離
外部研修は手軽に始められ、一定の体系化されたカリキュラムを提供してくれます。
しかし、次のような課題が浮上する可能性があります。
- 自社の業務内容や課題とリンクしていない
- 受講後の行動変容につながらない
- 上司や現場が学びを活かす前提を持っていない
- 結果的に「やった気」だけで終わる
つまり、外部研修は“点”の学びに留まりがちなのです。
一方、社内育成は現場と密接に連携しながら、「現実の業務の中で学び、実践し、定着させる」ことが可能です。これこそが、外部研修では得られない社内育成の大きな強みと言えるでしょう。
社内育成は「戦略的人事」への第一歩
社内育成を成功させることは、単なる「教育の効率化」ではありません。それは、組織の競争力そのものを高める戦略であり、「人を活かす経営」に直結します。
具体的には
- 社員のスキルや成長段階を可視化し、的確な配置や登用ができる
- 属人化を防ぎ、ナレッジを“組織の資産”として蓄積できる
- 中長期的なリスキリングやキャリア形成が可能になる
つまり、人材開発は「経営戦略」として再設計すべきテーマであり、社内育成の仕組みはその中核です。
社内人材育成がうまくいかない企業の共通点
せっかく採用した人材も、「研修をして終わり」「成長が見えない」「離職してしまう」。そんな状況に、心当たりはありませんか?
人材育成がうまくいかない企業には、いくつかの共通した“つまずきポイントがあります。
ここでは、ありがちな失敗パターンを4つに整理してご紹介します。自社がどれに当てはまるかをチェックしながら、課題を可視化してみてください。
①目的やスキルの定義が曖昧なまま始まっている
よくあるのが、「育成の目的がふわっとしている」状態です。
- 何のために育成するのか(戦力化?次世代リーダー?)
- どんなスキルを、どのレベルまで伸ばせば合格なのか
- そのスキルは業務にどうつながるのか
こうした点が定義されていないと、育成は“熱意任せ”になり、評価も感覚的になってしまいます。この状態では、学習意欲も上がらず、育成担当者も疲弊します。
②属人化したOJTで教える人によって差が激しい
OJTは現場で実務を通じて学べる効果的な手法です。
しかし、育成の仕組みがない状態でOJTに頼ると、「◯◯さんに教わるとわかりやすいけど、△△さんは厳しいだけで全然教えてくれない」など、教え方のバラつきや属人化が顕在化します。
結果的に、育成が組織として機能せず、人材育成が個人の資質任せになってしまうのです。
関連記事
属人化からの脱却方法|生成AIで仕組み化を実現する手順と事例
③教育体系が存在せず、コンテンツも場当たり的
以下のような状況に陥る企業は少なくありません。
「前に使った資料を流用しておいて」
「マニュアルはあるけどどこにあるかわからない」
「そもそも誰が何を教えるべきか決まっていない」
こうした状態では、育成が継続せず、“点”で終わってしまいます。
本来は、教育体系図・スキルマップ・キャリアステップ表など、組織全体の設計が必要です。
④育成と評価・配置が連動していない
人材育成が“機能する組織”では、育成と人事評価、配置・登用が連動しています。一方で、多くの企業では「教育と評価が切り離されている」状態にあります。
- スキルが身についたかどうかが評価されない
- 成長しても役割やキャリアに反映されない
- フィードバックの場がなく、育てっぱなし
これでは育成の意義が薄れ、モチベーションの低下と離職の温床になります。
ここまでの共通点にひとつでも当てはまったら要注意です。
社内育成のメリットと、外部研修との違いを整理しよう
「うちでは研修=外注」「とりあえずOff-JTで基礎を学ばせて、OJTで何とかしてる」。このように、教育が外部任せになっている企業は多く見られます。
もちろん外部研修にはメリットもありますが、業務との接続性や定着率の観点から見ると、社内で育成を仕組み化している企業ほど人材力を高めています。
ここでは、「外部研修と社内育成の違い」を比較しながら、社内育成の強みをわかりやすく整理します。
【比較表】外部研修と社内育成の違い
「うちのような中小企業に社内育成は本当に必要?」「やっぱり外部に任せたほうが楽では?
そんな悩みをお持ちの方のために、外部研修と社内育成、それぞれのメリット・デメリットを客観的に比較した表をご用意しました。
自社の状況や課題に照らしながら、最適な方法を見つけていきましょう。
| 比較項目 | 外部研修 | 社内育成(内製型) |
| 教育内容の柔軟性 | 汎用的。内容は固定 | 自社課題に応じて設計可能 |
| 実務との接続性 | 一般論が中心。現場で活かしづらいことも | 業務に直結。即実践できる設計が可能 |
| 定着率 | 単発で終わりがち | 継続的フォローが可能。定着しやすい |
| 費用感 | 1人あたり数万円〜。継続的にかかる | 初期は設計コストがかかるが中長期で低コストに |
| ナレッジ蓄積 | 蓄積されない | 教材や仕組みが組織資産として残る |
| 属人化リスク | 講師次第で内容が左右される | 組織標準として整備可能 |
「社内育成の仕組み」がある企業は、教育を“場当たり”ではなく再現可能な資産として運用しています。
社内育成は「定着率・現場適応性・コスパ」で勝る
とくに注目すべきは現場との接続性と育成後の変化です。外部研修は理解したつもりで終わってしまうことも多く、現場での行動変容が起きにくいのが実情です。
一方で、社内育成は業務と密接に紐づいており、学びを即座にアウトプットできる環境が用意しやすくなります。
また、外注に頼ると研修のたびに費用がかさみますが、社内育成は一度仕組みを構築すればコストの平準化・低減が可能。教育の投資対効果という視点でも優位です。
「内製×外部のノウハウ」ハイブリッド型という選択肢も
とはいえ、社内で全て完結するのが難しいという企業も少なくありません。そうした場合は、「外部ノウハウを取り入れつつ、社内で運用できる仕組みを整える」というハイブリッド型が現実的かつ有効です。
例としては、
- 外部の生成AI研修を導入し、社内ナレッジとして再活用
- ベースとなるスキルマップや教育体系は外部と共創し、現場主導で展開
このように、「部分的に外注しながら、最終的には内製で回せる」仕組みにすることで、育成の自走化を実現できます。
社内育成を成功に導く「4つの仕組み」
社内育成は「やったほうがいい」とわかっていても、「どこから手をつけたらいいかわからない」 「現場任せで全体設計ができていない」という声が非常に多いのが実情です。
ですが安心してください。社内育成を成功に導くには、やみくもに始めるのではなく、4つの仕組みを順に整えることがカギになります。
①目的・ゴールの明確化:どんな人材をどう育てたいのか?
まず最初に取り組むべきは、「育成の目的とゴールの明文化」です。
- どんなスキルを持った人材を育てたいのか?
- それはどの部署・職種にとってどんな価値があるのか?
- どこまで育ったら“完了”なのか?(レベル定義)
このように「人材像」と「ゴール基準」を可視化することで、育成は個人の感覚から組織の戦略になります。
<ヒント>
人事戦略や中期経営計画に育成のKPIをリンクさせると、経営視点とも一貫性が生まれます。
②教育体系図・スキルマップの構築:育成を“見える化”する
育成のゴールが決まったら、次は「育成の全体像を構造化する」ステップです。
- 教育体系図:誰に、いつ、何を、どの手法で教えるかの全体設計
- スキルマップ:職種・レイヤーごとのスキルとレベルを一覧化したもの
これらが整備されることで、「属人化」や「場当たり的な指導」が防げるようになります。
また、社員も自分の“現在地”と“目標地点”がわかることで、育成が納得感あるキャリア支援に変わります。
関連記事
▶︎ 採用業務を効率化する6ステップ!生成AIの活用法・成功事例・チェックリストまで完全解説
③育成手法の最適化:OJT/Off-JT/eラーニング/生成AI活用
育成方法は一つではありません。重要なのは、目的に応じて手法を最適化することです。
| 手法 | 特徴 | 活用例 |
| OJT | 実務を通じた学習 | 現場スキル・業務フローの習得 |
| Off-JT | 講義や集合研修 | 理論・マインドセットの習得 |
| eラーニング | スキマ時間での学習 | 自主学習・復習・知識定着 |
| 生成AI支援 | 個別化・即時対応が可能 | 育成コンテンツ生成/FAQ対応/スキル習得サポート |
とくに注目したいのが生成AIの活用です。育成計画の作成、社員一人ひとりに合った学習課題の提示、ロールプレイの文章化など、従来は手間がかかっていた育成の運用業務が劇的に効率化します。
関連記事
▶︎ 生成AIで残業時間を月30時間削減?成功企業に学ぶ業務効率化の実践法
▶︎ 「形だけの業務効率化」を脱却するには?改善の再設計ステップと生成AI活用術
④効果測定と改善のPDCA運用:やりっぱなしを防ぐ
最後に整えるべきなのが、育成の効果測定と改善サイクル(PDCA)です。
- 研修後アンケートだけで終わっていないか?
- 実務でどう活かされているかを観察・面談できているか?
- 次回の育成計画に反映されているか?
このサイクルが回って初めて、「育てて終わり」から脱却し、育成が組織の成長戦略として機能するようになります。
【チェックリスト】社内育成が「仕組み化」できているか確認しよう
「社内育成が大事なのは分かった。でも、うちはもうやってるし大丈夫じゃない?」そんな方も、本当に仕組みとして機能しているのか?を一度冷静にチェックしてみましょう。
以下のチェックリストに、いくつ「YES」がつくかで、現在の育成体制の成熟度が見えてきます。
<社内育成 仕組み化チェックリスト(10項目)>
| No | チェック項目 | YES/NO |
| 1 | 育成の目的や「あるべき人材像」が明文化されている | □ YES / □ NO |
| 2 | 教育体系図やスキルマップが整備されている | □ YES / □ NO |
| 3 | 職種・役職ごとに育成カリキュラムが定義されている | □ YES / □ NO |
| 4 | OJT/Off-JT/eラーニングなどが意図的に設計されている | □ YES / □ NO |
| 5 | 教育コンテンツが最新化され、社内で一元管理されている | □ YES / □ NO |
| 6 | 育成後の行動変容やスキル定着を定期的に測定している | □ YES / □ NO |
| 7 | 人事評価・配置と育成が連動して設計されている | □ YES / □ NO |
| 8 | 現場の上司・育成者に対する指導スキル支援が行われている | □ YES / □ NO |
| 9 | 社員が自分の成長ステップを自発的に確認できる仕組みがある | □ YES / □ NO |
| 10 | 育成の設計・運用においてAIやツールを活用している | □ YES / □ NO |
チェック結果の目安
- 8〜10個がYES
→ 素晴らしい!社内育成の「戦略化・自走化」が進んでいます。 - 5〜7個がYES
→ 一部の仕組みは整っていますが、属人化や定着の課題が残っている可能性大。 - 0〜4個がYES
→ 要注意!育成はしているつもりでも、仕組みとして機能していない状態かもしれません。
<育成の仕組み化に自信が持てなかった方へ>
SHIFT AIでは、教育体系の設計・コンテンツ整備・生成AIを活用した学習支援まで、企業ごとの課題に合わせた育成プログラムをご用意しています。
「教育×生成AI」で社内育成はここまで変わる
従来の社内育成は、「計画を立てるのに時間がかかる」「現場に負担がかかる」「効果が見えにくい」など、仕組み化に時間と工数がかかるのが難点でした。
しかし、今や生成AIの登場によって育成の在り方そのものが変わろうとしています。
ここでは、実際にSHIFT AIが提供している法人研修支援でも活用されている、生成AIを活用した育成改革のインパクトをご紹介します。
業務と育成を並行で回す:生成AIによるOJT支援
現場では、教える余裕がなくて育成が後回しにされがちです。そこで活躍するのがAIによる伴走型OJT支援です。
- チャット形式で新入社員が質問できる「仮想メンターAI」
- 実務マニュアルや社内ナレッジをAIがその場で要約・解説
- 日報や行動記録をもとに「次の学習ステップ」を自動提示
現場の負担を最小限にしながら、日常業務=育成の場に変えることが可能になります。
関連記事
▶︎ 生成AIで残業時間を月30時間削減?成功企業に学ぶ業務効率化の実践法
スキル可視化・進捗トラッキングの自動化
生成AIは「育成の進捗」や「スキル習得度」を可視化する上でも強力な武器です。
- 学習ログや業務データを分析し、どこまで理解できているかを自動評価
- 個人別の“伸び悩みポイント”を分析し、ピンポイントで追加教材を提示
- チーム全体の成長傾向をダッシュボード化し、人事が戦略的に把握可能
これにより、教育が属人的な印象評価から客観的なデータドリブンへと進化します。
社員一人ひとりに合わせた育成が可能になる
従来の研修では、同じ内容を全員に一斉に届ける「画一型」が主流でした。しかし生成AIを使えば、各社員のスキルや理解度、業務内容に応じてパーソナライズした学習支援が可能になります。
- Aさんには応用問題、Bさんには基礎の復習
- マネージャーにはリーダーシップ課題、若手には実務演習
- 過去の失敗傾向から“つまずきやすいポイント”を事前予測し、対策を打てる
まさに、社員一人ひとりに寄り添う育成が「人手をかけずに」実現できる時代が来ています。
関連記事
▶︎ 「形だけの業務効率化」を脱却するには?改善の再設計ステップと生成AI活用術
まとめ|採用より育成!SHIFT AIと一緒に社内育成を再構築しましょう
人材育成を社内で仕組み化することは、今や「コスト削減」や「人材の定着」だけでなく、企業の競争力を左右する戦略的テーマです。
採用に頼らず、外注に流されず、自社の中で人を育て、活かせる組織をつくることこそ、持続可能な成長のカギです。
そして、生成AIの力を使えば、その育成は属人化しない・迷わない・再現できる形で実現できます。
<この記事で分かったこと>
- 採用依存・外注任せのリスクと限界
- 社内育成を成功させる「4つの仕組み」
- 仕組みの成熟度を確認できるチェックリスト
- 生成AIで変わる「育成の効率・深さ・再現性」
<ここまで読んで「やってみたい」と思った方へ>
SHIFT AIでは、教育体系の構築から生成AIを活用した育成支援まで、貴社の課題に寄り添った法人向け研修プログラムをご提供しています。
まずは、導入事例・設計フロー・支援内容をまとめた資料をぜひご覧ください。
社内育成に関するよくある質問(FAQ)
- Q社内育成はどこから手をつけるべきですか?
- A
最初に行うべきは「育成の目的」と「ゴール(人材像)」の明確化です。これが曖昧だと、育成方針や手法選定もブレてしまいます。本記事で紹介した「4つの仕組み(目的→体系図→手法→PDCA)」を参考に、まずは全体像を設計することをおすすめします。
- Qスキルマップや教育体系図を社内で作るのは難しくないですか?
- A
はい、ゼロから独自で構築するのは正直大変です。そこで活用できるのが、外部の知見やテンプレート支援です。SHIFT AIでは、業種別の育成テンプレートや生成AIによる支援ツールをご用意していますので、ご負担を大幅に軽減できます。
- Q小規模な会社でも社内育成はできますか?
- A
可能です。むしろ小規模組織こそ、人材の成長=事業成長に直結するため、育成の仕組み化が大きな効果を生みます。属人化しがちな教育も、仕組みを入れることで他メンバーへの展開・定着が進みやすくなります。
- Q社内育成と人事評価はどう連動させればいいですか?
- A
理想は、スキルマップや成長段階に応じて評価基準を紐づけることです。たとえば「◯◯の業務が自立してできるようになったらB評価」など、定性的な行動を定量評価に落とし込む仕組みづくりがカギになります。
- Q社内育成に生成AIを取り入れるには何から始めれば?
- A
まずは「どこに時間がかかっているか」「属人化しているか」を棚卸してみましょう。その上で、育成計画の作成支援・育成コンテンツの自動化・社員ごとの学習支援などから導入するのがスムーズです。 SHIFT AIでは、生成AIを育成に取り入れるステップを段階的にサポートしています。
- Q導入相談だけでもできますか?
- A
はい、可能です。SHIFT AIでは、法人向けに「育成戦略×生成AI」領域の無料相談/課題ヒアリングも実施中です。まずは資料をダウンロードいただいた方に、導入相談のご案内もお送りしています。