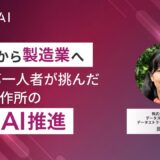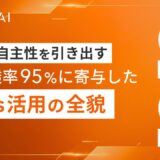フードデリバリーサービスを展開する株式会社出前館。同社は「テクノロジーで時間価値を高める」をミッションに掲げ、ユーザー・加盟店・配達員・従業員といった多様なステークホルダーを支えるサービス基盤を築いてきました。
同社の生成AI活用は、2023年に加盟店向けプロダクトへの導入から始まりました。その後、2025年には従業員の業務効率化を目的として、ChatGPTなどのAIツールが各部門へと展開されています。背景には、IT本部の執行役員本部長 兼 VPoEを務める米山氏の強い危機感がありました。
「導入しないことこそリスク」と語る米山氏は、ROI(投資対効果)が短期的に見えにくい中でも積極的な活用を推進。従業員が安心してAIを使えるよう、eラーニングや生成物のレビュー制度を整え、社内文化として定着させる取り組みを進めています。
米山氏はこう強調します。
「生成AIは短期的な人員削減ではなく、一人ひとりの市場価値を高め、“できることを3倍にする”ためのツールです」
現場からはすでに、営業企画による業務効率化やCS部門での問い合わせ対応支援など、具体的な成果が報告されています。単なる効率化を超え、生活インフラを支える存在へ。出前館の取り組みは、生成AI活用に迷う企業にとって大きな示唆を与えています。

株式会社出前館
執行役員 IT本部 本部長 兼 VPoE
2021年に出前館へ入社。プロダクト本部にて採用戦略の立案・実行を担い、組織の基盤を構築。その後、IT本部の立ち上げを主導し、業務オペレーションの最適化や社内システムの抜本的な改革を推進。現在は執行役員として、出前館全体のIT戦略を統括し、事業の成長を支えるIT基盤の強化に取り組んでいる。
※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
多くの企業を阻む「ROIの壁」と、出前館の“逆張り”
生成AIの導入にあたって、多くの企業が直面するのが「ROIの壁」です。出前館も例外ではありません。米山氏は次のように語ります。
「例えば1,000万円を投資したら、すぐに1,200万円分のコスト削減につながる、といった分かりやすい成果は出にくいんです。どちらかというと、生成AIの導入は先行投資です」
短期的な数値化が難しい一方で、現場レベルでは着実な成果が積み上がっています。例えば営業企画チームでは、これまで外部委託に頼っていたアタックリストの作成をAIで自動化し、外注コストの削減に成功しました。米山氏はこう指摘します。
「数字としてはまだ小さいかもしれませんが、従業員が“これは便利だ”と実感している事例は数多くあります。そうした小さな成功体験の積み重ねが、やがて大きなROIにつながると考えています」
米山氏が重視しているのは、ROIという「短期的な成果指標」よりも、生成AIを社内文化として根付かせることです。従業員が日常的にAIを使いこなし、業務を効率化しながら創造的な仕事に注力できるようになれば、結果的に事業全体の生産性は大きく向上します。
「生成AIを導入するかどうかは、もはや選択肢ではなく必然です。すぐにROIが見えなくても進めるのは、将来の競争力を確保するためなんです」と米山氏は語ります。
ROIはすぐに出なくても、長期的な視点で見ればAI活用は避けて通れない。その確信が、出前館の積極的な取り組みを支えています。
「導入しないこと」こそが、最大のコスト(リスク)である
出前館が生成AIの導入を始めたのは2023年からです。最初の取り組みは、業務効率化ではなく加盟店向けプロダクトへの導入でした。従業員による生成AI活用は当初、情報収集やアイデア出しにとどまり、業務効率化に直結する段階には至っていないという問題もありました。
大きな転機となったのは2024年末。ChatGPTのo3が登場した時期です。精度が飛躍的に高まり、「これを使いこなせなければ競争力を失う」という危機感が一気に高まりました。
この危機感は、単に技術トレンドを追いかけるという話にとどまりません。従業員のキャリア形成にも直結していました。米山氏は次のように語ります。
「もちろん従業員には長く出前館で働いてほしいと思っていますが、自身のキャリアやライフプランと向き合って卒業していく人もいます。そのときに市場価値を最大化できていた方が本人にとっても有利です。生成AIを使いこなさないまま外に出るのはもったいないと感じています」
さらに現場では、従業員が個人で契約しているツールを利用してしまう“シャドーIT”のリスクも浮上していました。
「会社として禁止すれば、従業員は無料版や個人ライセンスを使い始めます。それでは会社としてコントロールができず、情報漏洩のリスクが高まります。だからこそ会社として公式な利用環境を急いで整える必要がありました」と米山氏は指摘します。
出前館が生成AI導入を本格化させた背景には、プロダクト改善ニーズ、技術進化への危機感、従業員の市場価値を高めたいという思い、そしてシャドーITのリスク回避が重なっていました。危機感はネガティブに聞こえがちですが、同社にとっては前進を後押しするポジティブな原動力となったのです。
投資を無駄にしないためにガバナンスと文化醸成に注力
生成AIを全社的に根付かせるには、単にツールを導入するだけでは不十分です。出前館では「従業員が安心して、日常的に活用できる環境」を整えることに力を注いできました。
具体的には、利用ライセンスの運用を徹底。利用率の低い従業員のライセンスは回収し、待機リストにいる従業員に割り当てる仕組みを構築しました。結果として常に利用率95%以上を維持し、「使いたいのに使えない」という不満を最小化しています。
また、従業員が安心して生成AIを活用できるよう「公開レビュー」のプロセスを導入しました。生成AIが出力した文章や画像は、専門部署が最終確認を行うルールを設け、文化的・倫理的に不適切な成果物が外部に出ないようガバナンスを徹底。業務に組み込む安心感を高めています。
教育面でも、利用希望者には必ずeラーニングの受講を義務付けました。生成AI特有のリスクや権利問題を理解したうえでアカウントを発行する仕組みとし、全従業員に共通の基盤知識を浸透させています。
さらに、Slack上には専用チャンネルを設け、アップデート情報や活用ノウハウを従業員同士で共有。現場から生まれた小さな成功事例を横展開することで、草の根的な浸透を促しました。米山氏は、生成AIの社内浸透についてこう語ります。
「AI活用はトップダウンの号令だけでは広がりません。従業員が安心して挑戦できる環境を整え、現場からの声を拾いながら促進することが重要です」
出前館における社内促進の取り組みは、単なる導入を超えて「使われ続ける仕組み」を築くことに直結しているのです。
本当の目的はコスト削減ではなく「従業員の能力を3倍にする」こと
AI活用は「効率化=人員削減」と短絡的に語られがちですが、米山氏の考えはまったく逆です。
「人数は変わらなくても、従業員一人ひとりができることを3倍にしたいと思っています。たとえばオペレーション担当者が単純作業から解放され、企画や改善提案など、より高度な仕事に挑戦できるようになる。そうやって市場価値を高められる人材を増やしたいです」
実際、社内ではその兆しが現れています。営業企画チームでは、営業戦略の立案や新規施策の企画といった、よりクリエイティブで影響力の大きい業務に時間を使えるようになっています。
また、カスタマーサポート部門では、若手メンバーが過去事例を学習したAIのサポートを受けながら対応できるようになり、「CSの質を守りつつ人材育成も進む」という相乗効果を生んでいます。
つまり、AIは人を置き換える存在ではなく、人がより人間らしい価値を発揮するための“加速装置”です。議事録作成やデータ整理といった「時間はかかるが付加価値の低い業務」をAIに任せることで、従業員は創造性や判断力を要する領域に集中できるようになります。
「結果として、従業員数は変わらなくても、会社としての生産性は大きく跳ね上がるはずです。これは単なるコスト削減以上に大きな意味があると考えています」と米山氏は語ります。
AIがもたらすのは、効率化の先にある「従業員の成長」と「市場価値の最大化」です。出前館は、人員削減ではなく、従業員一人ひとりの可能性が広がる世界の実現を目指しています。
ROIの先にある未来──AIを「社会インフラ」にするという長期的リターン
出前館が描く未来像は、生成AIを単なる業務効率化のツールにとどめず、生活インフラを支える存在になるために活用することです。
「出前館は“テクノロジーで時間価値を高める”というミッションを掲げています。生成AIはその実現に欠かせない存在です。理想は、水道や電気のように、なくてはならないインフラとして根付いていくことだと思っています」と米山氏はいいます。
例えば、フードデリバリーでは「商品が届かない」「注文内容が間違っている」といったトラブルが一定の確率で発生します。これらは完全に防ぎきれない問題ですが、重要なのは「発生したときにどう解決するか」です。米山氏は次のように語ります。
「AIが即座に状況を判定し、キャンセル処理などの対応を自動で行えるようになれば、ユーザー体験は格段に向上します。一方で、不正の可能性や重篤な問題が発生した場合には人間が介入して精査する。その切り分けをAIが担うのです」
こうした仕組みが実現すれば、多くの問い合わせはAIが即時対応できるようになり、人間は本当に複雑で高度なケースに専念できます。結果として顧客対応のスピードと品質が大きく向上し、フードデリバリーを「安心して使えるライフインフラ」として定着させることができます。
AIに任せる部分と、人が介入すべき部分をきちんと整理すれば、ユーザーにとっても従業員にとっても快適なサービス運営が実現可能です。同社ではそこまで到達して初めて、生成AIが社会に根付くインフラになると考えています。
出前館から学ぶ「真似するべき」5ポイント
出前館の生成AI活用は、特別な技術力や大規模投資に依存するものではなく、多くの企業がすぐに取り入れられる取り組みが多いのが特徴です。再現性の高い取り組みを、5つのポイントに整理しました。
- 危機感を原動力に変える
生成AIの急速な進化に対して「導入しないリスク」を直視し、会社の競争力と従業員の市場価値向上の両面から積極的に取り組む姿勢を学ぶべきです。 - シャドーITを防ぐ公式環境の整備
従業員が個人ライセンスを使ってしまうリスクを認識し、安全に使える公式環境を早期に整えた点は、多くの企業が真似すべき重要な施策です。 - 文化や感覚の違いを踏まえたレビュー体制
AIが生成したコンテンツは文化的背景等のリスクを十分に反映できません。出前館が導入した「公開レビュー」の仕組みは、リスクを最小化する有効な方法です。 - ROIを短期で求めず“投資”として取り組む
すぐに数値化できる成果に固執せず、小さな成功事例を積み重ねて文化として定着させる姿勢は、長期的な競争力につながります。 - AIを生活インフラとして位置づける発想
業務効率化の道具にとどまらず、「人の仕事を拡張する仕組み」「生活を支えるインフラ」として生成AIを捉える視点が、未来を切り拓くカギとなります。
これらの取り組みは、大規模な投資や独自技術を必要とせず、業種や企業規模を問わず応用可能です。特に「シャドーITを防ぐ公式環境づくり」や「公開レビューによるガバナンスの仕組み」は、多くの企業がすぐに取り入れられる実践例と言えるでしょう。
出前館の事例が示すのは、生成AI定着のカギは単なるROIの即効性ではなく、“従業員が安心して日常的に使える仕組み”にあります。導入して終わりではなく、文化や制度にまで落とし込むことこそが、全社的な活用につながる近道です。
しかし、自社でこれを実践しようとすると、
「どの業務領域から導入すべきか?」
「現場の声と経営の方針をどう両立させるか?」
「文化として浸透させるためにどんな制度が必要か?」
といった壁に直面するケースも少なくありません。これは出前館だけでなく、多くの企業が抱えている共通の課題なのです。
SHIFT AIでは、生成AIの活用・研修・展開に関する伴走支援を行っています。「どこから始めればいいかわからない」「全社展開するうえで、ルールや教育の整備が課題」といったお悩みに対して、現場視点に立った設計・支援を提供します。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応

🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?
AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、
業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。