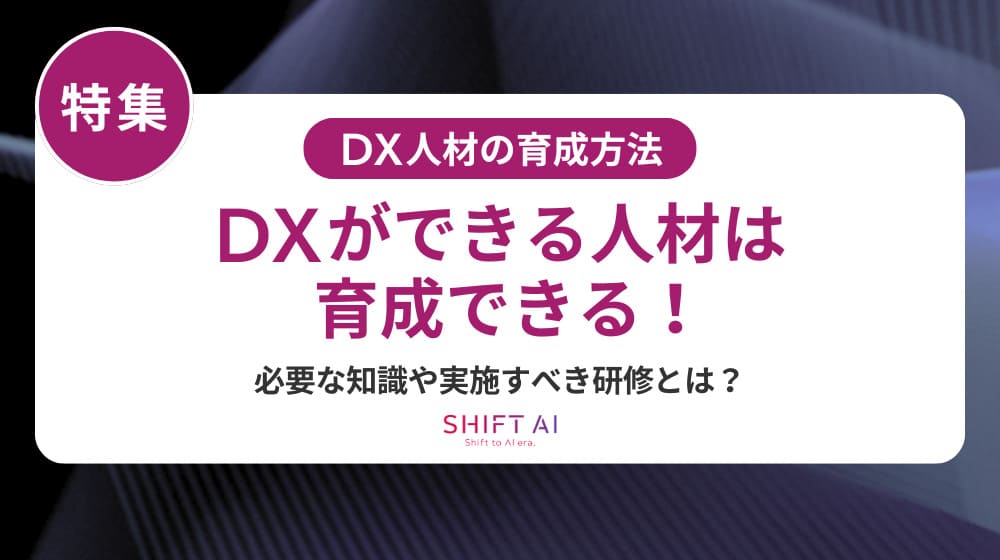「DX推進が必要なのは分かるけれど、社内にDX人材がいない…」
このような悩みを抱えている企業は決して少なくありません。
しかし、外注依存には大きなリスクが潜んでいます。システムがブラックボックス化し、開発コストは膨らみ続け、競合他社との差は広がるばかり。「DX人材を採用すればいい」と思っても、激しい争奪戦で高額な人件費がかかり、定着も困難です。
では、どうすればこの問題を解決できるのでしょうか?
実は、多くの企業が見落としている「社内の潜在DX人材」を発掘し、段階的に育成する方法があります。特に生成AI研修から始めることで、低コストで効果的にDX人材を育成することが可能です。
本記事では、DX人材不足の根本原因から具体的な解決策まで、実践的な方法を詳しく解説します。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
DX人材が社内にいない企業が直面する深刻な課題
DX人材が社内にいない状況は、企業の成長を大きく阻害します。
外注依存やコスト増大、競争力低下など、様々な問題が連鎖的に発生するためです。まずは現状を正しく把握しましょう。
DX推進が完全に外注依存となる
社内にDX人材がいないと、すべてのデジタル化を外部に委託せざるを得なくなります。
システム開発から運用まで外注に頼ることで、自社のノウハウが蓄積されません。また、急なシステム障害や仕様変更が必要な際も、すぐに対応できない状況が生まれます。
外注先の都合に左右されるため、DX推進のスピードも思うようにコントロールできなくなるのです。
システム開発コストが膨らみ続ける
外注依存により、DX関連のコストが継続的に増加していきます。
初期開発費用だけでなく、保守・運用費用、カスタマイズ費用なども外注先に支払い続ける必要があります。特に、自社の業務に合わせたシステム修正を依頼するたびに、高額な費用が発生するでしょう。
さらに、ベンダーロックインの状態になると、価格交渉力も失ってしまいます。
競合他社との差が拡大していく
自社でDXを推進できない企業は、競合他社に大きく遅れをとってしまいます。
DX人材を内製化している企業は、市場変化に素早く対応し、新しいサービスを次々と展開できます。一方、外注依存の企業は対応が後手に回り、顧客ニーズへの適応が遅れがちです。
この差は時間とともに拡大し、最終的には事業の存続にも関わる問題となるでしょう。
社内にDX人材がいない根本的な4つの原因
DX人材が社内にいない状況は偶然ではありません。組織の意識、リーダーシップ、戦略、育成環境の4つの要因が複合的に作用しているのです。
根本原因を理解することで、的確な対策を講じることができます。
社員がDXを「自分事」として捉えていないから
多くの社員が「DXはIT部門の仕事」と考えているため、主体的に関わろうとしません。
DXの必要性は理解していても、自分の業務との関連性を感じられない社員が大半です。「デジタル化は専門知識が必要で、自分には無理」という先入観も強く、学習意欲が湧かない状況が生まれています。
経営層からの発信が不足していることも、社員の無関心につながる大きな要因となっているでしょう。
DXを推進するリーダーが存在しないから
組織全体を牽引するDXリーダーがいないと、変革は進みません。
DXには技術的知識だけでなく、組織を動かすリーダーシップが不可欠です。しかし、多くの企業では「技術に詳しい人=DX担当者」という誤った認識で人選を行い、結果的に推進力のない体制になってしまいます。
真のDXリーダーには、ビジョンを描き、社内を巻き込む力が求められるのです。
DXのビジョンと戦略が不明確だから
「なんとなくDXが必要」という曖昧な認識では、人材育成の方向性も定まりません。
明確な目標がないまま研修を実施しても、社員は学んだスキルをどう活かせばいいか分からず、結果的に形だけの取り組みに終わってしまいます。
DXで何を実現したいのか、どのような人材が必要なのかを具体的に定義することが重要です。
人材育成の仕組みが整っていないから
体系的な教育プログラムや継続的な学習環境がないと、DX人材は育ちません。
単発の研修だけでは、実務で活用できるレベルまでスキルを向上させることは困難です。また、学んだ内容を実践する機会や、メンター制度などのサポート体制も必要でしょう。
投資対効果が見えにくいことも、人材育成への取り組みを躊躇させる要因となっています。
社内にいないDX人材を確保する3つの解決方法
DX人材不足を解決するには、採用・育成・外注協働の3つのアプローチがあります。それぞれに特徴があり、企業の状況に応じて最適な手法を選択することが重要です。
組み合わせて活用することで、より効果的な結果を得られるでしょう。
💡関連記事
👉DX人材育成の完全ガイド|AI時代に求められるスキルと効果的な6ステップ
即戦力のDX人材を採用する
すぐにDXプロジェクトを始めたい場合は、経験豊富な人材の採用が有効です。
新卒採用では、IT系学部出身者やプログラミング経験のある人材を積極的に獲得しましょう。中途採用では、他社でDXプロジェクトを経験した人材や、システム開発の実務経験がある人材が狙い目です。
ただし、DX人材の市場価値は高く、採用競争は非常に激しくなっています。魅力的な労働環境と適正な待遇を用意することが採用成功の鍵となるでしょう。
社内の既存社員をDX人材に育成する
最もコストパフォーマンスが高く、継続的な効果が期待できる方法です。
既存社員は自社の業務を深く理解しているため、実用性の高いDXソリューションを開発できる可能性が高いでしょう。また、企業文化にも馴染んでおり、他部署との連携もスムーズに進められます。
特に生成AI研修から始める段階的なアプローチにより、学習のハードルを下げながら確実にスキルを身につけることができます。
外注パートナーとの協働体制を構築する
完全外注ではなく、パートナーシップ型の協働体制を築くことで効率的にDXを推進できます。
社内人材とITベンダーが密に連携し、知識移転を行いながらプロジェクトを進める方法です。外部の専門知識を活用しつつ、社内にもノウハウを蓄積していけるでしょう。
将来的な内製化を見据えて、段階的に社内の役割を拡大していくことが重要です。
各解決方法のメリット・デメリット比較
3つの解決方法にはそれぞれ異なる特徴があります。自社の予算、時間軸、組織の状況を考慮して最適な手法を選択しましょう。
複数の方法を組み合わせることで、リスクを分散しながら効果を最大化できます。
DX人材採用のメリット・デメリット
即効性は高いものの、コストとリスクも大きい手法です。
メリットとしては、すぐにプロジェクトを開始でき、専門的な知識を活用できる点が挙げられます。また、社内の技術レベル向上にも貢献するでしょう。
一方、デメリットは採用コストの高さと定着率の低さです。採用コストが高額になりがちで、中小企業には負担が重くなります。企業文化への適応に時間がかかることも課題となるでしょう。
社内育成のメリット・デメリット
長期的な投資効果が最も高く、持続可能な手法です。
メリットは、自社業務への理解が深く実用的なソリューションを開発できることです。また、企業への愛着があるため離職リスクも低く、育成投資が無駄になりにくいでしょう。
デメリットは、即効性に欠ける点と教育コストです。スキル習得まで3〜6ヶ月程度かかるため、緊急性の高いプロジェクトには向きません。
外注協働のメリット・デメリット
専門性と内製化のバランスを取れる現実的な手法です。
メリットは、高度な技術を活用しながら社内にノウハウを蓄積できることです。また、プロジェクトの規模に応じて柔軟にリソースを調整できるでしょう。
デメリットは、パートナー選定の難しさと継続的なコストです。相性の良いベンダーを見つけるまで時間がかかる場合があり、長期的にはコストが膨らむ可能性もあります。
社内の潜在DX人材を発掘する具体的な手順
多くの企業に「隠れたDX人材候補」が存在します。適切な手順で発掘・評価・配置を行うことで、短期間でDX推進体制を構築できるでしょう。
既存社員の活用は、最もコストパフォーマンスの高い人材確保手法です。
Step.1|DX適性のある社員を見極める
デジタル技術への関心と論理的思考力がある社員を特定しましょう。
まず、社内アンケートで「新しいツールへの興味」「業務改善への意欲」「学習への積極性」を調査します。普段からExcelの関数を活用したり、業務効率化を提案したりする社員は有力候補です。
変化を恐れずチャレンジする姿勢も重要な適性の一つとなります。部署や年齢に関係なく、幅広い視点で候補者を探すことが成功の鍵でしょう。
Step.2|社内人材のスキルを診断・評価する
客観的な指標でスキルレベルと成長ポテンシャルを測定します。
ITリテラシー診断テストやプログラミング適性検査を実施し、現在のスキルを可視化しましょう。同時に、コミュニケーション能力や問題解決能力も評価する必要があります。
短期間での成長可能性を重視し、現在のスキルよりも学習意欲と適応力を優先して評価することが重要です。
Step.3|適材適所の配置転換を実施する
評価結果に基づいて、最適なポジションに人材を配置します。
DX推進チームを新設するか、既存部署内でDX担当者を任命しましょう。配置転換時は、本人の意向を尊重し、キャリアパスを明確に示すことが大切です。
段階的にDX業務の比重を高めることで、スムーズな移行を実現できるでしょう。
生成AI研修から始めるDX人材育成の効果的なステップ
生成AI研修は、DX人材育成の最適なスタートポイントです。学習コストが低く効果を実感しやすいため、社員のモチベーション維持にも効果的でしょう。
段階的にスキルを積み上げることで、確実にDX人材を育成できます。
生成AI研修から始める
ChatGPTやCopilotなどの生成AIツールの活用方法を習得します。
まず、基本的なプロンプト作成から始めて、業務効率化への応用を学びましょう。文書作成、データ分析、アイデア発想など、日常業務ですぐに活用できる実践的なスキルを身につけることが重要です。
研修期間は2〜4週間程度で、受講者が効果を実感できるレベルまで到達できます。成功体験を積むことで、さらなる学習への意欲を高められるでしょう。
データ活用スキルに発展させる
生成AIで基礎を固めた後、より高度なデータ分析スキルを習得します。
ExcelやBIツールを使った基本的なデータ分析から始めて、統計学の知識やSQLの基礎を学習しましょう。生成AIと組み合わせることで、効率的にデータインサイトを導出できるようになります。
この段階では実際の業務データを使った演習を行い、実務への応用力を高めることが重要です。
高度なDXスキルまで段階的に育成する
最終段階では、システム設計やプロジェクト管理などの高度なスキルを習得します。
プログラミングの基礎、システム開発の流れ、DX戦略の立案など、より専門的な領域に進みましょう。全員がここまで到達する必要はなく、適性のある人材を選抜して重点的に育成することが効果的です。
継続的な学習環境を整備し、社内外の専門家からのサポートを受けられる体制を構築することが成功の鍵となります。
まとめ|DX人材が社内にいない課題は段階的育成で解決できる
DX人材が社内にいない状況は、多くの企業が直面する共通の課題です。しかし、この問題は適切なアプローチにより必ず解決できます。
重要なのは、完璧なDX人材を一度に育成しようとするのではなく、生成AI研修から始める段階的なアプローチを取ることです。社内には思っている以上に多くの「潜在DX人材」が存在しており、適切な発掘と育成により短期間で戦力化できるでしょう。
外注依存を続ける限り、真の競争優位は築けません。一方で、社内でDX人材を育成できれば、長期的なコスト削減と迅速な意思決定が可能になります。
まずは社内の人材適性診断から始めて、小さな一歩を踏み出してみてください。DX人材育成は時間がかかりますが、生成AI研修なら比較的短期間で効果を実感できます。
当社では、DX人材育成に特化した生成AI研修プログラムをご用意しています。

DX人材が社内にいない課題に関するよくある質問
- QDX人材はどのくらいの期間で育成できますか?
- A
生成AI研修から始める場合、基本的なスキル習得までは2〜4週間程度で可能です。その後、データ活用スキルまで発展させるには3〜6ヶ月、高度なDXスキルまで到達するには1〜2年程度を見込んでおきましょう。段階的にスキルを積み上げることで、確実な成長を実現できます。重要なのは継続的な学習環境を整備することです。
- Q社内にIT知識がない社員でもDX人材になれますか?
- A
IT知識がなくても、適性があればDX人材として育成可能です。デジタル技術への関心と学習意欲があることが最も重要な条件となります。生成AIツールは直感的に使えるため、プログラミング経験がない社員でも短期間で業務効率化を実現できるでしょう。むしろ現場業務を深く理解している社員の方が、実用性の高いソリューションを開発できる場合も多いです。
- QDX人材育成にかかる費用はどのくらいですか?
- A
社内育成の場合、一人当たり月額5〜10万円程度の研修費用で始められます。外部から採用する場合の高額な年収と比較すると、大幅にコストを抑制できるでしょう。生成AI研修であれば、さらに低コストでの育成が可能です。長期的には最も投資対効果の高い手法となり、継続的な効果が期待できます。
- Qどの部署の社員をDX人材として育成すべきですか?
- A
特定の部署に限定せず、全社的に適性のある人材を発掘することが重要です。営業、経理、人事など、あらゆる部署にDX人材候補が存在します。むしろ多様な部署から選出することで、それぞれの業務領域に特化したDXソリューションを開発できるでしょう。デジタル技術への関心と学習意欲を最優先に選定してください。
- Q生成AI研修から始める理由は何ですか?
- A
生成AI研修は学習コストが低く、すぐに業務で活用できるため成功体験を積みやすいからです。プログラミング知識不要で即効性があり、モチベーション維持に最適です。ChatGPTやCopilotなどのツールを使って文書作成やデータ分析の効率化を実現でき、DXへの心理的ハードルを大幅に下げられます。段階的なスキルアップの理想的なスタートポイントとなるでしょう。