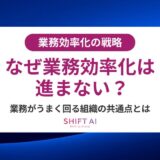「業務効率化を進めたいのに、現場がなかなか動いてくれない」
そう感じたことはありませんか?ツールを導入した。マニュアルも整えた。それでも以下の悩みが尽きません。
- 惰性で旧来のやり方に戻ってしまう
- 属人化された業務が残ったまま
- 「効率化って、結局誰のため?」といった現場の温度差が解消されない
こうした状況に、もどかしさを感じている方は少なくないはずです。
私たちSHIFT AIが多くの企業現場と対話するなかで実感しているのは、「業務効率化が進まない」のは、現場の“能力”の問題ではなく、“構造”の問題であるということ。
つまり、業務の見えにくさ・目的の不明確さ・改善活動の属人化など、“仕組み”が人の行動を止めてしまっているのです。
この記事では、業務効率化が進まない企業に共通する5つの課題を明らかにしたうえで、現場が「やらされ感」なく自走できる改善の仕組みと、その実行を支える生成AI活用のリアルなユースケースを紹介します。
また下記のリンクからは、生成AIを本格導入し「業務改善・効率化」「AI人材育成」を推進し成果をあげている様々な業種の取り組み17選をまとめた事例集をダウンロードいただけます。自社と似た課題感を持つ会社が、どのようにAIを活用しているのか知りたい方はお気軽にご覧ください。
\ 生成AIによる業務効率化の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
業務効率化が進まない5つの根本原因とは?
業務効率化が進まない企業には、驚くほど共通した「詰まりの構造」があります。現場の能力や熱意の問題ではなく、改善を阻む要素が“見えないところ”に潜んでいるのです。
ここでは、SHIFT AIが数多くの組織支援で見てきた5つの根本原因を紹介します。
1. 改善の目的が現場に伝わっていない
効率化が進まない現場の多くで、「なぜ改善が必要なのか」が曖昧なまま施策が進行しています。現場からは「上が勝手に決めたこと」「理由もわからずやらされている」と感じられ、当事者意識が育ちません。
目的と意義が伝わらない改善活動は、行動として形だけになり、すぐに元に戻るのが常です。
2. 属人化された業務がボトルネック化している
「○○さんしかできない仕事」が社内に複数存在していませんか?属人化された業務は効率化の最大の敵です。可視化もできず、代替も利かず、改善対象としても抜け落ちがち。
結果として、誰も手を出せない“ブラックボックス業務”が温存され、効率化の抜け穴となります。
3. 導入したツールが使われていない
業務効率化の一環として、タスク管理ツールやRPA、ナレッジ共有システムを導入する企業は増えています。しかし実態として、「導入しただけ」「一部の人しか使っていない」といったケースが後を絶ちません。
ツール導入は手段であって目的ではありません。「なぜそれを使うのか」まで設計されていなければ、形骸化するのは当然です。
4. 改善が「やらされ感」になっている
トップダウンの改革がうまくいかない理由の一つが、「現場の納得感の欠如」です。改善施策が「現場を管理するためのもの」と認識されると、反発や無関心が生まれ、定着率は大きく下がります。
やらされ感は効率化の敵。現場の巻き込みと、意見を吸い上げる「対話の場」が不可欠です。
👉 関連記事
仕事が楽しくないのは「やらされ感」のせい?その原因と抜け出す3ステップ
5. 組織としての評価・支援体制が機能していない
効率化の取り組みに対して、「何が評価され、どこまで支援されるか」が明確でない企業も多く見受けられます。結果、「やっても報われない」「負荷が増えるだけ」と現場が感じ、改善活動への熱量は落ちていきます。
改善は個人で背負うものではなく、組織で回すものです。評価設計と支援体制が整ってこそ、継続可能な取り組みとなります。
【事例】なぜ業務効率化は戻ってしまうのか?
業務効率化の取り組みを始めた直後は、社内でも一時的に改善意識が高まり、ツール導入やマニュアル整備が進みます。しかし、数ヶ月も経たないうちに元のやり方に戻ってしまう……。そんな経験をしたことはありませんか?
それは、表面的な改善だけでは「現場の構造」や「心理」が変わっていないからです。
ここでは、実際に多くの企業で見られる戻ってしまう理由を3つの事例で紹介します。
事例①ツール導入後も「紙と口頭」が残ったままだった
ある製造業の会社では、日報をクラウド管理できるツールを導入しました。ところが、現場では「紙にメモ→あとでまとめて入力」という二重作業が常態化。結果としてツールは使われず、紙文化だけが残ってしまったのです。
これは、既存業務との接続設計が不十分だったことが原因でした。「どうすれば現場の手間が減るか」まで落とし込めなければ、定着は難しいのです。
事例②ルール重視が窮屈さを生み、離職が増加
別の企業では、業務効率化を目的に業務フローの標準化を進めました。ところが、「フローにないからやれない」「柔軟に対応できない」と、現場では不満が蓄積。
結果として、「ルールは増えたが現場の自由度が失われ、生産性はむしろ低下」してしまったのです。効率化は、現場の裁量とバランスを取りながら進めることが不可欠です。
事例③「改善しろ」と言われただけで支援がなかった
とあるIT企業では、「現場主導で改善しよう」という方針が打ち出されました。ところが、実際には支援も予算もなく、現場に丸投げの状態。
「改善活動=余計な仕事」と認識され、現場は早々に取り組みをやめてしまいました。“やれ”ではなく、“どうやるかを共に考える”支援体制がないと、改善は続かない。それがこの事例の教訓です。
\ 生成AIによる業務効率化の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
改善を定着させる!現場が動き出す3ステップ
業務効率化が“進まない”理由が明らかになったら、次に考えるべきは「どうすれば、現場が動き、改善が定着するのか」です。
重要なのは、「一気に完璧を目指さないこと」。小さな成功体験の積み重ねこそが、現場の自走を促します。
ここでは、SHIFT AIが数多くの企業で導入している改善定着のための3ステップを紹介します。
STEP1:業務の“見える化”で属人化を排除する
業務がブラックボックス化していると、誰も改善の手を入れられません。まずはタスクの洗い出し、フローの整理、担当者と手順の可視化が出発点になります。
たとえば、「社内問い合わせ対応」という一見シンプルな業務でも
- 何を、誰が、どの順で処理しているのか?
- どのタイミングで属人化しているのか?
- どの部分にAIや自動化を組み込めるのか?
といった分析が不可欠です。属人化の排除なくして、業務効率化の定着はありません。
STEP2:「できた」を可視化してスモール成功体験を積む
改善が現場に根づくには、「ちゃんとできた」「業務が楽になった」というポジティブな体験の積み重ねが必要です。
たとえば
- 会議の議事録をAIが自動作成 → 書記の負担が激減
- よくある問い合わせをFAQに統合 → 回答コストが1/3に
- 探しにくかったマニュアルを一元化 → 社内問い合わせが半減
こうした“手応えのある成功”があることで、現場は改善を自分ごととしてとらえ始めます。
効率化は、押しつけではなく体感から始まるのです。
STEP3:成果が仕組みに残る「再現可能な改善」を設計する
成功事例が一部の現場だけで終わるのではなく、他部署でも再現可能な仕組みに落とし込むことがカギです。
- AIプロンプトのテンプレート化
- 問い合わせ対応マニュアルの構造設計
- 改善フローを明文化し、研修に組み込む
改善のナレッジが「人に属する」のではなく、「組織に残る」ことで、人が入れ替わっても取り組みが継続し、“改善が文化になる”組織へと進化します。
生成AIが変える!業務効率化の定着率
「業務効率化が進まないのは、現場が納得していないから」
「改善の定着には、小さな成功体験と再現性が必要」
ここまでのステップを踏まえたうえで、今注目すべきは、 その改善を加速・定着させる力としての生成AIの活用です。
生成AIは、従来の業務改善では届かなかった“現場の細部”にこそ力を発揮します。ここでは、SHIFT AIが実践している具体的なユースケースをご紹介します。
1. マニュアル作成の自動化で、業務属人化を防ぐ
口頭や暗黙知で進められていた業務フローを、生成AIで即座にドキュメント化。たとえば、録音された会議音声や議事メモから自動で「業務手順マニュアル」を生成。現場からは「共有コストが激減した」「教育時間が1/3になった」との声も。
ポイントは、面倒なことをAIに任せることで続けられる仕組みにすることです。
2. 社内問い合わせの対応時間を半分以下に
「この書類どこにある?」「申請ってどうするんだっけ?」。そんなよくある質問こそ、生成AIが活躍する場面です。
- チャット上で自然文検索
- 社内FAQを自動統合・更新
- 問い合わせ履歴から次のFAQ候補を自動提案
現場の声を拾いながらナレッジが進化していくAI設計により、運用の手間なく、情報の属人化を抑止できます。
3. 議事録・報告資料の作成もAIで自動化
会議内容を録音しておくだけで、AIが議事録を自動生成。さらにその内容をベースに報告資料や次回アクション案も提案可能。
「議事録を作ることが目的になっていた状態」から脱却し、本来注力すべき業務に時間を割ける体制を実現します。
「AIがいるからこそ、改善が続く組織へ」
改善活動は「始めること」より「続けること」のほうが何倍も難しい。だからこそ、生成AIのように現場の“面倒”を代替し、継続を支える仕組みが必要なのです。
SHIFT AIでは、このような業務支援のAI活用を、現場視点に落とし込んだ研修設計で提供しています。
他社ではどうやっている?改善定着の成功事例
「他の会社はどうやって業務効率化を成功させているのか?」多くの担当者が気になるのが、再現性のある成功パターンです。
ここでは、SHIFT AIが支援した企業での実際の成功事例をご紹介します。いずれも、「業務効率化が進まない状態」から脱却し、改善を“定着”させた企業のリアルな声です。
事例①ITベンチャー × 情報共有の属人化をAIで解消
社内の問い合わせが多く、ナレッジの分散に悩んでいたA社。生成AIを用いた社内FAQの統合・自動応答システムを導入し、問い合わせ件数が月100件以上→40件に減少。現場の負担が軽くなったことで、空いた時間で改善提案が出るように。
成果だけでなく「改善する余裕」を生み出せたことが最大の効果でした。
事例②製造業 × マニュアル作成の自動化で教育コスト削減
業務マニュアルが古く、現場で「人に聞く」が常態化していたB社。業務フローをヒアリング・録音したうえで、生成AIが自動で手順書を作成。導入後、新入社員の習熟スピードが約2倍になり、教育担当者の負担も大幅減少。
教える時間を改善に使える時間へ変換できた点が、組織としての生産性向上に直結しました。
事例③人事・情シス連携による、全社横断的な改善設計
DX推進に苦戦していた中堅企業C社では、人事と情シスが連携し、SHIFT AIの生成AI研修を導入。
まずは管理部門から小さな改善を始め、効果を見せながら他部署へ展開。結果、業務改善活動の参加率が全社で70%を超え、改善報告会が文化として定着。
改善を“やらされるもの”から“共有するもの”へ変えたプロセスが成功のカギでした。
👉 関連記事
人手不足でも回る職場へ|業務効率化で「採用に頼らない組織」をつくる方法
\ 生成AIによる業務効率化の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
まとめ:業務効率化が進まないのは「人」ではなく「構造」の問題
- ツールを導入しても動かない
- 改善が定着せず元に戻る
- 現場の反応が薄く、推進役だけが空回りする
これらはすべて、「現場が納得できる構造と仕組み」が足りていないことが原因です。
改善活動は、属人化を解き、納得感を生み、仕組みに落とし込むことで初めて“定着”します。そしてそのプロセスを、生成AIの力で現場に寄り添いながらサポートするのがSHIFT AIの役割です。
SHIFT AIでは、生成AIと教育を組み合わせた「現場自走型の業務改善研修」を提供しています。
- 小さく始めて、組織に定着させる
- 属人化を排除し、再現性ある改善文化を育てる
- 業務改善を、現場起点で回る仕組みに変える
下記のリンクからは、生成AIを本格導入し「業務改善・効率化」「AI人材育成」を推進し成果をあげている様々な業種の取り組み17選をまとめた事例集をダウンロードいただけます。自社と似た課題感を持つ会社が、どのようにAIを活用しているのか知りたい方はお気軽にご覧ください。
\ 生成AIによる業務効率化の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
業務効率化に関するよくある質問
- Qなぜ業務効率化がうまくいかない企業が多いのですか?
- A
原因の多くは「現場に改善の目的が伝わっていない」「仕組みが属人化している」「改善が定着する構造がない」ことにあります。
ツール導入やルール整備だけでは変わりません。重要なのは、「なぜ」「どうやって」改善するのかを、現場と一緒に考える仕組みづくりです。
- Q生成AIは本当に業務改善に効果があるのですか?
- A
はい、特に「マニュアル作成」「問い合わせ対応」「議事録の自動生成」など、定型業務の効率化に即効性があります。
SHIFT AIでは、現場にフィットした活用方法を研修で丁寧に設計し、継続的な改善につなげます。
- Q業務効率化を“定着”させるには、まず何から始めるべきですか?
- A
まずは業務の「見える化」と、小さな改善の“成功体験”を作ることから始めるのがおすすめです。
属人化された業務を棚卸しし、現場が「改善してよかった」と思える体験を設計することで、自走する仕組みが育っていきます。
- QSHIFT AIの研修は、どのような企業に向いていますか?
- A
中小〜中堅企業で「業務改善が進まない」「現場が動かない」と感じている企業様に最適です。
管理部門・情シス・人事部など、複数部署の連携を通じて「改善を定着させる土台づくり」を支援します。
- Q資料にはどんな情報が載っていますか?
- A
研修プログラムの構成・導入事例・生成AI活用事例・導入プロセス・価格感などを詳しく掲載しています。「まずは情報収集から」という方も歓迎です。