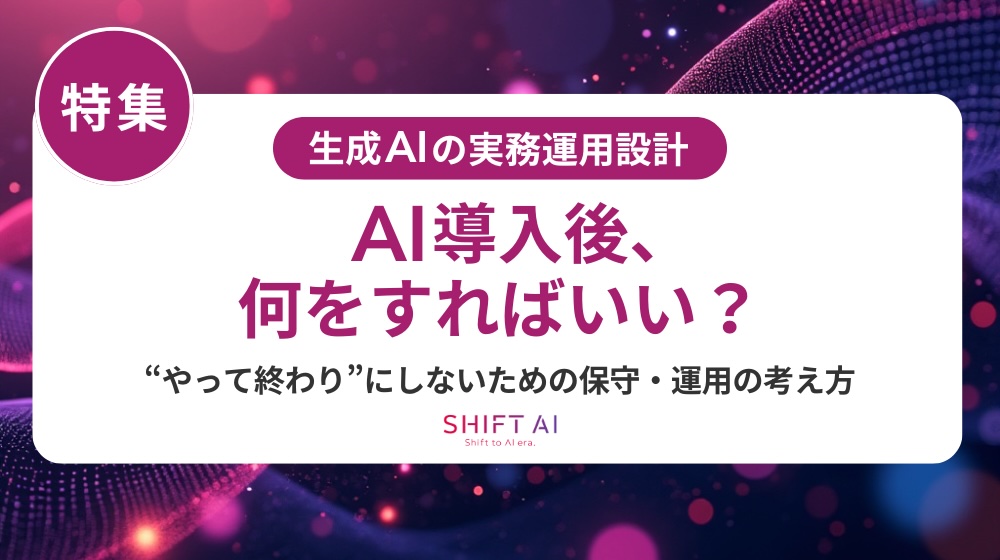「生成AIを導入したのに、結局うまく活用できていない」
そんな声を、いま多くの企業で耳にします。ChatGPTやClaudeなどの生成AIツールを取り入れ、社内展開を始めたものの、実際に使いこなせているのは一部の社員だけ。
現場では「結局、何に使えばいいのか分からない」「効果が感じられない」という声も根強く、最初の盛り上がりとは裏腹に、生成AIの社内定着に苦戦している企業が少なくありません。
この「使いこなせない状態」は、個人のスキルややる気の問題ではなく、組織全体の設計や教育体制の不備が原因であるケースが大半です。つまり、仕組みを見直せば、誰もが活用できる環境はつくれるということです。
この記事では、
- なぜ生成AIが「使いこなせない」状態に陥るのか
- 成果を出している企業の共通点
- 社内定着につながる再設計ステップ
を具体例やよくある失敗を交えながら解説します。
生成AIを導入して終わりにしないために。自社に合った活用の仕組みを、ここから一緒に考えていきましょう。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
生成AIを導入したのに活用できない」企業が増えている
多くの企業がChatGPTやClaudeなどの生成AIを導入し、活用を模索していますが、実際に成果を感じている企業は意外に少数派です。
業務での活用率は3割未満、日本企業の効果実感率も低い
全国ビジネスパーソン9,000人超を対象とした調査では、 業務で生成AIを活用しているのはわずか29.3%。一方で 約59.1%は全く活用していないと答えています。
また、帝国データバンクの調査でも、 日本企業全体の約17.3%が生成AI活用企業で、そのうち約9割が一定の効果を実感しているものの、全体としてはまだ少数派です。
PwCのクロス国比較調査では、日本で「期待を上回る効果」を実感している企業はわずか13%と極めて低く、米国(55%)、英国(50%)と比べて大きな差があることも明らかになっています。
出典:【生成AIの営業活用に関する実態調査】3割の企業が生成AI活用。時間短縮や成果向上などの効果を実感。一方で、生成AI活用の課題は情報の正確性とセキュリティとの声
出典:アルサーガパートナーズ、生成AIの活用実態に関する調査を実施 業務での活用率は全体で3割未満
出典:生成AIの活用状況調査—日本企業の生成AI活用率は17.3%
このギャップが生まれる背景と現場の声
次のような声が現場で頻繁に聞かれ、その背景が明らかになっています。
- 「試してみたけど業務にどう使えばよいか分からない」
- 「ツール導入で安心してしまい、具体的な活用設計が後回しになっている」
- 「一部の人だけ活用できて、社内で“使える人”と“使えない人”の差が広がっている」
つまり、ツール導入だけが目的化し、活用設計・教育・定量測定が伴っていないケースが多いということです。
| 問題点 | 説明 |
| 活用率が低い | 29%しか業務で活用されておらず、半数以上が活用できていない |
| 成果の実感が薄い | 導入企業でも世界的に見て効果実感が低い(13%) |
| 教育・制度の整備不足 | スキル・習得機会・体制不足といった組織構造上のハードルが散見される |
まずこの「導入はしたが定着せず成果が見えない」という現場の典型的な課題構造を整理し、次章以降で「なぜ使いこなせない状態が生まれるのか」を深堀、さらに成果を出している企業に共通する構造と施策をご紹介していきます。
「使いこなせない」状態にある企業の3つの典型パターン
生成AIを導入したのに「活用しきれていない」と感じている企業の多くには、いくつか共通したパターンがあります。ここでは、現場でよく見られる“つまずきポイント”を3つに整理してご紹介します。
① 利用が特定の人に偏っている(属人化)
一部の社員、特にITリテラシーの高い人や興味関心が強い人だけが使っている。そんな状態になっていませんか?
このような「属人化」は、全社的な活用文化が根づかない典型例です。導入当初は盛り上がっても、「誰がいつ何のために使うか」が明確でなければ、自然と使われなくなっていきます。
<社内あるある>
「〇〇さんがやってくれるから」と依存状態になり、他の社員は他人ごとになる。その結果、属人的なスキルに留まり、全体の変革にはつながらない。
関連記事
属人化からの脱却方法|生成AIで仕組み化を実現する手順と事例
② 定着・活用の仕組みがない(制度化不足)
「使ってみてください」「自由に試してください」で終わっていませんか?
生成AIは、単に提供するだけでは定着しません。活用ルールや利用ガイド、プロンプト例の共有、継続的なスキルアップの仕組みなど、制度化・仕組み化の支援がなければ現場では動きません。
<SHIFT AIでの支援例>
- 部署横断での「プロンプト共有会」開催
- 活用ケースをテンプレ化し社内Wikiに掲載
- 操作+実務応用の二層研修を導入
③ 業務プロセスと接続していない(効果が見えない)
「ChatGPTはすごいけど、うちの仕事には関係ないよね」という言葉が出てきたら危険信号です。
ツールの機能理解だけで終わってしまい、業務にどう活かすかの設計が伴っていない状態では、定着も効果も望めません。現場での使いどころを明確にしない限り、生成AIは単なるお試しツールに終わってしまいます。
たとえば以下のような項目が挙げられます。
- 営業:提案文書の下書き生成
- 人事:求人票・面談レポートの作成支援
- 総務:社内通知・FAQ対応の自動化
ここまで読んで、「自社もこのどれかに当てはまっているかも」と思った方は、まさに再設計の好機です。
使いこなす組織は何が違う?成果を出している企業の3つの共通点
「使える人と使えない人の差」ではなく、使える組織と使えない組織の差に目を向けてみましょう。
生成AI活用で成果を出している企業には、共通する仕組みの特徴があります。ここでは、実際に現場で定着・展開を実現している企業が取り入れている3つの鍵をご紹介します。
① 小さな成功事例を早期に作っている
最初から全社展開を目指すのではなく、「一部署」「一業務」など、スモールスタートで確実に成果を出すことが共通点の一つです。
たとえば
- 営業チームが、提案書のたたき台をChatGPTで自動生成し、作成時間を50%短縮
- カスタマーサポートが、回答文例の下書きをAIに任せ、対応品質を平準化
このように「業務で本当に役立った」という実体験が共有されることで、他部署への波及もスムーズになります。
ポイントは、成功体験の共有=使いたくなる文化の土台です。
② 部門横断でノウハウを共有している
属人化を防ぐためには、活用の「知見の見える化」が不可欠です。うまくいったプロンプト、失敗した使い方、AIの反応傾向など、試行錯誤をナレッジとして共有する仕組みを整えている企業は、組織全体のレベルアップが早い傾向にあります。
<例>
- 社内SlackやNotionで「AI活用チャンネル」を開設
- 月1で「プロンプト共有会」を開催
- 成果事例は社内ポータルにテンプレとして格納
③ 外部研修や社内ガイドラインを整備している
生成AIは、操作だけでなく考え方から教える必要があります。
「何を聞けば良いのか?」「どこで使えるのか?」というプロンプト設計の教育や、業務ルール・セキュリティ・倫理観の整備まで含めて支援体制を構築している企業ほど、社内への定着と拡張がスムーズです。
ここで必要なのは、単なる勉強会ではなく、業務接続と思考習慣の変化に繋がる教育設計です。これらの共通点を踏まえれば、生成AIを導入しただけの企業と成果を出す企業の違いがはっきり見えてきます。
成果につなげるための「生成AI活用 再設計」ロードマップ
生成AIは、試して終わりのツールではありません。本当に価値を発揮するのは、業務の中で使いこなされ、文化として定着したときです。
では、どうすればそれを実現できるのか?ここでは、SHIFT AI for Bizが実際に伴走してきた企業の事例をもとに、成果につながる3ステップの再設計をご紹介します。
STEP1 業務と生成AIの「接続点」を可視化する
「AIって便利そうだけど、うちの業務では何に使えばいいの?」。この疑問が放置されたままだと、現場は動きません。
まずやるべきは、現場の業務と生成AIの得意なことを線でつなげる。言い換えれば、「この業務のこの部分、AIがやった方が早くてラクだよね」と見える化することです。
<例(抜粋)>
| 部門 | 活用例 | 得られる効果 |
| 営業 | 提案書の骨子作成 | 作成時間を30分短縮、品質均一化 |
| 人事 | 面談記録の要約 | 記録作成の自動化、書き起こし不要 |
| 管理部 | 社内文書のドラフト | 発信スピードUP、伝達ロス削減 |
大切なのは、「AIができること」ではなく、「人がやらなくてもいいこと」を洗い出すことです。
生成AIをどの業務でどう活用できるか?より詳しく知りたい方はこちら
👉 生成AIの使い方が分からないあなたへ!初心者でも業務で使える完全ガイド
STEP2 使いこなせる人を増やす教育と仕組みを設計する
生成AI活用のカギは、リテラシーではなく実感です。つまり、「あ、これ便利だわ」と感じる瞬間を、どれだけ多くの社員に提供できるかが勝負なのです。
そのために必要なのは、以下の3点です。
- 業務別・職種別に最適化されたプロンプト例(汎用じゃ伝わらない)
- 実務で「使ってみる」演習型研修(聞くだけで終わらせない)
- 活用の成功・失敗を社内で共有できる場の設計(孤独にしない)
このように、「AIは得意な人がやるもの」ではなく、「全員が頼れるパートナー」に変えるための設計が必要です。
研修設計のポイントや、教育・育成の全体像を知りたい方はこちらも参考に
👉 ITツールを使いこなせない3つの原因とは?生成AI研修から始めるデジタル人材育成法
STEP3 「やってよかった」をつくる。成功体験の仕込み
社員がAIを使い続けたくなるのは、便利だからでも、強制されるからでもありません。「やってよかった」という、リアルな成功体験があるからです。
そこで重要なのは以下のポイントです。
- 成功体験を仕込みとして設計すること(偶発任せにしない)
- その経験を「チームにシェアしたくなる仕組み」をつくること
例えば、
- 「AIで業務時間を●分短縮できたら、社内掲示板に自慢投稿」
- 「ナレッジ共有会でベストプロンプト賞を選出」
- 「初めてAIを使った人限定の“はじめて表彰”」
このように、成功体験の積み上げが、AIを使いたくなる文化に育てられます。
しかし、業務分析も教育設計も、現場調整も、ノウハウも……となると「自社だけでやるのは正直しんどい」となってしまいます。すべてゼロからでは、時間も労力もかかりすぎるのです。
だからこそ、私たちがいます。
SHIFT AI for Bizでは、
- 「業務×生成AIの接続点の洗い出し」
- 「研修・教育・ナレッジ設計」
- 「定着施策のデザイン」
まで、まるっと支援可能です。
よくある誤解と失敗!生成AI活用が空中分解する前に
「生成AI、結局使いこなせなかったね」 「最初は盛り上がったけど、最近誰も話題にしないよね」──そんな空中分解の兆候、あなたの会社にも忍び寄っていませんか?
生成AIの活用が軌道に乗らない企業には、いくつかの典型的な誤解と落とし穴があります。それは決して怠慢ではなく、準備不足と設計のミスによるものです。
誤解①「ツールを導入すれば現場が勝手に使うだろう」
最も多い失敗のひとつが、「道具を渡せば、現場が自律的に使うだろう」という幻想。実際は、「何にどう使えばいいのか分からない」状態のまま、誰も手を動かさないパターンがほとんどです。
これは、ツールそのものの問題ではなく、活用の仕組み(教育・ルール・支援)をセットで整えていないことが原因です。
誤解②「最初から全社展開すれば効率的」
逆に「一気に広げれば早く成果が出る」と考えてしまうのも危険です。現場には職種・業務・文化ごとのAI耐性の差があり、一律展開はむしろ反発や混乱を招くこともあります。
「結局、誰のためのツールだったの?」という声が出た時点で、定着は難しくなります。
誤解③「使える人と使えない人はセンスの差」
「うちは誰もAIに向いてなかった」と諦めてしまうケースもありますが、それは誤解です。
生成AIの活用は、センスではなく設計と練習の積み重ねで身につくスキルです。導入当初のリテラシー格差は、研修・実践の機会次第で確実に埋まります。
「センスのある個人」ではなく、「全員が使いこなせる仕組み」へと考え方をシフトすることが重要です。
このまま放置すると、導入コストが無駄金に
以下のような問題が起こってしまうと導入したコストが無駄になってしまう可能性があります。
- 生成AI導入にかかったライセンス費、教育コスト、検討会議の時間…
- 成果が出なければ、「あれって何だったの?」と社内で疑問視される
- 現場からは「また新しいツールか」と変化疲れが広がる
- 管理職は「AI活用、うまくいってますか?」と上層部に説明できない
まだ遅くはありません。今こそ、立て直しのチャンスです。
より本質的な運用改善のヒントが欲しい方はこちらもおすすめ!
👉 生成AI運用で成果を出す完全ガイド|導入後の課題解決から継続的改善まで
まとめ|生成AI活用の鍵は、再設計と現場に寄り添う教育にある
生成AIは、導入するだけでは成果につながりません。むしろ「うまく使いこなせない」という声が現場から上がったときこそ、本当のスタートラインです。
使いこなせていない原因の多くは、社員の能力や意欲ではなく、業務との接続が曖昧だったり、活用方法を学ぶ機会がなかったりと、仕組み側の問題にあります。
今必要なのは、活用の再設計です。業務における接続点を明確にし、教育やルールを整備し、小さな成功体験を全社に共有していく。その繰り返しが、「使いこなせる組織」を生み出します。
もう“試して終わるAI活用”から脱却しませんか?
私たちSHIFT AIは、法人向けに、生成AI活用を 「定着させるための研修」をご提供しています。今すぐ資料をご覧いただき、貴社の一歩目を設計してください。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応
生成AIに関するよくある質問(FAQ)
- Qなぜ生成AIを導入しても、うまくいかない企業が多いのですか?
- A
ツールを導入するだけで「使いこなせる」と考えてしまい、活用設計・教育・仕組み化の準備が不足しているケースが多いからです。
- Q現場で「使える人」と「使えない人」が分かれてしまいます。
- A
それは個人のセンスではなく、プロンプト設計や業務接続の知識が共有されていないからです。適切な研修とサポートで、どんな職種でも使いこなせるようになります。