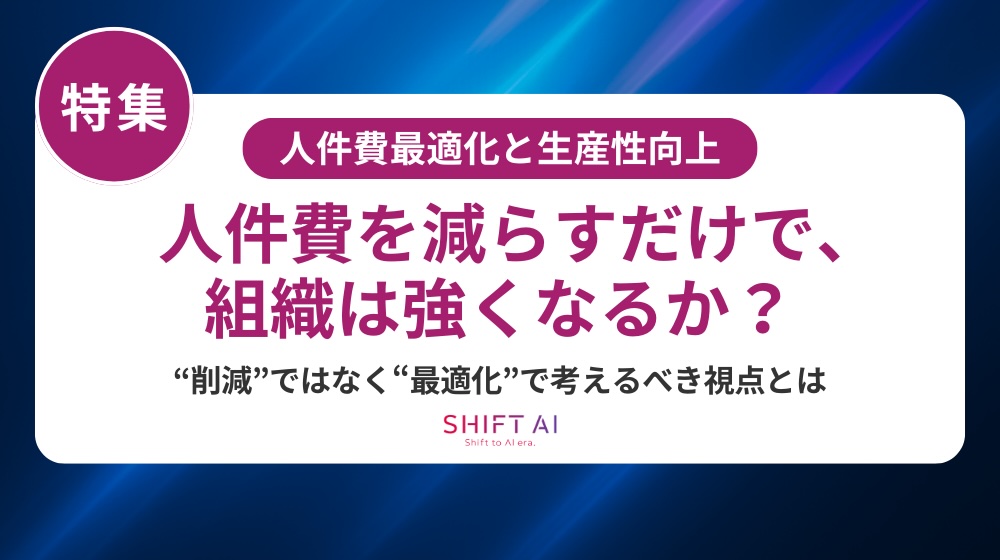「人が余っているように感じる」「仕事が薄い従業員が多い気がする」──
このような違和感を覚えている経営者やマネージャーの方も多いのではないでしょうか。
人件費は企業にとって最大の固定費。にもかかわらず、業務の棚卸しや適正配置がなされないまま組織が肥大化していると、コストだけが膨らみ、収益を圧迫する大きな要因になりかねません。
また、従業員にとっても「仕事がない状態」が続くことは、モチベーション低下や生産性の停滞を招くリスクがあります。単に「人が多いから減らそう」という発想ではなく、“活かし方”や“配置の見直し”といった視点が求められます。
本記事では、「従業員が多すぎる」と感じたときに見直すべきポイントや、固定費を抑えつつ最適な人員体制をつくる方法を、戦略的かつ実践的なアプローチで解説します。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ“従業員が多すぎる”と感じるのか?
従業員数が適正かどうかを判断するのは簡単ではありません。ですが、次のような兆候がある場合、組織に「余剰人員」が存在している可能性があります。
業務の偏りや遊休人員の発生
特定部門だけが常に忙しく、別の部署は手持ち無沙汰。こうした「業務の偏り」は、全体の人員配置が最適化されていないサインです。繁忙部署に人を補充せず、閑散部門に人が余っているままでは、組織の生産性は上がりません。
人件費率の高さと売上効率の低下
人件費率(=売上に対する人件費の割合)が業界水準を大きく上回っている場合、それは“人が多すぎる”のではなく“人を活かしきれていない”という状態かもしれません。人件費の絶対額だけでなく、労働生産性の視点で見直すことが重要です。
「とりあえず採用」や惰性的な配置
過去に「将来の成長を見込んで人を多めに採用した」「辞められると困るから残した」といった理由で維持された人員が、結果的に活用されず固定費を圧迫しているケースもあります。定期的な見直しがされていないと、こうした「なんとなく在籍している人材」が増えていきます。
従業員数が多すぎると起こる問題
適正以上の人員を抱えることで、企業の収益性や組織の健全性に悪影響を及ぼすリスクが高まります。ここでは、具体的な問題点を整理します。
①人件費負担の増大
言うまでもなく、従業員が多ければ多いほど人件費はかさみます。売上や利益が伸びていない中でこのコストが固定化していると、経営の柔軟性を損ないます。特に業績が落ち込んだ際には、資金繰りの圧迫要因となりやすく、経営危機を招く恐れもあります。
②一人あたり生産性の低下
人が多いことで「自分がやらなくても誰かがやってくれる」という空気が生まれやすくなり、結果として一人ひとりの生産性が下がる傾向があります。特に業務の定義があいまいな環境では、仕事が属人化しない代わりに「仕事が生まれにくい」状況にもなりえます。
③モチベーションや組織活力の低下
“余っている人”が存在することは、周囲の働きがいにも影を落とします。「なぜあの人が何もしていないのに同じ給料なのか?」といった不公平感が蓄積され、やる気のある社員の離職や内部不満につながることもあります。
④経営判断の鈍化・責任の所在不明
人が多いことで意思決定のスピードが落ちたり、責任の所在が曖昧になったりするケースも見受けられます。これは組織のアジリティ(俊敏性)を損ねる要因であり、市場変化への対応が遅れる温床となります。
従業員が多すぎる原因をどう見極めるか?
「従業員が多すぎるかもしれない」と感じても、すぐに削減に踏み切るのはリスクがあります。まずは冷静に、なぜそう感じるのか、何が根本原因なのかを見極めましょう。
①業務量と人員配置の不均衡をチェック
- 部門ごとの業務量に対して、適切な人員が割かれているか
- 閑散期や繁忙期の稼働率に偏りがないか
- 特定の部門に“やることがない人”が集まっていないか
などを指標としてチェックします。
②業務の重複・属人化の有無を確認
「別々の人が、似たような仕事をしている」ケースや、「その人にしかできない業務がある」状態は、適正人員の見極めを困難にします。マニュアル化や業務フローの可視化が進んでいない場合は、余剰人員の温床となりがちです。
③一人あたりの生産性を定量的に把握する
人件費率や労働分配率、売上・利益に対する従業員数の比率などを活用し、「多すぎるかどうか」の客観的指標を持つことが重要です。感覚で語るのではなく、数字で語ることが組織全体の納得形成にもつながります。
従業員が多すぎる状態から脱却する5つの改善策
「人が余っているように見える」状況でも、単純なリストラに走るのは危険です。ここでは、組織へのダメージを最小限に抑えながら、最適な人員配置を実現するための5つのアプローチをご紹介します。
①業務の棚卸しと標準化
- 全業務を可視化し、「本当に必要な仕事」かを判断
- 無駄な工程や重複業務を削減
- マニュアル整備とナレッジ共有により、生産性の底上げを図る
これにより、「人を減らす」のではなく「業務を減らす」ことでバランスを取る視点が得られます。
②業務量とスキルの再マッチング
部署間での業務偏在や個人の得意不得意を見直し、配置転換や兼務などで適正な人員配置を行います。単なる“余剰人員”も、視点を変えれば新しい価値を発揮する可能性があります。
③間接部門の最適化
管理部門やバックオフィスに人が偏っている場合、ツール導入や業務フローの見直しで効率化を進めましょう。たとえば、生成AIやRPAの導入による定型業務の自動化も有効です。
関連記事:属人化しない組織とは?文化・仕組み・AI活用による根本対策
④外注・業務委託との最適なバランスを探る
「社内で抱え込むべき仕事」と「外部に委託してよい仕事」を再評価します。業務内容によっては、フリーランスやBPO、SaaSツールの活用の方が効率的な場合もあります。
⑤リスキリングによる価値転換
余剰人員と見なされがちな層も、スキルを転換すれば“新たな戦力”になります。生成AIの活用研修や業務改革のリーダー育成など、社内の役割を再定義するチャンスです。
従業員数が多いことで起きるリスクと課題
従業員が多いことは一見すると「安心感」や「組織の余裕」にも見えますが、放置すると組織の健全性を損なうリスクも潜んでいます。以下のような点に注意が必要です。
①固定費の肥大化による収益圧迫
最も大きなリスクは、人件費が収益構造を圧迫することです。売上が横ばい、もしくは減少傾向にある中で人件費が維持されると、利益率が著しく低下し、経営判断の自由度が狭まります。
②業務効率の低下・モチベーションの低下
人が多すぎると、業務に対する責任や緊張感が希薄になり、「自分がやらなくてもいい」という空気が生まれやすくなります。これにより、非効率な仕事の進め方や、緩慢な組織風土が定着してしまう恐れがあります。
③意思決定の遅延・コミュニケーションコストの増加
人が多いほど、会議の回数や調整にかかる時間が増え、決定スピードが落ちる傾向があります。情報伝達のロスや誤解も起きやすくなり、全体最適が難しくなります。
④評価の形骸化と離職リスク
従業員数が多いことで一人ひとりの働きぶりが見えにくくなり、評価や育成が形だけになりがちです。「自分は評価されていない」と感じる社員が増えると、優秀な人材の離職にもつながります。
関連記事:「管理職なのに給料が割に合わない」と感じるのはなぜか?責任と報酬がズレる構造的理由と対策を解説
人件費バランスの見直しに成功する企業が実践していること
従業員数が多くなりすぎた企業でも、適切な見直しによって組織のパフォーマンスと財務健全性を両立させている企業は少なくありません。成功企業に共通するポイントは以下の通りです。
①属人化の排除と業務プロセスの標準化
まず取り組むべきは、業務の棚卸しとマニュアル化です。属人化された業務は人が減らせない構造を生みます。プロセスの標準化により、適正人員でも回る体制が構築されます。
②業務設計と人員配置の見直し
単純な人員削減ではなく、「誰が・何を・どのくらいの頻度で行っているか」を可視化し、過剰配置や無駄な業務を見直します。ここでのポイントは、コストカットではなく“業務再設計”の観点で捉えることです。
③AI・デジタルツールの活用で業務代替を進める
定型業務を生成AIやRPAなどのツールで代替することで、人が担うべき業務に集中させる仕組みを整備している企業が増えています。業務効率が上がれば、従業員数を減らしても回る体制が実現可能です。
関連記事:AIで人件費はどこまで削減できる?具体業務と成功のコツを解説
④評価制度の見直しで生産性と成果を両立
人件費バランスを見直す際に重要なのは、従業員のモチベーションを落とさずに改革を進めることです。生産性や成果に応じて報いる評価制度に切り替えることで、少数精鋭でもパフォーマンスを最大化できます。
関連記事:人手不足なのに人件費削減?現場が崩壊しないために今すぐ見直すべき5つの対策
まとめ|人件費と従業員数を最適化するために必要な視点とは
従業員数が多すぎる状態は、一見すると人材が豊富で安定しているように思えるかもしれませんが、実態としては「人件費が固定費を圧迫している」「一人あたりの生産性が低い」「組織の意思決定が遅い」といった課題を生み出しやすくなります。
本記事では、以下の観点から見直しのポイントを解説してきました。
- 従業員数が増えすぎる原因と、それにより生じるコスト・組織課題
- 適正人員を判断するための基準とアプローチ
- リストラに頼らずに人件費を抑える代替手段
- AIや評価制度の見直しを通じた長期的な最適化の方法
単なる削減ではなく、「業務と組織構造の再設計」「納得感のある仕組みづくり」「人材活用の最大化」といった視点を持つことが、従業員数と人件費のバランスを保ちながら持続可能な経営へとつながります。
- Q従業員が多すぎると、どのような問題が起こりますか?
- A
人件費の増加により固定費が圧迫されるほか、生産性の低下や意思決定の遅延、業務の非効率、モチベーションの低下といった課題が発生しやすくなります。
- Q従業員数を見直す適切なタイミングはいつですか?
- A
売上や業務量に対して人件費率が高すぎる場合、業務が一部の人に集中していないかを確認し、非効率や空き工数が多い場合は見直しを検討すべきです。
- Q人員削減せずに人件費を抑える方法はありますか?
- A
業務効率化による生産性向上、評価制度の見直し、役割の再定義、AIツールの活用などによって、人員数を変えずにコスト最適化を図ることは可能です。
- Q組織がスリム化すると、逆にリスクはありませんか?
- A
過度なスリム化は業務過多や離職を招く可能性があります。適正人員の維持と業務分担のバランスを取りながら進めることが重要です。
- QAIを活用した人件費の最適化には、どんな方法がありますか?
- A
業務の可視化、自動化、スキルマップの整備、適材適所の配置などをAIで支援することで、従業員一人あたりの付加価値を高め、人件費の過剰を防げます。