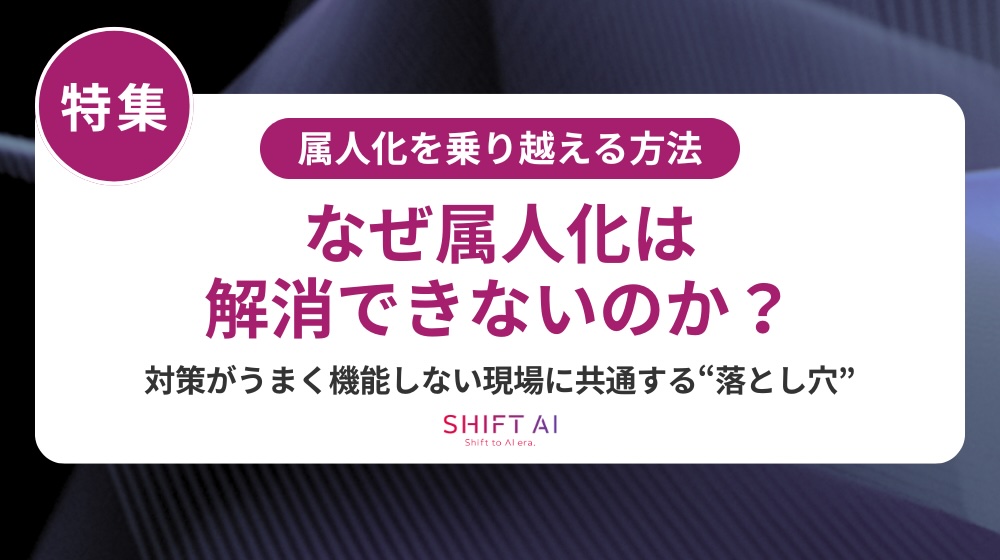「その人がいないと回らない業務がある」「ベテラン社員しか対応できない仕事が残っている」 そうした状態に、あなたも心当たりがあるかもしれません。
いわゆる「業務の属人化」。多くの企業で課題とされ、マニュアル化や業務整理といった対策が繰り返し行われてきました。しかし現実には、一度は仕組み化を試みたが定着しなかった、現場から反発を受けて頓挫したという声も後を絶ちません。
なぜ属人化の解消は、これほどまでに難しいのでしょうか?
本記事では、属人化の本質的な構造とリスクを紐解き、従来の“標準化”では手の届かなかった領域を、生成AIの力でどう変えられるのかを解説します。
「人に依存する状態」から、「誰でも回せる仕組み」へ。そして、AIによる支援で“現場が納得できる改善”を実現する方法を探っていきましょう。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
属人化とは何か?仕組み化との違いを明確にする
属人化とは、「特定の人にしかできない仕事が存在し、その人がいなければ業務が滞ってしまう状態」を指します。
たとえば、ある業務フローがベテラン社員の頭の中にしかなく、マニュアルも引き継ぎ資料もない。新人が手を出そうとしても「◯◯さんに聞かないと分からない」と止まってしまう。これが典型的な属人化の例です。
一方で、仕組み化とは、業務を誰が行っても一定の品質で再現できる状態をつくることを意味します。個人のスキルや経験に頼らず、手順・ルール・情報が組織全体に共有され、属人性を排除した状態です。
<属人化と仕組み化の対比>
| 項目 | 属人化 | 仕組み化 |
| 情報の所在 | 特定の個人の頭の中 | ドキュメント・システム・プロセスに蓄積 |
| 業務の属人度 | 高い(代替不可) | 低い(誰でも対応可能) |
| 引き継ぎ | 非効率・不明瞭 | スムーズに実施できる |
| 組織リスク | 離職・異動でブラックボックス化 | 安定運用が可能 |
ただし、ここで注意すべきは、「属人化=悪」「仕組み化=善」と一刀両断できないことです。属人化には、経験や判断力といった暗黙知・スキルの結晶という側面もあります。そのため、属人化を単にマニュアルで形式化しようとすると、逆に品質が落ちたり、現場の納得感を得られなかったりするケースもあります。
このあと属人化がなぜ起こるのか、そしてどうすれば“納得感をもって仕組み化”できるのかを、生成AIの活用を含めて具体的に解説していきます。
属人化はなぜ起きるのか?組織構造に潜む5つの原因
属人化は、単なる“個人のこだわり”や“非協力的な態度”によって起きるわけではありません。実は多くの属人化は、組織構造や評価制度、業務の特性そのものに起因しています。ここでは、特に属人化を助長しやすい5つの背景を整理します。
① 非定型業務が多く、マニュアル化が難しい
業務内容に「判断」「例外処理」「対人調整」が多く含まれる場合、手順を形式知化するのは容易ではありません。
たとえば、社外との交渉やクレーム対応、プロジェクト進行などは、ケースごとの判断が必要で、「テンプレート化」が難しい業務の代表です。
② 評価制度が「個人の成果」に偏っている
属人化を助長する根本原因の一つが、評価基準の設計です。 「この人が頑張ってくれている」「あの人でないと困る」という状態が評価されやすい文化では、知識やノウハウを共有するインセンティブが働きません。
結果として、ナレッジが個人の中に閉じ込められやすくなります。
③ 情報共有の仕組みが不十分
情報がファイルサーバーの奥に眠っていたり、ナレッジがチャットに断片的に散らばっていたりすると、属人化は進行します。
さらに、「あの人に聞いた方が早い」という習慣がある職場では、仕組みよりも属人頼みの流れが固定化されてしまいがちです。
④ 引き継ぎを前提とした文化がない
「忙しいから引き継ぎ準備を後回しにしてしまう」「とりあえず自分で処理した方が早い」。
こうした日常的な判断の積み重ねが、属人化を慢性化させます。属人化は放置されると“その人の仕事”として定着し、後任が育たない/対応できないという事態を引き起こします。
⑤ 現場リーダーが「孤立」している
部下には任せられない、上司には相談しにくい、他部署からの問い合わせも一手に引き受ける。
このように、中間管理職や現場リーダーが業務の“ハブ”として機能してしまっている場合、本人の責任感ゆえに属人化が加速します。
属人化は「人の問題」ではなく、構造の問題である。この認識を持たずに、属人化を個人に押し付けても根本的な解決にはつながりません。
関連記事
仕事の属人化が退職理由に?生成AI活用で組織の安定化を実現
属人化の本当の問題点:組織が気づけない4つのリスク
属人化の問題は、「その人しかできない」という表面的な困りごとに留まりません。本質的なリスクは、組織の運営・成長・変化に対する柔軟性を奪ってしまうことにあります。ここでは、多くの企業が見落としがちな「属人化の深層リスク」を4つに分けて解説します。
① 業務のブラックボックス化が、経営判断を誤らせる
属人化された業務では、手順・コスト・工数の実態が見えにくくなります。すると、経営層が業務負荷を正確に把握できず、誤ったリソース配分や改善策を取ってしまう危険性が高まります。
「なぜこの業務がこんなに時間がかかるのか?」が誰にも答えられない状態は、現場の疲弊と経営の誤算を同時に招きます。
② 突発的な退職・異動で業務が停止する
属人化された業務を担う人が突然退職・休職・異動した場合、業務が完全に止まるという事態が起こります。
しかも、その影響範囲は業務単体に留まらず、顧客対応の遅延、売上損失、ブランド毀損にまで及ぶ可能性があります。 何とか属人化で回っている状態は、実は非常に不安定で危ういバランスの上に成り立っているのです。
③ 教育が進まず、組織が「育たない」
属人化は、新人や若手への教育を難しくします。「見て覚えて」「経験がものを言う」といった非言語的な教育スタイルは、属人的な業務の温床となり、若手の定着率・成長スピードを著しく低下させます。
長期的には、人が育たず組織が拡張できない状態に陥ってしまいます。
④ 改善・改革のボトルネックになる
属人化された業務は、変更が難しい。
「やり方を変えるとミスが出る」「担当者の負担が増える」といった理由で、改善提案が握りつぶされる風土が生まれます。
結果として、改善が進まず、変化に弱い組織になってしまうのです。
属人化は、日々の業務の中では目立たない「静かなリスク」かもしれません。しかしそれは、いざという時に組織の根幹を揺るがす火種にもなり得ます。このリスクを正しく認識し、構造からの対策が求められています。
関連記事
業務が属人化している企業必見|AI活用による段階的解決の方法
従来型の「標準化」「マニュアル化」だけでは属人化は防げない
多くの企業が属人化対策としてまず着手するのが、業務の見える化やマニュアル化です。具体的には、業務棚卸し、手順書の作成、チェックリストの導入などがよく見られる施策です。これらは確かに有効な一手ではありますが、属人化の根本解決にはなりません。
理由は明確です。属人化の“本丸”は、業務の中に潜む「判断」「例外対応」「人間関係への配慮」といった暗黙知や非定型要素にあるからです。こうした情報は、単なるフロー図や手順書では捉えきれません。言い換えれば、マニュアルで可視化できる部分は属人化の一部にすぎないのです。
また、マニュアルが形骸化してしまうケースも後を絶ちません。「更新されない」「現場の実態と乖離している」「読む暇がない」といった理由から、作っただけで活用されない状態になってしまうのです。こうした状況では、属人化を“書類の山”に移し替えただけになってしまいます。
つまり、従来型の標準化では「やり方」を残すことはできても、「なぜその判断をしたのか」「どのような文脈で最適な対応を選んだのか」といった情報は失われてしまいます。属人化を真に解消するためには、この“見えない知識”をいかに仕組み化できるかが問われているのです。
このような背景をふまえ、次章ではこうした非定型業務の知見や判断を含めて仕組み化するために、生成AIがどのように活用され始めているのかを解説します。
生成AIによる属人化解消の新アプローチ:業務の再設計とは
属人化の解消は、単なる「作業の引き継ぎ」ではなく、「業務構造の再設計」が求められます。生成AIの登場により、これまでブラックボックス化されていた知識や判断プロセスを“言語化”し、仕組みの中に取り込むことが現実的になってきました。ここでは、生成AIを活用した属人化解消の3つの切り口を紹介します。
1. 業務ナレッジの構造化と自然言語化
生成AIの最大の強みは、非定型な会話や経験知を言語化し、ナレッジとして整理できる点にあります。たとえば、熟練担当者が持つ「顧客対応のコツ」や「イレギュラー時の判断基準」など、従来は口頭ベースでしか伝えられなかった知識を、AIとの対話を通じてプロンプト形式で抽出・記録できます。
これにより、“誰かに聞かないとわからない”という属人化の壁を越え、ナレッジを組織の資産として再利用できるようになります。
2. AIによる業務フローの補助・代替
属人化しやすい業務の中には、「定型と非定型が混在している」領域が多くあります。生成AIは、単なる自動化では対応できなかったこうしたグレーゾーンにも適応可能です。
たとえば、社内問合せへの対応、分析レポートの一次生成、定例資料の骨子作成といった作業をAIが担うことで、担当者の業務負荷が大幅に軽減されます。これにより、特定の個人に業務が集中するリスクを抑えながら、全体の業務フローを平準化することができます。
3. 対話を通じたナレッジ継承と教育
属人化の解消において重要なのが「育成の仕組み化」です。生成AIを活用すれば、経験者とAIが対話しながら業務ナレッジを蓄積し、それを新人や後任がAIと対話することで学ぶという“循環的な教育フロー”が構築できます。
マニュアルでは伝わりにくいニュアンスや背景事情も、AIとの会話を通じて自然に補足されるため、OJTや引き継ぎの精度が格段に向上します。
このように、生成AIは属人化の「見えない課題」を可視化し、「繰り返し使える仕組み」に変える可能性を持っています。
関連記事
業務の属人化を解消する5つの方法|生成AI時代の新しい組織づくり
成功のカギは対話と納得|人を責めず、仕組みを変える発想
属人化の問題は、「あの人が悪い」「引き継がないのが悪い」といった個人批判に矮小化されがちです。しかし本質的には、業務設計・情報共有の仕組み・組織文化といった構造の問題です。だからこそ、「人を責める」のではなく、「仕組みを変える」視点が不可欠です。
その中で、生成AIは人と仕組みの橋渡しとなる存在です。ベテラン社員の経験を自然言語で抽出し、誰でもアクセスできるナレッジに変換する。マネージャーの判断パターンを言語化し、後任が再現できるようにする。こうしたAI活用の積み重ねは、属人化の解消だけでなく、組織としての成長スピードと安定性を飛躍的に高めます。
ただし、こうした取り組みは単発のツール導入では実現しません。現場との対話を重ね、徐々に仕組みを変えていくプロセスが重要です。そのためには、生成AIそのものの理解と、業務への適用方法を段階的に学ぶ「組織内の土台づくり」が必要になります。
SHIFT AI for Bizでは、属人化の課題を抱える企業に向けて、AI活用を体系的に学べる法人研修プログラムを提供しています。今あるリソースを活かしながら、無理なく属人化を仕組みに変えていくステップを、現場と一緒に構築していきます。
まとめ:属人化は仕組みで変える時代へ。AIと現場がつながる第一歩を
属人化の問題は、もはや“放置できる業務課題”ではありません。人的リスクの増大、育成の停滞、業務改善の硬直化など、放置すればするほど、企業活動の柔軟性と競争力を奪っていきます。
従来のようなマニュアル化や定型業務の棚卸しだけでは、複雑化した業務の属人化には太刀打ちできません。今こそ、生成AIという新しい仕組みを活用し、業務の見える化・再設計・育成の再構築に踏み出す時です。
SHIFT AI for Bizでは、こうした変革を段階的に、現場の理解と納得を得ながら実現するサポートを提供しています。属人化からの脱却を、本気で目指す企業のために——。