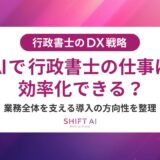せっかくCopilotを導入したのに、現場ではほとんど使われていない——。
そんな声をよく耳にします。
技術的なトラブルではなく、「使える環境は整っているのに、実際の業務では活用されていない」という課題は、多くの企業で共通しています。
Copilotは業務効率化の強力な武器である一方で、「どう使えばいいか分からない」「現場がピンときていない」といった“活用の壁”が存在します。
本記事では、Copilotが活用されない主な原因とその背後にある組織的課題を整理しながら、活用を促進するための仕組みづくりとチェックポイントをわかりやすく解説します。
生成AIを“現場に根付かせる”ヒントをお探しの方は、ぜひ最後までご覧ください。
また下記のリンクからは、「全社員のCopilot活用」「Copilot活用人材育成」をテーマにした複数の事例を含め、AI導入・活用に成功し成果をあげている様々な業種の実際の取り組み17選をまとめた事例集をダウンロードいただけます。自社と似た課題感を持つ会社が、どうやってAIを活用しているのか知りたい方はお気軽にご覧ください。
\ Copilot導入の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
Copilotが“活用されない”5つのよくある理由
Copilotの導入環境は整っていても、実際に現場で「使われない」ケースは少なくありません。
その背景には、技術ではなく人や組織の側にある課題が潜んでいます。以下では、特に多くの企業で見られる5つの原因を取り上げます。
「そもそも何に使うのか分からない」
Copilotができることは多岐にわたりますが、社員一人ひとりにとって「自分の業務のどこに役立つのか」が見えていなければ、活用は進みません。
マニュアルがあっても、目的やゴールがイメージできない状態では、現場は動きません。
「AIに指示するより自分でやった方が早い」という思い込み
操作に慣れていないうちは、Copilotにプロンプトを打つより、自分で手を動かしたほうが早いと感じてしまうものです。
その結果、学習やトライを避け、使わないまま定着しない…という悪循環に陥ることもあります。
「間違ってたら怖い」心理的ハードル
Copilotが生成した内容を使うことに不安を感じる人も少なくありません。
「誤った情報で資料を作ってしまったらどうしよう」「精査が大変そう」といった心理的な抵抗が、活用を妨げます。
「一部の人しか使っていない」属人化の問題
特定の社員だけがCopilotを使いこなし、他のメンバーは「便利そうだけど、自分には無理」と距離を置く。
このような“生成AI格差”が生まれると、活用は一部の人に偏ってしまい、組織全体には広がりません。
「成功体験が共有されていない」ナレッジの断絶
たとえ誰かがうまく活用していても、それが社内で共有されていなければ意味がありません。
「誰が」「どんな業務で」「どんな成果が出たのか」という具体的な活用事例が見えない状態では、他の人が真似をするきっかけが生まれにくくなります。
\ Copilot導入の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
「使える組織」に共通する3つのポイント
Copilotの導入効果を最大化できている組織には、いくつかの共通した特徴があります。
単に「ツールを配った」だけではなく、使うための仕組みや文化を意図的に設計しているのです。ここでは、その中でも特に重要な3つの要素をご紹介します。
ユースケースをテンプレ化し、現場に合わせて言語化
「何に使えばよいのか分からない」という状態をなくすには、ユースケースを“テンプレート化”することが効果的です。
たとえば以下のように、具体的な業務×活用例をセットで整理しておくことで、現場は「まずこれを試してみよう」と動きやすくなります。
- 議事録作成→Teamsの会話ログを要約
- 稟議書作成→過去の類似文書から構成を提案させる
- メール下書き→返信案を自動生成して時短
属人的なノウハウではなく、組織としてのナレッジに落とし込むことが、活用の第一歩です。
業務フローにCopilotを“埋め込む”活用設計
「Copilotを使ってもいいですよ」では、忙しい現場は動きません。
実際に使われている組織では、業務プロセスそのものにCopilotの活用ステップを組み込んでいます。
たとえば、
- 月次レポート作成の際、「まずCopilotでドラフトを生成」→「確認・編集」→「提出」というステップを標準化
- 会議前に「議題に対する事前要約をCopilotで準備」といったルールを設定
このように、“使わざるを得ない”設計にすることで、自然とCopilotが業務に根付きます。
現場とマネジメントをつなぐ“AI推進役”の存在
最後のカギは、現場と管理層の橋渡しをする推進担当者の存在です。
現場の困りごとを吸い上げ、活用のハードルを下げるサポートを行う役割は、社内展開に不可欠です。
また、こうした推進役が社内ナレッジの蓄積・共有をリードすることで、活用の波が組織内に広がっていきます。
自社でCopilotを導入したものの、うまく定着していないと感じる場合、以下の項目をチェックしてみてください。
3つ以上当てはまる場合は、「活用設計の見直し」が必要かもしれません。
| チェック項目 | 該当 |
| Copilotが“使われている業務”を具体的に説明できない | □ |
| マニュアルはあるが、現場でほとんど読まれていない | □ |
| 「使い方が分からない」という声が多い | □ |
| Copilotを使っているのは一部の人だけ | □ |
| 会議や資料作成など“具体的な業務”での活用例が社内にない | □ |
| Copilotを使ってミスをしたらどうしよう、という不安がある | □ |
| 成功事例やTIPSがナレッジとして共有されていない | □ |
| 経営層がCopilot活用に関心を示していない・支援していない | □ |
いくつ当てはまりましたか?
該当数が多いほど、「Copilotが活用されない構造」が組織内に残っている可能性が高いです。
\ Copilot導入の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
Copilot活用を“定着”させるための3つの施策
単に使い方を伝えるだけでは、Copilotの活用は定着しません。
「どの業務で」「どう使えば」「どんな成果につながるか」を組織として設計・共有することが、定着への鍵となります。
ここでは、実践的な3つの施策をご紹介します。
1.業務ごとの“プロンプト例”を共通ナレッジ化する
Copilot活用において最も多いつまずきは、「どんなプロンプトを打てばいいか分からない」という悩みです。
この課題は、業務単位で使える具体的なプロンプト例をナレッジとしてまとめておくことで解消できます。
例:議事録作成のプロンプト
以下の会話ログを要約し、箇条書きで議事録形式にまとめてください。重要な意思決定と担当者の名前は明記してください。
このような“すぐに使えるテンプレ”を部署ごとに整備しておくと、活用のハードルは一気に下がります。
2.小さく始めて“成果”を言語化・可視化する
いきなり全社展開を目指すのではなく、まずは一部の業務や部署でトライし、得られた成果を定量・定性の両面で言語化しましょう。
- 【定量例】資料作成時間が平均60分→20分に短縮
- 【定性例】「資料作成の骨組みが自動でできるから考える時間に集中できた」などの声
このような「成功の実感」を言語化・共有することで、他部署への横展開や上層部の理解も進みやすくなります。
3.“生成AI研修”を通じたリテラシー底上げと文化醸成
Copilotはツールである以上、それを使いこなすためのリテラシーと習慣が欠かせません。
社内展開を本気で目指すなら、以下のような生成AI研修の実施が有効です。
- ツールの基本操作とプロンプトの考え方
- 各業務での使いどころと注意点
- セキュリティや精査の観点など、組織としての運用ルール
SHIFT AIでは、こうした“現場定着”をゴールに設計された研修パッケージを提供しています。
まずは資料を見てみたい方はこちらからご確認ください。
まとめ|Copilotを「使える組織」へ変えるには?
MicrosoftCopilotは、業務の生産性を大きく高める可能性を秘めた生成AIツールです。
しかし、導入しただけでは活用は進まず、「現場で使われないまま終わってしまう」ケースも少なくありません。
本記事では、Copilotが活用されない原因を整理し、そこから脱却するためのポイントをお伝えしました。
本記事のポイント
- 活用されない背景には「使い方が分からない」「業務に組み込まれていない」などの構造的な問題がある
- ユースケースやプロンプトを“見える化”し、業務フローに組み込む設計が必要
- 成果の言語化と社内ナレッジ共有、リテラシー強化のための研修が定着のカギ
Copilotを“絵に描いた餅”にしないためには、仕組みと文化の両面からアプローチすることが不可欠です。
また下記のリンクからは、「全社員のCopilot活用」「Copilot活用人材育成」をテーマにした複数の事例を含め、AI導入・活用に成功し成果をあげている様々な業種の実際の取り組み17選をまとめた事例集をダウンロードいただけます。自社と似た課題感を持つ会社が、どうやってAIを活用しているのか知りたい方はお気軽にご覧ください。
\ Copilot導入の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
- QMicrosoftCopilotを導入しても使われない理由は?
- A
多くの場合、「何に使えるのか分からない」「業務フローに組み込まれていない」「現場が使い方を知らない」などの理由が挙げられます。技術的な設定だけでなく、業務設計や教育もセットで考える必要があります。
- QCopilotの活用を定着させるには何から始めればいいですか?
- A
まずは「業務別の活用テンプレート(プロンプト)」を用意し、少人数・小規模な業務で成功事例を作ることが有効です。その後、成果を全社で共有する流れがおすすめです。
- Q現場がうまく使えない場合、外部支援は必要ですか?
- A
生成AI活用の社内展開には一定の専門性が求められるため、外部の知見を活用することで展開スピードと定着率が向上します。SHIFT AIでは、業務に即した生成AI研修も提供しています。
- QCopilotが活用されていないかどうか、どう判断すればいいですか?
- A
定着状況を可視化するには、活用頻度や利用ユーザーの偏り、現場からの問い合わせの内容などを確認するのが有効です。記事内の「チェックリスト」を参考に、現場の実態を見える化しましょう。
- QChatGPTや他の生成AIとCopilotは何が違うのですか?
- A
CopilotはMicrosoft365アプリに統合されているため、WordやExcel、Outlookなどでの業務支援に特化しています。汎用型のChatGPTとは異なり、社内ドキュメントや予定表などの“業務データと連携できる”点が大きな強みです。