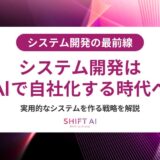「Copilotを導入すれば、業務の効率化が一気に進む」
そんな期待を持って、導入を進める企業が増えています。
実際、Microsoft 365 CopilotやGitHub Copilotなどの生成AIツールは、ドキュメント作成やプログラミングといった定型業務を劇的にスピードアップさせるポテンシャルを持っています。
しかし、 現場で「思ったほど使われない」「セキュリティの懸念が拭えない」「誤った出力で業務が混乱した」といった声が上がるのもまた事実です。
Copilotは、導入するだけでは成果につながりません。情報管理・教育体制・活用ルールなどの制度設計が不十分なまま進めてしまうと、むしろ社内の混乱を招く可能性すらあるのです。
本記事では、Copilot導入における典型的な5つのデメリットと、それらを未然に防ぐための対策や制度設計のポイントを、現場視点で徹底的に解説します。
「導入するべきか悩んでいる」「うまく活用されるか不安」「法務や情報システム部門との調整がネック」。そんな悩みを持つ担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
Copilot導入のよくあるデメリット5選
導入を急ぎすぎて「こんなはずじゃなかった」と後悔する企業も少なくありません。ここでは、Copilot導入時に起きがちな失敗パターンを5つに分類してご紹介します。
1. 社外秘が外に漏れる?情報漏洩・セキュリティリスク
Copilotは、クラウド上の大規模言語モデルを利用して応答を生成するため、社内情報が意図せず外部に送信されてしまうリスクがあります。
特に、Microsoft 365 CopilotではTeamsやOutlook、Word、Excelなどと連携するため、個人情報や取引先情報などの機密情報が学習対象になる可能性もゼロではありません。
情報システム部門やセキュリティチームとの連携を疎かにすると、「誰が何をどこまで使っていいのか」が曖昧になり、情報漏洩のリスクが現実化してしまいます。
▶ 対策のヒント
- 利用権限・対象範囲の明確化(例:経理部門は一部利用制限)
- 利用ログの可視化と監査体制の整備
- 社内ガイドライン(禁止ワードや業務でのNG活用例)の明文化
2. 間違った答えで現場が混乱|誤生成・ハルシネーション
Copilotはあくまで「AI予測」に基づく出力を行うため、事実とは異なる情報をもっともらしく提示してしまうことがあります。
例えば
- 顧客向け資料の中に、誤った統計データが含まれていた
- プログラムの自動生成で、仕様と異なる挙動のコードが提案された
など、誤生成=ハルシネーションによるトラブルが発生する可能性があります。
導入初期段階では特に、「AIを100%信じてしまう現場」が発生しがちです。レビュー体制や人の介在を前提に設計しないと、業務効率どころか混乱の拡大を招く恐れがあります。
▶ 対策のヒント
- 「Copilotの出力は必ず確認する」文化の浸透
- プロンプト設計トレーニング(SHIFT AIの研修など)
- 部門ごとのユースケースに応じた使いどころの線引き
3. 著作権や規約の壁|法務リスクを甘く見ない
Copilotが生成したテキストやコードには、既存の著作物と類似する可能性があります。そのため、提案された内容をそのまま利用した結果、著作権侵害を問われる可能性も否定できません。
また、企業によっては業務でのAI利用に関する規定が整備されておらず、「誰が責任を取るのか不明確」という状態が生まれやすいのも問題です。
法務部門との早期連携は、導入成功の鍵です。
▶ 対策のヒント
- AI生成物に対する再チェックのルール策定
- 商用利用・ライセンス的にNGな出力のフィルタリング設定
- 法務部門との「導入判断会議」の早期実施
4. 若手が育たない?スキル低下・思考停止の懸念
Copilotを使うことで、文書作成やコーディングが“自動化”される反面、自分で考える・試行錯誤する力が育ちにくくなるという副作用もあります。
特に、経験の浅い社員ほどAIの提案に依存しやすく、
- 「内容を理解せず提出する」
- 「エラーが出ても直せない」
といった、スキルの形骸化が進行するリスクがあります。
▶ 対策のヒント
- Copilot活用の前に「人力でやる訓練」の重要性を共有
- OJTとCopilotを組み合わせた育成プロセス設計
- 若手向けプロンプトレビュー制度の導入
5. 導入しても使われない|定着しない組織の特徴
いざ導入しても、現場でまったく活用されず、「高価な投資が無駄になる」ケースも少なくありません。
よくある失敗パターン
- 導入直後に教育をせず、誰も使い方がわからない
- 成果測定がなく、成功体験が広まらない
- ITリテラシー格差によって活用が属人化
▶ 対策のヒント
- ユースケースの事前提示と共有(例:営業×Excel分析)
- KPI設計と効果検証サイクルの確立
- プロジェクト単位の“導入リーダー”設置
▶️ 関連記事:Copilot導入後に定着しない理由と対処法はこちら
👉 Copilotを導入したのに活用できない原因とは?定着のための3つの打ち手
デメリットは回避できる|Copilot導入で押さえるべき3つの制度設計
Copilotは確かに強力なツールです。しかし、“使いこなせる組織”にするには、ツール以上に「制度の設計」が重要です。
ここでは、Copilot導入で失敗しないために、あらかじめ整えておくべき3つの制度設計ポイントをご紹介します。
1. 社内ポリシーと利用範囲の明確化
Copilotのような生成AIツールは、何でもできるようでいて、“どこまで使っていいか”が極めて曖昧になりがちです。
「どの部署が、どの業務で、どんなデータを使ってよいのか」。この基本ルールが決まっていないと、以下のような問題が起こります。
- セキュリティリスクの拡大
- 誤情報の混入
- 情報システム部の対応負荷増加
社内利用ポリシーを整備することは、Copilot導入のスタートラインです。
💡SHIFT AI研修では:
業種・職種ごとに使える/使えない領域を切り分け、
「現場で迷わず使えるポリシー設計」までサポートしています。
2. 情報システム部・法務部との早期連携
Copilot導入において、最もよくあるボトルネックが、情報システム部や法務部との調整不足です。
特に法務部からは以下のような懸念が挙がりがちです。
- AIが生成した情報の著作権リスク
- 商用利用の可否やライセンス確認
- データ送信・保存ルールの明確化
この調整を後回しにすると、「導入直前でNGが出る」という事態にもなりかねません。技術部門・法務・現場が共通言語で話せるようにする“翻訳設計”が必要です。
3. KPI設計とプロンプト教育による定着設計
どれだけCopilotを導入しても、定着しなければ投資は無意味です。そして、多くの企業が「定着しない理由」は以下の2つに集約されます。
- 成果が測定できない(KPIが曖昧)
- 使い方がわからない(教育が不十分)
そこで必要になるのが、「定着を前提とした制度設計」です。
つまり、
- 部署別の活用KPI(例:週に〇件自動化)
- リーダー層への先行研修
- ユースケースに沿ったプロンプト教育
といった仕組みを最初から組み込むことが鍵になります。
SHIFT AI研修ではやってみて終わりではなく、定着させるまで伴走する支援設計が可能です。
▶️ 関連リンク:Copilotの導入効果を最大化する設計・評価の方法はこちら
👉 Copilot導入の効果とは?成功企業の実例と成果が出ない原因を徹底解説
Copilotと他の生成AIツールとの違いと選び方
「Copilotって結局、他の生成AIツールとどう違うの?」
そんな疑問を持つ方も少なくありません。
結論から言うと、Copilotは業務アプリケーションと密接に連携する特化型ツールです。
ここでは、主な生成AIツール3種の特徴を整理し、自社に合った選び方の視点をご紹介します。
| ツール名 | 強み | 注意点/弱み | 導入に向いている部署 |
| Microsoft 365 Copilot | Word/Excel/Outlookなどに直結。業務の中で自然に活用可能 | セキュリティポリシー整備が必要。誤生成の精査体制がないと混乱の元 | 営業/企画/バックオフィス系 |
| GitHub Copilot | コーディング支援に特化。開発スピードが加速 | ライセンスリスクとレビュー必須。初心者の依存に注意 | エンジニア/開発部門 |
| ChatGPT(+社内ナレッジ) | カスタマイズ性・応答精度が高く、幅広い用途に対応 | プロンプト設計と運用の学習コストが大きい | DX推進チーム/情報システム部門 |
Copilotの魅力は「業務ツールに自然に入り込めること」ですが、その裏には誤操作しやすさや使われなくなるリスクも潜んでいます。
ツール単体の機能比較だけでなく、社内の利用ルールや教育設計が整っているかどうかを判断軸に加えることが重要です。
▶️【補足:Copilotが使えないと感じたら】
👉 Copilotが使えない?グレーアウト・非表示・設定ミスの原因と法人向けの対処法を徹底解説
<SHIFT AI研修では何ができる?>
ツールごとの特性に合わせて、
- ユースケース設計
- 部署別プロンプトトレーニング
- 情シス・法務への導入支援設計
までを一貫して伴走支援できます。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応
まとめ|Copilot導入は、制度設計と教育体制が成功のカギ
Copilotは、ただ導入するだけでは成果に結びつきません。セキュリティ・誤生成・著作権・スキル低下・定着不全など、企業にとってのリスクも現実に存在します。
しかし、それらのデメリットは「正しい制度設計」と「教育体制」があれば、すべて回避可能です。
SHIFT AIでは、Copilotを社内に定着させるための制度設計・研修設計を一貫して支援しています。導入に不安がある方も、すでに進めている方も、まずは資料で準備の第一歩を。
Copilot導入に関するよくある質問(FAQ)
読者が記事を読み進めたあと、最後に引っかかるのは「でも…うちの場合は大丈夫?」という不安です。ここでは、よくある疑問とその答えを整理しました。
- QCopilotを使うと社内のデータが外部に送信されるのでは?
- A
Copilotはクラウド上のAIモデルを使って応答を生成するため、確かにデータ送信のリスクは存在します。
ただし、Microsoft 365 Copilotではエンタープライズ向けにセキュリティ制御が設けられており、適切なポリシー設定とガバナンス運用が前提です。
<POINT>
導入前に「どのデータを、どの用途で使うか」を明確にした設計が重要です。
- QAIが生成した文章やコードに著作権上の問題はないの?
- A
Copilotが生成するコンテンツの中には、学習元と類似するパターンが出力される可能性があります。
そのため、商用利用や再配布を行う場合には、必ず法務部との確認プロセスを設けましょう。SHIFT AIの研修では、著作権のグレーゾーンを回避するための運用ルール設計まで支援しています。
- Q社員への教育や活用サポートはどうすれば?
- A
Copilotを導入しても、「使い方がわからない」と現場が戸惑えば定着しません。
実際に多くの企業で「教育・研修不足」がボトルネックになっています。
<POINT>- ユーザーごとのプロンプトスキルに応じた段階的研修
- 部署別の活用ユースケース提示
- KPI評価までを含めた“伴走型教育”の設計