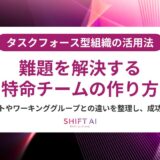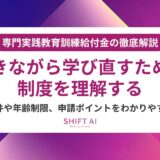コンビニ業界では、深刻な人手不足や長時間労働が続き、加盟店オーナーや本部の担当者にとって「いかに事務作業を効率化するか」が大きな課題となっています。売上管理、シフト作成、発注業務、本部への報告書作成など、毎日の店舗運営には多くのバックオフィス業務が発生し、現場スタッフの負担を増やしているのが現状です。
こうした状況を受けて、セブン-イレブンやファミリーマート、ローソンといった大手各社もAIを積極的に導入し、発注システムや文章作成支援などで成果を上げ始めています。しかし、多くのオーナーや事務担当者にとっては「実際にどんな事務作業をAIで効率化できるのか」「導入にはどんな準備や注意点があるのか」が明確でないケースも少なくありません。
本記事では、コンビニ業界における事務作業の課題を整理し、AIを活用して効率化できる具体的な領域や導入ステップを解説します。さらに、各社の最新事例を踏まえながら、失敗しないためのポイントや全社展開に必要なリテラシー向上についても紹介します。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
コンビニの事務作業に潜む課題とは
コンビニ店舗の運営は「接客・販売」だけではなく、多岐にわたる事務作業によって支えられています。加盟店オーナーや本部担当者にとって、これらの業務が日々の大きな負担となっているのが現状です。ここでは代表的な課題を整理します。
売上管理や会計処理の煩雑さ
毎日の売上データ集計や入出金の確認、帳簿処理は欠かせません。しかし、レジからのデータ取り込みや精算作業には人の手が多く関わり、ミスや二度手間が発生しやすい領域です。会計システムとの連携不足も効率化を阻む要因となっています。
シフト作成・勤怠管理の工数
スタッフの希望や人員不足、時間帯ごとの繁忙度を踏まえたシフト作成は、オーナーや店長にとって大きな負担です。さらに勤怠の打刻確認や労働時間の集計も、紙やExcelでの処理に頼る場合、管理に時間がかかります。
発注・在庫管理における属人化
商品の発注は、天候・曜日・イベントなど多くの要因を考慮する必要があり、経験や勘に依存しているケースも少なくありません。在庫が余れば廃棄ロス、足りなければ機会損失につながるため、店舗にとって重要かつ負担の大きい業務です。
本部への各種報告業務
本部への売上報告や改善提案、各種資料作成は定期的に発生します。標準フォーマットに沿ってデータをまとめる作業は単純ながら時間を奪われ、現場のオペレーションに割くべきリソースを圧迫しています。
AIで効率化できるコンビニの事務領域【4大テーマ】
事務作業の負担を軽減するために、多くのコンビニ企業が注目しているのがAIの活用です。AIは単なる「自動化」ではなく、データをもとに判断や提案を行う点で従来のシステムと異なります。ここでは特に効果が期待できる4つの領域を整理します。
売上・会計管理の自動化
売上データの入力や日次・週次の帳票作成は、AIとRPAを組み合わせることで大幅に省力化できます。例えば、レジデータを自動で集計し、会計システムに連携すれば、入力ミスの削減と同時に集計作業の時間短縮が実現可能です。AIによる異常値検知を組み合わせれば、不正や計上ミスの早期発見にもつながります。
勤怠管理・シフト作成の効率化
AIは、従業員の勤務希望や過去の売上データ、天候やイベント情報を分析し、最適なシフトを自動提案できます。これにより店長の調整負担が軽減され、労務管理の精度も向上します。勤怠データの自動集計やアラート機能を導入することで、働き方改革関連の法令遵守にも寄与します。
発注・在庫管理の最適化
発注業務はAI活用の代表例です。需要予測AIは曜日や時間帯、天候、地域イベントの情報を組み合わせ、最適な発注数を提案します。これにより、廃棄ロスを減らしつつ品切れを防ぎ、販売機会の最大化につながります。すでにファミリーマートやセブン-イレブンが試験導入を進めており、週数時間の業務削減効果が報告されています。
報告書・マニュアル作成の省力化
生成AIを活用すれば、店舗日報や本部向け報告書の作成時間を短縮できます。たとえば、定型フォーマットに売上や在庫状況を入力するだけで、自動でレポート文面を生成。従業員向けマニュアルの更新や顧客対応文書の作成も効率化でき、情報共有のスピードが向上します。
コンビニ各社のAI活用動向(セブン・ファミマ・ローソン比較)
大手コンビニ3社は、それぞれ独自のアプローチでAIを導入し、事務作業や店舗オペレーションの効率化を進めています。加盟店オーナーや本部担当者にとって、各社の取り組みを俯瞰することは、自店舗に合った活用法を考えるヒントになります。
セブン-イレブン:AI人員を大幅増強し全社的に活用
セブン-イレブンは、生成AIを商品企画や社内事務に活用し、業務効率化を推進しています。2024年度にはAIを使いこなせる社員数を従来の約1500人から倍増させ、約3000人規模に拡大しました。議事録や稟議書作成、プログラミング補助など幅広い業務で導入されており、商品開発プロセスでは作業時間が最大で10分の1に短縮されるなど大きな効果が確認されています。
参考:コンビニ、AIで効率化 セブン、活用人員3000人に倍増 ローソンは文章作成の時間半減
ファミリーマート:発注AIによる週6時間削減
ファミリーマートは、2025年6月末から約500店舗でAI発注システムを本格導入しました。天候やイベント、周辺の人流データなどを加味した需要予測に基づき、最適な発注数を自動で提示します。これにより、発注担当者の作業時間が1店舗あたり週約6時間削減されたと報告されており、欠品防止や廃棄ロス削減にもつながっています。今後は効果を検証しつつ、さらなる店舗への拡大が見込まれています。
参考:AIを活用した新たな発注システムを導入~店舗の業務効率化と販売機会の最大化を実現~
ローソン:生成AIで報告・文章作成を効率化
ローソンは、2024年から本社社員約4000人を対象に生成AIを業務利用できる体制を整備しました。日報や会議資料、稟議書などの定型文書をAIに下書きさせ、人が修正・加筆する運用により、文章作成にかかる時間を約50%削減。社員の事務負担を減らし、より付加価値の高い業務へ時間を振り分ける取り組みを進めています。
参考:コンビニ、AIで効率化 セブン、活用人員3000人に倍増 ローソンは文章作成の時間半減
AI導入のメリットと期待できる効果
コンビニの事務作業にAIを導入すると、単なる作業時間の削減にとどまらず、店舗運営全体にさまざまなプラス効果が生まれます。ここでは代表的なメリットを整理します。
業務時間の削減でスタッフの負担を軽減
AIが発注数の提案や帳票作成を自動で行うことで、店長やスタッフが手作業に費やしていた時間を削減できます。ファミマの発注AI導入事例では、1店舗あたり週6時間以上の削減効果が確認されており、他の事務領域でも同様の成果が期待できます。
人件費の抑制と人手不足対応
従来は事務作業に割かれていた人員を、接客や品出しなど顧客体験に直結する業務へ振り分けることが可能です。結果として必要人員の最適化につながり、人手不足の課題に対する有効な打ち手となります。
作業精度の向上とヒューマンエラーの削減
AIは膨大なデータをもとに処理を行うため、人の感覚に頼った業務よりも精度が高まります。発注や勤怠管理においては、人的ミスの削減が期待でき、廃棄ロスや労務トラブルの防止にも寄与します。
店舗と本部の情報共有効率化
生成AIを活用すれば、本部への報告書や資料作成の時間を短縮できるだけでなく、内容の標準化も可能です。データに基づいたレポートがスピーディーに共有されることで、意思決定の迅速化や戦略立案の精度向上にもつながります。
導入時に注意すべきリスク・課題
AIは事務作業を大きく効率化できる一方で、導入にあたっては慎重に検討すべき点があります。過度な期待や準備不足のまま導入を進めると、期待した効果が得られないケースも少なくありません。
過度な期待による失敗
「AIを入れればすべての業務が自動化できる」と考えるのは誤解です。AIはあくまで人の業務を支援するツールであり、運用ルールやチェック体制が整っていなければ効果は限定的になります。
セキュリティ・情報漏洩リスク
AIを利用する際には、売上データや従業員情報など機密性の高いデータを扱う場合があります。ツールの選定や運用ルールが不十分だと、情報漏洩や不正利用につながる危険性があります。
コスト回収(ROI)の見極め
AIシステムの導入には初期費用やランニングコストが発生します。小規模店舗では投資に見合う効果が出にくい場合もあり、導入前にROI(投資対効果)の試算が欠かせません。
従業員のリテラシー不足
AIを現場で使いこなせなければ、せっかく導入しても成果が出ません。スタッフや店長がAIをどう使うのかを理解し、日常業務に定着させるための教育が必要です。
事務作業効率化を進めるためのステップ
AI導入を成功させるためには、いきなり全社展開するのではなく、段階を踏んで進めることが重要です。ここでは、コンビニにおける事務作業効率化を実現するための基本的な流れを整理します。
① 現状の業務棚卸
まずは、店舗や本部で発生している事務作業を洗い出します。売上管理や勤怠集計、発注、報告書作成など、それぞれにかかっている時間や担当者を可視化することで、どの領域からAI導入を進めるべきかが明確になります。
② 小規模領域から導入
最初から大規模にシステムを導入すると、コストや教育負担が大きくなり失敗リスクも高まります。まずは勤怠管理や日報作成など、比較的導入が容易で効果が見えやすい領域から始めるのが効果的です。
③ 成果を可視化しKPIを設定
導入後は、削減できた時間やエラー率の低下といった数値を明確に記録します。KPIを設定して効果を検証することで、投資対効果を示せるだけでなく、次の展開に向けた説得材料にもなります。
④ 本部と連携し全社展開へ
成果が確認できたら、本部と連携して他店舗へ展開していきます。共通のシステムや運用ルールを整備することで、全体最適を実現でき、業界全体での効率化にもつながります。
全社展開には「AIリテラシー研修」が不可欠
AIを導入しても、現場のスタッフや管理者が正しく使いこなせなければ効果は限定的です。事務作業効率化を全社的に根付かせるためには、システム導入と並行して「AIリテラシー研修」を実施することが欠かせません。
ツール導入だけでは成果が出ない
多くの企業が陥るのが、「AIを入れれば自動的に業務が改善する」という誤解です。実際には、ツールの使い方や運用ルールを現場が理解していないと、効果を実感できずに形骸化してしまうケースが目立ちます。
店舗スタッフに必要なリテラシー
発注AIや勤怠管理AIを活用する場合、基本的な操作だけでなく「なぜその数値や提案が導き出されているのか」を理解することが重要です。現場での納得感が高まることで、AIの提案を活かした柔軟な判断ができるようになります。
本部と店舗をつなぐ共通基盤に
AIリテラシー研修は、店舗と本部の共通言語をつくる役割も果たします。本部が示す方針やKPIを店舗側が理解しやすくなり、組織全体での効率化がスムーズに進みます。
\ “研修が定着しない”会社でも導入しやすい内容とは? /
まとめ|コンビニの事務作業はAIで効率化できる
コンビニの事務作業は、売上管理や勤怠、発注、報告書作成など多岐にわたり、店舗運営を圧迫する大きな要因となっています。AIを活用することで、これらの業務を効率化し、スタッフの負担軽減や人手不足対応、さらには店舗全体のパフォーマンス向上につなげることが可能です。
ただし、AIは導入すれば自動的に成果が出るわけではなく、段階的な導入ステップや現場スタッフの理解が欠かせません。特に全社展開を目指す場合には、AIリテラシー研修を通じて「現場で使いこなす力」を育てることが成功の鍵となります。
AIを味方につけた店舗運営を進めたい方は、まずは現状の業務負担を棚卸しし、小さな改善から取り組むことをおすすめします。そのうえで、研修を通じてスタッフ全員がAIを使える状態をつくれば、コンビニ業務の未来は大きく変わります。

よくある質問|コンビニ事務作業のAI効率化
- Qコンビニの事務作業でAIが活用できる具体例は?
- A
売上集計や帳票作成、勤怠管理、シフト作成、発注業務、本部への報告書作成などが挙げられます。とくに発注AIや生成AIを使ったレポート作成は効果が出やすい分野です。
- Q発注AIと勤怠AIではどちらが効果的ですか?
- A
店舗の状況によって異なります。発注AIは在庫ロス削減や売上機会の最大化に効果的で、勤怠AIは店長のシフト調整負担を軽減します。導入効果が早く見えやすいのは勤怠AIですが、長期的な利益改善には発注AIも有効です。
- QAI導入コストはどのくらいかかりますか?
- A
ツールや導入規模によって幅があります。クラウド型のサービスでは月額数千円から始められるものもあれば、大規模な発注システムでは数百万円単位の投資が必要になるケースもあります。重要なのは、投資対効果(ROI)を事前に試算することです。
- Q店舗スタッフがAIを使いこなせるか不安です。
- A
研修を通じてリテラシーを高めることで、現場でも十分に活用できます。難しいプログラミング知識は不要で、操作に慣れることが成果につながります。
- Q本部と連携してAI活用を広げる際の注意点は?
- A
店舗ごとの成果を数値化して本部に共有することが重要です。効果を可視化することで本部側も導入を進めやすくなり、全社的な効率化につながります。