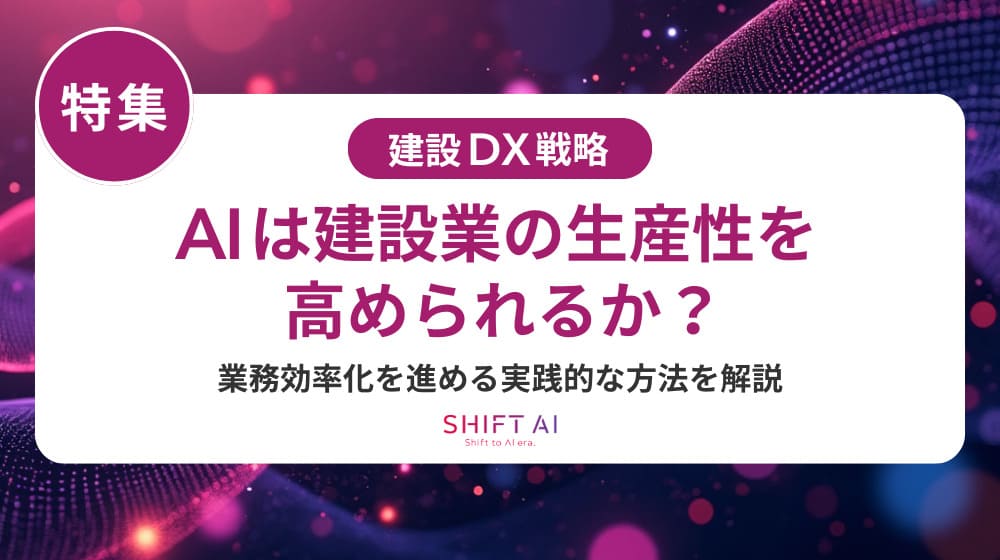建設業界では深刻な人材不足が続いています。国土交通省の調査でも、2025年には技能労働者が90万人以上不足すると予測されており、現場の生産性低下や安全性への影響が懸念されています。
採用活動の強化だけではこの課題を乗り越えることは難しく、今後は「限られた人材でいかに効率的に現場を回すか」が大きなテーマとなっています。
そこで注目されているのがAIの活用です。施工管理や設計・積算、安全管理から事務作業の効率化まで、AIは幅広い領域で省人化を支え、働き方改革の推進にも寄与します。
本記事では、建設業における人材不足を解消するためのAI活用方法と導入ステップを整理し、企業が取るべき次の一手を解説します。
また下記のリンクからは、建設会社による生成AI活用人材の創出やRAG(生成AIと社外秘データを組み合わせる技術)実装事例を含めた、生成AIを活用し少ない人員でも成果をあげる仕組みを整えた様々な取り組み17選をまとめた事例集をダウンロードいただけます。自社と似た課題感を持つ会社が、どのようにAIを活用しているのか知りたい方はお気軽にご覧ください。
\ 建設会社も含めた、生成AI活用の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
建設業における人材不足の現状と背景
建設業は日本経済を支える重要な産業ですが、深刻な人材不足が避けられない課題となっています。背景にはいくつかの要因があります。
まず大きな要因は技能労働者の高齢化と若手不足です。国土交通省の統計によれば、建設技能労働者の平均年齢は40代後半を超えており、今後の大量離職が予測されています。一方で若年層の新規入職は減少傾向にあり、世代交代が進んでいません。
さらに、働き方改革による労働時間の上限制約も影響しています。従来は長時間労働で人手不足を補っていましたが、それが難しくなり、同じ仕事量をより少ない時間と人員でこなす必要が出てきました。
また、現場の業務が属人化している点も問題です。熟練者の経験や勘に依存した作業が多く、標準化が進んでいないため、若手人材へのスムーズな技術伝承が難しい状況です。
加えて、国の政策目標として「建設業の生産性を2025年までに2割向上させる」ことが掲げられています。業界全体で効率化を進めなければ、慢性的な人材不足と需要拡大の両立は困難といえるでしょう。
このような背景から、「AIによる省人化・効率化」は建設業にとって避けて通れない取り組みとなっています。
AIが人材不足を解消できる5つの領域
建設業でのAI活用は単なる自動化にとどまらず、少人数で現場を回す仕組みづくりに直結します。ここでは、人材不足解消に効果的な5つの領域を整理します。
施工管理の効率化
AIカメラやドローンを用いた自動記録により、進捗確認や出来形管理にかかる手間を大幅に削減できます。従来は現場監督が長時間を費やしていた業務を省人化することで、管理者1人あたりの担当範囲を拡大できるようになります。
設計・積算の自動化
BIM(Building Information Modeling)や生成AIを活用することで、設計や積算業務を効率化できます。従来は熟練者の経験に依存していた作業も、AIがサポートすることでスピードと精度が向上し、限られた人材でより多くの案件に対応可能になります。
安全管理・労災防止
現場では人手不足が安全性低下につながりやすいですが、AIは危険行動や異常をリアルタイムで検知できます。例えばヘルメットの未着用や立入禁止エリアへの侵入などを検出し、人が少ない現場でも安全を確保できます。
教育・技術伝承
熟練者不足の中で注目されるのがAIを活用した教育支援です。生成AIを活用したシミュレーションやVR研修は、新人のスキル習得を加速させ、短期間での戦力化を実現します。結果として、人材不足による教育負担を軽減できます。
事務・労務作業の削減
現場以外の事務領域でもAIの効果は大きく、日報作成、労務管理、入退場管理などの作業を自動化できます。これにより、現場担当者が本来の業務に集中できる環境が整い、人材不足の影響を和らげられます。
これら5つの領域は、どれも「人手不足の現場をどう回すか」という建設業の根本課題に直結しています。
AI導入で期待できる効果
AIを導入する最大のメリットは、単なる効率化にとどまらず、人材不足を前提とした持続的な現場運営を実現できる点にあります。
まず、少人数で現場を回せる体制を整えられます。これまで数人がかりで行っていた管理・記録業務をAIが自動化することで、1人の担当者でもより広い範囲をカバーできるようになります。
次に、ミスや手戻りの削減につながります。AIは膨大なデータを基にチェックや予測を行うため、人間の確認作業だけに頼るよりも精度が高まり、無駄な工数を防ぎます。これは、人材不足の現場において特に大きな効果を発揮します。
さらに、技術伝承や教育コストの削減も期待できます。AIによる自動学習コンテンツやシミュレーションを活用することで、新人教育を効率化し、短期間で即戦力化を実現できます。
そして、働きやすさの改善による離職防止や採用力強化にも直結します。AIによる省人化で労働負担が軽減されると、従業員の定着率が上がり、採用時のアピールポイントとしても有効です。
人材不足への対応策は「新しい人を採ること」だけではなく、いまいる人材で成果を最大化する仕組みづくりであることが分かります。
\ 人手不足の現場で成果を出す“生成AI活用法”とは? /
AI導入による離職防止と定着率向上
AIによる省人化や効率化は、単に業務を楽にするだけでなく、従業員の働きやすさを改善し、離職防止にも直結します。
国土交通省の調査でも、建設業の離職率は全産業平均より高く、特に若手層での早期離職が課題となっています。過重労働や教育負担の大きさが理由として挙げられることが多く、ここにAIの導入効果が期待できます。
例えば、AIによる自動記録や進捗管理で残業が減れば、長時間労働に悩まされるケースが減少します。また、VRや生成AIを用いた教育システムで新人のスキル習得を早められれば、先輩社員の教育負担も軽減され、職場全体のストレスが軽くなります。
こうした取り組みは「働きやすい環境づくり」として外部にもアピールでき、採用活動の際にも「定着率の高い会社」というブランド形成につながります。
つまり、AI活用は「人材不足を補う施策」であると同時に「離職を防ぎ人材を守る施策」としても機能するのです。
AI導入のステップと注意点
AIを活用して人材不足を補うには、いきなり大規模に導入するのではなく、段階的に進めることが成功のポイントです。
- 現場課題の洗い出し
まずは「どの業務で人材不足が最も深刻か」を明確にすることが重要です。施工管理なのか、設計・積算なのか、あるいは労務や事務作業なのか。課題を特定することで、AI導入の優先順位を定められます。 - スモールスタートで効果を検証
いきなり全社的に導入するのではなく、一部の業務やプロジェクトで試験的に運用し、効果を検証するのが効果的です。小さく始めて成果を確認することで、現場の抵抗感も和らぎます。 - 社員教育・AIリテラシー研修
ツールを入れるだけでは効果は限定的です。実際に使いこなせる人材を育てることが欠かせません。AIリテラシーを高める研修を行うことで、導入効果を最大化できます。 - データ活用とセキュリティ対策
AIはデータを活用して成果を出すため、情報の取り扱いに注意が必要です。個人情報や施工データの管理体制を整えることで、リスクを最小限に抑えられます。
これらのステップを踏むことで、AIは「人手不足を補うための現実的な戦略」として機能します。
関連記事:
建設業界のAI活用完全ガイド|経営効率化から全社展開まで成功戦略を徹底解説
\ 生成AI研修の選定に必要な考え方がわかる /
建設業の人材不足解消には「AI人材育成」も不可欠
AIは導入するだけでは効果を発揮しません。実際に現場で使いこなせる人材がいなければ、せっかくの投資も十分な成果につながらないでしょう。建設業の人材不足を補うためには、「AIを扱える人材」を育成すること自体が解決策となります。
例えば、施工管理や積算を支援するAIを導入しても、現場担当者が操作に不慣れであれば従来と変わらない非効率が続きます。逆に、社員がAIを理解し適切に活用できれば、少人数でも効率的に現場を回せる仕組みを定着させられます。
そのためには、ツールの使い方にとどまらず、AIの仕組みやリスクも含めたリテラシー教育が欠かせません。現場で安心して活用できる環境をつくることが、長期的な人材不足解消に直結します。
\ 生成AI研修の選定に必要な考え方がわかる /
建設業の人材不足をAIで克服するために必要なこと
建設業の人材不足は今後も続く深刻な課題です。
高齢化や若手不足、働き方改革による労働時間の制約など、従来の採用活動や業務改善だけでは解決が難しい現実があります。
そのなかでAIは、施工管理・設計積算・安全管理・教育・事務作業の効率化といった幅広い領域で、人材不足を補いながら生産性を高める有効な手段となります。導入を成功させるには、課題の特定、スモールスタートでの検証、そして社員のAIリテラシー向上が欠かせません。
人材不足を「嘆く課題」から「成長へのチャンス」に変えるためには、AIを使いこなせる人材育成が最も重要な投資といえるでしょう。今こそ、AIを活用できる人材づくりを始めませんか?
下記のリンクからは、建設会社による生成AI活用人材の創出やRAG(生成AIと社外秘データを組み合わせる技術)実装事例を含めた、生成AIを活用し少ない人員でも成果をあげる仕組みを整えた様々な取り組み17選をまとめた事例集をダウンロードいただけます。自社と似た課題感を持つ会社が、どのようにAIを活用しているのか知りたい方はお気軽にご覧ください。
\ 建設会社も含めた、生成AI活用の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
よくある質問|建設業の人材不足とAI活用のポイント
- Q建設業の人材不足はなぜ深刻化しているのですか?
- A
主な理由は、技能労働者の高齢化、若年層の入職者不足、働き方改革による労働時間の制約です。特に熟練者の大量離職が見込まれる一方で、若手が十分に育っていないことが大きな要因となっています。
- QAI導入でどの程度人材不足を解消できますか?
- A
AIは直接「人を増やす」わけではありませんが、施工管理や積算、安全管理、事務作業を効率化することで、少人数でも現場を回せるようになります。これにより、採用強化だけに頼らずに人材不足を補えるのが大きな強みです。
- QAIを導入する際の注意点は何ですか?
- A
最初から大規模に取り入れるのではなく、課題の洗い出しとスモールスタートが重要です。また、情報セキュリティや誤情報リスクへの配慮も欠かせません。さらに、社員がAIを正しく理解・活用できるよう教育体制を整えることも必要です。
- Q中小規模の建設会社でもAI導入は可能ですか?
- A
可能です。最近ではクラウド型の手軽に導入できるサービスも増えており、現場の課題に合わせて段階的に取り入れることができます。むしろ人材不足の影響を受けやすい中小企業にこそ、AI活用は効果的です。
- QAI導入にあたり、まず何から始めるべきでしょうか?
- A
最初のステップは「現場の課題を明確にすること」です。そのうえで小規模にAIを試し、効果を検証することが推奨されます。加えて、社員のAIリテラシーを高める研修を並行して行うことで、導入効果を最大化できます。