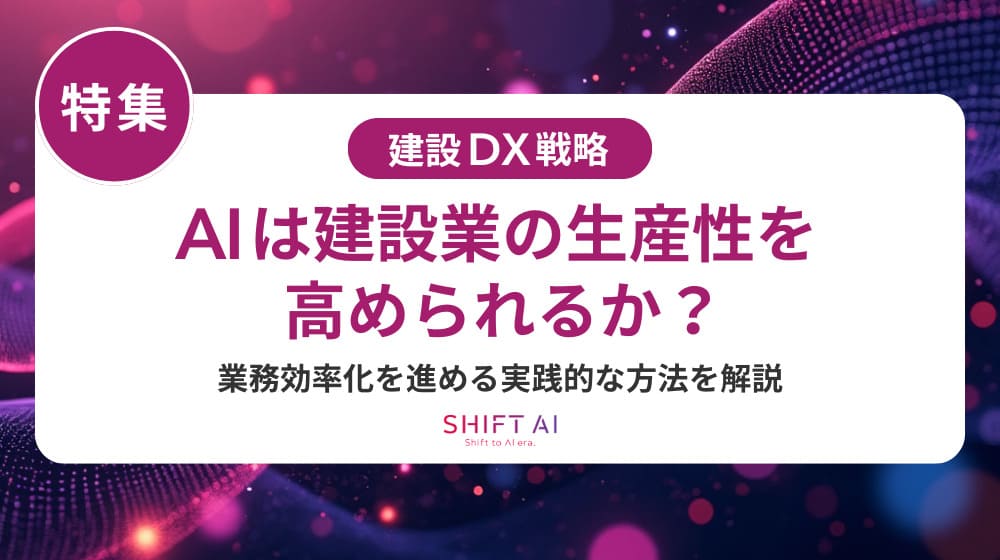建設業界では、深刻な人手不足や安全管理の強化、生産性向上のニーズから、AIの導入が急速に広がっています。現場の効率化やコスト削減に効果が期待される一方で、「実際に導入するにはどのくらい費用がかかるのか」「クラウド利用と自社開発ではどの程度違うのか」といった疑問を持つ担当者も少なくありません。
本記事では、AI導入に必要な費用の内訳や導入形態別の相場、費用対効果(ROI)の考え方、さらに補助金を活用してコストを抑える方法までを徹底解説します。導入を検討している企業が予算を正しく見積もり、投資判断を下せるようになる内容です。
また下記のリンクからは、建設会社によるRAG(生成AIと社外秘データを組み合わせる技術)実装を支援した事例を含めた、生成AI活用の様々な取り組み17選をまとめた事例集をダウンロードいただけます。自社と似た課題感を持つ会社が、どのようにAIを活用しているのか知りたい方はお気軽にご覧ください。
\ 建設会社も含めた、生成AI活用の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
建設業でAI導入が加速する背景と「費用感」が重要な理由
建設業は、他産業と比べても深刻な人材不足に直面しています。国土交通省の調査によると、技能労働者の高齢化が進み、若手の新規参入は減少傾向にあります。その結果、施工管理や安全管理といった現場業務の効率化が喫緊の課題となり、AIを活用した自動化やデータ解析の需要が高まっています。
さらに、公共工事をはじめとする建設プロジェクトでは、安全性や品質を確保しながらコストを抑えることが求められます。AIによる施工計画の最適化や画像解析による検査の自動化は、その解決策として期待されています。
しかし、AI導入を成功させるには「どのくらいの費用がかかるのか」を正しく把握しておくことが欠かせません。初期費用だけでなく、クラウド利用料や保守費用、人材育成などのランニングコストも含めた総合的な費用感を理解していないと、途中で予算が不足したりROI(投資回収率)が合わずに失敗に終わるリスクがあります。
つまり、AI導入における費用感を正しく把握することは、建設DXを推進する第一歩なのです。導入を検討している企業にとって、費用の内訳や相場を整理しておくことが成功への分岐点になります。
建設業界におけるAIの活用全体像については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
建設業界のAI活用完全ガイド|経営効率化から全社展開まで成功戦略を徹底解説
AI導入にかかる費用の内訳
建設業でAIを導入する際には、「初期費用」と「運用費用」、そして見落とされがちな「隠れコスト」の3つに分けて考える必要があります。それぞれを把握することで、導入後の総コストを正確に見積もれるようになります。
初期費用
AI導入のスタート時に発生するのが初期費用です。代表的な項目は以下の通りです。
- システム構築費用:AIモデルの開発、既存システムとの連携
- 機材購入費用:AIカメラ、ドローン、IoTセンサーなどのハードウェア
- コンサルティング費用:導入設計やプロジェクトマネジメント支援
特に自社専用にカスタマイズする場合、初期費用が高額になりやすい点に注意が必要です。
運用費用
AIは導入したら終わりではなく、継続的な運用が欠かせません。
- クラウド利用料:AIサービスやプラットフォームのサブスクリプション費用
- 保守・サポート費用:システムの安定稼働や不具合対応
- 人材教育費用:社内でツールを使いこなすための研修やトレーニング
月額・年額で継続的にかかる費用を想定しておくことが重要です。
隠れコスト
導入前に見落とされがちなのが「隠れコスト」です。
- データ整備:AIに学習させるためのデータ収集やクリーニング作業
- 社内体制づくり:AIを使いこなす担当部署の設置やオペレーション調整
- 追加カスタマイズ費用:運用後に必要となる機能拡張や仕様変更
これらは見積書に明確に書かれないことが多く、導入後のトラブルやコスト超過の原因になりやすい部分です。
導入形態別の費用相場|クラウド・自社開発・PoCの比較
AI導入にかかる費用は、選ぶ導入形態によって大きく異なります。ここでは代表的な3つのパターンを取り上げ、それぞれの相場感と特徴を整理します。
クラウドサービス利用型
- 費用相場:月5万〜30万円程度
- 特徴:AIカメラや施工管理支援システムなど、既に開発済みのサービスを利用する形態。
- 初期費用を抑えやすく、小規模現場や特定業務の効率化から始められる点が強みです。
- 一方で、自社固有の業務プロセスに合わせた柔軟なカスタマイズには限界があります。
自社開発・カスタマイズ型
- 費用相場:500万〜数千万円規模
- 特徴:自社専用にAIを開発し、既存の基幹システムや現場フローに完全統合する形態。
- 精度の高い効果が得られる一方で、開発期間が長く、初期投資も大きくなります。
- 中長期的に全社規模で活用を考えている場合に適した方法です。
PoC(小規模実証実験)型
- 費用相場:50万〜300万円程度
- 特徴:本格導入の前に、特定の現場や業務で試験的にAIを導入し効果を測定する取り組み。
- 導入リスクを最小限に抑え、費用対効果を見極めるための手段として有効です。
- 成果が確認できた場合にスケールアップすれば、投資効率を高めやすいのも利点です。
比較のまとめ
表形式で整理すると以下のようになります。
| 導入形態 | 費用相場 | 特徴 | 適したケース |
| クラウド型 | 月5万〜30万円 | 低コスト・即導入可 | 小規模現場、特定業務の効率化 |
| 自社開発型 | 500万〜数千万円 | 高度なカスタマイズ | 全社的なDX推進、大規模プロジェクト |
| PoC型 | 50万〜300万円 | リスク最小化 | 本格導入前の効果検証 |
建設業におけるAI導入のROIを考える
AI導入の検討では「費用はいくらかかるか」と同時に、「どれだけの効果を得られるか」を見極めることが欠かせません。費用対効果(ROI:Return on Investment)を把握することで、導入の意思決定がより現実的になります。
人件費削減効果
建設現場では、進捗管理や安全管理、検査作業に多くの人員が割かれています。
- 例:AIカメラによる安全監視を導入することで、1人あたり月20時間の監視業務を削減できれば、年間で数百万円規模の人件費削減につながります。
工期短縮・品質向上
AIによる施工シミュレーションや資材発注の最適化は、工期短縮と品質安定化に直結します。
- 工期が1割短縮されれば、その分の人件費削減に加え、追加案件を受注できるチャンスも増加。
投資回収期間の目安
ROIをシンプルに計算する式は以下です。
ROI(%)=(効果額-投資額)÷投資額×100ROI(%)=(効果額-投資額)÷ 投資額 × 100ROI(%)=(効果額-投資額)÷投資額×100例えば、導入費用500万円に対し、年間の人件費・工期短縮効果が700万円であれば、ROIは40%。投資回収期間(Payback Period)は約1年弱で見込めることになります。
数字で示す説得力
AI導入は「便利そうだから導入する」では社内稟議が通りにくいのが実情です。ROIを数値で示し、「費用はこれだけ、効果はこれだけ」と明確にすることで、経営層の合意形成もスムーズになります。
AI導入による離職防止と定着率向上
建設業界では人材不足が大きな課題となっていますが、その要因のひとつが高い離職率です。過重労働や安全面の不安が残る現場環境では、せっかく採用した人材が定着せず、採用コストや教育コストが無駄になってしまうケースも少なくありません。
AIを導入することで、作業の自動化や安全管理の高度化、業務の標準化 が可能になり、現場の負担が軽減されます。その結果、社員の働きやすさや安心感が高まり、離職率の低下につながります。
人材定着は単なる「働きやすさ」だけでなく、採用コスト削減や技能の蓄積による生産性向上 に直結します。AI導入は費用削減や業務効率化に加え、長期的な人材戦略の観点からも投資価値があるといえます。
関連記事:
建設業の人材定着をAIで実現|離職防止と効率化を両立する最新戦略
補助金・助成金を活用してコストを抑える方法
AI導入は初期投資が大きくなりがちですが、IT導入補助金やものづくり補助金 といった国の制度を活用すれば、費用の一部を補填できます。
また、労働環境改善に取り組む企業を支援する助成金もあり、最大で導入費用の1/2程度が補助されるケースもあります。
補助金は申請要件やスケジュールが複雑なため、専門家に相談しながら活用を検討するとスムーズです。
費用を最適化する導入ステップ
AI導入は、一度に大規模投資をするのではなく、段階的に進めることで費用対効果を高められます。以下のステップを意識すると、無理のない投資で成果を実感しやすくなります。
ステップ1:小規模導入からスタート
- AIカメラや積算システムなど、効果が測定しやすい領域に限定して導入。
- 初期費用を抑えながらROIを確認でき、社内の理解促進にもつながります。
ステップ2:効果測定と改善
- 導入後は必ず「削減できた工数」「短縮できた工期」「削減できたコスト」を数値化。
- 成果をデータで示すことで、追加投資の根拠が明確になります。
ステップ3:段階的な全社展開
- PoCでの成果を踏まえ、対象業務を拡大。
- 部署横断的に導入する際は、既存システムとの統合や標準化を進めることでコストの重複を防ぎます。
ステップ4:人材育成と研修
- AIツールは導入するだけでは十分な効果を発揮できません。
- 社員が現場で使いこなせるよう、AIリテラシー研修を組み合わせることが不可欠です。
- 運用体制を強化することで、長期的なコスト削減と生産性向上につながります。
ポイントは「スモールスタート → 効果検証 → 拡張」の流れを確実に踏むこと。
これにより、初期費用を最小限に抑えつつ、投資効果を最大化できます。
関連記事:建設業×AIで業務効率化|施工管理・事務処理を変える導入ステップと研修活用法
\ 建設会社も含めた、生成AI活用の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
費用感を正しく把握し、投資判断を最適化する
建設業でAIを導入する際には、初期費用や運用コストだけでなく、データ整備や人材育成といった隠れたコストまで見据えて計画することが重要です。導入形態によって数十万円から数千万円まで幅広い費用がかかりますが、ROIを正しく算出し、補助金を活用すれば投資回収を現実的に進められます。
成功のポイントは、スモールスタートで効果を検証し、段階的に導入範囲を拡大していくことです。これにより無駄なコストを抑えながら、確実に成果へつなげられます。
AIは単なる費用ではなく、将来的な利益と競争力を生む「投資」として捉えるべきものです。費用感を正しく理解し、最適なステップで導入を進めることが、建設DXを成功させる近道となります。
導入コストを正しく把握し、投資効果を最大化するには社内の知識強化が欠かせません。SHIFT AI for Bizの法人研修では、最新ツールの使い方からリスク管理、導入プロセスまでを実践的に学べます。
一緒に成功の第一歩を踏み出しましょう。
また下記のリンクからは、建設会社によるRAG(生成AIと社外秘データを組み合わせる技術)実装を支援した事例を含めた、生成AI活用の様々な取り組み17選をまとめた事例集をダウンロードいただけます。自社と似た課題感を持つ会社が、どのようにAIを活用しているのか知りたい方はお気軽にご覧ください。
\ 建設会社も含めた、生成AI活用の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
建設業のAI導入費用に関するよくある質問
- Q建設業でAIを導入する場合、最小の費用はいくらから可能ですか?
- A
小規模なクラウド型サービスであれば、月額5万円前後から始められるケースがあります。AIカメラや施工管理支援ツールなど、部分的に導入する形なら低コストでのスタートが可能です。
- Q自社開発とクラウド利用では、費用にどのくらい差がありますか?
- A
クラウド利用は月数万円〜30万円程度で運用できる一方、自社開発は数百万円〜数千万円規模になる場合があります。導入範囲とカスタマイズ性の違いが費用差につながります。
- QAI導入後のランニングコストには何が含まれますか?
- A
主に以下が挙げられます。
- クラウド利用料
- システム保守・サポート費
- 社員研修や人材育成にかかる費用
これらを含めた年間コストを把握することが重要です。
- クラウド利用料
- Q費用対効果(ROI)はどうやって算出すればよいですか?
- A
基本式は以下の通りです。
ROI(%)=(効果額-投資額)÷投資額×100ROI(%)=(効果額-投資額)÷ 投資額 × 100ROI(%)=(効果額-投資額)÷投資額×100
人件費削減や工期短縮による利益増を「効果額」として算出すると、投資回収の見込みを明確にできます。