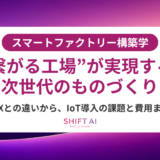「市役所のDXが進まない」
その根本的な理由は、システムではなく「人」にあります。
どれだけ最新のデジタルツールを導入しても、それを活かせる職員がいなければ、庁内の業務改革は形だけで終わります。
多くの自治体がいま直面しているのは、次のような課題です。
- 「DX=IT導入」と捉えられ、現場が主体的に動けない
- 一部の担当者に業務が集中し、全庁的な推進につながらない
- 研修を実施しても、知識が定着せずやりっぱなしで終わる
つまり、市役所DXの本当の壁は「人材育成の仕組みがないこと」なのです。
総務省も「デジタル人材の確保・育成」をDX推進の最優先課題に掲げていますが、実際の現場では「どの層に」「どんなスキルを」「どんな順序で育てるべきか」が明確でないケースがほとんどです。
その結果、「DX推進担当はいるが、全庁が動かない」という構造的な停滞が生まれています。
本記事では、市役所職員が自走的にDXを推進できるようになる人材育成体制のつくり方を、実務レベルで解説します。組織設計、研修体系、スキルマップ、そして継続的な定着の仕組みまでを段階的に整理し、「研修で終わらせないDX人材育成」の具体像を描きます。庁内のDXを本気で進めたい担当者にとって、この記事が変革の設計図となるはずです。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ市役所DXには人材育成が欠かせないのか
市役所のDX推進が難航する最大の理由は、デジタル技術よりも「人の意識と組織構造」が変わっていないことにあります。国が掲げる「自治体DX推進計画」では、技術導入よりもまず「人材の確保・育成」を最優先課題と位置づけていますが、現場ではその重要性がまだ十分に浸透していません。
DXとは単なるツールの導入ではなく、業務の考え方・進め方を抜本的に変える文化変革です。その文化を支えるのが、人材育成です。
人材育成が機能していないと、どんなに優れたシステムを導入しても成果は一時的で終わります。逆に、DXの目的や価値を理解し、自ら動ける職員が増えれば、庁内全体の改善サイクルが自走し始めます。ここからは、なぜ人材育成がDXの「前提条件」になるのかを具体的に見ていきましょう。
技術ではなく「人」がDXを止めている
庁内でDXが進まない理由の多くは、システムの問題ではなく人の構造の問題です。次のようなケースはどこの自治体でもよく見られます。
- DX担当が少数に固定され、現場が巻き込まれない
- 管理職が変革の必要性を理解していない
- 研修を実施しても、実務に結びつかない
- 現場の成功体験が共有されず、改善が続かない
これらは、組織的な学びが循環していない状態です。DXを動かすには、一人の専門家ではなく、庁内全体がデジタルに強い文化を持つことが必要です。
実際、総務省の「デジタル人材育成ガイドブック」でも、自治体のDX推進を持続させるには全庁的な学びと役割の明確化が鍵だとされています。
DX人材育成が生む「持続する仕組み」
DX人材育成の真価は、単なるスキルアップではありません。職員一人ひとりが自ら課題を発見し、改善を提案・実行できる仕組みを庁内に生み出すことにあります。
以下の表は、「人材育成を行わない自治体」と「体系的に育成を行っている自治体」の違いを整理したものです。
| 観点 | 育成を行っていない自治体 | 育成を体系化している自治体 |
| DX理解 | 一部職員のみが理解 | 全庁的に共通言語を持つ |
| 業務改善 | 個人依存・断続的 | チームで継続的に改善 |
| 研修 | 単発型 | 段階的・職層別 |
| 成果 | 一時的な効率化 | 継続的な業務変革 |
この違いが、プロジェクトで終わるDXと文化として根付くDXの分岐点です。市役所が本当の意味でデジタル化を果たすには、まず「人を育てる仕組み」を整備しなければなりません。
市役所DX人材に求められる3タイプの職員像
DXを本格的に進めるには、「誰を育てるのか」を明確にすることが出発点です。市役所には多様な職員がいますが、全員が同じ方向を向くためには役割ごとの人材像を定義し、育成の重点を分けることが欠かせません。
DXを推進できる組織には、目的と役割の異なる3つの人材タイプがバランスよく存在します。ここでは、その3タイプと育成の方向性を整理します。
推進リーダー型:庁内を横断して変革を導く人材
市役所DXの推進には、全庁を俯瞰しながら調整・企画を担う「推進リーダー型」が不可欠です。彼らは単にプロジェクトを進めるだけでなく、組織を巻き込み、職員の意識を変える推進の軸となる存在です。
求められる主なスキルは次の通りです。
- DX戦略・施策を庁内に伝えるファシリテーション力
- 部署間調整・課題抽出・ロードマップ設計力
- トップマネジメントとの合意形成・説明責任を果たす力
推進リーダーは、DXの旗振り役として組織全体の方向性を示します。彼らの育成は、「庁内全体の文化変革をリードする力」を育てることに直結します。
専門スキル型:データと技術を使いこなす実践人材
次に求められるのが、データ・AI・システムを活用し、実際に業務変革を設計・実装できる「専門スキル型」です。
この層がいなければ、企画されたDX構想は実行段階で止まってしまいます。
必要なスキル領域の例:
- データ分析・可視化・業務改善提案
- AI・RPA・クラウドなどの活用知識
- セキュリティ・ガバナンス理解
ただし、専門性だけに偏ると「現場から浮く」リスクがあります。したがって、現場理解+技術活用力を両立した実務エンジニア型職員を育成するのが理想です。
実務改革型:現場から改善を積み重ねる人材
最後の層は、日々の業務を通して小さなDXを積み重ねる「実務改革型」です。この層が自ら課題を見つけ、ツールを活用して業務を改善できるようになると、DXは一部部署ではなく庁内文化として浸透していきます。
具体的には、次のような動きが理想です。
- 現場業務をデジタルで可視化し、無駄を削減
- チーム単位で改善を共有し、ノウハウを庁内に展開
- 小さな成功体験を蓄積し、意識改革を促進
こうした草の根DXを支援するために、研修ではツール操作よりも課題発見・改善提案のスキルを重点的に学ぶことが重要です。
この3タイプの人材が有機的に連携することで、DX推進体制は初めて機能します。
次の章では、それぞれの人材をどのような手順で育て、定着させていくのかを実践ロードマップとして整理します。
市役所DX人材育成の全体像(ロードマップ)
市役所DX人材の育成は、単発の研修や座学では完結しません。「意識改革から実践・定着までを一気通貫で設計すること」が成功の鍵です。
DXを進める自治体ほど、人材育成を「教育」ではなく「組織を動かす仕組み」として設計しています。ここでは、市役所がDX人材育成を体系的に進めるための5ステップを整理します。
ステップ①:庁内のDX成熟度を診断する
まず必要なのは、現状を正確に把握することです。どの部署が強みを持ち、どこに遅れがあるのかを把握しなければ、研修や体制設計が的を外します。
診断では、職員のDXリテラシー水準、部署間のデータ連携状況、トップ層と現場の温度差、育成や評価の仕組みなどを整理し、庁内の「現状スコア」を可視化します。この工程を踏むことで、次のステップで描く育成ロードマップが現実的で実行可能なものになります。
ステップ②:職層別・スキル別に育成方針を策定する
次に取り組むべきは、「誰に」「どのスキルを」「どの深さで」育てるかの整理です。全職員を一律に研修するよりも、職層ごとに目的を分けて設計したほうが圧倒的に効果が上がります。管理職にはDX戦略や合意形成力を、中堅職員には実務改善やプロジェクト推進力を、一般職にはツール活用や課題発見力を重視した研修を実施します。
| 職層 | 主な役割 | 育成の狙い |
| 管理職層 | 推進リーダー・方針決定 | DX戦略立案・組織設計・合意形成 |
| 中堅職員層 | 実務改革リーダー | プロジェクト設計・改善推進 |
| 一般職層 | 現場実践者 | ツール活用・課題発見・改善提案 |
このように層ごとに目的を明確化し、「階層別×スキル別」のマトリクス型育成計画を設けることで、研修が庁内全体に波及していきます。
ステップ③:段階的な研修体系を設計する
職層ごとの方針が固まったら、次は研修を意識改革・スキル習得・実践の3段階構造で設計します。フェーズ1ではDXの目的と意義を共有し、庁内で共通言語を形成。フェーズ2では、AI・データ活用・業務改善といったスキルを実務に即して学びます。フェーズ3では、庁内課題をテーマにしたプロジェクト型研修を実施し、「学び→実践→共有」の循環をつくります。重要なのは、受講後に終わらせず、行動と振り返りを組み込む仕組みを並行して作ることです。
ステップ④:OJTと内製化による定着を図る
学んだ知識は、現場で使われて初めて意味を持ちます。研修で得た知見を庁内に定着させるには、OJT(On-the-Job Training)と内製化の仕組みが重要です。
部署単位で小規模なDXプロジェクトを設定し、実務を通じて職員が経験を積み、成果を庁内共有会などで可視化することで、成功体験が横展開されます。外部パートナーとの伴走支援を組み合わせると、スキルが個人ではなく組織として蓄積されるようになります。
ステップ⑤:成果を測り、改善サイクルを回す
最後に、育成の成果をKPI・KGIで見える化し、改善を繰り返します。研修参加率やDX提案件数といったKPIを設定しつつ、最終的には「DXプロジェクトの自走率」「業務効率化」「住民満足度向上」といったKGIに紐づけて評価します。このプロセスがあることで、職員が「やりっぱなしにしない文化」を維持でき、育成体制が年々成熟していきます。
庁内全体でDX人材を育てるための仕組み設計
個々の研修でスキルを高めるだけでは、DXは一過性で終わります。市役所全体が継続的にデジタル化を進めるには、「人材育成を組織運営に組み込む仕組み」が欠かせません。これは、DXを特定の部署や担当者の課題ではなく、庁内全体の共通ミッションとして機能させる仕組みでもあります。ここでは、組織としてDX人材を育て続けるための3つの柱を紹介します。
職層別スキル定義で「DXを自分ごと化」させる
DX推進を庁内で浸透させる第一歩は、職層ごとに求められるスキルと役割を明確化することです。役割が曖昧なままだと、「DXは専門部署の仕事」と捉えられ、現場の当事者意識が育ちません。
職層別スキル定義を策定することで、各職員が「自分がDXのどの部分に貢献できるか」を具体的に理解できます。たとえば、管理職は推進体制を設計し、現場職員は業務改善を実行する、といったように、役割を明確に分担することで庁内全体の推進力が上がります。
| 職層 | DXにおける主な役割 | 育成の重点 |
| 管理職層 | 戦略立案・推進方針策定 | 意識改革・リーダーシップ強化 |
| 中堅職員層 | プロジェクト推進・改善設計 | チーム推進・データ活用力 |
| 一般職層 | 現場改善・業務効率化 | 課題発見・デジタルツール運用 |
このように職層別スキルを明文化することが、「誰もがDXに関わる」文化の第一歩になります。
研修と実践を循環させる「学びの仕組み」を作る
DX人材育成で最も失敗しやすいのは、「研修をやって終わり」になるケースです。知識を得ても実践の場がなければ、学びは定着しません。したがって、研修→実践→共有→改善のサイクルを組織的に設計することが重要です。
具体的には、研修後すぐに庁内課題をテーマにした改善活動を設定し、成果を共有会などで発表する形式が効果的です。こうすることで、学びが個人に閉じず庁内で共有され、他部署への展開が促されます。また、改善活動を評価制度に反映することで、「学ぶほど評価される文化」を醸成できます。
学びを庁内に還元するナレッジ共有体制を整える
DXを推進するうえで、最も価値があるのは「職員が現場で得た知見」です。この知見を庁内全体に共有するナレッジ基盤を整えることで、DXが個人依存ではなく仕組みとして循環し始めます。
共有方法は大規模なシステム導入に限らず、グループウェアや庁内Wiki、Slackなどの簡易ツールで十分です。重要なのは、「失敗も含めて共有する文化」を育てること。成功例だけを集めると表面的な改善に留まりますが、失敗からの学びが共有されることで、庁内のDXはより実践的で強靭なものになります。
市役所DX人材育成のよくある課題と乗り越え方
DX人材育成の必要性を理解しても、実際に進める段階で多くの自治体が壁にぶつかります。その多くは制度設計よりも「現場の意識・組織の構造」に根差した課題です。ここでは、市役所が直面しやすい3つの代表的な課題と、それを乗り越えるための実践的な解決策を整理します。
課題①:DXが「IT導入」で止まってしまう
最も多い誤解が、DX=デジタルツールの導入と捉えてしまうケースです。実際には、DXは「技術の導入」ではなく「業務・文化の変革」です。ツールを導入しても、使う側の思考や業務フローが変わらなければ効果は一時的に終わります。
この課題を乗り越えるには、まず庁内で「DXの定義を共通化」することが不可欠です。たとえば、研修冒頭で「DXとは何を目的とするか」を整理し、各職員が自分の業務との関連を考えるワークを設けると、DXを自分ごととして捉えやすくなります。管理職層には戦略的視点を、現場職員には業務改善の視点を持たせることで、全庁で共通言語が形成されます。
課題②:研修を実施しても定着しない
研修を行っても、数ヶ月後には学びが忘れられてしまう。これは多くの市役所が直面する問題です。原因は、研修が実務と結びついていないことにあります。人は「必要な場面」で使わない知識を記憶に留めません。
解決策として有効なのは、研修と実践を一体化させる設計です。たとえば、研修直後に庁内課題をテーマにした小規模プロジェクトを設定し、参加者自身がそのテーマで実践する機会を作ります。さらに、改善の成果を庁内共有会で発表させることで、他部署への波及効果が生まれ、モチベーションも維持されます。
また、上司が進捗を確認し、成果を評価する仕組みを導入すると、「学びが評価される風土」が生まれます。
課題③:現場職員が「自分には関係ない」と感じてしまう
多くの自治体でDXが停滞する原因のひとつが、現場の当事者意識の欠如です。現場の職員が「DXは専門部署の仕事」と思っている限り、全庁的な変革は起こりません。
この課題を克服するには、小さな成功体験を積ませることが最も効果的です。たとえば、1部署単位で簡単な業務改善(フォーム自動化・データ整理など)を実施し、その成果を全庁会議で共有する。これが「自分たちでもできる」という自信につながり、他部署にも波及します。
また、成功事例だけでなく「失敗事例」も共有することで、DXが挑戦を評価する文化として定着します。
これら3つの課題を乗り越えるための共通ポイントは、「教育」と「実践」を切り離さないことです。学びを現場で活かす仕組みを設ければ、DX人材育成は短期的な施策から、庁内文化として根付く変革へと進化します。
DX人材育成を「一過性」ではなく「自走型」へ変えるには
DX人材育成を成功させたとしても、「仕組みが継続しない」ことが最大の落とし穴です。多くの自治体では、年度単位の研修で終わり、翌年には担当者が変わってノウハウが途切れてしまいます。DXを一過性の施策で終わらせないためには、人材育成を仕組みとして自走する体制に転換することが欠かせません。ここでは、そのための3つの視点を整理します。
継続的に学び続ける「DX文化」を醸成する
DXは一度学べば完了するものではなく、変化し続ける環境の中で学び続ける姿勢が求められます。庁内においても、「DXは特定のプロジェクトではなく、日常業務の中にある」という意識を育てる必要があります。
そのためには、年に数回の座学研修だけでなく、学びを日常化する仕掛けが効果的です。
たとえば、定期的に庁内でDX共有ミーティングを開催し、各部署の改善事例を共有する。これにより、職員同士の刺激が生まれ、「学びが自然に続く文化」が育ちます。また、庁内ポータルなどでDXナレッジを共有し、だれでも参照できる環境を整えることで、情報の属人化を防げます。
内製化と外部支援のハイブリッドを設計する
DX人材育成を長期的に続けるためには、外部支援に頼りきらず、内製化とのバランスを取ることが重要です。
最初のフェーズでは専門機関や外部パートナーの支援を受けながら、庁内にナレッジを蓄積。その後、庁内職員が講師役やファシリテーターとして研修を運営できるように移行します。
この「外部支援→共創→内製化」という流れを意識することで、コストを抑えながらも持続的にスキルを広げられます。
また、AIツールの活用も内製化を後押しします。たとえば、AIチャットによる業務相談窓口や、生成AIを活用した文書作成トレーニングを導入することで、職員自身が教え合い・学び合う循環が生まれます。
組織として「人材育成を更新し続ける仕組み」を持つ
DXの世界は日々進化しており、数年前の知識がすぐに陳腐化します。したがって、人材育成そのものを更新し続けるメカニズムを持つことが、自治体DXの持続性を左右します。
そのためには、年度ごとに研修内容を見直すPDCA体制を明文化し、庁内でデータをもとに成果を分析する仕組みを作ることが重要です。研修満足度ではなく、改善提案件数・導入率・定着率など「行動変容を測るKPI」を設定し、次年度の育成計画に反映させる。これにより、庁内全体が「成長する組織」として進化していきます。
まとめ|市役所DXを動かすのは「人材育成体制の設計」から
市役所のDXは、システム導入や業務効率化といった目に見える成果だけでは長続きしません。真に変化を生み出すのは、人を育て、学びを仕組みとして循環させる体制づくりです。DX推進の本質は、技術ではなく「人」と「文化」を変えることにあります。
ここまで紹介してきたように、DX人材育成を成功させるためには、庁内の成熟度を見える化し、職層ごとのスキル定義を行い、研修・実践・評価のサイクルを継続的に回すことが欠かせません。さらに、外部支援と内製化をバランスよく組み合わせ、学びを庁内に蓄積していくことで、DXは一過性のプロジェクトから自走する文化へと変わっていきます。
市役所DXの未来を左右するのは、どれだけ優れたツールを導入するかではなく、どれだけ自ら考え行動できる職員を増やせるかです。DX人材育成は、庁内の意識改革と構造変革を同時に進めるための最も確実な手段です。
よくある質問(FAQ)|市役所DX人材育成の疑問を解消
- QQ1. DX人材育成はどのくらいの期間で成果が出ますか?
- A
DX人材育成は、短期間で完結するものではありません。一般的に、基礎的な意識改革とスキル定着までに6〜12か月、組織全体に浸透するまでに2〜3年を要します。
ただし、研修だけでなく実践プロジェクトを並行して進めることで、早期に成果を見える化することは可能です。たとえば、1年目にパイロット部署で改善活動を実施し、2年目以降に庁内全体へ展開する形が現実的です。重要なのは、成果を数値と行動の両面で追うことです。
- QQ2. 予算が限られている中で、どこから始めるべきですか?
- A
限られたリソースで進める場合は、庁内のキーパーソン育成に集中するのが最も効果的です。最初から全庁展開を狙うのではなく、推進リーダー層や中堅職員に焦点を絞って研修・実践を行い、その結果を庁内に共有する。これにより、効果を見せながら徐々に予算・体制を拡大していくことができます。
また、外部パートナーの無料相談やオンライン研修など、初期コストを抑えながら着手する方法も増えています。
- QQ3. DX人材の採用と育成、どちらを優先すべきですか?
- A
理想的なのは両輪で進めることですが、自治体の場合は「育成」を優先すべきです。外部採用だけに頼ると、庁内文化とのギャップが生じやすく、定着に時間がかかります。
一方で、内部職員の育成は現場理解が深く、既存の業務知識を活かした改善が可能です。外部専門人材は伴走者として位置づけ、内部職員が主体的に動ける体制をつくることが理想的です。
- QQ4. DX研修を受けた職員が異動した場合、効果はどうなりますか?
- A
自治体特有の課題がこの「人事異動によるノウハウ断絶」です。解決のカギは、ナレッジ共有と育成体系の仕組み化にあります。
研修内容・成果・改善プロセスを庁内ポータルや共有ドキュメントに蓄積し、誰が異動しても引き継げる環境を整えることが重要です。加えて、異動先でもDX活動を継続できるよう、庁内全体で「学びを持ち運べる文化」を作ることが効果的です。