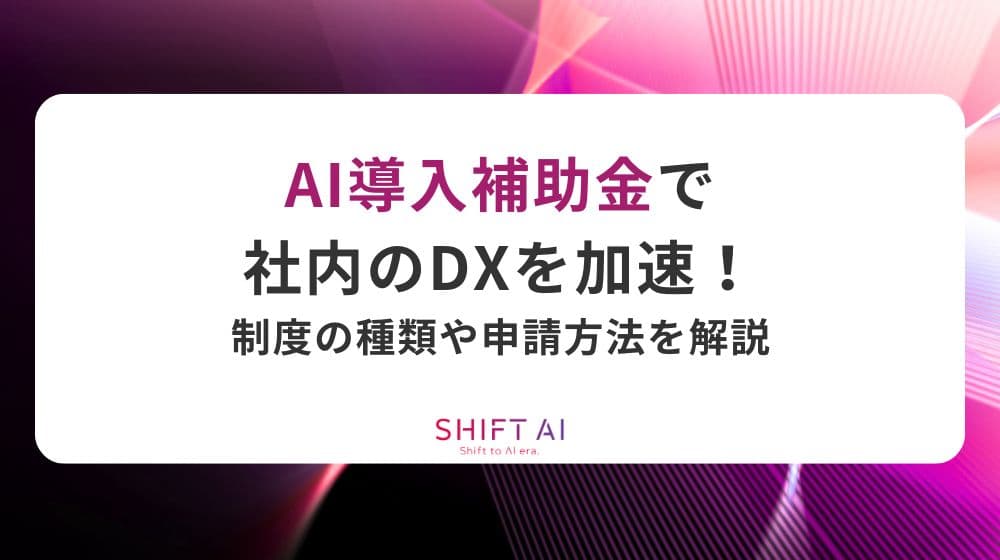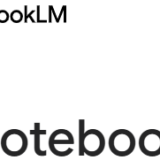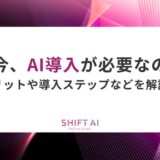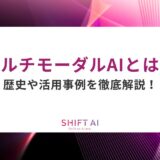AI(人工知能)の導入は企業の競争力を左右する重要なテーマです。近年では、国や地方自治体がAI導入を後押しする施策を充実させており、多くの企業がAI導入補助金を活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の動きを示しています。
この記事では、AI導入補助金の基本から申請方法、活用事例まで、企業のDX担当者が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。AI導入による業務効率化を実現するためにも、本記事でAI導入補助金について学んでいきましょう。
AI導入補助金の活用を検討し始めたものの、「どの制度が自社に合っているかわからない」「事業計画書の作成に自信がない」といった課題を抱えている方は、SHIFT AIの無料相談をご利用ください。貴社に最適な補助金選びから申請サポートまで、経験豊富なコンサルタントが伴走支援致します。
また、組織としてのAI活用についてお悩みの方に向けて、AIを導入だけで終わらずに成功に導くために必要な考え方を5つのステップ別に整理した資料をご用意しております。「どう進めたらいいかわからない」という方はお気軽にご覧ください。
\ AI導入を成功させ、成果を最大化する考え方を学ぶ /
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
AI導入補助金とは

AI導入補助金は、企業がAI技術を導入する際に国や地方自治体から受け取ることができる資金的支援です。
AIツールの購入やAIシステム開発など、AI導入によるさまざまな費用に対して一部が補助されます。また、受け取った導入補助金は返済が不要。国はAI技術の社会実装を進める国策として、特に中小企業のAI活用を積極的に支援しているのです。
経済産業省は、AI開発に不可欠な計算資源(GPUクラウドサービスなど)の国内整備を支援するため、国内IT企業に対し最大725億円規模の助成を決定するなど、AIへの投資を強化しています。
AI導入補助金の対象となる経費の種類

AI導入補助金で対象となる経費は補助金制度によって異なります。一般的に幅広い費用がカバーされているため、どのような費用が補助金の対象になるかを事前に確認しておくことが重要です。
ここでは、費用の補助対象について詳しく見ていきましょう。
AIシステム導入費・機械装置費
まず挙げられるのは、AIソフトウェア本体の購入費用です。購入費用にはクラウド型のAIサービス利用料やパッケージソフトウェアの購入費が含まれます。
例えば、AIチャットボットシステムやAI画像認識ソフトウェアなどが該当します。また、AIシステムを稼働させるために必要なサーバー、センサー、ロボットなどのハードウェア費用も補助の対象となるケースが多いです。
工場でのAI活用においては、画像認識カメラやIoTセンサーなどのデバイス費用も含まれることがあります。
AIシステム構築費・開発費
AIシステム構築費・開発費の対象には、次のような費用があります。
- AIモデルの開発費用
- 既存システムとの連携費用
- データの前処理
- 学習に必要なクラウドサービスの利用料
既存のAIソリューションをそのまま導入するだけでなく、自社向けにカスタマイズしたり、独自のAIモデルを開発したりする費用も補助金の対象です。
また、自社の顧客データを使った予測モデルの構築や特定業務向けのAIアルゴリズム開発にかかる費用も含まれます。生成AIを自社業務に適応させるためのファインチューニング費用が対象になるケースも増えています。
外注費・コンサルティング費
AI技術の専門家へのコンサルティング費用や、システム開発を外部業者に委託する費用も補助の対象です。
中小企業では、AI人材の確保が難しいことも少なくありません。外部の専門家に依頼する費用の補助は大きなメリットといえるでしょう。
AI導入のための要件定義や設計、AIシステムの開発を検討中の方は、補助金を活用して外部の専門家に依頼することをおすすめします。
知的財産権関連経費・その他
ソフトウェアやハードウェア以外の費用も見てみましょう。
- 開発したAIアルゴリズムの特許申請費用
- AI関連の研修費用や導入サポート費用
- 社員向けのAIツール教育研修費用
- AI導入に伴う社内体制の整備費用
- AI開発のためのデータ収集・整備・加工費用
- システム連携のためのAPI利用料
これらの費用も、補助金制度によっては対象として認められる可能性があります。事前に申請の内容を確認しておくことが重要です。
【2025年】AI導入におすすめの補助金制度5選

AI導入を対象とした補助金制度は複数あり、それぞれ目的や対象、支援内容が異なります。ここでは、2025年に活用できるおもなAI導入の補助金制度を5つ紹介します。
| 補助金制度 | おもな目的/AI活用例 | 対象事業者 | 補助上限額(代表例) | 補助率(代表例) | AI関連のおもな対象経費 |
| IT導入補助金 | 業務効率化、DX推進、AIチャットボット導入など | 中小企業・小規模事業者 | 通常枠:最大450万円 | 1/2(特定条件により、2/3または3/4) | ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年)、導入関連費 |
| ものづくり補助金 | 革新的サービス・試作品開発、AI組込み製品開発、品質管理AIなど | 中小企業・小規模事業者 | 成長分野進出枠(DX・GX):最大2,500万円(特例により、最大3,500万円) | 2/3 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、クラウド利用料 |
| 中小企業省力化投資補助金 | 人手不足解消のための省力化投資、AI搭載ロボット導入など | 中小企業等 | カタログ型:最大1,000万円(特例1,500万円) | 1/2 | カタログ登録AI製品、AIデータ分析システム、顧客対応自動化AI |
| 新事業進出補助金 | 新市場進出、事業転換、AI活用新サービス開発など | 中小企業等 | 最大7,000万円(特例9,000万円) | 1/2 | AIシステム導入費、AI開発クラウド利用費、外注費(専門家) |
| 小規模事業者持続化補助金 | 販路開拓、生産性向上、AIマーケティングツール導入など | 小規模事業者 | 通常枠:50万円特定枠:最大200万円 | 2/3(特定条件3/4) | 機械装置費、広報費、ウェブサイト関連費、開発費 |
各制度の詳細をひとつずつ見ていきましょう。
IT導入補助金
IT導入補助金は中小企業や小規模事業者の生産性向上を目的として、ITツールの導入費用を支援する制度です。AIチャットボットやAI搭載の業務ソフトなども補助対象となり、比較的申請のハードルが低いことから、AI導入の第一歩として活用しやすいのが特徴です。
2025年度のIT導入補助金では、通常枠の場合、導入するITツールがカバーする業務プロセスの数に応じて、補助額は5万円から最大450万円までとなります。補助率は原則1/2ですが、一定の賃金要件を満たす事業者は2/3に拡充されます。
申請には「IT導入支援事業者」と呼ばれる、事務局に登録された事業者との連携が必要です。IT導入支援事業者がサポートしてくれるため、補助金申請に不慣れな企業でも比較的取り組みやすいでしょう。
ものづくり補助金
ものづくり補助金(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業や小規模事業者などが行う革新的なサービス開発や試作品開発、生産プロセス改善などに必要な設備投資を支援する制度です。
2025年度は、成長分野進出類型(DX・GX)において、補助上限額は最大2,500万円、補助率は2/3と手厚い支援が受けられます。
事業計画の革新性、実現可能性、具体的な生産性向上の数値目標が厳しく審査されるため、申請準備には相応の計画と労力が必要です。
中小企業省力化投資補助金
中小企業省力化投資補助金は、深刻化する人手不足に対応するため、中小企業などがIoT、ロボット、AIなどの技術を導入する経費を補助する制度です。中小企業省力化投資補助金には「カタログ型」と「一般型」の2つの類型があります。
- カタログ型:あらかじめ事務局に登録された省力化製品(AI搭載システムなどを含む)から選んで導入
- 一般型:事業者の個別の状況に合わせたオーダーメイドのシステム導入に利用可能
補助上限額はカタログ型で最大1,000万円(大幅な賃上げ特例適用時は1,500万円)。一般型の場合は、最大8,000万円(特例適用時は1億円)です。
人手不足解消という明確な目的に特化しており、課題解決に直結するAI導入計画が評価される傾向にあります。
新事業進出補助金
新事業進出補助金(旧:事業再構築補助金)は、ポストコロナの経済社会変化に対応するための制度です。中小企業が新市場への進出、事業・業種転換、事業再編といった事業再構築に挑戦する取り組みを支援します。
AI技術を活用した新規市場の開拓や、新たなAIサービスの開発が補助金の対象です。補助上限額は最大で7,000万円(大幅な賃上げを行う特例適用時は最大9,000万円)、補助率は原則1/2となっています。
新事業進出補助金は大規模な事業転換や新規事業開発を伴うAI導入に適しており、事業計画の新規性、成長性、実現可能性が厳しく審査されます。計画策定には十分な時間と労力が必要ですが、大胆なAI活用による事業変革を目指す企業には強力な支援となるでしょう。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の持続的な経営を支援するため、自ら策定した経営計画に基づく販路開拓や生産性向上の取り組みに必要な経費の一部を補助する制度です。
AI技術を活用したマーケティング活動の強化やECサイトの最適化による販路拡大が対象となります。通常枠の上限は50万円。賃金引上げ枠・創業枠により最大200万円まで補助を受けられます。
他の補助金制度と比較すると補助上限額は低めですが、小規模事業者が取り組みやすい内容といえます。申請手続きも比較的簡素であり、初めて補助金を利用する事業者にも挑戦しやすいのが特徴です。
東京都のAI導入補助金
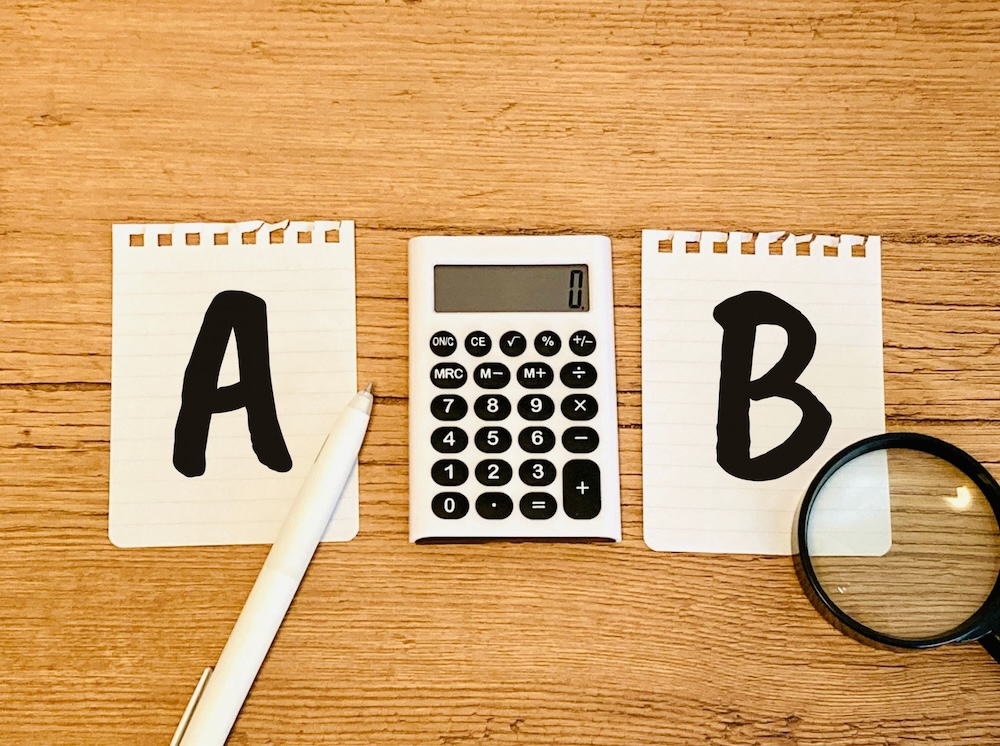
国の補助金に加えて、各地方自治体も独自の支援策を展開しています。特に東京都は、中小企業におけるAI技術の導入を積極的に支援しており、さまざまな補助金・助成金制度を用意しています。
東京都の補助金は国の制度と比較して競争率が比較的低い傾向にあるとされ、都内企業にとっては利用しやすい制度です。
ただし、これらの制度は年度によって内容が変更されたり、公募期間が限られていたりする場合があります。申請を検討される際は、必ず東京都や関連機関の公式サイトで最新の公募要領や詳細情報をご確認ください。
※ここで紹介する補助金の中には、すでに受付を終了しているものも含まれています。
革新的事業展開設備投資支援
革新的事業展開設備投資支援事業は、AIやIoT、ロボットなどの先端技術を活用して、競争力強化や生産性向上を目指すための設備投資やシステム導入を支援する事業です。
補助上限額は最大1億円と高額で、機械装置やソフトウェアの導入費用が対象です。申請には東京都内で2年以上の事業継続実績などの要件があります。
国の補助金と比較して申請要件が明確で、東京都の産業振興施策に合致した事業であれば採択される可能性が高まるのが特徴です。
デジタル技術を活用した先進的サービス創出支援事業
先進的サービス創出支援事業の目的は、都内の中小企業などがデジタル技術を駆使して、自社にとって全く新しいサービスの開発や、既存サービスの提供方法を刷新するような「先進的なサービスの事業化」を後押しすることです。単に新しい技術を導入するだけでなく、それをビジネスとして確立させる段階までを視野に入れた支援が特徴です。
例えば、過去の募集では助成限度額が最大2,000万円、助成率は対象経費の2/3以内といった条件が設定されていました。対象経費は、市場調査の委託費、システムの開発・導入費、専門家への依頼費用、販路開拓のための広告宣伝費などが挙げられます。
中小企業デジタルツール導入促進支援
中小企業デジタルツール導入促進支援事業は、都内中小企業者などが新たにデジタルツールを導入する際の経費を助成します。助成限度額は最大100万円、助成率は1/2(小規模企業者は2/3)です。
AIを活用した業務効率化ツールなども対象となる可能性があり、ハードウェア導入も一部対象となります。比較的小規模なAI導入から取り組みたい企業に適しています。
新製品・新技術開発助成
新製品・新技術開発助成事業は、実用化が見込まれる新製品・新技術の研究開発に係る経費を助成する制度です。助成限度額は最大2,500万円、助成率は原則1/2ですが、賃上げを実施した場合には優遇措置があります。
都内の地域課題解決や、東京都の重点産業分野におけるAI活用に関するプロジェクトは高く評価される傾向です。
AI導入補助金の申請から受給までの流れ

AI導入補助金を活用するためには、申請から受給までの一連の流れを理解し、計画的に進めることが重要です。
ここでは、一般的な申請から受給までの流れを紹介します。ただし、各補助金制度によって細部は異なるため、必ず公募要領で詳細を確認しましょう。
申請書類の準備と提出方法
補助金申請では、複数の書類を提出しなければなりません。
まず、自社の事業内容やAI導入計画に合致する補助金制度を探し、公募要領を熟読して必要な書類を把握します。一般的に、以下のような書類が必要です。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 経費内訳
- 確定申告書や決算書などの財務状況がわかる書類
- 会社の基本情報(登記事項証明書など)
- その他各制度で指定される書類
多くの場合、GビズIDプライムを利用した電子申請システム(例:Jグランツ)を通じて申請を行います。IT導入補助金の場合は、IT導入支援事業者と共同で申請内容を作成・提出します。
申請前の準備として、GビズIDプライムアカウントの取得、SECURITY ACTIONの宣言、みらデジ経営チェックの実施も必要です。特に、GビズIDプライムの取得には数週間かかる場合があるため、早めに準備を始めましょう。
審査・交付決定から事業実施
申請書類の提出後、補助金事務局による審査が行われます。
審査期間は補助金によって異なりますが、1〜3ヶ月程度かかるケースが一般的です。審査の結果、採択された場合は「交付決定通知」が送られてきます。
交付決定通知を受け取った後に、補助対象事業(AIツールの発注・契約・支払いなど)を開始します。交付決定前に発注・契約した経費は原則として補助の対象外となるため、必ず交付決定を確認してから進めましょう。
事業実施中は、契約書、発注書、請求書、領収書など、経費支出を証明する書類をすべて適切に保管しなければなりません。これらの書類は、後の実績報告でも必要です。
実績報告と補助金受給の手続き方法
事業完了後(全ての支払いが完了した後)、定められた期間内に事業実績報告書と経費支出の証拠書類を事務局に提出します。実績報告書には、実施した事業内容や得られた成果、支出した経費の詳細を記載していきます。
提出された実績報告書は事務局で確認・審査され、補助金額が確定します。通知を受け取った後、指定した口座に補助金が入金されたら手続き完了です。
多くの場合、補助金は後払い(精算払い)となるため、事業実施期間中の資金繰りには注意が必要です。補助金の入金までは事業完了から1〜3ヶ月程度かかることを想定しておきましょう。
審査に通る事業計画書の書き方

補助金審査において最も重視されるのが事業計画書です。審査員に「この事業は成功しそうだ」「税金を投入する価値がある」と納得させられる内容にすることが大切です。
目的・課題の明確化と数値目標を設定する
事業計画書で重要なのは、AIを導入する目的と解決したい経営課題を明確に示すことです。「AI技術が効率化できそうだから導入したい」といった曖昧な理由ではなく、自社の具体的な課題とAIによる解決方法を論理的に説明する必要があります。
例えば、以下のような設定をすると良いでしょう。
- 生産性向上:一人当たりの売上を20%向上
- コスト削減:外注費を年間300万円削減
- 品質向上:不良品率を3%から1%に低減
- 時間短縮:書類作成時間を1件あたり15分短縮
このように、具体的な数値で効果を示すことで、投資対効果が明確になり、審査での評価が高まります。
事業計画の具体化とスケジュール設定
審査員は、計画が実現可能かどうかも重視します。そのため、AIをどのように導入し、どのようなスケジュールで進めるのかを具体的に記述することが大切です。
計画の具体化には以下の要素を含めると良いでしょう。
- 導入するAI技術・ツールの具体的な内容と選定理由
- 実施体制(プロジェクトメンバーの役割、外部パートナーとの連携方法)
- 導入から運用までの詳細なスケジュール(できれば月単位や四半期単位)
- 各マイルストーンで達成すべき目標
- 予想される課題とその対応策
過度に短期間での実現を目指す計画よりも、着実に進められる堅実な計画のほうが信頼性が高く評価されます。
審査員の目を引く効果的な表現
多くの審査員は大量の申請書を短時間で確認するため、要点が分かりやすく、説得力のある表現を心がけることが重要です。
- 簡潔で分かりやすい文章を心がける
- 重要なポイントは太字やマーカーで強調する
- グラフや図表を用いて視覚的に説明する
- 専門用語は必要最小限にとどめ、使用する場合は簡単な説明を添える
- ビフォー・アフターの比較を明確に示す
例えば、人手不足解消、地域経済活性化、競争力強化といった政策的課題への貢献を示すことで、審査での評価が高まります。また、自社のAI導入が補助金制度の目的や国の政策方針と合致していることをアピールするのも有効です。
AI導入補助金申請のよくある失敗とその対策

ここでは、AI導入補助金を申請する際によくある失敗例とその対策を紹介します。補助金申請で思わぬところで不採択にならないよう、事前準備を整えていきましょう。
申請前の準備不足による不採択
補助金申請の前提準備が不十分なまま申請し、不採択となるケースが少なくありません。例えば、GビズID未取得、SECURITY ACTION未宣言など、申請前に必要な手続きを済ませていないことが原因で申請自体が通らないことがあります。
対策としては、公募要領を隅々まで確認し、申請前に必要な手続きをすべて完了させておくことです。特に、GビズIDプライムの取得には数週間かかる場合があるため、早めの準備が必要です。
また、AI導入の目的や効果に関する社内検討が不十分なまま申請すると、事業計画の説得力が低くなり不採択につながります。十分な社内議論を経て、明確な目的と効果を設定しましょう。
交付決定前の発注・契約による補助対象外
補助金の交付決定通知を受ける前に、AIツールや関連サービスを発注・契約してしまう失敗もよく見られます。
交付決定通知を受け取る前の発注・契約は原則として補助の対象外です。必ず交付決定を確認してから事業を開始(発注・契約)するようにしましょう。交付決定前の支出は自社負担となることを肝に銘じておく必要があります。
交付決定までのスケジュールも公募要領などで確認し、全体のプロジェクト計画に反映させることが重要です。
目的が曖昧な事業計画による審査落ち
具体的な経営課題の解決や事業目標の達成に結びつかない計画は不採択となりやすいです。先ほども触れましたが、「AIで効率化できそうだから導入したい」といった曖昧な事業計画では審査で高い評価を得られません。
対策としては、AIを導入する明確な理由と期待される効果を具体的に示すことです。特に数値目標の設定は重要であり、「〇〇の作業時間を△△%削減」「〇〇の精度を△△%向上」といった形で効果を定量化しましょう。
また、AI導入が自社の中長期的な経営戦略にどう位置づけられるかを明確にすることも大切です。
書類不備・期限切れによる申請無効
必要書類の不足、添付忘れ、期限切れによる申請無効も典型的な失敗例のひとつです。特に電子申請システムでは、アップロードミスや送信エラーのトラブルが発生するおそれもあります。
対策としては、公募要領に記載された提出書類のチェックリストを作成し、すべての書類を漏れなく準備することが大切です。申請期限に余裕をもった提出計画を立て、システムエラーなどの不測の事態にも対応できるようにしましょう。
電子申請システムの操作に不慣れな場合は、事前に操作方法を確認したり、IT導入支援事業者など専門家のサポートを受けたりすることも有効です。
\ AI導入を成功させ、成果を最大化する考え方を学ぶ /
AI導入補助金で活用できる導入事例を紹介

実際にAI導入補助金を活用して成功した企業の事例を見ることで、自社での活用イメージが湧きやすくなります。ここでは、業種や目的別のさまざまな成功事例を見てみましょう。
AIチャットボット導入によるIT導入補助金の活用
AIチャットボットを導入し、さらにIT導入補助金を活用することで、効果的に課題解決を図る企業が増えています。GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社が提供する、お問い合わせ対応AI導入支援サービス「GMO即レスAI」は、その好例と言えるでしょう。
「GMO即レスAI」は、2024年度に続き、2025年度の「IT導入補助金」の対象ツールとして認定されました。これにより、補助対象となる中小企業は「GMO即レスAI」を導入する際に、最大150万円未満(補助額5万円以上)の補助を受けられます(※交付には審査があり、利用内容により申請可能な補助金額は異なります)。
実際に、GMOペパボ社内では「GMO即レスAI」の前身となるAIチャットボットの導入により、5ヶ月間で業務時間を合計1,620時間削減するという顕著な業務効率化を達成しました。また、24時間の即時返答(一部有人対応を除く)が可能になったことなどから、顧客満足度も88%に向上した実績があります。
アイデミーが経済産業省の補助事業者に採択されデータサイエンス人材育成を推進
株式会社アイデミーは、2023年に経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の補助事業者に採択されました。
アイデミーはデータサイエンススキルを活かす職種への転職支援事業を展開し、デジタル人材のリスキリングを推進しています。
補助金を活用することで、個人の自己負担を軽減しながらデータサイエンスのスキルアップ支援を行い、日本のAI人材不足の解消に貢献しています。
\ 生成AIによる業務効率化の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
まとめ|補助金の制度を理解して、AI導入の不安を解消しよう

AI導入補助金は、中小企業のAI技術導入における初期投資の負担を軽減し、競争力強化を実現する強力な支援制度です。
2025年は多様な補助金が活用できる絶好の機会であり、IT導入補助金やものづくり補助金など、目的や規模に応じた選択肢があります。効果的な活用のためには、AI導入の目的を明確にし、自社に最適な補助金を選び、説得力のある事業計画を策定することが重要です。
なおSHIFT AIでは、企業のDX推進を支援し、補助金を活用したAI導入計画の策定から運用後のサポートまでを一貫して対応いたします。どのような補助金制度が自社に最適かを専門的な視点からアドバイスいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
\ 組織に定着する生成AI導入の進め方を資料で見る /