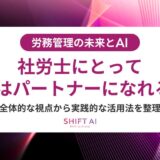「この仕事は◯◯さんにしかできないから」
「急に休まれたら回らない」
そんな“属人化”した業務が積み重なることで、気づけば特定の社員に業務が集中し、深刻な業務過多が生まれていませんか?
属人化は、最初は“頼れる人”の存在として評価されがちですが、放置すると組織の柔軟性を奪い、離職リスクや業務停滞を招く要因になります。
本記事では、属人化によって業務過多が生まれる構造的な問題にフォーカスし、
その原因・リスクを整理したうえで、現場で実践可能な解決ステップを解説します。
また、近年注目されている生成AIを活用した脱属人化のアプローチについても紹介します。
「人手が足りない」「引き継ぎができない」現場の不安を、仕組みで解消するヒントをぜひお持ち帰りください。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
属人化と業務過多はなぜセットで起きるのか?
業務過多が慢性化している職場では、その背景に「属人化」が潜んでいるケースが少なくありません。
そもそも属人化とは、「その業務を特定の人しか対応できない状態」を指します。
たとえば、営業資料の作成が特定のベテラン社員にしかできない、顧客対応の方法が担当者の頭の中にしかない——
こうした状態が続くと、その人が不在になるたびに業務が滞り、結果的に「その人がやらざるを得ない」構造が出来上がります。
属人化が進むと、業務は次第に集中し、周囲も「結局あの人に頼んだ方が早い」となって、負荷は加速度的に膨らんでいきます。
このように、属人化と業務過多は互いに影響しあいながら、負のループを形成してしまうのです。
さらに厄介なのは、属人化が暗黙の了解として組織に定着している場合です。
「ベテランのあの人に任せておけば大丈夫」
「急ぎの仕事はあの人に振ろう」
といった“ありがたがられる属人化”は、一見すると効率的に見えて、組織全体の柔軟性や再現性を奪います。
属人化が進行する職場では、業務が見えづらくなり、改善にもブレーキがかかります。
このような環境では、本当の意味での生産性向上や働きやすさの実現は困難です。
まずはこの「属人化→業務過多→更なる属人化」というループに気づくことが、改善への第一歩です。
属人化の主な原因5つとチェックリスト
属人化は自然に起きるものではなく、多くの場合、日々の業務環境や組織文化に原因があります。
ここでは、特に多くの現場で見られる属人化の原因5つを紹介します。
1.マニュアルや手順書が整備されていない
属人化の代表的な原因です。手順や判断基準が文書化されていないと、情報はその人の頭の中に留まり、他の人が対応できなくなります。
2.業務の引き継ぎや共有が後回しになっている
業務が忙しいほど「とりあえず自分でやったほうが早い」となり、共有のタイミングを逃してしまいます。この状態が常態化すると、他の人が入り込めなくなります。
3.業務範囲があいまいで担当者が固定化されている
「この仕事は◯◯さんの仕事」という認識が定着しすぎると、他のメンバーが関与しづらくなり、結果的に仕事が属人化していきます。
4.経験や勘に頼った仕事が多い
業務の進め方が「感覚」や「過去の経験」に依存していると、他の人が再現することが困難になり、業務の属人性が高まります。
5.属人化が“評価される文化”になっている
「この人じゃないと回らない」という状態が重宝されると、逆に業務の標準化が阻まれます。属人化は一時的に便利でも、長期的には組織のリスクになります。
属人化チェックリスト
あなたの職場で、次のような状態は当てはまりませんか?
- 特定の業務をいつも同じ人が担当している
- 休みや異動で業務が止まることがある
- 業務のやり方が口頭でしか伝わっていない
- 誰もが「忙しい」と言っているのに、一部の人は特に負荷が高い
- 引き継ぎが難しく、マニュアルが形骸化している
2つ以上当てはまる場合、属人化が進行している可能性が高いと言えます。まずは“見える化”による実態把握が、改善のスタートラインです。
放置すると危険!属人化のリスクとは
属人化が「なんとなく当たり前」になっている職場ほど、そのリスクに気づきにくいものです。
しかし、放置すればするほど、業務だけでなく組織運営や人材定着にも深刻な影響を及ぼします。
ここでは、属人化によって引き起こされる主なリスクを解説します。
1.特定の社員に業務が集中し、過労や離職につながる
属人化が進むと、重要な業務が特定の人に集中しがちです。
「この人しかできない」状態が続けば、代替要員がいないまま業務量だけが膨らみ、心身ともに限界を迎える可能性があります。
2.不在時に業務が止まり、組織としての柔軟性が失われる
急な休暇、病気、転職など、何が起きても業務が回る体制でなければ、企業は継続的に価値を提供できません。
属人化は、その柔軟性を根底から奪う要因です。
3.業務改善が進まず、全体の生産性が上がらない
業務内容が個人の経験や勘に依存していると、改善の対象として可視化されづらくなります。
結果として、非効率なやり方が放置され、チーム全体の生産性を損ねます。
4.引き継ぎ・人材育成が機能しなくなる
属人化された業務は、引き継ぎが非常に難しくなります。
結果として後任が育たず、人が育たない→さらに属人化が進むという悪循環に陥ります。
5.経営判断のスピードが鈍化する
業務に関する情報が属人化されていると、上層部が現場の状況を正しく把握できず、意思決定に遅れが生じます。
特に変化の早い現代では、この遅れがビジネスチャンスの損失に直結します。
属人化は、目に見える「人の負荷」だけでなく、組織全体の成長や持続性にかかわるリスクです。
属人化・業務過多を同時に解消するステップ
属人化による業務過多を解消するには、「人」に依存したやり方から脱却し、“仕組みで業務をまわす体制”に移行することが重要です。
ここでは、そのための実践ステップを4段階で紹介します。
STEP1|業務を見える化する(業務棚卸し)
まず必要なのは、今誰が何の業務を抱えているのかを明確にすることです。
Excelや業務可視化ツールを使って、以下を整理しましょう。
- 担当者名
- 業務内容
- 作業頻度/時間
- 難易度/属人性の高さ
業務を「一覧」にすることで、どこに負荷が集中しているのか、どの業務が属人化しているのかを把握できます。
関連記事:業務棚卸しのやり方を徹底解説|5ステップでムダを洗い出し改善につなげる方法とは?
STEP2|業務フローの標準化・ドキュメント化
属人化業務の多くは、やり方が明文化されていないことに起因します。
そのため、手順・判断基準・使用ツールなどをできるだけ再現可能な形で記録することが必要です。
- テキストマニュアル(NotionやGoogleドキュメント)
- 動画マニュアル(画面録画+ナレーション)
- FAQ集やチェックリストの整備
完璧を目指す必要はなく、「誰かが見て7割再現できるレベル」での作成が第一歩です。
STEP3|業務の分担とローテーション導入
業務を見える化・標準化できたら、チーム内での分担・協力体制を構築します。
以下のような取り組みが有効です。
- ペアワークや交代制
- 月1回の「逆引き継ぎ」日(普段やらない業務を体験)
- Wチェック体制の構築
こうした仕組みが属人化を防ぎ、業務の柔軟性を高めます。
STEP4|評価制度や業務配分の見直し
「できる人に偏る構造」が組織に根づいていると、改善は難航します。
属人化・業務過多を根本から解消するためには、評価や業務配分の仕組みも見直す必要があります。
- マルチスキル化の推進
- 属人化を解消した行動も評価対象に含める
- 担当業務量のバランスをモニタリングする仕組みをつくる
生成AIで属人化業務を代替する方法
近年、ChatGPTなどの生成AIの進化により、これまで“特定の人にしかできなかった業務”も仕組みで代替できるようになってきました。
特に、ルールが明確で繰り返し性の高い属人化業務には、生成AIの活用が非常に有効です。
ここでは、生成AIを活用して属人化を解消する具体的な方法を3つご紹介します。
1.マニュアル・FAQの作成を自動化
属人化解消の第一歩は、業務手順やノウハウを「誰でも見える化」すること。
ChatGPTのような生成AIを使えば、口頭やメモで残されていた業務をもとに、手順書・FAQ・チェックリストを自動生成することが可能です。
- 実務担当者の話を文字起こし→マニュアルに自動整形
- よくある問い合わせ→FAQ化して全社で共有
特定社員の頭の中にあるノウハウを、誰もが使える資産に変えられます。
2.文書作成・メール対応などの定型業務をAIで代行
「文章はあの人が上手いから」と属人化しているメール作成・報告書作成も、生成AIで大幅に効率化できます。
- 社内外の連絡文作成(例:進捗報告、謝罪メール)
- 定型資料の作成(議事録、日報、業務報告など)
テンプレートと生成AIを組み合わせることで、誰でも一定の品質で業務を遂行できる環境が整います。
3.ナレッジ共有プラットフォームとの連携
生成AIを「社内の業務ナレッジ検索エンジン」として活用することで、担当者しか答えられなかった質問に全員がアクセスできるようになります。
- 「この業務のやり方は?」→社内情報からAIが即回答
- 「あの人しか知らない情報」が可視化され、属人性が解消
属人化による情報格差を減らし、組織としての知的生産性を底上げできます。
属人化解消×生成AI活用の第一歩に
属人化を解消するには、単に業務を分散するだけでなく、「人でなくてもできる業務は、仕組みに任せる」という視点が必要です。
AI経営総合研究所では、こうした“脱属人化”を実現するための【生成AI研修】を提供しています。
現場の悩みを理解した上で、業務ごとのAI活用アイデアやツール活用法を体系的に学べます。
まとめ|属人化をなくし、仕組みで仕事を回す職場へ
属人化と業務過多がセットで発生する職場では、一部の人に業務が集中し、組織全体が疲弊する構造ができあがってしまいます。
この状態を放置すれば、個人の疲弊だけでなく、引き継ぎの難航・改善活動の停滞・人材育成の停滞といった、組織の“成長阻害”につながりかねません。
改善には、まず現状を可視化し、「誰が何をしているか」を全員で共有することから始めましょう。
そして、再現可能なマニュアル作成・業務フローの標準化・役割の見直しなどを通じて、「属人性を排除した業務体制」へと移行していくことが大切です。
属人化解消のカギを握るのは、“優秀な人に任せる”から“仕組みで回す”への転換です。
その転換を強力に後押ししてくれるのが、生成AIなどのテクノロジーです。
特定の人しかできなかった仕事をAIが支援・代替することで、業務の属人化と過多を同時に解消できるチャンスが広がっています。
- Q属人化を完全に防ぐことは可能ですか?
- A
完全に属人化をゼロにするのは難しいですが、再現性を高める工夫によってリスクを最小限に抑えることは可能です。
マニュアル整備・業務のローテーション・情報の共有文化づくりが有効です。
- Q少人数の職場でも属人化対策は必要ですか?
- A
むしろ少人数ほど要注意です。
人数が少ない分、1人にかかる負荷が大きく、欠員の影響も深刻です。
属人化対策は、組織の規模に関係なく取り組むべき課題です。
- Q属人化している業務をどう見つければいいですか?
- A
業務棚卸しを行い、「担当者が固定されている業務」「他の人が内容を知らない業務」「休むと止まる業務」などを洗い出すことが第一歩です。
チェックリストも活用すると効果的です。
- Q生成AIの導入は専門知識がないと難しいですか?
- A
難しくありません。今ではノーコードで使えるAIツールも多数あります。
また、研修を通じて具体的な業務への活用方法を学ぶことで、誰でも実務に取り入れられるようになります。