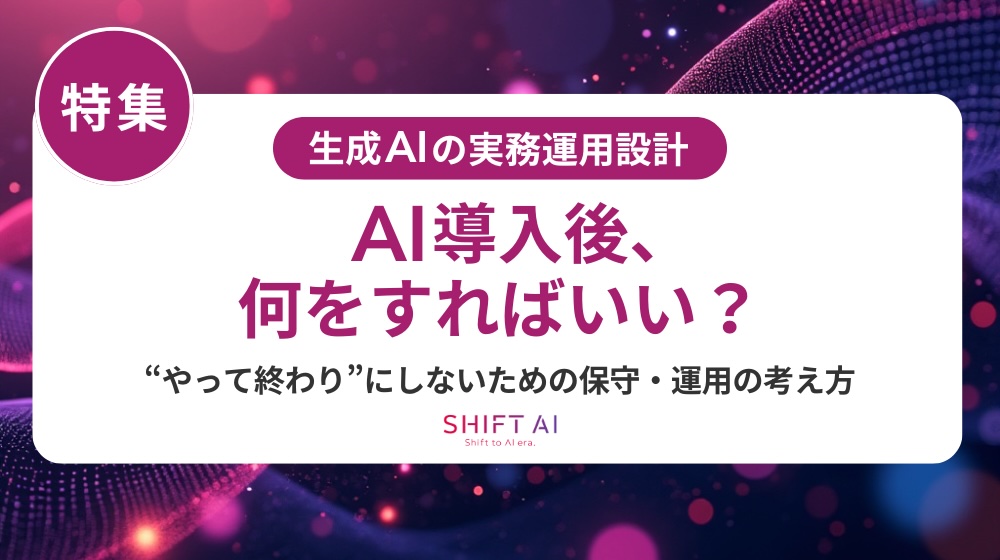「生成AIを活用したいのに、思い通りの結果が得られない」
そんな悩みを抱えていませんか?
実はその原因、AIの性能ではなく“プロンプトの書き方”にあるかもしれません。生成AIは、与えられた指示文(プロンプト)に忠実に応じて出力を生成します。つまり、あいまいな指示をすれば、あいまいな結果しか返ってこないということ。逆に、構造的で明確なプロンプトを使えば、驚くほど高精度な成果を引き出せます。
本記事では、生成AIを業務で使いこなすための「プロンプトの基本構造」や「書き方のコツ」を、5ステップでわかりやすく解説。実際にすぐ使えるテンプレートや、ありがちな失敗例の改善方法もご紹介します。
さらに、属人化せず全社で使いこなすための仕組み化のヒントまでお届け。
生成AIを“チームの武器”に変えるために、まずはプロンプト設計から始めましょう。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
そもそもプロンプトとは?生成AIと出力精度の関係
生成AI(GenerativeAI)にとって、プロンプトとは「どんな出力を望んでいるかを伝えるための指示文」のことです。
人間でいえば「依頼内容の説明書」にあたります。
たとえば「議事録を要約して」とだけ伝えるのと、「経営会議の議事録を部内向けに300文字で要約して、口調はビジネスライクで」と伝えるのとでは、出てくる文章の精度や使いやすさに大きな差が出るのは想像しやすいでしょう。
生成AIは「自ら意図をくみ取って補ってくれる存在」ではありません。
むしろ、曖昧なまま放り込めば、それなりの曖昧な出力が返ってくるのが現実です。
だからこそ、「誰に・何の目的で・どんな形式で出したいのか」を具体的かつ構造的に伝える必要があります。
つまり、生成AIの性能を最大限に引き出すカギは、「どんなAIを使うか」ではなく、
「どのようにプロンプトを設計するか」にあるのです。
関連記事:AIリテラシーとは何か|育て方・研修設計・定着支援まで企業向けに徹底解説
成果につながるプロンプトの基本構造と5ステップ
「AIに何をどう聞けばいいかわからない」
そんな悩みは、“プロンプトを構造的に組み立てる”ことで解消できます。
業務で成果を出すためのプロンプトには、以下の5つの要素を順序立てて組み込むのが効果的です。
ステップ①:目的を明確にする(What/Why)
まずは、「何を達成したいか」「何のために使うのか」を具体的に示します。
たとえば「社内報告書を要約したい」「新規事業アイデアを出したい」など。目的が曖昧だと、出力内容もブレやすくなります。
ステップ②:AIに役割を与える(Who)
生成AIに“どの視点で”考えてほしいかを指示します。
例:「あなたは採用担当です」「あなたは広報のプロです」など。
この一言があるだけで、回答のトーンや論点が業務にフィットしやすくなります。
ステップ③:前提や文脈を共有する(Background)
「誰向けのアウトプットか?」「どんな状況か?」といった背景情報も添えましょう。
例:「これは新入社員向けのマニュアルです」「BtoB向けの営業資料として使います」
AIにコンテキストを伝えることで、的外れな回答を防げます。
ステップ④:出力形式を指定する(Format)
生成AIは形式の指定にも対応できます。
例:「箇条書きで5つ」「300字以内の要約で」「Markdown形式で表にまとめて」など。
最初に形式を指定することで、手戻りや修正の手間が減るのも大きなメリットです。
ステップ⑤:条件や制約を明記する(Constraints)
最後に、トーン・文字数・含めない内容などのルールを加えると、出力の精度が一段と上がります。
例:「専門用語は使わず平易な表現で」「ネガティブな印象を与えないように」など。
補足:この5ステップは再利用・テンプレート化が可能
これらの構造は毎回ゼロから書く必要はありません。
「目的→役割→背景→形式→条件」の流れをテンプレート化しておけば、誰でも質の高いプロンプトが書ける状態を再現できます。
社内での標準化にも活用できるため、属人化を防ぎたい場合にも有効です。
【例文つき】すぐに使える!業務別プロンプトテンプレ集
ここでは、実際の業務でよくあるシーン別に、すぐに使えるプロンプトテンプレートを紹介します。
すべて、前述の「5ステップ構造」に沿って設計しており、そのまま使ってもOK。自社用にカスタマイズすれば、ナレッジとして展開しやすくなります。
会議議事録の要約
- 目的:社内共有用に要点を整理
- 役割:社内広報担当
- 背景:部内の定例会議
- 形式:箇条書き3点以内
- 条件:ビジネストーン、300文字以内
あなたは社内広報担当です。以下の会議議事録を、部内向け共有用に300文字以内・箇条書き3点以内で要約してください。口調はビジネスライクで、曖昧な表現は避けてください。
上司向けの報告メール作成
- 目的:業務報告
- 役割:チームリーダー
- 背景:プロジェクト進捗を報告
- 形式:メール文
- 条件:結論ファースト・簡潔に
あなたはチームリーダーです。以下の内容をもとに、上司宛ての業務報告メールを作成してください。結論から書き出し、要点を簡潔にまとめてください。
マーケティングアイデア出し
- 目的:キャンペーン施策立案
- 役割:マーケティングプランナー
- 背景:30代女性向けの商品
- 形式:箇条書き3案
- 条件:実現性重視・200文字以内
あなたはマーケティングプランナーです。30代女性向けの新商品をプロモーションするキャンペーン施策を3案、各200文字以内で提案してください。実現性のある内容にしてください。
社内FAQのドラフト作成
- 目的:新入社員向けFAQ整備
- 役割:人事部の教育担当
- 背景:よくある質問をもとに文章化
- 形式:Q&A形式、3問程度
- 条件:敬語・平易な表現
あなたは人事部の教育担当です。以下の質問リストをもとに、新入社員向けFAQを作成してください。形式はQ&A、トーンは丁寧でわかりやすくしてください。
これらはすべて、社内のドキュメントやナレッジベースに蓄積していくことで、属人化せず組織で使える“資産”に育てていけます。
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
曖昧な指示が出力ミスを生む|よくあるNGプロンプト集と改善のコツ
「AIに聞いてみたけど、ピンとこない答えが返ってきた…」
それ、AIの精度ではなく“あなたの指示文(プロンプト)”に原因があるかもしれません。
生成AIは、あいまいな指示に対しても“それっぽく”返す力を持っています。
だからこそ、具体的で論理的なプロンプトでないと、精度の高い成果は望めません。
以下に、ありがちなNGプロンプトと改善例を比較してご紹介します。
【改善比較表】NGプロンプトvsGOODプロンプト
| 用途 | NGプロンプト | GOODプロンプト(改善後) |
| 要約 | これ要約して | 「以下のテキストを300文字以内で、社内会議向けに箇条書きで要約してください」 |
| アイデア出し | なんか案出して | 「30代向けの美容商材に対するキャンペーン案を3つ、各200字以内で提案してください」 |
| 文章作成 | メール作って | 「上司向けの報告メールを作成してください。内容は以下、トーンはフォーマル、要点は3点です」 |
| 文章校正 | チェックして | 「以下の文章を、敬語を崩さずに自然な日本語に直してください。冗長表現や曖昧な語は避けてください」 |
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、生成AIを「個人のスキル」で終わらせず、業務で再現性高く使うためのプロンプト設計ノウハウを整理しています。属人化を防ぎ、チーム・組織で活用するための考え方を、チェックリスト形式でまとめました。
→ 生成AI推進担当者向けプロンプト設計資料を確認する(無料)
改善のコツ:曖昧ワードを避け、構造で考える
特に避けたい表現は以下のようなものです。
- 「いい感じに」「なんか」「ざっくり」「ちょっと」
- 「まとめて」「整理して」「文章にして」だけの曖昧な指示
代わりに、誰に向けて、どんな目的で、どんな形式でといった“構造”に分けて考えることで、AIの理解度が格段に上がります。
プロンプト改善は“試行錯誤の積み重ね”
AIとのやり取りは「一発で完璧な答えが出る」ものではありません。
むしろ、試行錯誤を繰り返しながら、改善サイクルを回すことが大切です。
1回目の出力が完璧でなくても、「もっと丁寧に」「出力形式を変えて」「対象者を意識して」など追記・再調整することで、理想のアウトプットに近づけていけます。
関連記事:AIリテラシーとは何か|育て方・研修設計・定着支援まで企業向けに徹底解説
生成AI活用を仕組みに変える|プロンプトの属人化を防ぐには?
「生成AIを使いこなせる人は一部だけ」
「誰が使っても同じ精度で活用できる状態にしたい」
このような課題に直面する企業は少なくありません。
せっかく生成AIを導入しても、活用が属人化してしまえば業務改善は一部の人材にとどまり、再現性も展開力も得られません。
そのために必要なのが、プロンプトの仕組み化=ナレッジ化・標準化・教育の3点セットです。
ナレッジ化:成功プロンプトを蓄積・共有する
効果の高いプロンプトは、個人の手元に置かずにチームで共有しましょう。
NotionやSharePointなどを使って「業務別プロンプト集」として公開するだけでも、活用ハードルはぐっと下がります。
- テンプレート形式で「目的/役割/背景/形式/条件」を整理
- NG例・改善例も一緒に残すことで学習効果もアップ
- 出力結果のスクショや用途シーンを添えると理解が深まる
標準化:再現性のあるプロンプト構造を全社に展開
プロンプトの構造(5ステップ)を社内標準として定めておくと、誰でも“そこそこの成果”が出せる状態を担保できます。
特に、生成AIを日常業務に組み込む企業にとっては、作業効率や品質管理にもつながる重要ポイントです。
- 営業・人事・総務など部門別テンプレを整備
- 全社で共通の命名ルールや保存フォーマットを策定
- 管理職が指導できるよう、標準化ガイドも整備
教育:研修によって属人化を根本から解消
ツール導入と同時に、プロンプト設計を軸とした研修を行うことで、活用スキルの組織内平均値を底上げできます。
単なる使い方ではなく、「業務目的とセットで活用する視点」を教えることがカギです。
- 成果を出す“考え方”を体系的に伝える
- 実務ワークやペアプロンプトで学習定着を促進
- 初心者・中級者・管理職向けに段階設計された研修が理想
属人化の解消・プロンプト設計力の底上げ・業務定着まで支援する、実践型の社内研修プログラムをご紹介しています。
まとめ|プロンプトの精度が生成AI活用の未来を決める
生成AIは、ただ使えば効果が出る“魔法のツール”ではありません。
活用の成否を分けるのは、「どのようなプロンプトを設計するか」という人間側の設計力にあります。
本記事で紹介したように、成果を生むプロンプトには共通する構造があります。
目的・役割・背景・形式・条件──この5ステップを意識するだけで、出力の精度は大きく変わります。
また、プロンプトの属人化を防ぐことで、組織全体の活用レベルを底上げし、業務の質・スピード・再現性をすべて高めることが可能です。
そのためには、テンプレートの共有や標準化だけでなく、プロンプト設計の考え方そのものを仕組み化する研修も非常に有効です。
- Q生成AIに質問するとき、なぜ意図しない答えが返ってくるのですか?
- A
多くの場合、プロンプトの情報が不足しているか、曖昧な表現になっていることが原因です。
生成AIは意図を汲むのではなく、与えられた情報だけをもとに回答するため、「何を・誰に・どんな目的で・どの形式で」といった指示が必要です。
- Qプロンプトに「あなたは〇〇の専門家です」と入れるのはなぜ有効?
- A
AIにロール(役割)を明示することで、出力の視点や語調が大きく変わるからです。
たとえば「法務の専門家」や「人事担当者」などの役割指定をすることで、現場に即した内容になりやすくなります。
- Qプロンプトテンプレはどのように社内で共有すべき?
- A
再利用可能なテンプレはNotionやGoogleスプレッドシートなどでカテゴリ別に整理し、誰でも参照・活用できる形でナレッジ化するのがおすすめです。
形式や文字数などの指定も含めて明文化すると、属人化の防止にもつながります。
- Qプロンプトの書き方を社員に教育するにはどうすればよい?
- A
最も効果的なのは、業務に即したプロンプト設計の研修を導入することです。
ツールの使い方だけではなく、「業務目的と出力形式を紐づけて設計する力」を体系的に学べる場が必要です。