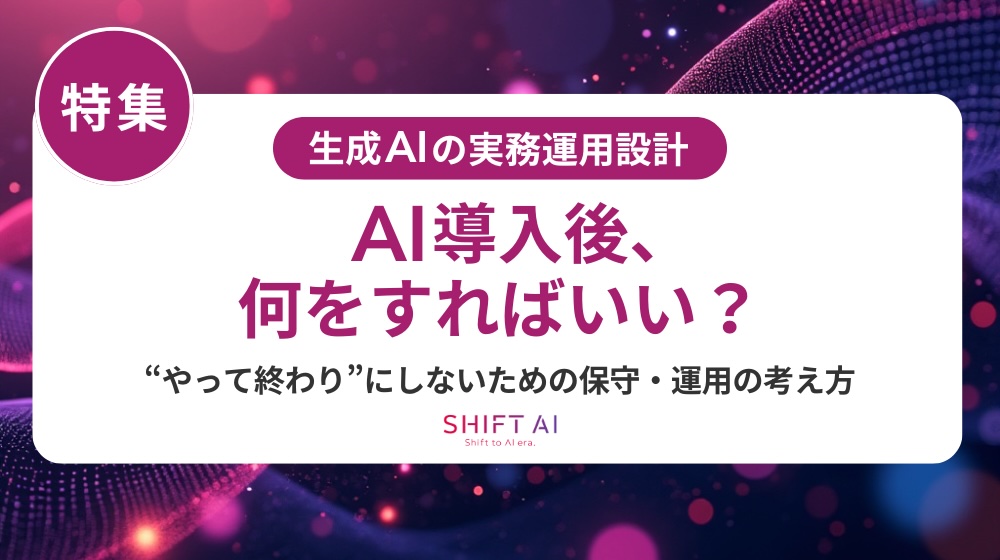「うちの会社、生成AIの使い方、明文化されてないけど大丈夫……?」
生成AI(ChatGPTなど)の業務活用が一気に進む中、「社内での安全な使い方が分からない」という悩みが多くの現場で浮き彫りになっています。
便利である一方、誤情報の出力や、うっかり社内情報を入力してしまうリスクなど、適切なルールなしに運用を始めることはむしろ大きなリスク要因になりかねません。
こうした背景から、いま注目されているのが「生成AI運用マニュアル」の整備です。ただし、「とりあえず禁止事項だけ並べた文書」では、現場は動きません。安全性と業務効率を両立しながら、現場で本当に“使われる”運用ルールを設計することが重要です。
本記事では、以下のような方を想定読者として、生成AIの業務活用を社内に定着させるための運用マニュアル作成・展開のステップを体系的に解説していきます。
- 情報システム部門、DX推進室、人事・総務部門の担当者
- 経営から「AI活用を進めてほしい」と言われているが、社内整備が追いついていない方
- ルールをつくっても形骸化してしまい、現場で使われていないことに課題を感じている方
「実務ノウハウ3選」を公開
- 【戦略】AI活用を社内で進める戦略設計
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】属人化させないプロンプト設計方法
なぜ「生成AI運用マニュアル」が必要なのか?
「便利だけど、どこまで使っていいのか分からない」生成AIの社内利用が急速に広がるなか、現場の多くでこうした声が上がっています。実際、以下のようなケースがすでに各所で起き始めています。
- 社員が提案書作成にChatGPTを使ったが、内容が誤っておりクレームに発展
- 社内の設計書をAIに読み込ませた結果、情報漏洩の懸念が発生
- 現場担当が「ルールがないから、とりあえず自己判断で使っている」状態
こうしたリスクの背景には、「生成AIの使い方を明文化していない」「利用ルールが部署ごとにバラバラ」など、ルール不在による混乱があります。
特に生成AIは、従来のツールと違い、
- 出力結果の正確性にばらつきがある(≠検索エンジン)
- 入力内容がそのままAIベンダーに送信される可能性がある
- 利用方法次第で成果が大きくもなれば、誤用のリスクもある
といった特性があるため、「どう使ってよいかを明確に定める運用マニュアル」が不可欠です。
逆に言えば、運用マニュアルがしっかり整備されていれば
- 利用シーンが統一され、活用の平準化が図れる
- 社員のリスク認識が高まり、事故の抑止につながる
- 利用促進や教育の足場にもなる
など、活用の推進力としても機能します。「ルールを作る」というと、“制限”や“縛り”のイメージを持たれがちですが、本来の目的は「安全に使ってもらい、成果を最大化するための支援ツール」です。
生成AI運用マニュアルに盛り込むべき7つの基本項目
「生成AIの社内活用を進めたい。でも、どこまで明文化すればいいのか分からない」そんな声に応えるために、ここでは運用マニュアルに必ず盛り込むべき7項目を解説します。いずれも、SHIFT AIが法人支援を行う際に現場で特にトラブルが多かった部分をベースにしています。
① 利用目的・対象範囲の明記
まず最初に明文化すべきは、「生成AIをどのような目的で利用するのか」という基本方針です。この定義があいまいなまま導入を進めると、部署ごとに使い方や解釈がばらつき、トラブルの温床になります。
<記載例>
- 利用目的:社内文書の要約、議事録の下書き、定型メールの作成支援など
- 利用対象:社内業務で完結する情報に限る
除外事項:クライアント資料・法的文書・外部公開資料は原則使用禁止
② 利用禁止事項とNG例の明文化
「何をしてはいけないか」を明確に定めることで、リスクある使い方を未然に防げます。禁止事項は抽象的な表現ではなく、具体例で明示することが重要です。
<記載例>
- 顧客の個人情報を入力する行為(氏名・住所・電話番号など)
- 社内機密・未公開の資料をそのまま貼り付ける行為
- 他社の契約書や提案書をそのまま入力する行為
補足: 情報区分(公開/社外秘/極秘など)ごとの「入力可否マトリクス」などを添えると、より実務に沿ったガイドになります。
③ プロンプト設計のルールと例示
生成AIの出力は、入力の質(プロンプト設計)によって大きく左右されます。想定と異なる出力や誤情報を防ぐためにも、社内ルールとして「正しい聞き方」を共有しましょう。
<良いプロンプトの例>
「以下の文章を要約してください。200文字以内で、箇条書きで3点に分けてください」
<悪いプロンプトの例>
「これ、わかりやすくして」
ポイント: 目的、条件、文字数、形式を指定することが大切です。
④ 出力内容の確認・責任範囲の明確化
生成AIは、事実誤認や“それっぽいウソ”を平然と出力します。そのため、「誰が何をどこまで確認するのか」を明確に定める必要があります。
<記載例>
- 社内利用であっても、出力内容は必ず本人が内容確認すること
- 対外資料への利用は、チームリーダー以上の承認が必要
- 出力結果は「事実かどうか」だけでなく、「誤解を招く表現」もチェック対象とする
推奨: 誤出力による事故が起きた際のログ保存ルールも、セットで定めると安全性が高まります。
⑤ 使用ツール・ログ管理に関するルール
「どのツールを使ってよいか」「ログはどう扱うか」といった技術面の指針も明記が必要です。
<記載例>
- 利用を許可する生成AI:ChatGPT(法人版)、Microsoft Copilot、Notion AI(社内アカウント限定)
- 禁止事項:個人アカウントの使用、プライベート端末でのアクセス
- ログ管理:利用履歴はSaaS管理ツールで3ヶ月以上保管。SlackやNotionとの連携も管理対象とする。
補足: 利用ログの保存は、トラブル発生時の検証・説明責任にもつながる重要な観点です。
⑥ 利用者教育・社内周知の方法
ルールを作っても、「誰も読まない」「浸透しない」では意味がありません。マニュアル=教育プログラムの一部と捉え、周知方法も設計しておきましょう。
<例>
- 利用開始時に必ずガイドライン説明会(オンライン30分)を実施
- よくある質問をまとめた「社内FAQ」を定期更新
- Slack・社内ポータルなどに週1で「プロンプト事例」や「失敗しがちな使い方」を共有
👉 詳細は:生成AIセキュリティ教育の設計・運用マニュアル
⑦ 改訂・更新ルールの明文化
生成AIは日々進化しており、「1年前のルールが通用しない」ことも珍しくありません。ルール自体をアップデートし続けるための体制をあらかじめ組み込んでおく必要があります。
<記載例>
- 改訂サイクル:半年に1回/大規模アップデート時
- 責任部署:情報システム部 or DX推進室
- 社内展開方法:ポータルへの掲載+Slack一斉通知+5分動画で要点解説
補足: 改訂があった場合、研修・教育とセットで周知する体制を整えておくのが理想です。
「ただ配っただけ」で終わらせない!社内展開と定着のための4ステップ
「せっかく運用マニュアルを整備しても、配っただけで現場が動かない」という声は少なくありません。特に生成AIのように使い方に習熟が求められるツールでは、ルールと活用スキルの両輪がなければ定着しません。
ここでは、SHIFT AIが数多くの企業支援で培った「社内展開〜定着」までの4ステップをご紹介します。
ステップ①部門横断で使える共通テンプレを設計する
まず重要なのは、「全社共通テンプレート」を作成しつつ、各部門でカスタマイズ可能な状態にしておくこと。
- 全社テンプレ例: 活用目的、禁止事項、責任範囲、承認フローなどの基本構成
- 部門別の追加項目: 使用事例、プロンプト集、業務への具体的な組み込み方
こうすることで、形だけのルールではなく実際に使えるルールになります。
ステップ②マニュアルを届けるだけでなく、“周知の仕組み”を作る
「PDFで配って終わり」では、ほとんど読まれません。読んでもらうための仕組み”や“見せ方を設計しましょう。
<効果的な周知方法>
- SlackやTeamsに「AI活用Tips」を週1で配信
- Notionや社内Wikiで、マニュアルの各章を短く区切って掲載
- 誤用・成功事例をまとめた社内ミニニュース(例:#AI失敗集)
こうした工夫が、「読むきっかけ」を生み、定着率を上げます。
ステップ③研修・オンボーディングで使い方の理解を促す
マニュアルがあるのと理解して使えるかはまったく別物です。特に新人や中途社員には、初期オンボーディング時にルールと活用方法をセットで教えることが重要です。
<研修で扱うべきテーマ例>
- プロンプト設計の基本と実演(良い例/悪い例)
- 誤出力・誤情報の事例と、その防ぎ方
- 自部署での活用イメージづくり(ワーク形式)
👉 詳しくは:生成AIセキュリティ教育の設計・運用マニュアル
ステップ④使い方のフィードバックをマニュアルに反映する仕組みを作る
一度作ったマニュアルも、現場の声を反映して改善を重ねることで初めて生きたルールになります。
<改善サイクル例>
- 利用者アンケートを四半期ごとに実施
- Slackでの「#プロンプト相談」から課題傾向を抽出
- 改訂内容を「Before/After」形式で社内共有
重要なのは、ルールを押し付けるものからみんなでつくるもの”へ変える意識。これにより、活用が自主的に広がり、マニュアルの存在価値も高まります。
【チェックリスト付き】生成AI活用ルール整備の実務ガイド
「何をどこまで整備すれば十分なのか分からない」そんなときに役立つのが、チェックリストとテンプレート構成の見本です。
ここでは、SHIFT AIが法人向け研修で活用している「ルール整備例・構成・確認項目」をもとに簡単に紹介します。
チェックリスト:生成AI運用マニュアルの整備状況を確認しよう
まずは、以下のチェックリストで自社の整備状況を自己診断してみてください。
| チェック項目 | 状態 |
| 利用目的や対象範囲を明記している | □ できている / □ まだ |
| 利用禁止事項を具体例付きで記載している | □ できている / □ まだ |
| プロンプト設計の基本ルールを定義している | □ できている / □ まだ |
| 出力内容のチェックルールを決めている | □ できている / □ まだ |
| 承認フロー・ログ管理の方針が定まっている | □ できている / □ まだ |
| 社内教育・周知の仕組みを構築している | □ できている / □ まだ |
| マニュアルの改訂サイクルと責任者が決まっている | □ できている / □ まだ |
5項目以上が「できている」なら、安全運用の土台はほぼクリア。逆に3項目以下なら、「ルールがあるつもり」でも現場は使えていない状態かもしれません。
マニュアル構成テンプレ:章立てと必要要素
生成AI運用マニュアルの基本構成は、以下のような「5章+付録」スタイルが多くの企業で使われています。
<基本構成例>
- はじめに
マニュアルの目的と背景、対象者 - 生成AI利用の基本方針
利用目的・範囲・禁止事項などの原則ルール - 利用方法の詳細
プロンプトの記入例、出力結果の確認手順、承認フロー - 教育・周知の方法
研修計画、社内FAQ、オンボーディング時の説明など - 管理・見直し体制
改訂ルール、更新タイミング、責任部署の明記
付録:プロンプト例集、禁止ワードリスト、承認フロー図 など
社内掲示用:1枚資料の「生成AI利用ガイド」見本
マニュアルとは別に、「現場にすぐ見せられる1枚資料」を作成しておくと、浸透率が格段に上がります。
<記載例(1枚で伝えるべき4項目)>
- 生成AIを使ってよい場面(例:議事録、案出し)
- 絶対にやってはいけないこと(例:個人情報の入力)
- 出力確認と承認の流れ(3ステップで記載)
- 困ったときの連絡先(Slack窓口、担当者名)
「読ませる」よりも「見れば分かる」ことが重要です。SHIFT AIではこのようなビジュアルテンプレートも研修内で活用するケースもあります。
フェーズ別:やるべき整備項目まとめ
最後に、導入から定着までの「フェーズ別チェック」をまとめておきます。
| フェーズ | 整備すべき内容 |
| 導入前 | 目的の明確化/ガイドライン草案の作成/関係部署の巻き込み |
| 導入時 | 利用ポリシー共有/利用ツール選定/簡易ガイド配布 |
| 運用中 | 利用状況の確認/フィードバック収集/FAQ整備 |
| 定着後 | マニュアルのアップデート/プロンプト共有文化の形成 |
他社事例に学ぶ!生成AI運用マニュアル成功のリアル
「うちと似たような企業は、どうやってマニュアルを整備しているんだろう?」そう感じている方は、ぜひともAI経営総合研究所が独自で取材したさまざまな企業の事例を参考にしてください。
業種や企業規模、使っている生成AIの種類から事例を検索できるページを用意したので、自社と似ている企業がどのような形で生成AIを使っているのかすぐにわかります。
🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?
AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、
業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。
生成AI利用マニュアルにありがちな課題と解決策
せっかくマニュアルを整備しても、使われない、守られないという声が後を絶ちません。ここでは、SHIFT AIがこれまで支援してきた中で頻出した生成AIマニュアルの失敗パターンと、その解決策をまとめました。
もし1つでも心当たりがあれば、マニュアルの「中身」ではなく「運用設計」を見直すチャンスです。
課題①禁止事項ばかりで使いたくなくなる
<よくあるNG>
「個人情報入力禁止」「機密情報入力禁止」「出力は参考程度に」…ばかりで、結局何ならOKか分からない。
<解決策>
- 「やっていいこと」も明示(例:社内報の下書き/FAQ案出しなど)
- 成功プロンプト例・活用シーンを併記することでガイドではなく支援ツールとして機能させる
課題②現場の業務とリンクしておらず、空中ルール化している
<よくあるNG>
マニュアルは存在するが、実際の業務フローには一切組み込まれていない(例:誰も承認フローを使っていない)。
<解決策>
- 業務別・部門別テンプレートを導入し、現場の文脈にフィットさせる
- 利用ケースを収集し、プロンプト例や注意点を社内ナレッジに変換
課題③教育・周知が不足し、知ってる人だけが使っている
<よくあるNG>
「マニュアル読んでないので知りません」「そんなルールがあるとは知らなかった」
<解決策>
- オンボーディング研修やe-learningで入口教育を標準化
- Slackや社内ポータルで定期的にルールを再周知
- チェックテスト形式で「理解→使う」状態を可視化
課題④改訂されず、内容が時代遅れに
<よくあるNG>
古いモデル前提のままルールが放置され、最新のモデルの制御に対応していない。
<解決策>
- 改訂ルール(頻度・責任部署・共有フロー)をマニュアル内に明文化
- 技術アップデート時には、影響範囲のチェックリストを使って見直す
課題⑤「ルールはあるのに成果が出ていない」
<よくあるNG>
形式的にルールは整っているのに、実際には業務効率化もされず、活用も進んでいない。
<解決策>
- 成果が出るプロンプトを収集して社内共有ナレッジ化
- SHIFT AIのような外部支援を活用し、現場での活用定着+成果測定までを支援対象に含める
SHIFT AIなら、「成果につながるマニュアル設計+定着支援」まで一貫サポート
「ルールはある、でも活用が進まない」そんな停滞感を変えるために、SHIFT AIでは単なる整備ではなく、運用し続けられる設計と定着の仕組みをご提供しています。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応
まとめ|マニュアル整備はリスク対策ではなく活用戦略の一部
生成AIの導入は、単なるツール導入ではありません。「業務のやり方そのものをアップデートする」企業変革の一歩です。
だからこそ、ルール整備において重要なのは、使わせないためではなく、安心して使ってもらうための仕組みをつくること。
今回ご紹介したように、
- 利用目的・範囲・プロンプトルールを明文化する
- 教育・定着フェーズまで含めて設計する
- チェックリストや事例で運用の質を担保する
こうした整備があってこそ、社内における生成AI活用は、個人技から組織戦略へと進化していきます。
<SHIFT AIは、整備・展開・定着まで一貫して伴走します>
「うちも整えなきゃと思っていたけど、どこから始めればいいのか…」
「ルールはあるけど、結局誰も使えていない」
「プロンプトや活用事例を共有する文化が社内にない」
そんな企業さまに向けて、SHIFT AIでは生成AI研修+運用マニュアル整備支援を一貫して提供しています。ルール整備のその先を見据えた設計で、社内活用を確実に定着させる。それが、私たちの提供価値です。
関連リンク
- マニュアル化が難しい理由と解決策|生成AIで効率化する実践的アプローチ
- 生成AIセキュリティ教育の設計・運用マニュアル|3ヶ月で全社展開を実現する方法
- マニュアルに目的が書かれていない企業の深刻な問題
- 報告書作りすぎで生産性低下!原因分析と生成AI活用による効率化対策
AI生成運用マニュアルに関するよくある質問(FAQ)
- Qマニュアルは社内全員に配る必要がありますか?
- A
基本的には「生成AIを利用する可能性があるすべての社員」に共有することが望ましいです。ただし、部署によって必要な情報は異なるため、共通マニュアル+部門別補足資料という二層構成が効果的です。
- Q「プロンプトルール」って、マニュアルにどこまで書けばいいんですか?
- A
最低限、良いプロンプト/悪いプロンプトの例、推奨フォーマット(例:目的+条件+出力形式)は記載しましょう。
加えて、「プロンプト事例集」や「業務別テンプレ」は別紙や社内Wikiで運用すると柔軟性が高まります。
- Qマニュアルを作ったあと、定着させるには何が必要ですか?
- A
研修・再周知・現場の声の反映の3点がカギです。SHIFT AIでは、マニュアル整備に加えて、現場定着のためのオンボーディング設計や活用カルチャーの醸成も支援しています。
- Q生成AIを業務に使うとき、誤情報への対処ってどうしていますか?
- A
出力結果は必ず人の目で確認・再編集することが前提です。また、「高リスク用途にはAIを使わない」「必ず事実確認を行う」など、マニュアルでリスクレベルに応じた使用ルールを設けることが推奨されます。
- Q小規模な会社でも運用マニュアルは必要ですか?
- A
必要です。むしろ、少人数だからこそ暗黙の了解に頼らず、明文化しておくことで全員が同じ方向に動けるようになります。SHIFT AIでは、50名未満の企業への導入支援実績も多数あります。
- QSHIFT AIの研修では、マニュアルの内容も一緒に作ってもらえますか?
- A
はい、可能です。SHIFT AIでは、各社ごとに最適なマニュアル構成・テンプレートをカスタマイズし、社内展開や研修設計まで一気通貫でサポートします。