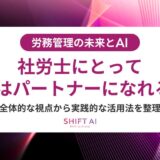Copilotを導入したのに、現場でまったく使われていない。そんな悩みを抱える企業が、いま増えています。
Microsoft 365 CopilotやGitHub Copilotといった生成AIツールは、業務の効率化や生産性向上を目的に導入されることが多い一方で、「そもそも使われない」「最初だけ使って終わった」という声も少なくありません。
使うべき理由が明文化されていない。活用ルールが存在しない。使っても評価されない。こうした状態では、Copilotは組織に根づかず、単なる「使い捨てツール」になってしまいます。
本記事では、Copilotが定着しない構造的な課題と、業務に自然と根づかせるための制度・文化の設計方法を解説します。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
Copilotが定着しない3つの理由!現場は使えないのではなく使う理由がない
導入しても現場に根づかない企業には、いくつかの共通点があります。単に「使い方がわからない」だけではなく、組織としてCopilotを活用するための前提条件が整っていないのです。
ここでは、とくに多くの企業がつまずいている3つの原因を見ていきましょう。
1. 活用の“目的”が社内で共有されていない
Copilotの導入時、多くの企業が「とにかく業務を効率化したい」という漠然とした期待を抱きます。しかし、その効率化が具体的にどの業務を指すのか、どの部署で、誰が、どのように使うのかまで落とし込まれていないケースが大半です。
現場の社員にとっては、「便利らしいけど、自分の仕事にどう役立つのかわからない」状態。経営層と現場のあいだで期待値がずれているままでは、ツールの利用は進みません。
定着の第一歩は、「なぜ導入したのか」「どの業務に活用するのか」という目的と活用シーンを、共通言語として社内に浸透させることです。
2. 仕組みがないまま展開されている
「ライセンスは配ったけど、あとは現場に任せている」。このような状態では、Copilotの活用は一部のITリテラシーが高い社員に留まり、社内に浸透しません。
活用ルールが整備されていないと、「使っても使わなくても問題ない」状態になり、やがて使用はフェードアウトします。
必要なのは、業務プロセスにCopilotを組み込む仕組み化です。たとえば、「議事録作成時にはCopilotを使う」「メール文案の初稿はCopilotで生成する」など、いつ・何に・どう使うかを業務設計の中に埋め込むことで、現場での活用が自然と定着していきます。
👉 関連記事
「Copilotが使われない本当の理由とは?」
3. 評価制度に紐づいていない=使っても得にならない
仮にCopilotを活用して業務が効率化されても、それが人事評価やチームの成果として見える化されなければ、使い続けるモチベーションには繋がりません。
現場の心理として、「使っても評価されないなら、今までどおりやった方が安全だ」となりがちです。
だからこそ、Copilot活用に連動した評価制度の設計が不可欠です。たとえば「AIを活用した業務改善提案の数」「プロンプトの品質改善活動」など、実際の行動をKPIとして組み込む仕組みがあるだけで、現場の空気は大きく変わります。
\ Copilot導入の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
Copilotが定着した企業がやっている仕組み化の工夫
「うちの現場では普通に使われてますよ」そんな企業がやっていることには、ある共通点があります。
それはCopilotを“努力しないと使えないツール”から、自然と使うものに変える仕組みを整えていることです。ここでは、定着に成功した企業が実践している3つの工夫をご紹介します。
1. KPIと評価にCopilot活用を紐づけている
定着に成功している企業の多くは、Copilotの活用をKPIに組み込んでいます。
たとえば、
- 「Copilotを使った提案の件数」
- 「AI活用による業務改善のインパクト」
- 「プロンプト改善の投稿回数」
といった指標を設定することで、社員に「活用するメリット」が生まれます。
また、こうしたKPIは人事評価や賞与の指標にも連動させることで、形だけの活用から成果を出す活用へと文化がシフトしていきます。
2. チーム単位でナレッジ共有→Slack・Notionに活用Tipsを蓄積
Copilotの使い方に正解はありません。だからこそ、社内でのナレッジ蓄積と共有の仕組みが重要です。
たとえば、
- Slackに「#copilot-tips」チャンネルを作り、活用法を日々共有
- Notionに部署ごとの使い方ハンドブックを整備
- 毎週の定例会で「今週のCopilot活用小ネタ」を発表
といった取り組みが、「使ってみた」が「使い続ける」につながる習慣を生み出します。
ここで重要なのは、成功事例だけでなく失敗例や改善ポイントも蓄積すること。属人化を防ぎ、組織全体でナレッジが回るようになります。
3. チャンピオン制度で社内伝播を促進
Copilot活用を社内に広げるうえで効果的なのが、部署ごとに旗振り役となるチャンピオンを立てることです。
チャンピオン制度では、以下のような役割を担う人材を配置します。
- 各部署での活用事例の収集と展開
- 現場の声をフィードバックし、活用ルールの改善提案
- 他部署との連携による横展開
これにより、トップダウンで強制するのではなく、現場主導で自然と広がっていく仕組みが生まれます。
👉 関連記事
AI活用が定着しない…?OJTで“使える力”に変える4ステップと育成設計ガイド
\ Copilot導入の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
「定着しない」を「自走する」に変えるために必要な設計3選
「定着させよう」と思っているうちは、Copilotは使われません。定着の鍵は、意識しなくても使う仕組みを組織のなかに埋め込むこと。ここでは、現場が自発的にCopilotを使い続けるようになるための設計ポイントを3つに絞って解説します。
1. ユースケースの棚卸しと業務別テンプレート化
「Copilotって、結局何に使えるの?」この問いに即答できない企業ほど、定着に苦戦しています。そこでまず必要なのは、部署ごと・業務ごとに“活用可能なユースケース”を棚卸しすること。
例としては、以下の3つ挙げられます。
- 営業部 → 提案資料のたたき台作成、メール文面生成
- 管理部 → 定型業務の自動化、契約書ドラフトチェック
- 開発部 → コードの自動生成、テストケース作成
この棚卸しをもとに、「Copilot活用テンプレート」を作成すれば、現場は迷わず使えるようになります。つまり、「使うために考える時間」をゼロにするのがポイントです。
2. 成果の見える化(Before/After可視化)
“成果が見えないツール”は、定着しません。だからこそ、Copilotを使ったことによる効果を「見える化」する仕組みが必要です。
たとえば、
- 活用前:提案資料作成に5時間 → 活用後:2.5時間
- コードレビュー時間:月20時間 → Copilot導入後:13時間
こうしたBefore / Afterの定量比較を社内で定期的に共有することで、「自分も使ってみよう」というモチベーションが自然と生まれます。
成果を可視化するだけでなく、社内報や共有ミーティングでポジティブに取り上げる仕掛けも大切です。
3. 忘却を前提とした再接触設計
人は忘れる生き物です。どれだけ丁寧な研修を受けても、一度きりでは使いこなせるようにはなりません。
そこで重要なのが、「忘れる前提」で設計する再接触の仕組みです。
- 週1のTips配信(Slackやメール)
- 活用トレンド共有会(部署ごとに5分でOK)
- 定期的なフィードバックMTGで「使ってみた話」を言語化する場づくり
このように、定着とは一回きりの導入ではなく継続的な再学習設計の積み重ねであると理解することが重要です。
👉関連記事
研修が定着しないのは“忘却前提”がないから?再接触設計×生成AIで行動に変える方法
Copilot定着を失敗しないためのチェックリスト【全社展開前に必読】
Copilotを導入したら、すぐに使われる。そんな理想の展開が起こることはほぼありません。定着には、事前にクリアしておくべき「準備条件」があります。
ここでは、Copilotを“定着させる企業”が満たしている5つの条件をチェックリスト形式でご紹介します。自社に足りないものがあれば、そこが「定着しない原因」かもしれません。
| チェック項目 | 説明 |
| 利用目的の明文化 | 経営層・現場の双方で「なぜ導入したか」が共有されている |
| 活用ルールの整備 | 業務プロセスに「いつ・どこで使うか」が定義されている |
| KPI/評価への反映 | 活用行動が評価や目標管理と結びついている |
| ナレッジ共有の仕組み | 成功例/失敗例が蓄積・展開される場がある(Slack・Notion等) |
| 再接触の設計 | 活用を継続させるための再学習の仕組み(リマインド・Tips配信等)がある |
全部にチェックがついていないなら、それは定着しない兆候です。
Copilotを社内に根づかせるためのSHIFT AIの支援とは?
「制度設計までは手が回らない」「現場への展開に時間がかかってしまう」そんな悩みに応えるのが、SHIFT AIの法人向け生成AI研修です。
私たちは、単なる研修提供にとどまりません。Copilotを定着させるための仕組みそのものを、企業と一緒につくることができます。
<提供している主な支援内容>
- 業務別ユースケースの棚卸し支援
- 部署別・役職別活用テンプレート設計
- 活用ルール策定&ナレッジ共有設計
- チャンピオン制度の導入支援
- KPI/評価制度への連携アドバイス
- 研修と再接触設計を一体化したプログラム提供
まとめ:Copilotを「使われないツール」にしないために、今すべきこと
- Copilotが定着しないのは、「人の問題」ではなく「仕組みと制度の欠如」
- 目的・ルール・評価・文化を設計すれば、“自然と使う”環境は作れる
- 属人化に頼らず、「組織としての活用力」を育てることが本当のDX
SHIFT AIは、その仕組み化を“ともにつくる”伴走パートナーです。
下記のリンクからは、「全社員のCopilot活用」「Copilot活用人材育成」をテーマにした複数の事例を含め、AI導入・活用に成功し成果をあげている様々な業種の実際の取り組み17選をまとめた事例集をダウンロードいただけます。自社と似た課題感を持つ会社が、どうやってAIを活用しているのか知りたい方はお気軽にご覧ください。
\ Copilot導入の『成功イメージ』が実際の取り組み例からわかる /
FAQ:Copilot定着に関するよくある質問
- QCopilot活用のKPIはどのように設定すればいいですか?
- A
提案件数」「AI活用の改善施策数」「使用時間」など定量+行動指標の組み合わせが有効です。
- Q社内に“使わない文化”が根づいているのですが、何から始めれば?
- A
ユースケースの棚卸しと“活用テンプレ化”から始めるのが効果的です。
- Q属人化を防ぐナレッジ共有の設計はどうすれば?
- A
SlackでのTips共有、Notionでの事例集管理が効果的。SHIFT AIではその設計支援も可能です。
- Q管理職の巻き込みが進みません…
- A
まずは部門ごとの“活用チャンピオン”を設け、成功事例を起点に上層部へ展開するのが現実的です。
- QSHIFT AIではどのレベルまで支援してくれますか?
- A
ユースケース設計・制度整備・KPI策定から、チャンピオン育成・研修実施・再接触設計まで“丸ごと支援”します。