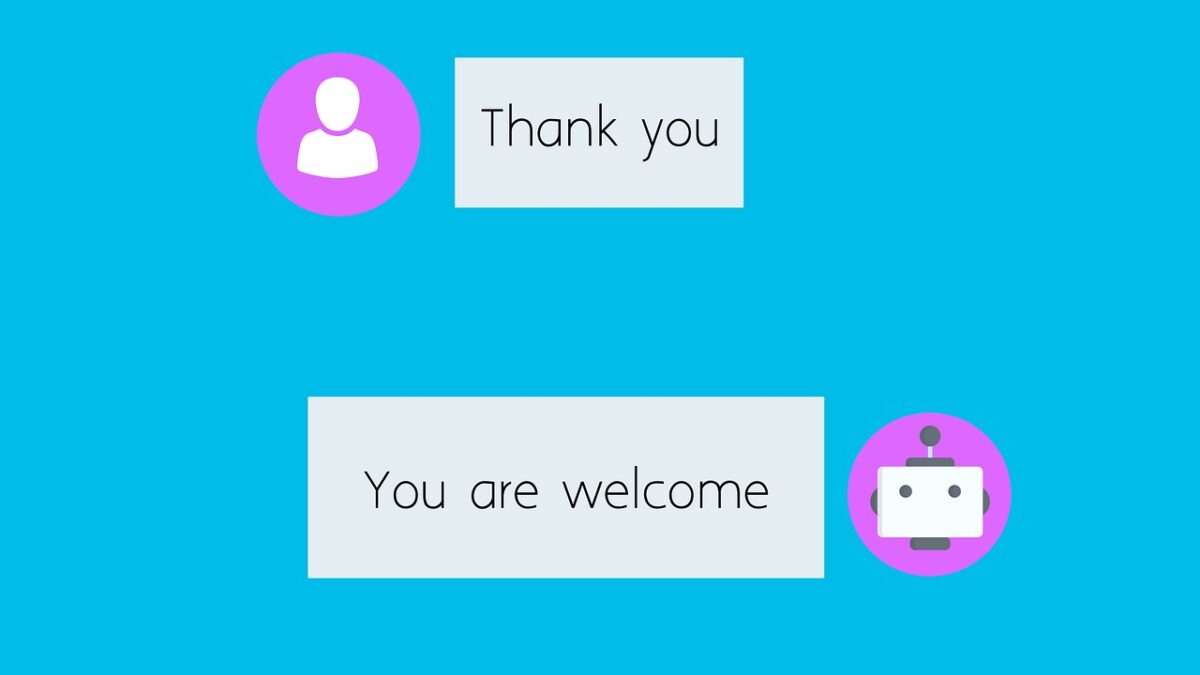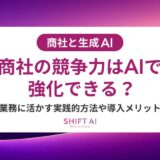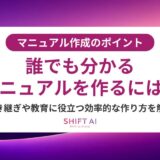生成AIとチャットボットの連携は、業務効率の向上や顧客対応の高度化を実現する手段として、多くの企業から注目されています。
とはいえ、「実際に導入するとどんな効果があるの?」「自社にも活かせるの?」と疑問を持つ方も少なくないでしょう。
この記事では生成AI×チャットボットの【成功事例20選】に加え、失敗事例や導入時の落とし穴、活用を成功に導くポイントまで、実践的な視点で解説します。
SHIFT AIでは、AIの活用や導入に関する相談を無料で受け付けています。また職種別のAI活用eラーニング、社内のAI人材育成支援、コンサルティングも行っております。AIの活用を検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。
- 生成AIとチャットボットの違い
- 生成AI×チャットボット成功事例20選
- 問い合わせ対応業務が約3割減少
- よくある質問の自動回答でお問い合わせが20%に減少
- AIチャットボットで顧客満足度が8割超に向上
- 問い合わせ対応が4分の1に削減、少人数体制でも運用可能に
- 問い合わせの80%を自動解決、業務効率も30%向上
- 問い合わせ件数を34.8%削減、営業負担も軽減
- 窓口業務の8割削減と出願数20%増を同時に実現
- 少人数体制でも対応件数が2倍に
- 問い合わせ対応業務を66%削減、3部門で業務効率が大幅改善
- チャットボット導入で電話問い合わせを24%削減
- 月間80〜100時間の問い合わせ対応を削減
- 社内資料の検索時間を3分の1に短縮
- チャットボット経由での集客がわずか4ヶ月で100件に
- 離脱ユーザーのコンバージョン率が2倍に向上
- EC購入率が150%アップ
- 新規顧客獲得数が110%に増加
- 休業中にも100件以上の入庫予約を獲得
- SNS診断コンテンツの完了率が約90%を達成
- 導入からわずか3ヶ月で申込件数が480%に増加
- チャットボット導入で顧客満足度90%を実現
- 生成AI×チャットボットの失敗事例
- 生成AI×チャットボットの導入を成功させるコツ
- まとめ:生成AI×チャットボットで新たな業務改革を
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
生成AIとチャットボットの違い
生成AIとは、文章や画像などを自動生成する技術で、人間のように創造的な出力が可能です。
一方、従来型のチャットボットは、あらかじめ設定されたシナリオやFAQに基づいて、定型的な応答を返す仕組みです。そのため、想定外の質問には対応しきれないという課題がありました。
しかし近年では、生成AIをチャットボットに組み合わせることで、より柔軟で自然な応答が可能になっています。未知の質問にも臨機応変に対応できるため、問い合わせ対応の効率化や顧客満足度の向上につながります。
こうした背景から、生成AIを搭載した次世代チャットボットを導入する企業が増えています。
生成AI×チャットボット成功事例20選
生成AIを搭載したチャットボットは、問い合わせ対応の自動化による業務効率の向上や、顧客満足度の向上など、さまざまな効果を生んでいます。中には、売上向上につながった事例もあります。
ここからは実際に導入された企業でどのような改善や成果があったのか、20の成功事例を厳選してご紹介します。自社での活用を検討する際のヒントにしてみてください。。
問い合わせ対応業務が約3割減少
家具メーカーのフランスベッドは、生成AI搭載のチャットボットを導入することで、問い合わせ対応業務を約3割削減することに成功しました。
導入前は電話での問い合わせが中心で、スタッフが対応に追われる状況が続いていました。さらに、折り返しの連絡が必要になるケースも多く、顧客にとっても負担が大きいという課題がありました。
生成AIチャットボットの導入後は、チャットによる自己解決が進み、オペレーターの負荷が軽減。あわせて、営業時間外や休業日でも対応可能となったことで、顧客満足度の向上にもつながっています。
参考:「“たらい回し”を解消し、電話対応3割削減!他事業部展開も進むフランスベッドのチャットボット戦略」
よくある質問の自動回答でお問い合わせが20%に減少
お菓子メーカー・ISHIYAグループが運営するテーマパーク「白い恋人パーク」は、生成AIチャットボットの導入により、問い合わせ対応業務を20%削減しました。
もともと電話による問い合わせの多くは、ホームページに記載されている内容に関するものでした。また、外国人顧客からの問い合わせメールへの対応では、翻訳作業に時間がかかり、返信の遅れが課題となっていました。
そこで、よくある質問を自動回答する生成AIチャットボットを導入。結果として、電話での問い合わせ件数は前年比で14%減少(=86%に抑制)し、電話回線も1回線削減することができました。
さらに、英語・中国語対応のチャットボットを設置したことで、海外からの問い合わせメールも大幅に減少。対応にかかっていた時間を、より重要な電話対応や事務業務に充てられるようになっています。
参考:「白い恋人パークのホームページに日本語/英語/中国語のチャットボットをリリース。来場者前年比120%にも関わらず、海外からのお問い合わせは前年比20%に減少!」
AIチャットボットで顧客満足度が8割超に向上
Webシステム開発を手がける株式会社フラッグシステムは、生成AIチャットボットの導入により、顧客満足度を80%以上まで向上させました。
同社ではサービスへの問い合わせが増加する中、人力によるメール対応だけでは対応が追いつかず、業務が逼迫していました。もともと設置していたFAQサービスも、使い勝手の問題から月150〜200件程度の利用にとどまっていました。
そんな中、AIによる自動応答の仕組みに着目し、チャットボットの導入を決定。生成AIチャットボットの導入後はFAQサービスの利用件数が月300件程度に増加しました。
単純な問い合わせは自動応答で解決できるため、人間が対応するべきより深い質問に対して担当者が集中して回答できるようになり、業務負荷の低減につながっています。
参考:「生成AIチャットボット×VOC自動分析で顧客満足度8割超え!月間300件の問い合わせを効率化しROI 1.5倍に」
問い合わせ対応が4分の1に削減、少人数体制でも運用可能に
人事評価システムを提供する株式会社あしたのチームは、生成AIチャットボットの導入により、問い合わせ対応業務を従来の4分の1に削減することに成功しました。
同社では以前、毎月300〜400件もの問い合わせが寄せられ、その多くがシステム操作に関する基本的な内容でした。対応はすべて人手で行っていたため、オペレーターの負担が大きく、対応の質やスピードにも課題がありました。
そこで、24時間365日自動応答できる生成AIチャットボットを導入。結果、月300件近くあった問い合わせは約80件まで減少。ルーティンな質問はAIが処理し、複雑なケースのみを人が対応するハイブリッド体制を実現しました。
これにより、従来8人体制だった対応チームは、2〜3名でも十分対応可能に。業務負荷を大幅に軽減しながら、顧客対応の品質も向上しています。
参考:「他社チャットシステムから、ChatPlusへリニューアル。チャットボットによる自動回答で自己解決へ誘導、問い合わせ数は1/4に大幅減!」
問い合わせの80%を自動解決、業務効率も30%向上
ICTサービスを展開する株式会社ネクストビートは、生成AIチャットボットの導入により、問い合わせの約80%を自動で解決し、全体で30%の業務効率化を実現しました。
とくに効果を発揮しているのが、保育園向けの勤怠管理システムに関するサポートです。使い方に関する問い合わせが非常に多く、従来のFAQでは対応しきれない状況となっていました。そこで、自然言語処理に優れた生成AIチャットボットを導入。複雑な質問にも柔軟に対応できるようになり、顧客の自己解決を大きく促進しました。
さらに、回答できなかった質問を定期的に洗い出して新たなQ&Aに反映させるなど、継続的な改善を実施。その結果、問い合わせ対応の品質と顧客満足度の向上にもつながっています。
参考:「保育所スタッフの複雑な問い合わせ対応に生成AIを導入。80%の解決率と30%の業務効率化を実現!」
問い合わせ件数を34.8%削減、営業負担も軽減
採用関連サービスを展開する株式会社リクルートは、生成AIチャットボットの導入により、サポートセンターへの問い合わせ件数を34.8%(約2万件)削減することに成功しました。
主力サービス「リクナビ」では、採用活動の繁忙期に問い合わせが集中し、電話がつながりにくい状況が続いていました。また、一部の顧客は営業担当を介して質問せざるを得ず、営業現場の業務効率にも支障が出ていたのです。
生成AIチャットボットを導入したことで、従来の電話やメール対応と比べて回答スピードが大幅に向上し、顧客は24時間いつでも自身で疑問を解消できるようになりました。そのため同社では問い合わせ件数の大幅削減とともに、営業の負担軽減にもつながりました。
参考:「リクナビの企業用ヘルプサイトでチャットボットが大活躍!高いROI目標値を試験運用から達成し、その後のサポートセンターへの問い合わせ数は34.8%削減。」
窓口業務の8割削減と出願数20%増を同時に実現
専門学校を運営する穴吹カレッジグループは、生成AIチャットボットの導入により、窓口業務を約8割削減し、さらに出願数を前年比20%増加させる成果を上げました。
同校ではこれまで、ホームページ上で必要な情報が見つけにくく、多くの問い合わせが発生していました。特に入学説明やオープンキャンパスの詳細など、基本的な質問への対応に多くの時間を費やしていたのです。
そこで生成AIチャットボットを導入し、利用者が24時間ストレスなく情報にアクセスできる環境を整備。これによりチャット利用数は前年比327%に増加し、入学希望者の利便性向上が出願数の増加にもつながりました。
さらに、問い合わせが集中する時期でも夜間対応が不要となり、スタッフの業務負担も大幅に軽減されています。
参考:「生成AIチャットボットの導入で入学希望者とのコミュケーションを増やしてエンゲージメントを強化。窓口業務の8割を削減しながら初回出願数を20%増!」
少人数体制でも対応件数が2倍に
お弁当のテイクアウト事業を展開する株式会社ほっかほっか亭総本部は、生成AIチャットボットの導入により、限られた人員のまま対応可能件数を1年で2倍に拡大しました。
導入前は、電話やウェブ経由で毎日多数の問い合わせが寄せられ、内容もキャンペーン情報など定型的なものが多く、スタッフの負担となっていました。
そこで、業務効率の向上と顧客満足の両立を図るため、24時間対応が可能な生成AIチャットボットを導入。これにより営業時間外でも対応が可能になり、問い合わせ対応にかかる人的リソースが大幅に削減されました。
さらに、スタッフはチャットの会話ログを確認できるため、回答の質の均一化やナレッジ共有にもつながり、サポート全体の品質向上にも貢献しています。
参考:「少人数でも対応件数は、2倍!PEPはカスタマーセンター全スタッフの右腕」
問い合わせ対応業務を66%削減、3部門で業務効率が大幅改善
東洋エンジニアリング株式会社は、総務・人事・ITの3部門で生成AIチャットボットを導入し、社内問い合わせ対応業務を約66%削減することに成功しました。
導入前は、従業員からの操作方法や制度に関する基本的な問い合わせが多く寄せられ、各チームの本来業務に支障を来していました。さらに、海外拠点との時差によるタイムラグもコミュニケーションの課題となっていました。
こうした状況を踏まえ、共通FAQやマニュアルを整理・体系化し、生成AIチャットボットによる自動応答体制を構築。時間や言語の壁を越え、迅速かつ正確に回答できる環境を整えました。
結果として、繰り返し寄せられる定型的な質問の対応が不要となり、各チームはより付加価値の高い業務に集中できるようになっています。
参考:「人事部門の3つのチームで約66%のお問い合わせ削減 従業員から愛されるAIチャットボットAKANEちゃん」
チャットボット導入で電話問い合わせを24%削減
株式会社ゲオでは、生成AIチャットボットを導入することで、社内からの電話問い合わせ件数を24%削減することに成功しました。
同社は、DVD・コミックレンタルやゲーム買取を展開する「ゲオショップ」、総合リユースの「セカンドストリート」など、国内外に約2,000店舗を展開。月あたり8,000〜13,000件にものぼる社内問い合わせの多くは、マニュアルを参照すれば解決できる基本的な内容でした。
こうした状況を改善するため、生成AIチャットボットを社内向けに導入。マニュアルの検索性が向上したことで、店舗スタッフが必要な情報に素早くアクセスできるようになり、電話問い合わせの大幅な削減に寄与しました。
その結果、サポートスタッフの業務負荷が軽減されるとともに、店舗現場の生産性向上にもつながっています。
参考:「導入後2年間、毎月5,000人以上が利用。店舗スタッフから社内問い合わせ窓口への電話問い合わせを24%削減。」
月間80〜100時間の問い合わせ対応を削減
メガネ専門店「Zoff」を展開する株式会社インターメスティックでは、社内ヘルプデスク業務の効率化により、月あたり80〜100時間の問い合わせ対応工数を削減することに成功しました。
同社の情報システム部は店舗からの問い合わせ対応を担っていましたが、繁忙期やシステム変更時には問い合わせが集中し、対応に追われていました。とくにレジや店舗管理システムに関する技術的な質問は店舗側での自己解決が難しく、電話対応が常態化していたのです。
こうした課題に対し、社内アシスタントとして生成AIチャットボットを導入。マニュアルや対応ナレッジをAIに学習させた結果、導入からわずか2ヶ月で電話対応の問い合わせがほぼゼロに。
さらに、LINE WORKS経由の個別チャットでの問い合わせも3分の1以上削減されるなど、現場と本部双方の負担を大幅に軽減しています。
社内資料の検索時間を3分の1に短縮
老舗ながら革新を続ける多角経営企業である株式会社カクイチでは、生成AIチャットボットの導入により、社内資料の検索にかかる時間を従来の3分の1に短縮することに成功しました。
同社では社内ポータルの情報が増える一方で、社員が目的の資料を探すのに手間がかかり、検索効率の低下が課題となっていました。
そこで、生成AIチャットボットに社内のよくある問い合わせや情報構造を学習させ、検索業務の自動化を実施。質問に自然言語で答える仕組みを整えました。
その結果、資料検索にかかる時間は平均30秒から10秒へと大幅に短縮。全社的な業務効率の向上と工数削減に貢献しています。
参考:「資料検索にかかる時間が3分の1に。導入担当者は社長賞を受賞!」
チャットボット経由での集客がわずか4ヶ月で100件に
不動産会社・株式会社フージャース コーポレーションでは、生成AIチャットボットを導入したことで、わずか4ヶ月間で100件以上の集客を実現しました。
同社は以前、ウェブサイト経由の問い合わせ数が伸び悩んでおり、潜在顧客との接点拡大が課題でした。
そこでLINE公式アカウントと連携可能な生成AIチャットボットを活用。ユーザーの興味や状況に応じたスムーズな対話が可能になり、資料請求やモデルルーム来場予約が大幅に増加しました。
この結果、不動産購入意欲の高い見込み客を効率よく獲得できるようになり、成約数も着実に伸びています。
参考:「チャットコマース経由の集客は4ヶ月で100件超!新たな集客・販売の形を切り拓くフージャースの不動産マーケティング」
離脱ユーザーのコンバージョン率が2倍に向上
スキマバイトサービスを展開する株式会社タイミーは、広告からLP(ランディングページ)へ誘導したユーザーのうち、サービス利用へと移行する「コンバージョン率(CVR)」を2倍に引き上げることに成功しました。
従来は広告流入は一定数あったものの、LP閲覧後に離脱しようとするユーザーへのフォローが不十分で、潜在的な利用者を取りこぼしてしまうという課題がありました。
そこでユーザーをLINEへ誘導し、生成AIチャットボットで質問に対応する仕組みを導入。チャットボットがユーザーの悩みや状況を読み取り、最適な情報やアクションを提案することで、離脱を防ぎながら関係性を深めることができました。
その結果、資料請求だけでなく、アカウント開設や求人掲載といった本質的なCVにもつながり、実効性の高い施策として機能しています。
参考:「ユーザー転換率2倍を超える会話体験で、急拡大するワーカーと事業者双方のスキマ時間ニーズをつなぐ」
EC購入率が150%アップ
ペットフードやペットケア事業を手がける犬猫生活株式会社では、ECサイトにおける購入率が150%アップする成果を上げました。
従来の課題は、人的リソースの不足により、LP(ランディングページ)から離脱したユーザーへのフォローが難しく、購入機会を逃していた点にありました。
そこで導入したのが、ユーザーの悩みや関心を丁寧にヒアリングできる生成AIチャットボット。適切なタイミングで最適な情報を届けることで、離脱したユーザーの購入率が着実に改善しました。
さらに、チャットボット提供企業からのシナリオ設計支援や広告クリエイティブ改善のアドバイスも後押しとなり、全体的な成果の底上げにつながっています。
参考:「犬猫生活がビジョンの共感を生みながらEC購入率150%アップを実現した秘訣とは」
新規顧客獲得数が110%に増加
英会話サービスを展開する株式会社NOVAランゲージカンパニーでは、生成AIチャットボットの導入により、新規顧客の獲得数を前年比110%まで伸ばすことに成功しました。
同社が抱えていた課題は、英語学習に関心はあるもののハードルを感じて申し込みに至らない層や、他社と比較検討中に離脱してしまうユーザーの取りこぼしでした。また、コロナ禍以降は対面型スクールからの離脱が進み、Webサイト訪問者のコンバージョン最大化が急務となっていました。
そこで、ユーザーの興味や不安に寄り添った会話をAIが行い、申込へとつなげていくチャットボットを導入。ユーザーごとに最適な案内を行うことで、来校・申込に至るケースが増え、コンバージョン率の向上に貢献しています。
参考:「厳しい費用対効果基準をクリア。 新規獲得数110%のチャットコマース®運用施策とは」
休業中にも100件以上の入庫予約を獲得
自動車販売を手がける岡山トヨペットは、生成AIチャットボットの導入によって、ゴールデンウィークのような長期休業期間中にもかかわらず、100件を超える入庫予約を獲得しました。
従来は電話やメールによる予約対応が主で、顧客と営業スタッフとの連絡の行き違いによる対応遅れや機会損失が課題となっていました。また、LINEも一方的な情報配信にとどまり、予約にはつながりにくい状況でした。
そこでLINEと連携し、双方向のコミュニケーションが可能な生成AIチャットボットを導入。ユーザーがいつでも簡単に予約を完了できる環境を整えました。
その結果、休業中にも安定した予約が入り、アカウント登録数の増加とあわせて、継続的な成果につながっています。
参考:「継続意向は95%!岡山トヨペットはLINEチャットボットで「やさしいデジタル」を推進し、さらなる顧客満足度向上を目指す。」
SNS診断コンテンツの完了率が約90%を達成
化粧品を展開する資生堂は、日焼け止め商品の「アネッサ」について発信するSNS診断コンテンツの完了率90%達成に成功しました。
同社は、「アネッサ」の魅力を伝え、購買意欲をアップさせる計画を立てていました。しかし、日焼け止めは夏だけ使うイメージが強いうえ、チャットボットは無機質で購買行動につながりにくいという懸念が課題になっていました。
そこで、Instagram内で完結する「肌悩みに応じたUVジェル診断コンテンツ」を開発。各ユーザーに最適な商品を診断するというもので、生成AIチャットボットの導入により診断コンテンツの完了率が90%を超えました。
結果として顧客の体験品質向上やブランド理解につながり、チャット診断を受けた約20%が、24時間以内に商品を購入したと回答したと報告されています。
参考:「資生堂「アネッサ」が目指すインタラクティブなコミュニケーションとは?ブランド理解を深めるInstagram版チャットコマース」
導入からわずか3ヶ月で申込件数が480%に増加
株式会社仙台銀行では、生成AIチャットボットの導入により、Web経由の個人ローン申込件数が導入前比で480%に増加しました(導入からわずか3ヶ月での実績)。
同社では従来、Webサイトを訪問した顧客の多くが途中で離脱してしまい、店頭のような丁寧な接客がオンライン上では実現しにくいという課題を抱えていました。
この課題に対して、生成AIチャットボットを活用し、ユーザーの関心や状況に応じた診断コンテンツや継続的なプッシュ配信を強化。さらに、ユーザー行動データをもとにチャットのシナリオを随時改善しました。
結果として申込件数の大幅な増加につながり、追加の人件費や広告費をかけずに、着実な成果を生み出しています。
参考:「【仙台銀行×ZEALS】わずか3ヶ月でチャットコマース経由のローン獲得件数480%UP!!競争力強化につながるリテールバンクのDX施策」
チャットボット導入で顧客満足度90%を実現
東京電力エナジーパートナー株式会社では、カスタマーセンターに生成AIチャットボットを導入した結果、顧客満足度90%を達成しました。
従来は、月間100万件以上の問い合わせを電話で対応しており、オペレーターの負担が大きく、FAQの使いにくさや情報の分散、入電後の処理の煩雑さなど、複数の課題を抱えていました。
チャットボット導入後は、1日あたり約15,000件の問い合わせを自動対応できるようになり、多くの顧客が手軽に利用可能に。さらに対応件数も大幅に改善。電話対応では1時間あたり約3件が限界だったのに対し、チャットでは1時間あたり6件以上を安定して処理できるようになりました。業務効率と顧客体験の両面で大きな成果を上げた事例です。
参考:「未来を支え続ける柔軟性を強みに 最良のエクスペリエンスを徹底追求」
生成AI×チャットボットの失敗事例
多くの企業が生成AIチャットボットの導入によって成果を上げていますが、必ずしもすべての導入事例が成功しているわけではありません。ここでは、よく見られる4つの失敗パターンを紹介します。自社で導入を検討・実施する際のリスク回避に、ぜひお役立てください。
回答の精度が低い
十分なデータ準備やシナリオ設計を行わないまま導入を急ぐと、ユーザーの質問意図を正確に把握できず、誤回答や曖昧な返答が発生しやすくなります。その結果、顧客の信頼を損ない、追加の問い合わせ対応が発生して、かえって業務負荷が増えることも。
導入前に、想定される質問に対する回答パターンやユーザー行動を十分に設計・準備し、実用性のあるAI運用を心がけましょう。
ユーザーのニーズに応えられない
自動応答が定型的・表面的にとどまり、個別の悩みやイレギュラーな要望に対応できない場合、ユーザーから「役に立たない」と見なされてしまいます。結果として人間のオペレーター対応が必要になり、顧客満足度の低下に加え、企業側の業務負荷も増加してしまう恐れがあります。
こうした事態を防ぐには、ユーザーの具体的な質問傾向や過去の問い合わせ履歴を分析し、「よくあるが複雑な質問」や「感情を伴いやすい質問」に先回りして対応できる設計が重要です。
また、シナリオ型チャットボットだけでなく、FAQデータベースと連動した自然言語処理モデルを併用するなど、複数の回答手段を柔軟に組み合わせたハイブリッド運用も有効です。
運用フェーズでは、一定期間ごとに離脱ポイントやユーザー満足度を可視化し、対話ログに基づいたシナリオの精査・再設計を習慣化することで、継続的なパフォーマンス向上につながります。
費用対効果が感じられない
コスト削減や業務効率化を期待して生成AIチャットボットを導入しても、「想定より効果が出ない」「結局コストがかかる」と感じるケースは少なくありません。
このような結果に陥る主な原因は、初期費用や運用コストの見積もりが甘いこと、そして目的やKPIが不明瞭なまま導入を進めてしまうことにあります。
費用対効果を最大化するには、まず自社にとってのチャットボット導入の“目的”を明確にし、「削減したい工数は何か」「何件の対応が人手から移行できるか」などのシナリオベースで仮説を立てることが重要です。
加えて、ROI(投資対効果)を見積もるシミュレーションを事前に行い、数値目標を立てることで、導入後の検証もしやすくなります。さらに運用開始後も、ログ分析やユーザー満足度調査をもとに改善を重ね、定期的に“見直せる仕組み”を組み込んでおくことが鍵になります。
運用が停滞してしまう
生成AIチャットボットは導入がゴールではありません。むしろ導入後こそが本番です。しかし、担当者の異動や社内体制の変化、業務の繁忙などにより、改善やメンテナンスが後回しにされ、放置されてしまうケースが少なくありません。
このような「放置ボット」化を防ぐには、単に担当者を決めるだけでなく、定期的なログ分析・改善プロセスをルーティン化することが不可欠です。
また、KPI(例:自己解決率、チャット利用率、CSスコア)を明確に設定し、成果を可視化できる体制を整えることで、社内での合意形成や優先順位づけもしやすくなります。
さらに、現場が安心して使えるよう、FAQ更新のフローや簡易な運用マニュアルを整備し、属人化を避けることも重要です。定期的な社内研修や勉強会を通じて関係者の理解と関与を促し、組織全体での活用推進を図りましょう。
生成AI×チャットボットの導入を成功させるコツ
生成AIチャットボットの効果を最大化するには、以下の4つのポイントを押さえることが重要です。
- 明確な目標を設定する
- 社内運用体制を整える
- 有人チャットと適切に使い分ける
- 導入後も継続的に改善する
それぞれ順に解説していきます。
明確な目標を設定する
生成AIチャットボットの導入を成功させるには、「なぜ導入するのか」「何を達成したいのか」を最初に明確にしておくことが不可欠です。
例えば、「問い合わせの自動化率を◯◯%まで向上させる」「顧客対応時間を平均◯分短縮する」など、定量的なKPIを設定しましょう。こうした指標があれば、導入後の効果測定がしやすくなり、改善ポイントも見えやすくなります。
社内運用体制を整える
チャットボットは導入して終わりではありません。効果を継続的に発揮させるには、アップデート・改善を回せる運用体制が必要です。
- シナリオやFAQの見直し
- ユーザーログの分析
- AIへの再学習や改善対応
これらを担える担当者やチームを明確にしましょう。また、マニュアルやナレッジを残し、体制変更時にも継続できる仕組みを作っておくことが重要です。
有人チャットと適切に使い分ける
生成AIチャットボットは万能ではありません。効果的に活用するには、人間による対応とのハイブリッド運用がカギとなります。
- 定型的な質問やよくある問い合わせ → チャットボットが対応
- クレームや個別事情を含む複雑なケース → 有人チャットへ引き継ぐ
こうした棲み分けを事前に定め、ユーザーが迷わず最適なサポートを受けられるように設計しましょう。
導入後も継続的に改善する
生成AIチャットボットは、使いながら育てるものです。初期の設定で満足せず、実際のユーザー行動に基づいて調整を続けることが重要です。
- ログデータやユーザー評価を定期的に分析
- 新たな質問傾向やニーズに応じて応答内容を更新
- 導入時に立てた目標と成果を定期的に照合
このようにPDCAを継続することで、チャットボットの精度や価値は着実に高まっていきます。
まとめ:生成AI×チャットボットで新たな業務改革を
生成AIチャットボットは、問い合わせ対応の効率化だけでなく、業務改革や顧客体験の向上につながる強力なツールです。
しかし、ただ導入するだけでは十分な成果は得られません。重要なのは「導入後の活用」です。本記事で紹介した成功のコツを参考にしながら、自社に合った運用スタイルを構築していきましょう。SHIFT AIではAIの使い方や導入に関することなど、幅広い相談を無料で受け付けています。また、AI人材の育成支援やワークショップも実施しています。AIの活用を検討している方はぜひお気軽にご相談ください。