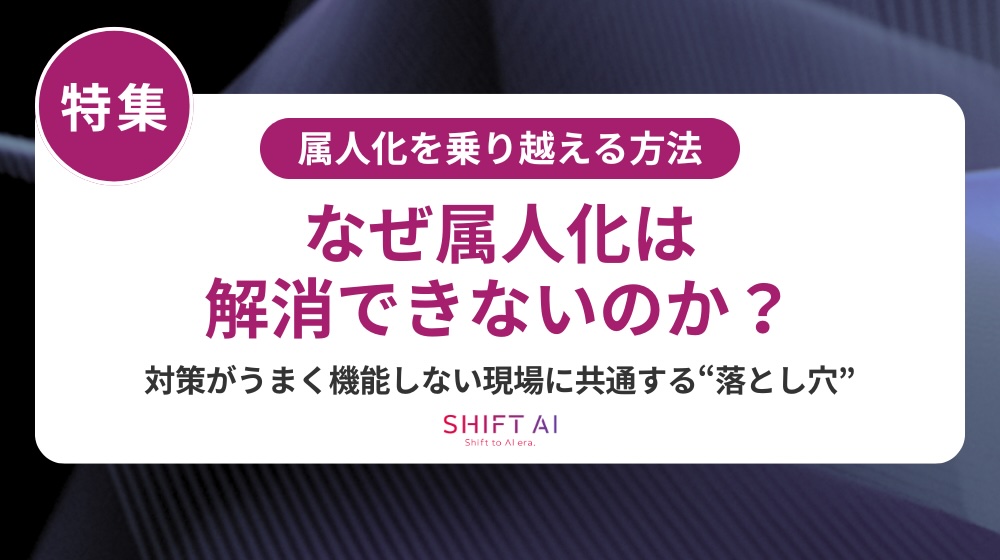「あの人が休んだら、業務が止まる——」
そんな状況に、心当たりはありませんか?
属人化とは、業務の知識や手順が特定の担当者に依存してしまい、他のメンバーが代わりに対応できない状態のことです。
一見、頼れる存在のように見えても、その人がいないと回らない状態は、チーム全体にとって大きなリスクになります。
とくに問題になるのが、「休めない」という状況です。
代替要員がいないために有休が取れず、万一休んでも、連絡が絶えず心から休めない——。
これは本人の責任ではなく、組織としての仕組みの問題です。
本記事では、属人化によって生まれる「休めない職場」の構造を分解し、誰もが安心して休めるチームをつくるための具体策を紹介します。
さらに、生成AIなどのツールを活用して、マニュアル整備やスキル共有を効率化する方法も解説します。
「誰がいても回る」チーム作りの第一歩として、ぜひ参考にしてください。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ属人化すると「誰かが休めなくなる」のか?
「この仕事は〇〇さんにしかできない」
そんな状況が続いていると、その担当者がいないと業務が回らないという属人化の状態が生まれます。
問題は、これは本人の努力や能力に依存しているのではなく、業務の仕組みや情報共有の在り方に原因があるという点です。
ここでは、属人化によって「誰かが休めなくなる」理由を3つの視点から解説します。
業務が担当者の頭の中だけにある
多くの職場では、「業務の手順」や「判断の基準」が文書化されておらず、担当者本人の経験や勘、慣れに依存しているケースが少なくありません。
業務が見える化されていなければ、他のメンバーが代行しようにも何をどう進めればよいのかわからず、結果として「あの人がいないと何もできない」状態になります。
スキルや情報が特定の人に集中している
属人化が進むと、知識やノウハウだけでなく、取引先との関係、操作できるツール、過去の経緯などの情報も、特定の人に集約されがちです。
結果として、その人がいないと問い合わせに対応できず、業務がストップしてしまう。
これでは安心して休むことができません。
「この人でないとできない」という文化が残っている
属人化が起こる背景には、“属人性を評価する空気”がある場合もあります。
「〇〇さんにしかできない」「〇〇さんがやった方が早い」といった文化が続くと、周囲は学習・習得の機会を得られず、属人化が固定化されていきます。
本人も「自分しかできないから休めない」と思い込んでしまい、負のループから抜け出せなくなるのです。
「休めない社員」がいることによる3つのリスク
属人化により、特定の人が「休めない」状況に陥っている場合、その影響は本人の働き方だけにとどまりません。
放置すれば、チーム全体のパフォーマンスや組織の継続性にまで深刻な影響を及ぼします。
ここでは、属人化がもたらす3つの主要なリスクを見ていきましょう。
担当者の疲弊・離職につながる
「自分しかできない」というプレッシャーは、見えない負担として蓄積されます。
代われる人がいないために、有給も取れず、休日も連絡が絶えない——
こうした状況が続けば、心身ともに疲弊し、最終的にはモチベーションの低下や退職につながる可能性があります。
せっかくのスキルや経験も、属人化によって本人の負担になってしまっては本末転倒です。
業務の継続性・品質が低下する
属人化された業務は、代替が難しいだけでなく、再現性も低くなります。
万が一担当者が急に休んだ場合、業務が止まったり、クオリティが著しく下がったりする恐れがあります。
このように、業務が「人にひもづいている」状態は、組織としての脆弱性を生む要因となります。
チーム全体の生産性が下がる・連鎖的な属人化を生む
特定の人に負荷が集中すると、他のメンバーは「どうせ〇〇さんがやる」となり、学習や代替スキルの習得機会が減っていきます。
その結果、属人化が連鎖的に広がり、誰も手を出せない業務が増加。
仕事の分担や最適配置ができず、チームの生産性が下がる悪循環に陥ります。
関連記事:「全部自分で抱えて疲れた…」属人化が進む職場の問題と抜け出す方法を解説
誰もが休める組織にするための5つの実践ステップ
属人化をなくし、「誰がいても業務が止まらない状態」をつくるには、属人化の可視化→分散→標準化→共有の流れを、意図的に仕組み化していく必要があります。
ここでは、「属人化によって休めない社員」をなくすための5つのステップを紹介します。
チームや組織単位で段階的に取り入れていくことができます。
【H3】1.業務の棚卸しと属人化レベルの可視化
まずは現状把握から。
「誰が」「どの業務を」「どのくらいの頻度・重要度で」行っているのかを洗い出し、
属人度の高い業務を明確にします。
特に重要なのは、以下のような視点で分類することです。
- 定型業務/非定型業務
- 代替可能性の有無(その人以外が対応可能か)
- 属人化スコア(高・中・低)
表形式や業務マトリクスを使って見える化することで、
偏りやリスクの所在が明らかになります。
関連記事:業務の棚卸し、どう進める?方法・失敗例・AI活用まで徹底解説
2.担当者以外でも回せる「マルチスキル設計」
属人化の根本対策は、特定の人だけに頼らない体制づくりです。
「常に2名以上が担当できる状態」を目指して、スキルの平準化を図りましょう。
- OJTやペアワークでのスキル移転
- 定期的な担当業務のローテーション
- あえて「教える日」を設ける
属人化を防ぐには、“教えることを前提とした働き方”が求められます。
3.マニュアル・FAQ・業務フローの整備
スキルだけでなく、業務の再現性そのものを高めるための文書化も不可欠です。
属人化していた判断・手順を形式知に変えることで、誰でも代替可能な状態に近づけます。
おすすめのフォーマット
- 業務マニュアル(操作・フロー手順書)
- よくある問い合わせ対応集(FAQ)
- 「例外対応の判断基準」も含めた分岐図
定期的な更新ルールも設定しておくと、形骸化を防げます。
4.引き継ぎ・共有の“仕組み化”
属人化の防止は、一度きりの対策ではなく“継続的な運用”が命です。
たとえば、
- 月1回の業務棚卸しミーティング
- 属人化度を可視化するスコアシートの定着
- 「この業務、そろそろ別の人にも引き継げそう?」のチェック文化
「できる人がやる」から、「誰でもできるようにする」へ意識を変えていくことが重要です。
5.休暇制度と連動した業務設計
本当に休める組織にするには、休暇前提の業務設計が必要です。
属人業務があるままでは、休む=業務停止になってしまいます。
対策例
- 休暇予定をもとに事前の業務分担をシミュレーション
- 繁忙期にはサブ担当者を明確化
- 有給取得率をKPIに含め、マネジメント評価に連動
「誰かがいなくても仕事が回る」ことを前提に体制を設計していくことが、長期的に持続可能な組織づくりにつながります。
AIを活用した“属人化の見える化”と“仕組み化”支援
「業務の見える化」「マニュアル整備」は大切とわかっていても、忙しい現場では、誰が・いつ・どうやって文書化するのかが課題になりがちです。
そこで活躍するのが、生成AI(ChatGPTやNotionAIなど)を活用した属人化対策です。
業務の整理や共有にかかる手間を大幅に削減し、誰もが休める組織を、よりスピーディに実現できます。
ChatGPT×業務ヒアリング→自動マニュアル生成
ChatGPTを使えば、属人化された業務の中身を会話ベースで引き出し、文書化できます。
たとえば
- 担当者に「どうやって進めているか」をヒアリング形式で聞く
- ChatGPTにその内容を入力・要約させる
- 「判断基準」「分岐パターン」まで含めて手順書化
この流れを繰り返すだけで、業務マニュアルの“下書き”が自動的に完成します。
NotionAIや音声入力ツールで日常業務を可視化
会議の議事録や、日報、作業中の録音などをNotionAIに読み込ませることで、重要ポイントだけを抽出→引き継ぎ用ドキュメントに変換することが可能です。
- 会話をテキスト化し、自動で構成・要点整理
- 属人化されていたやり取りも、チームで共有しやすくなる
- 操作手順も、録画×文字起こし×自動要約で“見える化”が進む
これにより、現場の負担を最小限にしながら属人化の壁を超えることができます。
SHIFT AIの「AI活用研修」で実現した属人化解消の事例
SHIFT AIでは、こうした生成AIの活用を現場に定着させるための
「AIによる業務のマニュアル化研修」を多数支援しています。
実際の事例では、
- 属人化されていた社内対応フローを1週間でドキュメント化
- 引き継ぎトラブルが激減し、有給取得率が改善
- 「誰が休んでも仕事が止まらない」チーム構築に成功
といった成果が出ています。
まとめ:その“休めない状況”、仕組みで変えられます
属人化された業務があると、「この人がいないと回らない」状態になり、その人が休むこと自体が難しくなってしまいます。
これは本人の問題ではなく、組織の構造や仕組みの課題です。
この記事では、「休めない社員」を生まないために、以下のポイントを解説しました。
- 属人化によって休暇取得が難しくなる原因とリスク
- 可視化・分担・標準化を通じた、誰もが休めるチームの作り方
- 生成AIなどを活用した、マニュアル化・引き継ぎの効率化
重要なのは、属人化を「個人任せ」にせず、チームと仕組みで解消する視点を持つこと。
そしてその仕組み化は、生成AIの力を借りることで、無理なく現場に定着させることが可能です。
- Q属人化とはどのような状態を指しますか?
- A
.属人化とは、特定の人に業務の知識・手順・判断が集中し、他の人が代替できない状態を指します。
業務が可視化されていなかったり、マニュアルがなく本人の経験則に頼っている場合に起こりやすく、休暇取得や業務継続の妨げになります。
- Qなぜ属人化は「休めない」状態につながるのですか?
- A
属人化された業務は、他のメンバーが引き継げないため、担当者がいないと業務が滞ってしまいます。
その結果、有休が取りづらく、体調不良や家庭事情でも「自分がやらなければ」というプレッシャーから休めない状況に陥りがちです。
- Q属人化を防ぐには何から始めればいいですか?
- A
最初の一歩は「業務の棚卸し」です。
誰がどの業務を担当していて、どのくらい属人化されているかを可視化し、
優先度に応じてマルチスキル化・マニュアル化・分担化を進めると効果的です。
- Q業務が忙しく、マニュアル作成や共有に手が回りません…
- A
そのような現場こそ、生成AIの活用が有効です。
ChatGPTを使えば、会話形式で業務内容を語るだけで、
手順書やQ&Aの草案が自動生成されます。
NotionAIや音声文字起こしツールと組み合わせることで、文書化の負担を大幅に軽減できます。
- Q属人化の解消やAI導入に不安があります。サポートは受けられますか?
- A
はい。SHIFT AIでは、属人化を解消するための業務マニュアル化支援や生成AI研修を多数ご提供しています。
業務の見える化や仕組み化を実現するための伴走支援や研修資料もございます。お気軽にご相談ください。