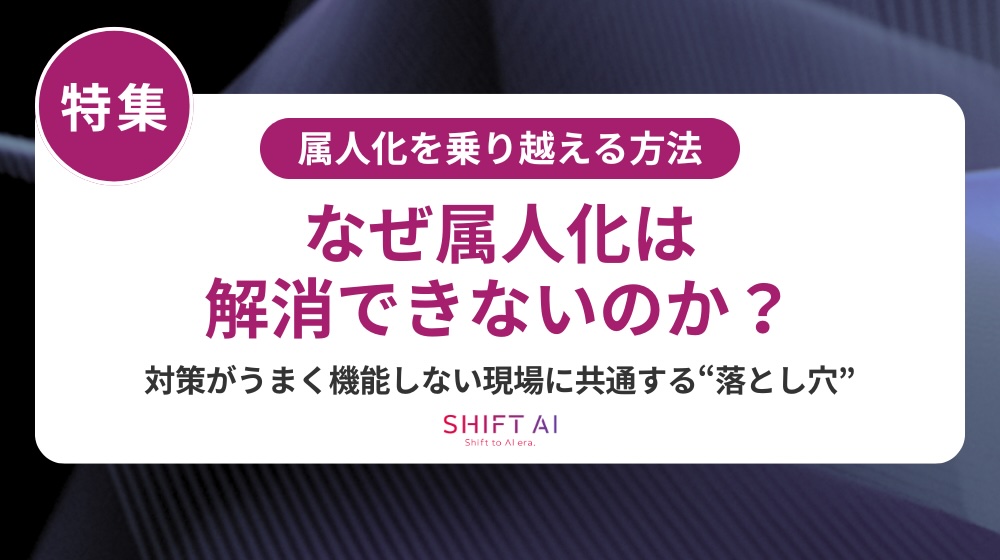「このプロジェクト、○○さんにしかわからないんです…」
そんな言葉が日常的に飛び交う職場では、“属人化”が深刻な課題になっているかもしれません。担当者の頭の中にしかない情報、他の社員が手を出せない作業、一人に依存してしまった判断ルール。
そのまま放置しておくと、担当者の退職や異動が引き金となって、業務の停滞やトラブル、品質低下につながる可能性があります。
とくに中間管理職や情シス部門では、
「引き継ぎをうまくやりたいけれど、何から始めればいいかわからない」
「そもそも業務がブラックボックス化していて手のつけようがない」
そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、属人化された業務やプロジェクトを、再現性のあるかたちでスムーズに引き継ぐ方法を解説します。
単なる引き継ぎマニュアル作りではなく、組織全体で“仕組みとして回せる状態”を作ることが目的です。さらに後半では、生成AIを活用して属人化を効率的に解消した事例も紹介します。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
そもそも「属人化された引き継ぎ」はなぜ起こるのか?
属人化は、突然始まるわけではありません。日々の業務の中で少しずつ、「この人にしかできない」「あの人に聞かないとわからない」という状態が積み重なっていきます。
引き継ぎの場面で初めてその属人化が“問題”として表面化することも少なくありません。
ここではまず、属人化とは何か、なぜ引き継ぎの場面で問題になるのかを整理していきます。
属人化とは?定義と引き継ぎに起きる問題
属人化とは、「特定の業務やプロジェクトが、特定の人に依存してしまっている状態」のことを指します。業務の手順・判断基準・過去の経緯などが、その人の頭の中にしか存在していない状態です。
こうした属人化が引き継ぎの場面で問題になるのは、再現性がないからです。
誰かが異動・退職したときに、業務を正しく引き継ぐためには、
- 「どんな業務が存在していて」
- 「どのような手順で実行され」
- 「どんな判断ポイントがあり」
- 「誰と連携していて、どんなルールがあるか」
といった情報が必要です。
しかし、属人化された業務では、こうした情報が言語化・可視化されていないため、
「引き継ぎ期間が足りない」
「引き継がれたけど、細かいところは分からない」
「トラブルが起きても誰にも聞けない」
といった問題が頻発します。
👉 関連記事
業務が属人化している企業必見|AI活用による段階的解決の方法
よくある失敗パターン3選
属人化された業務の引き継ぎがうまくいかないケースには、いくつかの典型パターンがあります。ここでは代表的な3つを紹介します。
パターン①:マニュアルが形骸化している
「マニュアルはあるけれど、誰も見ていない」
「更新されておらず、現場のやり方とズレている」
こうしたマニュアルは、引き継ぎ時にほとんど機能しません。属人化された業務ほど、実際のやり方は“現場の感覚”に依存していることが多いためです。
パターン②:OJTだけで引き継ぎを終わらせてしまう
口頭で伝えるOJTは一見効率的ですが、「聞いたけど忘れた」「タイミングが悪くて聞けなかった」など、記録に残らないリスクがあります。
また、人によって伝える内容が変わるなど、属人化を助長する側面もあります。
パターン③:判断基準が明文化されていない
属人化された業務では、「なぜその判断をしたのか?」という根拠がブラックボックス化しがちです。
これにより、引き継ぎ後の担当者が迷い、誤った判断や業務の遅延につながるケースもあります。
このように、属人化の本質的な問題は“情報の非構造化”にあります。
属人化された業務を引き継ぐための【5つのステップ】
属人化を解消し、誰でも再現可能なかたちで業務を引き継ぐには、「仕組み化」が必要です。ただマニュアルを用意するだけでは不十分で、業務の全体像や判断基準、背景となる情報まで含めて、構造的に整備していく必要があります。
ここでは、属人化を解消するために有効な5つのステップを紹介します。
STEP1:業務の棚卸しと可視化
まずは、属人化されている業務を正確に把握することから始めましょう。担当者が「普段やっていること」をすべて書き出してもらい、それを業務一覧として整理します。
このとき、関係者とのヒアリングを通じて、どの業務がどのように他部門と連携しているかもあわせて確認します。業務フローや関係図など、視覚的に整理すると全体像を掴みやすくなります。
STEP2:プロセスの分解と文書化
次に、各業務のプロセスをステップごとに分解し、それぞれのやり方や判断基準を文章化していきます。属人化された業務では、「感覚的にやっている」「前例にならっている」といった曖昧な工程が多く見られます。
そこを明文化し、チェックリストや操作手順として整理することで、他者にも再現可能な状態になります。また、生成AIを活用すれば、口頭説明や箇条書きのメモをもとに、簡単に手順書やFAQを生成できます。
STEP3:ナレッジの共有・レビュー体制の構築
文書化した内容は、必ず第三者にレビューしてもらうことが重要です。本人が「当然」と思っていた情報が、他者にとっては理解できないということはよくあります。
チーム内でレビューを重ねることで、文書の精度と共有性を高めていきましょう。ドキュメントは社内のナレッジベースや共有ドライブなどに一元管理し、誰でもアクセスできるようにすることが望ましいです。
STEP4:トレーニングと段階的な引き継ぎ実践
整備された業務マニュアルをもとに、新しい担当者へ引き継ぎを行います。一度にすべてを渡すのではなく、重要度や頻度に応じて段階的に移行するのがポイントです。
シミュレーションやペアワーク、ロールプレイングなどの形式で実務経験を積ませながら、現場に馴染ませていきます。引き継ぎ期間中は、旧担当者がサポート役としてつき、質問や不明点に随時対応できる体制を用意しましょう。
STEP5:定期更新と継続改善の仕組みを作る
一度マニュアルや手順書を作成しても、それを放置すれば再び属人化が進んでしまいます。定期的な見直しと改善を前提にした体制を組むことで、属人化の再発を防ぐことができます。
たとえば「ドキュメント責任者」を設けて更新のタイミングを管理したり、チーム内で月に一度ナレッジレビュー会を実施するなど、仕組みとして継続できるよう工夫しましょう。
生成AIを使えば属人化はもっと早く、確実に解消できる
属人化の解消には、「可視化」「構造化」「再現性の担保」という地道なプロセスが必要です。しかし、それをすべて人手で進めようとすると、膨大な時間と労力がかかります。
そこで注目されているのが、生成AIによる業務の文書化・ナレッジ整備の自動化です。属人化の課題に直面している企業にとって、生成AIは“仕組み化”を一気に前進させる強力なツールになります。
AIでできること:業務内容の要約・FAQ化・文書生成
たとえば、属人化されていた業務について、担当者にヒアリングした内容を録音・文字起こしし、その内容をもとに生成AIに指示を出すだけで、業務マニュアルや手順書、FAQの原稿が自動的に生成されます。
ChatGPTのような自然言語処理モデルであれば、「この業務の目的と手順を整理してください」といった曖昧な指示でも、構造化されたアウトプットが得られます。
加えて、属人化されがちな例外対応や判断基準についても、AIが文章として整えてくれるため、引き継ぎ文書としての精度が格段に高まります。
👉【関連記事】
属人化を防ぐ効果的な方法|AI活用で業務標準化を実現する実践ガイド
👉【関連記事】
若手が育たない職場の特徴とは?属人化を防ぎ育成を仕組み化する3つのステップと成功事例
引き継げる組織にするために、今すぐ始めること
属人化の解消は、決して一部の人だけが頑張って達成できるものではありません。組織全体で“再現性のある業務”を回す仕組みを育てていくことが重要です。ここでは、誰でも今すぐ始められる2つのアクションを紹介します。
まずは「属人化業務リスト」を洗い出す
最初の一歩は、「何が属人化しているのか」を明らかにすることです。次のような視点で業務を棚卸してみましょう。
- 他の人では対応できない業務がある
- 作業のやり方が担当者の頭の中にしかない
- トラブル発生時、特定の人にしか判断できない
- マニュアルや引き継ぎ資料が存在しない
これらの項目に当てはまるものは、属人化リスクが高い業務です。チェックリスト形式で整理して、チーム全体で認識を共有するところから始めましょう。
👉【関連記事】
ルールがない職場の問題点と解決策|属人化を防ぐ現場発のルール作り
AI活用の第一歩:社内ドキュメント整備にGPTを使ってみる
属人化業務が見えてきたら、次にやるべきはドキュメント化です。とはいえ、「ゼロから書くのは面倒」「表現に自信がない」と感じる方も多いでしょう。そこで役立つのが生成AIです。
たとえば、「この業務の流れを説明してください」と担当者に話してもらい、その内容を録音して文字起こし。それを生成AIに渡して「業務手順として整理してください」とプロンプトを打てば、構造的な手順書やマニュアルのドラフトが完成します。今は“完璧”を目指すよりも、“動き出せる”状態を早く作ることが重要です。
まとめ:属人化の引き継ぎには、仕組みとAIの両輪が必要
属人化された業務は、その担当者がいなくなった瞬間に、大きなリスクへと変わります。
「引き継ぎができない」「業務が止まる」「新人が育たない」。
そうした問題を防ぐには、人に依存しない仕組みをつくることが欠かせません。
本記事で紹介した5つのステップを実行すれば、業務は再現性をもって回り始めます。さらに生成AIを活用することで、そのプロセスはよりスピーディかつ高品質に。今、属人化の課題に悩む企業こそ、AIという新しい力を取り入れるチャンスです。
SHIFT AIでは、属人化の可視化・文書化・定着につながる法人向け生成AI研修をご提供しています「うちの現場でもできそうだ」と思われた方は、ぜひ資料をご覧ください。
FAQ:属人化の引き継ぎに関するよくある質問
- Q属人化された業務は、どこから手をつければいいですか?
- A
まずは業務の棚卸しから始めましょう。「この作業、あの人しかできない」と言われている業務を洗い出し、ヒアリングや業務フロー図などで全体像を整理するのが第一歩です。
- Q属人化を解消するにはマニュアル化だけで十分ですか?
- A
マニュアル化は重要な要素ですが、それだけでは不十分です。誰が見ても理解できる構成にすること、定期的に更新する仕組みを作ることが必要です。生成AIを活用すれば、その負担も軽減できます。
- QAIを使った引き継ぎって本当に実用的ですか?
- A
はい。生成AIを使えば、音声やメモから高精度な手順書やFAQを作ることができます。SHIFT AIの研修でも、多くの企業が「生成AIの活用でドキュメント整備が早くなった」と実感しています。
- Q引き継ぎ期間が短い場合、どうすれば失敗を防げますか?
- A
段階的に引き継ぐことと、ドキュメントを中心とした“いつでも確認できる仕組み”がカギです。OJTや一時的な引き継ぎだけでなく、再現性を意識した文書化が効果的です。
- QSHIFT AIの法人研修では、どんなサポートが受けられますか?
- A
属人化業務の棚卸しから、生成AIを活用したマニュアル・ナレッジ整備、社員教育までを一貫して支援します。実際の活用事例やテンプレートも含まれた資料をぜひご覧ください。