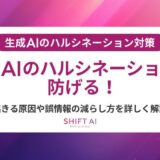AIやDXによる変化が加速する中で、これまでの“成功パターン”が通用しなくなっています。
いま多くの企業で注目されているのが、アンラーニング(unlearning)――過去の前提や思考習慣を手放す力です。
新しいスキルを学ぶ前に、まず「古い常識を疑う」こと。これが変化に強い人材の第一歩となります。
本記事では、アンラーニングを実践するための具体的なやり方・5つのステップを中心に、個人の成長と組織の変革を両立させる方法を解説します。
学び直し(リスキリング)を効果的に進めるためにも、まず“捨てる学び”を始めましょう。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
アンラーニングとは何か|「知識を増やす前に、思考を手放す」意味を理解する
アンラーニング(unlearning)とは、これまでの経験や常識をいったん手放し、新しい考え方を受け入れるプロセスのことです。
学びを止めるのではなく、“学びの前提をリセットする”行為といえます。
近年、AI・DXの進展によって、かつての成功モデルが急速に陳腐化しています。
「これが正しい」「こうすればうまくいく」といった思考の枠組みが、変化を妨げる“見えない壁”になるケースも少なくありません。
アンラーニングは、その壁を取り払い、新たな知を受け入れるための“下地づくり”です。
一方で、よく混同されるのがリスキリング(新しいスキルを学び直すこと)。
リスキリングは“学び足す”ことであり、アンラーニングは“学びを削ぎ落とす”こと。つまり、リスキリングの前段階にあるのがアンラーニングです。
古い前提を抱えたまま新しい知識を積み上げても、行動は変わりません。
まず「なぜ自分はそう考えるのか」を見つめ直すことが、変化に強い人材への第一歩です。
関連記事:アンラーニングとは?AI時代に求められる“学びを捨てる力”を解説
アンラーニングのやり方|個人で実践する5ステップ
アンラーニングは、ただ知識を忘れることではありません。
過去の成功体験や思考の癖をいったん疑い、より良い行動パターンへと再構築するプロセスです。
ここでは、誰でも今日から始められる実践ステップを5段階で紹介します。
STEP1:自分の「固定観念リスト」を書き出す
まずは、自分の中にある“当たり前”を可視化することから始めます。
「こうすべき」「このやり方が正解」と思い込んでいる仕事の進め方、人間関係、意思決定のルールなどをリストアップしましょう。
書き出すことで、自分の思考がどんな前提に支えられているかを客観的に見つめられます。
✏️ポイント:思いつかないときは「自分が他人に対してイラッとする瞬間」を振り返ると、固定観念のヒントが見つかります。
STEP2:「なぜそう思うのか?」を深掘りする
次に、それぞれの固定観念について「なぜそう思うのか」を問い直します。
たとえば「若手は上司の許可を取るべき」という考えなら、「それは誰に教わった?」「どんな経験からそう感じた?」と掘り下げてみましょう。
このステップで重要なのは、“信じてきた理由”を見つけることです。
理由が曖昧なものほど、変化への柔軟性を奪っている可能性があります。
💡コツ:一人で考えるより、信頼できる同僚やAIツール(例:ChatGPT)と“問い”を共有すると、新たな視点が得られます。
STEP3:異なる視点・環境に触れる
アンラーニングの核心は「自分とは違う世界に出会うこと」です。
他部署や異業種との交流、生成AIなど新しいツールの体験、異なる世代との会話――これらはすべて“思考の再構築”を促す刺激になります。
重要なのは、「理解できない」を拒絶せず、「どうしてそう考えるのか」を観察する姿勢。
自分の思考を一段上から見下ろすように捉えることで、思考の幅が広がります。
🧭実践例:月に1回、他部門の会議や勉強会に参加して“違和感ノート”をつけると効果的です。
STEP4:小さな実験で行動を変える
アンラーニングは頭の中だけでは進みません。
日常の中で“小さく試す”ことが大切です。
「いつもと逆の順序で仕事をしてみる」「あえて苦手な人の意見を先に聞く」など、行動の小さな実験を設定しましょう。
失敗しても構いません。重要なのは、「なぜうまくいかなかったか」を考えること。
行動の変化こそ、アンラーニングが“形になる瞬間”です。
🔁ポイント:「正しい方法」より「新しい発見」を評価する視点を持つと、継続しやすくなります。
STEP5:学びを再定義し、習慣化する
最後に、「新しく得た視点をどう日常に組み込むか」を考えます。
「この考え方は今も有効か?」「次に同じ状況が来たら、どう行動するか?」
定期的に振り返り、古い思考が戻っていないかを確認しましょう。
このサイクルを続けることで、“捨てる→試す→再定義”のループが自然に習慣化します。
📆実践法:週末や月初に“思考の棚卸しタイム”を設ける。短時間でも続けることで、思考の柔軟性が維持されます。
この5ステップを繰り返すことで、過去の成功体験に縛られず、新しい考え方を柔軟に受け入れられるようになります。
アンラーニングを習慣にする3つのコツ
アンラーニングは一度きりの学びではなく、思考を更新し続ける“習慣”として定着させることが重要です。
ここでは、日常の中でアンラーニングを自然に続けるための3つのポイントを紹介します。
1. 「内省の時間」をスケジュールに組み込む
アンラーニングの第一歩は“気づくこと”です。
そのためには、日常の中に自分の思考を振り返る時間を意識的に設ける必要があります。
1日10分でも構いません。
「今日は何を当たり前だと思って行動したか?」と問い直すだけで、思考の硬直を防げます。
💡ヒント:NotionやGoogleカレンダーに「リセットタイム」を設定し、AI日報やメモツールを使って記録するのもおすすめです。
2. 「正解を求めない」マインドを持つ
アンラーニングの目的は、“間違いをなくす”ことではなく、“視点を増やす”ことにあります。
私たちはつい「正しい答え」を求めがちですが、変化の速い時代に唯一の正解は存在しません。
むしろ、正解を探す姿勢そのものが思考を固定化させます。
「この考え方もあり得るかもしれない」と受け止める柔軟さが、新しい発見を生みます。
📎ワーク例:「自分が否定してきた意見の中に、どんな価値があるか?」を書き出してみましょう。
3. 周囲と「変化の共有」をする
アンラーニングは一人で完結しません。
学びの変化をチームで共有することで、組織にも波及していきます。
「最近の自分の気づき」や「手放した思考」を共有すれば、周囲の人も新しい視点に気づけます。
これが、チーム全体の“変化に強い文化”をつくる第一歩です。
🧭実践例:週1回のミーティング冒頭に“気づきシェア”を取り入れる。
上司が率先して実践することで、心理的安全性も生まれます。
アンラーニングを継続する鍵は、「気づき→共有→再定義」のサイクルを回すことです。
習慣として根づくほど、新しい学びが自然と吸収できるようになります。
組織でアンラーニングを促す方法|“捨てる学び”を文化にする
個人がアンラーニングを実践しても、組織全体にその変化が広がらなければ成果にはつながりません。
AIやDXの導入において最も大きな障壁となるのは、「新しいツール」よりも「古い考え方」です。
ここでは、組織としてアンラーニングを根づかせるための具体的な仕組みを紹介します。
1. 上司が「知らないことを認める」文化をつくる
組織のアンラーニングは、まずリーダーの姿勢から始まります。
上司が「知らない」「やってみよう」と口にできる環境は、挑戦を歓迎する心理的安全性を生み出します。
この一言があるだけで、部下は「失敗してもいい」と感じ、新しい発想に踏み出しやすくなります。
💬実践ポイント:会議で「これは分からないけど、やってみよう」とリーダーが言う。それだけで組織の空気は変わります。
2. 「役職」より「役割」で意見できる場をつくる
上下関係が強い環境では、固定観念が温存されやすくなります。
アンラーニングを促すには、肩書きではなく“役割ベース”で意見を出し合う仕組みが有効です。
プロジェクト単位でのフラットな議論や、職種を越えたディスカッションの場を設けることで、思考の境界線が薄まります。
💡ポイント:若手の発言から組織が学ぶ構造を意図的に設計する。
3. 現場に「越境体験」を取り入れる
人は自分の業務領域にとどまるほど、視野が狭くなりがちです。
異部門・異職種のメンバーと協働する“越境学習”の機会を制度化すると、既存の思考を見直すきっかけが生まれます。
生成AIなど新技術をテーマにした社内ワークショップも、越境体験として有効です。
現場が“自分ごと”として変化を体験することが、アンラーニングの定着を後押しします。
4. アンラーニング×リスキリングの連動設計
多くの企業では、リスキリング(新しいスキル習得)だけが研修テーマになりがちです。
しかし、古い前提を持ったまま学び直しても、行動変容は起きません。
アンラーニング→リスキリングの順序で研修を設計することで、社員の理解と実践の質が大きく変わります。
まず「思考のリセット」を行い、そのうえで新しい知識を吸収する構造が理想です。
アンラーニングがうまくいかない理由と対策
アンラーニングは「理解したつもり」で止まってしまうケースが多くあります。
思考や行動の習慣を変えるには、意識以上に“心理的な壁”を乗り越える必要があるためです。
ここでは、実践が進まない代表的な3つの理由と、それを乗り越えるための対策を紹介します。
理由①:過去の成功体験に執着してしまう
人は、自分の成功体験ほど手放しにくいものはありません。
特に長年の経験を積んだ人ほど、「昔はこれでうまくいった」という思考が強く残ります。
しかし環境が変われば、過去の成功法則は“未来のリスク”にもなり得ます。
対策
- 成功体験を「当時の最適解」として位置づけ、いまの現実に照らして更新する
- 「これからの時代に通用する考え方は何か?」という視点で自問する
- チーム内で“過去の常識を1つ捨てる”をテーマにディスカッションする
理由②:心理的安全性が不足している
失敗を恐れる環境では、人は新しい考えを試せません。
アンラーニングには「間違ってもいい」「発想を変えていい」という安心感が欠かせません。
対策
- 上司が“完璧でなくていい”姿勢を見せる
- チーム内で“失敗事例”を共有し、再学習の機会に変える
- 評価指標に“挑戦回数”や“改善提案”を取り入れる
こうした環境が整うと、アンラーニングは「怖いこと」から「楽しい実験」へと変わります。
理由③:新しい知識を詰め込みすぎている
「リスキリングをしなければ」と焦るあまり、学びを“上書き”しようとする人も多いですが、
古い思考を手放さないまま新しい情報を詰め込むと、行動が変わらないという落とし穴があります。
対策
- 新しい学びの前に「何を捨てるか」を決める
- 情報収集より“仮説を立てて試す”ことを優先する
- 学びを得たら「今後この知識を使う場面」を具体的に書き出す
アンラーニングの難しさは、「知識の問題」ではなく「感情の問題」にあります。
過去の自分を否定せず、アップデートしていく姿勢こそが、真の成長です。
アンラーニングを成功に導く実践フレーム|「捨てる→試す→再定義」のループ
アンラーニングを継続的に機能させるためには、「捨てる → 試す → 再定義する」というサイクルを意識して回すことが重要です。
このループを習慣化できる組織ほど、変化のスピードに柔軟に対応できます。
【STEP1:捨てる】— 古い前提・思考パターンを明確にする
アンラーニングの起点は、“何を手放すか”を明確にすることです。
業務フロー、意思決定の基準、人材評価の仕組みなど、「それは本当に今も正しいのか?」と問い直すことから始まります。
ここで重要なのは、過去を否定するのではなく“整理する”姿勢。
捨てることで、次に入る新しい考えの余白が生まれます。
【STEP2:試す】— 小さな実験で行動を変える
手放した思考に代わる“新しい仮説”を立て、小さな範囲で試してみます。
アンラーニングは座学ではなく実践です。
たとえば、「意思決定を上司に任せる」から「自分で仮説を立てて提案してみる」など、
“行動の変化”が生まれて初めて学びが更新されるのです。
実験の結果は成功でも失敗でも構いません。
重要なのは、その結果から「どんな前提が有効で、どれが古かったか」を見極めることです。
【STEP3:再定義する】— 新しい価値基準を組み込む
実践で得た気づきをもとに、思考や行動の基準を再定義します。
たとえば「上司の承認が必要」ではなく「目的を共有すれば任せていい」という新しいルールに書き換える。
この再定義こそがアンラーニングの完成形です。
組織で行う場合は、ここで共通言語化(ビジョン・原則の明文化)を行うと、アンラーニングの成果が文化として定着しやすくなります。
この「捨てる→試す→再定義」のループを回し続けることで、組織は“変化を恐れない学習体質”へと進化します。
重要なのは、1度の研修で終わらせず、継続的に回せる仕組みを整えることです。
まとめ|“手放す力”が、次の学びを拓く
アンラーニングとは、過去を否定することではなく、
状況に応じて“自分の考え方を更新できる力”を育てることです。
変化の激しい時代では、正解よりも“問い続ける姿勢”が価値になります。
「なぜそう考えているのか」「この方法は今も最適か」を見直しながら、一人ひとりが思考を柔軟に保つことで、組織は自然と強くしなやかに進化していきます。
アンラーニングを通じて、学びは「積み上げるもの」から「循環させるもの」へ。
手放すことが、次の成長を生む――この発想の転換こそが、AI時代における最大の競争力です。
アンラーニングは、単なるスキルではなく「変化を続ける文化」です。
SHIFT AIの生成AI研修では、思考を手放し、新しい学びを行動へと結びつける仕組みを提供しています。
組織の変革を、“人”の力から進めませんか?

アンラーニングに関するよくある質問(FAQ)
- Qアンラーニングとは具体的に何をすることですか?
- A
アンラーニングとは、過去の経験や常識をいったん手放し、新しい考え方や価値観を取り入れることです。
単に“忘れる”のではなく、「今の環境で有効か」を見直し、思考を更新するプロセスを指します。
- Qアンラーニングとリスキリングはどちらを先に行うべきですか?
- A
リスキリング(新しいスキルの習得)の前に、アンラーニングを行うのが効果的です。
古い考え方を残したまま新しい知識を学んでも、行動が変わらないためです。
思考をリセットしてから学び直すことで、定着度が高まります。
- Qアンラーニングを個人で始める最初の一歩は?
- A
まず、自分の中にある「こうすべき」という固定観念を紙に書き出してみましょう。
そのうえで、「なぜそう思うのか?」を深掘りすることで、思考の前提を自覚できます。
これがアンラーニングの第一歩です。
- Q組織でアンラーニングを進めるには、何から始めればいいですか?
- A
最初に必要なのは、心理的安全性のある環境づくりです。
上司が「知らない」と認め、挑戦や失敗を共有できる場を整えることで、組織全体にアンラーニングが広がりやすくなります。
- Qなぜアンラーニングが今、注目されているのですか?
- A
AIや自動化が進む時代では、過去の成功パターンが通用しなくなっています。
新しい学びを取り入れる前に、古い思考を手放す力――それがアンラーニングです。
“変化に強い人材”を育てるための基盤として、注目が集まっています。