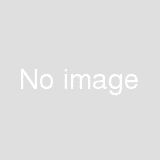近年、多くの企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に取り組む中で、セキュリティ課題が深刻な経営問題として浮上しています。
クラウドサービスの活用やリモートワークの普及により業務効率は向上する一方で、サイバー攻撃の脅威やデータ漏洩リスクも急速に拡大しているのが現状です。
本記事では、DX推進で企業が直面するセキュリティ課題を「技術面」「組織・人材面」「運用・管理面」の3つに分類し、それぞれの具体的な問題点と段階的な解決アプローチを解説します。
セキュリティ対策を後回しにしてDXを進めると、かえって企業リスクを高める結果になりかねません。安全で効果的なDX推進を実現するために、今押さえておくべきポイントを確認していきましょう。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
DX推進でセキュリティ課題が深刻化する理由
DX推進によってセキュリティ課題が深刻化する背景には、デジタル化に伴う根本的な環境変化があります。従来の境界型セキュリティモデルでは対応しきれない新たなリスクが生まれているためです。
💡関連記事
👉DX推進におけるセキュリティリスク|企業が直面する課題と解決策を徹底解説
デジタル化でデータ量が急増するから
企業が扱うデジタルデータの爆発的増加により、セキュリティ管理の複雑さが飛躍的に高まっています。
DX推進では顧客データ、業務データ、IoTセンサーデータなど、あらゆる情報がデジタル化されます。これらのデータは企業の競争力の源泉である一方、攻撃者にとって魅力的なターゲットでもあります。
データ量の増加は単純に管理対象が増えることを意味するだけでなく、データの重要度や機密レベルの判定、適切なアクセス権限の設定など、きめ細かな管理が必要になります。
アクセスポイントが分散・複雑化するから
クラウドサービスやモバイルデバイスの活用により、データへのアクセス経路が多様化し、セキュリティの管理範囲が拡大しています。
従来は社内ネットワークという明確な境界があったため、その入り口を守れば一定のセキュリティを確保できました。しかしDX推進により、社員は自宅、外出先、パートナー企業など様々な場所から業務システムにアクセスするようになりました。
この変化により、どこからでもアクセス可能な利便性を確保しながら、同時にセキュリティを維持するという難しい課題に直面しています。
サイバー攻撃が高度化・多様化するから
DXの普及に伴いサイバー攻撃の手法も進化し、従来の対策では防げない脅威が増加しています。
攻撃者もDXトレンドを研究し、クラウドサービスの設定ミスを狙った攻撃や、リモートワーク環境の脆弱性を突く手法を開発しています。また、AIを悪用したより巧妙なフィッシング攻撃や、標的型攻撃の精度向上も見られます。
このような攻撃の高度化により、技術的な対策だけでなく、組織全体でのセキュリティ意識向上と継続的な対策の見直しが不可欠になっています。
DXセキュリティ課題①:技術面の脅威とリスク拡大
技術面でのセキュリティ課題は、DXで導入される新技術特有の脆弱性と従来システムとの接続リスクに大別されます。これらの課題を理解し適切に対処しなければ、DXの効果を得る前にセキュリティ事故が発生する可能性があります。
クラウド移行で境界が曖昧になる
クラウドサービスの活用により従来の境界型セキュリティモデルが機能しなくなることが、最も大きな技術的課題です。
オンプレミス環境では社内ネットワークという明確な境界がありましたが、クラウド環境では企業のデータが様々なクラウドサービスに分散保存されます。この結果、「内側は安全、外側は危険」という従来の前提が成り立たなくなりました。
クラウドサービスの設定ミスによるデータ漏洩や、適切なアクセス制御が設定されていないことによる不正アクセスなど、新たなリスクへの対応が求められています。
IoT・エンドポイントが攻撃対象になる
IoTデバイスやエンドポイントの急増により攻撃対象が拡大し、セキュリティの死角が生まれやすくなっています。
DX推進では工場の製造装置、オフィスの環境制御システム、従業員のモバイルデバイスなど、ネットワークに接続される機器が大幅に増加します。これらのデバイスは従来のPCと比べてセキュリティ機能が限定的な場合が多く、攻撃の足がかりとして狙われやすい特徴があります。
特に製造業やインフラ業界では、これまでネットワークに接続されていなかった制御システムがDXによりネットワーク化されることで、新たなセキュリティリスクが生まれています。
レガシーシステムとの連携で脆弱性が生まれる
既存システムと新しいデジタル技術の連携により、システム全体の脆弱性が拡大する問題が発生しています。
多くの企業では、長年使用してきたレガシーシステムを完全に刷新することは現実的ではありません。そのため、既存システムにクラウドサービスやAPIを接続してDXを進めるケースが一般的です。
しかし、異なる技術基盤やセキュリティレベルのシステムを接続する際に、接続部分が新たな攻撃経路となったり、セキュリティ設定の不整合により脆弱性が生まれたりするリスクがあります。
DXセキュリティ課題②:組織・人材面の体制不足
組織・人材面の課題は、セキュリティに関する知識・スキル・意識の不足が根本原因となっています。技術的な対策を導入しても、それを適切に運用する人材と組織体制が整っていなければ、セキュリティの実効性は大幅に低下してしまいます。
セキュリティ専門人材が不足している
DXセキュリティに対応できる専門人材の確保が困難になっており、多くの企業で深刻な課題となっています。
従来のネットワークセキュリティに加えて、クラウドセキュリティ、IoTセキュリティ、データガバナンスなど、DXに必要なセキュリティ領域は大幅に拡大しました。これらの新しい技術分野に精通した人材は市場でも希少であり、採用競争が激化しています。
特に中小企業では専門人材の確保が困難なため、既存のIT担当者がセキュリティ業務を兼任するケースが多く、十分な対策が取れていない状況が見られます。
従業員のセキュリティ意識が低い
一般従業員のセキュリティリテラシー不足により、人的ミスによるセキュリティ事故が多発しています。
DX推進により従業員が新しいツールやサービスを利用する機会が増える一方で、それらの安全な使い方に関する教育が追いついていません。フィッシングメールの見分け方、安全なパスワードの設定、クラウドサービスの適切な利用方法など、基本的なセキュリティ知識が不足している従業員が多いのが現状です。
また、リモートワーク環境では従来の社内ルールが適用しにくく、個人判断でのセキュリティ対応が求められる場面が増えているため、従業員一人ひとりの意識向上がより重要になっています。
経営層の理解・投資判断が遅れる
経営層のセキュリティに対する理解不足により、必要な投資や体制整備の意思決定が遅れがちです。
セキュリティ対策は直接的な収益を生まない投資と捉えられがちで、その重要性や緊急性が経営層に十分理解されていないケースがあります。また、セキュリティ事故が発生するまでリスクを実感できないため、予防的な投資に対する優先度が低くなりがちです。
DXプロジェクトでは新機能の開発や業務効率化に注目が集まりやすく、セキュリティ対策が後回しになってしまう傾向も見られます。
DXセキュリティ課題③:運用・管理面のガバナンス問題
運用・管理面の課題は、セキュリティ対策の継続的な実行と改善体制の不備に起因しています。技術や人材が揃っていても、適切なガバナンス体制がなければセキュリティレベルの維持・向上は困難です。
セキュリティポリシーが現実に合わない
従来のセキュリティポリシーがDX環境の実情に対応できていないため、現場では形骸化が進んでいます。
多くの企業のセキュリティポリシーは、オンプレミス環境を前提として策定されており、クラウドサービスの利用やリモートワークなどDXで生まれた新しい働き方に対応していません。その結果、現場では実務に合わない古いルールを無視して業務を進めざるを得ない状況が生まれています。
また、DXで導入される新しいツールやサービスに対する利用ガイドラインが整備されていないため、従業員が独自判断で使用することによるセキュリティリスクも発生しています。
インシデント対応体制が整備されていない
セキュリティ事故発生時の対応体制と手順が確立されていないことが、被害拡大の要因となっています。
DX環境では従来とは異なる種類のセキュリティ事故が発生する可能性があるにも関わらず、対応体制がアップデートされていない企業が多く見られます。クラウドサービスでの事故対応、リモートワーク環境でのインシデント調査、IoTデバイスの感染拡大防止など、新しい技術環境に対応した手順が必要です。
また、事故発生時の連絡体制、意思決定プロセス、外部機関との連携方法などが明確でないため、初動対応の遅れにより被害が拡大するリスクがあります。
継続的なリスク評価ができていない
DX環境の変化に対応した継続的なリスク評価の仕組みが不足しており、新たな脅威への対応が後手に回っています。
DXでは新しい技術やサービスが次々と導入されるため、セキュリティリスクも常に変化しています。しかし、多くの企業では年1回の形式的なリスク評価に留まっており、環境変化に応じたタイムリーなリスク再評価ができていません。
また、サイバー攻撃の手法や脅威インテリジェンスの情報収集体制も整備されておらず、新しい脅威に対する予防的な対策が取れていない状況が見られます。
DXセキュリティ課題を解決する段階的アプローチ
DXセキュリティ課題の解決には、現状把握から始める段階的なアプローチが効果的です。一度にすべての課題を解決しようとするのではなく、優先度と実現可能性を考慮した計画的な取り組みが成功の鍵となります。
【第1段階】現状把握とリスク評価を実施する
自社のDX環境における具体的なセキュリティリスクを正確に把握することが、すべての対策の出発点となります。
まず、現在利用している全てのデジタル技術とサービスを洗い出し、それぞれのセキュリティリスクを評価します。クラウドサービス、業務アプリケーション、IoTデバイス、モバイル端末など、ネットワークに接続されるすべての要素を対象とした棚卸しが必要です。
次に、これらの要素に対する脅威分析を行い、発生可能性と影響度の観点からリスクの優先順位を決定します。この段階では外部の専門家による客観的な評価を活用することも有効です。
【第2段階】優先度に応じて技術対策を導入する
第1段階で特定したリスクの優先度に基づいて、技術的なセキュリティ対策を段階的に導入していきます。
高優先度のリスクから順番に、多要素認証、エンドポイント保護、クラウドセキュリティ対策などの技術的な対策を実装します。予算制約がある場合は、コストパフォーマンスの高い対策から着手し、段階的に対策範囲を拡大していくことが重要です。
また、技術対策の導入と並行して、セキュリティポリシーやガイドラインの見直しも実施し、DX環境に適合したルール整備を進めます。
【第3段階】組織体制と教育プログラムを構築する
技術対策の実効性を高めるための組織体制と継続的な教育プログラムを整備します。
セキュリティ専門チームの設置や既存メンバーのスキルアップ、外部パートナーとの連携体制など、自社に適した運用体制を構築します。同時に、全従業員を対象としたセキュリティ教育プログラムを開始し、継続的な意識向上を図ります。
さらに、インシデント対応手順の策定と訓練、定期的なリスク評価の仕組み化により、セキュリティレベルの継続的な改善体制を確立します。
まとめ|DXセキュリティ課題は段階的アプローチで解決可能
DX推進におけるセキュリティ課題は、技術面の脅威拡大、組織・人材面の体制不足、運用・管理面のガバナンス問題の3つに集約されます。これらの課題は一朝一夕には解決できませんが、現状把握から始まる段階的なアプローチにより着実に改善できます。
重要なのは、セキュリティを単なるコストではなく、DX推進を支える重要な投資として位置づけることです。技術対策だけでなく、組織全体のセキュリティ意識向上と継続的な教育プログラムの整備が、真の安全性確保につながります。
まずは自社の現状を正確に把握し、優先度の高いリスクから段階的に対策を進めていきましょう。
組織全体でセキュリティリテラシーを高めることが、DXの成功を支える基盤となります。

DXセキュリティ課題に関するよくある質問
- QDX推進でセキュリティ課題が発生する主な原因は何ですか?
- A
デジタル化に伴う環境変化が根本原因です。クラウドサービスの活用やリモートワークの普及により、従来の境界型セキュリティモデルでは対応できない新たなリスクが生まれています。データ量の急増、アクセスポイントの分散、サイバー攻撃の高度化により、セキュリティ管理の複雑さが飛躍的に高まっています。
- Q中小企業でもDXセキュリティ対策は必要ですか?
- A
中小企業こそDXセキュリティ対策が重要です。攻撃者は企業規模に関係なくターゲットを選択するため、むしろセキュリティ体制が手薄になりがちな中小企業が狙われやすい傾向があります。限られたリソースでも、現状把握から始める段階的なアプローチにより、効果的な対策を実施できます。
- Qセキュリティ人材が不足している場合の対処法は?
- A
外部の専門サービス活用と社内教育の並行実施が効果的です。技術的に高度な分野は外部パートナーに委託し、基本的なセキュリティ運用は社内人材のスキルアップで対応します。全従業員への継続的なセキュリティ教育により、組織全体の防御力を底上げすることが可能です。
- QセキュリティポリシーをDX環境に合わせて見直すポイントは?
- A
クラウドサービス利用とリモートワーク環境への対応が最重要ポイントです。従来のオンプレミス前提のルールでは現場の実情に合わず形骸化してしまいます。新しいツールやサービスの利用ガイドライン、データの分類と取り扱い基準、インシデント対応手順などをDX環境に適合させる必要があります。