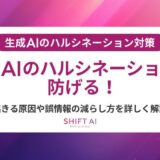紙の書類を回覧し、ハンコを押し、出社して稟議を通す——。
そんな“当たり前”の庁内業務が、いま全国の自治体・官公庁で見直されています。
テレワークや働き方改革が進む一方、文書・稟議・勤怠・申請といった庁内業務の多くはいまだにアナログのまま。
「結局、紙を回さなければ決裁が進まない」「電子決裁を入れたけれど、結局プリントしてハンコを押している」——そんな声も少なくありません。
こうした状況を変える鍵が、庁内DX(庁内業務のデジタル化)です。
行政サービスのDX(住民向け)を進める前に、まず庁舎の中——すなわち職員の働き方を変えることが、真の行政改革の第一歩といえます。
本記事では、庁内DXの基本構造と推進ステップを整理し、 「文書・稟議・勤怠」を中心とした業務のデジタル化手法、成功自治体の事例、そして生成AIを活用した次世代の庁内業務改革までを徹底解説します。
関連記事:行政DXとは?国の方針・導入状況・課題をわかりやすく解説
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ今、“庁内業務のDX化”が求められているのか
デジタル庁や総務省が掲げる「自治体DX推進計画」では、住民サービスのオンライン化だけでなく、庁舎内の業務プロセス改革=庁内DXを重要テーマと位置づけています。
しかし実際の現場では、いまだに紙書類・ハンコ・対面稟議が根強く残り、改革のスピードが追いついていません。
背景①:紙・ハンコ・出社依存が続く「昭和型行政スタイル」
多くの自治体では、文書の起案から決裁まで紙の回覧が必要で、出社しなければ業務が進まない状況が続いています。
電子決裁システムを導入しても、「最終押印のために出勤」「PDFを印刷して署名」など、デジタルの形をしたアナログ運用が常態化しているケースも少なくありません。
この構造が、テレワークや業務効率化の妨げとなり、職員の負担を増大させています。
背景②:テレワーク/働き方改革対応の遅れ
新型コロナ禍を機に、民間企業ではリモートワークが定着した一方で、行政機関では庁内ネットワークの制約やセキュリティルールが壁となり、柔軟な働き方が実現しにくい状況です。
「庁舎にいなければ決裁できない」「外部からアクセスできない」などの構造的課題が、業務の属人化と長時間労働を生み出しています。
庁内DXは、単なるシステム導入ではなく、こうした働き方を根本から見直す契機でもあります。
背景③:行政データを活かせない「縦割り庁内構造」
文書・稟議・勤怠・申請などのデータが各課で分断管理されているため、全庁的な分析や業務改善に活かしづらい現実もあります。
たとえば、勤怠情報と業務量データを突き合わせれば「残業の多い部署」や「手続きが滞る工程」を見える化できますが、実際にはそれぞれ別システム・別帳票で管理されており、庁内での情報活用が止まっているのです。
結果:業務の非効率化・ミス増加・職員負担の慢性化
これらの要因が重なり、行政現場では「処理に時間がかかる」「担当者が休むと止まる」「二重入力・確認作業が多い」といった非効率が常態化。
結果として、職員の残業増加や人材流出、さらには行政サービス全体の遅延にもつながっています。
庁内DXは単なる“効率化”ではなく、現場の変革力を取り戻すための「文化改革」です。
紙とハンコの文化を変えるのは、ツールではなく人。
庁舎の中から変化を起こせる“デジタルリーダー”を育てることが、次の行政競争力を決める鍵となります。
庁内DXの基本構造|デジタル化の3ステージモデル
庁内DXを成功させるには、単に「ツールを導入する」だけではなく、組織として段階的に進化していくプロセス設計が欠かせません。
AI経営メディアでは、全国の自治体・官公庁の取組を分析し、庁内DXを進めるための3ステージモデルとして整理しています。
| ステージ | 概要 | 目的 |
| ① 電子化 | 紙書類やハンコ文化をデジタルへ置き換える段階。電子決裁・電子文書管理・電子署名の導入が中心。 | 業務時間の短縮・ペーパーレス化・物理的制約の解消 |
| ② ワークフロー化 | 承認・回付・共有の流れをシステム上で自動化する段階。申請書・稟議書・勤怠管理などを共通基盤で管理。 | 処理の標準化・属人化防止・ミスの削減 |
| ③ データ活用 | 各業務で発生するデータを集約・分析し、業務改善や政策立案に活かす段階。AIによるレポート自動生成なども可能。 | 客観的な意思決定・継続的な業務改善・行政サービスの高度化 |
ステージ①:電子化 ― 紙とハンコからの脱却
最初のステップは「紙に依存した業務のデジタル化」です。
文書管理や稟議決裁を電子化するだけで、承認スピードが2〜3倍に向上した自治体もあります。
ただし、電子化だけで終わると「PDFを印刷してハンコを押す」など、アナログの延命に陥りやすい点には注意が必要です。
ステージ②:ワークフロー化 ― 業務プロセスの標準化
次に、申請・承認・共有の流れをシステム上で構築します。
これにより、「担当者が不在でも業務が止まらない」「決裁までのルートが自動で可視化される」など、組織としての業務の再現性が高まります。
属人化した“暗黙のルール”を明文化し、全職員が同じプロセスで動ける体制を整えることが重要です。
ステージ③:データ活用 ― 改善を自走できる組織へ
最終段階では、庁内の稟議・文書・勤怠・庶務など、あらゆる業務データを横断的に活用します。
たとえば、
- 稟議件数と処理日数を分析し、ボトルネックを特定
- 勤怠データと業務量を突き合わせ、部署間の負荷を可視化
- AIで過去データを学習し、処理量の予測や提案を自動化
これにより、“データが意思決定を導く庁舎運営”が実現します。
DXは一度きりの導入ではなく、「電子化 → ワークフロー化 → データ活用」へ進化していくプロセスです。
庁内DXの最終形とは、単にツールを使いこなすことではなく、職員自らデータを読み解き、改善を提案できる組織をつくること。
つまり、「変化を仕組みにできる行政」がDXのゴールなのです。
庁内業務ごとのDX化の具体策
庁内DXを推進するには、「どの業務を」「どうデジタル化するか」を具体的に落とし込むことが重要です。
ここでは、現場職員の負担が大きい文書管理・稟議・勤怠/庶務業務を中心に、実際の導入・改善策を整理します。
AI経営メディアでは、単なるツール紹介ではなく、導入後の成果を定量的に示すことで、庁内DXの実効性を明らかにします。
文書管理業務のデジタル化
文書業務は、庁内DXの中でも最も改善効果が出やすい領域です。
紙での保管・検索・回覧をデジタル化することで、作業時間と保管コストを大幅に削減できます。
- 電子決裁・電子文書管理システムの導入
→ 承認履歴や修正履歴を自動で記録し、監査対応も容易に。 - 文書分類・検索・保存ルールの統一
→ 課ごとに異なる管理ルールを統一することで、職員異動時の引き継ぎもスムーズ。 - 公文書法/保存要件への対応
→ 法令で定められた保存年限・改ざん防止に対応したクラウド型文書管理が主流に。
成果例:ある県庁では、電子文書検索の自動化により、年間約300時間の書類探索工数を削減。
稟議・決裁フローの効率化
ハンコ文化からの脱却は、庁内DXにおける最大の関門です。
「電子署名制度」の整備とワークフローの再設計を行うことで、承認スピードと透明性を同時に高められます。
- ハンコ文化脱却と電子署名の活用
→ 電子印鑑・署名を法的効力をもつ形で運用し、押印業務をゼロに。 - 並列承認・自動回付で処理を高速化
→ 複数承認を同時進行に切り替えることで、回付時間を最大50%削減。 - 成果指標(KPI)を設定する
→ 「決裁完了までの平均日数」「差し戻し率」「ログ透明性」などで進捗を見える化。
ある政令市では、稟議ワークフローを電子化した結果、1件あたりの決裁日数が8日→3日に短縮。
勤怠・庶務・申請業務の自動化
職員の日常業務(勤怠・出張・経費申請)は、頻度が高く煩雑になりがちです。
ここを自動化することで、“庁舎の見えない残業”を解消できます。
- 勤怠・出張・経費申請のクラウド化
→ 各種申請フォームをデジタル化し、承認ルートを自動設定。 - スマホ打刻・AIシフト管理の導入
→ 外出時・出先でも打刻でき、シフト作成をAIが最適化。 - 連携ツールの活用
→ 庁内ポータルやチャットボットと連携し、問い合わせや再申請を自動化。
実際の導入事例:A市では「庁内勤怠DX」を推進し、月間約40時間分の集計・修正業務を削減。
多くのメディアが「どんなシステムを導入すべきか」で止まる中、 AI経営メディアは導入後の“成果”を定量的に評価し、職員の働き方改善にどの程度寄与したかを可視化します。
成功自治体に学ぶ庁内DX事例(2024〜2025)
庁内DXを本格的に進めている自治体では、単なるツール導入ではなく、業務プロセスと人材育成の両面から仕組みを再設計しています。
ここでは、AI経営メディアが分析した代表的な3自治体の取組を紹介します。
| 自治体 | 取組内容 | 成果 |
| 京都市 | ワークフロー電子化+全庁ポータル統合 | 承認時間を70%短縮。稟議の回付ルートを最適化し、各課の承認プロセスを自動化。 |
| 松本市 | 職員向けAI研修で庁内DXリーダーを育成 | 各課のAI活用率50%達成。生成AIを活用した業務報告書作成・住民対応の効率化を推進。 |
| 金沢市 | 文書管理×AI検索システム導入 | 検索時間を年間200時間削減。庁内文書の全文検索と自動分類機能により、属人化を解消。 |
これらの事例に共通しているのは、「ツール導入=目的」ではなく、「職員の変化を促す仕組み」を中心に置いている点です。
例えば京都市では、電子稟議化に合わせて“承認プロセスの見直し”を実施。
単にシステムを導入するだけでなく、「誰が何をどの順で承認するのが最も合理的か」を全庁で議論しました。
松本市では、生成AIを活用した職員研修プログラムを導入し、現場の担当者が自らAI活用アイデアを提案する文化を醸成。
金沢市では、データ活用におけるルール整備と同時に、AI検索システムを運用できるデジタル人材チームを庁内に新設しています。
成功自治体のDXは、「ツールの導入」ではなく、“人と仕組みの変化”への投資から始まっています。
真のDXの成果は、数値化できる削減効果だけでなく、「職員が新しい働き方を当たり前にできる文化を作れたか」 という点に現れます。
庁内DXとは、テクノロジーではなく「文化の再設計」である——。
それが、AI経営メディアが考える行政変革の本質です。
庁内DXを進めるための4ステップロードマップ
庁内DXを進める上で最も重要なのは、「何から着手し、どの順番で進めるか」を明確にすることです。
単にシステムを導入しても、現場が混乱したり、使いこなせず定着しないケースは少なくありません。
AI経営メディアでは、全国自治体の成功・失敗事例を分析し、庁内DXを確実に定着させるための4ステップロードマップを提案しています。
現状可視化 — 紙・ハンコ・回付など現行フローを棚卸
まずは、庁内で「どんな業務が、どんな手順で行われているか」を見える化します。
- 稟議書や申請書の回付ルート
- 紙書類・ハンコを使用している業務
- データが紙で止まっているポイント
これらを部署横断で棚卸し、一覧化することで「何がDXの対象か」が明確になります。
可視化の段階で職員を巻き込むことが、後の現場理解を高める第一歩です。
課題特定と優先順位化 — ボトルネック業務を定義
棚卸した業務の中から、 「処理件数が多く・手作業が多い・決裁に時間がかかる」ものを優先的に選びましょう。
たとえば
- 稟議書の回覧が平均5日以上かかる
- 勤怠申請が紙ベースで月末に集中している
- 文書検索に1件あたり10分以上を要している
これらの定量的データをもとに優先順位を付けることで、PoC(試行導入)対象が明確になります。
デジタル化計画策定 — PoC(試行導入)+横展開の設計
次に、最も効果が出やすい領域で小規模な実証(PoC)を行います。
- まずは1課・1業務からスタート
- 成果指標(例:承認スピード/残業時間削減)を設定
- 成果が出たら横展開する設計を事前に構築
PoCを通じて得たデータを庁内で共有し、「成功体験の見える化」を行うことで、DX推進への理解が加速します。
職員教育と定着化 — デジタルリテラシー・AI研修の実施
庁内DXを持続的に進めるためには、「システムを運用できる職員」を育てることが不可欠です。
単発の操作研修にとどまらず、職員がAI・デジタルを業務改善に活かす力を育むことが鍵となります。
- デジタルリテラシー研修(全職員対象)
- 生成AI研修(企画・業務改善担当者対象)
- 内製化支援プログラム(現場主導で改善できる体制づくり)
これにより、庁舎全体で「デジタルを使いこなす文化」が根づきます。
庁内DXの成功は、最終的に「人」にかかっています。
いくらツールを導入しても、職員がAIを使いこなせなければ改革は止まります。
生成AIが変える“庁内業務の次のステージ”
電子決裁や文書管理などのデジタル化が進んだ今、庁内DXは「業務を効率化する段階」から、「知的業務を再設計する段階」へと進化しています。
その中心にあるのが、生成AI(Generative AI)です。
生成AIは、文書作成・報告・意思決定支援など、これまで人が膨大な時間をかけていた“考える仕事”を支援し、行政業務の質そのものを変え始めています。
文書・稟議・報告書のAI自動化
庁内業務の中でも、特に時間を要するのが文書・稟議・報告書の作成です。
生成AIを活用すれば、自然言語処理技術によって内容を自動で要約・分類・起案でき、職員の負担を大幅に削減できます。
- 文書要約・分類の自動化
→ 長文の報告書や会議録をAIが要約し、重要キーワードを抽出。 - 起案文書のドラフト生成
→ 過去の稟議・公文書を学習し、AIが“雛形”を提案。 - 安全な生成AI運用のガイドライン設計
→ ChatGPTやGeminiを庁内利用する際のセキュリティ・個人情報保護指針を策定。
たとえば、ある市役所では「AIによる報告書自動要約」を導入した結果、月に平均120時間の文書作成時間を削減。
AIを補助的に使うことで、本来の政策検討や住民対応に時間を割ける体制を整えています。
職員の意思決定支援としてのAI活用
生成AIは、単なる業務効率化ツールではありません。
職員の意思決定を“データに基づき支援する”ことで、行政の質を根本から高めることができます。
- 勤怠データや業務ログの分析
→ AIが長時間労働や業務偏りを検出し、改善提案を自動提示。 - 庁内問い合わせ・FAQ履歴の分析
→ 職員間の質問データを解析し、よくある課題や業務改善の糸口を可視化。 - 政策・予算立案の支援
→ 文献や法令、過去データをAIが横断分析し、根拠資料を提示。
AIを“判断の補助輪”として活用することで、職員がより高付加価値な業務に専念できる環境が整います。
そして何より重要なのは、これらの仕組みを活かす「人」——つまり、AIを理解し、活用できる職員の存在です。
庁内DXの進化を支えるのは、システムではなく「人」。
AIを理解し、庁内DXを推進できる職員を育てましょう。
まとめ|庁内DXは「紙を減らす」ではなく「仕組みを変える」こと
庁内DXとは、単に紙やハンコをなくすための取り組みではありません。
それは、行政の“現場を強くする”ための組織改革です。
どれだけ最新のツールを導入しても、それを使いこなし、仕組みに落とし込める人材と文化がなければ、真のDXは定着しません。
庁内DXの成功の鍵は、「人 × 仕組み × 文化」の3つを同時に育てていくことにあります。
まずは、身近な業務——たとえば、文書回付や勤怠申請など、小さな一歩からデジタル化を始めることが重要です。
その過程でAIを取り入れ、現場が自ら変化を起こせる体制を整える。
それこそが、持続的な行政変革への最短ルートです。
AIを使える職員が増えるほど、行政は柔軟に、そして速く変わっていく。
庁内DXは、「現場の改善力」を取り戻すためのプロジェクトなのです。
関連リンク
- Q庁内DXとは具体的に何を指しますか?
- A
庁内DXとは、庁舎内で行われる行政内部業務(文書管理・稟議・勤怠・庶務など)をデジタル化する取り組みです。
電子決裁やワークフロー化を通じて、業務効率を高めるだけでなく、職員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を整えることが目的です。
- Q自治体DXや官公庁DXとどう違うのですか?
- A
「自治体DX」「官公庁DX」は、行政全体のデジタル化を指す広い概念です。
一方、庁内DXは行政内部に焦点を当てた“内向きのDX”です。
庁内業務が効率化されることで、結果的に住民サービスの迅速化や政策立案の質向上につながります。
- Q庁内DXはどの業務から始めるべきですか?
- A
最初は、紙とハンコが多い・承認に時間がかかる・処理件数が多い業務から始めるのが効果的です。
具体的には、- 稟議・決裁フロー
- 勤怠・出張・経費申請
- 文書管理・報告書作成
などが対象です。
成果が出やすい領域から小さく始めて横展開することで、職員の理解と定着を得やすくなります。
- Q庁内DXを進める上での課題は何ですか?
- A
主な課題は次の3つです。
- レガシーシステムの制約(既存システムとの連携が困難)
- 人材不足とスキルの断層(現場がデジタルに不慣れ)
- 組織文化の壁(失敗を避ける意識が強く、変革が進まない)
これらを解決するには、段階的な導入計画と職員教育の両立が不可欠です。
- Q庁内DXにAIを導入するメリットは?
- A
AIを活用することで、単なる業務効率化を超えた“業務の再設計”が可能になります。
たとえば、- 文書や報告書の自動要約
- 稟議書の起案支援
- 勤怠・業務ログ分析による改善提案
など、AIがデータに基づいて改善を提案することで、職員の意思決定力を高めることができます。