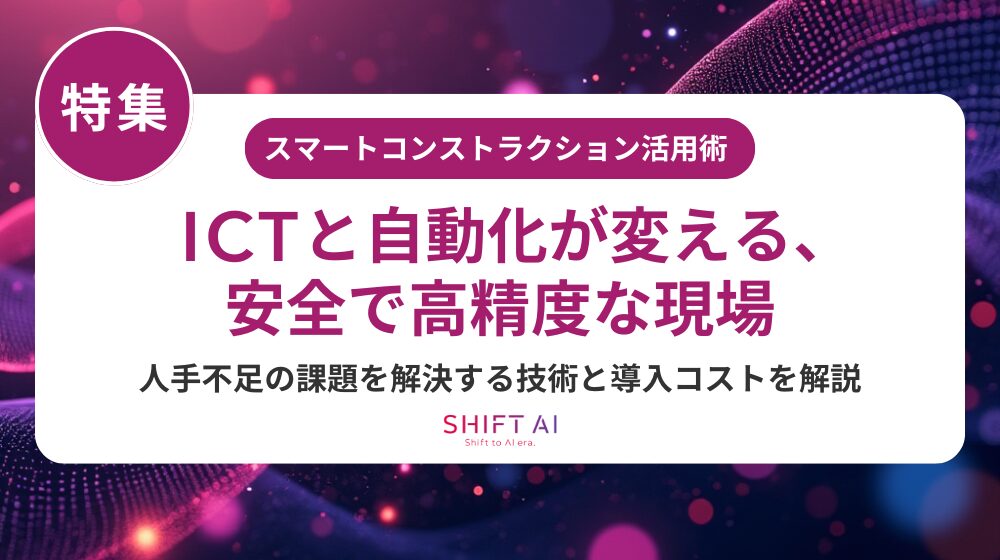建設現場のデジタル化を象徴する「スマートコンストラクション」。
ICT建機、BIM/CIM、AI解析など、先端技術が次々と現場に導入される一方で、 「それを使いこなせる人がいない」という課題が、全国の建設企業で共通して聞かれます。
いま、求められているのは──
最新技術を導入することではなく、“デジタルを現場で運用できる人材”を育てること。
つまり、スマートコンストラクションを動かす主役はテクノロジーではなく“人”なのです。
本記事では、スマート建設を支えるために必要な人材スキル、 育成のステップ、そして求人市場の最新動向までを徹底解説します。
さらに、国や自治体の補助金を活用して教育コストを抑えながら、 「現場が自走できるDX人材」を育てるための実践戦略も紹介します。
まず「スマートコンストラクションの仕組み」を知りたい方は
スマートコンストラクションとは?建設業DXを加速させる仕組みと導入の全体像
もあわせてご覧ください。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ今「スマート建設人材」が注目されているのか
スマートコンストラクションは、もはや一部の大手ゼネコンだけの取り組みではなく、 中小建設業までを巻き込んだ業界全体の変革テーマになっています。
国交省や自治体が進めるDX支援、補助金の拡大など、環境は急速に整いつつありますが、 その一方で多くの企業が直面しているのが「技術を導入しても成果が出ない」という壁です。
この背景には、単なるツールの理解ではなく、 “デジタルで現場を変える人材”の不足という本質的な課題があります。
AI・BIM・ドローンなど新しい技術を導入しても、 現場でそれを活かすスキルや考え方を持つ人がいなければ、生産性は上がりません。
では、なぜ今この“スマート建設人材”がこれほど注目されているのか。
その理由を、「業界構造の変化」「政策動向」「企業競争力」の3つの視点から解説していきます。
深刻化する人手不足と2024年問題──技術導入だけでは解決しない構造的課題
建設業界では、職人・管理職の高齢化と若手不足が同時に進行しています。
国土交通省の調査によれば、建設技能者の3人に1人が55歳以上で、29歳以下はわずか1割。
さらに2024年問題(時間外労働の上限規制)により、従来の長時間労働で支えられていた現場運営が維持できなくなるという現実が目前に迫っています。
その打開策として注目されているのが、ICT施工やBIM/CIM、AI解析などによる「スマートコンストラクション」。
しかし、機械を入れただけでは現場の生産性は上がりません。
実際、導入企業の多くが「オペレーターが使いこなせない」「データ活用が進まない」という壁に直面しています。
技術導入は“入口”にすぎず、それを現場で動かす“人材の理解とスキル”がなければ成果は生まれない──
この構造的課題こそが、「スマート建設人材」が注目される理由です。
「i-Construction」以降の国交省方針と“人材要件の拡張”
2016年に国交省が掲げた「i-Construction」は、 ICT施工・3次元データ・ドローン測量などを現場に取り入れることで、 建設生産性を20%向上させることを目指す国家プロジェクトでした。
しかし、初期のi-Constructionは“技術導入”が中心。
2020年代以降はその方向性が変化し、 国の各種政策文書では「人材育成・教育体系の整備」が明確に打ち出されています。
たとえば、
- 「建設業DXアクションプラン(国交省)」では、
ICTやBIM/CIMを扱える人材育成を重点施策に。 - 「デジタル田園都市国家構想」でも、
地方建設業におけるDX人材の確保・教育を重要テーマに位置づけ。
つまり国策の焦点は、 “技術を導入する”段階から“それを活用できる人を育てる”段階へと進化しているのです。
スマート建設の成否を分けるのは「技術導入力」ではなく「運用人材力」
建設DXの導入効果は、導入したツールそのものではなく、 現場がそれをどれだけ日常業務に定着させられるかで決まります。
ICT建機もAI解析も、扱う人によって結果が変わる。
操作スキルだけでなく、データをもとに「どう現場改善を設計するか」という思考力こそが鍵です。
この意味で、今の建設業界で本当に必要なのは、 「機械を動かす人」ではなく、「データで現場を動かす人」。
そして、そのような“運用人材”を育てる仕組みを持つ企業が、 今後のスマート建設競争をリードしていくでしょう。
【図解】技術中心→人材中心へ──国の政策変化で読み解くスマート建設の未来
2016年〜2025年の政策トレンドシフト
──────────────────────────────
2016年:「i-Construction」=ICT導入による生産性向上(技術中心)
↓
2020年:「建設業DX」=クラウド・AI連携でのデータ化推進(仕組み中心)
↓
2025年:「人材DX」=デジタルを“使いこなす人”の育成と組織変革(人中心)
──────────────────────────────
いま求められているのは、 「建設業DX」ではなく「人材DX」です。
企業の競争力を決めるのは、 どんなICTを入れたかではなく、どんな人がその技術を運用できるか。
だからこそ、これからの建設業において「人材戦略」は、 経営の中心テーマになっていくのです。
スマートコンストラクションに求められる人材スキル【5分類で体系化】
スマートコンストラクションを推進するために必要なのは、 ICT機器やBIM/CIMを扱う技術力だけではありません。
データを理解し、チームを動かし、組織として成果を出せる人材が求められています。
AI経営総合研究所では、スマート建設人材のスキルを次の5つに分類して体系化しました。
それぞれの能力は独立して存在するものではなく、現場・設計・マネジメントが連携して初めて成果が出る構造です。
① ICT施工・BIM/CIMを扱うデジタルリテラシー
スマート建設の基盤となるのがICT施工とBIM/CIMです。
設計段階から施工データを3Dで統合し、精度の高い施工計画を立てるには、 現場担当者自身がデジタルデータの意味と使い方を理解する力が欠かせません。
「機械のオペレーター」ではなく「データの活用者」として、
- 測量データの読み取り
- モデル修正・設計変更への対応
- BIM/CIMを使った進捗可視化
といった作業を自ら実行・改善できるスキルが求められます。
これが、現場のデジタルリテラシーの第一歩です。
② 施工データを活用するAI・自動化ツール活用力
次に求められるのは、AIや自動化ツールを使いこなす力。
AIによる工程シミュレーション、画像認識による品質検査、 クラウド上での自動報告書生成など、現場業務の自動化が急速に進んでいます。
特に2025年以降、建設AIツールの多くは「ノーコード化」され、 現場リーダーが直接操作できるようになります。
そのため、AIを“使う側の人間”として設計・運用できる力が重要です。
AI導入は、IT部門の仕事ではなく現場担当者の武器へ──。
これが、これからのスマート建設における“標準スキル”となっていきます。
③ 部署・業者間をつなぐコミュニケーション/調整力
スマートコンストラクションの特性は「現場がデータでつながること」。
設計・施工・管理・発注者など、多様なステークホルダーがクラウド上で連携するため、
従来の“現場の感覚”だけでなく、情報共有と意思決定をスムーズに行う力が求められます。
- BIMデータを軸に設計者と現場をつなぐ
- ICT施工の進捗を発注者と共有する
- システム導入に対する現場側の意見を吸い上げる
こうした横断的なコミュニケーションスキルは、 もはや「ソフトスキル」ではなく“生産性を左右するスキル”へと位置づけられています。
④ プロジェクト全体を設計するマネジメントスキル
デジタル化が進むほど、求められるのは「全体を俯瞰し、設計できる人」。
各工程をデータで結び、複数チームをまとめるマネジメントスキルが重要になります。
スマート建設時代のマネージャーは、
- 各工程データを読み解き、ボトルネックを分析する
- 施工・安全・コストをリアルタイムで見える化する
- DXツール導入を“現場の言葉”で翻訳し、チームに浸透させる
といった、“データをもとに現場を動かす管理者”であることが求められます。
この層が育たなければ、どれだけツールを導入しても定着しません。
⑤ クラウド・セキュリティを理解するデジタル安全知識
建設DXの進展に伴い、施工情報・設計図・地形データなど、 重要情報の多くがクラウドで共有される時代になりました。
そのため、情報管理とセキュリティ意識も欠かせないスキルです。
- データ共有範囲やアクセス権限の設定
- 現場端末(タブレット・ドローン)の管理
- 外部業者とのセキュリティポリシー遵守
こうしたルールを現場単位で理解・実践できる人材が、 デジタル社会の“安全施工”を担う鍵となります。
【図表】スマート建設人材スキルマップ2025
| 層 | 主な役割 | 必要スキル例 |
| 現場層 | ICT建機操作・BIMデータの活用 | デジタルリテラシー・AIツール操作 |
| 設計層 | モデル設計・3Dデータ連携 | BIM/CIM活用・情報共有設計 |
| マネジメント層 | プロジェクト全体管理・進捗分析 | データ分析・リーダーシップ |
| データ層 | DX戦略・システム統合 | AI活用・データ戦略設計 |
| 教育層 | 社内研修・人材育成 | 研修設計・教育運営スキル |
育成が鍵!スマート建設人材を社内で育てる3ステップ
スマートコンストラクションを導入しても、 「現場で使える人が育っていない」という声は少なくありません。
技術の習得はもちろん大切ですが、 本当に重要なのは“組織としてデジタルを定着させる教育設計”。
AI経営総合研究所では、スマート建設人材の育成を次の3ステップで整理しています。
ステップ① 現場のDX理解を浸透させる「リテラシー教育」
まず土台となるのが、現場全員のDXリテラシーを底上げすること。
「デジタル化=自分の業務にどう関係するのか」を理解しない限り、 ツール導入は“形だけの改革”で終わってしまいます。
研修の初期段階では、
- DXの目的や国の政策動向(i-Constructionなど)
- ICT施工・BIM/CIMの基本概念
- データを使った改善事例紹介
といった意識醸成型の教育を行うことが効果的です。
現場で「なぜ変わるのか」「なぜ必要なのか」を腹落ちさせることで、 次のステップ――実践研修の吸収率が大きく変わります。
ステップ② ICT機器・AIツールを使いこなす「実践研修」
次に行うべきは、現場での実践を前提としたスキル研修です。
この段階では「触って覚える」よりも、“業務の中で使いこなす”訓練が鍵となります。
- ICT建機の操作トレーニング
- BIM/CIMモデルを使った施工計画の立案
- AIによる工程管理や報告書自動化の演習
といった実務連動型カリキュラムを設計することで、 現場単位でのデジタル活用が定着しやすくなります。
ここでのポイントは、“機械を覚える”ではなく“仕組みを理解する”こと。
システム導入後の現場トラブルを減らし、ツールのROIを最大化できます。
ステップ③ データを活かし改善をリードする「マネジメント教育」
最後のステップは、データを活用し組織を動かすマネジメント層の育成です。
いくら現場がツールを使いこなしても、管理職がデータを読めなければ成果は続きません。
ここで求められるのは、
- 各工程データを分析して改善点を抽出する力
- 数字をもとに現場判断を行う力
- チーム全体にデジタル文化を根付かせる力
つまり、「データを経営判断に転換できる人材」を育てることが目的です。
管理職の教育に力を入れることで、 “導入後に止まらないスマート建設”が実現します。
【成功事例】AI研修を導入した中堅ゼネコンが工期短縮を実現
ある中堅ゼネコンでは、AI施工管理ツールを導入した際に同時にAI研修を全社展開しました。
現場リーダー向けに「AIを使った進捗分析」「異常検知の自動化」を実践的に学ばせた結果、 わずか半年で工期短縮25%、レポート作成時間50%削減を実現。
同社の人事担当者はこう語ります。
「AIツールを入れただけでは変わらなかった。
“使える人を育てる”ことで、初めて投資効果が出た。」
このように、教育を導入フェーズと同列で設計することが、 スマート建設成功企業の共通点です。
求人市場から見る「スマートコンストラクション人材」のリアル
技術の進化とともに、建設業界の求人市場にも大きな変化が起きています。
かつては「現場経験者」が主流だった採用が、いまや“デジタル施工をリードできる人材”にシフトしています。
ここでは、最新の求人データやスキル動向をもとに、スマート建設人材の“今”を読み解きます。
ICT施工/BIM・CIM職種の求人推移と平均年収
近年、「ICT施工」「BIMオペレーター」「CIMエンジニア」といった職種が急増しています。
求人サイトdodaの集計では、BIM/CIM関連職の求人数は2020年比で約2.3倍に拡大。
特にゼネコンや建設コンサルタントでは、設計・施工をデジタルで連携できる人材の需要が顕著です。
平均年収は以下の通りです(2024年下半期データ・概算)。
| 職種 | 平均年収(目安) | 求人数トレンド |
| ICT施工管理技士 | 約520〜650万円 | 増加傾向(+30%/前年比) |
| BIM/CIMエンジニア | 約550〜700万円 | 急増(+45%/前年比) |
| DX推進担当(建設業) | 約600〜800万円 | 新設ポジションとして拡大中 |
従来型の施工管理よりも、“デジタル+マネジメント”の複合スキルを持つ人材が高く評価されています。
採用競争は激化しており、「育成か、外部採用か」の判断が企業課題になりつつあります。
大手ゼネコン・地方企業で高まる“DX推進職”の需要
大手ゼネコン各社では、DX推進部門の新設が相次いでいます。
清水建設・大林組・鹿島建設などが中心となり、 施工データの統合管理や生成AIによる設計支援の実証が進行中です。
一方、地方中堅・中小企業でも、 自治体の補助金や共同プロジェクトを通じて「デジタル推進担当」を採用する動きが活発化。
“現場も分かるDX人材”というハイブリッド型の職域が、全国的に生まれています。
つまり、スマート建設の広がりは、 「ICT施工職」から「DX推進職」へと求人領域を拡張しているのです。
AI・データ人材が建設業界に流入する新潮流
これまで建設業界とは縁が薄かったAI・データ分析・プログラミング系の人材が、 いま、スマートコンストラクション領域に参入し始めています。
- 機械学習による施工進捗予測モデル開発
- 画像認識AIによる安全管理
- ドローン+AIでの地形解析
といった分野では、IT業界出身者や理系データサイエンティストの転職事例が増加中。
この流れは「スマート建設=建設×デジタル×AI」という新たな産業構造を形成しつつあります。
今後は、建設業界が“デジタル人材を育てる側”に回れるかどうかが、競争力を左右するでしょう。
転職市場で評価されるスキルセットと資格一覧(建設DX推進員など)
転職市場では、単なる施工経験ではなく、 「DXプロジェクトを推進できるかどうか」が評価基準になっています。
とくに評価されやすい資格・スキル領域は以下の通りです。
| カテゴリ | 主な資格・スキル例 | ポイント |
| ICT施工 | 建設ICT施工技士、測量士補など | 現場デジタル化の基礎スキル |
| BIM/CIM | BIMマネージャー/CIMエンジニア認定 | 設計と施工の統合力を評価 |
| DX推進 | 建設DX推進員(国交省認定)、デジタル人材育成士 | 経営視点からのDX理解 |
| AI・データ | Python/機械学習基礎、データ分析実務スキル | 他業界からの転入に有利 |
これらのスキルを複合的に持つ人材は、 “スマート建設を動かせる即戦力”として市場価値が急上昇しています。
“補助金×教育”で人材育成を加速させる戦略
スマートコンストラクション導入を考える企業の多くが、 「機器を導入する予算は確保できても、教育まで手が回らない」という課題を抱えています。
しかし実は近年、国の補助金制度では、教育・研修費も補助対象に含まれるケースが増えています。
つまり、補助金を「設備投資のための支援」から「人材育成のための投資資金」へと転換できるのです。
建設業DX推進支援事業で「教育費」も補助対象に
2024年度以降、国交省が主導する「建設業DX推進支援事業」では、 ICT建機やBIM/CIMツールだけでなく、それを使いこなすための研修・教育費が補助対象に含まれています。
たとえば、以下のような項目が対象となる例があります。
| 補助対象経費 | 内容 | 補助率 |
| 教育・研修費 | ICT機器操作・AIツール操作研修 | 1/2〜2/3 |
| 外部講師委託費 | DX推進人材向け研修 | 同上 |
| クラウド利用料 | 教育用シミュレーター・AI教材 | 同上 |
これにより、企業は“導入と教育を同時に進める”ことが可能に。
国の政策方針も、単なる機械導入支援から、「現場のスキル定着支援」へとシフトしています。
補助金を“導入資金”ではなく“教育投資”に変える方法
補助金を「導入コストの軽減」に使うだけでは、一時的な効果で終わります。
一方、教育投資として設計すれば、長期的なROI(投資対効果)を高めることが可能です。
AI経営総合研究所が推奨するのは、以下のような“再投資モデル”です。
【補助金再投資モデル】
- 補助金でICT・AIツールを導入
- 導入後すぐに「操作・運用研修」を社内展開
- 翌年度以降、社内教育者(トレーナー)を育成し自走体制へ
この流れを作ることで、補助金の効果を単年度で終わらせず、 「教育を資産化」できる企業体質に変えられます。
さらに、教育計画を明確に設計しておくと、 補助金の採択率アップにもつながる点が見逃せません。
成功企業の事例──補助金+AI研修で現場工数25%削減
ある地方中堅ゼネコンでは、国交省のDX推進支援事業を活用してICT建機を導入。
同時に、補助対象経費の範囲でAI施工支援ツールの操作研修を社内展開しました。
結果として、
- 現場記録・報告書作成の自動化
- 施工進捗の可視化による工期短縮
- 社員のAI活用スキル向上による再現性の確立
これらを実現し、工期25%短縮・現場工数20%削減という具体的成果を出しました。
つまり、「補助金+教育」を組み合わせることで、 “導入して終わり”ではなく“現場を変える投資”に転化できたのです。
【ケーススタディ】教育で成果を出したスマート建設企業
「教育にコストをかけても、すぐに成果が出るのか?」
──多くの企業が抱えるこの疑問に、すでに答えを出している企業があります。
ここでは、ICT導入と教育を一体で進めた3社の成功事例を紹介します。
それぞれの共通点は、「技術を入れて終わり」ではなく、 “使いこなす人”を育てることで生産性・品質・提案力を同時に高めた点にあります。
ケース① ICT建機導入+AI研修で現場生産性25%向上(中堅ゼネコン)
関西エリアの中堅ゼネコンA社は、ICT建機を複数台導入したものの、 当初は「操作できる人が限られている」「データ活用が進まない」という課題に直面していました。
そこで同社は、導入と同時にAI施工管理ツールの活用研修を実施。
現場代理人・オペレーター・若手社員が同じ教材で「データを見る」「AIに指示を出す」演習を行いました。
結果、
- 重機稼働率の可視化による無駄削減
- 報告書作成の自動化による事務負担軽減
- 工期全体の25%短縮
といった成果を実現。
教育投資がROI(投資対効果)を3倍以上に押し上げた代表的な事例です。
ケース② BIM連携教育で設計工期を20%短縮(設計事務所)
首都圏の総合設計事務所B社では、BIMソフトを導入しても 「担当者ごとにデータ形式が異なり、共有に時間がかかる」ことが課題でした。
同社は、社内BIM教育チームを立ち上げ、週次でモデリング演習+レビュー会を実施。
さらに、設計と施工担当が同じデータベース上で意見交換できる体制を構築しました。
教育から半年で、
- 図面修正工数の大幅削減
- 設計〜施工間の調整時間を約20%短縮
- 社内コミュニケーションの改善
という定量的成果が見られました。
社員の声には、「技術よりも“共通言語としてのBIM理解”が大きかった」 とあり、教育が組織文化を変える起点になったことがわかります。
ケース③ DX教育を通じて現場提案が増加(地方工務店)
地方都市でリフォーム・土木事業を手掛けるC工務店では、 デジタル活用が遅れ、見積作業や報告業務が属人化していました。
自治体の補助金を活用し、AI経営総合研究所の生成AI研修プログラムを受講。
現場スタッフが自分でAIに質問し、図面説明や顧客対応文書を自動生成できるように。
その結果、
- 顧客への提案資料作成時間が半減
- 新規顧客提案数が前年比1.5倍
- 社員のAI利用率80%以上
という成果を実現しました。
特に注目すべきは、「教育によって現場の提案力が向上した」点。
単なる効率化ではなく、“人材が成長する仕組み”が企業価値を高める好例です。
成功事例に共通する3つのポイント
- 導入と教育を同時設計し、「使う段階」を初期から想定していた
- 現場全員参加型の研修で、理解度と再現性を確保した
- データ・AI活用が“個人スキル”から“組織文化”へと進化した
まとめ|スマートコンストラクションの未来を動かすのは“人”
スマートコンストラクションの本質は、ICT建機でもAIでもありません。
それらを現場で使いこなし、成果に変えられる“人”にこそ、真の価値があります。
いま業界全体が「デジタル導入」から「人材育成」へと舵を切る中で、 企業の競争力を決めるのは、どんな技術を導入したかではなく、 その技術を活かす“人と文化”をどう育てたかにあります。
教育はコストではなく、未来への投資です。
機器を買うだけではROIは一時的、 しかし「学びの仕組み」を社内に根づかせれば、 現場が自走するスマート建設へと進化していきます。
そして、この“育成を内製化できる企業”こそ、変化の激しい建設業界で持続的に成長を続ける企業になるでしょう。
次の一歩は、教育を「属人的な研修」ではなく、 “仕組みとして設計する”段階へ。
補助金・AIツール・データ環境を組み合わせ、 “人が育つDX基盤”を整えることが、これからの経営戦略の中心です。
- Qスマートコンストラクションに必要な人材とはどのような人ですか?
- A
スマートコンストラクションを動かす人材とは、 ICT施工・BIM/CIM・AIツールを使いこなせる現場リーダー層です。
単なるオペレーターではなく、データを読み解き現場を改善できる人が求められています。また、コミュニケーションやマネジメントなどの“人を動かすスキル”も重要です。
AI経営総合研究所では、こうした総合的スキルを5分類に体系化し解説しています。
- Qスマート建設人材はどのように育成すればいいですか?
- A
ポイントは「リテラシー → 実践 → マネジメント」の3段階教育です。
現場理解から始め、ICT機器・AIツールの活用研修、 そしてデータを活かして改善をリードするマネジメント教育へと進めます。このステップを設計することで、現場が自走するスマート建設体制が実現します。
- Qスマートコンストラクション人材の採用市場は伸びていますか?
- A
はい。ICT施工・BIM/CIMエンジニア、建設DX推進担当など、 関連職種の求人数はこの5年で2倍以上に拡大しています。
大手ゼネコンだけでなく、地方企業や設計事務所でも採用が加速中です。今後は、AI・データ分析など異業種スキルを持つ人材の流入も増える見通しです。
- Q補助金で人材教育や研修にも活用できますか?
- A
はい。国交省の「建設業DX推進支援事業」などでは、 ICT建機やBIMツールの導入費用に加えて教育・研修費も補助対象です。
補助金を“導入資金”として使うだけでなく、 “教育投資”として活用する企業が成果を上げています。
- Qどんな研修を導入すればスマート建設人材を育てられますか?
- A
おすすめは、AI・データを現場に活かす実践型研修です。
特に生成AIやデータ解析ツールの活用法を、 「現場の課題に即した形」で学ぶプログラムが効果的です。AI経営総合研究所の研修では、 “ツール操作”ではなく“業務改善を設計できる力”を身につける内容を提供しています。