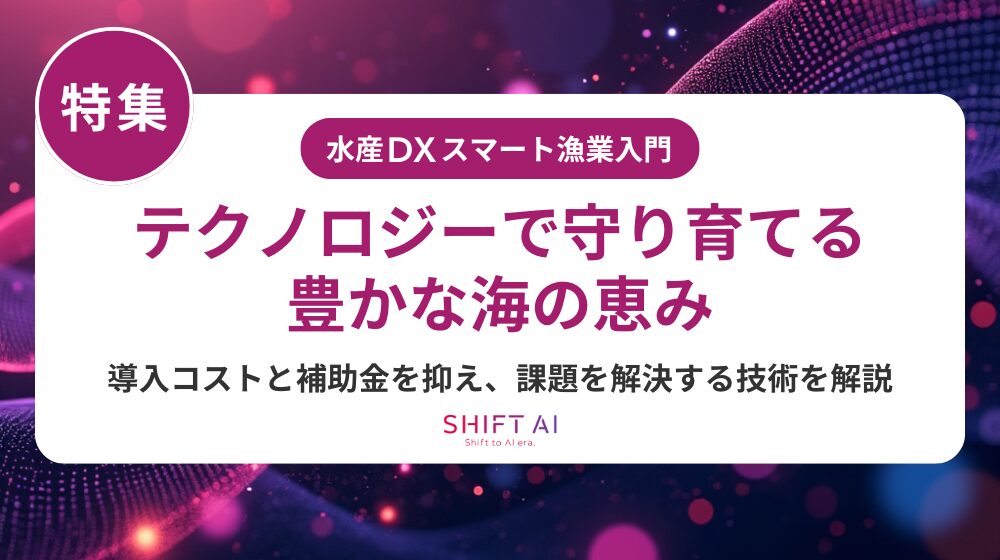気象変動や赤潮による漁業被害が増えるなか、現場では「勘と経験」だけに頼らない新しい操業スタイルが求められています。
その鍵を握るのが、ドローンによる“空からのスマート漁業”です。
上空から海況を撮影し、AIが赤潮や魚群の変化を解析。燃料費や作業時間を削減しつつ、環境変化への対応力を高めています。
すでに自治体や漁協でも導入が始まり、データを活かした「見える漁業」へと進化が進行中です。
この記事では、スマート漁業におけるドローン活用の最新事例と効果、導入課題、そしてAI連携による今後の展望をわかりやすく解説します。
スマート漁業の全体像を知りたい方はこちら:
スマート漁業(スマート水産業)とは?AI・IoTで進化する持続可能な漁業と導入ステップを解説
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ今「ドローン×スマート漁業」なのか
漁業の担い手不足が深刻化し、海況の変化も年々激しくなる中、「経験と勘」だけでは操業判断が難しくなっています。
特に赤潮や水温上昇などの環境変化は、数日遅れの対応が漁獲量や品質に直結します。
こうした課題に対し、ドローンが“空からのセンサー”として現場を支える動きが進んでいます。
上空から撮影した映像や温度データをAIが解析することで、魚群の動きや海面の異変をリアルタイムで把握できるようになりました。
その結果、操業計画の精度が向上し、無駄な燃料消費を抑えながら効率的な漁を実現できます。
国や自治体もこの動きを後押ししており、水産庁は「スマート水産業推進事業」を通じて、
AI・IoT・ドローンの実証実験や普及支援を進めています。
これまで“人の目”に頼っていた海の情報が、データで見える化される時代が到来しているのです。
ドローンの種類と特長|空撮・水中・自律航行の3タイプ
スマート漁業で活用されるドローンは、大きく 「空撮型」「水中型」「自律航行型」 の3種類に分けられます。
それぞれの特長と活用シーンを理解することで、導入目的に合った機体選定がしやすくなります。
空撮型ドローン
主に海面や沿岸のモニタリングに使用され、赤潮検知や魚群探索で活躍します。
上空から広範囲を俯瞰できるため、AI解析と組み合わせることで海況の変化をリアルタイムに把握可能です。
水中ドローン
水深数十メートルの海中を潜行し、カメラやセンサーで魚群や養殖網の状態を撮影します。
近年はAIが映像を解析して、魚の成長状況や異常行動を自動検知できる機種も登場しています。
自律航行型ドローン
あらかじめ設定したルートを自動で飛行または潜行し、定期的な監視やデータ取得を行うタイプです。
養殖場や港湾の巡回監視、夜間点検など、人手のかかる作業の自動化に適しています。
これらを適切に組み合わせることで、“空・海中・データ”をつなぐ統合的なスマート漁業システムが構築できます。
赤潮検知におけるドローン活用|“早期対応”が被害を防ぐ
赤潮の発生は、漁業被害の中でも最も深刻な問題のひとつです。
これまでは漁業者の目視や採水検査による監視が中心で、発見が遅れると、わずか数日のうちに漁場全体が被害を受けるケースもありました。
こうした課題に対し、各地で注目されているのがドローンを活用した赤潮検知システムです。
上空から海面を撮影し、AIが画像の色調や濁度の変化を解析。異常な水質パターンを自動検出し、赤潮発生の兆候を早期に警告します。
たとえば長崎県五島市や愛媛県宇和島市では、自治体と企業が連携してAI搭載ドローンによる赤潮監視の実証を進めています。
海上を広範囲に飛行し、取得した映像をクラウド上で解析。
現場のスマートフォンやタブレットにリアルタイムで結果が通知される仕組みです。
この仕組みにより、従来の監視業務に比べて検知スピードは数時間単位から数十分単位へ。
赤潮被害の抑制だけでなく、漁業者の労働負担や燃料コストも大きく軽減されています。
ドローンは、単なる“監視の代替”ではなく、海況を数値化して判断を支える意思決定ツールへ進化しているのです。
スマート漁業の導入ステップ全体を知りたい方はこちら:
スマート漁業(スマート水産業)とは?AI・IoTで進化する持続可能な漁業と導入ステップを解説
魚群監視・漁場探索の最前線|“海のデータ化”で操業効率を最大化
漁場を見極める作業は、これまで熟練の経験や勘に大きく依存してきました。
しかし、漁業者の高齢化や気象の変動により、経験だけで安定した成果を上げることが難しくなっています。
こうした中で注目を集めているのが、ドローンとAIを組み合わせた魚群監視システムです。
上空から赤外線や超音波を用いて海中の温度分布や魚群の動きを把握し、AIが解析して「魚群の密度」「移動方向」「水温との相関」などをリアルタイムに可視化します。
このデータをもとに、漁業者はアプリ上で操業計画を立てられるようになり、無駄な燃料消費を抑えつつ、短時間で効率的な漁を行うことが可能になっています。
実際に一部の自治体では、ドローンの取得データと衛星観測情報を連携させることで、 “高精度な漁場予測モデル”の構築も進められています。
従来の「感覚的な操業」から、データに基づく「戦略的な操業」へ――
スマート漁業の核心は、まさにこの“海のデータ化”にあります。
こうしたデータの読み取りや運用を自社で行うためには、AI解析やデータリテラシーを持つ人材の育成が不可欠です。
現場で得られるデータをどう活かすかが、今後の競争力を左右します。
養殖場・港湾で進む自動巡回と遠隔監視
ドローンの活用は、操業や魚群探知だけにとどまりません。近年では、養殖場や港湾の巡回・監視業務にも導入が広がっています。
養殖現場では、給餌や網の点検、水質確認といった作業が毎日必要です。
従来は人が船を出して行っていましたが、波や天候の影響を受けやすく、人手不足が進む中では継続的な管理が難しくなっていました。
そこで活躍するのが、自律航行型の水中・空中ドローンです。設定したルートを自動で巡回し、カメラやセンサーで水質データや映像を取得。
AIが映像を解析して、魚の動き・給餌量・網の損傷などを検知します。異常があれば自動でアラートを発し、現場のタブレットやPCに通知します。
人がすぐに確認・対応できる体制を整えられるようになりました。
このような“遠隔+自動監視”の仕組みは、省人化だけでなく安全性向上にもつながります。
夜間や悪天候時でもドローンが代わりに巡回できるため、作業者のリスクを最小限に抑えられます。
また、取得したデータをAIが継続的に分析することで、魚の成長傾向や飼育環境の変化を“見える化”し、最適な運用判断を支援します。
このように、ドローンは“飛ぶカメラ”から、「自動運用の一員」へと進化しています。
人の作業を補完する存在ではなく、現場のチームメンバーとして機能する段階に入っているのです。
スマート漁業の全体像や他の技術活用も知りたい方はこちら:
スマート漁業(スマート水産業)とは?AI・IoTで進化する持続可能な漁業と導入ステップを解説
導入コスト・運用課題とその解決策
── 技術導入の壁を超えるための3つの視点
スマート漁業でドローンを導入する際、最初のハードルになるのがコストと運用体制の整備です。
ドローン本体の価格は、機能や耐環境性能によって大きく異なります。
基本的な空撮型で50〜100万円前後、水中撮影・AI解析を搭載したモデルでは数百万円規模となる場合もあります。
ただし、燃料費削減や人件費抑制といったランニングコストの削減効果を考慮すると、数年で投資を回収できるケースも増えています。
次に課題となるのが通信インフラと安全管理です。
ドローンは海上を飛行するため、LTE通信やGPS信号が届きにくい地域では安定した運用が難しくなります。
こうした地域では、衛星通信対応型ドローンやリレー基地局の設置によって通信を確保する方法が有効です。
また、飛行ルートや高度を制御する自動運航ソフトウェアの整備も欠かせません。
さらに、忘れてはならないのが法規制と補助制度です。
2022年以降、航空法改正によりレベル4(有人地帯上空)の飛行も条件付きで可能となり、
漁港や沿岸でのドローン運用が現実的になりました。
同時に、水産庁の「スマート水産業推進実証事業」や各自治体のスマート化補助金を活用すれば、機材導入やAI解析ソフトの開発費を一部支援してもらうことが可能です。
コスト・通信・制度――この3つを整理すれば、導入の壁は高くありません。
むしろ、AI活用とデータ運用を前提とした“仕組み設計”こそが、長期的な成果を生む鍵となります。
補助金・支援策の詳細はこちら:
スマート漁業・スマート水産業の補助金2025|採択のコツと申請手順を徹底解説
AI解析との連携で広がる“データ駆動型漁業”
── ドローンが集める膨大なデータを、どう活かすか?
ドローンが撮影・収集するのは、海面映像や水温データ、魚群の分布といった膨大な情報です。
このデータをAI解析と組み合わせることで、海の“状態”を数値として把握できるようになりました。
たとえばAIが過去の漁獲データと海況を照合し、
「どのエリアで、どの時間帯に、どんな魚が集まりやすいか」を自動で予測する。
この分析結果を現場のタブレットに表示することで、漁業者はリアルタイムに操業計画を調整できるようになっています。
また、赤潮や海洋異変の予兆をAIが早期に検出し、被害を最小限に抑えるリスクマネジメントにも活用されています。
さらに、ドローンのデータと衛星観測・気象情報を統合することで、広域的な漁場予測や海洋資源のモニタリングが可能になり、将来的には“持続可能な水産資源管理”の基盤にもつながると期待されています。
しかし、こうした技術を真に活かすには、現場でデータを理解し、AIの判断を正しく読み取れる人材が欠かせません。
単にドローンを飛ばすだけでなく、得られたデータを事業判断に結びつけられるスキル――それが今、最も求められています。
AI解析を活用する力は、漁業だけでなく製造・物流・建設など他産業でも共通する基盤です。
現場でのデータ活用を社内に根づかせるために、生成AIやデータ分析のリテラシー教育を体系的に行うことが、次のステップになります。
関連記事:
スマート漁業が進まない3つの課題とは?高齢化・導入コスト・データ連携の壁と解決策を解説
未来展望|ドローンが拓く「持続可能な漁業経営」の新モデル
スマート漁業におけるドローン活用は、いまや一過性のトレンドではありません。
AI解析や衛星データと連携することで、ドローンは「環境変化を読むセンサー」から「意思決定を支えるパートナー」へと進化しています。
これまで漁業は、天候や潮流など自然の変化に左右される産業でした。
しかし、ドローンによるデータ収集とAI解析を組み合わせることで、変化を“予測可能な情報”として扱えるようになりつつあります。
こうした「データ駆動型の漁業経営」は、単なる効率化ではなく、環境保全と収益性を両立する“持続可能な経営モデル”を生み出します。
また、地域連携の動きも加速しています。
複数の漁協や自治体が、ドローンで取得したデータを共有し、漁場資源の最適利用や災害対策に役立てる“オープンデータ型の水産DX”が広がり始めました。
技術だけでなく、人・組織・地域がつながることで、海と共に生きる産業としての再成長が期待されています。
ドローンをはじめとするテクノロジーは、現場の知恵と組み合わせてこそ真価を発揮します。
AIを理解し、運用できる人材が増えるほど、技術は地域の力に変わる。
その第一歩として、社内にAI活用スキルを根づかせる教育が欠かせません。
まとめ|“空からの視点”が、水産業の未来を変える
ドローンの登場によって、海の現場は確実に変わりつつあります。
これまで人の経験と感覚に頼っていた操業判断が、今ではデータとAI分析によって“見える化”され、科学的な裏づけを持つ漁業へと進化しています。
赤潮検知、魚群監視、養殖場の自動巡回――
こうした技術のすべては、ドローンが集めた情報をもとにAIが導き出す「最適な判断」です。
つまり、ドローンは単なる機械ではなく、人の意思決定を支える“空のパートナー”になりつつあります。
一方で、こうしたテクノロジーを真に活かすには、AIやデータを理解し、活用できる人材が欠かせません。
スマート漁業の未来を担うのは、機械でもAIでもなく、それらを正しく使いこなす人です。
SHIFT AIでは、現場で使える生成AI・データ分析研修を通じて、水産業の次世代人材育成を支援しています。
「ドローン×AI」で広がるスマート漁業の可能性を、 人の力で“未来の現場”に変えていく――その第一歩を、今ここから。
よくある質問|スマート漁業×ドローンの仕組み・価格・導入ポイント
- Qスマート漁業に使われるドローンの価格はどのくらいですか?
- A
用途によって価格帯は異なります。
海面観測用の小型ドローンは50〜100万円前後、水中撮影やAI解析機能を搭載した機体は200〜500万円程度が一般的です。補助金を活用すれば導入コストを大幅に抑えることもできます。
- Q赤潮検知ドローンはどのような仕組みでAIが解析しているのですか?
- A
上空から取得した海面映像をAIが色調・濁度・水温変化などのパターンとして解析します。
通常の海水と比較して異常な変化が見られた箇所を検知し、赤潮の発生リスクをリアルタイムに通知する仕組みです。
こうしたAI画像解析は、漁業被害の早期抑制に大きく貢献しています。
- Q養殖業でもドローンは活用できますか?
- A
はい。近年では、給餌・水質確認・網の点検などを自動で行う養殖ドローンが実用化されています。
AIが映像を解析し、魚の成長状況や健康状態を判断することも可能です。
人手不足や夜間作業の安全確保など、養殖業特有の課題にも効果的です。
- Qドローンを漁業で使う際、どんな許可や法規制が必要ですか?
- A
航空法に基づき、原則として国土交通省の飛行許可・承認が必要です。
特に漁港や沿岸での飛行は、第三者上空や目視外飛行に該当するため、事前申請が求められます。
2022年の改正で「レベル4飛行」が一部解禁され、条件を満たせば有人地帯上空での運用も可能になりました。
安全運用のためには、最新の法改正情報を常に確認することが大切です。
- Qドローンで集めたデータをAIで扱うには、どんな知識が必要ですか?
- A
基本的なデータ分析スキルと生成AIの活用知識が求められます。
AIの判断を正しく読み取り、現場の判断に活かせる人材がいることで、ドローン導入の成果は大きく変わります。