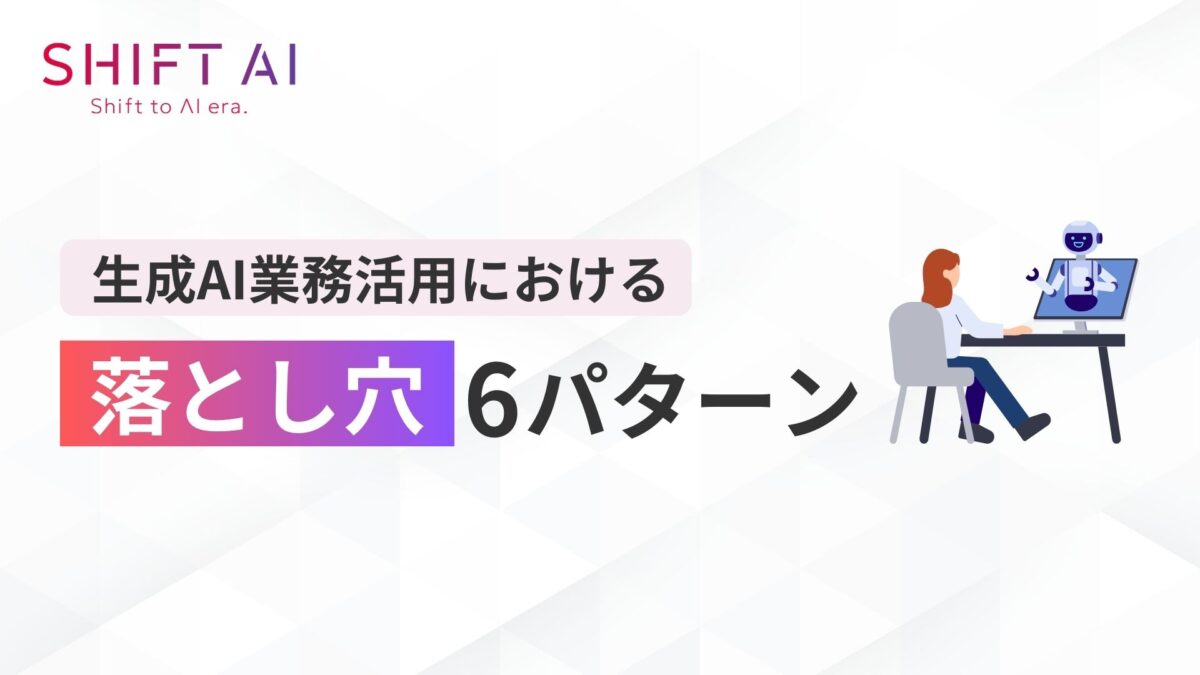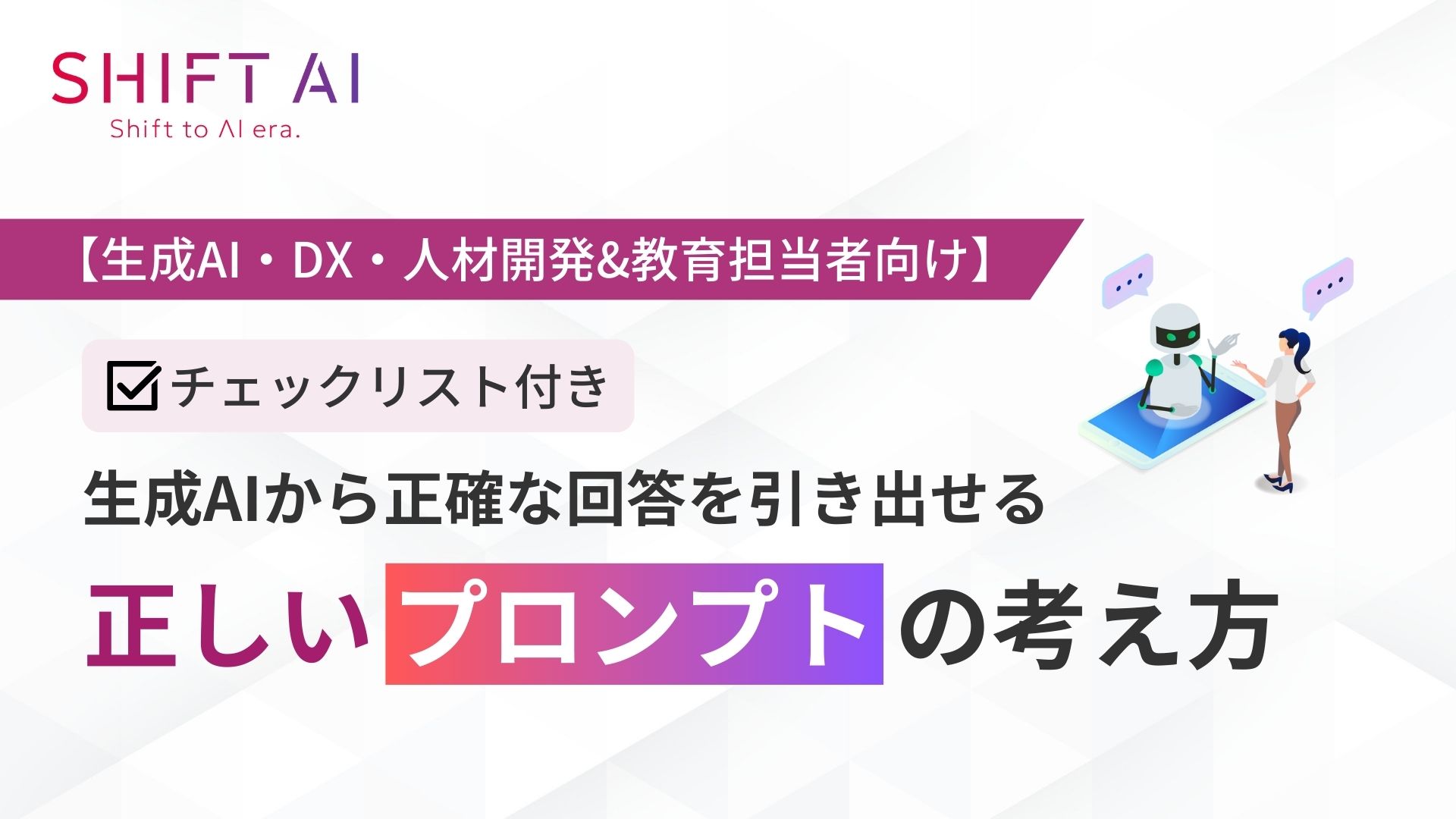自治体のDX(デジタルトランスフォーメーション)は、 「導入までは進んだのに、思ったほど成果が出ない」「職員が疲弊してしまった」 という声が全国で相次いでいます。
AIチャットやRPA、電子申請などの仕組みを整えても、 運用が定着せず“形だけのDX”に終わるケースは少なくありません。
その背景には、目的の不明確さ・外部依存・職員リテラシーの格差といった “人と組織”の構造的な問題が潜んでいます。
DXの失敗は、単なるシステムトラブルではなく、「現場で使いこなせない仕組みを作ること」にあります。
しかし裏を返せば、そこにこそ「再挑戦できる改善の余地」があります。
本記事では、自治体DXが失敗する典型パターンとその原因を整理し、 現場が疲弊しないための再発防止策を5つのステップで解説。
あわせて、成功している自治体が実践する「AI人材育成」や「定着型DX推進」の仕組みも紹介します。
今すぐ知りたい方へ
自治体DXを成功に導く5ステップ|現場課題とAI人材育成の実践法
DXの全体像を理解したい方はこちらもおすすめです。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ自治体DXは失敗するのか?“進まない”との違いを理解する
DXの推進に取り組む自治体の多くが抱える課題は、大きく分けて2種類あります。
ひとつは「進まないDX」──計画や方針は立てたものの、予算確保や体制づくりで止まってしまうケース。
もうひとつは「失敗するDX」──導入までは完了したものの、運用が続かず形骸化していくケースです。
「進まない」DX=計画段階で止まる
進まないDXは、主に準備不足が原因です。
具体的には、
- DXの目的やゴールが明確でない
- 専任部署や推進担当者が不在
- 他部署の理解・協力が得られない
といった、組織体制の未整備によって計画が頓挫します。
これは、いわば“スタートできないDX”。
「何から始めればいいか分からない」状態で時間だけが経過してしまうパターンです。
「失敗する」DX=導入後に形骸化・現場が疲弊
一方で、導入まで進んだ自治体でも、運用が続かないDXが増えています。
AIチャットやRPA、電子申請などのシステムを導入したものの、 現場では「むしろ仕事が増えた」「新しい仕組みに慣れずミスが増えた」といった声が多く、 職員の疲弊を招いてしまう例も少なくありません。
こうした“導入後に息切れするDX”の特徴は、
- 導入目的が職員に共有されていない
- システム運用が特定部署に集中している
- 教育・フォローアップ体制が整っていない
など、仕組みではなく“人と運用”が機能していないことにあります。
デジタル庁・都市センター調査から見る“失敗の構造”
デジタル庁が2024年に実施した自治体DX推進状況調査でも、 約6割の自治体が「DXを推進中」と回答する一方、 “効果が出ている”と実感できている自治体は全体のわずか2割程度に留まっています。
また、公益財団法人日本都市センターの職員アンケートでは、 DX推進によって「業務が楽になった」と回答した職員が31%に対し、 「むしろ業務が増えた」が46%と上回る結果に。
これらの調査から見えてくる“失敗の構造”は、以下の3つに集約されます。
- 職員リテラシー格差:ツールを使いこなせる職員と使えない職員の差が拡大
- 外部依存:ベンダー任せで庁内に知見が残らない
- 目的不在:導入目的や成果指標が明確でなく、形骸化する
DXの失敗は、システムそのものの問題ではなく、 「人材」「運用」「目的設計」──この3つが噛み合っていないことが本質的な原因です。
DXの進め方や組織設計の全体像を知りたい方は、 自治体DXを成功に導く5ステップ|現場課題とAI人材育成の実践法 で詳しく解説しています。
自治体DXが失敗する5つの典型パターン
自治体DXがうまくいかない背景には、単なる「予算不足」や「人手不足」だけではない、
“構造的な共通パターン”があります。
多くの自治体が同じ道をたどり、同じ落とし穴に陥っているのです。
ここでは、上位自治体や各種調査で明らかになった「5つの典型的な失敗パターン」を整理し、 その根底にある“人と組織”の課題、そしてAI経営メディアが考える再発防止のヒントを紹介します。
① 目的不明のまま“システム導入”が先行
補助金活用の期限ありきで、業務設計が置き去りになる
多くの自治体で見られるのが、「補助金の期限に合わせて急ぎ導入した結果、活用されない」ケースです。
DXの目的が明確でないままシステムを入れてしまうと、 職員は“なぜ導入したのか”を理解できず、現場に浸透しません。
実際、導入直後に「結局紙の申請も並行運用」「操作が複雑で利用率が低下」といった問題が発生するのは、 “業務の棚卸し”をしないままDXを進めたことが原因です。
対策:
導入の第一歩は、ツール選定ではなくBPR(業務プロセス再設計)です。
「どの業務を、なぜ変えるのか」を職員自身が整理し、 “手段ではなく目的”から始める文化づくりが不可欠です。
② ベンダー依存で庁内にノウハウが残らない
外注任せの結果、改善サイクルが止まる
DX推進を外部ベンダーに委託する自治体は多いですが、 そのまま任せきりにしてしまうと、庁内にノウハウが蓄積されません。
結果として、「担当者が異動したら何も分からない」「更新や改善ができない」という事態に陥ります。
この構造は、“導入後の持続力”を奪う最大の要因です。
対策:
外部ベンダーとの協働を前提にしつつも、 庁内に“デジタル推進リーダー”を配置し、内製化を少しずつ進めることが重要です。
AI・RPAの運用やデータ分析を理解できる人材を育て、 “外部に依存せず、改善を回せる体制”を作りましょう。
補足:
DXの持続性は、技術よりも「人の理解と自走力」で決まります。
これは企業DXにも共通する“成功の法則”です。
③ 現場の声を反映せず、職員が“疲弊”するDX
現場ではむしろ作業量が増加、職員が離反
DXの目的が“現場の負担軽減”であるはずなのに、 実際には「入力作業が増えた」「ミスが増えて残業が増えた」という声が多く聞かれます。
これは、導入プロセスに現場の意見が反映されていないことが原因です。
DX推進が“上からの施策”として進むと、職員は「やらされ感」を抱き、 結果として運用が続かずに失敗へとつながります。
対策:
新しい仕組みを導入する前に、PoC(小規模実証)を行い、 現場の業務フローにどのような負担が生じるかを検証しましょう。
小さく試し、職員の意見を反映させることで、 “やらされるDX”から“共につくるDX”へと転換できます。
現場の「成功体験」を共有すると、DXへの信頼が一気に高まります。
④ 部署間でデータ連携ができず、効果が限定的
横の連携不全がシステムの“壁”になる
DXは本来、部署や分野を超えたデータ活用を実現するものですが、 自治体では依然としてシステム間の連携不足が大きな課題です。
たとえば、福祉・税・住民記録などが別々の基盤で動いており、 データを横断的に活用できない状況が続いています。
結果、導入したシステムが“点の改善”で終わり、 全体としての業務効率化や住民サービス向上につながらない。
対策:
- SaaSの標準化:国が推進する「自治体情報システム標準化ガイドライン」に沿って統一仕様を採用。
- API連携の推進:既存システム間をAPIでつなぎ、データを“流れる”形に。
これにより、「一度入力したデータを何度も使える」体制を実現し、 業務全体の一貫性とスピードを高められます。
⑤ 教育・運用体制が続かず“形骸化”する
担当異動でノウハウが消失、結局“戻る”
導入時に熱意を持ってDXを進めたとしても、 担当者の異動や退職で運用ノウハウが途切れ、 「誰も使えなくなって結局元に戻る」というケースが後を絶ちません。
多くの自治体がこの“継続性の壁”にぶつかっています。
対策:
DXを定着させるには、「人を入れ替えても回る仕組み」が必要です。
そのために、AIリテラシー研修を仕組み化し、職員の基礎理解を均一化しましょう。
また、導入後も継続的に学び直す「アップデート教育」を行うことで、
庁内全体の“デジタル文化”が根づきます。
DXは技術の問題ではなく、学習する組織を作れるかが鍵です。
成功自治体ほど、研修と運用が一体化しています。
これら5つの失敗パターンは、どれも“特殊な事情”ではなく、 全国の自治体で共通して起きている構造的課題です。
しかし裏を返せば、共通しているからこそ、改善の道筋も再現可能です。
DX失敗の裏にある“職員疲弊”という構造問題
自治体DXの失敗の背景には、システムや予算の問題だけでなく、 「人の疲労」と「組織文化のひずみ」が潜んでいます。
「業務が減らない」「むしろ仕事が増えた」と感じる職員は、 公益財団法人日本都市センターの調査によると約6割にのぼります。
導入当初は期待が高かったものの、実際には現場が“負担を押しつけられた”形になっているのです。
デジタル化=「追加業務化」という現場の現実
本来、DXは業務を効率化し、職員の負担を減らす取り組みです。
しかし、実際の現場では「紙とシステムの並行運用」「二重入力」「マニュアル整備」など、 一時的な追加業務が必ず発生します。
これらを「移行期だから仕方ない」と軽視すると、 職員のモチベーションが急速に低下し、 「どうせ楽にならない」「また新しい仕事が増えるだけ」といった“DX疲れ”が広がります。
これは単なる作業負担ではなく、 「目的が見えないまま変化だけを求められる心理的負荷」が原因です。
目的共有・教育・運用設計の欠如が、疲弊を生む
DXにおける“疲弊構造”を分解すると、以下の3つに集約されます。
- 目的共有の欠如
──「なぜ導入するのか」「どんな成果を目指すのか」が現場に伝わらない。
その結果、変化が“押しつけ”として受け取られる。 - 人材教育の不足
──操作方法の研修はあっても、「なぜそれを使うのか」という背景理解が不足。
不安が大きいまま実務に追われ、結果的にミスや負担が増える。 - 運用設計の欠如
──業務プロセスの見直しが不十分なままシステムを導入し、 紙とデジタルが併存する「中途半端な状態」が続く。
これらが重なると、DXは“効率化”どころか“複雑化”を招き、 「システムを使うことが目的化する」状態に陥ります。
DX疲れを防ぐには、「減らす設計」と「支える研修」の両輪が必要
DXの真の目的は、業務を“デジタル化すること”ではなく、 人が安心して価値ある仕事に集中できる環境をつくることです。
そのためには、次の2つの視点が欠かせません。
- 減らす設計:
導入前に「どの業務を削減・統合できるか」を洗い出し、 デジタル化によって確実に“減る実感”を得られる設計にする。 - 支える研修:
操作説明ではなく、AIリテラシー・データ理解・問題解決思考など、 “自ら改善できる職員”を育てる教育体系を整える。
この両輪が揃ってはじめて、DXは“人を疲弊させる仕組み”から“人を支える仕組み”へと変わります。
DXはツールではなく「組織文化の再設計」。
成功する自治体ほど、“現場の幸福度”をKPIに含めているのが特徴です。
失敗を防ぐための5つの再発防止ステップ
DXの失敗は、システムや予算ではなく、進め方と人の関わり方に原因があります。
そのため、失敗を防ぐには“もう一度仕組みを整える”のではなく、 「現場に根づくDX」を再設計することが必要です。
ここでは、実際に成果を上げている自治体の取組事例をもとに、 再発防止につながる5つの実践ステップを紹介します。
STEP1:業務を棚卸しし、課題を“可視化”する
DXを進める前に、まずは「何を変えるべきか」を可視化しましょう。
この段階で有効なのが、業務棚卸し(BPR)です。
現場単位で業務フローを洗い出し、手作業・重複・属人化している部分を明確にします。
ExcelやGoogleスプレッドシートでも十分対応可能で、 住民・職員の双方の視点から課題を数値で把握することが重要です。
ポイント:
「業務時間」や「処理件数」などの客観データをもとに議論することで、 「なんとなく非効率」から「どこを改善すべきか」へ焦点を絞れます。
STEP2:現場リーダーを中心に“目的を共有”する
DXの成否を分けるのは、目的の共有度です。
「なぜそれを導入するのか」「どんな成果を目指すのか」が明確でないと、 現場は“やらされ感”を抱き、継続的な改善が止まります。
部署横断の会議体を設け、住民対応・情報システム・総務などが一堂に集まり、 共通KPI(例:処理時間短縮率・住民満足度など)を設定することで、 「何を改善するDXなのか」を具体的に共有できます。
成功自治体の多くは「DX推進会議」を定例化し、 現場リーダーが“説明できるDX”を実現しています。
STEP3:PoC(小規模実証)で“失敗できる場”を作る
DXの導入は、一気に全庁展開する必要はありません。
むしろ、失敗を許容できる“小さな成功体験”を積み重ねることが重要です。
PoC(Proof of Concept:概念実証)を行い、 現場の負担や効果を定量的に検証した上で、 他部署へと段階的に広げていくことで、無理のない定着が可能になります。
ポイント:
「失敗できるDX」を設計することが、“失敗しないDX”への第一歩です。
STEP4:AI・データを活用し、“人が減らない効率化”を実現
DXの目的は、単に作業を自動化することではありません。
AIやデータを活用し、職員の判断や提案を支援する仕組みをつくることが本質です。
たとえば、
- AIチャットで問い合わせ対応を自動化し、時間を創出
- RPAで定型業務を処理し、職員を“考える業務”へ再配置
- データ分析により、住民ニーズを把握し、政策企画に活かす
こうした「人の力を引き出す効率化」が、 “人が減っても業務が回る”DXではなく、 “人が減らずに成長するDX”を実現します。
STEP5:教育・研修で“使いこなせる人”を増やす
DXを持続させる最大のカギは、“人”です。
どれほど優れたシステムを導入しても、使いこなせる人がいなければ意味がありません。
- 新規導入時:全職員向けに「操作+背景理解」の研修を実施
- 定着期:リーダー層に向けた「AI活用・データリテラシー研修」を展開
- 継続期:異動や新任職員への「更新研修」で知識を継承
このように研修を仕組み化することで、 担当者が変わっても運用が止まらない「学習する組織」を構築できます。
DXは“ツールの刷新”ではなく“人材の更新”。
職員教育を制度化することで、DXの成果が持続します。
現場の職員が自ら使いこなせるようになるまで支援。
“続くDX”を実現するための育成ステップを無料で確認できます。
成功自治体に共通する「失敗を活かす仕組み」
DXの成功事例は、最初から完璧だったわけではありません。
多くの自治体が「最初の失敗」を経験し、そこから改善を重ねてきました。
重要なのは、“失敗をデータで検証し、改善を文化にする”ことです。
ここでは、DXを「導入して終わり」にせず、 現場の運用力とデータ活用で成果を出した3つの自治体の事例を紹介します。
千葉市:AIチャット導入後、問い合わせデータをKPI管理に転用
千葉市では、住民からの問い合わせ対応の効率化を目的にAIチャットを導入しました。
当初はFAQ精度の低さや回答漏れが課題でしたが、 チャット履歴データを分析し、“問い合わせ傾向”をKPIとして可視化。
これにより、頻出質問の整理や担当部署の配置見直しが進み、 現在では1日200件以上の問い合わせを自動処理し、 職員対応の工数を30%削減するまでに改善しました。
ポイント:
「AIを導入して満足」ではなく、“データを活かして育てる”運用姿勢が成功要因。
釧路市:AI-OCRで業務時間を1/3削減し、職員を再配置
釧路市は、手作業で行っていた申請書のデータ入力をAI-OCRで自動化。
導入初期には読み取り精度や書式ズレなどの課題がありましたが、 現場の職員が自ら改善ポイントを報告し、システム設定を最適化しました。
結果、手入力工数を約1/3に削減。
余剰時間を住民対応や政策企画へ再配分することで、 「単なる効率化」ではなく「人が活かされるDX」を実現しています。
DXの成果は“時間削減”だけで測るものではありません。
生まれた時間を“どの業務に再投資するか”が、持続的成果を左右します。
横浜市:電子決済導入後、来庁予約で満足度40%向上
横浜市は、窓口混雑の解消を目的に電子決済と来庁予約システムを導入。
初期段階では利用率が伸び悩みましたが、 市民アンケートとアクセスログを分析し、 「利用しやすい時間帯」「スマホ操作のつまずき箇所」をデータで把握。
その結果、UI改善と周知施策を強化し、利用率が急上昇。
来庁者の平均待ち時間を40%短縮し、 住民満足度も大幅に向上しました。
ポイント:
成果を“市民体験の変化”で測定し、 “データに基づく改善文化”を行政運営に取り入れたことが鍵。
成功自治体に共通するのは「失敗を活かす力」
これらの自治体に共通するのは、 「失敗をデータで検証し、改善を続ける運用体制」を確立している点です。
導入直後に課題が出るのは当然。
大切なのは、その課題を“現場の知恵”として蓄積し、次に活かす仕組みを持っていることです。
DXは“導入して終わり”ではなく、 “改善が文化化”したときに真価を発揮します。
そしてその文化の核となるのは、システムではなく“人”。
現場で課題を見つけ、データを読み解き、改善を提案できる職員こそ、DXを支える主役です。
DXを持続させる“人と組織”の育て方
自治体DXを成功に導く最大のポイントは、 「導入して終わり」ではなく「育てながら続ける」こと。
多くの自治体では、担当部署に負荷が集中し、 DXが一部業務として“孤立”してしまうケースが見られます。
DXを一過性のプロジェクトではなく、 全庁的な文化へと昇華させることが、持続的な成果を生む鍵です。
DXを「担当部署の業務」から「全庁的文化」へ変える
DX推進を情報システム課や企画部署だけの取り組みとして閉じてしまうと、 現場との温度差が生まれ、運用が定着しません。
成功している自治体では、DXを“全庁の共通課題”として共有し、 庁内の各部門が「自分ごと」として関われる仕組みを整えています。
- 定例会でDX進捗を共有
- 成果を“庁内表彰制度”などで見える化
- 部署をまたぐ横断プロジェクトの設置
このように、DXを“みんなで育てる文化”に変えていくことが、 継続力を生み出す最初の一歩です。
階層別AIリテラシー研修で現場の理解を底上げ
DXの理解度は、職位や担当業務によって大きく異なります。
現場職員には「操作・実務の理解」が、 管理職には「戦略・成果管理の視点」が求められます。
そのため、階層別のAIリテラシー研修を実施し、 全員が“自分の立場でDXを語れる”状態をつくることが重要です。
成功自治体ほど、「研修=教育」ではなく「共通言語づくり」と捉えています。
DX推進に必要なのは、“理解の深さより理解の一致”です。
内製チーム×外部伴走で“育てながら運用する”体制へ
システム導入やAI活用を外部ベンダーに任せきりにせず、 庁内に“内製チーム”を持つことが持続の要です。
ただし、最初からすべてを自力で賄う必要はありません。
理想は、「外部の専門家が伴走しながら、庁内人材を育てる」体制。
初期は支援を受けつつ、徐々に職員が主導権を持てるように設計します。
- 内製人材がツール設定・改善提案を担う
- 外部パートナーが運用と教育をサポート
- 定例ミーティングで知見を共有・蓄積
このような“育てながら回す仕組み”こそ、 DXを“一度きりではなく続く仕組み”に変える鍵です。
研修は単発で終わらせず、KPIと連動させるのがポイント
DX研修は「実施して終わり」ではなく、成果と結びつけることが重要です。
たとえば、研修後に以下のような指標を設定し、 効果を定量的に把握することで、職員のモチベーションを高められます。
- 研修受講後の業務改善提案件数
- ツール利用率の推移
- AI・RPAを使った業務時間削減率
このように、研修をKPIと連動させることで、 「学ぶ→活かす→成果が見える」という成長サイクルが回り始めます。
教育はコストではなく“投資”。
「研修を仕組みに組み込むこと」が、DXを止めない最大の戦略です。
現場が動き続ける“止まらないDX組織”をつくる第一歩。
失敗を成功に変え、持続的に成果を出せる自治体へ。
まとめ|DXの失敗は終わりではなく、“成功の設計図”になる
自治体DXの失敗の多くは、技術や仕組みではなく、 「人と組織の運用力」に起因しています。
目的が共有されないまま導入が進み、 職員教育や現場フォローが後回しになることで、 “システムはあるのに成果が出ない”状態に陥ってしまうのです。
しかし、DXの失敗は「終わり」ではありません。
むしろ、成功への設計図を描き直すチャンスです。
成功している自治体に共通しているのは、 「最初からうまくいった」ことではなく、 “失敗を分析し、学びとして次に活かす文化”を持っている点です。
- データで課題を可視化する
- 職員の声を拾い上げる
- 教育と運用を一体化する
こうした“再挑戦の文化”が根づくことで、 DXは単なるツール導入から、継続的な組織変革へと進化します。
そして今、DXを立て直す上で最も重要なのは、 「AIを活かせる人材育成」です。
AIやデータ分析を理解し、業務に落とし込める職員が増えるほど、 DXは現場に定着し、持続的な改善を生み出します。
DXの成功を支えるのは、テクノロジーではなく“人”。
その人を育てる仕組みこそ、次の時代の行政運営の基盤となります。
DXを継続的に成功させるステップは、自治体DXを成功に導く5ステップ|現場課題とAI人材育成の実践法 で詳しく解説しています。
- Q自治体DXの「失敗」と「進まない」の違いは何ですか?
- A
「進まないDX」は計画や体制づくりの段階で止まってしまうケース、 「失敗するDX」は導入後に運用が続かず形骸化してしまうケースを指します。
後者は、仕組みよりも“人と組織の運用設計”に問題があることが多く、 目的共有や教育体制の不足が主な原因です。
- Q自治体DXでよくある失敗のパターンは?
- A
代表的なのは以下の5つです。
① 目的が曖昧なままシステム導入が先行
② 外部ベンダーに依存し庁内に知見が残らない
③ 現場の声を無視して職員が疲弊
④ 部署間のデータ連携ができず効果が限定的
⑤ 教育・運用体制が続かず形骸化
これらはいずれも“人材・体制の課題”が根底にあります。
- QDXが「職員の負担増」につながるのはなぜですか?
- A
紙とシステムの並行運用期間が長いことが原因です。
導入初期に業務を整理せずに進めると、入力・確認作業が増え、 「業務が減らないDX」になってしまいます。
この負担を防ぐには、導入前に業務棚卸し(BPR)と目的共有を行うことが重要です。
- Q失敗を防ぐためにまず取り組むべきことは?
- A
「現場を巻き込んだ小規模実証(PoC)」です。
一度に全庁展開するのではなく、 小さく試して課題を見つけ、改善点を庁内で共有することで、 無理なく定着するDXを実現できます。
- Q職員のAIリテラシー研修は本当に必要ですか?
- A
はい。DXの定着には、ツールの使い方だけでなく、 「AIやデータをどう業務に活かすか」を理解できる人材が不可欠です。
階層別のAIリテラシー研修を通じて、 全職員が“自分の立場でDXを語れる”状態を目指しましょう。