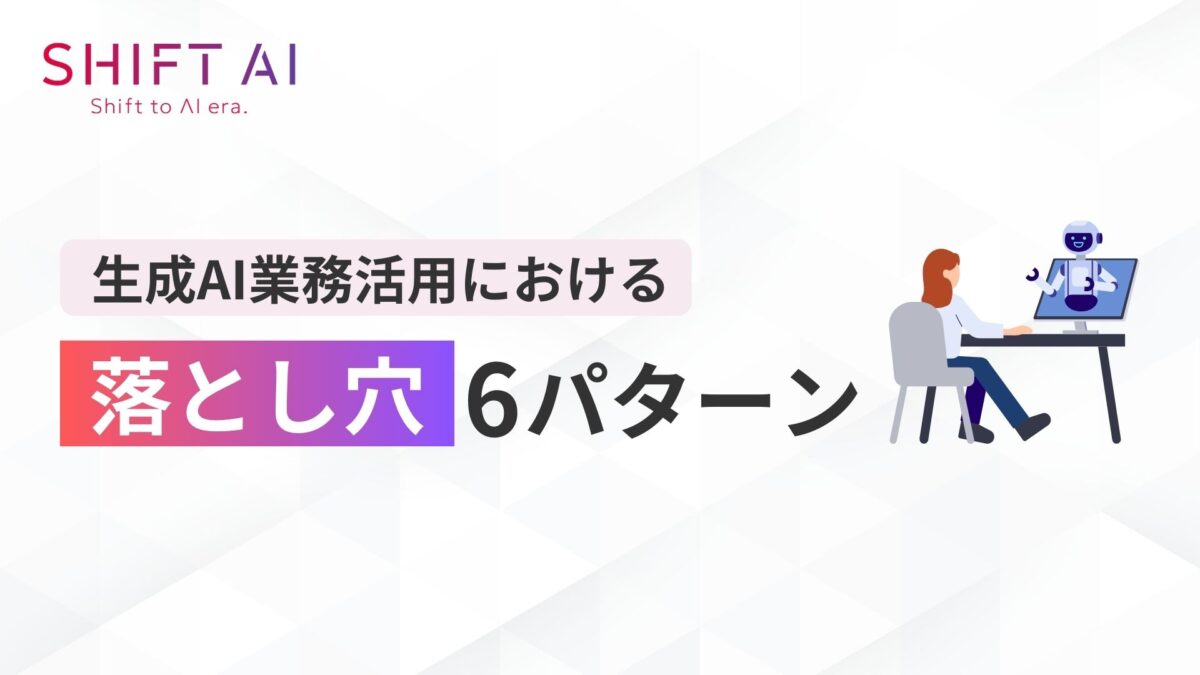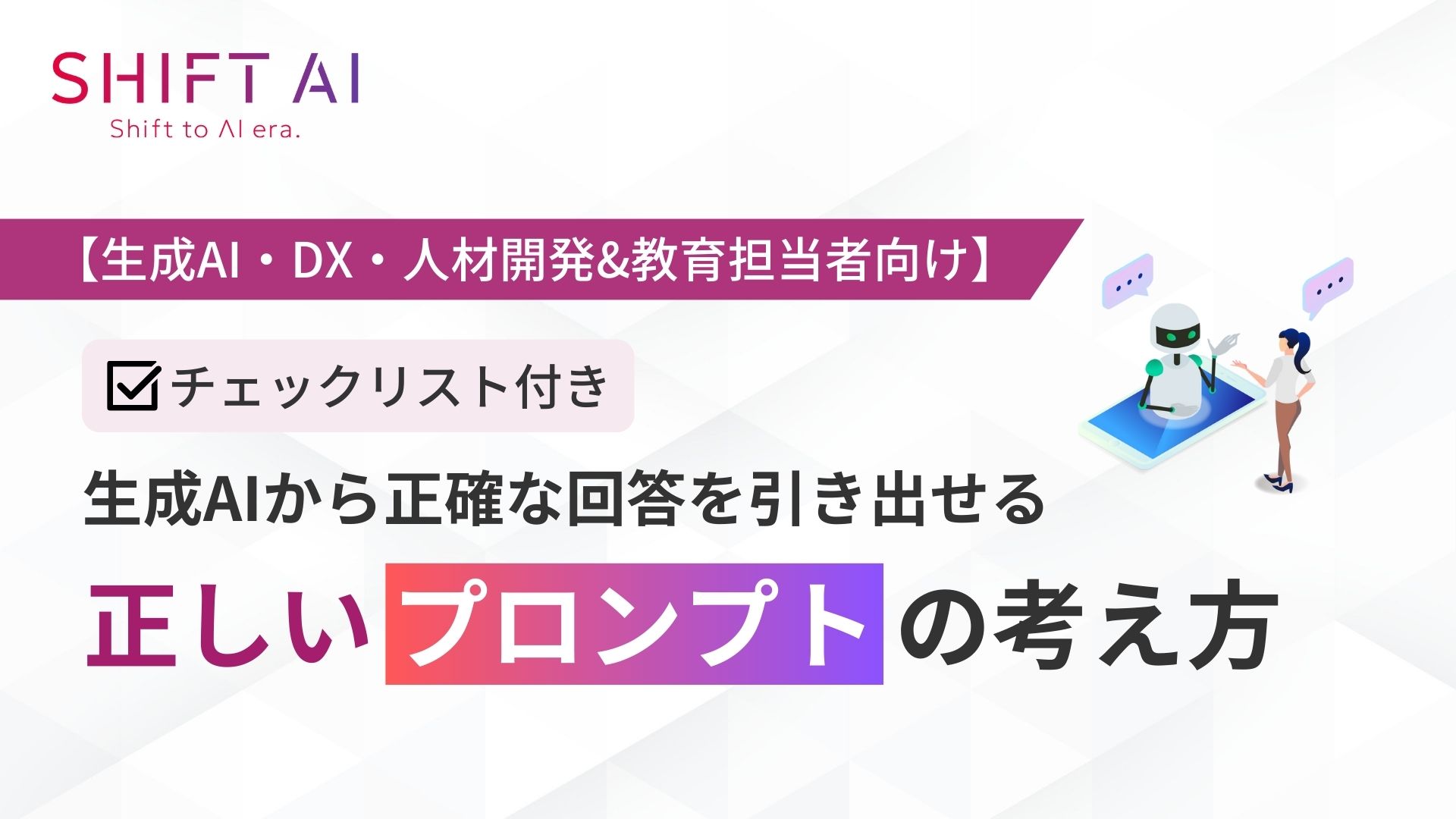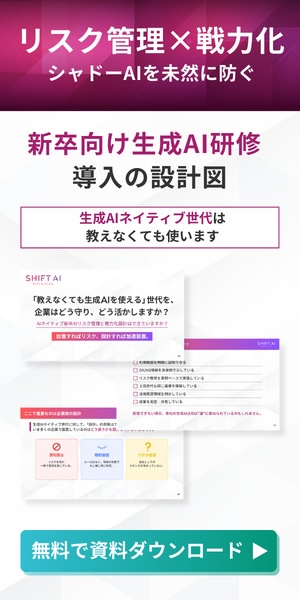生成AIは、「導入するかどうか」を議論する段階ではなく、それを「どう組織の力に変えていくか」という状況に変わりつつあります。
多くの企業で、生成AIは一部の先進層や特定部門にとどまり、全社的な生産性向上や事業価値の創出には十分につながっていません。その背景には、技術の問題ではなく、経営としてどう位置づけ、どう実装するかという設計の不在があります。
こうした課題に対し、株式会社LIFULLは早期から生成AIを「全社員が当たり前に使う経営基盤」と捉え、トップダウンとボトムアップを組み合わせた浸透設計を進めてきました。その結果、生成AI活用率96%という水準に到達しています。
本記事では、LIFULLの取り組みを通じて、生成AIを単なる効率化ツールではなく、組織と事業を進化させる経営アジェンダとして実装するための方法をCAIO(Chief AI Officer) 長沢 翼氏と実装当時に社内の有志にて結成された「生成AI活用プロジェクト」のリーダー 廣瀬 智英氏に伺いました。

株式会社LIFULL
執行役員 CTO(Chief Technology Officer) 兼 CAIO(Chief AI Officer)
2008年にLIFULLへ新卒入社。LIFULL HOME’SのWeb・iOSアプリ開発やAPI基盤刷新、事業系システム移行を責任者として推進。2017年CTO就任。海外開発子会社2社で取締役を兼任。2023年に生成AI組織を立ち上げ、社外向けの複数プロダクトリリースと社内業務効率化を主導。

株式会社LIFULL
人事本部 日次採算性向上推進グループ長 兼 AIイノベーション本部 AIトランスフォーメーション部 推進ユニット
2017年にLIFULL入社。LIFULL HOME’Sの営業を経て、社内の労働生産性向上プロジェクトの立ち上げに参画。戦術立案・実行、制度設計、発信、社内コンサルを担当。2023年には生成AI活用による業務効率化を目的とした軽量化プロジェクトを立ち上げ、2025年9月までリーダーとして全社の生成AI活用を推進。
※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
まずは経営層が姿勢を見せる──トップダウンとボトムアップをどう接続したか
生成AIを全社に浸透させるうえで、長沢氏が重視したのは、トップダウンかボトムアップかという二者択一ではありませんでした。必要だったのは、経営の意思を起点にしながら、現場が自走できる状態をどうつくるかという接続の設計です。
その前提にあったのが、生成AIに対する経営層の強い危機感でした。LIFULLの経営層は生成AIを、単なる業務効率化ツールではなく、仕事の前提や意思決定のあり方そのものを変えうる存在として捉えていました。
長沢氏は当時を振り返り、「生成AIはExcelやWordと同じように、当たり前に使える存在にしていかなきゃいけないという危機感があった」と語っています。一部の人だけが使う先進ツールにとどめてしまえば、組織全体の変化にはつながらないという認識がありました。
この認識があったからこそ、LIFULLでは現場任せの実験から始めるのではなく、まず経営層が生成AIを理解し、自ら判断できる状態をつくることを重視しました。経営層が「何が起きているのか」「何が変わり得るのか」を理解していなければ、生成AIは組織の優先順位に乗らず、結果として浸透も進みません。
同社代表取締役社長の伊東 祐司氏からは、「生成AIを全社で使っていく」という明確なメッセージが発信されました。これにより、生成AIは個人の工夫や任意の取り組みではなく、組織として取り組む前提条件になります。廣瀬氏は、「経営層から『生成AIを使っていこう』というメッセージが最初に出たことで、現場の空気が『やってもいい』から『やる前提』に変わった」と語ります。
一方で、使い方までトップが細かく指示することはありませんでした。生成AIがどの業務にどう効くかは、実際に業務を担っている現場でしか分からないからです。LIFULLでは、経営層が方向性と覚悟を示したうえで、具体的な活用は各部門・各個人に委ねられました。
長沢氏は、「どの業務でどう使うかは、実際に業務をやっている人が一番分かっている」と語ります。そのため、現場の試行錯誤や成功事例を拾い上げ、部門を越えて共有する仕組みづくりが進められていきました。
計測と伴走で、浸透を「感覚」で終わらせなかった理由
生成AIの社内浸透において、長沢氏がもう一つ重視していたのは、「なんとなく使われている状態」で満足しないことでした。便利そう、盛り上がっている、という感覚だけでは、経営として次の判断ができません。
「浸透しているかどうかを、雰囲気や声の大きさだけで判断するのは危険だと思っていました」(廣瀬氏)
そこでLIFULLでは、生成AIの活用状況を定期的に可視化する仕組みを設けました。半年に一度のアンケートによって、どれくらいの社員が業務効率化を実感できているのかを把握し、数字として現状を捉えていきます。その結果、最初は「業務に活かせている」と答えた社員が3割台にとどまっていることも明らかになりました。
重要だったのは、アンケートで回収した数字を評価で終わらせなかったことです。使えていない人がいる理由を丁寧に拾い上げ、勉強会や個別サポートにつなげていきました。さらに、日々のツールの利用状況をトラッキングすることで、アンケートよりも早い段階で変化の兆しを捉え、必要な部門に伴走する体制を整えています。
「つまずいた瞬間に、どれだけ早くサポートできるかが、使い続けてもらえるかどうかを左右すると考えていました」(長沢氏)
生成AIは、最初の体験でつまずくと、そのまま使われなくなることが少なくありません。だからこそLIFULLでは、計測とサポートをセットで回すことが意識されました。
こうした取り組みによって、生成AI浸透は一過性のブームではなく、改善を続けるプロセスとして組織に根づいていきます。感覚ではなく事実で捉え、放置せずに伴走する。この姿勢が、全社浸透を持続させた大きな要因でした。
称賛が次の挑戦を生んだ──「ジェネレーティブAIアワード」開催の意図とねらい
生成AIの活用を一過性で終わらせず、文化として根づかせるために、LIFULLで取り入れられたのが、ジェネレーティブAIアワードの取り組みでした。目的は成果を競うことではなく、使ってみたこと、工夫したこと自体を肯定する空気をつくることにありました。
「生成AIを使っている人がきちんと見えるようにしたかったんです。うまくいった事例だけではなく、試してみたこと自体が価値になると思っています」(長沢氏)
生成AIの活用は、最初から完成度の高い成果が出るとは限りません。だからこそ、「挑戦したこと」を称える場を意図的につくりました。商品や報酬を用意するのではなく、社内で共有され、認識されること自体を価値とした点も特徴です。
廣瀬氏も、「表彰があることで、あの人もやっているなら自分も試してみよう、という連鎖が生まれた」と振り返ります。その結果、称賛は次の挑戦者を生む装置として機能しました。
この取り組みによって、生成AI活用は個人の工夫にとどまらず、組織全体の学習へと広がっていきます。成功事例が共有され、別の部門で再解釈され、また新しい使い方が生まれる。その循環が、生成AIを「特別な取り組み」から「当たり前の選択肢」へと押し上げていきました。
生成AI浸透の最後の一押しは、ルールでもKPIでもなく、LIFULLが長年育ててきた「人の挑戦を肯定する文化」でした。
「使わせる」ではなく「使いたくなる」──keelaiで「使う前提」を業務動線に埋め込む
生成AIを全社に浸透させる際、長沢氏が強く意識していたのは、「使わせる」状態をつくらないことでした。ルールや号令で利用を強制すれば、一時的に利用率は上がるかもしれません。しかし、それでは本当の意味で業務に根づくことはないと考えていました。
長沢氏は、「生成AIは、使うまでのハードルが少しでも高いと、多くの人は触らなくなってしまう」と振り返ります。だからこそ重視したのは、生成AIを「新しいツール」として意識させない設計でした。
特別な画面を開いたり、新しい操作を覚えたりするのではなく、普段使っているSlack上でメンションするだけで反応し、業務で日常的に使っているブラウザからワンクリックで呼び出せる。生成AIを業務動線の中に自然に溶け込ませることを徹底しています。
この思想を具体的な形にしたのが、内製AIであるkeelaiでした。長沢氏は、「生成AIを全社員に使ってもらうには、安心して、何も考えずに使える環境を先に用意する必要があると思っていました」と語ります。
情報セキュリティや心理的安全性に対する不安が残ったままでは、現場はなかなか一歩を踏み出せません。そこでkeelaiでは、API経由の設計によって入力情報が学習に使われない仕組みを整え、「これなら業務で使っても大丈夫だ」という前提を組織全体に提供しました。
さらにkeelaiは、Slack上でメンションするだけで使える形で実装されています。新しいツールを立ち上げる必要はなく、普段の業務の流れの中で自然に呼び出せる。この設計によって、生成AIは「学ぶもの」ではなく、「困ったときに自然と頼るもの」へと位置づけが変わっていきました。
廣瀬氏は、「別の画面を立ち上げたり、新しい操作を覚えたりするだけで、心理的ハードルは一気に上がる」と語ります。だからこそLIFULLにおいては、生成AIを使うために「頑張る」必要がない状態をつくることが重視されました。その結果、社員は「使わなければいけない」ではなく、「気づいたら使っている」状態へと移行していきます。
LIFULLで目指されたのは、利用率を上げることではありません。生成AIが自分の仕事の質を高めてくれる存在だと、社員一人ひとりが実感できる状態をつくることでした。そのための答えが、「使わせる」のではなく「使いたくなる設計」を先に用意する、というアプローチだったのです。
「keelai」が中核から「並行利用」へ移ったことが示す成熟度
LIFULLの生成AI浸透を語るうえで、内製AIであるkeelaiの現在の位置づけは重要な示唆を持っています。
keelaiは、単に社内で便利に使われる生成AIツールだったわけではありません。生成AIを「安心して触れるもの」「業務で使っても大丈夫なもの」として組織に定着させ、さらにその先へ進むための土台をつくる役割を担っていました。
keelaiを通じて生成AIに慣れたことで、社員の意識も変わっていきます。「生成AIは特別な人が使うもの」ではなく、「業務に応じて使い分けていいツール」という認識が自然と育っていきました。その結果、現在LIFULLではkeelaiを起点としながら、GeminiやNotebookLMなど、他の生成AIツールも並行して活用する状態が生まれています。
廣瀬氏は、「keelaiがあったからこそ、生成AIをまず試してみる空気が社内にできたのです。その延長で、他のツールにも関心が広がっていきました」と振り返ります。keelaiは「唯一の正解」として使い続けるための存在ではなく、生成AI活用の入口として機能することで、選択肢を広げる役割を果たしていたのです。
続けて長沢氏は、「keelaiは、常に中心であり続ける必要はない」と強調しました。この変化は、keelaiの役割が終わったことを意味するものではありません。むしろ、keelaiを起点に生成AI活用が管理や啓蒙のフェーズを越え、現場が自律的にツールを選び、使いこなす段階に入ったことを示しています。
生まれた「余白」は経営価値につなげなければ意味がない
生成AIの浸透によって、LIFULLでは半年で約5万時間、業務時間の余白が生まれました。しかし、この数字自体がゴールだったわけではありません。むしろ経営としては、「その時間はどこに行ったのか」「何に再配分されたのか」を説明できなければ意味がない、という認識を持っていました。
廣瀬氏は、「使って便利だった、楽になった、という感覚だけでは、経営判断にはつながらない」と語ります。生成AIによって生まれた余白が、単なる余剰時間で終わるのか、それとも事業成長につながる再投資になるのか。その分岐点に、経営の視点がありました。
そこでLIFULLでは、時間削減そのものよりも、コア業務に使える時間がどれだけ増えたか、成果創出に向けた活動にどう変化が出たかが重視されます。結果として、コア業務比率の上昇や、組織目標の達成率改善といった変化が見え始めました。
一方で長沢氏は、こうした成果を冷静に受け止めながらも、次の課題を見据えていました。
「正直に言うと、生成AI前提で業務プロセスそのものを設計し直す、というところまでは、まだ十分にできていないと思っています。今は効率化で余白が生まれている段階ですが、本当はそこを前提にした仕事の流れに変えていかなきゃいけない。その部分を、これからもっと突き詰めていきたいです」
長沢氏は続けて、「生成AIで効率化した先に、人を減らすという発想はなかった」とも語ります。重要だったのは、浮いた時間をどう使うかではなく、生成AIがある前提で、仕事の設計そのものをどう更新していくかでした。その可視化と再設計こそが、次の投資判断につながります。
生成AI活用を経営に結びつけるとは、導入効果を数字で語ることではありません。生まれた余白を、どこにどう使う組織なのか、そしてその余白を前提に業務プロセスをどう進化させていくのかを示すことです。LIFULLは今、生成AIを「効率化の道具」から、「業務設計そのものを更新する経営基盤」へと進化させようとしています。
LIFULLから学ぶ5つのポイント
生成AI活用が進まない理由は、ツールや個人のスキル不足ではないことがほとんどです。多くの場合、課題は「生成AIを経営としてどう位置づけ、どの順番で組織に組み込むか」という設計が曖昧なまま、導入だけが先行してしまっている点にあります。
LIFULLの取り組みは、生成AIを一部の先進層のものではなく、組織全体の前提として根づかせてきました。ここからは、その実践から見えてきた、生成AIを組織の力に変えるための5つのポイントを整理します。
1. 経営層が先に「前提」を示す
生成AI浸透の出発点は、現場の工夫ではなく経営層の立ち位置です。LIFULLでは、生成AIを「一部の先進層が使うツール」ではなく、「ExcelやWordと同じように当たり前に使われるもの」と定義しました。この認識を経営層が明確に言語化し、姿勢として示したことで、現場の空気は「やってもいい」から「やる前提」へと切り替わりました。
2. トップダウンとボトムアップを「役割分担」で接続する
LIFULLで実施されたのは、トップダウンかボトムアップかの二者択一ではありません。経営層は「なぜやるのか」「優先順位は何か」を示し、現場は「どう使うか」「どこに効くか」を育てる。この役割分担によって、経営の意思は現場の自由度を奪うのではなく、安心して試せる余白を生みました。
3. 「使わせる」のではなく「使いたくなる設計」を先につくる
生成AI浸透を阻む最大の壁は、使うまでの心理的・操作的ハードルです。LIFULLでは、Slackなど日常業務の動線に生成AIを溶け込ませ、「新しいツールを学ぶ」感覚を極力なくしました。その結果、社員は「使わなければならない」ではなく、「困ったら自然と使う」状態へと移行していきました。
4. 計測と伴走で、浸透を「感覚」で終わらせない
「盛り上がっている」「便利そう」という感覚だけでは、経営判断にはつながりません。LIFULLでは、アンケートや利用状況の可視化によって浸透度を把握し、使えていない理由に対して勉強会や個別サポートで伴走しました。計測は評価のためではなく、支援の起点として機能していました。
5. 入口を固定せず、自律的に広がる状態をつくる
内製AIである「keelai」は、全社員が安心して生成AIに触れるための「入口」として大きな役割を果たしました。一方で、それを使い続けることに固執せず、現在は外部ツールとの並行利用へと移行しています。これは、生成AI活用が管理フェーズを越え、現場が自律的に使い分ける成熟段階に入った証拠です。
LIFULLの事例が示しているのは、生成AI浸透の成否は「ツール選定」ではなく、
経営の定義 → 接続設計 → 環境 → 計測 → 文化
という一連の設計にかかっている、という点です。
しかし、実際に自社でこれを実践しようとすると、
「うちの組織に合ったAIの活用方法は?」
「社内に広げるには、どんな人材が必要?」
「成果をどうやって可視化すればいい?」
といった壁に直面する企業も少なくありません。多くの組織が同じ悩みを抱えています。
私たちSHIFT AIは、こうした「導入したが定着しない」という課題解決を得意としています。
貴社の文化や業務内容に合わせた浸透施策の設計から社員のスキルを底上げする伴走型研修、活用成果を“見える化”する仕組みづくりまで、AI活用の定着に必要なプロセスを一気通貫で支援します。
「AIを導入したのに現場で使われていない」「成果をどう評価すればよいかわからない」
そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、私たちの支援内容をご覧ください。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応
🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?
AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、
業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。