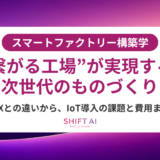「『DXを進めよう』と号令をかけても、社内が動かない」
多くの企業が直面するこの壁は、技術や予算の問題ではありません。原因は、組織が変化を受け入れる仕組みを持っていないことにあります。
経営層は「デジタル化による競争力強化」を掲げ、現場は「また新しいツールか」と疲弊する。結果、プロジェクトは誰のものでもないDXになり、進捗は止まり、熱も冷めていく。
本来DXとは、システム導入ではなく「人と組織が新しい価値を生み出す仕組みを再構築すること」。つまり、社内DXの進め方を誤ると、どれだけ優れたツールを導入しても成果は出ません。
この記事では、DX推進を任されたプロジェクトリーダーや担当者の方に向けて、
- 経営層と現場を同時に動かすための5ステップ
- 部署間調整を円滑にする体制設計の考え方
- 成果を定着させるための改善サイクルの作り方
を、AI経営総合研究所の知見をもとに体系的に解説します。
「社内DXを動かす力」を持つかどうかが、これからの企業を分ける。その第一歩を、このページで明確にしましょう。
併せて読みたい
社内DXとは?7通りの進め方と定着の仕組み|失敗しないDX推進体制を解説
「実務ノウハウ3選」を公開
- 【戦略】AI活用を社内で進める戦略設計
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】属人化させないプロンプト設計方法
なぜ社内DXは進まないのか
社内DXの停滞には、単なる「やる気の問題」ではなく構造的な原因があります。多くの企業では、経営層と現場、さらには情報システム部門の間で目的や視点がズレたまま進行しているのです。こうしたズレを放置すると、プロジェクトは「進めること」自体が目的化し、最終的に成果が曖昧なまま終わってしまいます。ここでは、DXが進まない代表的な3つの壁を整理します。
経営層と現場の温度差
DX推進の最大の障壁は、経営と現場の間にある認識ギャップです。経営層は「将来への投資」としてDXを掲げますが、現場にとっては「今の業務が複雑になるだけ」と感じるケースが多いのが現実です。この温度差を放置すると、施策は浸透せず、システムだけが残る「形だけのDX」に陥ります。
このギャップを埋めるには、経営層がなぜDXが必要なのかを現場目線で語る必要があります。現場にとってのメリット「業務がラクになる」「ミスが減る」「判断が早くなる」を具体的に示すことが、最初の一歩です。
目的・評価指標が曖昧なまま走り出している
DXの失敗例で共通しているのが、「何をもって成功とするか」が定義されていないままスタートしてしまうことです。
「システムを導入した」「ツールを契約した」で満足してしまうと、施策の成果を測定できず、現場の納得も得られません。
正しい進め方は、目的 → 成果指標(KPI) → 定着プロセスの順で設計することです。以下は、DX推進でよくある目的とKPIのズレを整理した表です。
| 誤った進め方 | 望ましい進め方 |
| 「業務をデジタル化したい」→ ツール導入がゴール | 「業務効率を20%改善したい」→ KPI設定で効果検証 |
| 「AIを使いたい」→ 技術導入が目的化 | 「顧客対応を短縮し、満足度を上げたい」→ AIは手段 |
| 「他社もやっているから」→ トレンド追随 | 「自社課題の解決手段としてのDX」→ 経営戦略に直結 |
KPIを測れる形に落とし込むことが、DX推進を加速させる原動力です。
人材・体制の整備不足
DXが進まない3つ目の理由は、「誰がやるのか」が不明確なまま進めてしまうことです。プロジェクト責任者が曖昧な状態では、決裁も遅れ、推進スピードが落ちます。また、専門知識を持つメンバーがいないままツールを導入すると、運用負荷が現場に偏り、結果的に形骸化します。
必要なのは、経営層・推進リーダー・現場担当者の三位一体モデル。それぞれの役割を明確にし、短期成果と長期的な変革を両立できる体制を設計することが重要です。
このように、DXが進まない原因の多くは「戦略の欠如」よりも「社内構造の歪み」にあります。次では、こうした壁を乗り越えるための実践的な5つのステップを紹介します。
社内DXを進める5つのステップ
DXを成功に導くには、壮大なビジョンよりも一歩ずつ確実に成果を積み重ねることが重要です。多くの企業が最初のフェーズでつまずくのは、順序を誤り、準備不足のまま走り出してしまうからです。ここでは、経営層と現場の両輪を動かしながらDXを着実に進めるための5つのステップを紹介します。
ステップ1 現状の可視化と課題整理
最初のステップは、「現状を正しく知る」ことです。現場が抱える課題を明確にせずに新しいツールを導入しても、根本的な改善にはつながりません。まずは、業務フロー・システム構成・データ活用状況を洗い出し、どこにムダや属人化があるかを把握しましょう。
- 現場担当者へのヒアリングで、非効率なプロセスを特定する
- システム間のデータ連携や二重入力などを整理する
- デジタル化による効果が大きい業務から優先順位をつける
こうした可視化を行うことで、DXの目的が具体的な課題解決に結びつきやすくなります。課題整理の結果は後のKPI設定にも直結するため、この段階を丁寧に行うことがDX成功の起点です。
関連記事
DX×AI活用で組織を変える!導入から効果測定・人材育成までをわかりやすく解説
ステップ2 DXの目的とゴールを明確化
課題を把握したら、次は「なぜDXを行うのか」を定義します。ここを曖昧にしたまま進めると、施策がバラバラになり現場の納得も得られません。目的は「何をデジタル化するか」ではなく、「何のために変えるのか」を軸に据えることが大切です。
たとえば、「営業活動を効率化するためにCRMを導入する」「人事評価の精度を高めるためにデータ分析基盤を整える」など、目的と手段をセットで明確化しましょう。
さらに、成果を測るためのKGI・KPIを設定します。
- KGI(最終目標):業績向上・コスト削減・顧客満足度向上など
- KPI(中間指標):工数削減率・リード獲得数・社内アンケート満足度など
目的と指標を明確にしておけば、施策の進捗を定量的に評価でき、組織全体の理解も得やすくなります。
ステップ3 推進体制を整える(CDO・横断組織・責任分担)
DXを進める上で不可欠なのが「誰が推進するのか」を明確にすることです。経営層が旗を振り、現場が動くためには、組織を横断するDX推進体制が必要です。
まず、CDO(Chief Digital Officer)やDX推進責任者を中心に、経営・IT・現場の三位一体モデルを構築しましょう。各部署が連携しやすいよう、役割と責任を明文化することが重要です。
| 役割 | 主なミッション |
| 経営層 | 方向性とリソース配分の決定、KGI管理 |
| DX推進リーダー | 全体設計・進捗管理・効果測定 |
| 各部門代表 | 現場課題の吸い上げとフィードバック |
このように役割を明確にしておけば、意思決定のスピードが上がり、DXが組織全体で進行します。
DX体制づくりに悩む企業様へ
SHIFT AI for Bizの法人研修では、DX推進人材の育成から実行支援までを包括的にサポートしています。
ステップ4 スモールスタートで成功体験をつくる
いきなり全社展開を目指すより、まずは小さく始めて確実に成果を出すことが効果的です。特定の部署やプロセスでPoC(実証実験)を行い、短期的な成功事例を作ることで、社内の理解と協力を得やすくなります。
- 影響範囲が限定される部署から着手する
- 成果を定量的に可視化し、全社に共有する
- 成功体験を横展開して他部門のモチベーションを喚起する
こうした小さな成功を積み重ねることで、DXは特別なプロジェクトではなく、日常の改善活動として定着していきます。
ステップ5 効果測定と文化定着
最後のステップは、「DXを文化として根づかせる」ことです。ツール導入が終わっても、運用改善を止めてしまえばすぐに元通りになってしまいます。
定量・定性の両面で効果を測定し、改善サイクルを継続的に回すことが重要です。
- 定量評価:ROI、業務効率、顧客満足度など
- 定性評価:社員のデジタル活用意識、変化への適応度など
また、研修や勉強会を通じてDXを自分ごと化できる社員を増やすことが定着のカギです。
関連記事
DXを加速させるAI活用とは?失敗しない導入プロセスと人材戦略を解説
DXを進める5つのステップを着実に実践できれば、組織は確実に変わり始めます。次では、複数部署が関わる中でDXをスムーズに進めるための調整のポイントを解説します。
部署間調整をスムーズに進めるための実践ポイント
DXを推進する際に最も時間がかかるのが、部署間の調整です。どんなに優れた戦略を描いても、社内での合意形成が遅れればDXは前に進みません。関係部署をスムーズに巻き込むためには、各部門の立場を理解し、それぞれが納得できる動機を提示することが重要です。ここでは、現場・経営・情報システム部門の3つの視点から調整のコツを解説します。
経営層には「リターン」を数字で見せる
経営層を動かすには、「DXの成果が利益にどうつながるか」を定量的に示すことが最も効果的です。抽象的なビジョンよりも、投資対効果(ROI)を具体的に見せることで、理解と意思決定のスピードが上がります。
- 導入コストに対して何年で回収できるかを明示する
- 工数削減・売上増加など、数字で示せる成果を試算する
- 経営課題(人手不足・業務非効率など)とDX施策を直結させて語る
「ROIが明確なDXは経営課題の解決策である」というメッセージを打ち出せば、経営層からの支援は得やすくなります。
現場には「負担軽減」を言語化する
現場の協力を得るためには、「自分たちの業務がどうラクになるか」を明確に伝えることが不可欠です。DXの目的が現場にとって余計な仕事に見えると、抵抗感が生まれます。
たとえば、
- 「データ入力の自動化で残業が減る」
- 「ミス防止機能でチェック工数が削減される」
- 「社内申請がスマートフォンで完結する」
こうした小さな利便性の積み重ねが、現場の納得感につながります。導入初期の成功体験を共有し、DXは現場を助ける取り組みという意識を浸透させましょう。
情報システム部門とは早期に連携
DX推進において最も軽視されがちなのが、情報システム部門との連携です。実際には、ここを軽んじると導入後にトラブルが発生し、リカバリーに膨大なコストがかかります。
- 既存システムとの互換性やセキュリティ制約を早期に確認する
- API連携やデータ構造の制約を明文化し、プロジェクト全体で共有する
- システム部門をサポート役ではなく共創パートナーとして巻き込む
こうした段階的なすり合わせが、DXプロジェクト全体の品質を大きく左右します。
関連記事
中小企業のためのDX×AI導入費用ガイド|内訳・相場・ROI・コスト最適化の戦略
部署間調整を「面倒な作業」と捉えるのではなく、DXを社内文化に変えるための最初の訓練として位置づけることが大切です。次では、こうした調整を乗り越えた企業に共通する成功の条件を解説します。
社内DXを成功させる企業の共通点
DXの成功は偶然ではありません。成果を出している企業には明確な共通点があり、それらは業種や規模を問わず再現可能な原則として機能しています。ここでは、DXを単なるデジタル化で終わらせず、企業文化として定着させている企業が実践している3つのポイントを紹介します。
経営層のコミットメントが高い
DXは「現場発」では限界があります。経営層が本気で取り組む姿勢を示すことが、全社を動かす最初の条件です。経営層がDXの重要性を自ら語り、リソース配分や評価制度に反映させることで、プロジェクトは会社全体の意思として推進されます。
また、経営層が積極的に進捗報告を受ける仕組みを設けると、現場の意識も大きく変わります。DXはトップダウンで始まり、ボトムアップで定着する。この両輪を意識することが成功企業の共通点です。
現場がデータで意思決定できる仕組みを持っている
成功している企業ほど、「勘や経験」ではなく「データ」で判断する文化が根づいています。BIツールや分析基盤の整備はもちろん、現場がそのデータを使いこなす環境づくりに投資を惜しみません。
ポイントは、ツールを導入することではなく、「データを活用する人材と仕組み」を育てること。データ可視化を経営判断や改善提案に結びつけることで、DXは単なる業務改善ではなく事業変革の手段へと進化します。
人材育成を継続的に行っている
DXを文化として定着させるためには、一度の研修で終わらせない継続的な人材育成が不可欠です。デジタルリテラシーの差は社内格差を生み、推進スピードを阻害します。
成功企業は、階層別研修や実践型ワークショップを通じて、現場が主体的に改善を提案できる環境を整えています。こうした自走できる人材の存在こそが、DXを持続可能にする原動力です。
SHIFT AI for Bizの法人研修では、企業のAI活用を支援します。実践的な活用方法を体系的に学ぶことができ、DXを効率よく進める手助けとなるはずです。
まとめ|DXは「進め方」で9割が決まる
DXの成否を分けるのは、ツールでも資金でもありません。「どのように社内を巻き込み、変化を定着させるか」こそが最も重要なポイントです。DXを成功させる企業は、経営層がビジョンを示し、現場が自ら動ける仕組みを整えています。つまり、DXとは導入の技術ではなく運営の哲学なのです。
本記事で紹介した5つのステップを軸に、目的の明確化から体制構築、そして文化定着までを一貫して取り組めば、DXは確実に企業の競争力へとつながります。
SHIFT AIは、AI×DXの実践知をもとに企業の変革を支援しています。単なる理論ではなく、現場を動かす仕組みづくりをともに考えるパートナーとして、組織の成長を後押しします。
DXは一度の導入で終わるものではありません。進め方を磨き続け、組織が自ら進化できる状態をつくる。それが、AI経営時代における本当の競争力です。
社内DX推進に関するよくある質問(FAQ)
- QDX推進がうまくいかない最大の理由は?
- A
最も多い原因は、目的とKPIが曖昧なままプロジェクトを進めてしまうことです。ツール導入がゴール化し、成果が測れないまま現場のモチベーションが下がるケースが多く見られます。まずは「何を解決したいのか」「どのような成果をもって成功とするのか」を明確に定義しましょう。
- Q社内DXはどの部署が主導すべき?
- A
理想は、経営層・DX推進部門・現場の三位一体体制です。経営層が方向性を示し、DX推進部門が全体を統括し、現場が実行の中心を担う。この連携が機能して初めてDXは動き出します。特定の部署だけで完結させると、他部門との連携が途切れやすくなります。
- QDXの効果測定はどのように行う?
- A
効果は定量と定性の両面から測定します。定量的にはROI(投資対効果)や工数削減率、リード獲得数などを設定し、数値で成果を確認します。定性的には、社員の意識変化や業務改善提案の数などを評価軸に含めましょう。数字と感覚の両面で効果を確認することが、持続的な改善につながります。
- QDX文化を根づかせるコツは?
- A
「DX=特別な取り組み」から「日常業務の一部」へと意識を変えることです。そのためには、継続的な研修とナレッジ共有が欠かせません。短期のプロジェクトではなく、学びと実践を繰り返すことでDXは企業文化として定着します。
DXの疑問を一つずつ解消しながら進めていけば、組織は確実に変わっていきます。重要なのは、一度で完璧を目指すのではなく、改善を積み重ね続ける姿勢です。