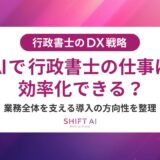AIでプレゼン資料や提案書を作ってみたけれど、「構成がまとまらない」「内容が浅い」「結局、手直しに時間がかかる」――そんな経験はありませんか?
AIは確かに資料作成の時間を短縮できますが、“考える部分”を完全に代替できるわけではありません。
多くの人が「AIで資料作成は難しい」と感じるのは、AIが苦手とする“情報整理”や“文脈理解”を任せてしまうことに原因があります。
この記事では、AI資料作成がうまくいかない理由を構造的に解き明かし、実務で成果を出すための使い方・チェックポイント・改善策を紹介します。
AIの特性を正しく理解すれば、資料の品質とスピードはどちらも向上します。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜAIで資料作成は“難しい”と感じるのか?
AIを使えば簡単に資料が作れそう――そう思って試してみたものの、思ったような仕上がりにならない。
その原因は、「AIが苦手とする領域」に人間の期待をかけすぎていることにあります。
AIは大量の情報から文章を組み立てるのは得意ですが、目的や受け手の意図を読み取る“論理的な設計”は人間の仕事です。
ここを理解せずに使うと、出力はどうしても表面的で、まとまりのない内容になってしまいます。
AIは「目的」や「受け手の文脈」を理解できない
AIはあくまで入力されたテキストをもとに確率的に文章を生成するため、「この資料を誰に見せたいのか」「どんな行動を促したいのか」といった意図や背景までは理解できません。
たとえば「営業提案資料を作って」と指示しても、AIは自社の商材や相手企業の課題を踏まえた内容までは考慮できないため、“誰のための資料か不明瞭な構成”になりがちです。
構造設計(ロジック構成)は人間の思考に依存する
良い資料は「結論→根拠→提案」というストーリー設計で構築されます。
AIは文章生成こそ得意でも、論理の流れを設計する力は弱く、章立てやスライド構成を任せると矛盾や重複が生じます。
そのため、最初に人間が“目次レベルで構造を決める”ことが成功の鍵となります。
AIは「情報の正確性」と「表現の一貫性」を保証できない
AIが生成する内容は、学習データに依存しています。
最新情報や専門的な数値、固有名詞を含む内容では、誤情報の混入や根拠不明な文章が出やすい傾向にあります。
また、1回の出力で使う語彙やトーンが変化するため、スライド全体の表現が統一されないのも特徴です。
このため、AIを「自動生成ツール」ではなく、「下書きを作るアシスタント」として捉える視点が重要になります。
関連記事:
実際にAIを使って「伝わる構成」を作る具体的な手順は、こちらの記事でも紹介しています。
資料作成をAIで効率化する方法|品質を落とさず“伝わる”資料を作る実践ガイド【2025年版】
実務でよくある「AI資料作成の失敗パターン」
AIで資料を作ると、最初は「すごい、こんなに早く形になるのか」と感動します。
しかし、いざ内容を精査してみると「構成がバラバラ」「根拠が弱い」「トーンが統一されていない」――。
こうした“使いこなせていない違和感”は、ほとんどの担当者が一度は経験しています。
以下では、現場でよく見られる失敗パターンとその原因、改善の方向性を整理します。
① 構成がバラバラで、話の流れがつかめない
最も多い失敗が、「章立ての論理がつながらない」ケースです。
ChatGPTなどに「企画書を作って」と入力すると、一般論として正しい内容は出ますが、目的に沿ったストーリー設計にはなりません。
結果、「誰に、何を、なぜ伝えたいのか」が不明確なままスライドが並ぶ構成になり、読み手の理解を妨げます。
改善策:
AIに丸投げするのではなく、最初に人間が「ゴール」「読者」「要点(3つ)」を明示し、AIには“肉付け”を任せる。
構成骨格を人が作ることで、資料全体に一貫したストーリーが生まれます。
② 情報の精度が低く、信頼性に欠ける
AIは過去データや一般的な知識をもとに生成するため、事実確認を前提としない内容を出すことがあります。
特に市場データ・製品比較・業界トレンドなど、根拠が求められる内容では誤りが混入しやすいです。
また、複数回出力を重ねるうちに情報が変化し、どれが正しいか判断しづらくなることもあります。
改善策:
出典を明示するようプロンプトに含める、または社内ナレッジ(Teams、SharePointなど)と連携できるAIを使う。
Copilot for Microsoft 365のように、自社内の資料を検索して引用できる環境を整えることで、精度と根拠を確保できます。
③ トーンや表現が統一されず、全体がちぐはぐになる
AIの出力は一見まとまって見えますが、ページをまたぐと「言い回し」「語彙」「敬体・常体」が統一されていないことが多く、結果として資料全体の印象が不安定になります。
特に複数メンバーでAIを併用して作ると、同じ資料内で“文体がバラつく”問題が発生しがちです。
改善策:
「リライト指示」や「社内用語辞書」「文体ガイドライン」を共有し、AI出力に一貫性を持たせる。
また、最終段階でAIに“トーン統一の再編集”を依頼するのも効果的です。
例:「全体の文体を統一し、読み手が経営層の場合にふさわしい表現にしてください。」
④ 図やグラフが不適切で、伝わらない
AI生成のスライドでは、図解が内容に対して過剰だったり、メッセージと合っていなかったりすることがあります。
特にデザイン重視型ツール(Gammaなど)では、見た目は良くても中身が伴わないという事態も。
改善策:
AIに「この章で図が必要か」「何を可視化すべきか」を考えさせるのではなく、
人間が「この情報は図解向きか」を判断したうえで、AIには“形の整え役”を担わせるのが理想です。
「AIに任せすぎる」ほど手戻りが増えます。
“AIは補助輪”と捉え、設計・チェック・リライトの3工程を人が担うことで、 資料の完成度とスピードを両立できます。
AI資料作成を“使いこなす”ための4ステップ
AIで資料を作るうえで最も重要なのは、「どの工程をAIに任せ、どこを人が担うか」を明確にすることです。
AIを“万能ツール”と捉えるのではなく、“設計に沿って動くアシスタント”として扱う。
この考え方をもとにすれば、AI資料作成の“難しさ”は一気に軽減されます。
ここでは、誰でも実務に落とし込める4つのステップを紹介します。
STEP1:目的と受け手を明確にする
AIに資料を作らせる前に、「誰に」「何を」「どう伝えたいか」を明文化します。
この“設計フェーズ”を曖昧にしたままAIに指示すると、論点がずれた資料になります。
たとえば営業提案であれば「意思決定者に購入を納得させる」、社内報告なら「上長に進捗を簡潔に伝える」など、行動目標を一文で書くことが重要です。
💬 プロンプト例:
「経営層向けに、導入効果を3分で説明できるスライド構成を提案してください。」
STEP2:構成を人が設計し、AIに“肉付け”させる
AIの得意領域は「素材を出すこと」であり、「構造を作ること」ではありません。
したがって、まず人間が目次(章立て)レベルまで設計し、その後にAIへ「各章を埋める文章」を生成させる流れが最適です。
この分業により、ストーリーの一貫性とスピードが両立します。
💬 プロンプト例:
「以下の構成に基づいて、各章の本文を400字以内で生成してください。」
(構成を明示して指示を分割する)
STEP3:チェックリストで品質を管理する
AIの出力結果は必ず人がレビューし、「構成」「事実」「トーン」の3軸で確認します。
この工程を怠ると、誤情報や言い回しの不統一がそのまま資料に残ります。
社内では簡易チェックリストを作成して共有しておくと、メンバー間の品質差を減らせます。
| チェック項目 | 内容 |
| 構成 | ストーリーが一貫しているか |
| 事実 | 数値・根拠は正確か |
| トーン | 文体・語彙が統一されているか |
STEP4:AI出力をテンプレート化し、再利用する
良質な出力を得られたら、そのプロンプトと構成をテンプレート化して社内共有します。
これにより、「毎回ゼロから作る」負担が減り、AI活用が組織的に定着します。
たとえば「営業提案書テンプレ」「報告書テンプレ」などを作っておけば、AIが自動で再現できる精度も向上します。
AI資料作成を“難しい”ままにしているのは、AIではなく「人の使い方」です。
設計・分業・検証・共有の4ステップを整えることで、AIの出力は確実に変わります。
ツール別に見る「難しさの違い」と対処法
一口に「資料作成AI」といっても、ツールによって得意分野・生成の癖・難しさのポイントは異なります。
同じプロンプトを入力しても結果が大きく変わるのは、AIモデルや生成ロジックの設計思想が異なるためです。
ここでは代表的な4ツールを比較し、それぞれで生じやすい“難しさ”と対処法を整理します。
| ツール名 | 得意領域 | 難しさのポイント | 対処法 |
| ChatGPT(OpenAI) | 文章構成、要約、ストーリー生成 | 構成を理解せずに情報を並べがち。長文すぎてスライドに落とし込みづらい。 | 「章構成を箇条書きで出力」など、事前にアウトラインを指定。段階生成で制御する。 |
| Copilot for Microsoft 365 | Word・PowerPointでの実務資料生成 | 指示が抽象的だとテンプレを正しく活用できない。 | 社内テンプレートを設定し、「~の社内フォーマットに沿って作成」と明示する。 |
| Gamma | デザイン性重視のスライド生成 | 見た目は整うが、情報が浅くなる傾向。根拠の裏付けが弱い。 | 内容をChatGPTなどで生成→Gammaで整形する「二段構え」を推奨。 |
| Elucile(旧IRUSIRU) | スライド構成テンプレートの豊富さ | 汎用構成ゆえに表現が単調。自社文脈に合わないことも。 | 出力後に「自社事例を反映して書き換えて」とAIに再指示。表現チューニングで精度向上。 |
ツールの違いを理解すると、AIの“難しさ”が見えてくる
多くの担当者が「AIが難しい」と感じるのは、ツールの特性を把握せずに同じ使い方をしてしまうからです。
ChatGPTでスライド構成を作ろうとして破綻するのも、Copilotで曖昧な指示を出して失敗するのも、“AIとの分業設計”がない状態で使っていることが根本原因です。
ツールの強みと限界を理解したうえで、「構成→文章→デザイン→チェック」の工程を組み合わせることで、AI資料作成は格段に扱いやすくなります。
関連記事:
各ツールの特徴や活用の流れをさらに詳しく知りたい方は、
資料作成をAIで効率化する方法|品質を落とさず“伝わる”資料を作る実践ガイド【2025年版】
ツールを“正しく選ぶ”よりも、“正しく使える人”を育てる
どのAIツールを使うかよりも、使う人のリテラシーと設計力のほうが成果を左右します。
ツールの操作方法を学ぶだけでは、実務で活かすことはできません。
AI資料作成の“難しさ”を乗り越えるには、「目的を設計し、AIを使いこなす人材」を育てる仕組みが必要です。
チームでAI資料作成を活かす“仕組みづくり”
AIを使った資料作成を個人レベルで完結させているうちは、成果が限定的です。
本当に業務効率と品質を両立させるには、チーム全体でのAI活用ルールと共通フォーマットが欠かせません。
ここでは、企業や部署単位でAIを定着させるための3つの仕組みを紹介します。
① AI活用ルールとスタイルガイドを整備する
チーム内でAIを使う場合、最初に整えるべきは「どんな情報をAIに入力してよいか」「どのトーン・文体で出力するか」という共通ルールです。
この基盤がないと、資料のトーンや内容がバラバラになり、結局修正の手間が増えます。
「文体:です・ます調」「図表の色:企業カラー基準」など、スタイルガイドをAIにも共有できる形で設計するのが理想です。
② 成功した出力をテンプレート化し、ナレッジ化する
一度良い出力が得られたら、そのプロンプト・構成・トーン指示をテンプレートとして保存し、チーム全体で共有します。
「営業提案書テンプレ」「報告書テンプレ」などを整備しておくことで、誰でも一定品質の資料を短時間で作成できる環境が整います。
また、AI出力の再利用を前提にすると、学習コストも大幅に削減できます。
③ 研修やトレーニングでAIリテラシーを底上げする
ツールを導入しても、使い方が人によって異なれば成果に差が出ます。
社内に“AIの使い方を理解した推進役”を置くことで、組織的な活用が進みます。
特に「AIプロンプトの設計」「情報セキュリティの基本」「生成結果の検証方法」などは、研修を通じて体系的に学ぶことが重要です。
まとめ|AIが“難しい”のではなく、人が設計していないだけ
AIによる資料作成が「難しい」と感じるのは、AIの限界ではなく、使う側の“設計不足”にあります。
AIは目的や文脈を理解して考えることはできません。
しかし、明確な指示・構成・評価基準を与えれば、スピードと品質を両立できる強力なパートナーになります。
AIに任せるべきは“生成”、人が担うべきは“設計と判断”。
この分業を前提に、社内でルールやナレッジを共有すれば、資料作成にかかる時間は大幅に短縮し、チーム全体の生産性が飛躍的に向上します。
AIの活用を一部の個人スキルで終わらせず、組織として成果につなげる――
それがこれからの“AI活用企業”に求められる視点です。
よくある質問|AI資料作成で多い悩みとその解決策
- QAIで作成した資料をそのまま使っても大丈夫?
- A
そのまま提出するのはおすすめできません。
AIは構成や文章を自動生成しますが、事実確認・文脈整合・表現の正確性は人間の判断が欠かせません。
最終チェックで内容・根拠・トーンを確認し、必要に応じて修正しましょう。
AIは“叩き台”として活用するのが最も効果的です。
- QChatGPTとCopilotではどちらが資料作成に向いていますか?
- A
的によって使い分けが最適です。
- ChatGPT:構成や要約、文章化が得意。企画段階や構想整理に向く。
- Copilot for Microsoft 365:PowerPoint・Wordでの自動生成や社内資料の参照に強い。
構成設計はChatGPT、仕上げや整形はCopilotという併用型が最も効率的です。
- ChatGPT:構成や要約、文章化が得意。企画段階や構想整理に向く。
- Q資料作成AIを使うときに注意すべき情報は?
- A
外部クラウド上で動作するAI(ChatGPTなど)には、機密情報や顧客データを入力しないことが原則です。
企業利用の場合は、セキュリティ対策が明示された法人向けプラン(ChatGPT Team/Enterpriseなど)や社内導入型AIを利用しましょう。
- QチームでAIを使う場合、どんな体制が理想?
- A
AIを定着させるには、「AI活用ルール」「共有テンプレート」「AIリーダー人材」の3つをセットで整えることが重要です。
全員が自由に使うのではなく、プロンプト設計やナレッジ共有を管理できる担当者を置くことで、品質のばらつきを防げます。