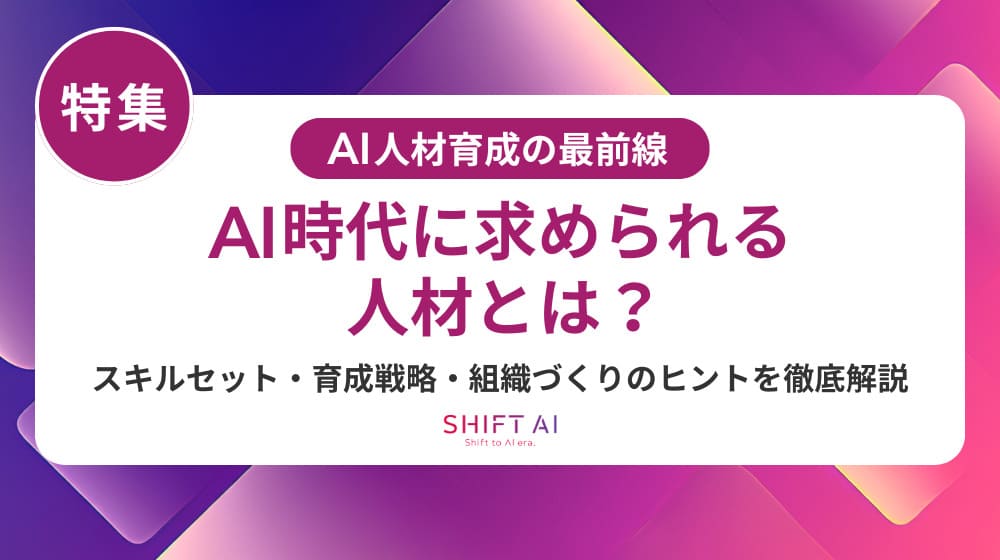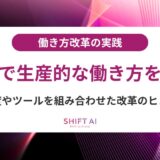AI導入を進める企業の多くが直面するのが、「AI人材を採用すべきか、それとも社内で育てるべきか」という判断です。
特に中堅企業や非IT企業では、「AI人材を雇うほどの予算も業務規模もない」という声が少なくありません。
一方で、専任のAI人材を置かずに成果を出す企業も確実に増えています。
「AI人材はいらない」という意見の裏には、単なる人材不要論ではなく、AI技術の民主化と業務ツールの進化があります。
生成AIやノーコードツールの登場により、かつて専門職の領域だったAI活用が、一般社員でも実務レベルで使える時代に変わりました。
もはや“AIを作る人”ではなく、“AIを使いこなす人”が成果を左右する時代です。
本記事では、「AI人材はいらない」と言えるケースの判断基準から、AI人材を採用せずに成果を出す企業の共通点、そして社内でAI活用人材を育てるステップまでを体系的に解説します。
「実務ノウハウ3選」を公開
- 【戦略】AI活用を社内で進める戦略設計
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】属人化させないプロンプト設計方法
なぜ「AI人材はいらない」と言われるのか|その背景と誤解
近年、「AI人材はいらない」「AIエンジニアは不要になる」といった言葉を目にする機会が増えました。
一見すると過激な主張に見えますが、その背景にはAI技術の進化と企業の実情の変化があります。
まず押さえておきたいのは、かつてのAI導入は「データ分析やモデル構築を専門エンジニアが行う」ことが前提だったという点です。
しかし今は、ChatGPTやGeminiのような生成AIツールの登場によって、非エンジニアでもAIを扱える環境が整ったことが大きく影響しています。
AIのコードを書くのではなく、プロンプト(指示文)を使って誰でもAIを操作できる時代になったのです。
また、企業の導入目的も変わりつつあります。
かつては「新しいAIプロダクトを開発する」ことが目的でしたが、現在は「既存業務を効率化し、生産性を上げる」ことが主軸となっています。
つまりAIは“研究対象”から“日常ツール”へと立ち位置を変え、AI専門職を置かなくても導入できる領域が広がったのです。
一方で、「AI人材はいらない」という言葉には、誤解も多く含まれています。
AIそのものが不要なのではなく、“専任のAIエンジニアを雇う必要がない”ケースが増えているということです。
ツールの理解や業務活用スキルを持つ「AI活用人材」はむしろ各部署で欠かせない存在になっています。
結局のところ、「AI人材はいらない」と言われる時代とは、AIを専門部署だけのものにしない時代でもあります。
経営層やミドルマネージャーがAI活用を推進し、現場に実装する力を育てることこそ、いま求められる方向性なのです。
AI人材がいなくても導入できる企業の3つの共通点
AI導入を成功させている企業のすべてが、専任のAIエンジニアを抱えているわけではありません。
むしろ、多くの中堅・中小企業は既存メンバーだけでAIを運用し、成果を出しています。
そうした企業には、共通する3つの特徴があります。
共通点①:目的を“AI導入”ではなく“課題解決”に置いている
AI活用を成功させる企業は、「AIを導入すること」自体を目的にしていません。
最初に行うのは、“何をAIで解決したいのか”という業務課題の特定です。
たとえば、営業部門での見積もり作業の自動化、広報部門での資料作成支援、総務部門での問い合わせ対応など。
こうした具体的な業務課題を起点にすることで、AI活用のゴールが明確になり、専門人材がいなくても成果が見えやすくなります。
共通点②:既存社員がツールを業務に自然に組み込んでいる
ChatGPT、Microsoft Copilot、Geminiなどの生成AIツールは、「AIスキルがなくても使える」ことが最大の特徴です。
成功企業では、既存社員がこうしたツールを“日常業務の延長”として活用しています。
たとえば、営業資料の叩き台をChatGPTで作る、Excel分析をCopilotで補助する、議事録作成を自動化するなど、業務プロセスの中にAIを溶け込ませているのです。
重要なのは、「AIを扱う部署を新設する」ことではなく、「社員全員が少しずつAIを使う文化をつくる」ことにあります。
共通点③:小さく試し、結果を見ながら改善している
AI活用で失敗する企業の多くは、最初から全社展開を目指してしまうケースです。
一方で成果を上げている企業は、PoC(試験導入)から始めて、小さく検証しながら段階的に広げています。
最初の成功体験を現場に共有し、他部門へ横展開することで、社員の抵抗感も減り、自然とAI活用が定着していきます。
AI導入は一気に進めるものではなく、“小さく始めて、大きく育てる”アプローチが効果的なのです。
これら3つの共通点に見られるのは、「AI人材がいない」ことを課題にせず、現場の知見と実践力を最大限に活かす姿勢です。
AIを導入する前に“AIを使える文化”をつくること。それこそが、最小のコストで最大の成果を生み出す第一歩となります。
それでもAI人材が必要なケースとは?
「AI人材はいらない」とは言っても、すべての企業に当てはまるわけではありません。
業務の性質や導入目的によっては、AI人材の専門的な知見が欠かせないケースも存在します。
ここでは、専任人材が必要となる代表的なシーンを整理してみましょう。
① 自社でAIモデルやシステムを開発する場合
ChatGPTやGeminiなどの既存ツールを使う段階を超え、自社開発によるAIシステムを構築する場合は、高度なエンジニアリングスキルが求められます。
特に製造・金融・医療のように独自データを活用する業種では、AIモデルの構築や精度管理、アルゴリズムの検証など、専門知識が必要です。
このレベルでは“AIを使う人”ではなく、“AIを作る人”が重要な役割を担います。
② 大規模組織でAIを全社横断的に運用する場合
全社的にAI活用を推進する段階では、統制・教育・データ管理といった領域で専任者が必要になります。
部署ごとの個別運用ではなく、全社統一のAI方針を策定するには、AI技術の基礎を理解しながら経営戦略を描ける“橋渡し人材”が不可欠です。
とくにガバナンス整備やセキュリティ管理は、現場レベルでは対応しきれない範囲です。
③ AI倫理・透明性・法規制対応が求められる場合
AIの導入が進むにつれ、倫理的な判断や説明責任(Explainability)が重視されるようになっています。
不適切な学習データや差別的出力を防ぐための監査体制を整えるには、専門的視点を持つAI担当者の存在が不可欠です。
特に官公庁や大企業では、こうした“AIリスクマネジメント”がAI人材の役割の中心になりつつあります。
④ データ基盤整備や分析体制が未成熟な企業
AIの活用にはデータの質が直結します。
もし社内に整ったデータ基盤がない場合、データエンジニアやデータサイエンティストの支援が必要です。
AIモデルを動かす前段階として、データ統合・前処理・セキュリティ管理を専門家が設計することで、運用の安定性と精度が保たれます。
AI人材が必要かどうかを見極める判断基準
AI導入を検討する際、「自社にはAI人材が必要なのか、それとも社内育成で足りるのか」を見極めることは非常に重要です。
AIを専門職として採用すべきケースもあれば、既存メンバーのリスキリングで十分に成果を出せる場合もあります。
この章では、その判断を行うための軸を整理し、自社の規模・目的・データ体制に応じた最適な選択肢を明確にします。
まず押さえたい判断軸は「目的・規模・データ体制」
AI人材の必要性は、企業規模よりも「どの目的で導入するか」「どこまで内製化したいか」で変わります。
たとえば自社開発を行うならエンジニアが不可欠ですが、ツール活用レベルなら既存人材の教育で十分対応できます。
以下の表に、主な判断軸を整理しました。
| 判断軸 | 専任AI人材が必要なケース | 社内リソースで対応可能なケース |
| 導入目的 | 独自AIシステムや分析モデルの開発 | 業務効率化やツール活用 |
| 組織規模 | 大企業・多拠点展開型 | 中小企業・部門単位導入 |
| 活用範囲 | 全社横断・戦略レベル | 一部業務・試験導入レベル |
| データ体制 | 専門チーム・大規模データあり | 既存ツールで処理可能 |
| コスト体制 | 採用・育成に投資余力あり | 研修・外部支援で補完可能 |
中堅・中小企業の多くは“社内育成で十分”
実際、SHIFT AIの支援企業でも、AI専門職を採用せずに成果を上げる事例が多数あります。
共通しているのは、「研修・外部伴走・PoCを通じて自社人材を育てている」点です。
採用よりも教育投資を優先することで、AI活用を持続的に定着させる企業が増えています。
こうして見てみると、AI人材が“本当に必要”なのは、AIを経営戦略や開発軸に組み込む企業に限られることが分かります。
多くの企業にとっては、外部支援や社内リスキリングによる育成のほうが合理的です。
「採用せずに育てる」AI活用人材の育成ステップ
AI人材を採用せずに成果を上げている企業の多くは、既存社員をAI活用人材へと育てる仕組みを整えています。
ここでは、実際に社内でAIリテラシーを高めるための4つのステップを紹介します。
ステップ①:現状リテラシーの把握と対象者の選定
最初に行うべきは、社員のAI理解度を把握することです。
全員を一律に教育するのではなく、まずはAIに関心が高い層・影響力を持つ中堅層を中心に選定します。
アンケートやヒアリングで現状を見える化し、「誰に・どんな教育が必要か」を明確にすることがスタートラインです。
ステップ②:生成AIツールを使った実践型研修の実施
理解よりも実践が重要です。ChatGPT、Gemini、Microsoft Copilotなどのツールを使いながら、自社業務に即した演習形式で学ぶことが効果的です。
たとえば「議事録作成」「企画書作成」「データ要約」といった実務課題を題材にすることで、学びが即戦力につながります。
この段階で「AIを業務にどう使えるか」という発想が定着し、現場の自走力が育ちます。
ステップ③:小規模PoC(試験導入)と業務内実践
研修で得た知識を、すぐに現場で試すフェーズです。
AIを使った改善テーマを各部署で1つ設定し、短期間で成果検証を行うPoC(Proof of Concept)を実施します。
「少人数×短期間」で効果を見える化することで、現場の信頼を得ながら次のステップにつなげられます。
ステップ④:成功事例の共有と全社展開
PoCで得られた成果を社内報や勉強会で共有し、他部署に横展開します。
ここで重要なのは、“AI推進リーダー”を中心に継続的な教育サイクルを回すこと。
一度研修を終えた人材が社内トレーナーとなり、新たなメンバーへ知見を広げることで、AI活用の文化が社内に根付きます。
このサイクルを確立できれば、外部採用に頼らずに持続的な成長を実現できます。
外部パートナー・ベンダーと「共創」するAI活用体制
AI導入において、「すべてを社内で完結させよう」と考える企業は少なくありません。
しかし現実には、外部パートナーとの連携こそが導入成功の近道になるケースも多く見られます。
重要なのは「外注に任せること」ではなく、「社内と外部が共に学び、知見を蓄積する体制を作ること」です。
① 外部パートナーは“実装の伴走者”として活用する
AIコンサルティング会社やSIer、教育ベンダーなどは、初期導入から運用設計までを伴走支援する存在です。
ツール選定・データ整備・教育設計といった初期フェーズで、外部の知見を取り入れることで、時間とコストのロスを防げます。
特に初めてAIを導入する企業では、こうした支援を受けながら社内人材を育てる“ハイブリッド体制”が効果的です。
② “依存型外注”ではなく“共創型支援”を設計する
AI導入における失敗例の多くは、「外注に丸投げして、知識が社内に残らない」パターンです。
一方、成功企業は外部に頼りつつ、社内に知見を残す“共創型支援”を採用しています。
例えば、研修やプロジェクト設計を外部パートナーと共同で進めながら、ノウハウを社内文書や教育カリキュラムとして蓄積するスタイルです。
こうした共創モデルでは、プロジェクトが終わっても「AIを扱える組織力」が社内に残ります。
③ 外部支援を併用する際のチェックポイント
外部と協働する際は、以下の3つを基準に選定すると効果的です。
| チェック項目 | 内容 |
| 目的の明確化 | 「開発支援」「教育支援」「運用支援」のどれを期待するのかを明示する |
| 知識移転の仕組み | 実施後にノウハウが社内に残るかを契約前に確認 |
| 社内連携の体制 | 担当部署・窓口・共有ツールを事前に決めることでスムーズな連携を実現 |
これらを整理しておくことで、「外部に任せたけれど社内に何も残らなかった」という失敗を防げます。
④ SHIFT AIの研修支援モデル
AI経営総合研究所を運営するSHIFT AIでは、外部支援と内製化を両立させる教育モデルを採用しています。
単なる研修提供ではなく、受講企業の業務課題に合わせた「カスタマイズ型共創支援」を実施。
導入後の運用や人材定着までを伴走し、“研修が終わっても続くAI文化”の醸成を支援しています。
関連記事:
AI人材育成で成果を出す5ステップ|企業が押さえるべき実践ロードマップ
AI人材がいなくても成果を出すための導入ステップ
「AI人材がいないから導入できない」と考えている企業の多くは、進め方の全体像を描けていないだけです。
AI導入は専門家がいなくても、正しいステップを踏めば確実に成果を出せます。
ここでは、社内リソースを活かしてAI導入を成功させるための5つのプロセスを紹介します。
ステップ①:目的設定と活用領域の特定
まずは、「どの業務を、何のためにAI化するのか」を明確にします。
“AI導入そのもの”をゴールにするのではなく、「業務課題をどのように解決したいか」を起点に考えることが重要です。
たとえば「資料作成時間を半減したい」「社内問い合わせ対応を効率化したい」など、具体的なKPI設定が導入成功の鍵となります。
ステップ②:業務プロセスを洗い出し、AIで代替できる範囲を見極める
AIを導入する前に、業務プロセスを可視化し、AIが支援できる部分と人の判断が必要な部分を整理します。
この段階で無理にAI化しようとせず、現場が使いやすい範囲から導入することで、失敗リスクを抑えられます。
たとえば「議事録作成」「レポート要約」「顧客メール返信」など、定型業務から始めるのが鉄則です。
ステップ③:小規模なトライアル(PoC)を実施する
次に、実際の業務フローの中でAIツールを使い、効果を短期間で検証します。
このPoC段階でのポイントは、「成功・失敗どちらも記録すること」。運用結果を定量的に分析し、どの業務で最も効果が出たかを社内で共有します。
この段階で得たデータが、全社展開の説得材料になります。
ステップ④:教育・ガバナンス体制を整備する
AIツールを運用するうえで欠かせないのが、教育とルール整備の両輪です。
特に、プロンプト設計の品質やセキュリティリスク、情報漏えい防止に関するガイドラインを整備しておくことで、安心して社内展開できます。
管理職層には「AIのリスクと責任の所在」を、一般社員には「ツール利用の基本ルール」を明確に示しましょう。
\社内でAI活用人材を育てるなら /
生成AI研修の詳細資料ダウンロードはこちら
ステップ⑤:効果測定と継続的改善
導入して終わりではなく、成果を測定し、定期的に改善サイクルを回すことが成功の条件です。
AIによる生産性向上を定量的に評価し、運用ルールや教育内容をアップデートしていくことで、AI活用が一時的なブームで終わらず、企業文化として根づきます。
関連記事:
生成AI運用で成果を出す完全ガイド|導入後の課題解決から継続的改善まで
まとめ|“AI人材はいらない”は採用しないだけの選択肢
「AI人材はいらない」という言葉は、決してAI活用を否定するものではありません。
その本質は、“AI人材を新たに採用しなくても、社内人材を育てて成果を出せる”という発想の転換にあります。
AI技術が急速に進化し、ツールも低コストで利用できる今、必要なのはエンジニアではなく、業務とAIをつなげて考えられる人材です。
現場を知る社員こそが、最も現実的なAI活用アイデアを生み出せる存在といえるでしょう。
AI導入を「特別なプロジェクト」と捉える時代は終わりました。
これからは、全社員がAIを自然に使いこなす組織文化をどうつくるかが問われます。その第一歩が、社内でのリテラシー向上と実践研修です。
AI人材を“外から採る”か“中から育てる”か——。
採用に頼らずとも、教育によって人とAIの力を引き出せる企業こそが、これからの時代に強く生き残ります。

AI人材を採用せずに導入する際によくある質問(FAQ)
- QAI人材を採用しないと導入は難しいのでは?
- A
必ずしも採用が必要とは限りません。
最近では、ChatGPTやGeminiなどの生成AIツールを活用することで、非エンジニアでも業務改善を進められる環境が整っています。
まずは社内メンバーのリテラシーを高め、小規模な実践からスタートすることが成功の近道です。
- QAIリテラシー教育は全社員に行うべきですか?
- A
初期段階では、全社員一斉ではなく、AI推進リーダー層や管理職層から着手するのが効果的です。
実践で成果を出した人材が社内トレーナーとなり、徐々に範囲を広げる形が定着しやすいでしょう。
この「段階的教育モデル」は、SHIFT AIの研修でも多くの企業が採用しています。
- Q生成AI研修はどんな効果があるのですか?
- A
研修を通じて、社員が自分の業務でAIをどう活かせるかを具体的にイメージできるようになります。
たとえば、報告書作成やデータ整理、アイデア出しなどでAIを日常業務に取り入れることで、
業務時間の削減と生産性向上を同時に実現できます。
- QAI活用におけるセキュリティや情報漏えいが心配です。
- A
多くの企業で共通の懸念ですが、ガイドラインと運用ルールを整備すれば安全に活用可能です。
特に「どのツールを、どんなデータで使うか」を明確にしておくことで、リスクは最小化できます。
- Q外部支援を受ける場合、どんな体制が理想ですか?
- A
理想は“外部依存”ではなく“共創型支援”です。
コンサルや研修ベンダーに丸投げするのではなく、社内担当者が学びながら導入を進める体制を整えることで、
プロジェクト終了後も自社内に知見が残り、持続的なAI活用が可能になります。