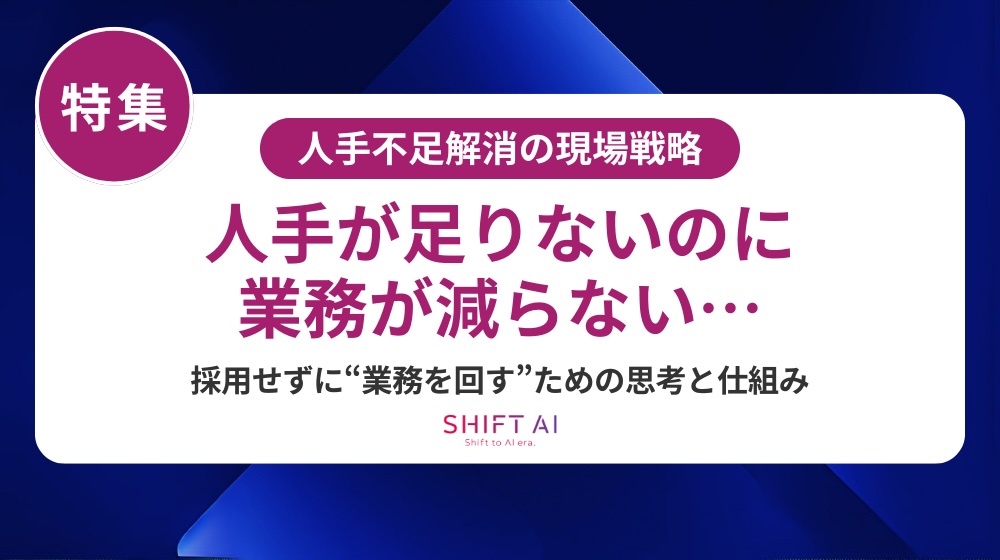「せっかく採用しても、すぐ辞めてしまう……」
そんな悩みを抱える企業が増えています。
採用難が続く人手不足の時代。
限られた人材をどう確保するかだけでなく、「どう定着させ、戦力として育てていくか」が今、問われています。
離職が続けば、現場の負担は増すばかり。
ベテランの退職、新人の早期離職が重なれば、育成の余力すら奪われ、組織全体が回らなくなってしまいます。
だからこそ必要なのが、「辞めない仕組み」を持った組織づくり。
本記事では、離職の構造的な原因を押さえたうえで、 定着率を高める施策・制度設計・AI活用までを体系的に解説します。
SHIFT AIとしての視点で、“仕組み化された離職防止戦略”のつくり方をご紹介します。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ今、「離職防止」が経営課題になっているのか
「人が辞めるのは当たり前」と思っていませんか?
確かに、転職市場の活性化や働き方の多様化により、かつてより離職は珍しいことではなくなりました。
しかしそれを放置すれば、企業にとって致命的な損失につながります。
人手不足の本質は、“定着できない構造”にある
人手不足というと「人が足りない」状態にばかり目が向きがちですが、その多くは「採った人が定着しない」「育たずに辞める」ことに起因しています。
つまり、本質は“採用”ではなく“定着”の設計にあるのです。
採用→早期離職→現場疲弊の悪循環が発生
ひとり辞めるたびに、現場ではその穴埋めに時間も手間もかかります。
採用活動の再開、引き継ぎ対応、教育コストの損失——
しかも再び辞めれば、また同じことの繰り返しです。
このような「採っても辞める」サイクルが続けば、現場は疲弊し、定着していた人材すらやる気を失い、さらに離職が加速します。
離職は“目に見えないコスト”と“士気の低下”をもたらす
ひとりの離職が、現場に与える影響は想像以上に大きいものです。
直接的な人件費の損失に加え、「また辞めるのでは」という不安感がチーム内に広がり、社員のモチベーションや心理的安全性までもが損なわれていきます。
離職を防ぐことは、単なる“人をつなぎとめる”施策ではありません。
それは「組織の持続可能性」を高める、戦略的な経営課題なのです。
社員が辞める主な原因とは?【実データから見る離職要因】
「待遇が悪いから辞めたんでしょ?」
そう思い込んでいませんか?
確かに給与や福利厚生は離職要因の一部ですが、実際には“働きやすさ”や“将来への不安”が大きな理由として挙げられています。
給与よりも深刻なのは「人間関係」と「キャリア不安」
厚生労働省のデータによれば、離職理由として多く挙がるのは以下の項目です。
- 職場の人間関係がうまくいかなかった
- 将来のキャリアが見えなかった
- 成長実感ややりがいを持てなかった
- 適切な評価が得られなかった
これらはすべて、「職場の中での不安や不満」によるものです。
つまり、待遇改善だけでは離職は防げません。
組織の内側にある“見えない不満”を放置することこそが、離職を生む温床なのです。
メンタルヘルス・業務負荷・上司との相性も見逃せない
特に人手不足の現場では、業務の属人化や過重労働が常態化しがちです。
適切なサポート体制がなければ、社員は孤立し、心身のバランスを崩してしまうリスクも高まります。
また、上司との関係性やコミュニケーション不足が離職を引き起こすきっかけになることも少なくありません。
「静かな退職」を見過ごすな
最近では、「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉も注目されています。
目立った不満を口にせず、業務だけを淡々とこなし、やがて会社への関心を失っていく——
このような状態を早期に察知できなければ、離職の予兆はいつも“見えないうち”に始まっています。
だからこそ、組織として必要なのは、「辞める理由をなくす」のではなく、「辞めたくならない職場を設計すること」なのです。
関連記事:中堅社員向けAIリテラシー研修|“使える”から“使いこなす”へ変える実践設計とは?
辞めない組織が実践している“定着率向上”の3つの視点
離職防止は、属人的なケアでは限界があります。
「上司の努力」や「根性論」ではなく、構造として“辞めにくい”組織をどう設計するかがカギです。
実際に高い定着率を維持している企業では、共通して以下の3つの視点に力を入れています。
①入社後の不安と混乱を防ぐ「オンボーディング設計」
早期離職の多くは、入社から最初の3か月に集中しています。
業務内容、社内文化、評価基準などの“見えない前提”が伝わっていなければ、社員は孤立し、ミスマッチを感じやすくなるからです。
【取り組み例】
- 初期研修やOJTに加え、「1か月後」「3か月後」の振り返り面談を実施
- 担当業務だけでなく、組織の目的やビジョンも丁寧に共有
- 「失敗してもいい環境づくり」を上司主導で仕掛ける
オンボーディングは単なる導入ではなく、“安心して根を張れる土壌づくり”です。
②継続的な対話がある「フィードバック×1on1」文化
離職の背景には、「声が届かない」環境があります。
だからこそ、上司と部下の1対1の対話機会(1on1)が重要です。
ただし、「何となく雑談する」「進捗を聞くだけ」では意味がありません。
【ポイント】
- キャリアの不安や感情面に踏み込むフィードバック設計
- 言いづらいことを言える“心理的安全性”を意識した運用
- 定期性・記録・アクションを徹底して、組織全体で改善に活かす
AIツールを活用した1on1のログ分析なども、近年注目されています。
③キャリアと成長の“見える化”で未来への納得をつくる
「この会社にいて、自分はどうなれるのか?」
社員が不安を感じたとき、その問いに答えられなければ離職リスクが高まります。
【改善アプローチ】
- スキルマップ/キャリアパスの明示化
- 昇格条件・評価基準の透明化
- 挑戦機会の提供と公募制度の導入
重要なのは、ただ制度を用意するだけでなく、“納得感のある設計”にすること。
評価やキャリアがブラックボックスである限り、優秀な人材ほど離れていきます。
離職を防ぐ組織の“仕組み”とは?5つの改善アプローチ
個別対応だけでは、離職の連鎖を止めることはできません。
重要なのは、仕組みとして「辞めにくい構造」を整えることです。
ここでは、定着率を高めるための5つのアプローチを紹介します。
①評価制度の見直しと“納得感”のある運用
「頑張っても報われない」評価制度は、離職の温床です。
問題は評価基準が曖昧だったり、運用が属人的だったりすることにあります。
【改善のポイント】
- 評価項目・重みづけを明文化し、全社で共有
- フィードバック面談での対話の質を向上
- 昇格や報酬との連動性を明確化
公正な評価は、離職を防ぐだけでなく、社員の成長意欲も引き出します。
②マネジメント層の再設計|「離職は上司がつくる」
社員が辞める理由の多くは、「直属の上司」に関係しています。
上司との相性、放置、過干渉、不公平な采配——こうした問題が積もると、離職の決断につながります。
【取り組み例】
- マネジメント研修の義務化
- 1on1や育成の進め方の型化(仕組み提供)
- 部下からの“逆フィードバック制度”導入
“プレイヤー”から“育成者”への役割転換を支援することが鍵です。
③業務負荷・属人化の解消(DX・AI活用含む)
現場が疲弊する背景には、「業務が回らない」という構造的課題があります。
属人化・ムダな手作業・引き継ぎ困難などが、ストレスの原因になっているケースも多いです。
【改善策】
- マニュアル化や業務の可視化(Notion/動画共有など)
- RPAや生成AIによる定型業務の自動化
- 業務分担の再設計と“標準業務”の仕組みづくり
業務を最適化することは、社員の余白を生み出すことにもつながります。
④キャリア支援とスキルアップの“可視化”
「自分の成長が見えない」と感じたとき、社員は離職を考えます。
逆に、成長の道筋が可視化されていれば、人は組織に残りやすくなります。
【仕組みの例】
- LMS(学習管理システム)導入による習熟度の見える化
- スキル評価→研修→実践という“学習サイクル”の構築
- 社内公募・ローテーション制度で挑戦機会を設計
SHIFT AIではこの部分に特に注力しており、AI×育成設計の仕組み化支援を行っています。
⑤離職予兆の可視化と早期対応
離職は、突然起きるものではありません。
日々の変化や不満の兆しを捉えられるかどうかが重要です。
【予防策】
- 定期的なエンゲージメントサーベイの実施
- 面談記録やSlack発言のAI分析
- 小さなサインを拾える“対話の型”を社内に共有
退職届が出る前に、兆候を察知できる仕組みを整えることが、本当の意味での「離職防止」につながります。
AIと人の力で“辞めない職場”を実現するには
離職防止は属人的な取り組みでは限界があります。
だからこそ、AIの力を使って、仕組みとして定着を支える設計が求められています。
ここでは、SHIFT AIの視点から「AI×人の力」を活かした離職防止の実践例をご紹介します。
LMS×AIで“育成の抜け漏れ”を防ぐ
新入社員や若手層が「置いていかれた」と感じることは、離職の引き金になります。
LMS(Learning Management System)を活用すれば、誰がどのスキルを修得できているかを可視化し、一人ひとりの学習進捗や習熟度をもとに育成設計を最適化できます。
さらに、AIを組み合わせることで、
- 学習ログから理解度のばらつきを検出
- 離職しやすいパターンと学習履歴の相関を分析
- 次に提供すべき研修内容をレコメンド
といった高度な活用が可能になります。
生成AIで業務マニュアル整備と定型業務の効率化を
属人化が進むと、業務がブラックボックス化し、引き継ぎも困難になります。
この状態が、ベテラン離職や新人の早期離職を引き起こすのです。
生成AIを使えば、
- 社員が実践している業務をマニュアル化・動画化
- よくあるQ&Aを自動生成し、社内ヘルプボットを構築
- 定型業務をAIで処理し、業務負荷を軽減
といった施策が現実的なスピードで進められます。
1on1や面談記録をAIで分析し、離職リスクを可視化
「面談はしていたのに辞められてしまった」——
こうしたケースでは、“言葉にできない違和感”を見逃していることが多いです。
そこで、面談ログや日報・チャット内容をAIが解析することで、
- 感情の変化(ポジ・ネガ)をスコア化
- 離職傾向にあるフレーズや反応を自動抽出
- 「似た社員が辞めた兆候」との類似度を計測
など、人では気づけない小さなサインを拾い上げることができます。
こうした「AIを活用した定着戦略の仕組み化」は、SHIFT AIが得意とする領域です。
関連記事:人手不足解消にDXが効果的な理由とは?生成AI研修と自動化ツールの導入手順を解説
SHIFT AI for Bizの「離職防止×組織設計」支援とは
人が辞めない組織には、明確な理由があります。
それは、属人的なケアではなく、仕組みによって“定着を生む構造”を設計していること。
SHIFT AI for Bizでは、その実現に向けた支援をトータルで行っています。
①採用〜育成〜定着まで“すべてつながる”人材戦略を設計
離職は、単一の原因では起きません。
採用のミスマッチ、育成の不足、評価の不信——
あらゆるプロセスがつながっているからこそ、分断をなくす設計が必要です。
SHIFT AIでは、以下のような支援を提供しています。
- 採用要件の見直しとオンボーディング体制の構築
- LMSや評価制度の連携による“育成の可視化”
- 定着に直結するマネジメント層の再教育
②LMS×AIで「離職の予兆を可視化」し、打ち手を先回り
“辞めそうな社員”を人の感覚に頼って察知するのは限界があります。
SHIFT AIでは、LMSや面談ログ・アンケートなどのデータを統合し、離職傾向をスコアリングして、早期の対応を可能にします。
- どの層に離職リスクが高いか
- どのチームで疲弊傾向があるか
- どの評価制度が定着率に影響しているか
といったインサイトを、AIの力で可視化・分析する仕組みを構築します。
③組織全体を変える「制度設計」まで一貫支援
「ツールを入れただけ」「制度を作っただけ」で終わらせない。
私たちは、現場の運用まで見据えた“組織ごとの最適化”を重視しています。
- 評価制度の設計・アップデート
- 管理職研修・1on1設計・フィードバック文化の構築
- LMS導入・AI分析環境の整備と社内浸透支援
属人化に依存しない“持続可能な定着モデル”を共に設計します。
まとめ|“辞めない仕組み”が、人手不足を根本から変える
人手不足の本質は「人がいない」ことではなく、「人が辞めていく」構造にあります。
せっかく採用しても、すぐに離職してしまう。
現場は育成の余裕を失い、また人が辞める——
この負の連鎖を断ち切らない限り、組織の未来は見通せません。
本記事では、以下の観点から、定着率を高めるための戦略を解説してきました。
- 離職の背景にある構造的な原因の把握
- “辞めたくならない職場”のつくり方
- 評価制度・マネジメント・業務負荷の仕組み的改善
- AI活用による離職予兆の可視化と予防
- LMSや育成設計による、成長実感をもたらす環境づくり
重要なのは、個別対応ではなく、仕組みで定着をつくること。社員が長く安心して働ける環境こそが、企業の競争力を支えます。
- Qなぜ離職防止が今、特に重要なのでしょうか?
- A
少子高齢化に伴う労働人口の減少により、新規採用が難しくなっている今、既存社員の定着こそが組織の生産性維持の鍵になっています。採用コストや教育の手間を考えても、「辞めさせない戦略」が経営課題として注目されています。
- Q離職防止に効果的な施策にはどんなものがありますか?
- A
オンボーディングの充実、1on1面談の制度化、評価制度の透明化、キャリア支援、業務負荷の見直しなどが挙げられます。これらを属人化せずに“仕組み”として設計することが、継続的な効果につながります。
- QAIを使って離職防止は本当に可能ですか?
- A
はい、可能です。たとえばLMSの学習データや面談記録をAIで解析し、離職予兆の検出やフィードバックの質向上に役立てる事例があります。SHIFT AIではこれらのデータを活用した“定着支援の仕組み化”をご提案しています。
- Q離職の予兆を早めに察知するにはどうすればいいですか?
- A
エンゲージメントサーベイや定期面談、日報・チャットの変化などから兆候を拾うことが重要です。最近ではこれらの情報をAIでスコア化し、早期対応につなげる仕組みを導入する企業も増えています。
- Q離職防止に役立つSHIFT AIのサービスには何がありますか?
- A
LMSと連携した育成設計支援、AIによる面談データ分析、評価制度や1on1文化の再設計などを通じて、“辞めない組織設計”を仕組み化する支援を行っています。詳細は[サービス資料(無料DL)]からご覧いただけます。