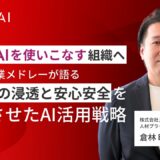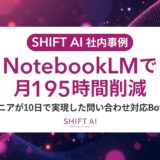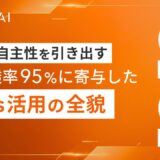営業という職種は、生成AIの登場によって大きな転換点を迎えています。
しかしながら、「生成AIを活用しよう」と掛け声をかけても、日々の商談に追われる営業現場では、どこから手をつければよいのか戸惑うケースも多いのではないでしょうか。
こうした営業組織の変革に対して、実務に深く入り込みながら支援を行っているのが、CLF PARTNERS株式会社です。CLF PARTNERSでは、一般的な営業研修やアドバイザリーとは一線を画す「実行支援型」の営業支援を行っています。特徴的なのは、営業部長クラス・マネージャークラス・実務担当者の3名体制でチームを組み、実際に営業現場に入り込むという点です。
営業支援や組織開発を手がける同社では、早くから生成AIを取り入れ、営業現場における「準備・育成・ナレッジ共有」といった属人化しやすい工程で、AIによる生産性向上と文化づくりの両立を実現しています。
本記事では、代表取締役社長・松下和誉氏への取材をもとに、CLF PARTNERSが実践する営業支援×生成AIの活用法をご紹介します。営業職の生産性を高めたいと考える企業の皆さまにとって、再現性のあるヒントをお届けできれば幸いです。
※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。
「実務ノウハウ3選」を公開
- 【戦略】AI活用を社内で進める戦略設計
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】属人化させないプロンプト設計方法
営業現場の課題は「準備不足」──生成AIによる事前調査の自動化
「営業がうまくいかない原因は“アポが取れない”ことではありません。最も大きな課題は、商談に向けた事前準備の不足だと感じています」と松下氏は語ります。
多くの営業現場では、商談直前に慌ただしく企業サイトを確認し、定型的なヒアリングに終始してしまうケースが少なくありません。しかし、CLF PARTNERSではこの“準備フェーズ”こそが成果を左右すると捉え、生成AIによる事前調査の仕組み化したツールを自社で開発・運用しています。
このツールは、以下の情報をもとに商談前のインサイトを自動で提示します。
- 企業のWebサイトや業界情報
- 担当者の部署・役職・SNS投稿などの公開情報
- 自社サービスの特徴や強み
さらに、商談の「アイスブレイク」に使える小ネタや、相手企業の課題仮説、提供できる価値の整理まで出力されるため、短時間で高品質な事前準備が可能となります。
この生成AIツールは社内での活用にとどまらず、クライアント企業向けにカスタマイズ提供もしており、「提案精度の向上」や「新人教育の効率化」にも効果を発揮しています。
属人的になりがちな“準備の質”を標準化し、営業スキルの再現性を高めること。それが、同社の生成AI活用の出発点なのです。
文化を変えるには“一緒にやる”──思考プロセスごとに伴走する支援
CLF PARTNERSがクライアント企業に対して営業支援を行う際、生成AIの活用は「ツール導入」にとどまりません。AIを使いながら、いかに営業文化を変革していくかまでを視野に入れた支援を提供しています。
「ツールを渡して“やっておいてください”では、絶対に浸透しないんです」と松下氏は語ります。
大切なのは、生成AIを用いた“思考のプロセス”を支援チームがクライアントと一緒に体験しながら進めていくことです。
たとえば、営業準備の支援では、相手企業のWeb情報やSNS投稿からAIが抽出した内容をもとに、「この発言にはどんな背景があるのか」「何が示唆されるのか」といった仮説を立てるところまで並走します。このプロセスを共に繰り返すことで、初めて活用が定着していきます。
また、商談の録画データを分析し、「どの発言が刺さったか」「成果につながった要素は何か」をAIが自動抽出。こうしたデータを蓄積・言語化することで、営業スキルの属人化を防ぎ、ナレッジの共通資産化を実現しています。
生成AIをただの効率化ツールにせず、「思考と学習を支える仕組み」として定着させる。その文化づくりまで支援に組み込む姿勢が、CLF PARTNERSならではの強みです。
社内に浸透した理由──“教わる立場”から得た実践知
CLF PARTNERSでは、自社内でも生成AIを積極的に活用していますが、その背景には少しユニークな経緯があります。
実は、同社のクライアントにはAIプロダクトの開発や活用を行う企業が多く、支援の過程で自然とAIの知識や事例を吸収していったというのです。
「我々はもともと営業支援の立場ですが、AI開発をしているお客様と接している中で、結果的に“教わる立場”として多くを学ばせてもらいました」と松下氏は振り返ります。たとえば、クライアントとのプロダクト共同開発の中でセキュアな環境下での生成AI活用を試行したり、教育系企業からAI研修の内容をインプットしたりと、現場で得た実践知が社内文化として定着していったのです。
そのうえで、社内で生成AIを活用する際には「トップの旗振り」と「プロ人材の導入」の2点が鍵だといいます。とくに従業員数300名以下の企業では、現場任せにせず経営陣が強いコミットメントを示すことが重要。また、自社内にAIの専門家がいない場合は、業務委託でもいいのでプロ人材を招聘し、適切な導入支援を受けることが必要だと語ります。
生成AIを組織に根づかせるには、偶然に頼らない明確な意思と仕掛けが求められます。同社が蓄積した“教わる側”としての経験は、クライアント支援においても貴重なナレッジとなっています。
AI活用でコンサル案件は1.5倍に──資料作成・リサーチの生産性が飛躍
CLF PARTNERSが生成AIを活用する最大の目的は、「時間を生み出すこと」です。
松下氏自身、膨大な業務を抱える中でAIの可能性を強く実感したといいます。「忙しすぎる人ほど、AIを使うべきです。こんなに生産性を上げてくれるツールは他にない」と語る通り、同社では営業準備・資料作成・リサーチ業務などのあらゆる場面で生成AIを活用しています。
とくに効果が大きかったのが営業資料や提案書の作成です。
「Genspark」を活用し、あらかじめ設計したテンプレートに沿って資料の下地を自動生成。その後、必要に応じて微調整を加えることで、“85%完成状態”からスタートできる体制を構築しています。
また、アジェンダ作成やヒアリングシートの下準備、商談後の振り返りレポートなど、営業関連のドキュメント業務もAIがカバー。プロンプト設計の工夫によって、初期アウトプットの精度を高めています。
こうした積み重ねにより、1人のコンサルタントが対応できる案件数は約1.5倍に増加しました。営業支援という「人が動く」ビジネスモデルにおいて、これは決して小さくない変化です。
生産性が向上したことで、より多くの顧客に深く向き合える時間が生まれた──これこそ、CLF PARTNERSが生成AIを実務に組み込む本質的な狙いといえるでしょう。
今後の展望──AIで“世の中の小さな課題”をプロダクト化したい
CLF PARTNERSでは、生成AIを単なる業務効率化の手段としてだけでなく、事業そのものの可能性を広げる武器として捉えています。
「我々が解決したいのは、世の中にある“手が届かない課題”です。大手企業が注力しにくい、けれど確実に存在する問題に対して、AIを使って小さなプロダクトを形にしていきたい」と松下氏は語ります。
同社ではすでにAIエンジニアの採用も進めており、自社プロダクトの構想が水面下で動き始めています。その背景には、営業支援の現場で得た“困りごと”の一次情報と、AIを活用して仮説・検証・改善を回してきた実践知があります。
また、社内ではXでの発信やコラム記事の執筆にもAIを活用。松下氏は「発信の方向性や構成は人が主導しながら、AIにはアイデア出しや壁打ちのパートナーとして補完的に関わってもらった。フォロワー5,000人までの立ち上げも、そうした協働の成果」と語っています。
さらに今後は、営業支援を超えて「人とAIが共に働く組織づくり」や「人材の能力を最大化する仕組み」へと支援領域を拡張していく構想もあります。
AIを用いて目指すのは、“効率化”ではなく、“変革”。
CLF PARTNERSは、現場起点で蓄積してきた知見をもとに、新たなプロダクトと価値創造のステージへと進もうとしています。
CLF PARTNERSの取り組みに学ぶ「真似すべき」5つのポイント
CLF PARTNERSは、営業支援のプロとして、成果に直結する“実戦的な仕組みづくり”を実現してきました。単なる業務のAI化ではなく、「営業の質と再現性を高める」ための生成AI活用が徹底されているのが特徴です。以下に、他社でも取り入れやすいエッセンスを5つに整理しました。
- 営業最大の課題を「準備不足」と再定義する
成果が出ない原因をスキル不足のせいにせず、AIで解決可能な「準備」の質と量にフォーカスする視点。 - 事前調査・仮説立案プロセスをAIで自動化・標準化する
属人化しがちな商談準備を、AIツールによって「誰でも高品質に」行える仕組みを構築する。 - ツール提供だけでなく「思考プロセス」に伴走し文化を変える
AIの出力結果をどう解釈し、仮説を立てるか。その思考の過程を共に実践することで、単なるツール利用に終わらない文化変革を促す。 - 資料作成を「85%完成状態」から始め、時間を創出する
Genspark等を活用し、資料作成の“最も面倒な部分”をAIに任せ、人間はより創造的な部分に集中する。 - 顧客から“教わる立場”になり、実践知を吸収する
自社だけで完結せず、最先端を走るクライアントやパートナーから謙虚に学び、自社のナレッジとして取り入れる姿勢。
「特定の部署だけ」で終わらせないために
生成AIの活用は、特定の部署や一部の業務だけで成果を出しても、組織全体の変化にはつながりません。CLF PARTNERSのように、起点となる活用から組織的な展開へとスケールさせていく視点が、今後ますます重要になります。
このように、特定の業務領域にとどまらず、生成AIを組織的に展開していく視点は、どの企業にとっても重要なヒントとなるでしょう。
SHIFT AIでは、
「まずは一部門で試したい」
「PoCで社内を説得したい」
「全社展開を見据えて、活用とルール整備を両立させたい」
といったフェーズごとの課題にあわせた伴走支援を行っています。
もし自社内で「生成AIを活用して、さらに事業を推進させていきたい」「人だけに依存する業務を変革させたい」といった考えがすこしでもあるなら、ぜひとも一度SHIFT AIにご相談ください。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応