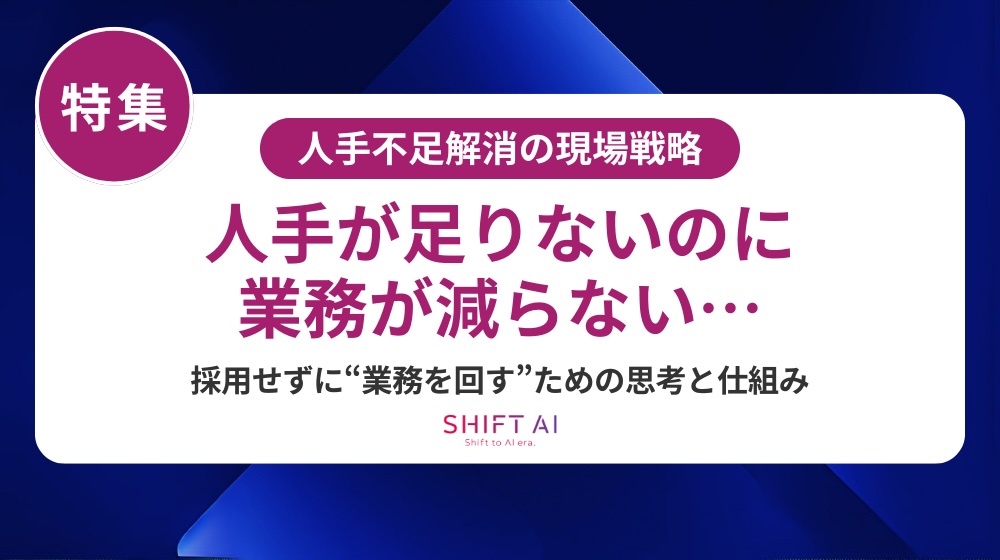「採用しても、すぐに辞めてしまう」
「制度を整えても、現場が回らない」
多くの企業が、“人手不足”と“働き方改革”のはざまで立ち止まっています。
特に中小企業や現場中心の業種では、「人が足りないから改革できない」「改革しないから人が辞める」という負のループに陥りがちです。
しかし今、問われているのは「もっと人を集めること」ではなく、“今いる人材でどう持続的に仕事が回る組織をつくるか”という視点です。
本記事では、
- なぜ働き方改革が人手不足対策になるのか
- その実現を阻む組織構造の壁
- 業種別の特性と対処法
- そしてSHIFT AIが支援する「仕組み化による定着と再設計」のアプローチ
を通じて、“辞めない職場づくり”のための改革戦略をお伝えします。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
なぜ“働き方改革”が人手不足対策になるのか?
働き方改革が「人手不足の抜本的な対策」として注目されるのは、単なる労働時間の短縮や制度変更にとどまらず、組織全体の“生産性と定着力”を底上げできるからです。
では、具体的にどのような点が人手不足の改善につながるのか、3つの視点から見ていきましょう。
「採用」ではなく「仕組み」の見直しがカギ
多くの企業が人手不足の解消を「採用」に頼りがちですが、人材の確保には時間とコストがかかり、確実性も低いのが実情です。
それに対して「働き方改革」は、今いる人材が辞めずに、最大限に活躍できる組織設計を行うアプローチです。
つまり、根本的な人手不足の対策とは「人を増やす」ことではなく、“今いる人で回る状態”をつくる仕組みを整えることに他なりません。
働き方改革が人手不足に効く3つの理由
働き方改革が人手不足対策として効果を発揮するのは、「人が辞めない」「人が活躍できる」「人を呼び込める」という3つの側面を同時に強化できるからです。
それぞれの観点から、具体的に見ていきましょう。
①定着率の向上=離職による人材ロスを防げる
働きやすい職場環境は、社員の満足度と定着率を大きく高めます。
人が辞めなければ、新たな補充や引き継ぎの負担も減ります。
②業務の効率化で“少人数でも成果が出せる”体制に
業務フローやツールの見直しによって、生産性は大きく改善できます。
特に生成AIやRPAなどの活用は、間接業務の削減に直結します。
③多様な働き方が採用範囲を広げる
柔軟な勤務制度(フレックス/短時間/リモート)を導入することで、
子育て中の人材や副業希望者、高齢人材など、多様な層の就業が可能になります。
「制度変更だけ」では成果につながらない
注意すべきは、「制度の導入=働き方改革の完了」ではないという点です。
制度だけ整えても、運用が追いつかなければ現場は混乱し、むしろ働きにくさが増す結果にもなりかねません。
本当の働き方改革とは、
- 制度
- 運用ルール
- 評価制度
- 管理職の意識改革
までを含む、“組織全体の再設計”にほかなりません。
関連記事:人手不足をAI活用で解決する完全ガイド|導入手順・研修・成功ポイントまで徹底解説
人手不足企業で働き方改革が進まない5つの壁
働き方改革の必要性を感じてはいても、実際に取り組みが進んでいない企業は少なくありません。
とくに人手不足の企業ほど、「人が足りないから改革できない」というジレンマに陥りがちです。
ここでは、働き方改革が進まない主な“5つの壁”を整理し、課題の本質を明らかにします。
①長時間労働が常態化し、“改革疲れ”が起きている
慢性的な人手不足により、一人あたりの業務量が多すぎる状態では、新しい制度の運用や改善活動を行う余力が残されていません。
結果、「働き方改革」を進めるはずが、制度の導入だけで満足してしまい、実態は何も変わらないというケースが散見されます。
②現場任せで制度が形骸化している
制度を導入しただけで、現場に丸投げになっている企業も多くあります。
「使われない制度」「意味が理解されていないルール」は、社員の不信感や不満を生み、逆に離職リスクを高める要因にもなりかねません。
③上層部が「今までどおり」にこだわってしまう
経営層や管理職が過去の成功体験に縛られていると、「変えようとする動き」にブレーキがかかります。
特に中間管理職層が「業務改革」と「部下の管理」に挟まれると、
現場の改革は進まず、“頑張るほど消耗する職場”になってしまいます。
関連記事:プレイングマネージャーは限界?現場と管理の両立に疲れたあなたへ
④評価制度と働き方が一致していない
働き方改革によってリモートワークや時短勤務が可能になっても、評価軸が従来通り「長時間・常駐・対面重視」であれば、社員は新制度を安心して使うことができません。
制度と人事評価のズレが、活用率の低下につながっているのです。
⑤多様な働き方を受け入れる仕組みがない
リモートワーク、副業、短時間正社員などに対応するには、業務フローや管理体制、ITツールの整備が欠かせません。
それが整っていない企業では、かえって混乱や摩擦が増えることもあります。
こうした“構造的な壁”を乗り越えるには、制度だけでなく「運用と定着の仕組み化」が必要です。
業種別に異なる「人手不足×働き方改革」のハードル
人手不足への対策として働き方改革を進めるとき、業種ごとにぶつかる壁は大きく異なります。
業務の性質や求められるスキル、時間帯、顧客対応の有無などによって、改革の難易度も課題も変わってきます。
ここでは、特に人手不足の影響が深刻な3業種(製造・医療・接客)を取り上げ、それぞれの実情と対処のヒントを見ていきましょう。
製造・物流|物理的制約と生産性の両立
製造・物流業界では、「現場にいなければできない作業」が大半を占めており、リモートワークやフレックスタイムといった改革手法の適用が難しいという現実があります。
それでも、「業務の標準化・省力化」や「工程別のAI・機械導入」など、生産性を上げつつ、少人数でも回る体制を模索する動きが広がっています。
医療・介護|人命対応と柔軟性のトレードオフ
医療・介護分野では、人手不足の深刻さが命に直結するため、働き方改革にも慎重な対応が求められます。
一方で、過酷な勤務体制による離職が後を絶たず、「改革しなければ人が辞める」構造になっているのも事実です。
夜勤負担の平準化や、ICT活用による業務削減、定期的なメンタルケアの制度化など、
安全性と柔軟性をどう両立させるかが鍵となります。
飲食・接客|短時間勤務と教育の課題
飲食・接客業界では、学生や主婦層の短時間人材が多く、シフト調整と教育の手間が常に課題となります。
また、接客品質を保つためのOJT依存が高く、属人的なノウハウが多いことも、改革の障壁になっています。
マニュアル整備やeラーニング導入、シフト自動化ツールの活用が、働きやすさと品質維持の両立につながります。
関連記事:「人手不足を解消する15の方法|従来手法+AI戦略で効率化を実現する最新戦略
成功する企業が実践する“人が辞めない働き方改革”とは?
働き方改革は制度やツールを導入するだけでは意味がありません。
本当に人手不足を補える改革とは、「人が辞めない仕組み」まで作り込めている企業が実践していることです。
ここでは、成功企業に共通する“3つの設計視点”を解説します。
①業務の「見える化」でムダ・属人化を削減
働き方改革の第一歩は、現場の仕事を誰が、いつ、どのように行っているかを可視化すること。
業務が属人化していると、誰かが辞めたときに業務が回らず、人手不足がさらに加速します。
業務フローのマッピング/タスク管理ツールの導入/AIによる業務記録分析など、
今の仕事の全体像を明らかにすることで、改革の余地が見えてきます。
②評価制度を「時間軸」から「成果軸」へ転換
長く働いた人が評価される時代から、「成果を出した人」が評価される時代へ。
リモート・フレックス・副業などを可能にするには、時間ではなくアウトプットで評価する制度が不可欠です。
評価軸が明確でないと、柔軟な働き方を導入しても、「結局フル出勤の人の方が有利」という事態を招きます。
③AI・RPAの活用で人の仕事を再設計
定型業務や反復作業は、生成AIやRPAによって代替・効率化が可能です。
これにより、人手が足りない中でも、社員のリソースを本来注力すべき業務に再配分できます。
SHIFT AIでは、業務棚卸しからAI適用範囲の選定、導入後の定着支援まで一気通貫で支援しています。
成功する企業が実践する“人が辞めない働き方改革”とは?
「働き方改革」という言葉が広まり、制度導入だけで満足してしまうケースも増えました。
しかし実際に人手不足を改善している企業には、共通する“仕組み”と“姿勢”があります。
ここでは、人が辞めず、パフォーマンスを維持できる組織が実践している具体的な取り組みを紹介します。
多様な勤務制度の整備(フレックス/短時間正社員/副業OK)
一律の「出社・フルタイム」では、ライフステージや価値観が異なる社員を活かしきれません。
成功企業は、勤務形態を柔軟にすることで“辞めない選択肢”を増やしています。
- 育児・介護との両立を可能にする時短正社員制度
- キャリアの幅を広げる副業解禁
- 自律性を高めるフレックスタイムや週4勤務制度
「一律」から「多様」への転換が、離職防止と採用力の強化を両立します。
テクノロジー活用による業務自動化(RPA/生成AI)
人手不足の根本解決には、「人でやらない業務」を増やすことが不可欠です。
業務の棚卸しを行い、ルーチンや単純作業はRPAや生成AIで効率化することで、限られた人材をコア業務に集中させられます。
SHIFT AIでは、業務プロセスの設計からAI導入、社員定着支援までを一貫して支援しています。
キャリア支援と対話を軸とした制度設計
離職理由の多くは、「将来が見えない」「自分が評価されていない」といったキャリアへの不安や不満です。
優れた企業は、以下のような制度で従業員との“対話”を重視しています。
- 定期的な1on1面談
- キャリア面談の仕組み化
- ジョブポスティング制度の導入
- 社内公募や異動希望受付フォームの設置
上司との信頼関係と、成長イメージの可視化が、定着率の底上げに直結します。
従業員満足度(ES)を可視化し、定点改善サイクルをつくる
感覚だけで「うちは働きやすい」と思い込んでいても、離職は止まりません。
実際に成果を出している企業は、ES(従業員満足度)を定量的に把握し、改善施策を回す体制を持っています。
- 毎月のESサーベイと可視化ダッシュボード
- 所属部署ごとの傾向把握
- ESと離職率・生産性の相関分析
- 改善施策のPDCAと組織間共有
人手不足に強い働き方改革“3層構造”モデル
人手不足を“構造的に補う”ためには、単発の制度導入やツール活用だけでは不十分です。
重要なのは、組織全体を「制度」「運用」「現場」の3層でとらえ、仕組みとして機能させることです。
この3層が連動することで、採用に頼らず「今いる人が辞めずに活躍できる」環境を作ることができます。
①制度設計層|勤務制度・福利厚生の再構築
まずは、社員が安心して働ける土台を整えることから。
制度設計層では、多様な働き方に対応した就業規則や福利厚生の見直しを行います。
- フレックスタイム、週4勤務、短時間正社員制度
- 副業容認、育児・介護両立支援、再雇用制度
- メンタルヘルス/健康経営/ストレスチェック強化
社員が「長く続けたい」と思える設計は、採用よりも効果的な“人材確保策”になります。
②運用・管理層|AI活用による勤務分析とリスク兆候の予測
制度を整えても、それが正しく運用されなければ意味がありません。
管理層では、AIやBIツールを活用した勤務実態の可視化と、離職予兆の検知がカギになります。
- 勤怠・残業・業務ログのデータ統合
- 「過重労働」「孤立」「不満」の早期兆候を可視化
- 従業員満足度やエンゲージメントの推移分析
SHIFT AIでは、これらを既存データに連携する形でAIモデル構築を支援しており、属人管理から脱却した“仕組みとしての離職防止”を実現します。
③現場実装層|リーダーのマネジメント行動の見直し
どんな制度も、現場で“使われなければ”定着しません。
最後の層は、現場マネージャーの行動変容と育成です。
- リモート部下との1on1頻度の明確化
- 成果評価のフィードバックトレーニング
- 「やらされ感」から「巻き込み型」への意識転換
- 教える側の育成疲れを減らす“育成設計”の導入
関連記事:育若手育成に疲れた管理職へ|“教える負担”を減らす3つの処方箋
業務設計×AIで「時間と役割」の最適化を
単にツールを入れるのではなく、まず業務フローをゼロベースで可視化・分解し、「やらなくていい仕事」「自動化できる仕事」「人がやるべき仕事」に再整理することが重要です。
そのうえで、AIやRPAを適用し、社員の“時間の使い方”と“担うべき役割”を最適化します。
【導入アプローチ・事例例(表形式または箇条書き)】
| 項目 | Before(従来の業務) | After(AI導入後) |
| 社内FAQ対応 | 情報が属人化/人力で回答 | 生成AIによる即時対応チャット |
| 会議議事録 | メモ取りに集中/漏れが多い | AI自動文字起こし+要約機能 |
| 営業リスト作成 | 人力で情報収集 | AI+RPAで条件抽出・整理 |
| クレーム対応分析 | 感覚的な属人対応 | 音声データをAIで感情分析 |
| 教育・研修 | OJT頼み/人によって差 | eラーニング+AI理解度評価 |
AIは単なる効率化手段ではなく、「人が価値を発揮できる時間」を最大化する手段です。
人手不足を逆手に取り、“やらなくていい仕事”を構造的に減らすことこそが改革の本質といえます。
関連記事:毎日同じことの繰り返しで仕事がつまらない人へ|生成AI研修で変わる業務改革
まとめ|“働き方改革”は制度ではなく、組織戦略である
多くの企業が、「働き方改革=制度の導入」と捉えがちです。
しかし、人手不足に悩む今、必要なのは制度だけでなく“組織の仕組みそのもの”の見直しです。
働き方改革とは、人手不足に“耐える”のではなく、“人が辞めない・活躍できる状態を設計する”こと。
制度・テクノロジー・マネジメントが連動した“戦略的な組織設計”が、本質的な打ち手になります。
今いる人材をどう活かすか、どうすれば辞めない組織にできるか。
その問いに本気で向き合った企業こそが、採用に頼らない強い組織を実現しています。
SHIFT AIでは、制度設計とAI活用を組み合わせた「持続可能な組織戦略」をご支援しています。
現場主導の業務改革から、マネジメント支援、AI導入まで、ぜひ一度ご相談ください。
- Q働き方改革で本当に人手不足は解消できますか?
- A
「すぐに人が増える」わけではありませんが、今いる人材の定着・活躍を最大化することで、採用に頼らない体制をつくることが可能です。業務設計・制度改革・AI活用の3本柱がポイントです。
- QAI導入は大企業だけの話では?中小企業にもできますか?
- A
すぐに人が増える」わけではありませんが、今いる人材の定着・活躍を最大化することで、採用に頼らない体制をつくることが可能です。業務設計・制度改革・AI活用の3本柱がポイントです。
- Q制度は整っていても、人が辞めてしまうのはなぜですか?
- A
制度と「現場運用」が乖離しているケースが多いためです。制度の“使われ方”までマネジメント設計しないと、形骸化してしまいます。現場で機能させるマネージャー支援も必要です。
- Qフレックスやリモート導入は労務管理が難しそうですが、どうすれば?
- A
勤怠データや稼働状況を可視化・分析できるツールを使うことで、マネジメント負荷を抑えた柔軟な勤務制度の運用が可能です。加えて、AIによる離職リスクの予兆検知も有効です。
- Q働き方改革やAI導入を一から相談したいのですが、可能ですか?
- A
はい、SHIFT AIでは業務可視化からAI導入、制度設計の再構築、マネジメント教育まで一気通貫で支援しています。まずは無料資料のダウンロードをご活用ください。