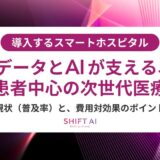AI導入やDX推進に取り組んでいる企業の多くが、こんな壁にぶつかります。
「経営層の理解が得られず、全社展開に踏み切れない」
「PoCは成功したのに、現場への定着が進まない」
「AIをどう戦略に組み込むべきか整理できない」
原因は、技術そのものではなく 組織の7つの要素”に隠されています。
マッキンゼーが提唱した「7Sフレームワーク」は、戦略・組織構造・人材・価値観など、企業変革に欠かせない要素を整理するための強力なツールです。これをAI時代の視点で再解釈したのが「AI 7Sフレームワーク」です。
本記事では、AI 7Sフレームワークを用いて以下の内容を解説します。
| この記事でわかること一覧🤞 |
| ・自社のどこに課題があるのかを診断する方法 ・戦略から人材育成まで、AI導入を成功させる改善のヒント ・実際に成果を出すための実践ステップ |
ぜひ、AI導入に悩む自社の「答え」を見つけるきっかけにしてください。
「正しいプロンプト」の考え方
業務活用の成否を分ける「指示設計」のノウハウを、生成AIを活用したい企業様向けに無料で公開します。
マッキンゼーの7Sフレームワークの基本
AI 7Sフレームワークを理解するうえで欠かせないのが、ベースとなるマッキンゼーの7Sモデルです。
このモデルは、戦略や組織構造だけでなく、企業文化や人材のスキルといった“ソフト面”まで含めて全体を捉えるのが特徴です。単に仕組みを整えるだけではなく、ハードとソフトの両輪をそろえてこそ、変革は加速するという考え方が根底にあります。
7Sモデルとは?(ハード3Sとソフト4S)
7Sモデルは、以下の7つの要素で構成されています。大きく分けると「ハード3S」と「ソフト4S」に整理されます。
- ハード3S(形を決める要素)
戦略(Strategy)、組織構造(Structure)、システム(System)を指し、経営層が設計できる見える仕組みです。例えば新しい事業戦略を掲げたり、組織図を再編成したりといった施策がここに含まれます。 - ソフト4S(組織文化を支える要素)
価値観(Shared Value)、マネジメントスタイル(Style)、人材(Staff)、スキル(Skill)の4つです。こちらは短期間で変えるのが難しく、経営変革を根付かせるかどうかを左右する部分です。AI導入においても、この“ソフトの壁”が成否を分けるケースが多いのです。
このように、7Sは「仕組み」と「文化」の両面から組織を診断するフレームワークであり、DXやAIの推進にも直結する考え方といえます。
なぜDXやAI導入に7Sが有効なのか
AI導入が失敗する企業の多くは、システムやツール選定だけに注力し、文化や人材のスキルといったソフト面を見落としがちです。7Sを使うことで、「AIが動かない理由は技術ではなく人や文化にある」ことを可視化できます。
また、7Sは単独で活用するだけでなく、外部環境を分析するPEST分析やSWOT分析と組み合わせることで、より実践的な戦略立案が可能になります。
👉 関連記事も参考に! AI PEST分析のやり方|生成AIで外部環境を効率的に把握する方法
こうした複数のフレームワークを相互に補完しながら使うことで、自社の強みや弱みをより立体的に把握し、AIを事業戦略にどう組み込むかという本質的な問いに答えやすくなります。
AI 7Sフレームワークの全体像
従来の7Sモデルは、戦略や組織文化を整理する優れたフレームワークですが、AI時代の変化スピードにはそのままでは対応しきれません。データ駆動型の意思決定や、自動化による業務変革を前提に考えると、7Sの各要素をAI視点で再定義する必要があります。
AI 7Sフレームワークは、次のような特徴を持っています。
AI時代に合わせた7つの視点
- 戦略(Strategy):AIを事業戦略に組み込み、どの領域で成果を出すかを明確化する
- 組織構造(Structure):AI推進部門と現場部門の連携を前提にした体制設計
- システム(System):ツール導入だけでなく、データ基盤・セキュリティを含めた全体最適化
- 価値観(Shared Value):AI活用を前提とした“データ文化”を組織に浸透させる
- マネジメントスタイル(Style):トップダウンとボトムアップを組み合わせたAI活用推進のリーダーシップ
- 人材(Staff):専門人材の採用だけでなく、既存社員のリスキリングも含めた配置
- スキル(Skill):エンジニアリングだけでなく、AIの成果を業務で活かすリテラシーを全社員に広げる
このようにAI 7Sでは、「AIが技術的にできること」だけでなく「組織全体でどう受け入れ、成果につなげるか」を立体的に整理できるのが大きな強みです。
AI 7Sで課題を見える化するメリット
AI導入が失敗する多くのケースは、技術選定よりも社内の準備不足が原因です。例えば「データが整っていない」「AIを活かす人材がいない」「経営層が本気で推進していない」といった課題は、従来のフレームワークでは見過ごされがちでした。
AI 7Sを使えば、こうしたボトルネックを7つの観点で具体的に洗い出せるため、次のアクションが明確になります。単にAIを導入するのではなく、「自社は何を整えれば成果が出るのか」を可視化できるのです。
他のフレームワークとの違いと補完関係
AI 7Sは単独で使うだけでなく、外部環境を把握するフレームワーク(PEST/PESTLE)や内部環境を整理するSWOTと組み合わせることで、より実践的な診断が可能になります。
関連記事もチェック!
AI 7Sが「組織の内部構造」を可視化し、PESTやSWOTが「外部環境や競争要因」を把握する。これらを掛け合わせれば、AI導入戦略の全体像を一枚の絵として描けるようになります。
AI 7Sフレームワーク|各要素の診断ポイント
AI 7Sフレームワークの強みは、組織を7つの視点から診断し、AI導入の成功を妨げる要因を可視化できる点にあります。ここでは各要素ごとに「何をチェックすべきか」を整理します。自社の現状と照らし合わせながら読み進めてみてください。
Strategy(戦略)|AIを事業戦略に組み込む視点
AI導入を単なる効率化の手段として捉えると、施策が点在して効果が見えにくくなります。「どの事業領域で成果を出すのか」を明確にし、経営戦略と一体化させることが重要です。
- 事業の柱ごとにAIの活用テーマを定義しているか?
- 成果指標(KPI)が「コスト削減」だけに偏っていないか?
戦略の欠如は「場当たり的導入」につながる典型パターンです。
Structure(組織構造)|AI推進体制の整備
DX推進部門と現場部門が分断していると、AI導入は必ず行き詰まります。AI推進を横串で支える組織設計が不可欠です。
- 経営層の意思決定と現場実行をつなぐ橋渡し役はいるか?
- プロジェクト単位ではなく、全社横断的な推進体制があるか?
System(仕組み)|データ基盤と業務プロセス
AIを活かすには、単なるツール導入ではなくデータの整備と業務プロセスの見直しがセットです。
- データは部門横断で統合・活用できているか?
- AIを業務に組み込む標準プロセスは設計されているか?
Shared Value(価値観)|データ文化と合意形成
AI導入は「文化」の抵抗に直面しがちです。トップから現場まで“AIを前提とした価値観”を共有できるかが肝になります。
- 現場が「AIに仕事を奪われる」と感じていないか?
- 経営層が「AIは経営に不可欠」というメッセージを発信しているか?
文化的な壁を乗り越えられない企業は、技術的に成功しても定着に失敗します。
Style(マネジメントスタイル)|リーダーシップの在り方
AI時代のリーダーには、データをもとに意思決定しつつ現場を巻き込む柔軟さが求められます。
- トップダウンとボトムアップを組み合わせた推進ができているか?
- 管理職がAI活用に前向きか?
Staff(人材)|適材適所とリスキリング
AI導入には専門人材も必要ですが、それ以上に重要なのは既存社員の再教育(リスキリング)です。
- AI人材の採用と育成に投資しているか?
- 既存スタッフにAIリテラシー研修を実施しているか?
Skill(スキル)|全社的なAIリテラシー
AI活用を一部の専門家に任せるのではなく、全社員が基礎的スキルを持つ状態を目指すことが理想です。
- 部門横断でAI活用の成功事例を共有できているか?
- 現場で「AIをどう使うか」を自ら考える文化があるか?
👉 「診断の結果、課題が見えてきた方へ」
AI 7Sフレームワークで浮き彫りになった課題を、実際に社内で解決へつなげるには研修や伴走支援が不可欠です。
AI 7Sフレームワーク活用の具体事例
AI 7Sフレームワークは、単なる理論にとどまらず、実際の企業変革にも応用されています。ここでは、業界ごとの活用イメージを取り上げ、自社にどう適用できるかを考えてみましょう。
製造業|品質管理と組織文化の変革
製造業では、AIを用いた画像解析やセンサー技術による品質管理が急速に広がっています。しかし、単にシステムを導入するだけでは現場に根付かず、成果も限定的になりがちです。
そこでAI 7Sの観点を使うと、
- System:不良品検知システムを導入
- Shared Value:現場スタッフが「AIが支援する=仕事が楽になる」と認識する文化醸成
- Skill:品質管理担当のAIリテラシー向上研修を実施
という3Sを同時に整えることで、「技術」×「文化」×「人材」のバランスが取れ、成果が持続的に出る仕組みが構築されます。
金融業|リスク管理と人材スキルの強化
金融業では、AIを活用した不正検知やリスク管理が一般的になりつつあります。しかし、「AIがブラックボックス化し、経営層や監督当局に説明できない」という課題が顕在化しています。
AI 7Sを当てはめると、
- Strategy:AIをリスク管理の中核に据え、経営方針に明記
- Style:マネジメント層が「説明責任を果たせるAI活用」を推進
- Staff/Skill:データサイエンティストと金融実務担当の混成チームを育成
このように組織全体で取り組むことで、AI活用の透明性と信頼性を両立できます。
サービス業|顧客接点のAI化と組織再設計
サービス業では、チャットボットやレコメンドエンジンなど、顧客接点にAIを活用する動きが加速しています。しかし現場では「現場スタッフの役割が減るのでは?」という不安が生まれがちです。
AI 7Sの視点では、
- Structure:顧客対応をAIと人で役割分担する新体制を構築
- Shared Value:AIは「人の仕事を奪う」ではなく「顧客体験を高める補助」であると周知
- Staff:接客スタッフにAIツール活用研修を実施
といった形で整合性を持たせれば、AI活用による顧客満足度向上と従業員満足度の両立が実現します。
事例を見て「うちの会社ならどこから着手すべきだろう?」と感じた方も多いはずです。そこで重要になるのが、自社に最適なアプローチを見つけるための研修・伴走支援です。
他フレームワークとの使い分け
AI 7Sフレームワークは組織内部の課題を整理するのに非常に有効ですが、万能ではありません。外部環境や競争環境を分析するフレームワークと組み合わせることで、より実践的で立体的な戦略立案が可能になります。
AI 7S × PEST分析|外部環境を見極める
PEST分析は、政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの観点から外部環境を捉える手法です。AI時代には、法律や環境問題も考慮できる PESTLE分析 も重要になります。
例えば、AI人材育成を進めたい企業であれば、
PESTで「労働市場の変化」「規制強化」「新技術の登場」を把握し、AI 7Sで「社内体制やスキル」を見直す、といった形で組み合わせると、外部と内部をバランス良く調整できるようになります。
👉 関連記事
AI 7S × SWOT分析|自社の強みと弱みを整理する
SWOT分析は、内部要因(Strength/Weakness)と外部要因(Opportunity/Threat)を掛け合わせ、自社の戦略を明確にするフレームワークです。
AI 7Sが組織の「現状把握」に強みを持つのに対し、SWOTは「戦略立案」に直結する点が特徴です。例えば、
- AI 7Sで「スキル不足」という課題を特定
- SWOTで「リスキリングを進めれば市場のAI需要を獲得できる」という機会を発見
といった具合に、診断→戦略化の橋渡しが可能になります。
AI 7S × ファイブフォース分析|競争環境を把握する
ファイブフォース分析は、自社を取り巻く競争要因(既存競合、新規参入、代替品、顧客、供給者)を整理するフレームワークです。
AI 7Sが社内の課題整理に強いのに対し、ファイブフォースは市場ポジションの理解に力を発揮します。両者を掛け合わせれば、
- 社内の強化ポイント(AI人材、データ基盤)
- 外部の脅威(新興AIスタートアップの台頭)
を同時に把握でき、より実効性の高いAI導入戦略を描けます。
関連記事:AI業界を制する5つの力!ファイブフォース分析で競争環境と戦略を可視化
複数フレームワークを掛け合わせる意義
AI 7Sは「組織内部」を可視化する力に優れています。しかし、外部環境や競争要因も加味しなければ、実行可能な戦略には落とし込めません。
そのためには、AI 7Sを起点に PEST/SWOT/ファイブフォースと組み合わせて使うことが有効です。
こうした組み合わせを理解すれば、経営企画やDX推進の担当者は「部分最適ではなく全体最適のAI戦略」を描けるようになります。
AI 7Sフレームワークを実践に落とし込むには?
AI 7Sフレームワークで課題を整理できたとしても、そこから先に進まなければ意味がありません。診断→改善施策→社内浸透という一連のプロセスに落とし込むことで、初めて成果が生まれます。
診断シートを活用して現状を可視化する
まずは7つの観点で自社をセルフチェックし、どこにギャップがあるのかを数値化・言語化することがスタートです。
- Strategy:AIが事業戦略に位置づけられているか?
- Staff:AI人材の育成・採用の仕組みはあるか?
- Shared Value:組織文化としてAIを受け入れる土壌があるか?
こうした診断は、経営企画部やDX推進部だけでなく、現場マネージャーを巻き込んで行うことが重要です。全社的に現状を共有することで「なぜAI導入が必要か」の理解が深まります。
課題抽出から施策立案へつなげる
診断の結果、ギャップが見えてきたら、それを改善施策に落とし込むステップに進みます。
- スキル不足 → 社員研修やリスキリングの計画を策定
- 組織構造の不整合 → 推進体制を横断的に再編成
- 文化的抵抗 → 経営トップからのメッセージ強化
ここで重要なのは、優先順位を明確にすることです。すべてを同時に進めるのは非現実的なので、「どの課題を最初に解決すべきか」を合意形成する必要があります。
SHIFT AI for Biz研修で実行支援を加速する
診断と施策立案だけでは、実行段階でつまずく企業が少なくありません。そこで効果を発揮するのが、外部の知見を活用した研修・伴走支援です。
SHIFT AI for Bizの法人研修では、
- 自社の診断結果をもとにしたカスタマイズ研修
- 経営層と現場を巻き込むワークショップ形式
- 実行計画まで落とし込む伴走サポート
を提供し、「診断で終わらせない」ための実践力を養うことができます。
まとめ|AI 7Sフレームワークで課題を可視化し、実行へ
AI導入を成功させるには、技術選定やシステム構築だけでは不十分です。戦略・組織構造・文化・人材・スキル──これら7つの要素がバランスよく整って初めて、成果が持続するのです。
AI 7Sフレームワークは、その課題を可視化し、改善の優先順位を整理するための強力な武器です。
| この記事のおさらいポイント🤞 |
| ・戦略にAIをどう位置づけるか ・組織体制は変革に適しているか ・社員のスキルや文化はAIを受け入れる準備ができているか |
こうした問いに答えることで、「なぜAI導入が進まないのか」を明確化できます。
しかし診断だけでは組織は変わりません。実際の現場に落とし込み、全社的な合意形成と実行力を伴わせることが成功の分かれ道です。
そこで重要なのが、外部の知見を取り入れた研修・伴走支援です。
SHIFT AI for Bizの法人研修では、
- 自社の診断結果に基づいたオーダーメイド研修
- 経営層から現場までを巻き込むワークショップ形式
- 実行計画をその場で策定し、行動に直結
を提供し、「診断から実行」へ最短で橋渡しします。
今こそ、AI 7Sフレームワークを自社に当てはめ、組織変革を加速させる一歩を踏み出しましょう。
AI 7Sフレームワークのよくある質問(FAQ)
AI 7Sフレームワークに関して、読者からよく寄せられる質問をまとめました。疑問を解消しながら、自社の状況に当てはめて考えてみてください。
- QAI 7Sフレームワークは中小企業にも使えますか?
- A
はい、規模にかかわらず活用可能です。大企業は「部門間の連携不足」や「複雑な組織文化」に課題を抱えるケースが多い一方、中小企業では「AI人材不足」や「データ基盤の未整備」がボトルネックになりがちです。
7つの観点で整理することで、規模に応じた優先順位を明確にできるため、中小企業にとっても導入メリットは大きいといえます。
- QDX推進が進まないのは7Sのどの要素が原因ですか?
- A
多くの場合、Shared Value(組織文化)やSkill(社員スキル)の不足が最大の障壁になります。
技術やシステムの整備だけでは、現場が「自分ごと化」せずに活用が進まないのです。逆に言えば、文化とスキルを補えば、戦略・構造・システムが一気に回り始めることも珍しくありません。
- QAI 7Sフレームワークと他の分析手法はどう使い分ければいいですか?
- A
AI 7Sは「内部構造の診断」に強みがあります。これに対して、
- PEST/PESTLE分析:外部環境(規制・市場動向・技術変化)の把握
- SWOT分析:内部と外部を組み合わせて戦略を設計
- ファイブフォース分析:競争環境を可視化
といったフレームワークを組み合わせることで、より実践的なAI導入戦略が描けます。
- Q社内にAI人材がいなくても始められますか?
- A
もちろん可能です。最初から高度なAIエンジニアを採用する必要はありません。むしろ、既存社員に基礎的なAIリテラシーを浸透させることが早期成功につながります。外部の研修や伴走支援を活用しながら、段階的にスキルを伸ばしていくのが現実的です。