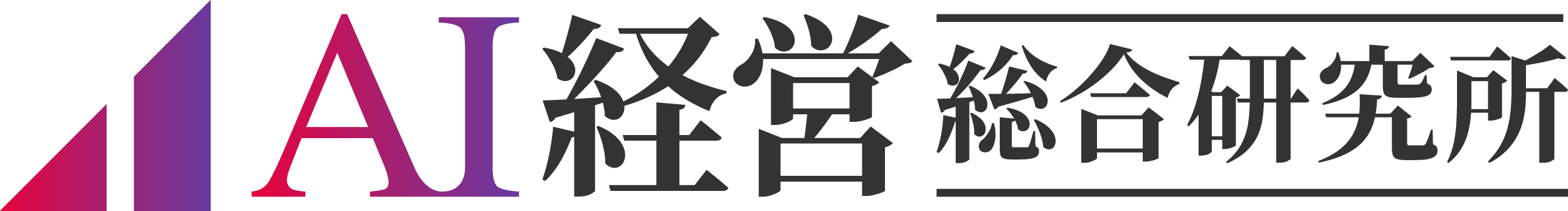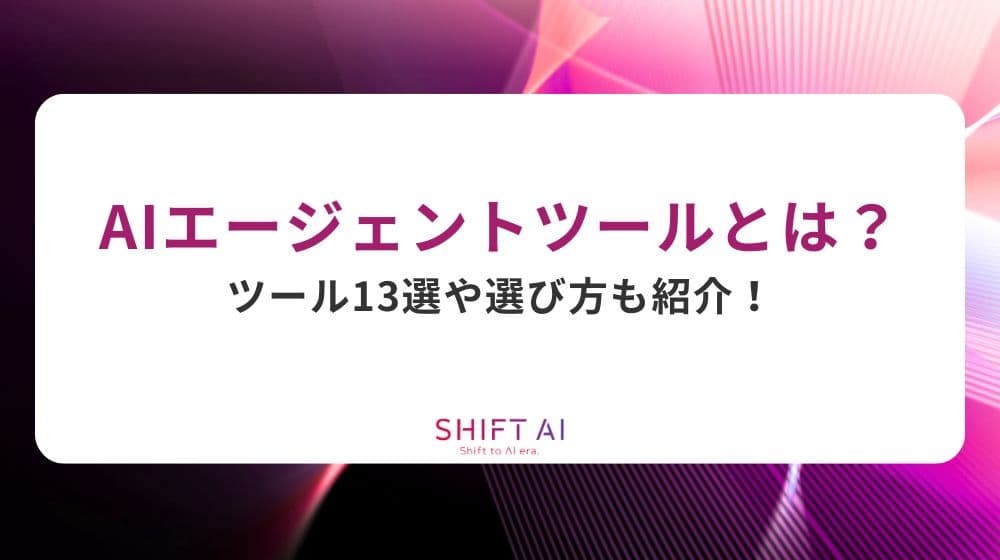業務の効率化やDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する中で、生成AIを活用した取り組みが急速に広がっています。なかでも注目されているのが「AIエージェントツール」です。
単なる質問応答型AIとは異なり、目的達成のために自律的にタスクを実行できるのが大きな特徴です。本記事では、AIエージェントの基礎知識から実際の活用シーン、導入メリットまでをわかりやすく解説します。
さらに、実務に役立つおすすめツール13選をタイプ別に紹介します。自社に合ったツールを見つけたい方、AI活用を一段深めたい方はぜひ最後までご覧ください。
また「自社ではどんな業務に使える?」「まず何から始めるべき?」とお悩みの方は、SHIFT AIの無料相談もご活用ください。導入設計から丁寧にサポートいたします。詳しく知りたい方は、下記のリンクからご確認ください!
\ 組織の実務力を底上げできる生成AI研修プログラム /
AIエージェントツールとは何か?

AIの進化により、単なる「質問に答える」だけでなく、「業務を任せられる」AIが登場しています。中でも注目を集めているのが、人の指示に基づき、自律的に業務を実行できる「AIエージェントツール」です。
この記事では、まず「AIエージェントとは何か?」を解説し、次にアシスタント型・自律型の違い、そして今なぜAIエージェントツールが注目されているのかについて紹介していきます。
そもそもAIエージェントツールとは
AIエージェントとは、人の指示に応じて、目的を達成するための行動を自動で考えて動くAIのことです。たとえば、「この商品について調べてまとめて」と頼むと、自分で検索し、情報をまとめてくれるようなイメージです。
このAIエージェントを、業務の中で使いやすいようにツールとして提供したものが「AIエージェントツール」です。パソコン操作やチャット対応、資料作成など、これまで人が行っていた作業をAIが代わりにこなしてくれます。
つまり「AIエージェントツール」とは、人のサポートをするだけでなく、業務を実行する能力を持った“働くAI”のような存在と考えるとわかりやすいでしょう。
アシスタント型と自律型の違い
よく耳にする「ChatGPT」も、広い意味ではAIエージェントの一種です。ChatGPTのように、質問に答えたり、文章を作ったりするタイプのAIは「アシスタント型」と呼ばれます。これは、1つの質問に1つずつ答えていくタイプのAIです。
一方、「自律型」のAIエージェントは、さらに進化しています。人が「このゴールを目指して」と伝えると、AIがタスクを自分で分解し、順番にこなしていくのです。目的に向かって複数の作業を自分で判断しながら進めるのが大きな特徴です。
ここでは、代表的なツールをいくつか紹介します。
| アシスタント型の例 | 自律型の例 |
| ・ChatGPT(OpenAI) ・Notion AI ・Bing Copilot(旧Bing Chat) | ・Auto-GPT ・AgentGPT |
ツールごとにできることや難易度が異なるため、自社の目的に合わせて選ぶことが大切です。
なぜ今、AIエージェントツールが注目されているのか
ここ数年で、「業務をもっと早く、正確にこなしたい」というニーズが一気に高まりました。背景にあるのは、人手不足・業務の複雑化・DX推進の必要性です。
従来のツールでは、一部の業務しか自動化できませんでした。しかし、AIエージェントツールは、複数の業務をまとめてこなすことができるのが強みです。たとえば、営業資料の作成や社内向けレポートの要約、問い合わせ対応など、「人が判断しながら進めていた作業」の代行が可能です。
これにより、少ない人数でより多くの仕事をこなしやすくなり、社員はより重要な仕事に集中できるようになります。こうした実務面でのインパクトがあるため、AIエージェントツールは今、多くの企業から注目されています。
AIエージェントツールの主なタイプと特徴

AIエージェントツールには、さまざまな種類があります。ここまでで「AIエージェントは業務をこなしてくれるAI」というイメージは持てたと思いますが、実は使い方やできることの幅によってタイプが分かれているのです。
ここでは、特によく使われている3つのタイプを紹介します。
アシスタント型
アシスタント型は、人からの問いかけに対して一つずつ答えるのが得意なAIです。たとえば、「議事録の要約を作って」「商品紹介文を書いて」などの依頼に対し、その場で回答を返してくれます。
代表的なツールとしては以下があります。
- ChatGPT(OpenAI):幅広い質問や文章生成に対応
- Microsoft Copilot:WordやExcelと連携して作業を支援
アシスタント型の特徴としては、対話形式で気軽に使えること、そして導入のハードルが低いことが挙げられます。日々の業務の「ちょっとした手間」を軽減したい場合に便利です。
自律型
自律型は、アシスタント型よりさらに進化したタイプです。こちらは、「○○を調べて、まとめて、資料にしておいて」といった複数ステップの作業も自分で分解して実行してくれます。
代表的なツールは以下の通りです。
- Auto-GPT:目標を設定すれば、自分で検索し、判断しながら処理を進める
- AgentGPT:ノーコードで自律型AIエージェントを作成できる
自律型の特徴は、人の手をほとんど借りずにタスクをこなしてくれることです。より本格的に業務を代行したい場面で力を発揮します。
ノーコード/ローコード対応型
AIエージェントツールの中には、「どのように作るか・導入するか」という構築・導入のしやすさに着目したタイプも存在します。ノーコード/ローコード対応型は、そうした分類のひとつです。
このタイプは、プログラミングの知識がなくても直感的な操作でアプリやツールなどを構築できます。たとえば、画面上で業務フローや回答パターンを設定するだけで、自社の業務に合ったチャットボットを簡単に作成できるのです。
代表的なツールは以下の通りです。
- Dify:生成AIを組み込んだ業務フローをGUIで設計可能
- Jitera:ノーコード/ローコード開発でAIアプリも簡単に構築可能
「AIを使いたいけれど開発までは難しい」という企業にとっては、これらのAIエージェントは専門人材に頼らず導入できる有効な選択肢といえるでしょう。
【タイプ別】おすすめAIエージェントツール

AIエージェントツールは、目的や業務領域によって選ぶべき製品が変わります。ここでは、「汎用業務」「特定業務」「開発・構築業務」の3タイプに分けて、実際におすすめできるツールを紹介します。
汎用業務におすすめのAIエージェントツール5選
まずは、幅広い業務で使える汎用性の高いAIエージェントツールです。
| ツール名 | 主な用途 | 特徴 |
| ChatGPT(OpenAI) | 会話型生成AI | 文章生成やアイデア出しに幅広く活用可能 |
| Notion AI | ドキュメント作成 | ナレッジ管理やチーム連携に最適 |
| Bing Copilot | 検索+要約 | 最新情報の収集に便利なWeb連携型 |
| You.com Chat | 検索+プライバシー重視 | 広告なしの多ソース検索が可能 |
| Claude | 要約・対話 | 安全性が高く、自然な会話が得意 |
それぞれのAIエージェントツールについて、より詳しく見ていきましょう。
ChatGPT(OpenAI):生成AI活用のスタンダード
ChatGPTは、文章生成・要約・翻訳・質問応答など幅広い用途に対応した対話型AIです。使い方は非常にシンプルで、テキストで質問や依頼をするだけです。
プロンプト(指示文)次第で柔軟に対応できるため、業務支援や企画アイデア出しにも活用が広がっています。
Notion AI:ドキュメント業務に強いAIアシスタント
Notion AIは、メモや議事録、企画書などの文書作成を自動化する機能を持つツールです。チームでのナレッジ共有やプロジェクト管理と組み合わせて活用することで、作業時間を大幅に短縮できます。
複数人で同時編集するような業務に特におすすめです。
Bing Copilot(旧Bing Chat):Web検索特化のアシスタントAI
Bing Copilotは、Web上の最新情報をリアルタイムで検索・要約し、質問に答えることができるAIツールです。インターネット検索に強く、調査・情報収集業務に向いています。
Microsoft Edgeと連携することで、Webブラウジング中でも気軽に利用できます。
You.com Chat:広告に左右されない検索連携型AI
You.com Chatは、プライバシー重視の検索型AIとして注目されています。広告や検索順位に左右されない中立的な情報取得が可能で、複数のWebソースを同時に横断検索可能です。
個人情報を気にせずに調査を行いたい企業や研究機関にも適しています。
Claude(Anthropic社):対話精度と安全性に優れたAI
Claudeは、自然な会話ができるだけでなく、誤解の少ない丁寧な回答ができることが特徴のAIです。セキュリティや倫理性も重視して設計されており、業務利用にも安心です。
長文の要約や、問い合わせ対応のドラフト作成などに適したツールといえるでしょう。
特定業務におすすめのAIエージェントツール4選
続いて、営業や人事、サポートなど、特定の業務領域に強いツールを紹介します。
| ツール名 | 主な用途 | 特徴 |
| LITRON Sales | 営業支援 | 商談の分析・要約を自動化。営業力を底上げ |
| リクルタ(Recruita) | 採用支援 | 面談記録や履歴書情報の自動管理に強い |
| VOC.AI | 顧客対応 | 顧客の声をリアルタイムで可視化・分析 |
| ServiceNow AI Agent | IT・CS支援 | IT・CS業務を広範囲にサポートする業務特化型AI |
それぞれのAIエージェントツールについて、より詳しく見ていきましょう。
LITRON Sales:営業力を底上げする会話分析AI
LITRON Salesは、商談の会話内容を自動で文字起こし・分析し、営業担当者の改善点や提案のヒントを可視化するツールです。
AIが重要なキーワードや反応を抽出するため、経験に頼らず営業力を強化できます。録音だけで振り返りや社内共有も簡単に行えます。
リクルタ(Recruita):採用担当者の業務を効率化
リクルタは、採用業務に特化したAIアシスタントです。面談の記録や履歴書の情報を自動整理し、候補者の比較や管理を効率化します。選考の進行状況や過去の評価も可視化できるため、採用ミスの防止や内定率の向上にも貢献します。
VOC.AI:カスタマーの声を活かすための分析AI
VOC.AIは、電話やチャットなどでやり取りした顧客の声をリアルタイムで分析するツールです。「どこに不満があるのか」「どう改善すべきか」をAIが自動で可視化してくれるため、カスタマーサポートや商品改善の場面で役立ちます。
ServiceNow AI Agent:社内外の問い合わせ対応を自動化
ServiceNow AI Agentは、社内ヘルプデスクやITサポートなどで寄せられる質問に対して、AIが自動応答するツールです。社員からの「パスワードを忘れた」「アカウント設定方法を教えて」といった定型的な問い合わせをAIが即時に処理します。
開発・構築業務におすすめのAIエージェントツール4選
最後に紹介するのは、AIを使った業務アプリやチャットボットなどの構築に役立つツールです。
| ツール名 | 主な用途 | 特徴 |
| Microsoft Copilot Studio | チャットボット構築 | Microsoft製品との統合が強みの開発ツール |
| Dify | ノーコード開発 | 業務用エージェントをGUIで簡単に構築可能 |
| Jitera | ローコード開発 | アプリ開発の高速化を支援するDXツール |
| Botpress | 自律型ボット開発 | 開発者向けの高機能なチャットボット構築ツール |
それぞれのAIエージェントツールについて、より詳しく見ていきましょう。
Microsoft Copilot Studio:Microsoft製品に特化した開発支援AI
Microsoft Copilot Studioは、Microsoft製品と連携してチャットボットや業務支援フローをノーコードで作れる開発ツールです。IT部門だけでなく、現場部門でも扱いやすく、社内業務の自動化や問い合わせ対応に活用されています。
Dify:ノーコードで業務特化AIを構築可能
Difyは、文章作成・情報抽出・回答生成などの機能を組み合わせて、AIエージェントを自作できるノーコードツールです。
パソコンやスマートフォンなどの画面上で、アイコンやボタンなどのグラフィックを使って直感的に操作できます。そのため、エンジニア以外の人でも業務に合わせたAIワークフローを構築できます。社内業務の効率化に最適です。
Jitera:業務アプリの高速構築を支援
Jiteraは、Webアプリや業務ツールの開発を高速化できるローコード/ノーコード開発ツールです。UI設計やデータベース連携も自動で行えるため、非エンジニアでも複雑なアプリを短期間で構築可能です。
AIと組み合わせて社内業務のDXを推進できます。
Botpress:開発者向けの自律型チャットボットプラットフォーム
Botpressは、会話の流れやユーザーの入力内容に応じて柔軟に応答できるチャットボットを開発できるオープンソースツールです。カスタマイズ性が高く、自然言語処理(NLP)機能も備えています。
より本格的な社内AIチャットボットを構築したい開発者の方におすすめです。
AIエージェントツール選びで気をつけたい4つのポイント
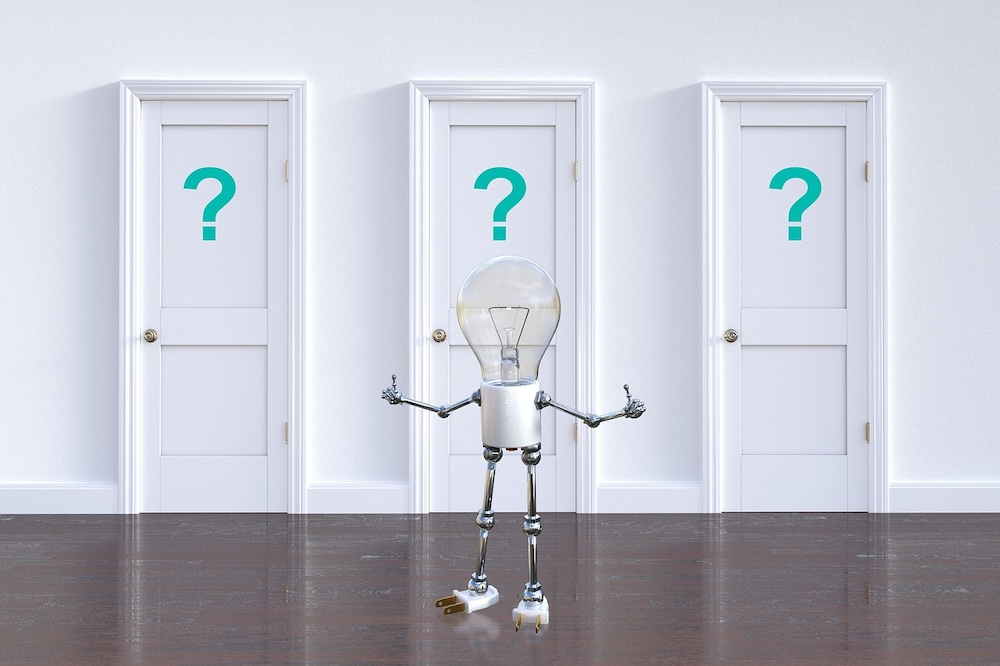
AIエージェントツールは数多くありますが、「なんとなく便利そう」という理由だけで選ぶと、使いこなせなかったり、現場に合わなかったりすることがあります。ここでは、失敗しないために押さえておきたい4つの選定ポイントを紹介します。
自社業務との相性を見極める
AIツールは見た目の使いやすさや豊富なテンプレートだけで選ぶと、あとで「現場の業務と合わなかった」と後悔することがあります。
導入前には、自社の業務フロー(仕事の流れ)とどれくらいフィットするかをしっかり確認しましょう。実際に現場で使う人の意見を聞くことも大切です。
導入・運用体制の整備がカギ
AIエージェントツールは、導入して終わりではありません。うまく活用するには、操作を覚える担当者の育成や、継続的な運用体制の整備が重要です。
特に、社内にIT担当者が少ない場合は、サポート体制が整ったツールを選ぶと安心です。また、週に一度のツール活用会議を設けたり、ITリテラシーの高い社員をAI人材に任命したりするのも効果的でしょう。
セキュリティと社内データ連携の可否
クラウド型のAIツールを使う場合、情報漏洩や外部アクセスのリスクがないかを事前に確認する必要があります。また、社内システムとAIを連携させる予定があるなら、技術的に連携できるかどうかも重要なチェックポイントです。
セキュリティチェックでは「データはどこに保存されるのか」「日本語でのプライバシーポリシーは整備されているか」なども事前に確認しておきましょう。
無料トライアルやPoCでリスクを減らす
導入前にいきなり契約するのではなく、無料トライアルやPoC(Proof of Concept:概念実証)を活用することで、実際の業務に合うかどうかを少ないリスクで確認しましょう。小さな単位から試して、効果や使い心地を確かめてから本格導入するのがおすすめです。
PoCでは、「実際の業務においてどの程度自動化できるか」「操作性に不満はないか」など、定量・定性の観点で評価項目を設定することをおすすめします。
まとめ:AIエージェントで業務変革を加速させよう
AIエージェントツールは、日常業務から専門業務まで幅広く活用でき、働き方そのものを変える力があります。まずは小さな業務から導入し、自社に合ったツールを見極めることが成功の第一歩です。
AIを味方につけることで、これからの業務はもっとスマートに、もっと戦略的に変わっていくでしょう。
自社の業務にフィットするAIエージェントをお探しの方は、SHIFT AIの導入支援サービスをご検討ください。テンプレート設計から運用支援まで、一気通貫でサポートいたします。SHIFT AIについて詳しく知りたい方は、下記のリンクをご確認ください!
\ 組織の実務力を底上げできる生成AI研修プログラム /