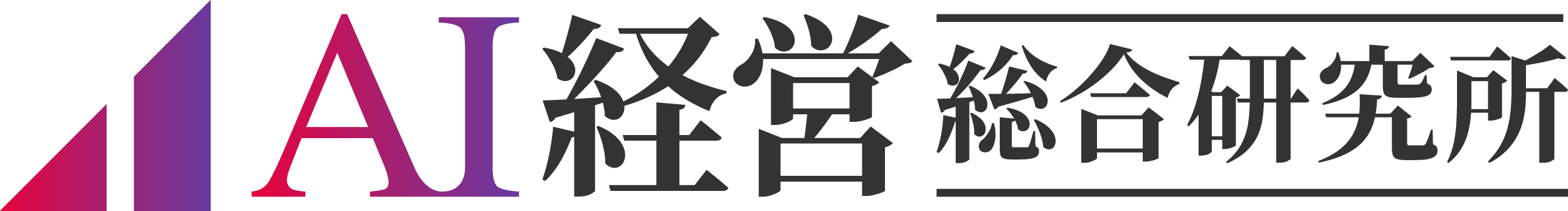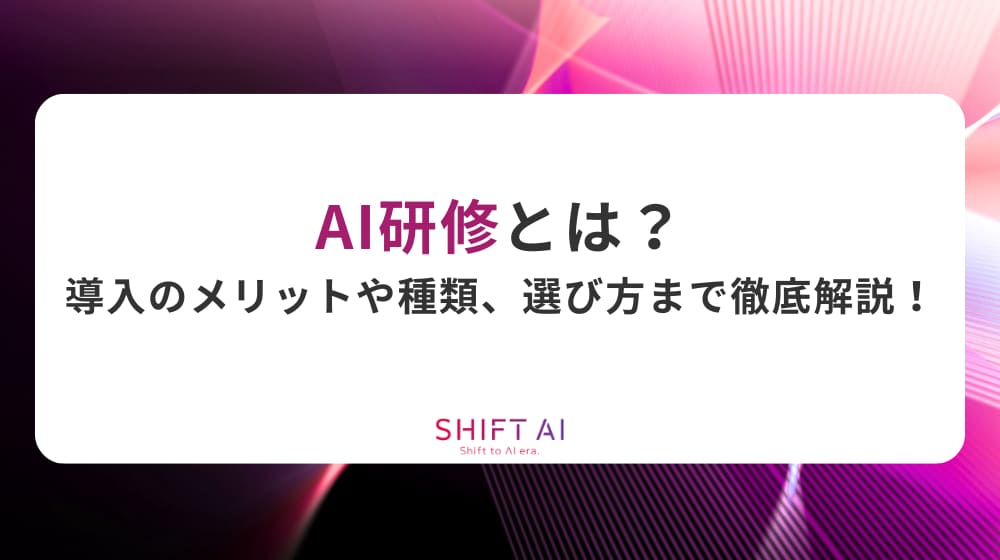現在、多くの企業がAIの活用を進めています。そんな中、AIの知識や技術力を身につけられるAI研修が注目されています。実際に多くの企業が利用しており、今後もこの流れは加速するでしょう。
しかし、「AI研修で何を学べるのだろう」「研修を受けて日々の業務に役立つのだろうか」と疑問に感じる方もいると思います。
そこで、この記事ではAI研修で学べる内容やメリット、うまく活用するコツを解説します。
実際にAI研修を活用して成功した企業事例も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
SHIFT AIでは、AI研修サービスを実施しています。AIの使い方が学べるeラーニングコンテンツやワークショップを提供しており、従業員がAIスキルを身につけるのに最適な内容となっています。AI活用についての無料相談も実施していますので、興味のある方はぜひお問い合わせください。
\ 組織の実務力を底上げできる生成AI研修プログラム /
AI研修とは?

AI研修は、その名前のとおり、AIについてレクチャーするサービスです。AIの使い方などの基礎知識から、プログラミングなど専門知識まで幅広い内容を学べます。受講することでAIの知識を体系的に習得できるでしょう。
AI研修はオンラインで利用できる場合が多く、Zoomなどで参加するサービスが一般的です。また、ただ講義を受けるだけではなく、質疑応答ができたり、課題が与えられたりするなど、学校の授業に近い形式のサービスもあります。
AI研修が注目される背景

AI研修は、企業のAI導入の加速を背景に注目を集めています。
近年、業務効率化やコスト削減などの目的でAIを導入する企業が増えており、AIを正しく理解し、ビジネスに応用できる人材の育成が急務となっています。しかし、AIに関する知識やスキルを持つ人材はまだまだ不足しています。また、社内にAIに詳しい人材がいたとしても、知識をしっかりと教えるためにはナレッジ共有のノウハウや労力が必要になり、ハードルが高いです。
そのギャップを埋める手段として「AI研修」が注目されています。従業員に体系的に知識を学んでもらい、スムーズに導入を進めるために活用されているのです。
また、経営層のAIに対する理解促進のニーズもAI研修の導入を後押ししています。AIの導入に興味があっても、そもそもAIでなにができるのか、どんな効果があるのかなどの基礎知識がなく、導入するか判断できずにいる企業は少なくありません。そこで、経営層が研修で知識を身につけ、AIの導入の可否を正確に判断するために利用するケースが増えています。
AI研修の主な種類

AI研修と一口にいっても、受講対象や目的によってその内容は大きく異なります。ここでは、代表的な4つの研修タイプを紹介します。
初心者向け研修
まず一般的なのが、AIに初めて触れる人向けの研修です。
AIとは何か、どのように使われているのかといった基本的な知識を学び、生成AIや機械学習の概念、活用事例などを通じてリテラシーを高めます。社内全体のAI理解を底上げするために、活用されることが多いです。また、経営層の理解促進に利用されるケースもあります。
サービスによって異なりますが、研修期間は短いことが多いです。1日で終わるものから、長くても1ヶ月ほどのものが一般的でしょう。
実務者向け研修
より応用的な知識を学べる研修もあります。
この研修では、AIの基礎知識はもちろん、専門知識がすでにあるエンジニアやデータサイエンティストといった実務担当者向けの内容になっています。データ分析の基礎やPythonの基礎プログラミング、機械学習モデルの活用方法など、より実践的な内容が中心となるのが一般的です。
AIを活用するというよりも、開発から進めたい場合に有用な研修だと言えるでしょう。社内でAIの専門家を育成する際にも用いられます。
学ぶ内容にもよりますが、研修期間は長くなる傾向にあり、数ヶ月から1年ほどかかるのが一般的です。
管理職・経営層向けの研修
より経営視点にフォーカスした研修もあります。
AIやDXの導入戦略、社内推進の課題、リスクマネジメントなど、AI導入の進め方や組織づくりに焦点を置いた内容になっています。
AIの導入方法を学び、うまく活用できる体制を整えたい企業に向いているでしょう。
業界別の研修
業種ごとに異なる課題やニーズに対応した研修も展開されています。
例えば、製造業では需要予測や異常検知、金融業では不正検知やリスク評価、小売業では在庫管理や顧客分析など、業務に直結したAI活用スキルを習得できます。
研修内容はこの4種類にきれいに分かれていることもあれば、組み合わせられている場合もあります。自社の目的や人材育成の方針に合わせて最適なプログラムを選ぶことが重要です。
AI研修を導入するメリット

AI研修を導入することは、単なる人材育成にとどまらず、企業全体の競争力強化につながります。ここでは、特に注目すべき4つのメリットを紹介します。
- AI導入の土台づくりができる
- 業務効率化につながる
- 経営層が正確な意思決定をできる
- 知識を短期間で効率よく学べる
- AI活用の実例を知ることができる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
AI導入の土台づくりができる
まず大きなメリットがAI導入を進めやすい組織づくりができることです。
AI研修を通じて社員一人ひとりがAIの基本的な考え方や活用方法を理解することで、活用が進みやすくなります。AIをどう仕事に活かせばいいかわかるので、現場では積極的に活用が進むはずです。また、サービスによっては導入が進みやすい組織づくりについても学べます。よりAIを効率よく浸透させられる組織を作れるでしょう。
AI研修は単なるシステム導入にとどまらず、組織文化そのものを変える第一歩となります。
業務効率化につながる
業務効率化そのものにつながるのもAI研修のメリットです。
AIリテラシーが身につけば、使い方が自然と分かるようになります。データ処理や定型業務の自動化、予測分析などが可能になるでしょう。
例えば、書類の大枠をAIに作らせたり、議事録を自動で生成したりなど、日々の業務の補助役として使えるようになるはずです。AIで業務効率化が実現すれば、労働時間や労働負担が減らせます。煩雑な業務をAIに任せて、取引先との交渉や経営戦略の立案など、より重要性が高くクリエイティブさが求められる業務にも集中しやすくなります。
また、労働時間が減ることで、人件費のカットにもつながるでしょう。
このように、AI研修で従業員がリテラシーを身につけ、実務での活用が進めば、さまざまな面で業務効率化が実現します。
経営層が正確な意思決定をできる
経営層がAI導入をするかを的確に判断できるのもいい点です。
経営層向けのAI研修では、AIの仕組みや導入時のリスク、他社事例などを学ぶことができるため、より現実的で戦略的な判断が可能になります。自社でAIを導入して効果が見込めそうか、どう導入すればいいかを理解しやすくなるでしょう。また、AIについて今後の動向やトレンドを察知して、適切に経営方針を決めやすくもなるはずです。
AIを導入すべきかわからず判断が停滞する、導入したのに思っていた効果を得られなかったという事態を防げるでしょう。
加えて、経営層がリーダーシップを発揮することで、より従業員から導入の理解を得られやすいはずです。目的やメリットを的確に説明できれば、従業員も納得感をもって活用を進めやすくなります。
知識を短期間で効率よく学べる
知識を素早く習得できるのもAI研修の良さです。
体系的に整理された研修プログラムを活用することで、基礎から応用までを短期間で効率よく学ぶことができます。特に、基礎知識を網羅的に学べることは、闇雲に学習を進めてしまうリスクを減らしてくれます。また、短期集中で知識を学べれば、学習意欲も低下しづらくなるため、知識も定着しやすいでしょう。
リソースの圧迫を防げるのもメリットだと言えます。AIは専門性が高く、従業員が独学で学ぶのは難しい側面があります。また、社内のAIに詳しい人が勉強会を開く場合でも、リソースを圧迫することに加え、頻繁には開催できないでしょう。そういったリスクや手間を省き、効率よく知識を学べるのは大きな魅力です。
AI活用の実例を知ることができる
AI活用の実例を詳しく知れる点もよさだと言えるでしょう。
サービスによっては、支援した企業や公表されている事例を整理して伝えてくれます。自社に似た業種や業態の企業の実例は、導入方法や組織づくりで参考になる点が多いはずです。また、AI活用の実践的なノウハウも学べるため、より実務に活かしやすくなるでしょう。
AI研修の成功事例3選

実際にAI研修を取り入れる企業は増えており、効果も現れています。ここでは、AI研修を有効に活用した企業を紹介します。
ソニー株式会社|4万人を対象としたAIリテラシー研修
日本を代表する大手企業のソニーでは、半導体やゲーム事業に関わる従業員を対象にAI研修を実施しました。
研修は動画を視聴するeラーニングの形で進められ、AI活用の考え方や学習方法など基礎知識がメインの内容になっています。この取り組みにより、技術職・事務職を問わず社員のAIスキルを底上げし、各事業部門でのAIの実践的な活用が進められています。実際に、製品やサービスでAIの活用が広がる結果となりました。
出典:ソニーG、社員4万人にオンラインでAI研修 – 日本経済新聞
東急不動産株式会社|AI研修で活用が加速
東急不動産株式会社はラインヤフー株式会社が提供するAI研修サービスを利用しました。従業員は研修を通して、AIの使い方や機能など基礎的な知識を学びました。
その結果、社内報やイベント関連の文章作成にAIが活用され、業務負担軽減につながっています。また、会議の議事録もChatGPTで作成することが増えるなど、さまざまな場面で活用が進んでいます。
研修でAIの知識が身についたからこそ、活用が進んだ事例だと言えます。
出典:生成AI活用で”新しい価値を創造する力”を育む「AI活用アカデミア」
ダイキン工業株式会社|社員が専門知識を学べる環境を整備
ダイキン工業株式会社はAIの専門知識を深く学べる「ダイキン情報技術大学」をスタートさせました。研修内容は大阪大学と連携しながら作成され、基礎知識から大学院レベルの深い知識まで学ぶことができます。
今まで1,500名以上の従業員が受講しており、事業企画部門などで活躍しています。将来的にはAI開発を担う中核の人材も育てていく方針です。
研修を内製化し、専門知識まで習得したAI人材を育成したいい事例です。
出典:デジタル時代における製造業の変革~ダイキン情報技術大学におけるAI人材の育成と卒業生の活躍
このように、AI研修は幅広い企業で実施されており、リテラシーが身につくことでAIの活用が進むのがわかります。
おすすめのAI研修サービス5選

続いて、実際に提供されているAI研修サービスを5つ紹介します。実績があり、内容の充実したものをまとめたので参考にしてみてください。
- SHIFT AI|社員のリテラシー底上げやコンサルを実施
- AVILEN|実務に即した生成AI研修が強み
- Aidemy Business|Python・AI実装の研修に強い
- SIGNATE Academy|AI人材の実務教育に特化
- Schoo for Business|リテラシー向上に最適な動画学習
それぞれの特徴を把握して、自社に最適なサービスを選びましょう。
SHIFT AI|社員のリテラシー底上げやコンサルを実施
SHIFT AIでは、法人向けにAI研修サービスを提供しています。中小から大手企業まで導入されており、今まで10,000名以上が利用してきた実績があります。
研修では、AIの基礎知識から使い方やメリットなど、AIを企業で活用するのに必要な知識を幅広く学べます。ChatGPTやCopilotなどのツールの使い方も学習でき、実務にすぐ活かせることも強みです。また、eラーニングとワークショップを組み合わせた形式で提供されており、適時質問などもできるため、しっかりと知識が身につくでしょう。
経営層や従業員のリテラシーを上げてAI活用が進みやすい環境を整えたい、そもそもAIを導入するか判断したい、といった場合に便利なサービスです。コンサルティング支援も実施しており、AI導入に関する悩み事や不安も解決しやすいことも強みです。
AVILEN|実務に即した生成AI研修が強み
AVILENは、企業向けに幅広いAI・DX人材育成プログラムを提供するサービスです。特に近年注目されている生成AI分野の研修に強く、ChatGPTの活用法やプロンプトエンジニアリング、Copilot for Microsoft 365の実践的使い方まで学べるコースを展開しています。
研修は、eラーニング・OJT・アイデアソンなどの形式で実施され、業務への即時応用が可能。全社員向けから開発者・企画担当者向けまで、幅広い階層に対応しているのも魅力です。
Aidemy Business|Python・AI実装の研修に強い
Aidemy(アイデミー)は、AIの開発や実装を実務で行う人材の育成を得意とする研修サービスです。Python、データ分析、機械学習など、より専門的な内容が充実しており、エンジニア職やデータサイエンティスト志望者向けの教育に最適です。また、AIの使い方など基礎的な内容の研修も受けられます。
カスタマイズ性も高く、企業の業務内容に即した実践的カリキュラムの設計が可能。基礎から応用まで幅広く対応しており、DX人材育成の中核を担うサービスとして高く評価されています。
SIGNATE Academy|AI人材の実務教育に特化
SIGNATE Academyは、ビジネス現場で活躍できるAI人材を育成することを目的としたサービスです。オンライン学習に加え、AIプロジェクトの実践経験を積めるコンテンツが充実しており、知識の定着と現場応用を両立できます。
経済産業省の「第四次産業革命スキル習得講座」にも認定されており、教育の質や社会的信頼性が高い点も魅力。AIエンジニア・データサイエンティスト育成を本格的に進めたい企業におすすめです。
Schoo for Business|リテラシー向上に最適な動画学習
Schoo(スクー)は、ビジネスパーソン向けに動画で学ぶオンライン研修サービスを展開しており、AIリテラシーやDX基礎の講座も充実しています。全社員の底上げを目的としたリスキリング研修に向いており、AIの専門知識がない従業員にも受け入れられやすい内容となっています。
社内での継続的な学びの文化を築くために最適で、月額定額制でコストパフォーマンスにも優れています。
AI研修の選び方と比較ポイント

AI研修を成功させるためには、「どの研修を選ぶか」が非常に重要なポイントです。優れた研修プログラムであっても、自社の課題や目的に合っていなければ、十分な成果を上げることは難しいかもしれません。ここでは、AI研修を比較・検討する際に押さえておきたい4つの主要なポイントについて、詳しく解説します。
カリキュラム内容を確認する
まず最も重要なのが、カリキュラムの内容です。
前の見出しで触れたように、AI研修の内容はサービスによって異なります。自社の目的に合いそうな内容であるか、しっかり確認しておきましょう。サービスのWebサイトなどをチェックしつつ、実際に問合せをしておくと安心です。また、サービスによってはカリキュラムを柔軟にカスタマイズできるところもあるため、組み合わせられる内容も聞いておくといいでしょう。
上記に加えて、実務に直結する演習が含まれているかも注目したいポイントです。座学を学ぶだけでも効果はありますが、演習が含まれているとより実務に応用しやすくなります。
研修受講後のサポート体制も把握しておくのが望ましいでしょう。研修後に、担当者に質問できたり、AI導入のコンサルを受けられるサービスもあるため、確認しておくと効果的です。
費用対効果を見極める
研修の費用を把握しておくことも重要です。
AI研修の費用は、1回数万円のeラーニング形式から、数十万円を超えるカスタマイズ型プログラムまで多岐にわたります。会社の予算と照らし合わせて、コストオーバーを防ぎましょう。
予算を試算する際には、料金体系にも注目しておきたいです。研修1回ごとに料金が発生する場合もあれば、月ごとに料金がかかることもあります。また、研修を受ける従業員が増えるに伴って、金額が加算されていくケースも珍しくありません。事前に問い合わせるなどして、費用を概算してもらうのが望ましいでしょう。
また、価格に含まれている内容も知っておきたいポイントです。サービスによっては、事後フォローやコンサルティング支援などは別料金になることもあるので、確認しておきましょう。
研修の提供形式
研修の形式も確認しておきましょう。
AI研修はオンラインで実施されるものと対面のものの2種類に大きく分かれます。オンラインの研修は、インターネット環境さえあれば従業員のいる場所を問わずに利用しやすいです。拠点が複数ある、出張などで移動する従業員が多いといった企業にとっては非常に便利でしょう。
一方で、対面研修ならではのメリットもあります。たとえば、グループワークやワークショップによる相互学習、講師との双方向のコミュニケーション、即時の質疑応答など、臨場感ある学習体験ができるのは対面ならではです。
最近では、ハイブリッド形式(録画+リアルタイムのQ&Aやグループセッション)を提供する研修も増えています。また、オンラインでのレクチャーに加えて、映像授業のように録画コンテンツを視聴するものもあります。
それぞれの形式の特徴を把握した上で、自社に合うものを選びましょう。
研修期間とスケジュールの柔軟性を確認する
研修のボリュームや期間も重要な比較ポイントです。
記事内で触れた通り、研修期間はサービスによって異なります。研修期間が長くなるほど学べる内容も増えますが、従業員のリソース確保やモチベーション維持も考えなければなりません。従業員とも相談しながら、最適な長さで研修を終えられるようにしましょう。
また、AI研修は業務と並行して受講することが多いため、受講可能な時間帯やペース(オンデマンド配信、週末集中など)に対応しているかも大きな判断基準になります。
AI研修を受ける際の注意点

続いて、AI研修を受ける際の注意点を解説します。
- 社内の理解と推進体制を整えておく
- 受講者のレベルに合ったものを選ぶ
- 業務との両立をできるようにする
ポイントを抑えて、より成果を出せるようにしましょう。
社内の理解と推進体制を整えておく
AI研修を効果的に機能させるためには、まず経営層やマネジメント層の理解と協力が不可欠です。現場任せにせず、企業としてなぜAI研修を実施するのか、どのような効果を期待しているのかを明確にし、社内で共有しておく必要があります。目的や意義が分からないまま受講してしまうと、研修に身が入らず効果が薄れてしまうため、従業員へ説明する場を設けましょう。
また、研修を一度きりで終わらせず、継続的な学びにつなげる体制づくりも重要です。たとえば、社内で研修後に成果を発表する場を設けたり、習得した知識を現場業務に活かすプロジェクトを設定したりすることで、学んだことが定着しやすくなります。
従業員のレベルに合ったプログラムを選ぶ
従業員のAI知識に合わせて研修を選ぶことも大事です。
たとえば、AIに初めて触れる人にいきなりPythonの実装研修を受けさせても、挫折する可能性が高くなってしまいます。一方で、すでに一定のデータ活用スキルがある人には、基礎的すぎる内容では物足りなさを感じてしまうでしょう。
理想的なのは、事前に簡単なスキルチェックやヒアリングを行い、レベルに応じて研修をカスタマイズすることです。最近では、個々の理解度に合わせたeラーニングやオンデマンド形式も充実しているため、柔軟な設計ができるでしょう。
業務との両立を前提に計画する
AI研修の効果を最大化するには、業務と両立させられるようにする必要があります。
多くの企業では研修中も日常業務が並行して進行するため、研修を詰め過ぎるとリソースが圧迫され負担が増えてしまいます。研修内容も身につきづらくなる可能性があるため、余裕を持って研修を受けられる環境を整えましょう。
例えば、業務の繁忙期は避けてなるべく閑散期に研修を短期集中でスケジュールすることが考えられます。また、研修を受ける従業員の業務量を減らすなど、リソースを空ける対策も有効でしょう。日時や社員ごとのスケジュール調整が柔軟にできる研修を選んでおくことも効果的です。
研修をただ受けさせるのではなく、負担がなるべく増えない形で受講を進められるように気をつけましょう。
まとめ:AI研修を利用してAI活用を進めよう
AI研修で、AIの使い方や機能などの基礎知識や深いレベルの専門知識を学べます。
従業員のリテラシーが向上し、現場での活用がスムーズに進むはずです。ゆくゆくは、業務効率化やコスト削減などの経営最適化につながるでしょう。
また、そもそもAIを活用するかどうかを判断するためにも、AIの効果や機能を知っておく必要があります。そういった点からも、体系的に知識を学べるAI研修は有意義です。
まずは、社内の一部の部署で基礎研修から実施し、AIが役立ちそうか確かめてみるといいでしょう。
SHIFT AIではAI研修を実施しています。eラーニングとワークショップを組み合わせた形式になっており、AIの使い方や導入方法などの基礎知識を学ぶことができます。AIの導入を判断したり、従業員のリテラシーを向上させたりするのに最適な内容です。
無料相談を実施していますので、興味のある方はぜひお問い合わせください。
\ 組織の実務力を底上げできる生成AI研修プログラム /