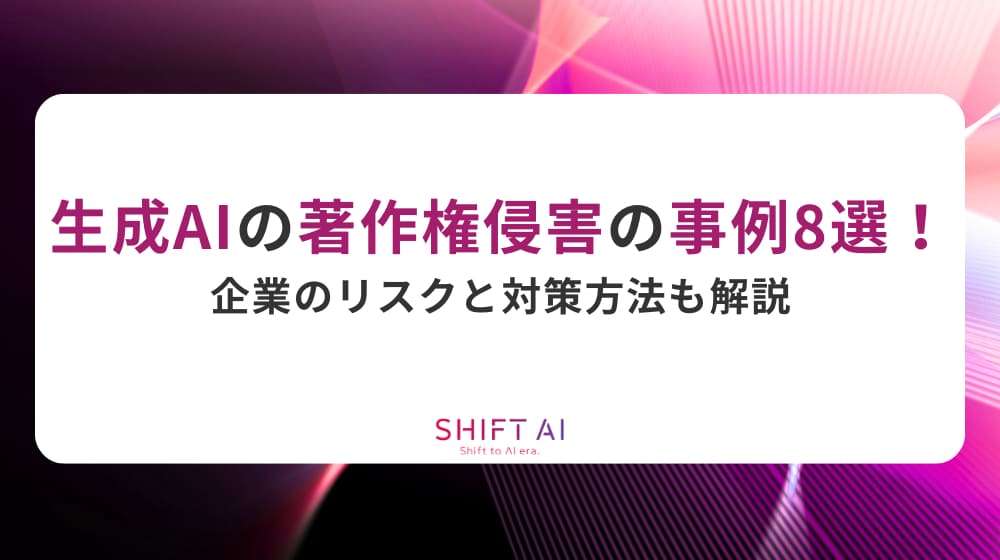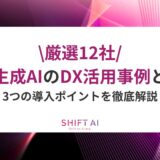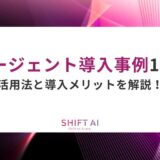生成AIの普及に伴い、ビジネスやクリエイティブな現場での活用が加速しています。一方で注目されているのが、著作権侵害のリスクです。
AIが既存の著作物を学習・生成に利用する過程で、知らず知らずのうちに他者の権利を侵害しているかもしれません。
そこで本記事では、企業が生成AIを導入・活用する際に知っておくべき著作権侵害の事例やリスク、トラブルを未然に防ぐためのポイントも詳しく解説します。
生成AIに関する正しい知識が不足している状態で業務に取り入れてしまうと、落とし穴に陥るケースも発生しています。代表的な失敗パターンから学ぶことで、生成AI導入を成功に導くために必要な知見を得られる資料を用意したので、以下のページも合わせてご覧ください。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
生成AIと著作権の基礎知識
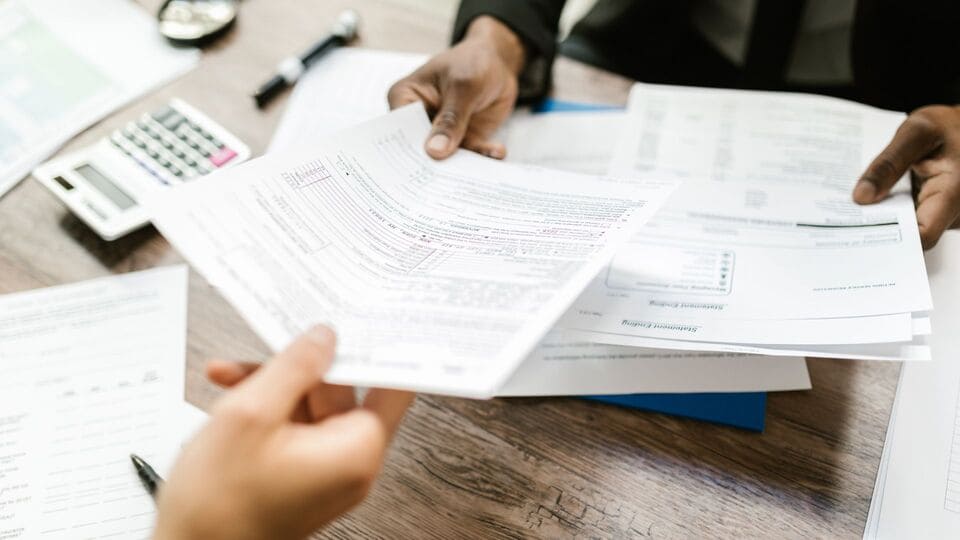
生成AIがどんどん進化する中で、著作権に関する理解が不可欠となっています。AIの特性と著作物の定義を正しく把握することは、ビジネスにおけるリスク回避の第一歩となるでしょう。
ここでは、生成AIの基本的な考えから、法律で保護される著作物の条件、そしてAIが生成したコンテンツの権利を紹介します。
そもそも生成AIとは?
生成AIとは、既存のデータから学習し、新たなコンテンツを創出する人工知能技術です。大量のテキストや画像、音声などのデータを分析して、パターンやルールを見出し、それに基づいて人間が作成したかのような新しいコンテンツを生み出します。
ChatGPTやDALL-E、Midjourneyなどが代表例で、ユーザーの指示(プロンプト)に応じて文章を書いたり、画像を描いたりできます。最近では、GoogleがGeminiやImagenといった高度な生成AI技術の開発に注力しています。特にGeminiはマルチモーダル対応で、テキストや画像、音声を横断的に理解・処理できる次世代AIとして注目されました。
従来のAIが情報の分類や検索など特定のタスクに特化していたのに対し、生成AIは創造的な作業をサポートするところが特徴です。
著作権とは?守られる対象と期間
著作権とは、創作された著作物に対して、創作者(著作者)が持つ権利のことです。文学や音楽、美術、写真、映画、プログラムなど、思想や感情を表現した創作物が対象となり、他人に無断で使用されないよう法的に保護されます。
また、著作権は原則として著作物が創作された時点で発生し、著作者の死後70年(法人著作物は公表後70年)まで守られるため、長期にわたり著作者の権利を保護できる制度となっています。
著作物とは何か
著作権法では、著作物を「思想または感情を創作的に表現したもの」と定義しています。これは具体的に何を意味するのでしょうか。
まず、著作物は、人間の思想や感情から生まれたものでなければなりません。そのため、AIが自動生成したコンテンツや動物が偶然作り出したものは、著作物に含まれません。次に創作性が求められ、芸術的な価値ではなく作者の個性が少しでも表れていることを意味する必要があります。子どもの絵や作文は立派な著作物です。
一方で、名画の模写や「こんにちは」のような誰が書いても同じになる表現は、創作性が認められません。さらに、アイデアや概念だけでは保護されず、具体的な表現形式になって初めて著作物となります。
生成AIが出力したコンテンツに著作権はあるのか?
AI生成物が著作物にあたるかどうか、またその著作者が誰になるのかは、まだ明確には定まっていません。議論の段階にあり、専門家によっても判断が分かれています。
著作権が発生するかどうかは、AIを用いたという事実だけではなく、「人の創作意図」と「創作的寄与」の有無によって判断されます。創作意図とは、思想や感情をある成果物として表現しようとする目的や意思を指します。AIに命令を出すだけでなく、どのような表現を目指すか、どのような内容を持たせるかなど、作者が主導して意思決定を行っているかが必要です。
一方で、創作的寄与は、生成された結果に対して人がどの程度関係性を持ち、独自性や創造性を加えているかという点が問われます。例えば、AIに入力するプロンプトの内容を詳細に決めたり、生成された結果を選別・修正・編集したりすることで、著作者として認められる可能性が生まれます。
反対に、AIに丸投げして自動的に生成されただけのコンテンツは、著作物とみなされず、著作権保護の対象外となる可能性があるため注意しなくてはなりません。
出典:文化庁|AIと著作権
企業で実際にあった生成AIによる著作権侵害の事例8選

ここからは実際に著作権侵害として訴訟問題となったケースを8選紹介します。日本だけではなく海外の事例もまとめましたので、参考にしてみてください。
- 中国の画像生成AIが「ウルトラマン」を生成し、著作権問題に発展
- 大手テック企業がYouTube動画をAI学習に利用していた問題
- 声優がAIスタートアップを音声無断使用で提訴
- ニューヨーク・タイムズがOpenAIとMicrosoftを著作権侵害で提訴
- アメリカ作家協会らがOpenAIを著作権侵害で提訴
- 生成AIによる「検索連動型回答」で著作権侵害の恐れ
- 学校のフリーイラスト素材の誤認による著作権侵害
- Getty ImagesがStablity AIを著作権侵害で提訴
なお、AIと著作権侵害に関する訴訟は判決が出ておらず、議論が継続しているものが多いです。それらも含めて紹介していますので、どんな内容で訴訟が起こされているか参考にしてみてください。
中国の画像生成AIが「ウルトラマン」を生成し、著作権問題に発展
2024年4月15日、中国の広州インターネット法院は生成AIによる著作物侵害を認める判決を下しました。裁判所はAIサービス提供事業者に対し、ウルトラマンに酷似したキャラクター画像を許可なく生成させたことによる著作権侵害責任を認め、損害賠償と生成停止を命じたのです。
この判決は、AIが生成したコンテンツにおける法的責任を明確にした重要な先例となります。特に日本のコンテンツ産業にとっては、自社キャラクターの権利保護という観点から大きな意味を持つケースとして注目されました。
海外の事例ではありますが、生成AIで作り出した画像が誰かの著作物に酷似している場合、トラブルにつながることを示す例だと言えるでしょう。
大手テック企業がYouTube動画をAI学習に利用していた問題
Proof NewsとWiredの共同調査により、AppleとAnthropic、Nvidia、Salesforceなどの大手テック企業が、17万本以上にわたりYouTube動画の字幕データをAIトレーニングに利用していたことが明らかになりました。
これらの企業は、直接YouTube動画を収集したわけではなく、非営利団体EleutherAIが公開した「The Pile」というデータセットを経由して利用していたということです。
この問題についてYouTubeのCEOは、「明らかな違反」と指摘しており、コンテンツ利用に関する新たな議論を引き起こしています。Salesforceは利用を認めつつも「公開データの使用」と主張し、NvidiaとAppleは明確なコメントを避けています。
この生成AIの使い方が著作権侵害になるかは不透明ですが、生成AIでトラブルを起こすと、社会的評価や印象が悪くなりかねないと言える事例です。
出典:AppleやAnthropicがYouTubeの文字起こしをAIトレーニングに無断で使用との報道
声優がAIスタートアップを音声無断使用で提訴
声優のポール・スカイ・レアマンとリネア・セージの両氏がAIスタートアップのLOVO社に対し、声の無断使用、虚偽広告を理由に集団訴訟を起こしました。当初、レアマン氏は「学術研究目的」と説明され録音に協力したものの、のちに自分の声が商用コンテンツで無断利用されていることを発見したからです。
特にYouTubeチャンネルやポッドキャストでの無許諾使用が問題となり、レアマン氏は仕事の約50%減少と評判低下の被害を訴えています。
SAG-AFTRAの法律顧問は「声に関する権利への理解不足」から同様の問題が増加すると警告しています。この事例は、AI音声複製技術の発展に法整備が追いついていない現状を浮き彫りにし、パブリシティ権の新たな課題を提起しました。
出典:声優が音声の悪用でAIスタートアップを集団提訴【米国】
アメリカ作家協会らがOpenAIを著作権侵害で提訴
「ゲーム・オブ・スローンズ」原作者のジョージ・R・R・マーティン氏や、ベストセラー作家ジョン・グリシャム氏を含む複数の著名作家は、OpenAIに対して著作権侵害訴訟を提起しました。
訴状では、ChatGPTの学習過程において彼らの文学作品が無断で使用されたと主張しています。この訴訟にはジョナサン・フランゼン氏、ジョディ・ピコー氏、ジョージ・ソーンダーズ氏など文学界の重鎮も参加しており、生成AI開発における著作権問題の法的なテストケースとなっています。
作家たちが主張している核心は、ChatGPTなどの大規模言語モデル(LLM)が、彼らの創作物を許可なく学習データとして取り込み、商業利益を得ていることにあります。
これに対しOpenAI側は、作家の権利を尊重しているとの立場を表明し、「作家らもAI技術から利益を得るべきだ」との見解を示したのです。
裁判の判決は出ていませんが、生成AIを商用利用する場合には慎重になるべき側面もあると言える事例でしょう。この裁判は、デジタル時代における創作者の権利とAI技術の進展のバランスをどう取るかという根本的な問題を提起しています。
出典:「ゲーム・オブ・スローンズ」作者ら、米オープンAIを提訴 チャットGPTの学習で著作権侵害と
ニューヨーク・タイムズがOpenAIとMicrosoftを著作権侵害で提訴
2023年12月27日、ニューヨーク・タイムズはOpenAIとその主要投資企業であるMicrosoftを著作権侵害で提訴しました。ニューヨーク・タイムズは、許可なく同社の記事をAIの学習データとして使用したと主張しています。
この訴訟は、大手報道機関がAI開発企業を著作権侵害で提訴した初のケースとして注目されました。訴状では、OpenAIとMicrosoftの事業モデルを「大量の著作権侵害に基づくもの」と厳しく批判し、被った損害は「数十億ドル」に上ると主張しています。
ニューヨーク・タイムズは、高いコストをかけて取材・編集し、事実確認を徹底した報道コンテンツを無断で商用利用することは法律違反だと強く訴えたのです。また、無断収集したコンテンツを使った言語モデルや訓練データの破棄を要求しています。
裁判の判決はまだ出ていませんが、他社や他人の著作物を無断でAI開発に利用することはトラブルにつながりかねないことを示す事例です。この裁判は今後のAI産業と報道機関の関係性に大きな影響を与える可能性があるでしょう。
出典:米NYタイムズ、OpenAIを提訴 記事流用で数千億円損害
生成AIによる「検索連動型回答」で著作権侵害の恐れ
2024年7月17日、日本新聞協会は、GoogleやMicrosoftなどが提供する検索連動型生成AIサービスについて、報道機関の記事を無断利用している可能性が高いとする声明を発表しました。
協会の調査では、SGEやMicrosoft Copilotなどのサービスが、ニュース記事を不適切に転用・加工した長文回答を生成する事例が多数確認されたとしています。協会は、著作権法が認める「軽微な利用」を超えた内容が提供されており、利用者が元の報道サイトを訪れないゼロクリックサーチが増加する懸念を示しました。
こうした「ただ乗り」が報道の持続可能性を脅かし、民主主義の基盤にも悪影響を及ぼすと警告しています。
また、協会はAIが複数記事を組み合わせることで誤情報が生じる恐れも指摘し、政府に対して著作権法改正など時代に即した法整備を急ぐよう要請しました。これに対しGoogleとMicrosoftは両社とも、日本の著作権法を順守してサービスを提供していると主張しています。
出典:生成AIにおける報道コンテンツの無断利用等に関する声明
Getty ImagesがStablity AIを著作権侵害で提訴
2023年にGetty ImagesはStability AIに対して著作権侵害で訴訟を起こしました。Stability AIが開発した生成AIである「Stable Diffusion」の学習データの中に、Getty Imagesが提供する著作権付きの画像が含まれていたとされるためです。
実際に、Stable Diffusionが生成する画像にGetty Imagesの画像に利用されるウォーターマークのようなものがあるケースがありました。Getty Imagesは著作権侵害や画像の無断使用を争点に裁判を起こし、判決はまだ出ていない状態です。
この例からも画像の無断使用は訴訟リスクを抱える危険性があることがわかります。また、AIによる生成物が何かに酷似すれば、著作権侵害になる可能性を示唆すると言えるでしょう。
生成AIによるアニメ業界の著作権侵害問題
生成AI技術の発展により、世界中の画像共有サイトで大量のアニメイラストが公開されています。誰でも簡単に生成・掲載できるプラットフォームには、著作権問題が潜んでいます。
日本経済新聞の調査では、世界的に人気の13タイトルのアニメキャラクター名で検索された9万枚以上の画像から、原作と複数の特徴が酷似した約2500枚が見つかりました。
生成AIを使うことで、意図せず類似画像を生成してしまい、著作権侵害のリスクを抱えてしまいかねない例だと言えます。AIクリエイターと著作権保護のバランスをどう取るかという新たな課題を提起しており、法規制の必要性を示唆しています。
出典:生成AIで日本アニメ「新・海賊版」横行 調査報道の裏側
日本で生成AIによる著作権侵害をしたらどうなる?

著作権侵害を受けた権利者は、侵害者に対して以下のような法的措置が可能です。
- 侵害行為の差止請求
- 損害賠償請求
- 不当利得の返還請求
- 名誉回復措置の請求
当事者間で解決しない場合は、最終的に裁判所の判断を仰ぐことになります。著作権侵害は親告罪(一部例外あり)として刑事罰の対象でもあります。
- 著作権・出版権・著作隣接権の侵害:最大10年の懲役または1,000万円以下の罰金
- 著作者人格権侵害:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
上記のような罰金が科されるため注意が必要です。なお、法人による侵害の場合は、最大3億円の罰金刑が定められています。
まだ生成AIに関する法整備は追いついていませんが、もし企業が生成AIによって著作権侵害をした場合、損害賠償の支払いや刑事罰につながる可能性は否定できません。
著作権侵害になる生成AIの使い方

今後、生成AIを利用するにあたり、著作権侵害になる可能性のある使い方を把握しておくことが非常に大切です。ここでは、リスクのある使い方を4つ紹介します。
- 他者の著作物を無断で学習データに使用する
- 学習元データを特定できるほど酷似した出力を利用する
- 生成物を自社作品として公表・販売する
- 明らかに既存作品に依存したプロンプト
それぞれ詳しく見ていきます。
他者の著作物を無断で学習データに使用する
生成AIを運用する際に問題となるのが、他者の著作物を許諾なく学習データとして使用することです。
例えば、小説や記事、写真、音楽などの著作物を著作権者の同意なくAIの訓練に使用すると、複製権や翻案権(翻訳・編曲・変形・脚色など)の侵害となる可能性があります。特に、商業目的でAIシステムを開発・運営する場合、無断使用は法的リスクを伴います。
学習元データを特定できるほど酷似した出力を利用する
AIが生成したテキストや画像が特定の著作物と実質的に同一であれば、実質的複製とみなされる可能性があります。
こうした行為は原著作者の複製権や翻案権を侵害し、差止請求や損害賠償の対象となる可能性があります。AIの出力結果が既存著作物と「偶然の一致」を超えて酷似している場合は、使用前に法的リスクを慎重に検討することが重要です。
生成物を自社作品として公表・販売する
生成AIが作成したコンテンツを自社のオリジナル作品として公表・販売する際は十分に注意する必要があります
AIの生成物には学習元データの著作権が残存している可能性があり、それを無断で商業利用すれば権利侵害となり得るからです。
特に問題となるのは、AIに有名な文学作品の続編を書かせたり、アーティストのスタイルで画像を生成したりして、元の創作物と区別がつかないほど類似した成果物を商用利用する場合です。
明らかに既存作品に依存したプロンプト
生成AIに対して「〇〇作品のキャラクターを描いて」「××の小説の続きを書いて」といった、特定の著作物に依拠したプロンプトを使用することは、著作権侵害の可能性を高めるでしょう。
このような指示によって作成されたAI生成物は、実質的な二次創作または模倣とみなされる恐れがあります。
注意点を挙げるとしたら、AIに実際に存在する映画キャラクターを描かせたり、人気小説シリーズの新たなエピソードを生成させたりするプロンプトです。
商用利用はもちろん、場合によっては個人利用であっても許諾なく公開・投稿すれば法的にNGとなる可能性があります。
AIの著作権侵害リスクを防ぐために企業ができる対策

ここからは、会社で著作権侵害のリスクを防ぐための対処方法を紹介します。
- AI活用時の社内ガイドラインを整備する
- 著作権確認ツールを活用する
- コンテンツをなるべく精査する
- 商用利用に対応した生成AIを使う
これから生成AIを導入予定の企業様は、ぜひ参考にしてください。
AI活用時の社内ガイドラインを整備する
企業が生成AIの著作権侵害リスクを低減するには、包括的な社内ガイドラインの策定が効果的です。ガイドラインは、AIツールの利用範囲や許容される学習データの種類、生成コンテンツの確認など、運用ルールを確立することが重要です。
2024年5月21日に成立し、8月1日に発効した「EU AI規制法」では、生成AIに関して透明性と著作権保護を重視し、AIモデルが学習に使ったデータの開示義務や、生成物にAI生成であることを明示する要件などが含まれています。
企業は国際的な規制の動向や国内の判例を注視しながら、利用目的に応じた権利処理の手順をスタッフに教えるのがおすすめです。また、経営層が生成AIの知識を身につけ、しっかりと活用指針を示せることも重要になるでしょう。
まだ明確な法整備はされていませんが、「AIの開発に他者の著作物を無断使用しない」「誰かの著作物と酷似していないか調べる」など、著作権にしっかりと配慮するルールが望ましいです。
コンテンツをなるべく精査する
生成AIが作成したコンテンツを活用する際は、必ず人間が介入してチェックしましょう。AIの出力は既存著作物の特徴を反映しており、そのまま使用すれば著作権侵害となる危険性があるためです。
著作物と類似性の評価を中心に、商標やロゴの使用、個人情報、プライバシーの侵害、そして偏見を含む表現などを総合的に精査しなくてはなりません。特に、生成AIは既存のロゴやマークに似た画像を生成する可能性があるため注意してチェックしたいポイントです。
商用利用する場合は、社内の法務部門や外部の専門家による二次チェックを採用することで、リスクをさらに低減できます。AIはあくまで支援ツールであり、最終的な責任と判断は人間にあることを忘れてはなりません。
著作権確認ツールを活用する
生成AIの制作物を利用する際、著作権確認ツールを活用するのが役立ちます。ツールは、AI生成コンテンツと既存の著作物との類似性を自動的に分析し、潜在的な権利侵害を事前に検出する機能を持っています。
例えば、テキストコンテンツであればコピーチェックツール、画像であれば逆画像検索や画像照合システムなどを使うことで安全性を確認できるでしょう。
商用利用に対応した生成AIを使う
著作権問題の根本的な解決策として、学習データが著作権フリーである生成AIツールを選択するのがおすすめです。例えば、Adobe Fireflyでは、商用利用可能なデータのみで開発されているため、企業での安全な活用が可能です。
ただし、こちらも完全にリスクフリーではないため、人間によるチェックや社内ガイドラインなど、複数の対策を組み合わせて管理するようにしましょう。
\ AI導入を成功させ、成果を最大化する考え方を学ぶ /
生成AIの活用における今後の法整備動向
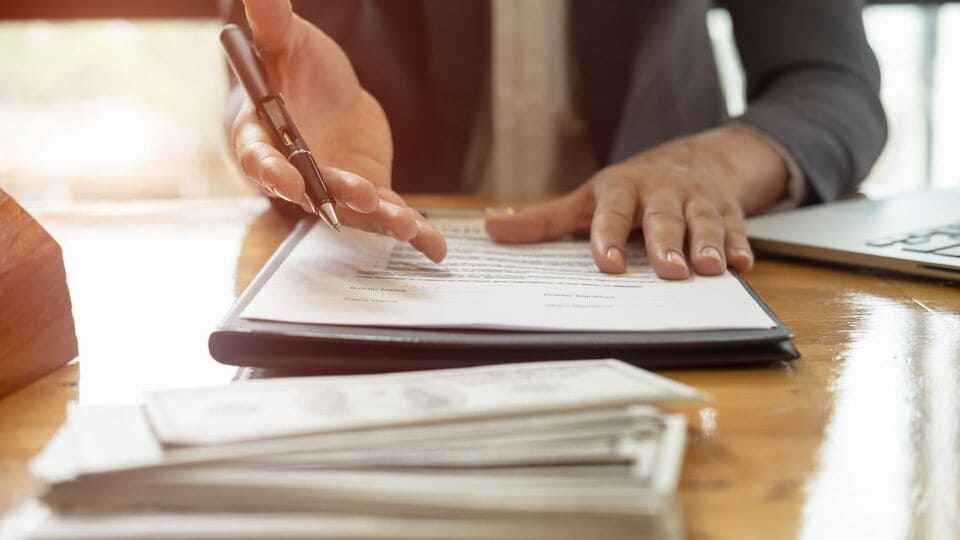
生成AIの著作権問題に対し、日本政府も本格的な対応を実施しています。特に注目されているのが、文化庁が公表した「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」です。
企業やクリエイターが生成AIを活用する際に著作権侵害のリスクを正しく認識し、適切に対処できるようにするための指針です。
このガイダンスは、生成AIが「著作物を学習に使用すること」や「AIが生成したコンテンツが既存の著作物に類似してしまうこと」に関して、どのような法的判断が求められるのかを明確にしようとしています。
また、文化庁はこのガイダンスを通じて、事業者が「AIを使った創作活動において、どこまでが合法で、どこからが違法の可能性があるか」という判断を自身で行えるようにし、トラブルの予防やコンプライアンス強化につなげる狙いを持っています。
この動きは、今後の法改正やガイドライン策定のベースとなる可能性も高く、生成AIの活用が加速する中で、著作権保護と技術革新へのバランスをどのように取っていくか、注目がさらに高まるでしょう。
出典:文化庁|AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス
まとめ:著作権に配慮して生成AIを活用しよう
生成AIは、企業の業務効率化や創造性の拡張に可能性をもたらす一方で、著作権侵害のリスクも潜んでいます。ニューヨーク・タイムズの訴訟やウルトラマン画像の判例、著名作家らの集団訴訟は、技術の法的な課題を浮き彫りにしました。
企業として、生成AIを責任ある形で活用するには、著作権の基本的な理解と、具体的な対策の実施が不可欠です。著作権に配慮しながら運用し、AIを適切に活用できる企業体制を整えましょう。
SHIFT AIでは、AI導入に関するご相談を無料で受け付けています。著作権に関して不安や疑問がある方は、お気軽にお問い合わせください。適切な知識と対策で、AIと著作権の共存を実現していきましょう。
下記リンクからは、リスク面を含めた自社の生成AI活用力を自己診断できるチェックリストをご覧いただけます。「生成AIのルール整備や活用に向けて、不足している点を認識したい」「自社の生成AIへの対応状況を可視化したい」といった方はお気軽にご覧ください。