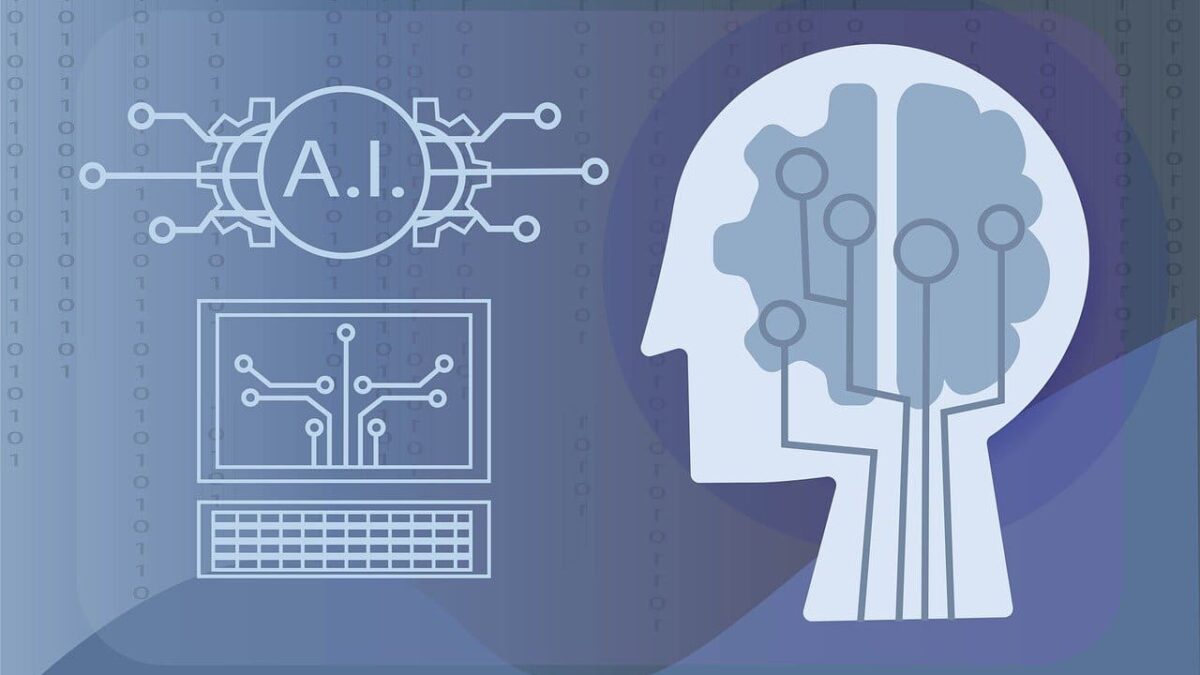業務の効率化が求められる今、RPA(Robotic Process Automation)と生成AIの連携が注目を集めています。定型作業の自動化に強みを持つRPAに、生成AIの柔軟な判断や文章生成の力を組み合わせることで、これまで自動化が難しかった業務にも対応可能になってきました。
本記事では、RPA×生成AIの相乗効果を解説するとともに、導入企業の成功事例20選とおすすめツールもご紹介します。
SHIFT AIではAIの活用や導入に関する相談を無料で受け付けています。また職種別AI活用方法のeラーニング、社内のAI人材育成支援、コンサルティングも行っております。AIの活用を検討している方は、ぜひお気軽にご相談ください。
- そもそもRPAとは
- RPA×AI組み合わせの種類
- RPAとAIを組み合わせた事例20選
- 【製造】5年間で約630業務の自動化
- 【製造】4年間で20万時間の創出効果
- 【金融】94,830時間の業務削減
- 【金融】5時間の作業を30分に
- 【医療】3年間で新薬開発に7万時間を創出
- 【公共】残業2,000時間削減に成功
- 【公共】窓口業務の自動化で年間約1,420時間の削減
- 【不動産】年間9,000時間分の作業が削減
- 【エネルギー】年間約17,000時間の創出
- 【通信】月1,000件の伝票確認が自動化
- 【通信】3分の1の業務が人手不要に
- 【運輸】未経験者でも120以上の自動化開発
- 【運輸】513プロセス、年間341,567時間の削減
- 【小売】170の業務を自動化
- 【小売】年間8,000時間の業務削減でストレスから解放
- 【サービス】業務の生産性が7倍に
- 【サービス】月間30,000件の手続きを効率化
- 【サービス】年間900時間を削減し、付加価値アップ
- 【保険】工数を40%削減し、コア業務に集中
- 【娯楽】年間14,000時間の削減
- RPAとAIを駆使したツール3選
- まとめ:RPAとAIの融合で、自動化は次のステージへ
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
そもそもRPAとは

RPA(Robotic Process Automation)とは、人間がパソコン上で行っている定型的な業務手順を、ソフトウェアのロボットが模倣して自動化する技術のことです。主に事務処理やデータ入力、集計作業などの反復的な作業を効率化します。
データ入力や集計、帳票作成などの繰り返し作業など、時間がかかる割にあまり創造的ではなかった業務を、人間の代わりにロボットが正確かつ高速に処理するので、業務の大幅な効率化ができます。
RPAと生成AIの違い
RPAと生成AIは、いずれも業務の効率化に役立つ技術ですが、その役割と強みには違いがあります。
RPAは、あらかじめ定義されたルールや手順に従い、繰り返し発生する定型業務を正確に処理するのが得意です。判断や対応の柔軟性はなく、人間が設計したフローに基づいて動作します。
一方、生成AIは、大量のデータをもとに文章や画像などのコンテンツを生成したり、自然言語を処理したりすることができます。特に非定型業務や創造的なアウトプットが求められる場面で活用が進んでいます。
| 比較内容 | RPA | 生成AI |
| 主な役割 | 定型業務の自動化 | コンテンツ生成・言語応答・創造的タスクの支援 |
| 業務例 | データ入力、転記、帳票作成 | 文章生成、要約、翻訳、画像生成など |
| 必要な設定 | 手順やルールの明文化が不可欠 | 学習済みモデルの活用、プロンプト設計が重要 |
RPAと生成AIを組み合わせる効果
RPAと生成AIを組み合わせることで、より柔軟で高度な業務自動化が可能になります。
たとえば、OCRなどのAI技術で紙帳票を読み取り、生成AIがその内容を要約・整形し、RPAがその情報を所定の業務システムに登録する——といった連携が考えられます。
また、生成AIによってユーザーからの問い合わせに自然言語で対応したり、非定型的な文書処理を支援したりすることができ、RPAの適用範囲が広がります。
これにより、人的ミスの削減や業務効率の向上が期待され、従業員はより創造的な業務に専念できるようになります。
RPA×AI組み合わせの種類
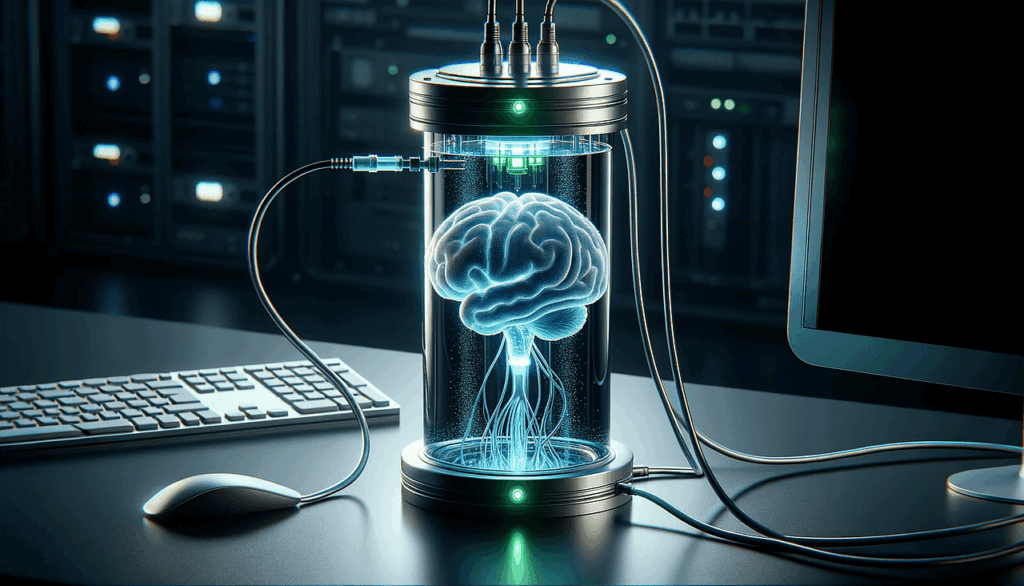
RPAは生成AIにかぎらず、AI技術全般と組み合わせて活用することができます。
RPAとAIの組み合わせ方には大きく分けて以下の3つのパターンがあります。
- RPAとAI-OCRの連携
- RPAと対話型AIの連携
- RPAと生成AIの連携
それぞれの特徴を、詳しく解説していきます。
RPAとAI-OCRの連携
AI-OCR(AIによる光学文字認識)は、ディープラーニング技術により、従来のOCRでは難しかった手書き文字や複雑なレイアウトの文書も高精度に読み取ることを可能にした技術です。
RPAとAI-OCRを連携させると、手書きのデータなどもデジタル化されてRPAが受け取ることができるようになり、紙書類を扱う業務の効率化・省力化が実現できます。
RPAと対話型AIの連携
RPAと対話型AIを連携させることで、これまで人手で対応していた問い合わせ対応や申請受付といった業務の一部を自動化し、大幅な効率化が可能になります。
たとえば、AIチャットボットが利用者からの質問に対応し、そのやりとりの内容に応じてRPAがチケットの発行や、関連システムへの情報登録などの後続処理を実行します。この仕組みにより、社内ヘルプデスクや顧客サポートの負荷を軽減しながら、24時間対応や対応品質の標準化といったメリットを実現できます。
RPAと生成AIの連携
生成AIを組み合わせることで、定型業務の自動化にとどまらず、文章作成など創造的な業務にも自動化の対象を広げることが可能になります。
たとえば、RPAがWebサイトから口コミ情報を収集し、生成AIがそれらを良い評価と悪い評価に分類。さらに、顧客属性ごとの傾向を分析し、その結果をもとにレポートを自動生成する、といった活用が考えられます。
このような連携により、単なる業務効率化だけでなく、情報分析の精度向上やアウトプットの品質向上にもつながり、組織全体の生産性を飛躍的に高めることが期待されます。
RPAとAIを組み合わせた事例20選

RPAとAIを組み合わせた業務自動化は、すでに多くの業界で導入が進んでいます。
ここでは、製造・保険・物流・小売など、業界ごとの事例を20選紹介します。自社での活用を具体的にイメージするためのヒントとして、ぜひご活用ください。
【製造】5年間で約630業務の自動化
キリングループの業務システムを担うキリンビジネスシステム株式会社では、グループ全体にAI搭載のRPAを導入し、手作業の時間を大幅に削減しています。
以前は、従業員が定型業務に追われ、精神的な負担も大きいことが課題でした。そこで同社はまず、営業部門における商品案内メールの配信業務から自動化に着手。
RPAが複数のフォルダに格納されたExcelファイルから新商品情報を収集し、生成AIが取引先ごとに案内メールの文面を作成。最終的な確認と送信は人が担当する形で業務を効率化しました。その結果、年間で約150時間の削減を達成。
この成功をきっかけに、工場や物流部門などにもAI搭載RPAを展開し、導入から5年で約630業務の自動化、約194,700時間の削減という大きな成果を上げています。
参考:「キリンビジネスシステム株式会社|価値創造を加速するICT、業務効率化や業務プロセス改革の1ツールに」
【製造】4年間で20万時間の創出効果
ジヤトコ株式会社は、RPAとAIの全社的な導入を通じて業務自動化を推進し、大幅な生産性向上を実現しています。
かつては、研究開発(R&D)部門を中心に、開発工数の管理や複数システム間でのデータ転記など、手作業による煩雑な業務が大きな負担となっていました。
そこで、AIを搭載したRPAを導入。以降4年間で、開発した自動化ワークフローは750本にのぼり、累計20万時間以上の業務時間を創出しています。たとえば、従来は1〜2時間かかっていたCSV形式へのデータ変換作業を、夜間にロボットが自動処理することで、大幅な効率化を実現しました。
この取り組みは、各部門の業務効率化にとどまらず、社員の働き方改革やITリテラシーの向上にも寄与。現在では「RPAなしでは業務が回らない」と言われるほど、社内に定着しています。
参考:「R&D部門から全社展開へ円滑なシフトチェンジ。RPAを業務改革の力に」
【金融】94,830時間の業務削減
住信SBIネット銀行は、RPAとAIの連携により、大規模な業務効率化を実現しました。
課題となっていたのは、急増する口座開設申込に伴う審査関連の事務作業が、現場に大きな負担をかけていた点です。
そこで、ユーザー部門とIT部門が連携してRPAの開発を推進。結果として、累計で約94,830時間分の業務時間を削減することに成功しました。これにより従業員は、より高度な案件審査に集中できるようになり、住宅ローンの審査時間も短縮されました。
さらに、以前は月に一度の繁忙日に残業をして、複数システムにまたがる入力や書類作成業務をこなす必要がありましたが、自動化によって残業が不要となりました。加えて、入力ミスの削減にもつながり、確認作業の負荷も大幅に軽減されたそうです。
参考:「2度目のチャレンジ、UiPathのRPA導入で成功に導く」
【金融】5時間の作業を30分に
三井住友信託銀行は、RPAとAIの連携によって業務のスピードと品質の両立を図っています。
導入前、個人顧客向け企画部では、オンラインセミナーのアンケート結果の集計に多くの時間を要し、フィードバックが迅速に行えないという課題を抱えていました。
そこでAIを搭載したRPAを導入した結果、平均5時間かかっていた集計作業が約30分に短縮され、作業効率と顧客満足度の向上を実現しました。
さらに、少量多品種の口座運用管理に関わる250の業務や、RPAの統括管理に関する500のワークフローにも同様の仕組みを適用。これにより、4年間で累計40万時間分の業務効率化を達成しています。加えて、システム開発や品質維持に不可欠なテスト工程にもRPAを活用し、自動化の範囲を拡大しています。
【医療】3年間で新薬開発に7万時間を創出
田辺三菱製薬は、RPAとAIの導入により生産性を大きく向上させました。
新薬メーカーとして海外展開も行う同社は、年々難易度が増す新薬開発の中で、煩雑な事務作業に多くの時間を取られ、開発業務に集中できないという課題を抱えていました。また、自動化を担う専門部署がなかったことから、現場主導でのRPA導入を決断しました。
社内での研修やスキル習得を着実に進めた結果、3年半で500以上の業務を自動化し、累計約7万時間の業務効率化を達成。この取り組みによって、単なる生産性の向上にとどまらず、従業員のストレス軽減や社内のデジタルリテラシー向上にもつながっています。
参考:「デジタル人材の育成と価値ある業務の創出、「自走型」の自動化で変革に挑む」
【公共】残業2,000時間削減に成功
横浜市教育委員会事務局では、RPAとAI技術を行政手続きに導入することで、大幅な業務効率化と残業時間の削減を実現しました。
従来は、年間3万件を超える就学援助申請書を、10名の職員が手作業と目視で確認しており、繁忙期には残業が常態化。職員の負担は大きく、業務の持続可能性にも課題がありました。
そこで同局は、RPAとAI-OCR(光学文字認識)を組み合わせた仕組みを導入。紙の申請書データをAIが98%の精度で読み取り、RPAが自動でシステムに登録・処理することで、審査業務の大幅な自動化に成功しました。
この取り組みにより、年間2,000時間以上の残業削減を実現。申請内容の修正・確認作業も大きく減少し、職員はより質の高いサービス提供に注力できるようになりました。
参考:「横浜市 | 小中学校における就学援助申請の審査にかかる一連の業務をRPA化したことで作業量が約6割減。業務の見直し・改善において波及効果も」
【公共】窓口業務の自動化で年間約1,420時間の削減
北海道北見市では、RPAとAIを活用し、窓口業務の効率化と市民サービスの向上を実現しました。
従来、市民は各種証明書の発行や転入・転出手続きの際、市役所で申請書に手書きで記入し、複数の窓口を回って提出する必要がありました。そのため、待ち時間が長くなるなど、申請者にも職員にも大きな負担がかかっていました。
また、職員側も申請書の内容を目視で確認し、各業務システムへ手入力するなど、煩雑な作業が発生していました。
こうした課題に対し、北見市は窓口支援システムを導入。市民はタッチパネル操作で申請情報を入力できるようになり、そのデータをもとにRPAが各システムへの自動入力と内容チェックを実行する仕組みを構築しました。
この取り組みにより、年間約51,000件の証明書発行業務と約7,000件のシステム入力作業が自動化され、市民の待ち時間は年間約450時間、職員の業務時間は年間約1,420時間削減されました。
参考:「北見市|注目を集めた「書かないワンストップ窓口」をWinActorでさらに効率化、職員の負担軽減と市民サービス向上へ」
【不動産】年間9,000時間分の作業が削減
三井不動産株式会社は、RPAとAIを連携活用することで、大幅な作業効率の向上と業務品質の改善を実現しています。
かつては、複数の担当者が毎月大量のデータを手作業で収集・格納しており、レポート作成もすべて手動で対応していました。こうした反復的かつ煩雑な業務が、多くの時間と労力を要していたのです。
この課題に対し、同社はAIを搭載したRPAを導入し、約95本のロボットを開発。データ処理やレポート作成の自動化を進めた結果、年間で約9,000時間の業務時間削減を達成しました。
単なる作業負荷の軽減にとどまらず、業務プロセス全体の可視化と改善にもつながり、より生産性の高い業務体制が構築されています。
参考:「正確性とガバナンス、 充実のクラウド対応で 現場のDX推進を支える」
【エネルギー】年間約17,000時間の創出
エネルギー供給を担う株式会社JERAは、RPAとAIを活用し、従業員主体で業務改革を推進する体制を構築しています。
導入前は、伝票登録などの経理業務をすべて手作業で処理しており、業務時間の大部分を費やしていました。また、火力発電の燃料成分に応じた最適なパラメータ設定が担当者に依存しており、属人化も課題となっていました。
こうした課題に対し、JERAはRPAとAI-OCRを導入。紙やPDFからの情報を自動で読み取り、システム登録から報告書作成までの一連のプロセスを自動化しました。
さらに、全社的な取り組みとして社内にRPAコミュニティを立ち上げ、250名の社員が参加。バックオフィス業務から発電所の現場まで、70本以上のワークフローを自ら開発し、実際に運用しています。
その結果、年間約17,000時間の業務時間を削減し、現場からの継続的な改善が根づく仕組みへと進化しています。
参考:「クラウド指向で進める 現場主導の業務改革、 その入口をRPAが開く」
【通信】月1,000件の伝票確認が自動化
KDDI株式会社は、RPAとAIを活用することで、購買業務における事務処理の負担を大幅に軽減しました。
同社の購買本部では、社内で使用する設備や物品の調達を担っており、発注データの入力や伝票の照合作業が大きな負担となっていました。
この課題に対して、AI-OCRを用いて見積書PDFから必要な情報を自動で抽出し、RPAが購買依頼データと突合する仕組みを導入。社内の各事業部からの購買依頼と、発注先業者が提出した見積書の内容を照合し、発注システムへの入力から決裁者への承認回付までを一気に自動化しました。
その結果、月に約1,000件発生する伝票処理を効率化。ロボットによる正確なチェックによりヒューマンエラーが排除され、承認者の確認作業の負担も大きく軽減されました。
参考:「購買発注業務にかかわる伝票確認作業をRPA+AI-OCRの組み合わせで自動化人員の作業負荷を軽減」
【通信】3分の1の業務が人手不要に
株式会社NTTドコモは、モバイルアプリ開発におけるテスト工程にRPAとAIを導入し、大幅な業務効率化を実現しました。
従来、アプリ開発における動作確認や検証は手作業で行われており、多大な労力と時間を要していました。新機能を追加するたびに、知見の共有や関連資料の再確認が必要となり、属人化も課題となっていました。
そこで同社は、AIを搭載したRPAを活用し、モバイルアプリとサーバーの接続動作を含むテスト業務を自動化。これにより、テストナレッジの継承や技術者の育成が円滑に進むようになりました。
結果として、テスト業務の約3分の1を自動化。かつては1日かかっていたテストが、1時間ほどで完了するようになり、アプリのリリーススピードも大幅に向上しています。
【運輸】未経験者でも120以上の自動化開発
輸入貨物事業を手がける大東港運株式会社は、RPAとAIを活用することで業務の自動化を進め、深刻化する人手不足への対応を図っています。
同社では、検疫や通関といった行政とのやり取りが多く、大量の紙書類による申請・申告作業が日常的に発生していました。こうした事務作業の負担は年々増加しており、将来的な人員確保にも課題を抱えていました。
そこで社内に推進チームを設け、部門を横断したRPA開発体制を構築。業務改善に向けて自動化の取り組みを本格化させました。
開発未経験の2名を含む体制ながら、わずか2年で120のワークフローを自動化し、年間25,000時間もの業務削減を実現。属人化の解消と業務効率の向上を両立し、持続可能なオペレーション体制を構築できています。
参考:「コア業務からのRPA導入が全社へ波及し400名の企業で12.5人月分のリソース創出 業務改善に向けた意識も社内に根付く」
【運輸】513プロセス、年間341,567時間の削減
日本通運株式会社は、RPAとAI技術を全社的に導入し、生産性の向上と働きやすい職場環境の両立を実現しています。
同社では、輸配送、倉庫管理、請求処理などに関わる多くの事務作業が、支店や部門を問わず業務負担となっており、従来の体制では対応に限界が見えていました。また、付加価値の高い物流サービスを提供するためには、社員が戦略業務に充てられる時間を創出することが急務でした。
こうした背景から、まず一部業務でRPAとAIを試験導入し、効果を確認しながら対象範囲を段階的に拡大。社内研修も積極的に実施し、社内全体への認知度向上と活用定着を図りました。
その結果、125体のロボットが導入され、計513プロセスの自動化に成功。累計で341,567時間の業務削減を達成しています。細かな手作業が減ったことで、社員の働きやすさも向上し、人材確保や定着にも好影響を与えているといいます。
参考:「2021年度末までに自動化による100万時間削減を計画」
【小売】170の業務を自動化
「ドン・キホーテ」を展開する株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスでは、RPAとAIを活用して店舗業務の効率化を進めています。
将来的な人手不足を見越し、同社は業界に先駆けてRPA専任体制を構築。社内から寄せられた約250件の業務のうち、170件もの自動化に成功しました。特に店舗オペレーションの負担軽減に注力しています。
たとえば、インバウンド客のキャッシュレス決済が多い「ドン・キホーテ」では、従来レジデータのチェックに多くの時間を費やしていました。
そこで、RPAとAIを組み合わせてレジデータを自動チェックし、異常があればアラートで通知する仕組みを導入。人はその通知に応じて最終確認を行うだけで済むようになり、大幅な業務効率化を実現しました。
参考:「プログラミング経験不問」で募集し結成したRPAチームがドン・キホーテのDX加速に大きく貢献」
【小売】年間8,000時間の業務削減でストレスから解放
環境に優しいプラスチック製品を世界に供給する伊藤忠プラスチックス株式会社は、RPAとAIを活用し、働き方改革を実現しました。
同社では、コンビニなどへの食品容器供給に伴い、大量の受発注業務や資料作成が発生。これにより、社員の残業や早朝出勤が常態化していました。さらに、取引先によってはFAXを用いるなどアナログな業務も残り、業務効率化の障壁となっていたのです。
この状況を打破するため、パソコン業務の大幅な効率化を目指してRPAプロジェクトを本格始動。現場社員が自らロボットを開発する方針を掲げ、社内アカデミーを通じて開発者を育成。全社規模で自動化を推進しました。
その結果、約100個のRPAを開発し、年間で約8,000時間の業務削減に成功。RPAが日常業務に浸透し、社員の働き方やモチベーションにもポジティブな変化が生まれています。
参考:「全社員の1割がRPA開発経験、RPAによる働き方改革」
【サービス】業務の生産性が7倍に
ノベルティ通販サイトの運営やWebコンサルティングを手がける株式会社ドリームデッサンは、AI搭載のRPA導入により業務効率化と働き方改革を実現しました。
同社では、従来のExcel業務に限界を感じ、より良い勤務環境を目指してRPAの導入を決定。受注書作成、見積書作成、画像加工の3つの主要業務において自動化を進めました。
その結果、月間約500件の処理を3〜4人で行っていた作業が、RPA導入後は1人で1,000件を処理できるようになり、業務によっては生産性が7倍に向上したケースもあります。
特に、以前は毎日1,000枚以上を手作業で加工していた画像処理も完全自動化を達成。これにより人的負担がゼロとなり、他社に先駆けてホームページに商品を掲載できるようになり、販売機会の損失削減にもつながっています。
参考:「株式会社ドリームデッサン | RPAを活用した働き方改革のお手本! 人手不足の時代に求人応募が殺到する理由とは?」
【サービス】月間30,000件の手続きを効率化
企業の労務管理や手続きを受託するSATO社会保険労務士法人は、AI搭載のRPAを活用し、煩雑な業務の自動化に成功しました。
同社では、行政手続きのオンライン申請後における進捗確認や、公文書のダウンロードに多大な時間を要しており、繁忙期には作業の遅延も発生。手続き件数が多い時には、月に3万件を超えることもありました。
そこで、まず札幌オフィスでRPAを導入。申請状況の照会や公文書の自動ダウンロードに加え、社内データベースとの連携やAIによる画像認識で処理の判定を行う仕組みを構築しました。
このロボットは24時間365日稼働可能で、業務時間外の待機や人手による確認作業を不要にし、大幅な時間短縮と効率化を実現しています。導入の効果を受けて、札幌以外の拠点へも展開が進み、現在では全社的な業務効率化に寄与しています。
参考:「SATO社会保険労務士法人 | いち早く行政手続きのデジタル化に対応、 e-Govでの電子申請・公文書ダウンロードを効率化」
【サービス】年間900時間を削減し、付加価値アップ
外資系企業の日本子会社に対し、記帳・支払・給与計算などの代行サービスを提供する株式会社JCアカウンティングは、RPAとAIの活用で業務効率化と付加価値の向上を実現しました。
かつては、膨大な定型業務に追われることで、税務・経営相談といった専門性の高いサービスに十分な時間を割けず、さらに業務の属人化も大きな課題となっていました。
そこで同社は、AI搭載のRPAを導入。会計データの入力、資料作成、チェック業務の自動化を進めた結果、年間900時間相当の作業を削減することに成功しました。
この効率化により、社員はより専門性の高いコンサルティング業務に注力できるようになり、業界全体が「将来なくなる職種」と言われる中でも、同社のクライアント数は毎年10%ずつ増加しています。
参考:「JCアカウンティング | 「無くなる仕事」の効率化によりデジタル・デザインの視点を醸成、「無くならない仕事」を強くする」
【保険】工数を40%削減し、コア業務に集中
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、AI搭載のRPAを導入することで、災害時における事故受付から保険金支払いまでの業務を自動化し、処理スピードと顧客対応力を大幅に向上させました。
災害発生時には、保険金支払い対象の案件が急増し、紙書類と人手に依存した従来の体制では対応が追いつかず、顧客対応の遅延が課題となっていました。
同社は、2018年の台風対応を契機にRPAの導入を決定。事故受付・登録・保険金支払いの各工程を段階的に自動化しました。その結果、関連業務の工数を約40%削減し、対応の迅速化によって顧客満足度の向上を実現しています。
さらに、従来40〜50人を要していた処理業務がわずか4人で対応可能となり、現場ではより高度な顧客サポート業務に集中できるように。災害時においても柔軟な人材配置が可能となるなど、業務体制全体の強化にもつながっています。
参考:「事故登録・支払業務をUiPathで自動化、災害発生時の対応力を強化し顧客サービスの品質向上にも寄与」
【娯楽】年間14,000時間の削減
パチンコ&スロット事業を展開する株式会社マルハンでは、RPAとAIの導入により、接客品質の向上と人材確保への対応を進めています。
同社の店舗運営では、報告書の作成や帳票の管理、日次の売上・経費データの集計など、多くの定型業務が従業員の負担となっていました。
そこでAI搭載のRPAを導入し、これらの事務作業を自動化。結果として、年間14,000時間もの業務削減を実現しました。
これによりスタッフは本来の接客業務に専念できるようになり、顧客満足度やチームの一体感が向上。人材の定着・確保にもつながっています。加えて、店舗業務だけでなく本社業務も効率化され、早出勤務が不要になるなど、働き方の改善も進んでいます。
参考:「店舗における間接業務の効率化により接客向上と人材不足への対応」
RPAとAIを駆使したツール3選

RPAとAIの組み合わせで業務を効率化するには、自社で開発する方法もありますが、サービス提供会社のツールを使う方法もあります。特に自社で人材やノウハウが足りていない場合には大いに活用できます。おすすめのツール3選を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
WinActor
WinActorは、NTTデータが提供する純国産のRPAツールで、日本企業や自治体をはじめ、多くの組織に導入されています。
プログラミングの知識がなくても使えるのが特徴で、直感的なシナリオ作成画面や豊富なテンプレートにより、操作性に優れています。さらに、日本語のマニュアルやサポート体制も整っているため、RPAを初めて導入する企業にも安心して利用できます。
| ツール名 | WinActor |
| 提供会社 | NTTデータ |
| 特徴 | 直感的な操作、国産、テンプレート豊富、AI連携やサポートも充実、Windows端末からの操作 |
| 料金プラン | ・「フル機能版ライセンス」1,098,680円/年 ・「実行版ライセンス」300,080円/年・「有償トライアルサービス(60日間)」209,000円 |
| 無料トライアル | あり(30日間) |
| 公式ホームページ | https://winactor.com/ |
UiPath
UiPathは、世界的に高いシェアを誇るグローバルRPAプラットフォームで、多くの企業が導入しています。
業務内容に応じた多彩な自動化ツールを提供しており、各種AIとの連携も進んでいるため、複雑な業務プロセスや非定型作業にも柔軟に対応できます。また、ノーコードで初心者でも扱いやすいツールから、ローコードで開発者向けの機能まで幅広く用意されています。
本社はアメリカにありますが、日本国内にも複数の拠点があり、大企業から中小企業まで幅広く活用されています。
| ツール名 | UiPath |
| 提供会社 | UiPath |
| 特徴 | 世界中で導入実績多数、豊富なAI統合、高度な自動化、拡張性あり |
| 料金プラン | 月額もしくは年額サブスクリプション型(プラン複数) |
| 無料トライアル | あり |
| 公式ホームページ | https://www.uipath.com/ja/ |
Robo-Pat DX(ロボパットDX)
Robo-Pat DXは、誰もが手軽に業務自動化に取り組める「現場主導型」をコンセプトに開発された、国産のRPAツールです。
日本企業の業務課題に合わせた機能と直感的な操作性が特徴で、プログラミング経験のないスタッフでも無理なくロボットを作成できます。
さらに、個人・チーム向けの丁寧な導入支援も用意されており、企業のDX推進をトータルでサポートします。
| ツール名 | Robo-Pat DX |
| 提供会社 | 株式会社FCE |
| 特徴 | 国産、現場主導型、ノーコード、操作が簡単、充実したサポート(無料) |
| 料金プラン | 月額制、詳しい値段は要問い合わせ |
| 無料トライアル | あり(1ヶ月3アカウント) |
| 公式ホームページ | https://fce-pat.co.jp/concept/ |
まとめ:RPAとAIの融合で、自動化は次のステージへ
RPAにAIを組み合わせることで、従来の定型業務だけでなく、非定型で判断を要する業務まで自動化の対象を広げることができます。
すでに多くの企業が業種を問わず導入し、業務時間の大幅な削減や生産性向上といった成果を上げています。今後はAI技術の進化により、さらに高度な業務自動化が期待されます。
RPAとAIをいかに効果的に活用できるかは、業務改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するうえで重要な鍵となります。まずは自社の課題を見極め、適切な分野への導入やツールの選定から着手し、段階的な社内展開を進めていきましょう。
SHIFT AIではAIの使い方や導入に関することなど、幅広い相談を無料で受け付けています。また、AI人材の育成支援やワークショップも実施しています。AIの活用を検討している方はぜひお気軽にご相談ください。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応