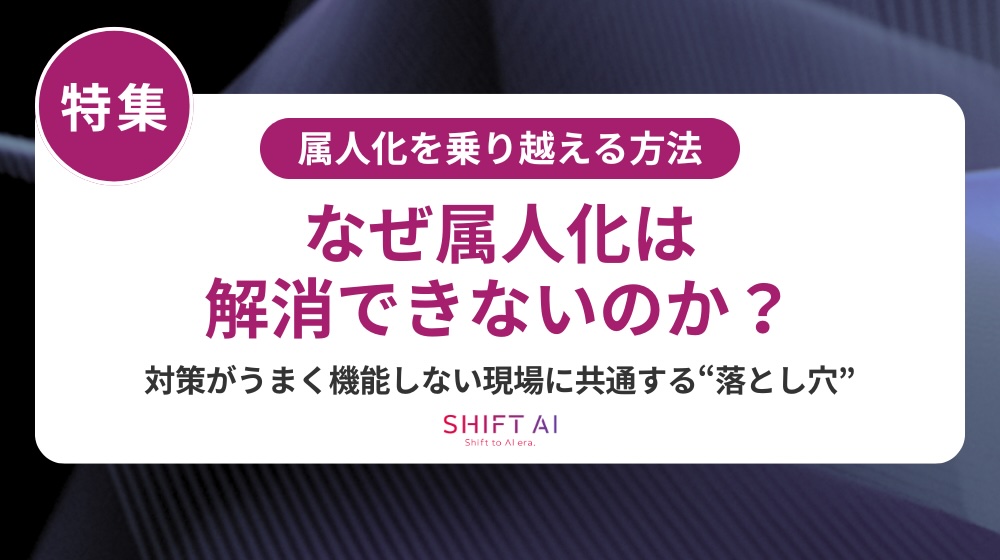「〇〇さんがいないと、この業務が進められません」「前任者しか知らない手順で、引き継ぎ資料もありません」——このような状況に直面したことはありませんか?
特定の個人にしか業務を遂行できない「属人化」は、多くの企業が抱える深刻な課題です。2025年現在、働き方の多様化やデジタル人材不足により、この問題はさらに複雑化しています。
属人化を放置すると、業務停滞、品質低下、ノウハウ流出など、企業経営に致命的な影響を与えかねません。しかし従来の解消法だけでは、もはや限界があるのも事実です。
本記事では、生成AI活用による新しいアプローチを含む5つの属人化解消法と、組織全体で取り組む実践的なステップを詳しく解説します。「誰かが抜けても回る強い組織」を作りたい経営者・管理職の方は、ぜひ最後までお読みください。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
業務の属人化とは?意味と基本概念を解説
業務の属人化とは、特定の個人しかその業務を遂行できない状態を指します。担当者以外は業務内容や手順を把握しておらず、その人が不在になると業務が停滞してしまう問題です。
従来の属人化に加え、2025年現在では「AIスキルの偏在」という新たな課題も浮上しています。生成AIツールを使いこなせる社員とそうでない社員の間に大きな生産性格差が生まれ、結果的にAI活用業務が特定の人材に集中する現象が起きているのです。
属人化の対義語である「標準化」とは、誰でも同じ手順で同じ成果を出せる仕組みを指し、現代企業が目指すべき理想の状態と言えるでしょう。
業務の属人化が起こる原因7つ
属人化が発生する根本的な原因を理解することで、適切な対策を講じることができます。現代の企業が直面する主要な原因は以下の7つです。
従来からの課題に加え、デジタル化の進展に伴う新しい要因も含まれています。
業務量が多すぎるから
業務量の過多は、情報共有や引き継ぎを阻害する最大の要因です。
担当者が目の前の業務をこなすだけで精一杯な状況では、マニュアル作成や他メンバーへの共有に時間を割けません。また、人員不足により一人当たりの業務負荷が増加すると、業務を分担する余裕もなくなります。
このような状況が続けば、必然的に特定の個人に業務が集中し、属人化が進行してしまいます。業務の効率化や人員配置の見直しが急務と言えるでしょう。
専門性が高すぎるから
高度な専門知識やスキルが必要な業務では、属人化が起こりやすくなります。
例えば、特殊なプログラミング言語を扱うシステム開発や、複雑な法的知識を要する契約業務などが該当します。このような業務は、画一的なマニュアル化が困難で、習得にも長期間を要するため、どうしても限られた人材に依存せざるを得ません。
専門性の高い業務でも、基本的な手順や注意点は言語化できる部分があります。完全な標準化は難しくても、部分的な共有化を目指すことが重要です。
情報共有の仕組みがないから
組織内に適切な情報共有システムが構築されていないと、ナレッジが個人に蓄積されてしまいます。
メールやチャットツールはあっても、業務手順やノウハウを体系的に管理・共有する仕組みがない企業は少なくありません。また、情報共有を促進する評価制度や組織文化が整備されていない場合、社員が積極的に知識を共有しようとしないケースもあります。
情報の透明性を確保し、誰でもアクセスできる環境を整えることが属人化防止の第一歩となります。
引継ぎが不十分だから
前任者からの引き継ぎが不完全だと、後任者が一から業務を構築せざるを得ません。
退職や異動の際に十分な引き継ぎ期間が確保されていない、口頭での説明に頼っている、業務の背景や判断基準が伝わらないなどの問題があります。結果として、後任者は手探りで業務を進めることになり、新たな属人化が生まれてしまうのです。
体系的な引き継ぎプロセスの確立と、充分な移行期間の設定が必要です。
レガシーシステムに依存しているから
古い基幹システムや複雑化したITインフラは、属人化の温床となります。
長年使用されてきたシステムは、導入当時の担当者しか詳細を把握していないケースが多く見られます。また、カスタマイズが重ねられた結果、システムの構造が複雑化し、新たな担当者が理解するのに膨大な時間を要する状況も珍しくありません。
システムの近代化やドキュメント整備を通じて、ITインフラの属人化解消を図ることが重要です。
デジタルリテラシーに格差があるから
社員間のデジタルスキル格差が、新たな属人化を生み出しています。
同じ職場でも、デジタルツールを使いこなせる人とそうでない人の間に大きな生産性の差が生まれています。特に、クラウドサービスやデータ分析ツールなどを活用した業務では、スキルの有無が直接的に業務効率に影響するため、できる人に業務が集中する傾向があります。
全社的なデジタルリテラシー向上施策が、現代の属人化対策には欠かせません。
AI活用スキルが偏っているから
生成AIツールの活用能力が特定の社員に偏ることで、新しい形の属人化が発生しています。
ChatGPTやその他の生成AIツールを業務で効果的に活用できる社員と、まったく使えない社員の間には、驚くほどの生産性格差が生まれています。AI活用により業務効率が飛躍的に向上する一方で、そのスキルを持つ人材にAI関連業務が集中してしまうのです。
組織全体のAIリテラシー向上が、2025年以降の属人化対策における最重要課題と言えるでしょう。
属人化によるリスクとデメリット5つ
業務の属人化を放置すると、企業経営に深刻な影響を与える様々なリスクが発生します。特に人材流動性が高まる現代では、これらのリスクはより顕在化しやすくなっています。
早期の対策により、組織の持続的成長を確保することが重要です。
業務が停滞する
担当者の不在により、重要な業務が完全にストップしてしまうリスクがあります。
病気や急な退職、長期休暇などで担当者がいなくなった瞬間、その業務に関わるすべてのプロセスが止まってしまいます。顧客からの問い合わせに対応できない、承認プロセスが進まない、データ更新ができないなど、事業運営に直接的な影響が出る可能性があります。
特にプロジェクトの中核業務が属人化していた場合、プロジェクト全体の遅延や中止に発展するケースも珍しくありません。
品質が低下する
属人化した業務では、一定の品質を保つことが困難になります。
担当者以外に適切な業務手順や品質基準を知る人がいないため、代理者が対応した場合に成果物の質が大きく下がってしまいます。また、第三者によるチェック機能が働かないため、ミスの発見が遅れたり、品質の悪化に気づかないまま業務が継続される危険性もあります。
顧客満足度の低下や信頼失墜につながる重大なリスクと言えるでしょう。
特定社員に負荷が集中する
属人化により、特定の社員だけに過度な業務負荷がかかってしまいます。
他の社員がサポートできない状況では、担当者一人ですべてを抱え込まざるを得ません。結果として長時間労働や休日出勤が常態化し、メンタルヘルスの悪化や燃え尽き症候群を引き起こすリスクが高まります。
最悪の場合、過労による休職や退職に発展し、さらなる業務停滞を招く悪循環に陥る可能性があります。
ノウハウが流出する
担当者の退職と同時に、貴重な業務ノウハウが組織から失われてしまいます。
長年の経験で培われた効率的な作業手順、顧客対応のコツ、トラブル対処法などは、企業にとって重要な資産です。しかし、これらが個人の頭の中にしか存在しない場合、その人が辞めれば知識も一緒に失われてしまいます。
後任者は一からノウハウを蓄積する必要があり、元の水準に戻るまでに長期間を要することになります。
DX推進が阻害される
属人化はデジタルトランスフォーメーション(DX)の大きな障壁となります。
業務プロセスが不透明で標準化されていない状況では、システム化や自動化を進めることができません。また、デジタルツールの導入を検討しても、現状の業務フローが把握できないため、適切なソリューション選定や設計ができない問題も発生します。
競合他社がDXにより効率化を進める中、属人化により取り残される企業リスクは深刻です。
業務の属人化を解消する方法5つ
属人化の解消には体系的なアプローチが必要です。従来の手法に加え、生成AI活用による新しい解決策を組み合わせることで、より効果的な成果を期待できます。
以下の5つの方法を段階的に実行し、持続可能な標準化を実現しましょう。
💡関連記事
👉生成AI導入のすべてがわかる決定版!メリット・手順・注意点を徹底解説
業務プロセスを可視化する
業務の流れを図式化し、誰でも理解できる状態にすることが属人化解消の第一歩です。
まず、担当者へのヒアリングを通じて業務の全体像を把握し、フローチャートや業務マップを作成します。この際、生成AIを活用して業務分析を行うことで、人間では気づきにくいボトルネックや改善点を発見できます。
次に、詳細な手順書やマニュアルを整備します。作業画面のスクリーンショットや動画を含めた視覚的な資料を作成することで、経験の浅い社員でも理解しやすいマニュアルが完成します。
権限と業務を分散する
特定の個人に集中している権限や業務を、複数のメンバーに適切に分散させます。
役割分担を明確にし、承認権限を段階的に設定することで、一人に依存する構造を解消できます。この際、AIによる最適配置分析を活用すれば、各メンバーのスキルや経験を考慮した効率的な分散が可能です。
また、属人化しない体制を構築するため、同一業務を複数人が担当できるクロストレーニングを実施します。ローテーション制度の導入により、幅広い業務経験を積める環境を整えることも重要です。
ナレッジマネジメントを推進する
個人が持つ暗黙知を、組織全体で活用できる形式知に変換します。
ベテラン社員の経験やコツを言語化し、社内で共有可能な知識として蓄積します。生成AIを活用すれば、膨大なヒアリング内容から自動的にマニュアルを作成したり、よくある質問をまとめた社内FAQを効率的に構築できます。
ナレッジベースやwikiシステムを導入し、誰でも必要な情報にアクセスできる環境を整備することで、知識の属人化を防げます。
ITツール・システムを導入する
適切なデジタルツールの導入により、業務の標準化と効率化を同時に実現します。
情報共有ツールやプロジェクト管理システムを活用することで、業務の進捗や課題を組織全体で把握できるようになります。また、定型業務のAI自動化を進めることで、人的依存度を大幅に削減できます。
AI搭載ツールを使った業務標準化では、過去のデータから最適な手順を学習し、一貫した品質での業務遂行が可能になります。
組織文化と評価制度を改革する
情報共有や標準化を推進する組織文化の醸成が、持続的な属人化解消には不可欠です。
情報共有の取り組みを人事評価に組み込み、積極的に知識を共有する社員を適切に評価する仕組みを構築します。また、全社員のAIリテラシー向上を図ることで、組織全体の生産性向上と属人化防止を同時に実現できます。
属人化解消を推進する文化を作るため、経営層が率先して情報共有の重要性を発信し、オープンなコミュニケーションを奨励することが重要です。
このような属人化リスクを根本解決するには、組織全体のAIリテラシー向上が不可欠です。従来の手法だけでは限界がある現代において、生成AI活用による新しいアプローチが注目されています。
属人化を解消するロードマップ【4ステップ】
属人化解消を成功させるには、計画的で段階的なアプローチが重要です。闇雲に取り組むのではなく、現状把握から継続的改善まで体系的に進めることで、確実な成果を得られます。
以下の4ステップに沿って、組織に適した解消策を実行しましょう。
現状分析と課題を特定する
まず組織内のどこに属人化が発生しているかを正確に把握します。
全部署を対象に業務棚卸しを実施し、特定の個人に依存している業務を洗い出します。各業務について、担当者数、引き継ぎ可能性、業務の重要度、停滞リスクなどを評価し、属人化の深刻度を数値化することが重要です。
データ分析ツールを活用すれば、業務量の偏りや工数配分を客観的に把握できます。また、アンケートやヒアリングを通じて、現場の声を収集し、見えにくい属人化も発見できるでしょう。
解消計画を策定する
リスクの高さと解消の難易度を軸に、優先順位を決めて計画を立てます。
「高リスク×低難易度」の業務から着手し、早期に成果を出すことでプロジェクトの推進力を高めます。各業務について、解消手法(マニュアル化、システム化、人員追加など)と必要なリソース、実行スケジュールを明確にします。
AI支援による最適計画立案では、過去の類似プロジェクトデータから成功確率の高いアプローチを提案してもらうことも可能です。
解消施策を実行する
計画に基づいて具体的な改善施策を段階的に実行します。
一度にすべてを変更するのではなく、影響範囲を限定したパイロット実施から始めることでリスクを抑えられます。マニュアル作成、システム導入、教育研修などを並行して進め、定期的に進捗を確認します。
特に生成AI研修の実施は、組織全体の業務効率化と属人化防止に大きな効果をもたらします。実務に即したトレーニングを通じて、AIツールを活用した標準化を推進しましょう。
継続的に改善する
属人化解消は一度実施すれば終わりではなく、継続的な取り組みが必要です。
KPI(業務停滞日数、引き継ぎ完了率、マニュアル整備率など)を設定し、定期的に効果を測定します。新たな属人化の発生を早期発見するため、四半期ごとの点検を制度化することが重要です。
AI分析により業務データから改善点を自動抽出し、PDCAサイクルを効率的に回すことで、継続的な組織力向上を実現できます。
まとめ|属人化解消は組織の未来を左右する重要課題
業務の属人化は、業務停滞・品質低下・ノウハウ流出など、企業経営に深刻な影響を与える問題です。特に2025年現在では、AI活用スキルの偏在により新しい形の属人化も発生しており、従来の対策だけでは限界があります。
効果的な解消には、業務の可視化から組織文化改革まで5つのアプローチを体系的に実行することが重要です。中でも生成AI活用による業務標準化は、従来手法を大きく上回る成果を期待できる革新的な解決策と言えるでしょう。
ただし、一部の社員だけがAIを使えても新たな属人化を生むだけです。組織全体のAIリテラシー向上こそが、真の属人化解消への近道となります。
まずは現状の属人化リスクを正しく把握し、計画的な取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。

属人化解消に関するよくある質問
- Q属人化解消のメリットは何ですか?
- A
業務継続性の確保が最大のメリットです。担当者が不在でも業務が停滞せず、組織全体の生産性向上につながります。また、複数人で業務を分担することで品質の安定化や改善点の発見も期待できます。ノウハウの組織内蓄積により、新人教育の効率化や離職による知識流出防止も実現できるでしょう。
- Q属人化解消にはどんなツールが効果的ですか?
- A
業務管理システムや情報共有ツールが基本となります。プロジェクト管理ツール、社内wiki、チャットツールなどで情報の透明化を図ります。近年では生成AIを活用したマニュアル自動作成ツールや、ナレッジ抽出システムも注目されています。重要なのはツール導入と併せて、運用ルールの整備も行うことです。
- Q属人化しやすい業務の特徴は?
- A
専門性が高く、手順が複雑な業務ほど属人化しやすくなります。システム運用、顧客対応、企画立案などが代表例です。また、業務量が多すぎて共有する時間がない、前任者からの引き継ぎが不十分、評価制度で情報共有が評価されないといった環境要因も属人化を促進します。
- Q属人化解消の成功事例はありますか?
- A
製造業での技術継承や、IT企業でのシステム運用標準化などで多くの成功例があります。具体的には、ベテラン技術者の暗黙知を動画マニュアル化した事例や、複雑なシステム運用手順をAI支援で標準化した事例などです。共通するのは、段階的なアプローチと全社的な取り組み体制の構築です。
- Q属人化解消が失敗する原因は?
- A
経営層のコミットメント不足と現場の抵抗が主な失敗要因です。標準化により自分の価値が下がると感じる社員の心理的抵抗や、短期的な工数増加を嫌がる現場の反発があります。また、一時的な取り組みで終わってしまい、継続的な改善体制が築けないケースも失敗につながりやすいでしょう。