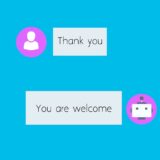生成AIを活用した業務効率化が広がる一方で、「誤って機密情報を入力してしまった」「社外秘の資料をAIに貼り付けてしまった」といった“うっかり”ミスによる情報流出リスクが注目されています。
とくにChatGPTやCopilotのような生成AIは、使いやすさと引き換えに、入力内容の管理が不十分なまま活用されるケースも多く、誤入力による事故は決して他人事ではありません。
本記事では、こうした生成AIにまつわる「誤入力事故」がなぜ起きるのか、どのような情報が危険なのか、そしてどうすれば防げるのかを、企業の視点から整理します。
生成AIの導入を進める上で「使わせない」ではなく「安全に使わせる」ための仕組みづくりを考える担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
また下記リンクからは、セキュリティ面も含めた自社の生成AI活用力を自己診断できるチェックリストをご覧いただけます。「自社の生成AIへの対応状況を可視化したい」「生成AIの活用に向けて、不足している点を認識したい」といった方はお気軽にご覧ください。
\ セキュリティを含めた自社の「生成AI力」を客観的に判断する /
「実務ノウハウ3選」を公開
- 【戦略】AI活用を社内で進める戦略設計
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】属人化させないプロンプト設計方法
生成AIの「誤入力事故」とは?企業にとってのリスクとは
生成AIの業務活用が進む中で、見過ごされがちなのが「誤入力」による情報リスクです。ここでいう誤入力とは、機密情報や社外秘の資料、個人情報などを、意図せず生成AIツールに入力してしまう行為を指します。
たとえば、ChatGPTに社内マニュアルを要約してもらおうと、全文をそのまま貼り付けてしまったり、顧客との商談記録をそのまま入力したりといったケースが、日常業務の中で頻繁に起こり得ます。
こうした入力内容は、利用するAIツールの仕様によっては外部に保存されたり、第三者が参照できる状態になる可能性もゼロではありません。たとえ学習対象にならない仕組みであっても、履歴管理やセキュリティ設定が甘いと、社内での情報漏洩や内部監査の指摘につながるリスクがあります。
また、「出力の誤り」や「プロンプトインジェクション(悪意ある入力による情報漏洩)」といった技術的なリスクとは異なり、誤入力はユーザーの認識不足やヒューマンエラーによって発生します。そのため、誰でも起こしうる“身近な事故”として対策が求められるのです。
\ セキュリティを含めた自社の「生成AI力」を客観的に判断する /
誤って入力されがちな情報の例
生成AIの利便性を活かそうとするあまり、業務で扱う情報を深く考えずに入力してしまうケースは少なくありません。ここでは、企業内でありがちな誤入力のパターンと、入力されやすい情報のカテゴリを整理します。
■よくある入力シーン
- 社内資料を「要約してほしい」と貼り付ける
- 営業メモや議事録を「メール文に変換して」と依頼する
- 評価コメントのドラフトを「自然な文に修正して」と入力
- AIに「テストコードを生成して」と依頼し、ソース全体を送信する
これらの行為自体は業務効率化の観点では合理的ですが、入力する内容が“誰に見られても問題ないものかどうか”を判断せずに実行すると、リスクを伴います。
■入力されがちな情報カテゴリ
| カテゴリ | 具体例 |
| 顧客情報 | 氏名、連絡先、購入履歴、CRMデータなど |
| 社外秘資料 | 新サービスの企画書、営業戦略、価格設定情報など |
| 人事情報 | 社員の評価コメント、給与情報、人事異動案など |
| 認証情報 | APIキー、ログインID、社内システムのURL等 |
| その他 | 社内の未公開ドキュメント、経営会議の議事録など |
特に注意したいのは、「このくらいは大丈夫だろう」という油断が、大きな事故の引き金になることです。生成AIの画面はフラットで親しみやすいため、つい“社内チャットの延長線”のように使ってしまいがちですが、相手はあくまで外部のツールです。
入力内容がどこにどう保管されるかを正しく理解し、「何を入れてはいけないのか」の基準を明確にすることが、第一の予防策になります。
なぜ誤入力が起こるのか?ありがちな原因と背景
誤入力は、悪意や重大な過失によって起きるものではなく、日常的な業務の中でごく自然に発生してしまうのが特徴です。ではなぜ、こうした“うっかり事故”が起きてしまうのでしょうか。その背景には、いくつかの共通した原因があります。
1.生成AIを「社内ツール」と誤認してしまう
ChatGPTやCopilotといった生成AIは、ユーザーにとってインターフェースがわかりやすく、あたかも社内のチャットツールや業務アプリのような感覚で使えてしまいます。
この心理的な“安心感”が、外部ツールであるという意識を薄れさせ、本来であれば入力すべきでない情報も安易に投入してしまう原因になります。
2.業務のスピード感に追われて確認が甘くなる
生成AIは、文章の下書きや要約、翻訳などに役立ち、とにかく「時短」になることが強みです。
その反面、「今すぐ処理したい」「とりあえず早く入力しよう」という焦りが、入力内容の精査をおろそかにし、不用意な情報の貼り付けやアップロードにつながります。
3.利用ルールや基準が曖昧なまま運用されている
「生成AIを使ってもよい」となったはいいものの、どんな情報を入力していいのか、ダメなのかが明文化されていないケースは多く見られます。
特に現場の社員にとっては、判断が属人的になりやすく、“自分の感覚で入力してよい”状態が常態化してしまう危険があります。
4.操作画面から“社外感”が感じられない
生成AIの操作画面は、従来の検索エンジンやメッセージアプリに似ており、「誰に何が届くのか」が見えづらい設計になっています。
そのため、「あとから履歴が残るかもしれない」「サーバーに保存されるかもしれない」という意識が持ちにくいのです。
5.「うちは大丈夫」という過信や慣れ
利用が日常化すると、「これくらいなら入力しても問題ないだろう」といった慣れや油断が判断を鈍らせることがあります。
特にツールの使用を自己判断に任せている企業では、暗黙のうちに“グレーゾーンの入力”が当たり前になっていることも少なくありません。
このように、誤入力の背景にはヒューマンエラー・ツールの特性・ルール不在という三位一体の構造があります。
\ セキュリティを含めた自社の「生成AI力」を客観的に判断する /
生成AIの誤入力による事故を防ぐために、企業が取るべき対策
誤入力による事故は、個人の注意力だけでは防ぎきれないこともあります。だからこそ、組織としての仕組みや教育体制が不可欠です。ここでは、誤入力を防止するために企業が講じるべき3つの基本対策を紹介します。
1.入力ルールの明文化と徹底共有
まず取り組むべきは、「何を入力してはいけないか」を明文化することです。
社外秘・機密情報・個人情報などを具体的に分類し、それぞれのNG例を示すことで、社員が判断に迷わず行動できるようになります。
たとえば、以下のような区分が有効です。
- 入力可:公開済みの製品マニュアル、自社Webサイトの文章
- 要注意:社内プレゼン資料(編集前のものなど)
- 入力禁止:顧客リスト、個人の評価情報、未発表の企画書など
また、ルールは“作って終わり”ではなく、定期的に周知・アップデートする体制が求められます。
関連記事:社内で使えるAI利用ルールの作り方|チェックリストと雛形付きで徹底解説
2.利用履歴・操作ログの可視化と監査体制の構築
ツールの使用状況を把握するには、利用履歴やログを記録・確認できる仕組みが必要です。
特に以下のような視点が重要です。
- 誰が、いつ、どのツールに、どのような内容を入力したか
- 過去の履歴がどのように残るか/削除されるかの確認
- 万が一事故が起きた際、責任範囲や影響度をトレースできる状態か
情報セキュリティ部門や情シス部門が中心となり、ツール選定時点からログ管理の可否を確認することが効果的です。
3.社員へのAIリテラシー教育の実施
ルールと仕組みだけでは不十分です。使う側のリテラシーを底上げするための教育も不可欠です。
特に以下のような視点を持った研修が効果的です。
- 「うっかり入力」がどうリスクになるのかを具体的に理解させる
- 実際の入力シミュレーションで判断力を養う
- 「AIは社外のツールである」という前提意識を徹底する
こうした研修を通じて、社員一人ひとりが「情報を入力する責任」を自覚できる状態を目指しましょう。
「使わせない」ではなく「安全に使わせる」環境づくりへ
誤入力による情報漏洩を恐れるあまり、「生成AIの使用を全面禁止にする」という選択をとる企業も一部に見られます。しかし、こうした対応は一時的な安心感をもたらす反面、業務効率やイノベーションの妨げになりかねません。
重要なのは、生成AIを“使わせない”のではなく、“安全に使わせる”環境を整えることです。
なぜ「禁止」では解決しないのか?
生成AIの利便性が広く認知されている現在、たとえ業務利用が禁止されていても、個人の判断で私物のデバイスやアカウントを使ってこっそり利用されるリスクは残ります。
禁止するだけでは、企業の管理外での“野良AI利用”が増える可能性さえあるのです。
組織全体を巻き込んだルール設計が鍵
安全に活用するには、次のような体制づくりが必要です。
- 情シス・情報セキュリティ部門によるツール選定と設定ガイドライン
- 管理職による現場へのルール周知と運用サポート
- 利用者(社員)自身による判断力とモラルの醸成
このように、一部の部門だけでなく組織全体を巻き込んだ“共通ルールと意識の共有”が求められます。
最小単位の「利用ルール」から始めよう
最初から完璧な制度を作ろうとすると、かえって導入が進まなくなってしまいます。
まずは以下のような最小単位のルール設計から始めるのがおすすめです。
- 「この情報は絶対に入力しない」リストを作る
- 利用ツールの範囲とバージョンを明確にする
- 社員へのガイダンス資料を簡易に整備する
こうした“最初の一歩”が、事故を未然に防ぎつつ、社内で生成AIを安全に展開する土台となります。
まとめ:誤入力は“誰でも起こす”からこそ、仕組みで防ぐ
生成AIの業務利用は、企業に大きなメリットをもたらす一方で、誤入力による情報漏洩という新たなリスクも抱えています。
しかもこのリスクは、悪意のある攻撃ではなく、日々の業務の中で誰にでも起こりうる“ヒューマンエラー”によって生じるという点で非常に厄介です。
だからこそ、個人の判断や意識に頼るのではなく、組織として「誤入力を防ぐ仕組み」をつくることが最も現実的な対策です。
- 「何を入力してはいけないか」を明確にするルール
- 入力履歴やツール利用を可視化する仕組み
- 社員一人ひとりにリスクを伝える教育や研修
こうした施策を段階的に進めることで、生成AIを安全に、かつ継続的に活用するための基盤が整っていきます。
また下記リンクからは、セキュリティ面も含めた自社の生成AI活用力を自己診断できるチェックリストをご覧いただけます。「自社の生成AIへの対応状況を可視化したい」「生成AIの活用に向けて、不足している点を認識したい」といった方はお気軽にご覧ください。
\ セキュリティを含めた自社の「生成AI力」を客観的に判断する /
- Q生成AIに誤って情報を入力してしまった場合、どうすればいいですか?
- A
まずは速やかに上司や情報セキュリティ部門に報告し、入力内容の確認と対応を行うことが重要です。
履歴が残っている場合は削除の可否や共有範囲の確認も必要です。再発防止の観点からも、事後の対応体制を整えておくことが求められます。
- QChatGPTなどの生成AIに入力した情報は学習に使われるのですか?
- A
OpenAI社のChatGPT(無料プラン)は、初期設定では入力内容が学習に利用される可能性があります。
ただし、ビジネスプランや「履歴を無効化する設定」を活用することで、学習対象外にできます。利用ツールの仕様を事前に確認し、適切な設定を行うことが大切です。
- Qどのような情報を生成AIに入力してはいけませんか?
- A
一般的に、以下のような情報は入力を避けるべきです。
- 顧客リストや個人情報(氏名、住所、連絡先など)
- 社外秘の資料や営業戦略
- 人事評価・給与情報など内部的な文書
- APIキーやログインID、システム情報
「入力前に“これは誰に見られても問題ないか?”を確認する意識が重要です。
- Q誤入力を防ぐための社内ルールはどのように整備すべきですか?
- A
まずは、「入力OK」「要注意」「入力NG」の区分けを社内で明文化することから始めましょう。
ルールは現場の社員にも理解しやすいよう、具体例を交えて説明するのが効果的です。
- Q社員に誤入力のリスクを伝えるには、どんな研修が効果的ですか?
- A
「なぜ危険なのか」を事例やシミュレーションで体感させる形式が効果的です。
知識の詰め込み型ではなく、“自分にも起こりうる”という実感を持ってもらうことが、行動変容につながります。