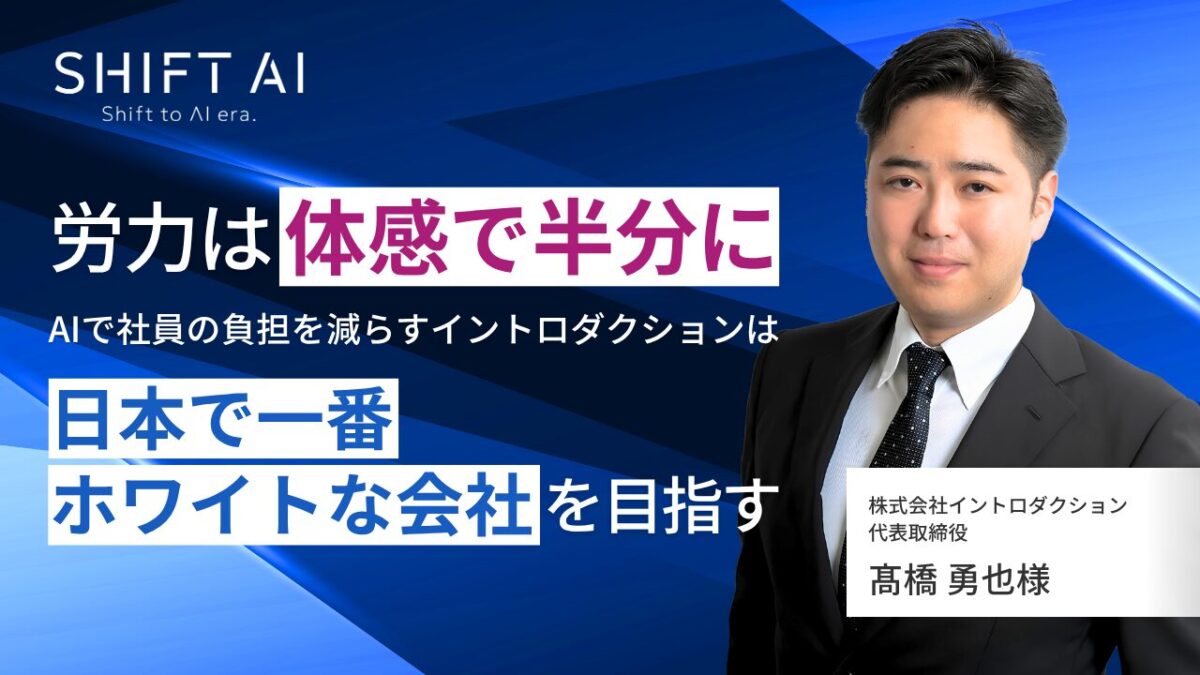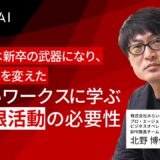株式会社イントロダクションは、SES事業を主力としながら自社アプリの開発や健康経営に取り組み、働きやすい環境づくりを進めている企業です。
同社が方針として掲げるのは「日本で一番ホワイトな会社」。かつてのIT業界に見られた長時間労働や低賃金といった課題を打破し、社員が安心してキャリアを積み重ねられる環境の実現を目標にしています。こうした理念を実際の仕組みへと落とし込むうえでは、AIが大きな役割を担っています。
本記事では、AIがどのように実務に取り入れられ、社員の働き方を支えているのかを紹介します。

株式会社イントロダクション
代表取締役
臨床検査技師として勤務後、一般企業にて事務職を経験。2017年に個人事業主としてITエンジニアに転身し、2019年にイントロダクション合同会社を設立。2021年に株式会社化し、代表取締役に就任。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
AIが下書き、人が仕上げ――効率と品質の両立へ
イントロダクションがAI導入を決めた背景には、既存の業務基盤がありました。同社では全社員がGoogle Workspaceを利用していたため、Googleの生成AI「Gemini」を自然に取り入れることができたのです。導入コストを抑えつつ全社員が同じ環境で試せる点が、大きな後押しになりました。
同社の採用業務では、求人原稿のたたき台作成をAIに任せるようになりました。

「どういう人材が欲しいかっていうのは明確にあるのですが、それをどう打ち出すかという点で悩んでしまい、求人作成に時間がかかっていたようです。まずはAIに案を出させて、それを人間が修正するというステップを踏むようになってから、体感として労力が半分ほどになったと聞いています」
開発業務でも変化が生まれています。単純なコード生成をAIに任せ、人間は確認と微調整を担当するスタイルが定着しつつあります。結果として作業スピードは向上し、品質も安定しました。
AIがホワイトな職場づくりを支える
イントロダクションは、自社製品の機能の一つにAI-OCRを導入しています。本製品は社内でも活用され、食事補助制度の申請時には社員がレシートを撮影してアップロードするだけで処理が完了する仕組みが整っています。
「申請作業は面倒だと感じる方も多いと思いますが、レシートを写真に撮るくらいなら、そこまで負担を感じずにやってもらえるかなと。OCRを導入したことによって、入力不備による差し戻しもかなり減って、会計業務の負担も大幅に削減されました」と髙橋氏は振り返ります。
同社のAI活用への姿勢は「どうすれば人の手間を減らせるか」という逆算から生まれている点が特徴的です。単に効率化するだけではなく、社員の実感に寄り添った導入が、同社の目指す「ホワイトな働き方」に直結しています。

楽しみながら学べる?AI研究会は試行錯誤
AIの効果を一過性のものにしないために、イントロダクションは社内での仕組みづくりにも注力しています。同社では実験的に「AI研究会」を立ち上げ、月に一度、土曜にオフィスを開放して自主的に学ぶ場を提供しました。

「AI研究会は出席率に波もありますが、社員が義務ではなく、自分の意思で学べる環境が特徴的だったと思います。ChatGPTの知名度が上がり始めた頃くらいにスタートして、最新情報の共有やアイコン画像の生成などを、仕事というよりは遊びに近い感覚でやっていました」
加えて、3カ月に一度行われる社内研修では、AIをテーマに扱う機会も増えています。研修はエンジニアに必要な知識や心得を幅広く学ぶためのものですが、クライアント、つまり自社の社員の常駐先企業でもAIを活用した開発が進んでいることから、日常的に親しんでおいたほうが良いと判断し、最近ではAI関連のトピックも目立つようになりました。
健康経営を次の段階へ導くAI活用の取り組み
イントロダクションは「健康経営優良法人 ブライト500」に選定されています。これは経済産業省などが主導し、健康経営に積極的に取り組む優良企業の中から特に高い水準にある中小企業を選定する制度です。中小企業にとって人材採用は難題ですが、選定をきっかけに応募が増えるなど効果が現れています。
法定健診だけでなく、ストレスチェックは年2回実施しており、AIを活用してデータを分析し、高ストレス状態の予兆を早期に把握できる仕組みの製品化を開始しています。従来のストレスチェックは煩雑で敬遠されがちですが、複数のデータを組み合わせて負担なく把握できれば、社員にとっても受け入れやすい取り組みとなると期待しています。
また、人事評価におけるAIの導入も視野に入れています。人間が関わると感情や相性が評価に影響する懸念がありますが、AIを用いれば公平性を高められる可能性があります。ただし、AI面接に前向きではない学生が多いというデータもあるため、従業員の意見も取り入れながら進めていく方針です。
AIの可能性を冷静に見極め、社員とともに歩む
イントロダクションは社外発信にもAIを取り入れています。SNS運用では画像や動画生成を試験的に活用して新しい表現手法を模索するなど、広報やマーケティングをはじめ、より幅広い業務領域でのAI活用を視野に入れています。
一方で、AIエージェントについては慎重な姿勢を崩していません。「現状では、まだAIエージェントが人間と同等の仕事をこなせるとは考えていません。事業環境的にも、社員の常駐先に自社のAIエージェントを持ち込めないという制約がある。今後も重視すべきは、AIを正しく使いこなせる人材を育てることです」と髙橋氏は語ります。
「日本で一番ホワイトな会社」を掲げる同社は、社員に寄り添いながら小さな改善を積み重ねてきました。対外的なインパクトよりも現場の声を大切にし、一歩ずつ取り組みを進める姿勢が、働きやすい環境づくりと着実な成長につながっています。

イントロダクションから学ぶ「真似するべき」5つのポイント
イントロダクションのAI活用は大規模投資を前提とするものではなく、多くの企業で応用できる取り組みが中心です。再現性の高い取り組みを、5つのポイントに整理しました。
- 既存の業務基盤を最大限に活かす
すでに全社員が利用しているGoogle WorkspaceにGeminiを組み合わせた点が特徴的です。 - AIを“下書き担当”として活用する
求人原稿やコード生成など、AIにまず下書きを任せ、人間が最終調整するスタイルを確立しました。AIと人の役割を切り分けることで効率と品質の両立を実現しています。 - 社員目線で手間を減らす仕組みを設計
レシートを撮影するだけで申請が完了するAI-OCRなど、社員が直感的に使える工夫を取り入れ、効率化そのものよりも「社員が負担なく続けられること」を優先しています。 - 学びを文化として根づかせる
AI研究会や社内研修を通じ、自主的に学べる場を整えています。社員が楽しみながらAIに触れる文化を育てることで、活用が一過性で終わらず定着しています。 - AI導入に冷静さと慎重さを持つ
最新のAIエージェントに飛びつくのではなく、自社の事業環境に合うかを見極め、人材育成を優先する姿勢が際立っています。
これらの取り組みは、企業の規模や業種を問わず応用できるものです。特に「学びを促す社内文化の醸成」と「社員目線で手間を減らす仕組み」は、多くの企業にとって取り組みやすい実践例といえるでしょう。
イントロダクションの事例が示すのは、生成AIの定着には“仕組み化と企業文化への落とし込み”が欠かせないということです。
しかし、実際に自社で実践しようとすると、
「どの層の社員から浸透させるべきか?」
「推進役となる人材をどう育てるか?」
「効果をどうやって測定するか?」
といった壁に直面するケースが少なくありません。
私たちSHIFT AIは、こうした「導入したが定着しない」という課題解決を得意としています。組織文化や業務内容に合わせた浸透施策の設計から、社員のスキルを底上げする伴走型研修、成果を可視化する仕組みづくりまで、AI定着に必要なプロセスをトータルで支援します。
「AIを活用する人材が育たない」「導入効果が見えづらい」──そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、私たちの支援内容をご覧ください。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応
本メディアでは、企業の生成AI活用に関するリアルな取り組みを取材しています。
また、社内での挑戦や工夫を共有することで、業界内での認知や採用・ブランディングにもつながります。
成功事例だけでなく、途中段階の取り組みや試行錯誤も大歓迎です。
※取材・掲載に費用は一切かかりません。
📩 取材のご相談はこちら(Googleフォームが開きます)