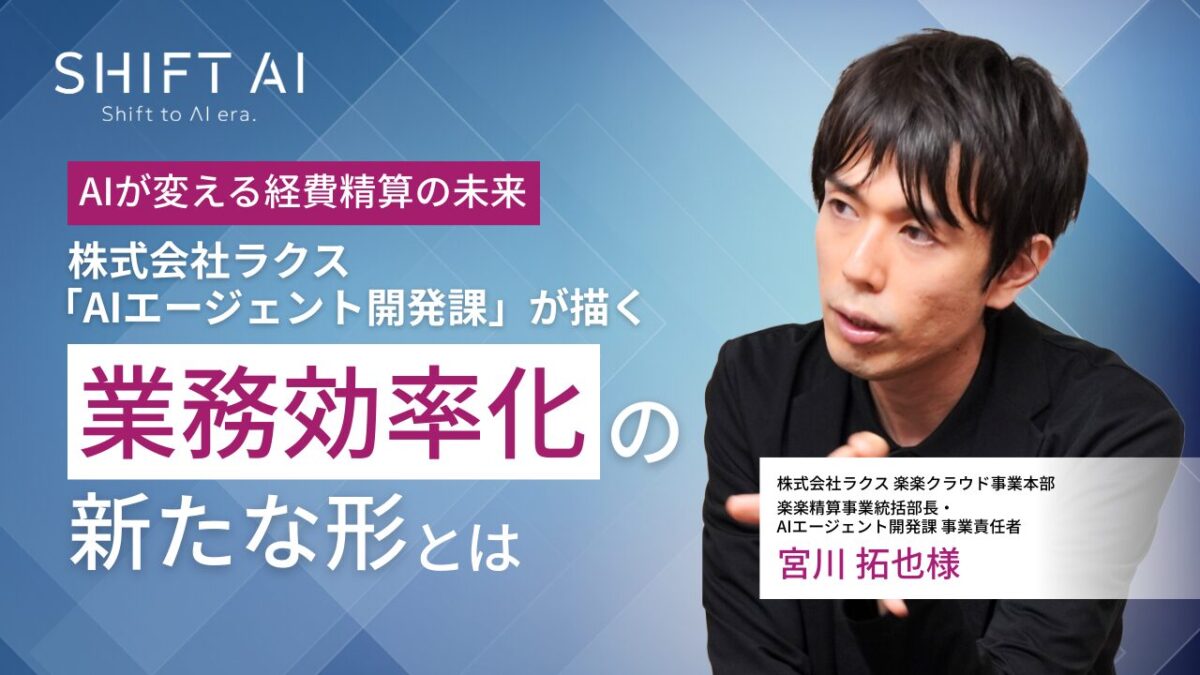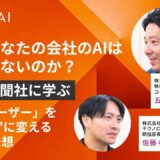経費精算業務の手間は、多くの企業で長年の課題となっています。領収書の整理から勘定科目の選択、詳細な内訳入力まで、月末に集中する煩雑な作業は、本業を妨げる要因の一つです。
こうした課題に対し、楽楽精算を展開する株式会社ラクスが、AI技術を活用した革新的な解決策に乗り出しています。同社が5月に新設した「AIエージェント開発課」では、領収書をアップロードするだけで経費精算の申請内容を自動作成するAIエージェントの開発を進めており、年内のリリースを目指しています。
同社に入社して以来、電子請求書発行システムの楽楽明細の立ち上げから楽楽精算の事業拡大まで一貫して牽引してきた宮川拓也氏は、なぜ今、この技術革新に挑戦するのでしょうか。競合環境の変化、組織体制の刷新、そして全社的なAI活用推進まで、同社が描く経費精算業務の未来について詳しく伺いました。

株式会社ラクス 楽楽クラウド事業本部
楽楽精算事業統括部長・AIエージェント開発課 事業責任者
新卒でエステティック業界のプロモーションを経験し、2011年にラクス入社。企画部門にてプロモーションや製品企画を担当後、2013年より楽楽明細の立ち上げに従事。営業・カスタマーサクセスの経験を経て、2019年より楽楽明細事業部長に就任。2024年より現職の楽楽精算事業統括部長に就任。
※株式会社SHIFT AIでは法人企業様向けに生成AIの利活用を推進する支援事業を行っていますが、本稿で紹介する企業様は弊社の支援先企業様ではなく、「AI経営総合研究所」独自で取材を実施した企業様です。
「必須ノウハウ3選」を無料公開
- 【戦略】AI活用を成功へ導く戦略的アプローチ
- 【失敗回避】業務活用での落とし穴6パターン
- 【現場】正しいプロンプトの考え方
多彩な職種経験を活かして主力サービスの成長に貢献

ーーまず、宮川様のご経歴について教えてください。
新卒でエステティック業界に入社し、マーケティングのプロモーション業務を3年ほど担当していました。その後ラクスに転職し、プロダクトマーケティングを中心に担当するようになりました。
入社から2年後に楽楽明細という請求書発行システムの立ち上げを経験したのが大きな転機でした。企画職でありながら営業活動やカスタマーサクセスも兼務し、いろんな職種を経験させてもらいました。その後、楽楽明細の事業責任者に就任し、昨年度からは楽楽精算の事業責任者を担っています。
0→1から1→100、そして現在の楽楽精算では100→1000のフェーズまで、一通り経験できたのは貴重だったと思います。
ーー異業種からの転職で苦労された点はありましたか?
業界は全く違いましたが、マーケティングの基礎的な考え方は変わらないということがわかったのは大きな発見でした。
もちろんIT系の専門知識は不足していましたし、求められる知識も全く異なるのでギャップはありました。でも、お客様の課題を理解して解決策を提供するという本質的な部分は、どの業界でも共通しているんですね。
19,000社の顧客基盤を守る|競合対策としてのAIエージェント導入
ーー現在のラクスの楽楽精算について、どのような特徴があるのでしょうか?
楽楽精算は現在累計19,000社以上の企業様にご利用いただいている経費精算システムです。経理担当者の方々からの評価が高く、細かなカスタマイズ性や会計ソフトとの連携などが強みです。
特徴としては、経費精算の管理項目や手当の計算などを細かく設定できる点や、申請ルールのチェック機能によって差し戻しの手間が省ける点があげられます。私たちは長年、経理担当者にとって本当に使いやすいサービスづくりに注力してきました。
それだけでなく、申請者向けにも、領収書のAI-OCR機能やクレジットカード連携などを実装して利便性を高めてきましたが、手入力が必要な部分はどうしても残り、業務を劇的に効率化するまでには至っていませんでした。
ですが、AI技術にはその部分を根本的に解決できる可能性を見出しています。
ーーそうした背景も、「AIエージェント開発課」の立ち上げを後押ししたのでしょうか。
はい。加えて、破壊的イノベーションを起こしうるAI技術をスピーディーに取り入れていかないと、既存のお客様を失いかねないという危機感もありました。
そんななか、AI技術をうまく取り入れれば、お客様により大きな価値を提供できると考えました。特に申請書作成業務は、AIエージェントとの相性が非常に良いです。
AIの技術革新の進歩スピードは非常に速いので、従来のウォーターフォール型開発では対応しきれません。そこで、より機動的に動けるよう、事業部の中に小さな開発組織を設置し、アジャイル型での開発を進めています。
「経費申請の手間を劇的に減らす」AIエージェントの革新性
ーー開発中のAIエージェントについて、具体的にどのような機能なのか教えてください。
申請者が領収書をアップロードすると、AIエージェントが経費申請書を代わりに作ってくれる機能です。従来は楽楽精算をご利用いただいている方が、自分で経費申請書を作成する必要がありました。
AIエージェント機能の具体的な流れとしては、まずスマホなどで領収書を撮影し、楽楽精算にアップロードします。すると、AIがその内容を読み取って、事前申請のデータや過去の申請内容、クレジットカードのデータなどを参照しながら、「これはこういう経費申請で間違いないですか?」と提案してくれます。

たとえば、飲食店の領収書を2枚申請したいとき、読み取った領収書のデータや過去の申請データを参照し、「このケースなら交際費ですね」といった具合に提案してくれます。最終的に申請者が「承認する」ボタンを押すと完了になるので、従来に比べ、申請作業にかかる時間が劇的に短くなります。
ーー正確性への配慮はいかがでしょうか?
AIの推論は100%正しい訳ではありませんので、できるだけ正確な予測をするのはもちろんですが、ユーザーが内容を確認しやすく、必要に応じて修正できるような仕組みにすることも大切です。
具体的には、AIエージェントが提案した内容をそのまま通すのではなく、対話形式で「こういった内容で大丈夫ですか?」と確認を取りながら進める設計にしています。

生成AIの技術は日々進化しているので、完璧を求めて時間をかけるよりも、まずはクローズドベータ版として一部のお客様に提供し、フィードバックをいただきながら少しずつ精度を上げていく方が良いと考えています。
5人の精鋭チームが実現するスピード開発
ーースピーディーに開発を進められていますが、AIエージェント開発課はどのような組織体制なのでしょうか?
私を含めて5人という小規模なチームです。私が事業責任者としてビジネス側の役割を担い、開発マネージャー1人とメンバー3人という構成になっています。
メンバーは20代から30代前半の若手で、大学時代にAIの勉強をしていた者もいて、全員が学習意欲が高く、新しい技術をどんどん取り入れようというマインドを持っています。
この体制の最大の特徴は、素早い意思決定と実行力です。5月に組織として立ち上がってから1〜2週間で実際に動くモックを作りました。お客様からフィードバックをいただいた際は、その日のうちに修正するようなスピード感のあるサイクルを回せています。
これは、ビジネス側の組織に開発チームを置いたことの大きなメリットです。「お客様の声を聞く必要がある」と思ったら、すぐに社内の関係者を集めてヒアリングの調整を進めることができています。
ーー組織立ち上げで苦労した点はありますか?
比較的に順調ですが強いて言えば、関係者を巻き込み推進していくことです。エージェント開発課は小規模ですが、実際のサービス提供には多くの部門や部署の協力が必要になります。請求管理部門や営業・カスタマーサクセス、マーケティングなど、本当に社内の多くの人が関わっています。
「なぜ今これだけスピーディーにAI技術を実装していかなければいけないのか」という背景を、すべての関係者に理解してもらい、同じ方向を向いて協力してもらう。ラクスや楽楽精算という大きな組織を動かしていくにあたっては、そのような組織推進も必要かと思います。
横断的な情報共有で加速|全社的なAI活用推進の仕組みづくり
ーー自社の業務においてもAIの活用は進められているのでしょうか?
ラクス全体として、全社員が業務に生成AIを活用していこうという方針を打ち出しています。お客様に提供するプロダクトだけでなく、自分たちの業務効率化や生産性向上のためにも積極的に活用していこうというマインドセットを、特に今期から強く発信しています。
具体的な取り組みとしては、まず全社員にChatGPTの有料版など複数のAIサービスの利用環境が提供されています。営業部門でも、お客様からの技術的な問い合わせに対して、弊社のサポートサイトの情報をもとにRAG(検索拡張生成)の手法を活用し、必要な情報を集約・生成することで、より迅速に対応できるようになりました。
カスタマーサクセス部門では、お客様との会話を自動でテキスト化して、そのまま案件管理システムに取り込むといった活用や、あるサービスでは非エンジニア職の社員がAIを通して独学でPythonを習得し、お客様の問い合わせに自動応答する機能の開発に携わったりと、活用シーンは日々拡大しています。
ーー社員のAIリテラシー向上のための取り組みはありますか?
横断的な取り組みを重視しています。情報システム系の部門が中心となって業務効率化のためのAIエージェントを構築したり、AIの使い方に関する社内メディアを作り、一般社員向けに情報発信をしています。
ほかにも、楽楽精算の営業メンバーが作った仕組みを、全社員向けの事例発表会で紹介するといったものや、有効な活用方法の共有を行う小規模な勉強会などは各部署で定期・非定期で行っています。
こうした動きは昨年度から徐々に始まっていましたが、特に今期からは社員総会においてトップからも強く発信されたこともあり、役職や部署を問わず、社内の様々なところでAIに関する取り組みが活発に進められていると実感しています。
AI導入を成果につなげるための2つのポイント

ーーAIエージェント開発課としての今後の展望を教えてください。
年内にはお客様への提供を開始したいと考えています。ただし、いきなり全てのお客様に提供するのではなく、まずはクローズドベータ版として一部のお客様に試していただく予定です。
AI技術は本当に変化が激しく、スピード感を持って対応していかないと思わぬリスクにつながる可能性があります。完璧なものを作ってから出すよりも、まずは市場に出してお客様の声を聞きながら改善していく方が、結果的により良いサービスになると考えています。
ーー最後に、他社でAI推進を担当される方へのアドバイスをお願いします。
正直、私たちもまだ立ち上げから1ヶ月ほどしか経っておらず、そのような立場でアドバイスするのは恐縮ですが、大切だと感じているのは2つの点です。
1つ目は、ユーザーが抱えている課題を含め、目的をきちんと見極めることです。解決すべき本質的な課題やそれを解決するのに相応しい手段を明確にしてから、必要な技術を選ぶ。AIを取り入れることは手段なので、それが目的になってしまっては本末転倒です。
2つ目は、AIと人間の協力です。AI単独の機能だけでは、すぐにコモディティ化してしまうと思います。しかし、弊社の楽楽精算のような既存のプロダクトの顧客基盤や提供価値を活かすことはもちろん、カスタマーサクセスなど現場でのサポートが組み合わさることで、簡単には代替されない価値を生み出すことができます。この協力関係が競争優位性につながると考えています。
ーーAIと人の協力によるDX推進は、多くの企業にとって重要なテーマとなっています。
SHIFT AIでは、法人向けAI活用支援サービス『SHIFT AI for Biz』を展開しています。AI導入や活用に関心のある方はぜひご活用ください。
法人向け支援サービス
「生成AIを導入したけど、現場が活用できていない」「ルールや教育体制が整っていない」
SHIFT AIでは、そんな課題に応える支援サービス「SHIFT AI for Biz」を展開しています。
AI顧問
活用に向けて、業務棚卸しやPoC設計などを柔軟に支援。社内にノウハウがない場合でも安心して進められます。
- AI導入戦略の伴走
- 業務棚卸し&ユースケースの整理
- ツール選定と使い方支援
AI経営研究会
経営層・リーダー層が集うワークショップ型コミュニティ。AI経営の実践知を共有し、他社事例を学べます。
- テーマ別セミナー
- トップリーダー交流
- 経営層向け壁打ち支援
AI活用推進
現場で活かせる生成AI人材の育成に特化した研修パッケージ。eラーニングとワークショップで定着を支援します。
- 業務直結型ワーク
- eラーニング+集合研修
- カスタマイズ対応
🔍 他社の生成AI活用事例も探してみませんか?
AI経営総合研究所の「活用事例データベース」では、
業種・従業員規模・使用ツールから、自社に近い企業の取り組みを検索できます。